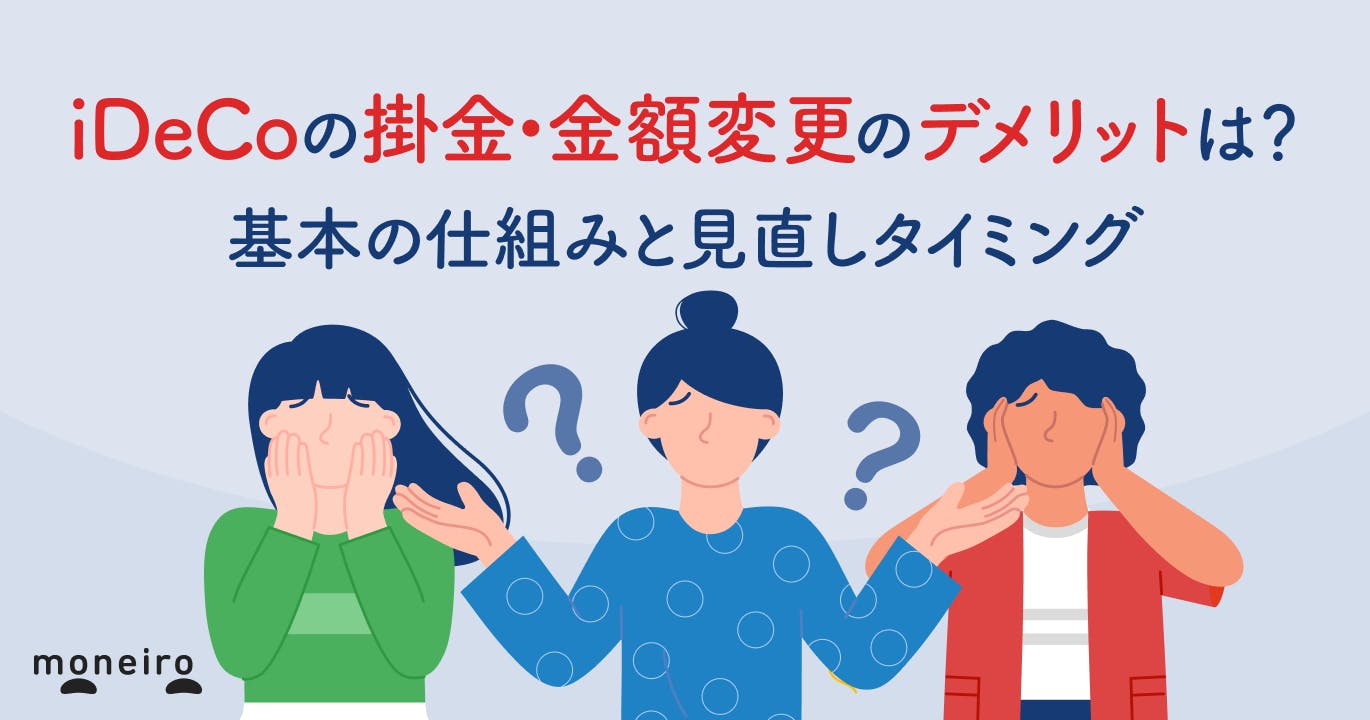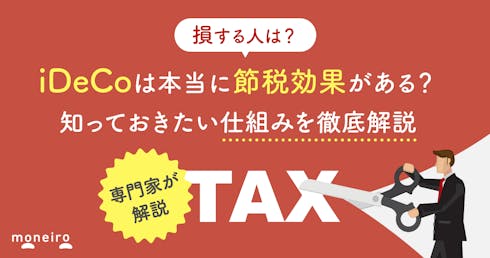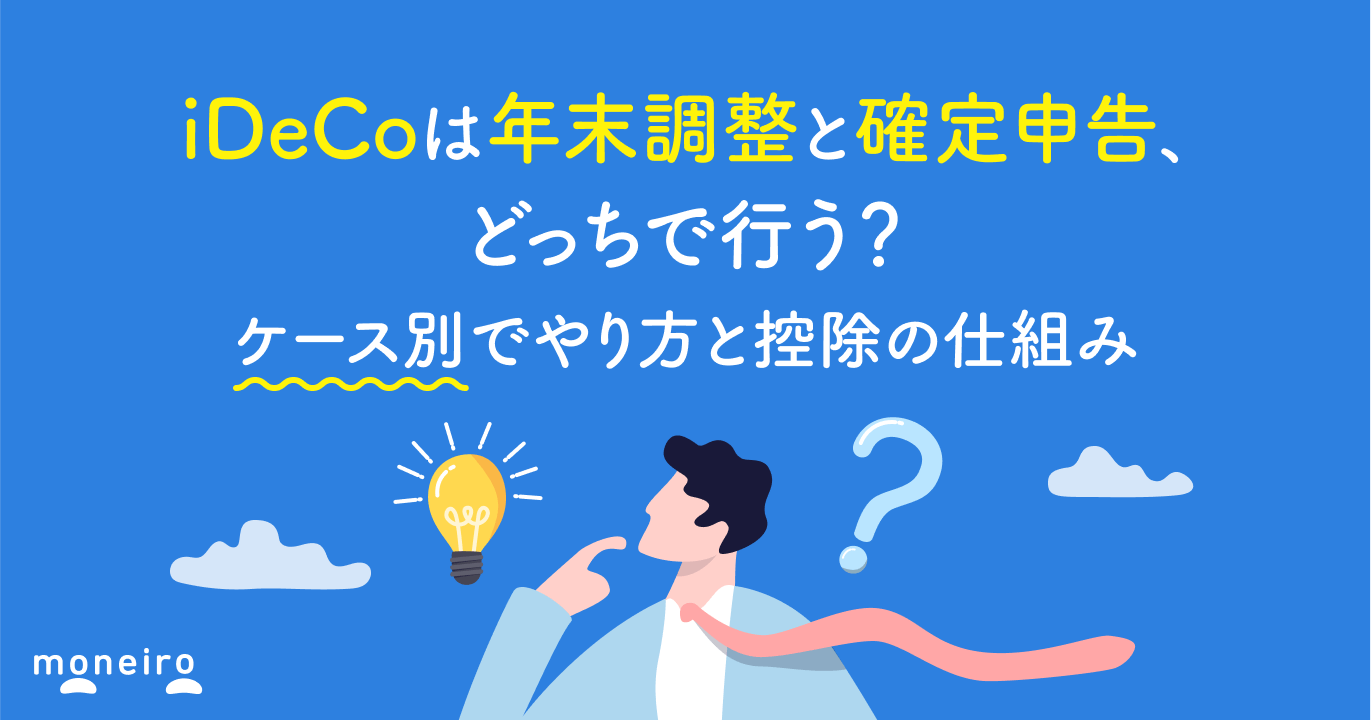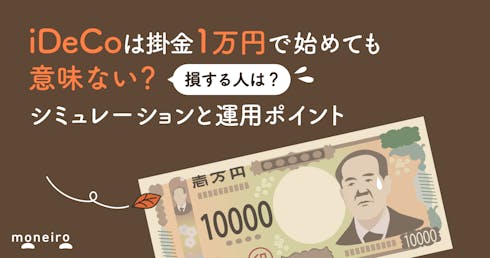
iDeCoの掛金・金額変更の意外なデメリットとは?基本の仕組みと見直しタイミング
»iDeCoと年金だけで老後は足りる?無料診断でチェック
「iDeCo(イデコ)の掛金を増やしたい/減らしたいけど、デメリットはあるの?」とiDeCoの掛金の金額について悩む人は少なくありません。実は、iDeCoの掛金は年1回しか変更できず、手続きにも時間がかかるため、安易な変更は注意が必要です。また、掛金の金額を頻繁に変更するのはあまりおすすめしません。
本記事では、iDeCoで掛金の金額変更をする際の基本のルールと注意点・デメリット、掛金を見直すタイミング、掛金の金額を決める時のポイントについて、専門家がわかりやすく解説します。
- 掛金変更の条件と手続きの流れ
- 金額変更に伴うデメリットと対策
- 掛金を見直すべき最適なタイミング
iDeCoの活用を迷っているあなたへ
資産運用の不安を解消するために、マネイロではさまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:必要な老後資金と自分に合う投資がわかる
▶プロも実践するiDeCoの活用法:専門家が解説する30分のWebセミナー
▶オンライン相談:iDeCoについて専門家に直接相談
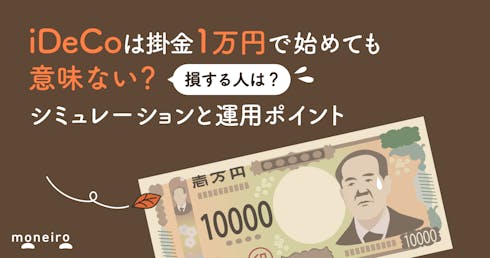

iDeCoの掛金は「年1回」だけ変更できる
iDeCoの掛金は、年に1回(12月分から翌年11月分の間)変更が可能です。ただし、手続きには一定の期間が必要で、金融機関ごとにルールが異なる点に注意が必要です。
掛金変更ができる条件と申請先
iDeCoの掛金はいつでも自由に変更できるわけではなく、年に1回のみと定められています。この「1年」とは、暦年(1月〜12月)ではなく、毎年12月分の掛金から翌年11月分の掛金までの期間を指します。
例えば、2025年5月に掛金額を変更した場合、次に変更できるのは2025年12月以降となります。
掛金を変更するには、まず加入している金融機関(運営管理機関)から「加入者掛金額変更届」という書類を入手する必要があります。この書類は金融機関のウェブサイトからダウンロードしたり、コールセンターに連絡して取り寄せたりするのが一般的です。
注意点として、「加入者掛金額変更届」は加入者の国民年金の区分によって様式が異なります。自営業者などの「第1号被保険者」、会社員などの「第2号被保険者」、専業主婦(主夫)などの「第3号被保険者」といった、自身の区分に応じた正しい書類を使用しましょう。
書類を記入後、加入先の金融機関へ郵送で提出します。
変更後が反映されるまでの期間と注意点
変更届を提出してから実際に掛金額が変更されるまでには、約1ヶ月半から2ヶ月半程度の時間が必要です。これは、提出された書類を金融機関が確認し、その後、iDeCo制度を運営する国民年金基金連合会での審査・登録手続きが行われるためです。
オンラインや電話で即時に変更することはできません。
変更が適用されるタイミングは、書類の提出時期に左右されます。多くの金融機関では、毎月特定の締切日までに書類が受理されると、翌月または翌々月の引き落とし分から新しい掛金額が適用されます。
例えば、締切日が毎月14日の金融機関で4月14日までに書類を提出した場合、5月26日の引き落としから変更後の金額になる、といった具合です。
締切日を過ぎてしまうと反映がさらに1ヶ月遅れるため、変更を決めたら早めに書類を提出することが重要です。
金融機関によって異なる締切・申請ルールに注意
掛金変更の手続きにおける具体的なルールは、加入している金融機関によって異なります。特に、書類提出の締切日や「加入者掛金額変更届」の入手方法(ウェブサイトでのダウンロード、コールセンターへの請求など)は各社で定められています。
手続きを始める前に、必ずご自身の加入している金融機関の公式サイトやコールセンターで詳細を確認しましょう。
iDeCoで掛金の金額変更をするデメリット
iDeCoの掛金変更には、節税メリットの減少や、再変更が1年後までできないといった制約があります。
また、手続きに時間がかかることや、長期投資の観点からのリスクも考慮する必要があります。
①節税メリットが減る可能性がある
iDeCoの大きなメリットの一つは、掛金の全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減される点です。掛金を減額するということは、この所得控除の額が減ることを意味します。その結果、年間の節税額も減少してしまいます。
毎月の積立額が減るため、当然ながら将来受け取れる資産額も少なくなります。iDeCoは長期運用によって資産を育てていく制度であり、運用益が非課税になるというメリットもあります。
掛金を減らすと、この非課税で運用できる元本も減るため、長期的に見ると資産の増加ペースが緩やかになります。
一時的な負担軽減と、将来の資産額のバランスを考えて判断することが重要です。
②反映まで約1〜2ヶ月かかる
掛金変更の手続きは、書類を提出してすぐに完了するわけではありません。金融機関での受付後、国民年金基金連合会での登録処理などを経るため、実際に引き落とし金額が変わるまでには1ヶ月半から2ヶ月半ほどかかります。
「来月から家計が厳しいので、すぐに掛金を減らしたい」と考えても、即座に対応することはできません。このタイムラグを考慮せず計画を立てると、資金繰りに影響が出る可能性があります。
変更を希望する場合は、最低でも2ヶ月程度の余裕をもって手続きを開始することが賢明です。この反映までの期間は、掛金を増額する場合も同様です。
③再変更は1年後までできない
iDeCoの掛金変更は、1年に1回しか行えません。この「1年」は、12月分の掛金から翌年11月分の掛金までの期間を指します。一度変更手続きを行うと、その期間内での再変更はできないため、慎重な判断が求められます。
例えば、一時的に収入が増えたからと安易に掛金を増額したものの、数ヶ月後に支出が増えてしまい、再度減額したくてもすぐには対応できません。次の変更機会である12月まで待つ必要があります。
掛金額を変更する際は、短期的な状況だけでなく、少なくとも1年間の家計の見通しを立てた上で、無理のない金額を設定することが重要です。
④頻繁な変更は複利効果を損ねるリスクに
iDeCoは、長期にわたってコツコツと資産を積み立てることで、複利効果やドルコスト平均法といった投資の恩恵を最大限に活かすことを目的とした制度です。複利効果とは、運用で得た利益が元本に加わり、その合計額に対してさらに利益が生まれることで、雪だるま式に資産が増えていく効果のことです。
また、毎月一定額を積み立てることで、価格が高い時には少なく、安い時には多く購入するドルコスト平均法が自然と実践され、購入価格が平準化されることで価格変動リスクを抑える効果が期待できます。
掛金を頻繁に変更したり、拠出を停止したりすると、この継続投資のメリットが薄れてしまいます。
相場の一時的な変動に一喜一憂して掛金額を変えることは、長期的な資産形成の観点からは推奨されません。
iDeCoの活用を迷っているあなたへ
資産運用の不安を解消するために、マネイロではさまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:必要な老後資金と自分に合う投資がわかる
▶プロも実践するiDeCoの活用法:専門家が解説する30分のWebセミナー
▶オンライン相談:iDeCoについて専門家に直接相談
掛金を見直すタイミング【ケース別】
iDeCoの掛金を見直す最適なタイミングは、結婚や住宅購入、転職など、ライフステージや収入に大きな変化があった時です。家計の状況に合わせて、無理なく継続できる金額に調整することが重要です。
掛金の変更は年1回しかできないため、将来の家計状況を予測した上で慎重に判断しましょう。
育休・住宅購入などで支出が一時的に増える時
結婚、出産・育児、子どもの進学、住宅の購入といったライフイベントは、家計の支出が大きく変動するタイミングです。特に、育児休業による収入の減少や、住宅ローンの返済開始など、一時的に支出が増えて掛金の支払いが負担になるケースが考えられます。
このような状況では、無理して従来の掛金を続けるのではなく、減額を検討するのが賢明な判断です。iDeCoの掛金は最低5000円まで、1000円単位で設定できます。
家計の状況を把握し、継続可能な金額に見直すことで、iDeCoを中断することなく資産形成を続けられます。
子どもが独立するなどして家計に余裕ができた際には、再び増額することも可能です。
収入が増え、節税効果を高めたい時
昇進や転職によって収入が増加した時は、掛金の増額を検討する絶好の機会です。家計に余裕が生まれた分をiDeCoの掛金に上乗せすることで、老後資金の準備を加速させることができます。
掛金を増やすと、その分だけ所得控除額が増加し、所得税・住民税の軽減効果が高まります。iDeCoは所得が高い人ほど節税メリットが大きくなる制度です。また、非課税で運用できる元本が増えるため、長期的な資産の伸びも期待できます。
ただし、手取り収入は減少するため、家計に無理のない範囲で増額することが大切です。
転職・退職などで職業区分が変わる時
転職や退職によって職業の区分(被保険者種別)が変わる場合、iDeCoの掛金上限額も変動します。例えば、会社員(第2号被保険者)から独立して自営業者(第1号被保険者)になった場合、掛金の上限額は月額2万3000円(企業年金なしの場合)から月額6万8000円※に引き上がります。一方、自営業者から会社員になった場合は上限額が下がることがあります。
このような場合は、掛金額の変更だけでなく、「加入者種別変更届」の提出も必要になります。ご自身の新しい状況に合わせて上限額を確認し、掛金額を見直すことで、制度のメリットを最大限に活用できます。
特に上限額が上がる場合は、より多くの資金を非課税で運用し、節税効果を高めるチャンスです。
※2027年から掛金の上限額は引き上げられます

減額よりも「一時停止」で対応できる場合も
掛金の支払いが一時的に非常に困難になった場合、減額するだけでなく、掛金の拠出を一時的に停止するという選択肢もあります。
拠出を停止するには、金融機関から「加入者資格喪失届」を取り寄せ、提出します。これにより、毎月の掛金の引き落としが止まります。
拠出を停止すると、加入者の身分は「運用指図者」に変わります。これは、新たな掛金の積み立ては行わず、これまで積み立てた資産の運用のみを続ける状態を指します。
ただし、拠出を停止している期間も口座管理手数料は発生し、資産から差し引かれる点には注意が必要です。家計が落ち着いたら、再度加入手続きを行うことで拠出を再開できます。
iDeCoの掛金の金額を決める時のポイント
iDeCoの掛金額を設定する際には、いくつかのポイントがあります。
後悔しないために、以下の点を総合的に考慮して金額を決定しましょう。
無理なく継続できる金額か
最も大切なのは、長期的に見て無理なく支払いを続けられる金額であることです。iDeCoは原則60歳まで資金を引き出せないため、日々の生活を圧迫するような金額設定は避けるべきです。
まずは最低掛金額の月々5000円から始め、家計に余裕が出てきたら増額を検討するのも一つの方法です。
節税メリットを意識する
iDeCoの大きな魅力は所得控除による節税効果です。自身の年収と適用される所得税率を確認し、どのくらいの節税が見込めるかをシミュレーションしてみましょう。
一般的に、所得が高い方ほど節税メリットは大きくなります。拠出限度額の範囲内で、節税効果を最大化できる金額を目指すのも良いでしょう。
生活防衛資金や他の支出とのバランス
急な病気や失業に備えるための「生活防衛資金」(生活費の半年〜1年分が目安)は、iDeCoとは別に確保しておく必要があります。
また、住宅ローンや教育費など、他の大きな支出とのバランスも考慮し、iDeCoの掛金が家計の柔軟性を損なわないように注意してください。
NISAなど他の制度との併用
iDeCoは老後資金に特化した制度ですが、より流動性の高い資産形成も並行して行いたい場合は、NISA(少額投資非課税制度)との併用が有効です。
いつでも引き出し可能なNISAと、強制的に老後資金を貯められるiDeCoを組み合わせることで、バランスの取れた資産ポートフォリオを構築できます。

iDeCoの運用を一時停止・再開する方法
iDeCoの掛金拠出は「加入者資格喪失届」を提出することで一時停止できます。停止期間中は「運用指図者」として資産運用を継続しますが、口座管理手数料はかかり続けます。
再開には再度加入手続きが必要です。停止・再開の手続きにも時間がかかるため、計画的に行いましょう。
一時停止(拠出中断)の手続き方法
iDeCoの掛金拠出を一時的に中断したい場合、加入している金融機関(運営管理機関)に連絡し、「加入者資格喪失届」という書類を取り寄せます。この名称から脱退をイメージするかもしれませんが、これはあくまで掛金の拠出を停止するための手続きです。
必要事項を記入した「加入者資格喪失届」を金融機関に提出し、手続きが完了すると、毎月の掛金の引き落としが停止します。これにより、加入者の資格を一時的に喪失し、資産の運用のみを行う「運用指図者」へと切り替わります。
手続きには時間がかかるため、停止したい月の引き落としに間に合うよう、早めに書類を提出することが重要です。
再開時の注意点と手数料
掛金の拠出を再開したい場合は、あらためてiDeCoの加入申込み手続きを行う必要があります。これは、初めてiDeCoに加入する時とほぼ同じプロセスです。以前利用していた金融機関に再度申し込むことも、このタイミングで別の金融機関に変更することも可能です。
再開手続きの際には、新規加入時と同様に国民年金基金連合会への手数料(2829円)が発生します。短期間での停止と再開を繰り返すと、その都度手数料がかかりコスト負担が増えるため注意が必要です。
家計の状況が安定し、長期的に拠出を継続できる見通しが立ってから再開を検討するのが良いでしょう。
停止期間中の運用はどうなる?
掛金の拠出を停止している期間中も、それまでに積み立てた資産がなくなるわけではありません。「運用指図者」として、引き続き資産の運用を継続します。つまり、保有している投資信託などの価格は市場の動きに応じて変動し、利益が生まれることもあれば、損失が出ることもあります。
重要な注意点として、掛金を拠出していなくても口座管理手数料は毎月発生し、積み立てた資産から差し引かれます。そのため、運用成果によっては資産が目減りする可能性もあります。
また、運用指図者であっても、保有している商品の配分を変更する「スイッチング(預け替え)」はいつでも可能です。市場の状況やご自身の考えに合わせて、定期的に資産内容を見直すことが推奨されます。
まとめ
iDeCoの掛金は、年に1回(12月分〜翌11月分)の期間に変更が可能です。ライフステージや収入の変化に合わせて見直すことが、無理なく資産形成を続けるための鍵となります。
ただし、掛金変更には以下のデメリットがあることを理解しておく必要があります。
- 節税メリットの変動:掛金を減らせば節税額も減ります。
- 反映までの時間:手続きから反映まで1〜2ヶ月かかります。
- 再変更の制限:一度変更すると、次の変更は1年後になります。
もし掛金の支払いが一時的に困難になった場合は、減額だけでなく拠出を一時的に停止する「運用指図者」になるという選択肢もあります。
ただし、停止期間中も口座管理手数料は発生し、それまでの資産は運用され続ける点に注意が必要です。
これらのルールとご自身のライフプランを照らし合わせ、最適な掛金額を設定することで、iDeCoのメリットを最大限に活用し、賢く老後資金を準備しましょう。
»まずは老後資金、いくら必要なのか無料診断しませんか?
iDeCoの活用を迷っているあなたへ
資産運用の不安を解消するために、マネイロではさまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:必要な老後資金と自分に合う投資がわかる
▶プロも実践するiDeCoの活用法:専門家が解説する30分のWebセミナー
▶オンライン相談:iDeCoについて専門家に直接相談
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。