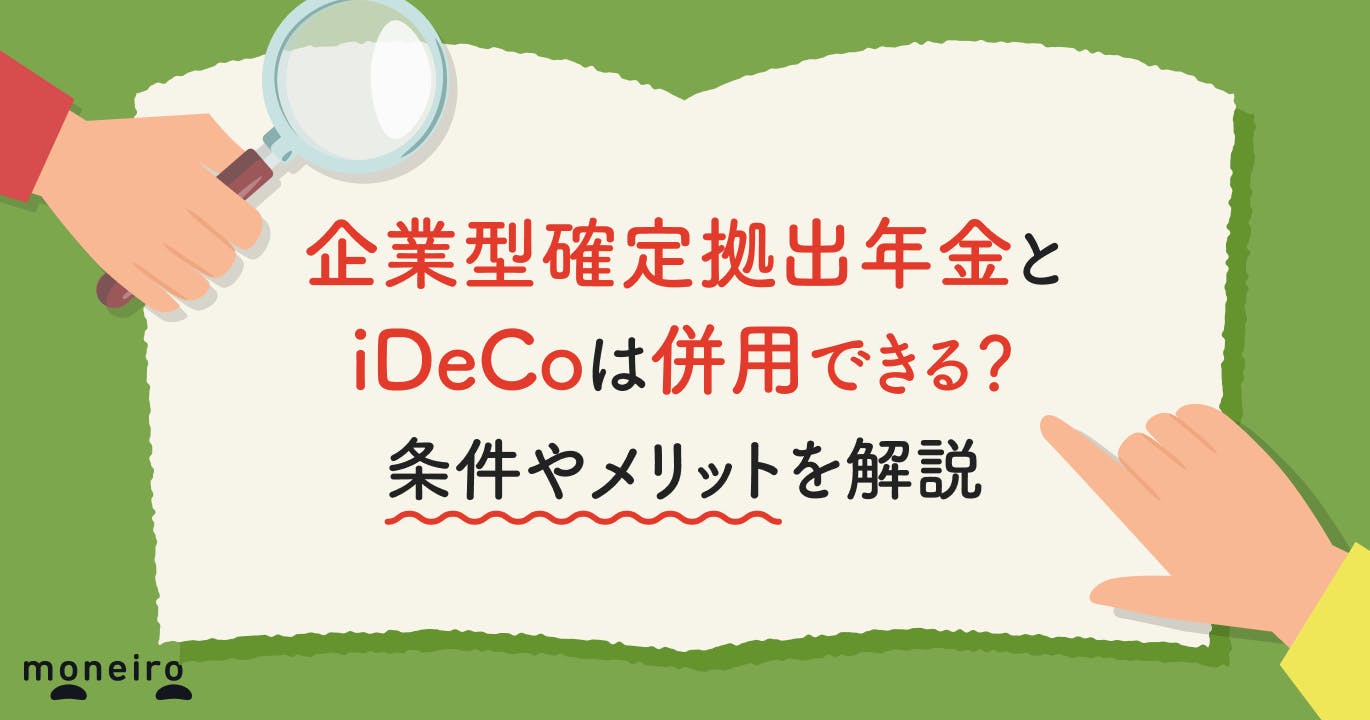
iDeCoと企業型DCの違いとは?併用の可否&注意点を分かりやすく解説
≫あなたはiDeCoやるべき?自分に合った資産運用を3分で診断
iDeCo(個人型確定拠出年金)と企業型DC(企業型確定拠出年金)は、将来の資産形成を助ける強力な制度ですが、制度設計やメリットに違いがあります。
本記事では、加入資格、掛金上限、手数料、税制優遇、そして併用の可否など、8つの視点から両制度の違いを徹底的に比較解説します。企業型DCのみを利用する場合やiDeCoと併用する場合など、状況に応じた最適な選択肢が分かります。
- iDeCoと企業型DCの制度の違い
- 企業型DC加入者がiDeCoを併用する際の注意点
- 勤務先の年金制度の状況に応じた、iDeCo・企業型DCの選び方
iDeCoでの資産づくりが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
iDeCoと企業型DCの基本
まずはiDeCo(個人型確定拠出年金)と企業型DC(企業型確定拠出年金)の基本からおさらいしておきましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは
iDeCoは、国民年金や厚生年金といった公的年金に上乗せして給付を受ける、私的年金制度の1つです。加入者が自ら金融機関を選び、掛金を拠出して運用し、その運用結果によって将来受け取る年金額が変動する「確定拠出年金」の仕組みに基づいています。
加入は任意で、会社員、自営業、主婦(夫)など、原則20歳以上65歳未満の幅広い層が利用可能です。
iDeCoの最大の特徴は、拠出時、運用時、受取時の3段階で税制優遇を受けられる点にあります。特に拠出金全額が所得控除の対象となる点は大きなメリットといえます。
加入年齢&拠出限度額の引き上げも
iDeCoは、2025年6月に成立した年金制度改正法により、2027年1月からさらなる見直しが予定されています。内容は大きく以下の2点です。
- 加入可能年齢の引上げ(施行目標:2027年の控除分から):加入可能年齢の上限が、現在の「65歳未満」から「70歳未満」に引き上げられる予定です。
- 拠出限度額の引上げ(施行目標:2027年の控除分から) 掛金の上限額についても、2027年の所得控除分からの実現を目指して、以下のように引き上げられる予定です。
- 第1号被保険者(自営業者など):現行 月6.8万円 → 月7.5万円
- 第2号被保険者(会社員・公務員など):現行 月5.5万円(※) → 月6.2万円(※) (※企業型DCやDB等の他制度の掛金相当額と合算した上限額)
企業型DC(企業型確定拠出年金)とは
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、企業が従業員のために導入する退職金制度の1つで、企業が掛金を拠出し、従業員が自ら運用を行います。
原則として企業が掛金を負担しますが、企業規約によっては従業員が自ら上乗せできる「マッチング拠出」制度がある場合もあります。これにより、従業員は企業の掛金に追加で資金を拠出し、運用することができます。
また、運用益が非課税になる他、企業が拠出する掛金は所得税・住民税の課税対象外となる、従業員が上乗せするマッチング拠出分は全額が所得控除の対象となるなど、税制上の優遇も大きな特徴です。
iDeCoと企業型DCは併用できる?
以前は企業型DC加入者のiDeCoへの加入は厳しく制限されていましたが、2022年10月の制度改正により、原則として併用が可能となりました。この改正により、企業型DCの加入者であっても、個人の判断でiDeCoに加入し、企業型DCの掛金とは別に掛金を拠出できるようになっています。
併用できないケースと上限額
併用できない主なケースは、以下の2つです。
- 企業型DCで「マッチング拠出」を導入している場合:勤務先の企業型DCの規約で「マッチング拠出」(加入者自身も掛金を上乗せできる制度)が導入されている場合、加入者は「マッチング拠出を利用する」か「iDeCoに加入する」のどちらか一方を選択する必要があります。両方の同時利用はできません。
- 企業型DCの規約でiDeCoの併用を認めていない場合:2022年10月以降、規約で併用を認める企業が大多数になりましたが、一部、規約で併用を禁止している場合は加入できません。
掛け金の上限額
掛金の合計上限は企業年金の種類によって異なります。
- 企業型DCのみの場合: 企業型DCの掛金とiDeCoの掛金の合計で月5.5万円(うちiDeCoの上限は2万円)までとなります。
- 企業型DCと確定給付企業年金(DB)両方の制度がある場合: まず、会社員全体の「大枠(月5.5万円)」から、「(実際の)DB等の他制度掛金相当額」が差し引かれます。 その残りの枠の中で、「企業型DCの掛金」と「iDeCoの掛金」を拠出することになります(うちiDeCoの上限は2万円)。
したがって、DB等に加入している場合は、自身の「DB等の他制度掛金相当額」がいくらなのかを勤務先に確認することが重要です。
≫あなたはiDeCoやるべき?自分に合った資産運用が見つかる無料診断
iDeCoと企業型DCの8つの違い
ここでは、両制度の「違い」を明確にするため、以下の8項目で徹底比較します。
違い1.加入対象者・加入の任意性
iDeCoは加入が任意であり、会社員、自営業者、専業主婦(夫)など、国民年金の第1号から第3号被保険者の多くが対象となります。iDeCoは「個人型」確定拠出年金であるため、個人の意思でいつでも加入を決められます。
一方、企業型DCは、制度を導入している企業の従業員が対象であり、加入は規約によって任意または強制となる場合があります。企業型DCは企業の福利厚生制度の一環として位置づけられます。
違い2.掛金(かけきん)の拠出者
iDeCoの掛金は、原則として加入者本人が拠出します。そのため、掛金の額は加入者が決定し、変更の自由度が高いといえます。対して、企業型DCの掛金は、原則として企業(事業主)が拠出します。従業員にとっては給与から天引きされない形で資産形成が進む点がメリットです。
ただし、企業によっては「マッチング拠出」が認められており、この仕組みでは従業員自身が掛金を上乗せすることになります。
違い3.手数料(コスト)の負担
iDeCoでは、加入時や口座管理料、給付を受ける際にかかるすべての手数料が加入者自身の自己負担となります。特に口座管理料は金融機関によって異なり、長期運用においては運用益を圧迫する可能性があります。
一方の企業型DCでは、原則として運営管理機関への手数料は企業が負担します。従業員がコストを意識せずに運用できる点が大きなメリットです。ただし、例外的に一部の費用が自己負担となるケースも存在します。この手数料負担の違いは、長期的な運用利回りに大きな差を生む可能性があります。
違い4.金融機関・運用商品の選択
iDeCoでは、加入者が自分で好きな金融機関を選び、その金融機関が提供する運用商品ラインナップから自由に商品を選択できます。これにより、リスク許容度や投資方針に合わせて最適な商品を選ぶことが可能です。
一方、企業型DCでは、企業が選定した金融機関を利用し、企業が用意した商品ラインナップの中からしか選べません。そのため、企業型DCの場合、自身が運用したい特定の商品がない可能性がある点がデメリットとなります。
違い5.掛金の上限額
掛金の上限額は、加入者の属性や他の年金制度の有無によって大きく異なります。iDeCoの場合、自営業者は月額6万8000円、企業年金のない会社員は月額2万3000円など、属性ごとに定められています。
企業型DCの場合、他の企業年金がない場合は月額5万5000円が上限です。iDeCoと企業型DCを併用する場合は、合計額に制限がかかるため、さらに複雑なルールが適用されます。
違い6.税制優遇(節税メリット)
拠出時、運用時、受取時の3つの税制優遇はiDeCoと企業型DCで共通しています。大きな違いは「拠出時」の扱いです。iDeCoで加入者本人が拠出した掛金は全額所得控除の対象となり、年末調整や確定申告で課税所得が減り、所得税・住民税が軽減されます。
企業型DCの場合、企業が拠出した掛金は非課税扱いとなり、給与所得に含まれないため、そもそも課税対象になりません。マッチング拠出(従業員上乗せ分)をした場合は、iDeCoと同様に所得控除の対象となります。
違い7.転職・退職時の手続き(ポータビリティ)
iDeCoと企業型DCは、どちらも積み立てた資産を次の制度に持ち運べるポータビリティが確保されています。これは、転職や退職をしても、年金資産を持ち運んで運用を継続できることを意味します。ポータビリティの確保は、確定拠出年金制度の大きな利点です。
ただし、手続きの主体に違いがあり、例えば転職で企業型DCがなくなる場合、その資産を新しい勤務先の企業型DCやiDeCoへ移換する手続きは加入者自身が行う必要があります。
6ヶ月以内に手続きを行わない場合、資産が自動的に「国民年金基金連合会」に自動移換され、運用できなくなる可能性があるため、早めに手続きすることが重要です。
iDeCoでの資産づくりが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
違い8.受取方法(出口戦略)
両制度とも、受取方法は、「一時金」として一括で受け取る、または「年金」として分割で受け取る、あるいはこれらを「併用」する形式から選択可能です。受取時の税制優遇についても、一時金の場合は退職所得控除、年金の場合は公的年金等控除の対象となり、両制度で共通しています。
また、どちらも原則として60歳以降に年金資産を受け取ることができますが、iDeCoでは、加入期間が10年未満の場合に受取開始可能年齢が以下のように繰り下げられます。
- 8年以上10年未満:61歳
- 6年以上8年未満:62歳
- 4年以上6年未満:63歳
- 2年以上4年未満:64歳
- 1ヶ月以上2年未満:65歳
【ケース別】iDeCoと企業型DC、どっちが得?
違いを把握したところで、実際にiDeCoと企業型DCではどちらを選択したほうが得なのか気になる方も多いでしょう。
iDeCoや企業型DCの利用で最適な選択をするためには、まず勤務先の企業年金制度を確認することが大切です。確認すべき主なポイントは以下の3点です。
- 企業型DC(確定拠出年金)の有無
- DB(確定給付企業年金)などの他の企業年金の有無
- 企業型DCにおけるマッチング拠出の有無
これらの情報は、就業規則や退職金規程、あるいは人事部に問い合わせることで確認できます。では、具体的なケースごとの最適な選択について以下で見ていきましょう。
ケース1:勤務先に企業型DCやDBが「ない」会社員
このケースでは、利用できる企業年金制度がないため、必然的にiDeCo一択となります。他の企業年金がない会社員の場合、iDeCoの掛金上限は月額2万3000円です。年間で最大27万6000円を拠出できます。
この上限までiDeCoを活用することで、全額所得控除による最大限の節税メリットを受けながら、効率的に老後資金を準備することができます。
ケース2:勤務先に「企業型DCのみ」がある会社員
この場合は、iDeCoとの併用を検討するのが合理的です。特に、勤務先の企業型DCで提供されている運用商品のラインナップに満足できない場合や、よりリスクの高い商品や特定のテーマ型ファンドなど、自身で商品を選びたい場合に、iDeCoを併用する価値は高いといえます。
併用する場合のiDeCoの掛金上限は、「月額2万円」と「月額5万5000円 − 勤務先の企業型DC事業主掛金額」の、いずれか低いほうの金額となります。例えば、企業の掛金が月額3万円の場合、iDeCoの上限は「2万円」と「5万5000円 − 3万円 = 2万5000円」を比べて、低いほうの「月額2万円」となります。
ケース3:企業型DCで「マッチング拠出」ができる会社員
企業型DCでマッチング拠出ができる場合、iDeCoとマッチング拠出は併用することができません。このため、従業員はどちらか一方を選択することになります。
- マッチング拠出のメリット・デメリット: 手数料が企業負担となるため安価に済む点が最大のメリットです。しかし、従業員が拠出できる額は企業が拠出した掛金額以下に制限され、運用商品は企業型DCの範囲内というデメリットがあります。
- iDeCoのメリット・デメリット: 運用商品を自由に選べる点、拠出額の自由度が高い点がメリットです。一方、手数料が自己負担となる点がデメリットです。
運用商品にこだわり、最大限の自由度を求める場合はiDeCoを、手数料を最小限に抑えたい場合はマッチング拠出を選択するとよいでしょう。
ケース4:勤務先に「DB(確定給付企業年金)」もある会社員
DB(確定給付企業年金)や厚生年金基金など、他の企業年金制度がある会社に勤めている場合は、iDeCoや企業型DCに拠出できる掛金額に制限があります。2024年の制度改正後は、計算方法が新しくなりました。 会社員全体の掛金の大枠である月額5.5万円から、「① 企業型DCの事業主掛金額」と「②(実際の)DB等の他制度掛金相当額」の両方を差し引いた残額が、iDeCoの掛金の上限となります(最大で月額2万円)。
iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象となり、確実に節税効果を得られるメリットが有るため、自分で拠出できる余地を確認したうえで、iDeCoの併用を検討するとよいでしょう。
まとめ
iDeCoと企業型DCは、確定拠出年金という共通の仕組みを持ちながらも、加入対象者、掛金拠出者、手数料負担、商品選択の自由度など、8つの重要な違いがあります。
2024年の制度改正により、iDeCoの掛金上限額が、勤務先の「企業型DCの事業主掛金額」や、加入中の「DB(確定給付企業年金)等の他制度掛金相当額」によって複雑に変動する点には、特に注意が必要です。
いずれにしても、まずは勤務している企業の制度(企業型DCやDB、マッチング拠出の有無)と、自分に適用される「他制度掛金相当額」を正しく把握することが、賢明な選択をするための基本となります。
手数料の安さを取るか、商品選択の自由度を取るか、そして最大限の節税効果を狙うかを総合的に比較することで、将来の資産形成に最適な制度を賢く選択しましょう。
≫あなたはiDeCoやるべき?自分に合った資産運用が見つかる無料診断
iDeCoでの資産づくりが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
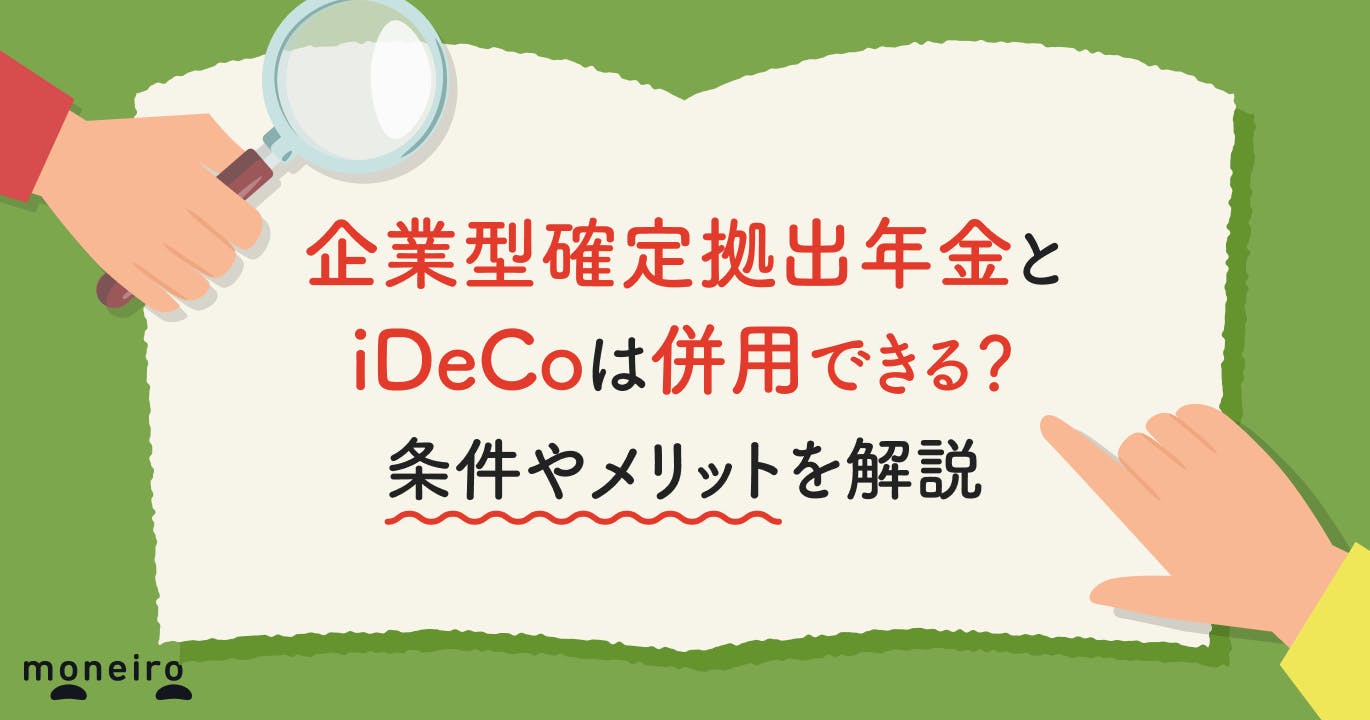

iDeCoの掛金上限が引き上げに!メリットと運用のポイントを専門家が徹底解説
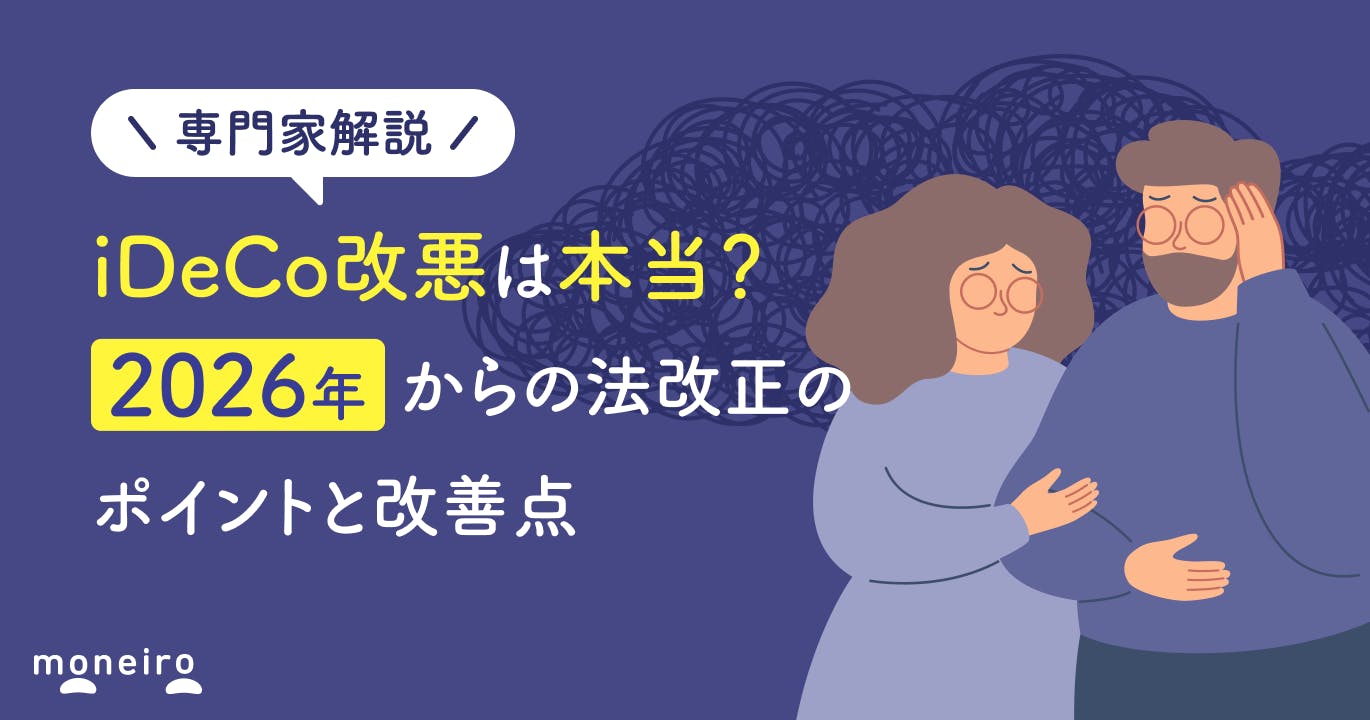
iDeCo改悪は本当?2026年からの法改正のポイントと改善点をわかりやすく解説
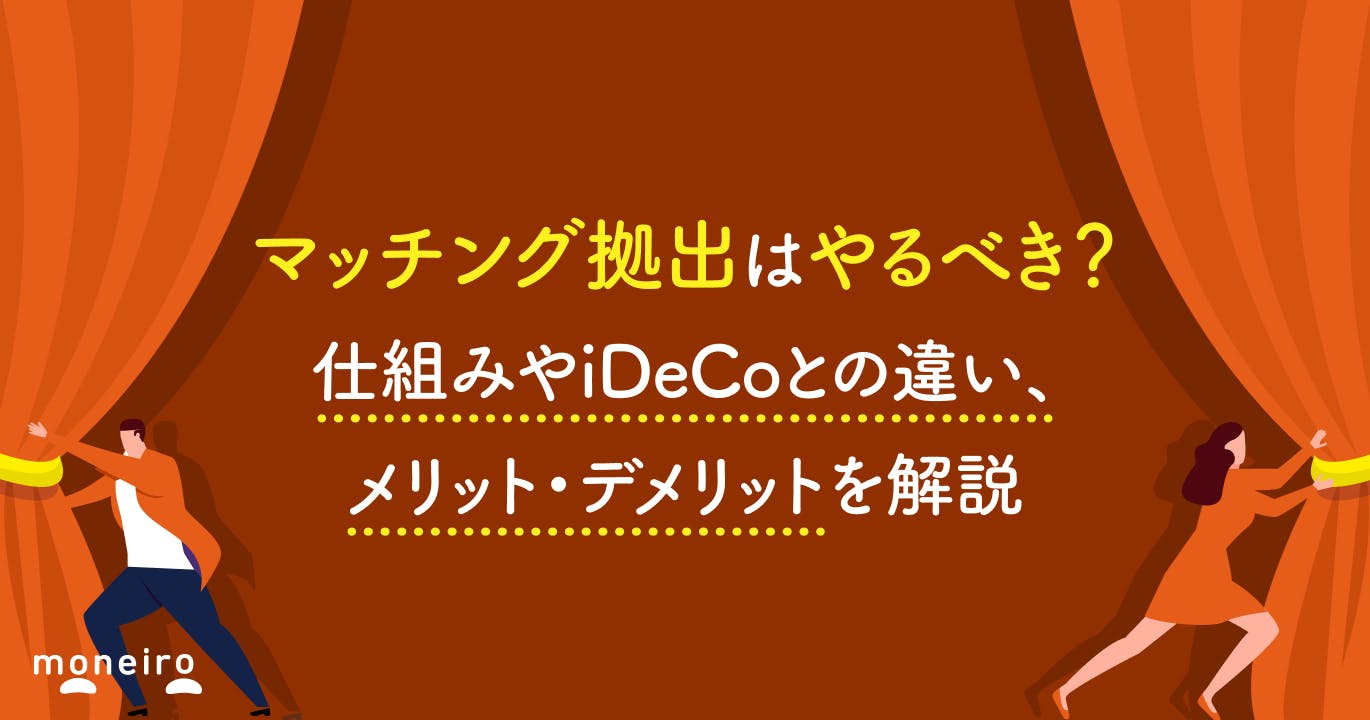
マッチング拠出はやるべき?仕組みやiDeCoとの違い、メリット・デメリットを解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
