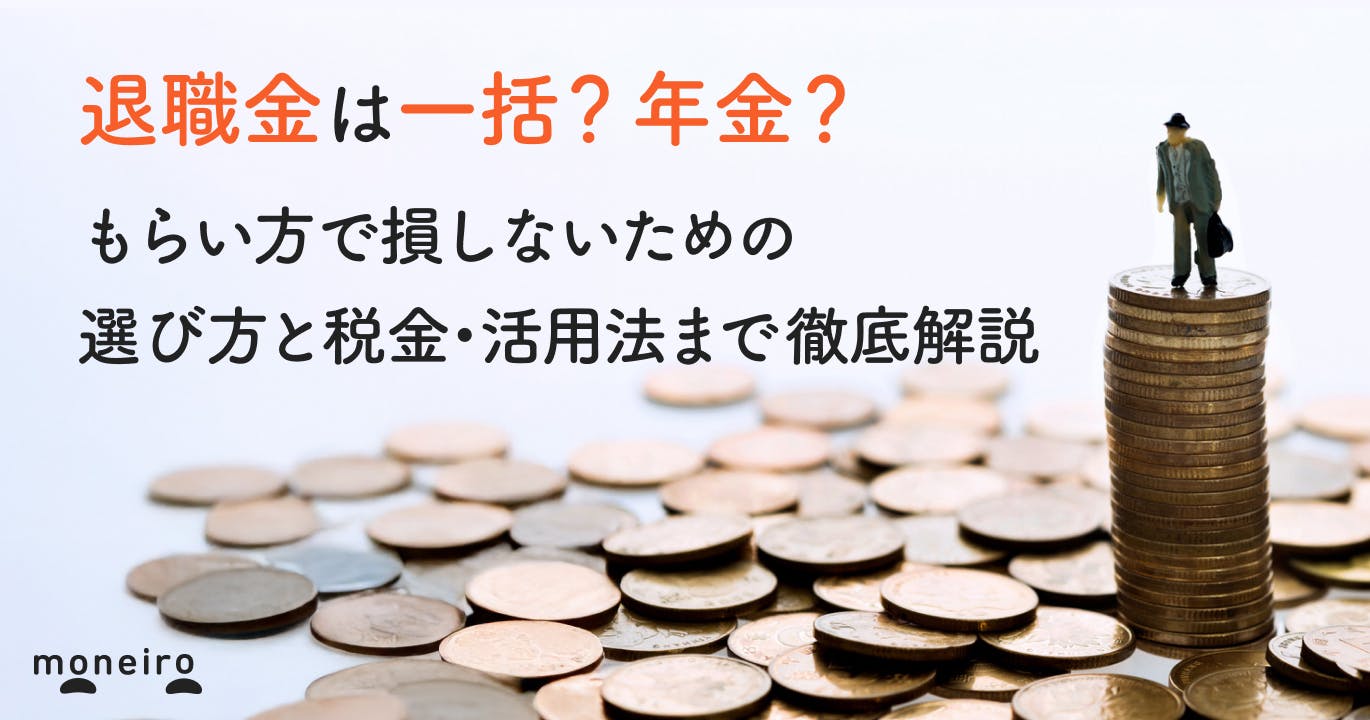iDeCo改悪は本当?2026年からの法改正のポイントと改善点をわかりやすく解説
»iDeCoをやるべき?3分でわかる無料診断はこちら
「iDeCoが改悪って本当?」「老後資金の計画が狂ってしまうかも…」インターネット上ではそんな不安の声とともに、「iDeCo改悪」という言葉が飛び交っています。その主な理由は、iDeCoと会社の退職金を同時期に受け取る際の税制ルールが変更される「10年ルール」にあります。
一方、2025年6月に年金制度改正法が成立したことにより、iDeCoはさらに柔軟に使いやすい制度となりました。本記事では、iDeCo「改悪」と言われる原因となった「10年ルール」の影響と対策に焦点を当て、その他の重要な改正点も合わせてプロがわかりやすく解説します。
(税金関連 監修:中川 美佐子|税理士)
- 「改悪」と言われる10年ルールの詳細
- 改善される掛金上限の拡大
- 今後の賢いiDeCoの活用法
iDeCoの活用を迷っているあなたへ
資産運用の不安を解消するために、マネイロではさまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:必要な老後資金と自分に合う投資がわかる
▶プロも実践するiDeCoの活用法:専門家が解説する30分のWebセミナー
▶オンライン相談:iDeCoについて専門家に直接相談
「iDeCo改悪」と言われる理由|10年ルールとは
iDeCoの制度変更が「改悪」と言われる主な理由は、お金を受け取る時の税金の優遇に関するルールが変わり、一部の人の税金が増える可能性があるためです。
特に、退職所得控除(勤続年数により受けられる控除)の適用ルールが厳しくなる点が大きな要因となっています。
2025年度の税制改正大綱で示され、2026年からの適用が予定されているこの変更は、iDeCoと会社の退職金を両方とも一度にまとめて受け取る場合に影響します。
具体的には、これまで利用できた税金を安くする方法が使いにくくなるため、事前に内容を理解しておくことが必要不可欠です。
退職所得控除の計算ルール変更:5年が10年に
退職所得控除とは、退職金やiDeCoの一時金を受け取る際に、勤続年数により受けられる控除額です。この控除額は、勤務年数やiDeCoの加入期間に応じて計算されます。
これまでの制度では、iDeCoの一時金を先に受け取り、5年以上の期間を空けてから会社の退職金を受け取る際は、それぞれの受け取り時に退職所得控除を別々に満額適用することが可能でした。この仕組みを利用することで、税負担を大幅に抑えることができました。
しかし、この期間が10年に延長されることになりました。つまり、iDeCoの一時金を受け取ってから10年以内に会社の退職金を受け取ると、退職所得控除の枠が通算で計算されることになります。
その結果、控除を満額受けることができなくなるケースが増えるため、「改悪」という声が上がっています。
影響を受ける対象者と具体的なケース
今回の10年ルールへの変更は、iDeCoに加入しているすべての人に影響するわけではありません。主に影響を受けるのは、iDeCoと会社の退職金の両方を一時金で受け取る予定の人です。
特に、65歳まで継続雇用がある企業に勤務しており、60歳でiDeCoを受け取り、65歳で退職金を受け取るようなケースが該当します。
例えば、勤続年数が長く、2000万円の退職金と500万円のiDeCoを受け取る場合を考えてみましょう。
現行の5年ルールであれば、iDeCoを60歳、退職金を65歳で受け取れば、それぞれで退職所得控除を最大限活用し、税負担を抑えることが可能です。
しかし、10年ルール適用後は受給間隔が10年未満だと控除額が調整され、課税対象となる所得が増加する可能性があります。
一方で、以下のようなケースは今回の改正による直接的な影響はほとんどありません。
- 勤務先に退職金制度がない場合
- iDeCoを年金形式で受け取る予定の場合
- 退職金の額が大きくない場合
今回の改正は、一部の人が利用できた税制上の優遇措置をより公平な形に是正する目的があるとされています。
改正により影響を受けない人も、自身の状況を正しく把握することが大切です。
iDeCoの受け取り方法の違い
iDeCoで積み立てた資産は原則60歳以降に受け取ることができますが、その方法には大きく分けて3つの選択肢があります。
どの方法を選ぶかによって税金の計算方法が異なるため、自身のライフプランや他の収入とのバランスを考えて選びましょう。
①年金形式
年金形式は、積み立てた資産を5年以上20年以下の期間で分割して定期的に受け取る方法です。公的年金と同様に、受け取る際には「公的年金等控除」が適用され、税負担が軽減されます。
この方法は、毎月の収入を安定させたい人や、一度に大きな資金を受け取るよりも計画的に使いたい人に適しています。
ただし、受け取る際にはiDeCoの口座管理手数料がかかり続ける点や、他の所得(公的年金など)と合算して税金が計算されるため、合計所得によっては税率が高くなる可能性がある点に注意が必要です。
②一時金として一括
一時金は、積み立てた資産を一度にまとめて受け取る方法です。この場合、受け取った資産は「退職所得」として扱われるため、「退職所得控除」の対象となります。
退職所得控除は、勤続年数やiDeCoの加入期間が長いほど非課税枠が大きくなるため、多くの場合、税金を低く抑えることが可能です。住宅ローンの繰り上げ返済やリフォームなど、まとまった資金が必要な場合に適した受け取り方と言えるでしょう。
ただし、会社の退職金など他の退職所得がある場合は、控除枠を合算して計算する必要があるため注意が必要です。
③年金と一時金の組み合わせ
一部の金融機関では、積み立てた資産の一部を一時金として受け取り、残りを年金形式で受け取るという併用が可能です。この方法は、それぞれのメリットを活かせるので、柔軟な選択肢と言えます。
例えば、当面のまとまった資金需要に一時金で対応しつつ、残りは老後の安定した収入源として年金で受け取る、といった活用が考えられます。
これにより、退職所得控除と公的年金等控除の両方の税制優遇を受けることができる可能性があります。
併用が可能かどうかは金融機関によって異なるため、iDeCo口座を開設している金融機関に事前に相談すると良いでしょう。
iDeCoの活用を迷っているあなたへ
資産運用の不安を解消するために、マネイロではさまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:必要な老後資金と自分に合う投資がわかる
▶プロも実践するiDeCoの活用法:専門家が解説する30分のWebセミナー
▶オンライン相談:iDeCoについて専門家に直接相談
iDeCoと退職金を併用する人が注意すべきポイント
iDeCoと会社の退職金の両方を受け取る予定の場合は、特に注意が必要です。受け取る順番やタイミング、受け取り方法によって、手取り額に大きな差が生じる可能性があるためです。
今回の制度改正で導入される「10年ルール」は、まさにこの点に大きく関わってきます。自身の退職プランとiDeCoの受け取り計画を照らし合わせ、受け取り方を考えることが大切です。
受け取り方で税金の計算方法が変わる
iDeCoと退職金を受け取る順番によって、税金の計算ルールが異なります。特に両方を一時金で受け取る場合は、この違いを理解しておくことが必要です。
まず、iDeCoの一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合、今回の改正で「10年ルール」が適用されます。受給間隔が10年未満の場合、退職所得控除額が調整され、税負担が増える可能性があります。
次に、会社の退職金を先に受け取り、その後にiDeCoの一時金を受け取る場合は、既存の「19年ルール(20年ルールとも呼ばれる)」が適用されます。
これは、退職金を受け取ってから19年以内にiDeCoを受け取ると、控除額の重複期間が調整されるというものです。
受け取る順番によって税金の計算の方法が異なるため、どちらを先に受け取るかによって最適な戦略が変わってきます。
退職時期やiDeCoの受給開始可能年齢を考える必要があります。
iDeCoの加入期間等によって受給開始年齢は異なる
iDeCoの老齢給付金は、原則として60歳から75歳までの間で受給を開始する時期を自分で決めることができます。自身のライフプランに合わせて受け取り方を考えることが可能です。
なお、60歳から受給を開始するためには、iDeCoの「通算加入者等期間」が10年以上必要という条件があります。
この期間は、iDeCoに加入して掛金を拠出した期間だけでなく、企業型DCに加入していた期間なども合算されます。
万一、通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給開始可能年齢が61歳から65歳へと段階的に繰り下げられます。
iDeCoの受け取り方でおすすめは?
iDeCoの受け取り方のひとつとして「一時金として一括で受け取り、その資金を自身で運用する」方法がおすすめです。
この方法の最大のメリットは、税負担を大きく軽減できる退職所得控除を活用できる点にあります。
退職所得控除は加入期間が長いほど控除額が大きくなるため、多くの場合、年金形式で受け取るよりも税額を低く抑えることができると言われています。
また、受け取ったまとまった資金を運用することで、運用益を得ることを期待できます。
なお、この方法がすべての人にとって最適とは限りません。退職金を一時金で受け取るか年金で受け取るかは退職金額や年金受給額、その他の所得状況によって有利・不利が変わるため、一概には判断できません。
例えば退職後に大きな資金が不要なら、一部を年金で受け取り、税負担を分散させる方法もあります。
また、iDeCoを一時金で受け取る場合、退職金と合算して退職所得控除を計算することがあるため、受け取り時期を調整することで有利に控除を受けることができます。
公的年金や他の所得を含めた全体像を踏まえ、専門家や金融機関に相談して最適な方法を検討することをおすすめします。
iDeCoを含む年金制度改正の全体像とメリット
iDeCoに関する制度改正は、「10年ルール」という側面から「改悪」と注目されがちですが、2025年6月の年金制度改正法では多くの加入者にとってメリットとなる「改善」点も含まれています。
あらためて2025年6月の年金制度改正法の全体像を正しく理解し、資産形成に活かしましょう。
(参考:年金制度改正法が成立しました|厚生労働省)
メリット① 加入可能年齢の上限引き上げ
改正前:65歳未満まで
改正後:70歳未満まで
今回の法改正における改善点の一つとして、iDeCoに加入できる年齢の上限が引き上げられる点が挙げられます。
現行制度では、iDeCoに加入できるのは原則として65歳未満までですが、改正後は70歳未満まで積立が可能になります。
これにより、60代以降働き続けている場合も、iDeCoの掛金拠出による所得控除のメリットを長く享受できるようになります。
メリット② 掛金上限額の引き上げ
今回の改正で最も大きな改善点と言えるのが、iDeCoの掛金上限額が大幅に引き上げられることです。これにより、より多くの人がiDeCoの強力な節税メリットを享受できるようになります。
職業別の主な変更点は以下の通りです。
- 会社員(企業年金なし): 月2万3000円 → 月6万2000円
- 会社員(企業年金あり): 月2万円 → 月6万2000円(企業型DC等との合計枠)
- 公務員: 月2万円 → 月5万4000円
- 自営業者など: 月6万8000円 → 月7万5000円
特に、これまで上限額が低く抑えられていた会社員にとっては、拠出できる金額が大幅に増加します。
掛金は全額が所得控除の対象となるため、課税所得が減少し、所得税・住民税の負担を軽減することができます。
また、企業型DCとiDeCoを併用している場合の上限額も引き上げられ、より柔軟な資産形成が可能になります。
メリット③ 企業年金の運用の「見える化」
今回の改正では、企業年金の運用状況を「見える化」する仕組みも盛り込まれており、公布から5年以内(おおむね2030年まで)に施行される予定です。
「見える化」が進むことで、従業員が他社と比較・分析できる情報環境が整備され、制度の透明性が高まります。現在は加入者本人への通知や企業から厚生労働省への報告は義務付けられていますが、情報は一般公開されていません。
今後は情報公開が進むことで、企業も加入者も公正な比較が可能となり、加入者の利益を重視した制度運営につながることが期待されます。
iDeCo以外の手段も比較検討を|マネイロがサポート
iDeCoは老後資金づくりに役立つ制度ですが、資産形成の手段はiDeCoだけではありません。特に2024年から新しくなったNISAと比較しながら検討する人も増えています。
iDeCoは掛金が全額所得控除になる大きな節税メリットがありますが、60歳まで引き出せない制約があります。
一方、NISAは掛金の控除はないものの、運用益が非課税となり、必要に応じて自由に資金を引き出せる柔軟さがあります。
どちらを選ぶかは、ライフプランや目的によって変わります。老後資金を重点的に備えたいのか、それとも必要に応じて引き出せる資金も確保したいのかによって最適な活用法は異なります。
マネイロでは「iDeCoが必要か」「NISAとどう使い分けるか」といった比較を踏まえ、目的に合った金融商品をご提案しています。
判断に迷った際は、ぜひ専門家に相談してみてください。
マネイロの無料相談予約はこちら▼
まとめ
退職所得控除の「5年ルール」が「10年ルール」になるなど、一部の方にとっては「iDeCoは改悪」と捉えられています。
しかし、その影響を受けるのは退職金が多く、iDeCoと近接した時期に一時金で受け取る人で、すべての人に影響がある訳ではありません。
また、iDeCoの改正には掛金上限の大幅な引き上げや加入可能年齢の延長など、多くの人にとってメリットとなる「改善」点も多く組み込まれています。
重要なのは変更点を正しく理解し、ご自身の状況にどのような影響があるかを見極めることです。
iDeCoは税制優遇を活用しながら、老後資金を準備できる私的年金制度です。今回の改正を踏まえて、ご自身のライフプランに合わせた最適な活用法を再検討してみてはいかがでしょうか。
»iDeCoは自分に必要?簡単無料診断はこちら
iDeCoの活用を迷っているあなたへ
資産運用の不安を解消するために、マネイロではさまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:必要な老後資金と自分に合う投資がわかる
▶プロも実践するiDeCoの活用法:専門家が解説する30分のWebセミナー
▶オンライン相談:iDeCoについて専門家に直接相談
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事


老後に必要なお金はいくら?単身・夫婦の世帯タイプ別必要額を解説
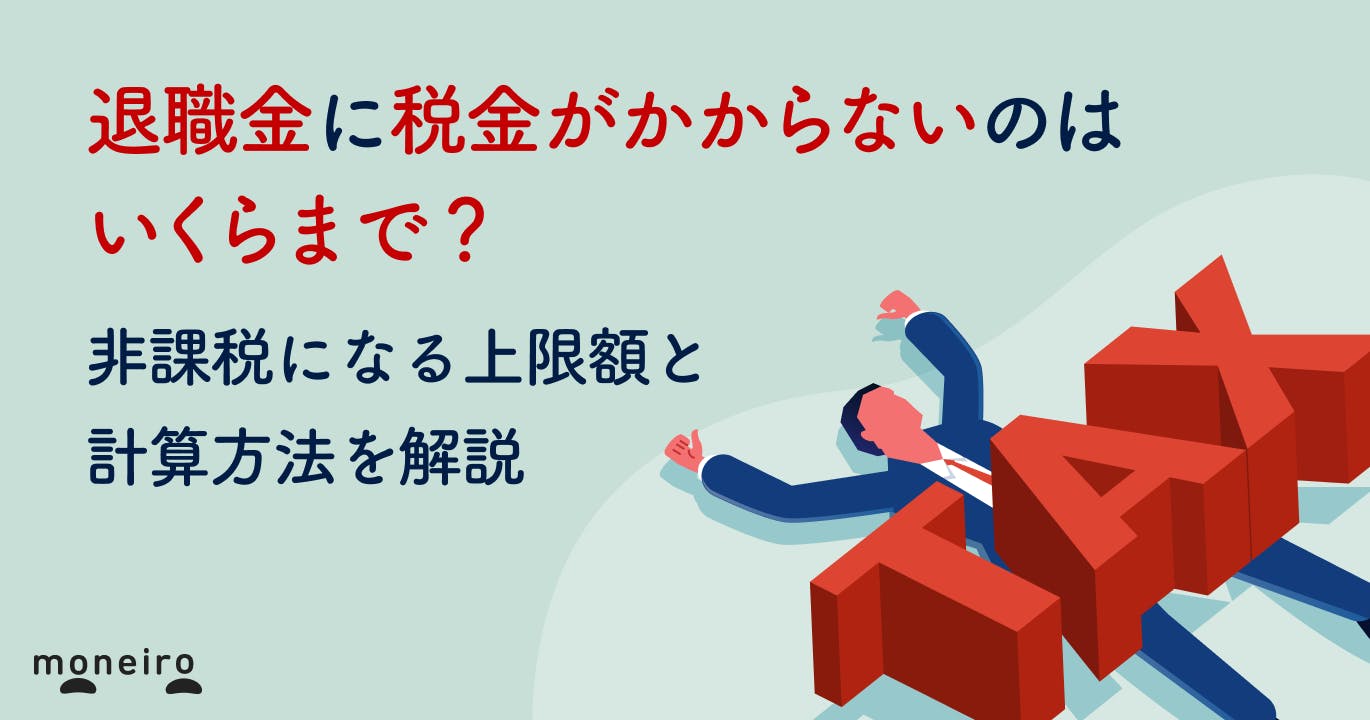
退職金に税金がかからないのはいくらまで?非課税になる上限額と計算方法を解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。