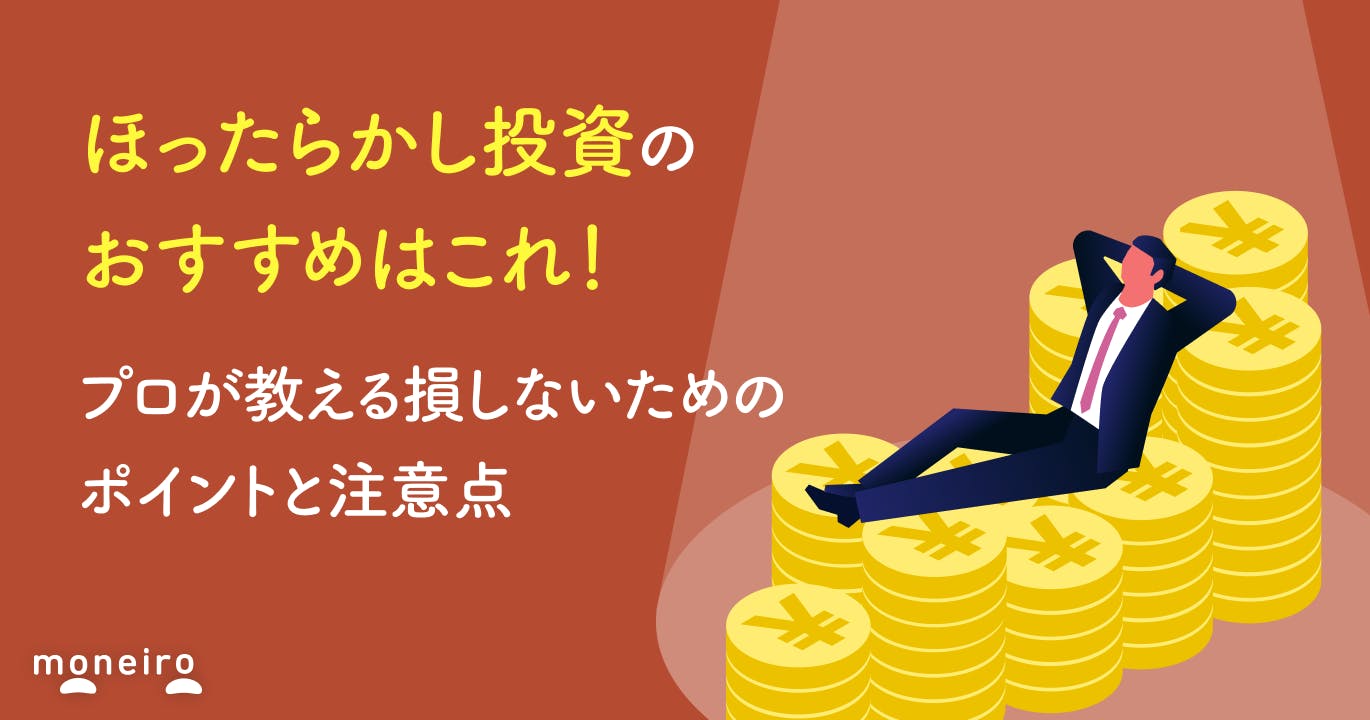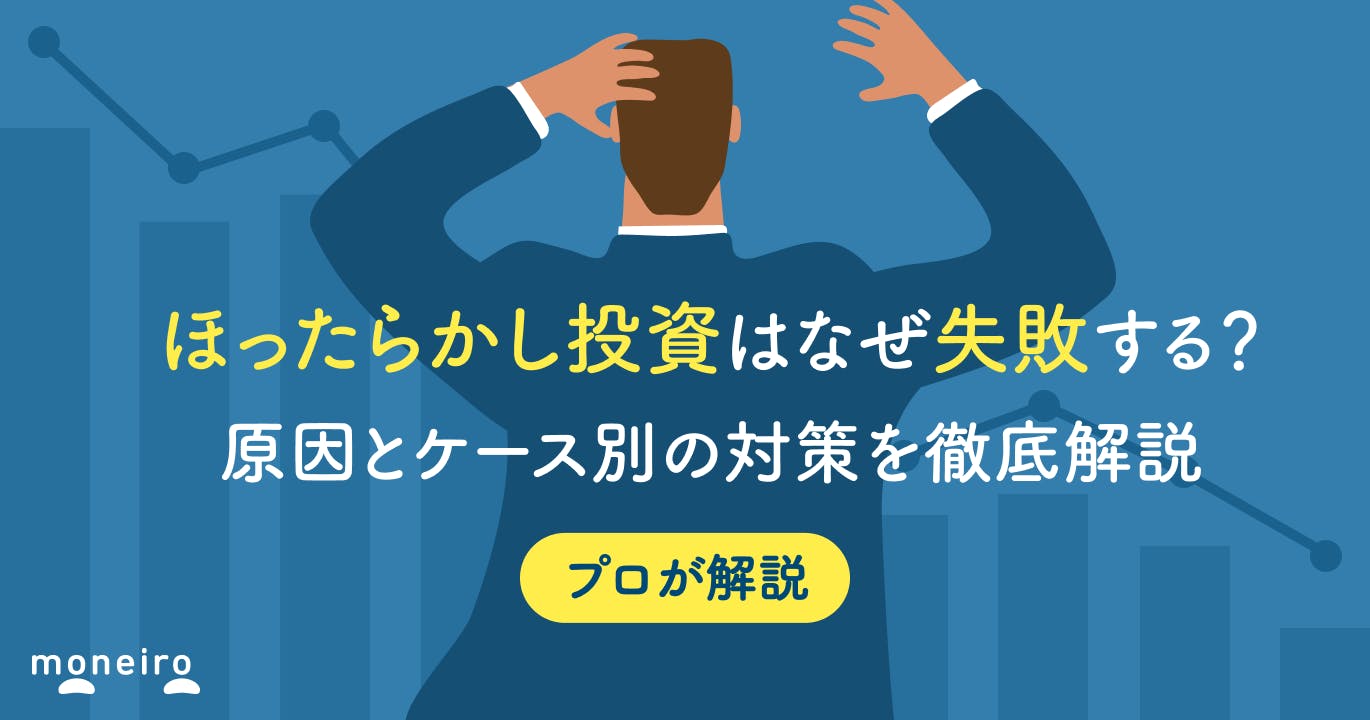ほったらかし投資のおすすめはこれ!プロが教える損しないためのポイントと注意点
»あなたに合った投資を今すぐ無料診断
「投資に時間をかけたくない」「なるべく放置で増やしたい」——そんな人に人気なのがほったらかし投資です。
ただし、“放置で問題ない”のは正しい仕組みを理解している場合のみです。特に、一括投資と積立投資では「ほったらかし」の意味が大きく異なり、リスクの取り方も変わります。
本記事では、ほったらかし投資の基本と、一括・積立それぞれのおすすめ運用法を投資の専門家の視点で解説します。さらに、失敗しないために押さえておきたいポイントもご紹介します。
- ほったらかし投資の基本的な仕組み
- おすすめのほったらかし投資方法
- ほったらかし投資で損しないためのポイント
投資で悩んでいるあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:自分に合う投資がわかる
▶一括投資診断:ほったらかしにしていくらになるか計算
▶オンライン無料相談:専門家にスマホで直接相談
ほったらかし投資とは?放置で増やせる仕組み
ほったらかし投資とは、最初に投資する商品や積立設定を決めた後は、基本的に放置して長期的な資産形成を目指す運用手法です。
日々の値動きを頻繁に確認したり、売買のタイミングを計ったりする必要がないため、投資初心者や多忙な場合でも手軽に始められます。
自動で積立・分散・再投資する仕組み
ほったらかし投資の多くは、資産を効率的に増やすための仕組みが自動化されています。
代表的なのが「自動積立」です。毎月決まった日に、指定した金額が自動で引き落とされ、投資信託などの金融商品が買い付けられます。これにより、投資タイミングに悩むことなく、計画的に資産形成を進めることが可能です。
また、投資信託のような商品は、それ自体が「分散投資」の役割を果たします。一つの商品に投資するだけで、国内外の多くの株式や債券などに資金を分けて投資することが可能になり、特定の資産が値下がりした際のリスクを軽減できます。
さらに、運用で得た利益を自動で再投資する仕組みも重要です。分配金などを受け取らずに再び投資に回すことで、「複利効果」が働き、利益が利益を生む形で雪だるま式に資産を増やしていくことが期待できます。
これらの仕組みにより、手間をかけずに合理的な資産運用が実現します。
なぜ“放置”でも増える?長期×複利の力を活かす
ほったらかし投資が放置していても資産が増える理由は、「長期投資」と「複利効果」という2つの強力な要素を最大限に活用するためです。
まず、長期投資は時間を味方につける戦略です。株式市場は短期的には価格が上下しますが、世界経済の成長に伴い、長期的には右肩上がりの成長を続けてきました。10年、20年という長い期間で投資を続けることで、一時的な価格下落のリスクを乗り越え、経済成長の恩恵を受けやすくなります。
そして、その長期投資の効果を飛躍的に高めるのが複利効果です。複利とは、投資で得た利益(利息や分配金)を元本に加えて再投資し、その合計額に対して新たな利益が生まれる仕組みを指します。
例えば、100万円を年利5%で運用した場合、1年後には105万円になります。単利であれば毎年5万円の利益ですが、複利の場合は翌年、105万円を元本として運用するため利益は5万2500円となり、利益が利益を生む形で資産が雪だるま式に増えていきます。
この「長期」と「複利」を組み合わせることで、日々の細かな売買を行わなくても、時間をかけて着実に資産を育てることが可能になります。
そもそも投資でほったらかしはNG?
20〜30年の長期運用を前提に、成長が見込める商品へ積立・分散投資をしている場合は、基本的に「ほったらかし運用」で問題ありません。
短期の値動きに惑わされず、コツコツと積み立てを続けることが成功の鍵です。
ただし、「ほったらかし」とは完全に放置することではない点に注意が必要です。
少なくとも年に1〜2回は運用状況を確認し、資産のバランスを見直したり、必要に応じて商品を調整したりしましょう。
年末年始などのタイミングを活用して、自分の資産を把握する習慣をつけることが大切です。
ほったらかし投資の基本スタイル|一括投資と積立投資
ほったらかし投資の始め方には、大きく分けて「一括投資」と「積立投資」の2つのスタイルがあります。
一括投資はまとまった資金を一度に投じる方法で、積立投資は毎月コツコツと一定額を投資し続ける方法です。どちらのスタイルが適しているかは、個人の資金状況やリスク許容度によって異なります。
一括投資の特徴
一括投資は、退職金や預貯金など、まとまった資金を一度に投資するスタイルです。
この方法の最大のメリットは、投資した全額が早期から運用されるため、複利効果を最大限に享受できる可能性がある点です。相場が上昇局面にある場合、積立投資よりも大きなリターンを期待できます。
一方で、デメリットは投資するタイミングが非常に重要になることです。もし価格が高い時期に一括投資してしまうと、その後の下落で大きな損失を抱える「高値掴み」のリスクがあります。
このため、市場の動向をある程度見極める必要があり、投資初心者にとっては心理的な負担が大きくなる可能性があります。
まとまった資金があり、長期的な視点で価格変動リスクを受け入れられる方に適した方法と言えるでしょう。
積立投資の特徴
積立投資は、毎月1万円など決まった金額を定期的にコツコツと投資し続けるスタイルです。
この方法の最大のメリットは、「ドルコスト平均法」の効果によって、価格変動リスクを抑えられる点にあります。ドルコスト平均法とは、価格が高いときには少なく、価格が安い時には多く購入することで、平均購入単価を平準化する手法です。これにより、一括投資で起こりがちな「高値掴み」のリスクを避けやすくなります。
また、少額から始められるため、投資初心者やまとまった資金がない方でも無理なく資産形成をスタートできるのが魅力です。一度設定すれば自動で買い付けが行われるため、投資のタイミングに悩む必要もありません。
デメリットとしては、相場が一貫して上昇する局面では、早期に全額を投資した一括投資に比べてリターンが小さくなる可能性があります。しかし、長期的に安定した資産形成を目指す上では、非常に有効な手法と言えます。
どちらが向いている?性格・資金・目的で選ぼう
一括投資と積立投資のどちらを選ぶべきかは、資金状況、リスクに対する考え方、そして投資の目的によって決まります。
一括投資が向いているのは、退職金などでまとまった資金があり、それを積極的に増やしたいと考えている人です。投資経験があり、市場がある程度下落しているタイミングを狙えるなど、リスクを許容できる場合に有効です。複利効果を早期から最大限に活かせるため、長期で大きなリターンを目指せます。
一方、積立投資は、投資初心者や、まだまとまった資金がない20代・30代の人に特におすすめです。毎月コツコツと無理のない範囲で投資を続けることで、リスクを抑えながら着実に資産を形成できます。市場のタイミングを計る必要がないため、精神的な負担も少なく、長期的に続けやすいのが特徴です。
最終的には、両者を組み合わせるという選択肢もあります。例えば、手元資金の一部を一括投資し、残りは毎月の収入から積立投資に回すといった方法です。
自身の状況に合わせて、最適なスタイルを見つけましょう。
おすすめのほったらかし投資方法
ほったらかし投資には様々な方法がありますが、特に初心者におすすめなのは、税制優遇制度を活用した積立投資や、リスクを抑えた一括投資です。
ここでは代表的な4つの方法、NISA、iDeCo、債券、貯蓄型保険について、それぞれの特徴を解説します。自身の目的やリスク許容度に合わせて最適な方法を選びましょう。
積立投資:NISA
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益(分配金や譲渡益)が非課税になる、国が設けた税制優遇制度です。通常、投資の利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内での取引ではこれが一切かからないため、効率的に資産を増やすことができます。
2024年から始まった新しいNISAでは、制度が恒久化され、非課税で保有できる期間も無期限になりました。年間投資枠も大幅に拡大し、「つみたて投資枠」で年間120万円、「成長投資枠」で年間240万円、合計で最大360万円まで投資が可能です。生涯にわたる非課税保有限度額は1800万円と設定されています。
特にほったらかし投資と相性が良いのが「つみたて投資枠」です。この枠では、金融庁が定めた長期・積立・分散投資に適した低コストの投資信託などを、毎月コツコツと積み立てていくことができます。
一度積立設定をすれば自動で買い付けが行われるため、手間なく非課税のメリットを享受しながら資産形成を進められます。
NISAでは一括投資もできる
NISAには「つみたて投資枠」だけでなく、「成長投資枠」が設けられており、こちらを活用することで一括投資も可能です。
成長投資枠は、年間240万円までの非課税投資枠があり、投資信託だけでなく個別株式やETF(上場投資信託)など、比較的幅広い商品に投資できます。まとまった資金がある場合、この成長投資枠を使って一度に投資することで、早期から大きな資金を運用に回し、複利効果を狙うことができます。
また、新NISAの大きな特徴として、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能な点が挙げられます。
例えば、ボーナスなどの臨時収入を成長投資枠で一括投資し、毎月の給与からはつみたて投資枠でコツコツ積立を行う、といった柔軟な使い方ができます。
積立投資:iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を作ることを目的とした私的年金制度です。毎月一定の掛金を拠出し、自分で選んだ金融商品で運用、その成果を原則60歳以降に受け取ります。
iDeCo最大のメリットは、強力な税制優遇にあります。具体的には以下の3つのメリットがあります。
- 掛金が全額所得控除:毎月の掛金がその年の所得から差し引かれ、所得税・住民税が軽減されます。
- 運用益が非課税:通常約20%かかる投資の利益が非課税となり、効率的に資産を増やせます。
- 受取時にも控除:年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」が適用され、税負担が軽くなります。
一方で、最大の注意点は、原則として60歳まで資金を引き出せないことです。
あくまで老後資金のための制度であるため、住宅購入資金や教育資金など、途中で必要になる可能性のある資金の運用には向いていません。
一括投資|債券
債券は、国や地方公共団体、企業などが資金を調達するために発行する「借用証書」のようなものです。投資家は債券を購入することで、発行体にお金を貸し付け、満期(償還日)まで定期的に利子を受け取り、満期日には額面金額(元本)が返還されます。
債券投資の最大のメリットは、安全性の高さにあります。特に国が発行する国債は、国が元本と利子の支払いを保証しているため、元本割れのリスクが極めて低いのが特徴です。このため、リスクをできるだけ抑えて着実に資産を守りたいと考える方に適しています。
一方で、デメリットはリターンが低いことです。株式投資などと比較すると、得られる利子は限定的であり、資産を大幅に増やすことには向きません。
ほったらかし投資としては、一度購入すれば満期まで保有し続けるだけで良いため、手間がかからないのが魅力です。
まとまった資金の安全な置き場所として、またはポートフォリオのリスクを抑えるための安定資産として活用するのが良いでしょう。
一括投資|貯蓄型保険
貯蓄型保険は、万が一の際の死亡保障などを確保しながら、同時に将来のための資金を貯蓄できる金融商品です。終身保険や個人年金保険などがこれに該当します。
メリットとしては、保険料を支払うことで、保障と資産形成を同時に行える点が挙げられます。特に変額保険のように、保険料の一部を投資信託などで運用し、運用成果次第で将来受け取る保険金や解約返戻金が増える可能性がある商品もあります。
一方で、手数料の高さと仕組みの複雑さに注意が必要です。支払う保険料には、保障のための費用や保険会社の運営経費などが含まれるため、純粋に投資に回る金額は少なくなります。
その結果、投資信託など他の金融商品と比較して、投資効率が劣るケースがほとんどです。
また、契約から早い段階で解約すると、支払った保険料の総額を下回る「元本割れ」を起こす可能性が高いです。流動性が低く、急な資金需要に対応しにくい点もデメリットと言えます。
投資を主目的とするならば、NISAなどを活用して低コストの投資信託を購入し、保障は別途、掛け捨ての保険で備える方が合理的でしょう。
ほったらかし投資で損しないためのポイント
ほったらかし投資で成功するためには、投資スタイルに応じた注意点を理解しておくことが不可欠です。積立投資では長期的な視点を持ち続けること、一括投資ではタイミングのリスクをどう管理するかが鍵となります。
積立投資の場合
積立投資で成功するための最も重要なポイントは、相場の下落局面に動揺せず、淡々と積立を継続することです。
積立投資は「ドルコスト平均法」のメリットを活かす手法です。価格が下がっている時は、同じ投資額でより多くの口数を購入できるため、むしろ「安く仕込むチャンス」と捉えるべきです。
多くの初心者は、価格が下落すると不安になって積立を停止したり、売却してしまったりしますが、これは最も避けるべき行動です。その後の相場回復の恩恵を受けられず、損失を確定させてしまいます。
また、長期的な視点を持ち続けることも不可欠です。数ヶ月や1年程度の結果で一喜一憂せず、10年、20年といったスパンで資産を育てていく心構えが求められます。
一括投資の場合
一括投資は、まとまった資金を一度に投じることで市場上昇の波に早く乗れるのが魅力です。投資元本全体が複利効果を享受できるため、長期的には積立投資より高いリターンを得られる可能性もあります。
一方で、投資直後の下落リスク(高値掴み)には注意が必要です。
一括投資で失敗しないための基本
- タイミングを完璧に狙わない:市場の底を読むのはプロでも難しいため、「成長が見込める資産を長期保有する」姿勢が大切です
- 15年以上の長期運用を前提に:短期の値動きに動揺せず、腰を据えて運用を続けましょう
- 余裕資金で投資する:生活費と切り分け、すぐ現金化しなくても困らない資金で運用するのが鉄則です
一括投資で成功するための工夫
- 商品選びは慎重に:自身の投資目的、リスク許容度に合わせた商品を選びましょう
- 完全放置は避ける:年に1回は運用状況をチェックし、バランスを確認することが大切です
- 市況を適度に把握する:経済ニュースや市場動向を意識し、必要に応じて柔軟に対応しましょう
- 専門家に相談する:判断に迷う場合は、IFA(独立系アドバイザー)など中立的な立場の専門家に相談を。自分に合った投資先やタイミングを見極めやすくなります
参考)よくある失敗例
ほったらかし投資で初心者が陥りがちな失敗は、主に3つのパターンに分類されます。
狼狽(ろうばい)売り
市場が一時的に大きく下落した際に、恐怖心から保有資産をすべて売却してしまうことです。長期投資では価格の変動はつきものであり、下落はむしろ安く買える好機です。
ここで売却してしまうと損失が確定し、その後の市場回復の恩恵を受けられなくなります
流行りのテーマへの高値掴み
メディアなどで話題になっている特定のテーマに関連する投資信託に、価格が上がりきったタイミングで投資してしまうことです。流行が過ぎ去ると価格が急落し、大きな損失を被る可能性があります。
ほったらかし投資の基本は、特定のテーマに偏らず、全世界の経済成長に広く分散投資することです。
手数料の高い商品を言われるがまま購入
金融機関の窓口などで勧められるがまま、手数料(信託報酬)の高い商品を購入してしまうケースです。長期運用において手数料はリターンを確実に蝕む要因となります。
勧められた商品を鵜呑みにせず、自分で商品の特徴をきちんと把握して判断しましょう
ほったらかし投資が向いている人・向いていない人
ほったらかし投資は、その手軽さから多くの人に推奨されますが、すべての人に最適なわけではありません。この投資スタイルが最も効果を発揮するのは、長期的な視点でコツコツ資産形成を目指せる人です。
一方で、短期的に大きな利益を求める人や、投資のプロセス自体を楽しみたい人には不向きかもしれません。
不安な場合はプロに相談で方針を確認する
「自分に合った投資方法がわからない」「始めてみたものの、このままで良いのか不安」と感じる場合、一人で悩まずに専門家に相談することをおすすめします。
金融機関の窓口やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)など、お金のプロに相談することで、客観的で専門的な視点からアドバイスを受けることができます。
彼らは多くの顧客の資産運用をサポートしてきた経験から、あなたの年齢、収入、家族構成、リスク許容度などを総合的に判断し、最適な資産配分や具体的な金融商品を提案してくれます。
特に、信頼できる専門家は、特定の金融商品を売ることだけが目的ではありません。あなたのライフプラン全体を見据え、長期的な資産形成のパートナーとなってくれるでしょう。
無料相談会やセミナーなどを活用し、まずは情報収集から始めてみるのも一つの手です。専門家の知見を借りることで、自信を持ってほったらかし投資を続けることができるようになります。
まとめ
ほったらかし投資は、専門的な知識や時間がなくても、誰でも手軽に始められる資産形成の有効な手段です。自動で積立・分散・再投資を行う仕組みと、長期運用による複利効果を活かすことで、着実に資産を増やすことが期待できます。
投資スタイルには「一括投資」と「積立投資」があり、ご自身の資金状況やリスク許容度に合わせて選ぶことが重要です。特に初心者の方には、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用した積立投資から始めることを推奨します。
ただし、「ほったらかし」といっても完全に放置するのではなく、年に1回程度の状況確認は必要です。市場の下落時に慌てて売却しないことや、成長が見込める商品を選ぶなど、損をしないためのポイントを押さえておきましょう。
もし不安な点があれば、金融機関の専門家に相談するのも一つの方法です。この記事を参考に、あなたも今日からほったらかし投資の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
»投資をするなら何がベスト?今すぐ無料診断
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。