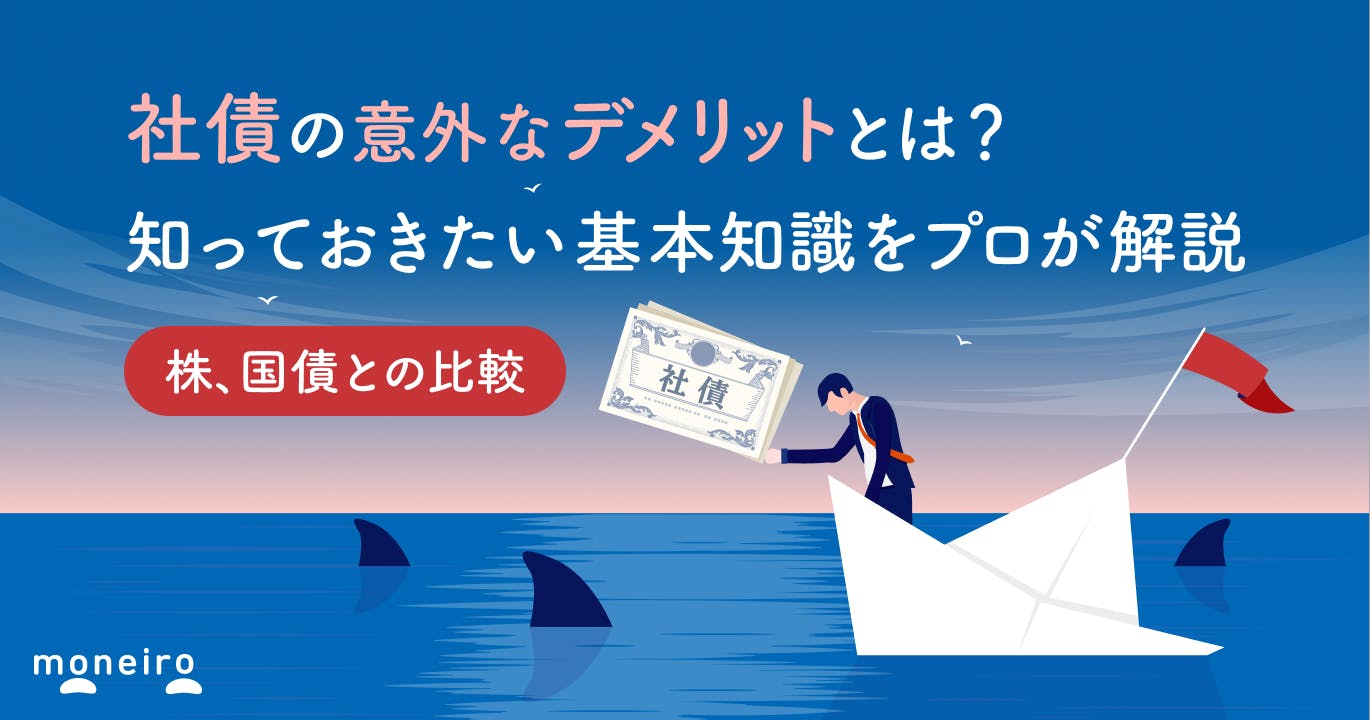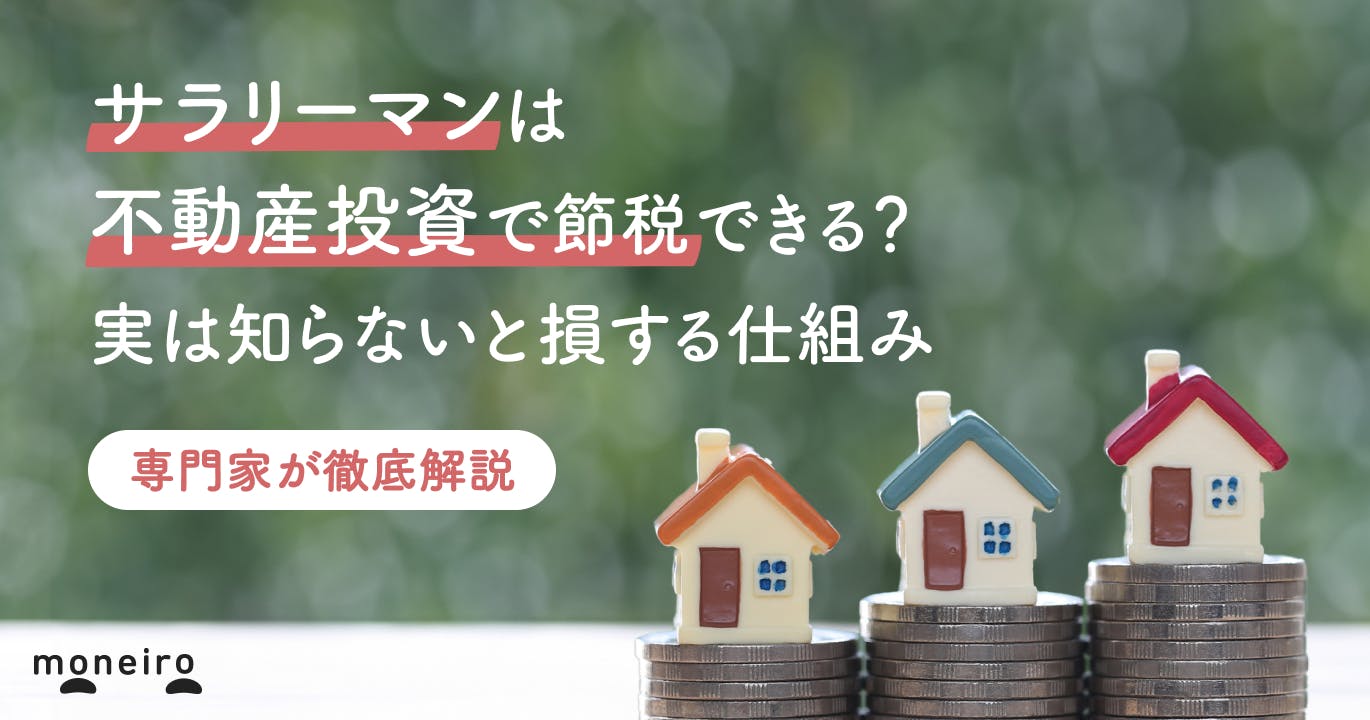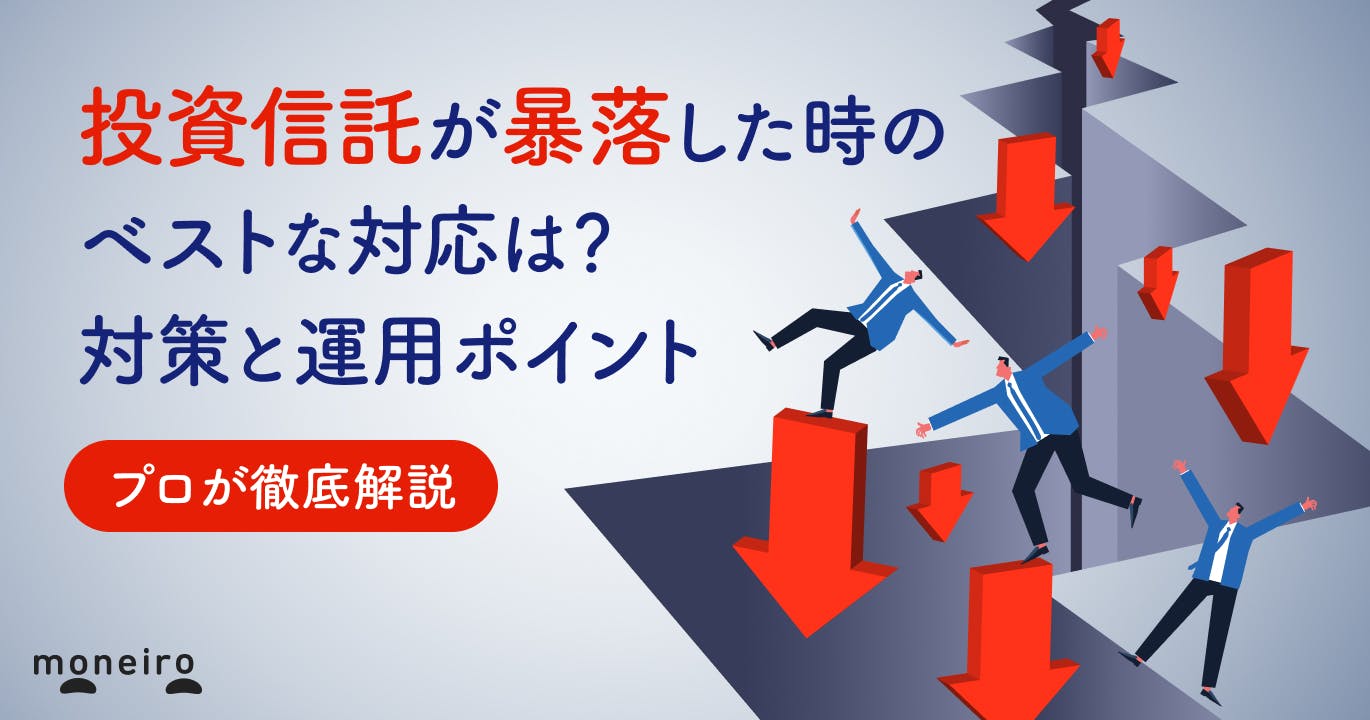リート(REIT)はおすすめしない?投資信託で損しないために知っておきたいリスクとメリット
>>どんな投資が向いている?3分でわかる投資診断
「リート(REIT)はおすすめしない」「やめたほうがいい」といった声を耳にして、不安を感じている人も多いでしょう。
リート(REIT)とは、投資家から集めたお金を不動産に投資し、賃貸収入や売却益を投資家に分配する不動産投資信託のことです。
リートは少額から不動産投資ができる便利な金融商品ですが、投資である以上、リスクやデメリットも存在します。
本記事では「リートはおすすめしない」と言われる理由を知りたい人に向けて、リートの基本知識、不動産への直接投資との違い、おすすめしないと言われる理由や注意点を投資のプロがわかりやすく解説します。
- リート(REIT)とは、投資家から集めた資金でオフィスビス、ホテルなどの不動産に投資し、賃料収入や売却益を投資家に分配する不動産投資信託のこと
- リートと不動産への直接投資の主な違いは「投資対象」「必要資金」「節税効果」など
- リートの主なデメリットは「不動産特有のリスク」「複利効果がない」など
不動産投資が気になるあなたへ
資産運用の不安を解消するために、さまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:iDeCoやNISAなど、相性の良い資産運用がわかる
▶500万円から始める債券投資セミナー:債券の活用法がわかる
▶資産運用の不安をプロに相談:自分専任の担当者に無料相談
リート(REIT)とは?仕組みと基本知識
リート(REIT)は、少額から始められる不動産投資の手段として、多くの投資家に利用されています。
リートの基本的な仕組みや投資対象の種類、エリアごとの特徴など、詳しく見ていきましょう。
リートの仕組み
リート(REIT:不動産投資信託)とは、投資家から集めた資金をもとに、オフィスビル、マンション、商業施設、ホテルなどの不動産に投資し、そこで得られた賃料収入や売却益を投資家に分配する仕組みの金融商品です。
また、リートは「不動産投資信託(Real Estate Investment Trust)」の略で、日本語では「不動産投信」とも呼ばれています。
リートは証券取引所に上場されており、株式と同じように市場で売買できます。商品によっては数万円から購入できるものもあり、不動産投資の中では比較的手軽に始められる点が魅力です。
ただし、リートの価格は不動産市場の動向や金利の変化によって変動します。そのため、元本割れのリスクや分配金の増減といったリスクも伴います。
①投資対象不動産の種類
リートの投資対象となる不動産にはさまざまな種類があり、主に「単一用途特化型」と「複数用途型」の2つに分類されます。
不動産の種類によって収益の安定性やリスクが異なるため、理解しておくことが大切です。
- 単一用途特化型リート…特定の用途に特化したリート。オフィスビル、住宅、ホテルなど、1つの用途に限定された不動産に投資します。特定分野に集中することで専門性を活かせる一方、市場環境の変化による影響を受けやすい側面もあります。
- 複数用途型リート…数の用途の不動産を組み合わせて投資するリートです。「住宅とオフィス」「ホテルと商業施設」など、多用途に分散投資することで、特定市場の影響を抑え、リスクの軽減を図る狙いがあります。
それぞれの特徴を理解したうえで、自分の投資スタイルや目的に合ったリートを選ぶことが大切です。
②投資対象不動産のエリア
リートが投資する不動産のエリアも、運用成績やリスクに大きな影響を与えます。主に以下の3つのタイプに分類されます。
- 首都圏中心型…東京をはじめとする首都圏エリアに集中投資するリートです。需要が安定しているため収益のブレが小さく、リスクを抑えたい投資家に人気です。一方で利回りはやや低めになる傾向があります。
- 地方都市型…地方都市の不動産に投資するリートは、比較的高い利回りが期待できます。ただし、地域によっては空室リスクや賃料の下落リスクが高くなる点に注意が必要です。
- 海外型…海外の不動産に投資するリートで、国や地域によっては高い収益性が見込まれます。その反面、為替変動や海外情勢の影響を受けやすく、リスクも大きくなります。
投資エリアによって収益性やリスクのバランスが異なるため、自身の投資目的やリスク許容度に応じて選択しましょう。
不動産への直接投資とリート(REIT)の違い
不動産への直接投資は、必要資金・管理の手間など、誰もが気軽に始めることができないという点があります。一方で、家賃収入・資産価値の上昇など大きな利益を得やすく、節税効果もリートと比べると良い傾向にあります。
リート(REIT)の場合は投資信託の仕組みとして、少額から気軽に不動産投資を始めることができます。また、管理などをプロに任せることができます。
しかし、不動産への直接投資と比べ、節税効果は小さいことが欠点と言えるでしょう。
リート(REIT)はおすすめしない?デメリットと注意点
リート(REIT)には多くのメリットがある一方で、デメリットもあります。
知っておきたいデメリット・注意点について解説します。
不動産特有のリスクがある
不動産投資は、安定した収益が期待できる一方で、株式や投資信託にはない独自のリスクも多く存在します。
特に注意しておきたいリスクとして「金利変動リスク」「地震・火災リスク」「倒産・上場廃止リスク」について見ていきましょう。
金利変動リスク
不動産投資でローンを利用する場合、金利の動向が返済額に大きな影響を与えます。特に変動金利で借り入れている場合は、金利が上昇すれば返済額も増加するため、収支バランスが崩れる可能性があります。
例えば、利回りが高くてもローンの金利が上がれば、実質的な利益は縮小します。
将来的な金利上昇リスクを見越したシミュレーションや、固定金利との比較検討が重要です。
地震・火災リスク
日本は世界的に地震が多い国の一つです。地震によって、不動産が全壊するケースも多く存在し、一般的には震度6強以上の地震があると、家が壊れてしまうと言われています。
地震・火災などの災害リスクは不動産特有のリスクと言えるでしょう。
こうしたリスクに備えるには、地震保険や火災保険への加入はもちろん、物件選びの段階で耐震性やハザードマップの確認を行うことが大切です。
倒産・上場廃止リスク
リートへの投資では、運用会社の経営状況も重要なリスク要因となります。リートは証券取引所に上場しているため、運用会社が倒産したり上場廃止になった場合、投資元本が大きく毀損する恐れがあります。
株式と同様に市場価格が変動するため、日々の価格推移にも注意が必要です。運用実績や資産内容、財務健全性を確認し、信頼できる銘柄を選ぶようにしましょう。
複利効果が得られない
リートの特徴の一つは、得られた利益を「分配金」として投資家に定期的に支払う点です。この仕組みにより、利益を再投資することで得られる「複利効果」は基本的に期待できません。
一方、投資信託のなかには、分配金を再投資できるタイプがあり、複利の力で資産をじっくり増やす運用が可能です。
ただし、リートは定期的に分配金を受け取れるため、「日々の収益を実感したい」「定期収入を得ながら運用したい」という人には適した投資手段といえるでしょう。
節税メリットが小さい
不動産投資には節税のイメージがありますが、リートではその効果は限定的です。
実物不動産への投資では、建物の減価償却費などを経費として計上できるため、課税所得を抑えることが可能です。
しかし、リートは法人が不動産を運用しており、投資家個人が節税できるわけではありません。
そのため、節税を重視する方には不向きですが、「少額で不動産投資を始めたい」「運用の手間をかけたくない」といったニーズには非常に適した投資商品です。
リート(REIT)に投資するメリット
不動産投資と聞くと、多額の資金や複雑な管理体制が必要で、始めるのが難しいというイメージを持つかもしれません。
少額から手軽に不動産に投資できるリート(REIT:不動産投資信託)のメリットについて、詳しくご紹介します。
少額・手間なしで不動産投資ができる
リートは、実物の不動産を直接購入するのではなく、複数の投資家から集めた資金で運用会社が不動産に投資します。そのため、数万円程度の少額からでも投資が可能です。
また、物件の選定・管理・入居者対応などの業務は専門の運用会社が行うため、投資家自身に手間がかかることはほとんどありません。
これにより、不動産投資のハードルが大きく下がります。
換金性が高く、売買しやすい
リートは証券取引所に上場しており、株式と同じように市場で自由に売買できます。証券口座と資金があれば、平日の取引時間内であればいつでも売買可能です。
また、多くの投資家が取引しているため流動性が高く、現金化しやすい点もメリットのひとつです。さらに、少額からの取引や手数料の低さも、売買のしやすさに繋がっています。
高い利回り・安定した分配金が期待できる
リートの主な収益源は、商業施設やオフィスビル、住宅などの賃貸収入です。複数の不動産に分散して投資されていることが多いため、特定物件に空室が出ても全体の収益に与える影響は限定的です。
また、日本のリート(J-REIT)は、収益の90%以上を分配することが、税制上の優遇を受けるための条件とされています。
この仕組みによって、投資家は比較的高い利回りや安定した分配金を得やすくなっているのが特徴です。
インフレに強い
インフレ(物価上昇)が進むと、不動産の賃料も上昇する傾向にあります。そのため、家賃収入を主な収益源とするリートは、インフレ局面でも実質的な資産価値を維持しやすい特徴があります。
同様にインフレに強い資産には金(ゴールド)や原油などのコモディティもありますが、債券のようにインフレに弱い資産と組み合わせることで、全体のポートフォリオの安定性を高めることが可能です。
リート(REIT)を選ぶ時のポイント
リート(REIT:不動産投資信託)を選ぶにあたって、抑えておくべき4つのポイントについて、投資のプロが徹底解説していきます。
①利回り
リートに投資する際、「利回り」は最も注目すべき指標のひとつです。
投資した金額に対して、どれだけの収益(分配金など)が得られるかを示す割合です。金融商品を比較・選定するうえで欠かせない情報といえるでしょう。
ただし、利回りが高いからといって安心とは限りません。利回りが高いリートは、物件の立地やテナントの安定性に課題がある場合や、将来的な分配金の減少リスクがあるケースも見受けられます。
リートを選ぶ際は「利回りが高い=安全」とは限らないことを理解し、自分のリスク許容度に合った商品を選ぶことが大切です。
②時価総額・NAV倍率
「時価総額」と「NAV倍率」も、リートの価値や市場での評価を判断するうえで重要な指標です。
時価総額とは、リートの全体的な市場価値を表します。一般的に、時価総額が大きいリートは規模が大きく安定性が高いとされ、逆に小さいものは成長余地があると考えられます。
また、NAV倍率(純資産倍率)は、リートの市場価格と実際の不動産価値(純資産)の比率を示すものです。1倍を基準に、1を下回れば割安、上回れば割高と判断されることがあります。
ただし、これらの指標はあくまで参考材料のひとつです。単独で判断するのではなく、他の情報と合わせて総合的に評価しましょう。
③格付け
リートには「格付け」と呼ばれる信用評価が付けられることがあります。これは、そのリートが借入金をきちんと返済できるかどうかを示す重要な指標です。
リートは複数の不動産を取得・運用するため、一定の借入を伴います。そのため、財務の健全性や返済能力を示す格付けは、投資家にとって非常に有益な判断材料となります。
格付けは「AAA」「AA」「A」「BBB」「BB」などのランクで表され、一般的に評価が高いほど信用力が高いとされています。
安全性を重視する場合は、格付けが高いリートを選ぶのが基本です。自身のリスク許容度を踏まえて選びましょう。
④運用会社の情報
リートを選ぶ際には、その運用会社の実績や信頼性をしっかり確認することが不可欠です。なぜなら、リートの運用成績は運用会社の判断に大きく左右されるためです。
不動産の選定や売買のタイミング、テナントの管理など、すべての運用方針を決定しているのは運用会社です。
また、親会社が大手金融機関や不動産会社である場合は、資金力や管理体制の面で安心感があります。
投資を検討する際には、過去の運用実績、情報開示の丁寧さ、資産規模などもあわせてチェックしましょう。自分が信頼できる運用会社かを見極めることが大切です。
リート(REIT)はどんな人に向いていない?向いている?
少額から始められる点や、管理の手間がかからない点から注目を集めているリート(REIT)ですが、すべての人に向いているとは限りません。
リートに「向いていない人」「向いている人」の特徴を整理してご紹介します。
リートが向いていない人の特徴
リートは、証券取引所で売買される金融商品であり、価格が日々変動します。元本が保証されているわけではないため、「絶対に損をしたくない」という方には不向きです。
また、短期間で大きな利益を狙う投資スタイルにもリートは合いません。リートは長期的に安定した収益を目指す設計です。そのため、頻繁に売買を繰り返すと手数料やタイミングのずれによって損失が出る可能性があります。
価格変動に対して過度にストレスを感じる人や、一攫千金を狙いたいタイプの投資家には、別の金融商品を検討するのが良いでしょう。
リートが向いている人の特徴
リートは、不動産に興味があるものの、まとまった資金や管理の手間をかけたくない人にぴったりの投資商品です。証券口座と少額の資金があれば、数万円から始めることができます。
また、リートはほとんどの場合、年2回分配金を得られる仕組みになっているため、定期的に収益を受け取りたい方にも適しています。
流動性が高く、必要な時に現金化しやすい点も魅力のひとつです。
長期的に資産を育てたい人や、副収入として分配金を得たい現役世代の方にとって、リートは非常に親和性の高い投資先といえるでしょう。
リート(REIT)以外にも?自分に合う金融商品の選び方
投資を始めるにあたっては、リート(REIT)以外にもさまざまな選択肢があります。株式、投資信託、債券、外貨建て商品、保険商品など、それぞれ特徴が異なります。
大切なのは、自分に合った商品を選ぶことです。そのためには、以下の3点を明確にしましょう。
- 投資の目的(例:老後資金形成、子どもの教育費準備)
- リスク許容度(価格変動にどこまで耐えられるか)
- 投資可能な金額・期間
例えば、安定性を重視したい人には、債券や分配型の投資信託などが向いています。一方、ある程度のリスクをとって資産を増やしたい人は、株式やREITなどの成長性のある商品を検討すると良いでしょう。
ただし、REITの中でもリスクレベルはさまざまです。「高利回りだが価格の変動が大きい銘柄」もあれば、「安定的な分配金を重視した銘柄」もあります。
初心者が自分だけで最適な商品を選ぶのは難しいことも多いため、判断に迷った時は専門家の力を借りるのも選択肢のひとつです。
悩んだ時はプロに相談がおすすめ
「投資信託に興味はあるけれど、どの銘柄を選んだら良いかわからない」「何を基準に比較すれば良い?」と悩んだ時は、マネイロのような投資アドバイザーに相談するのがおすすめです。
リートは、利回りや時価総額、NAV倍率、格付け、運用会社の違いなど、比較検討するポイントが多く、初めての方にとっては判断が難しいこともあります。
マネイロでは、投資信託はもちろん、債券・保険など幅広い金融商品の相談が可能です。
自分に合った商品を選びたい時や、不安や疑問を解消したい時は、気軽にプロの意見を聞いてみましょう。
まとめ
リート(REIT)は、少額から始められる上に、物件の運用や管理の手間がかからない、手軽な不動産投資の手段です。
証券口座があれば数万円からでも始めることができ、オフィスビルや住宅、商業施設といった多様な不動産に間接的に投資できます。
特に、賃料収入などをもとに高い分配金が期待できる点は、老後資金の準備や副収入の確保といった目的にも役立ちます。
一方で、価格変動リスクや複利効果の欠如、節税メリットの少なさといったデメリットも存在します。リートの仕組みやリスクを正しく理解したうえで、自分に合った投資スタイルを見つけることが大切です。
迷った時は専門家に相談することで、より安心して投資を進めることができるでしょう。
不動産投資が気になるあなたへ
資産運用の不安を解消するために、さまざまなサポートを無料でご提供しています。
▶3分投資診断:iDeCoやNISAなど、相性の良い資産運用がわかる
▶500万円から始める債券投資セミナー:債券の活用法がわかる
▶資産運用の不安をプロに相談:自分専任の担当者に無料相談
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
長井 祐人
- ファイナンシャルアドバイザー
日本大学国際関係学部卒業後、東洋証券株式会社に入社。国内外株式、債券、投資信託、保険商品の販売を通じ、主に個人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。特に中国株・投資信託の提案を得意とし、自身でも幅広く投資を行ってきたため、豊富な金融知識を活かした顧客ニーズに沿う提案が強み。現在は個人向け資産運用のサポート業務を行う。3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有