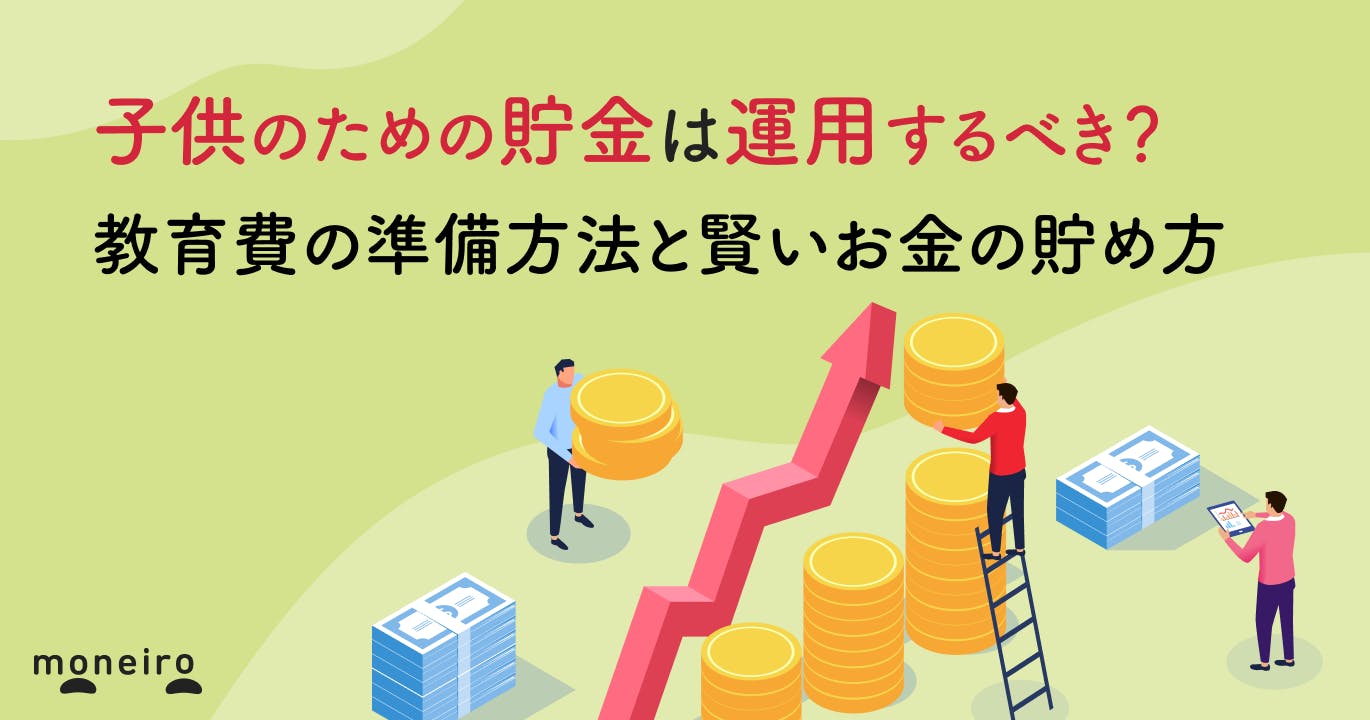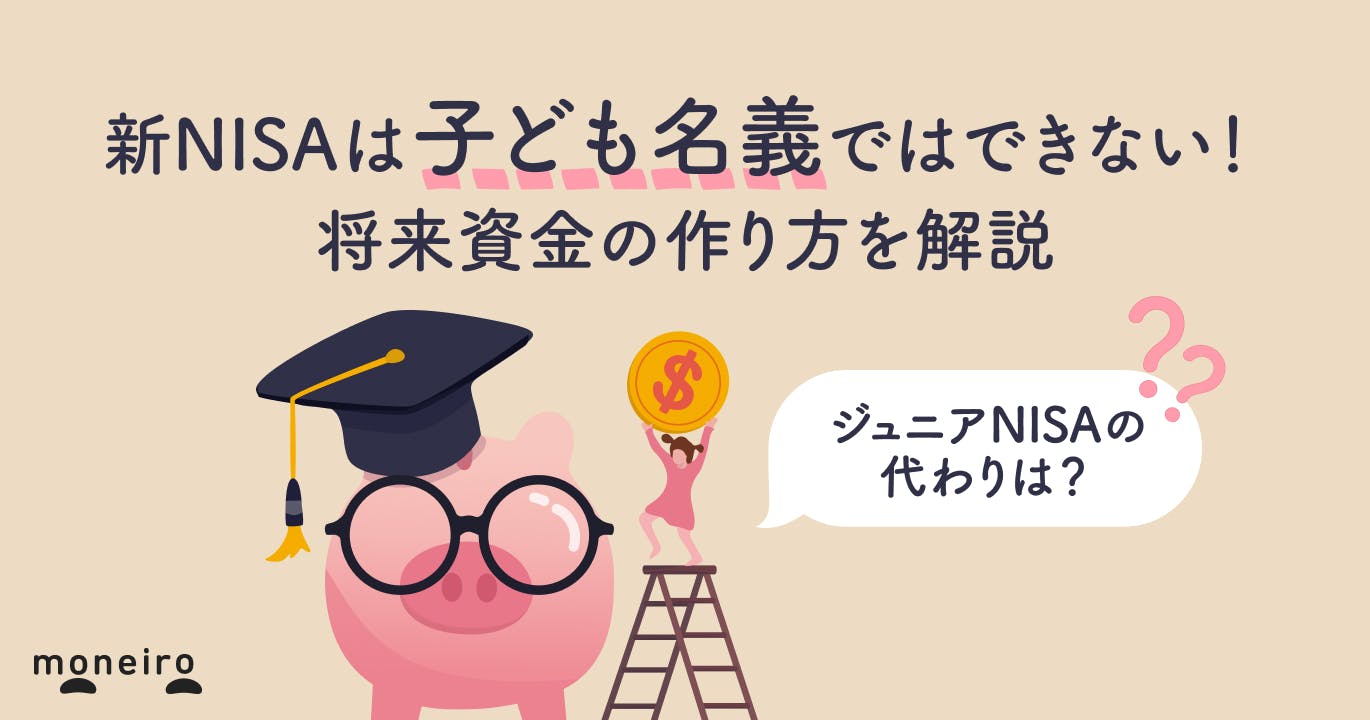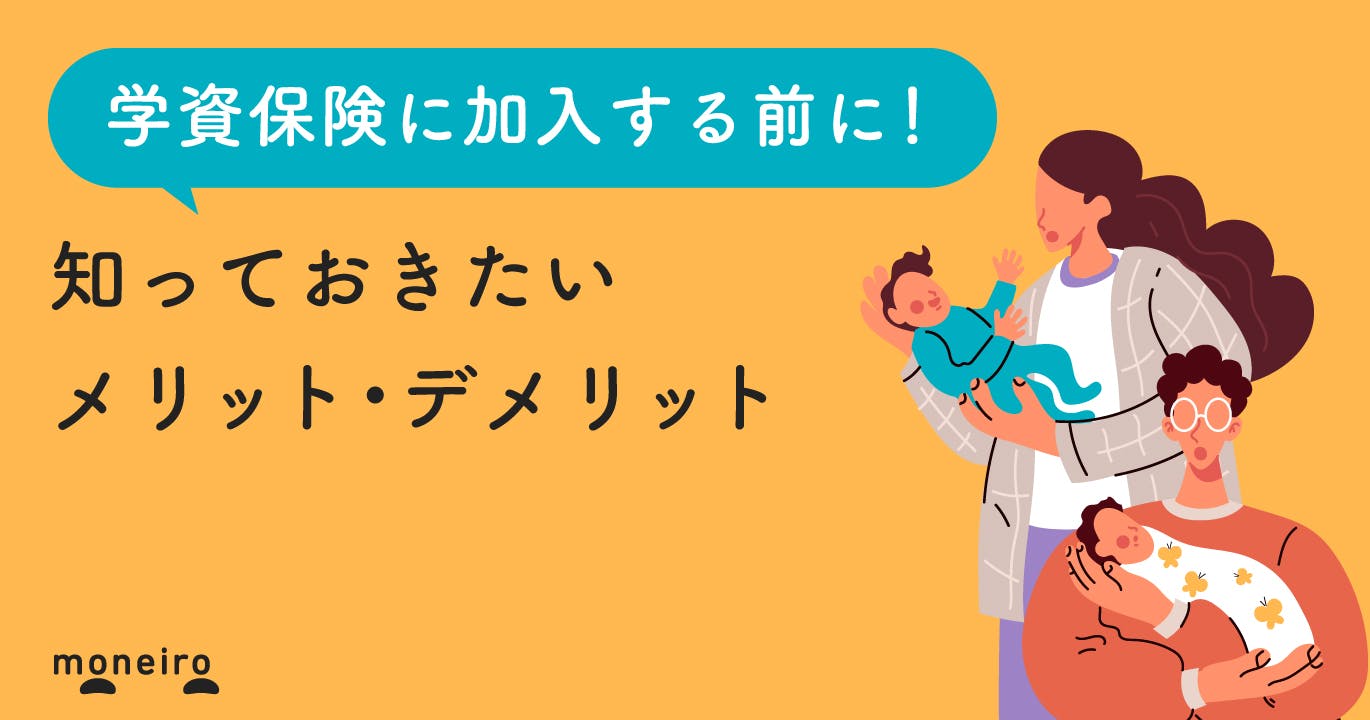子どもでも投資は始められる?始める上でのメリットや注意点を解説
≫将来の資金は足りる?あなたの不足額を診断
「子どもに投資を教えたいが、ジュニアNISAが終了してしまった」「教育資金を効率よく準備する方法を知りたい」といった疑問を持つ親御さんは多いのではないでしょうか。子どもの資産形成や金融教育をどう進めるかはこれからの社会での大きな課題といえます。
そこで本記事では、子どもの投資の始め方、ジュニアNISA終了後の最適な「NISA活用術」を、最新の税制改正動向(令和7年度改正、令和8年度要望)や、贈与税、扶養控除のルールを含めて詳しく解説していきます。
- ジュニアNISA終了後の、教育資金準備や金融教育における最適な投資方法
- 子どもの投資で注意すべき税務上のルール
- 金融庁が要望している「こども支援NISA」の具体的な構想や、今後の動向
子どもの投資が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
子どもの投資は0歳から可能!まずは基本を知ろう
子どもが投資を始めることは、親権者の管理のもと、0歳から可能です。未成年者が投資を行うには、親権者の同意を得た上で、証券会社等で子ども名義の「未成年口座(特定口座または一般口座)」を開設することが必要になります。
未成年口座を開設し、子ども名義で投資を始めるには、親権者(法定代理人)の同意が必須です。また、子ども名義で銀行口座を開設し、投資資金の入金経路を確立する必要があります。
重要な点として挙げられるのが、未成年口座での取引の主体は、あくまでも未成年者本人ではなく、原則として親権者が運用・管理を行うことです。親権者は、子どもの利益のために、その資金を適切に運用する義務を負います。
ジュニアNISA終了後、子どもの投資はどう考えるべき?
2023年末をもって、未成年者少額投資非課税制度であるジュニアNISAの新規投資枠は終了しました。これは、NISAの抜本的な拡充・恒久化、そして2024年からの新しいNISAへの一本化が進められたことによる措置です。
ジュニアNISAの終了により、未成年者の非課税枠を活用した資産形成手段は一時的になくなりましたが、NISAの普及をさらに進め、あらゆる世代の長期・安定的な資産形成を支援するため、制度のさらなる充実を図る必要性が認識されています。
これらを踏まえ、ジュニアNISA終了後の「子どもの投資」を考える際には、目的を以下の2つに分けて整理することが重要です。この記事でも詳しく解説していきます。
- 教育資金の準備:親名義の非課税枠を活用し、効率的な資産形成を目指す
- 金融教育の実施:子ども名義の口座を利用し、投資体験を通じて金融リテラシーを育む
こども支援NISAの構想
金融庁は、2025年8月に公表した「令和8(2026)年度 税制改正要望」において、「資産運用立国」の推進を主要項目の1つとして掲げ、NISA対象商品の拡充を含む制度の充実を要望しています。
この制度充実の要望項目の1つとして、「こども支援の一環としての、つみたて投資枠における対象年齢等の見直し」が挙げられています。これは、NISAの普及をさらに進め、これから資産形成を始めようとする若年層などを含め、あらゆる世代の長期・安定的な資産形成を支援するため、NISAの一層の充実を図るという方針に基づいています。
現行の新NISAの対象年齢は18歳以上とされていますが、今後、子どもの資産形成を支援する観点から、未成年者向けの非課税制度の再構築や、つみたて投資枠の対象年齢を18歳未満に引き下げるなど、さらなる制度改正の動向が注目されます。
子どもの投資を始める3つのメリット
子どものために投資を始めることには、単なる資金準備にとどまらない、重要なメリットが3つあります。
メリット1:教育資金を効率的に準備できる可能性がある
大学入学資金や留学費用など、将来的にまとまった資金が必要になる教育資金の準備において、貯金だけではインフレの影響や低金利に対応しきれないリスクがあります。投資を活用することで、元本に加え、運用益を得ることができ、教育資金をより効率的に準備できる可能性があります。
特に親名義のNISAを活用すれば、その運用益が非課税となるため、資金効率を最大化できるというメリットがあります。
メリット2:「時間」を味方にできる
子どもの投資は、親の投資と比較して、圧倒的な「時間」の優位性があります。0歳から始めれば、成人するまでの18年間、またはそれ以上にわたって長期投資を行うことが可能です。投資期間が長期にわたることで、運用益がさらに利益を生む「複利効果」を最大限に享受でき、時間とともに資産が雪だるま式に増加していく効果が期待できます。
メリット3:生きた「金融教育」になる
投資は、子どもにとって生きた「金融教育」の機会となります。親が子どもと一緒に投資先の企業や経済ニュースについて話し合うことで、子どもは社会や経済の仕組みに興味を持つきっかけを得ることができます。
例えば、身近な商品を作っている会社の業績や株価変動を観察し、それが世界情勢や消費者の動向とどのように関わっているかを学ぶことで、実践的な金融リテラシーを高めることにつながります。
≫将来必要な額はいくら?あなたの不足額を診断
【目的別】子どもの投資を始める2つの方法
ジュニアNISAが終了した現在、子どもの資金準備と金融教育という2つの目的に対し、以下の具体的な方法が最適解となります。
方法1:教育資金の準備なら「親名義のNISA」が最適解
子どもの教育資金を準備する上で、現時点での最大の代替策は「親名義の新NISA」を活用することです。新NISA制度は、生涯非課税保有限度額が1800万円(うち成長投資枠は1200万円)と非常に大きく設定されており、親が柔軟に運用・管理できるため、子どもの進路や資金が必要になるタイミングを調整しやすいというメリットがあります。
親が自身の非課税枠の中で子どもの教育資金を貯めることで、運用益が非課税となる恩恵を受けつつ、必要となるまで資金を確保しておくことができます。
一方、子ども名義の未成年口座を利用する場合、運用益は課税口座として利益に対して税金がかかるため、長期的な教育資金準備においては、税制上の優遇がある親名義のNISAのほうが有利であるといえます。
方法2:金融教育なら「未成年口座(課税口座)」の活用
子ども自身に投資を体験させ、金融リテラシーを育むことが主な目的であれば、「未成年口座(課税口座)」を活用するという選択肢があります。
メリットは、子どもが自分のお年玉やお小遣いといった自分のお金で実際に投資を学ぶ経験ができる点です。これにより、経済ニュースや企業の活動に対する関心が深まります。
デメリットとしては、得られた利益に対して税金がかかること、そして未成年者であるため、親による口座管理や投資判断のサポートが必須となることが挙げられます。教育目的であれば、少額から始めるのが適切でしょう。
子どもの投資が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
子どもの投資で絶対注意すべき税金・扶養のルール
子どもの名義で資産運用を行う場合、家計全体の税負担に影響を与える税務上のルールを理解しておくことが不可欠です。
贈与税:年間110万円の壁と「名義口座」のリスク
親が子ども名義の口座に資金を拠出することは、原則として贈与にあたります。日本の贈与税には基礎控除があり、年間110万円まで非課税となります。この基礎控除額を超えて贈与を行うと、贈与税が発生します。
また、年間110万円以下であっても、その資金を親が管理し、子どもがその資金の存在や利用について認識していない場合、税務署から「名義預金」と見なされるリスクがあります。名義預金と判断された場合、将来的に親の相続財産として扱われ、相続税の課税対象となる可能性があるため、資金の出所や管理方法を明確にし、贈与の意思を証明できるよう備えることが重要です。
利益にかかる税金:20.315%と確定申告の要否
未成年口座が新NISAのような非課税制度ではない課税口座である場合、株式や投資信託の売却益や配当金・分配金といった所得に対して、原則として所得税・住民税等が合計20.315%の税率で課税されます。
なお、金融庁は現在、「令和8(2026)年度 税制改正要望」において、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備を図る観点から、デリバティブ取引や預貯金等にまで損益通算範囲を拡大する「金融所得課税の一体化」を要望しています。
また、暗号資産取引についても、必要な法整備と併せて、分離課税の導入を含めた課税の見直しを行うことを要望しており、将来的に金融商品の税制環境が変わる可能性があります。
扶養控除(税制):合計所得金額58万円の壁
子どもの所得が一定額を超えると、親が税制上の扶養控除の対象から外れてしまうため、親の税負担が増加する可能性があります。
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除が見直されたことに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も改正されました。
具体的には、扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額の要件は、改正前の48万円以下から、令和7年分以後については58万円以下に引き上げられています。子ども名義の口座の運用益や給与所得などを合算した年間合計所得金額がこの58万円を超えると、親は扶養控除を受けられなくなります(※確定申告が必要な場合)。
19歳以上23歳未満の子に関する特例措置
また、令和7年度税制改正では、「特定親族特別控除」が創設されました。これは、居住者が特定親族(19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき63万円を限度として控除するというものです。
社会保険の扶養(健康保険):年間収入130万円の壁
この年間収入には、給与所得だけでなく、投資による収益(課税対象となる利益)も含まれる場合があるため、特に子どもがアルバイト等で給与を得ている場合は、総収入が130万円を超過しないよう、注意深く管理する必要があります。
この年間収入には、給与所得だけでなく、投資による収益(課税対象となる利益)も含まれる場合があるため、特に子どもがアルバイト等で給与を得ている場合は、総収入が130万円を超過しないよう、注意深く管理する必要があります。
【実践編】子どもへの「投資教育」の具体的な始め方
投資教育は知識の伝達だけでなく、実践的な体験を通じて理解を深めることが重要です。以下に具体的なステップを紹介します。
≫将来必要な額はいくら?あなたの不足額を診断
Step1. お金の「流れ」を理解させる
まずは、お金が社会でどのように流れているかを理解させることが基本です。「お小遣い」を単なる「毎月もらえるもの」ではなく、労働や提供された価値の対価として捉えさせることが重要です。
例えば、日々の買い物を通して、企業が商品やサービスを生み出し、消費者がそれを購入し、企業活動を通じて賃金や配当としてお金が循環しているといった、お金の「流れ」の全体像を理解させることを重視しましょう。
Step2. 「投資」の基本をインプットする
投資とは何か、貯金とどう違うのか、そして投資に伴うリスクの概念(増えることもあれば減ることもある)について、子どもにも分かりやすい方法で伝えるのが効果的です。
子ども向けに書かれたお金の本を読むこともよいですが、モノポリーや人生ゲームといったボードゲームを活用することで、お金や経済の仕組みを楽しく学ぶことができます。
Step3. 少額で「体験」させる
学んだ知識を定着させるためには、実際に少額で投資を体験させることがもっとも効果的です。未成年口座を活用し、子ども自身が興味を持った企業や、日常でよく利用する企業に少額から投資をさせてみましょう。
実際に投資をすることで、株価や経済ニュースが自分事となり、経済的な判断力を育むことにつながります。無理のない範囲で、継続的に投資を続けることが、長期的な資産形成の鍵となります。
子どもの投資に関するQ&A
子どもの投資に関するよくある質問に回答します。
Q. 子ども名義の口座の運用は、親が代行してもいい?
はい、子どもが未成年である限り、法律行為能力の制限があるため、子ども名義の未成年口座の運用は、親権者が法定代理人として代行して行う必要があります。
親権者は、子どもの利益のために、その資金を善良な管理者としての注意義務をもって運用する責任があります。ただし、親の財産と混同されないよう、資金の出所や管理状況を明確にし、名義預金と見なされるリスクを避ける必要があります。
Q. 子どもが成人(18歳)になったら、未成年口座はどうなる?
子どもが成人年齢である18歳に達すると、未成年口座は自動的に本人名義の口座に切り替わります。成人後は、親権者の管理下を離れ、子ども本人が口座の運用や管理、取引に関する一切の決定を行う主体となります。
この移行のタイミングで、子ども本人がNISA口座を開設し、それまでの課税口座の資産をどのように運用していくか、親子で今後の資産運用戦略について話し合うことが重要です。
未成年口座(課税口座)で保有している株式や投資信託を、直接NISA口座に移管(ロールオーバー)することはできません。NISA口座で運用したい場合は、一度課税口座の資産を売却して現金化し、その資金で新たにNISA口座で買い直す必要があります。
Q. 子どもへの投資、いくらから始められる?
投資は非常に少額から始めることが可能です。多くの証券会社では、投資信託の積立購入を100円や1000円といった単位から設定できます。
金融教育を目的とする場合は、子どもが納得して出せる額(例えば、お小遣いの一部など)からスタートし、投資体験を重視するのが良いでしょう。無理のない範囲で、継続的に投資を続けることが、長期的な資産形成の鍵となります。
まとめ
ジュニアNISAの新規投資枠は終了しましたが、子どもの資産形成においては、親名義の新NISA(生涯非課税保有限度額1800万円)を教育資金準備に活用し、未成年口座(課税口座)を金融教育のために少額で利用するという「二刀流」戦略が、現時点での最適解です。
特に、令和7年度税制改正により、扶養控除の対象となる扶養親族の合計所得金額要件が改正前の48万円以下から58万円以下に引き上げられているため、子ども名義で運用する場合は所得管理を徹底することが重要です。
また、金融庁は、NISAのさらなる拡充として、「こども支援の一環としての、つみたて投資枠における対象年齢等の見直し」を要望しており、今後、未成年者向けの非課税制度の再構築が期待されます。
今後、子どもへの金融教育はこれまで以上に重要になってきます。ぜひ長期的な視点をもって計画的に投資に触れる機会を作っていきましょう。
≫将来必要な額はいくら?あなたの不足額を診断
子どもの投資が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。