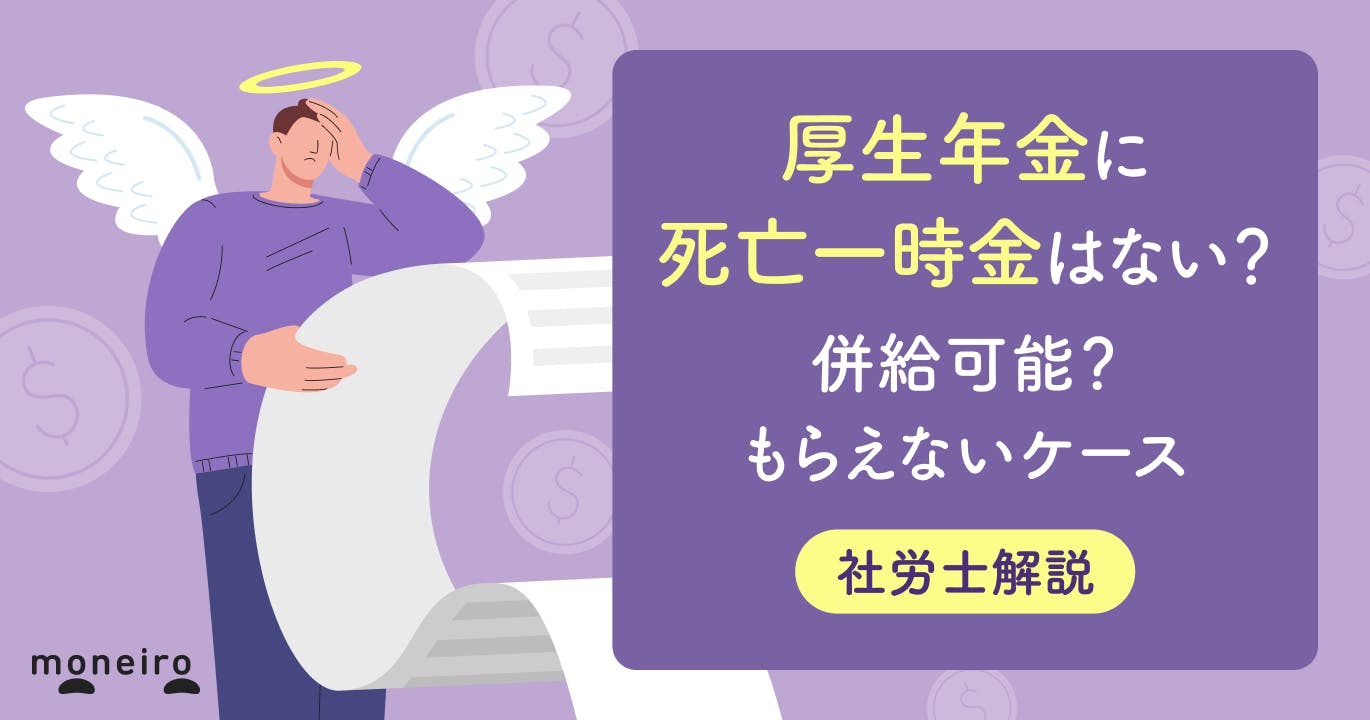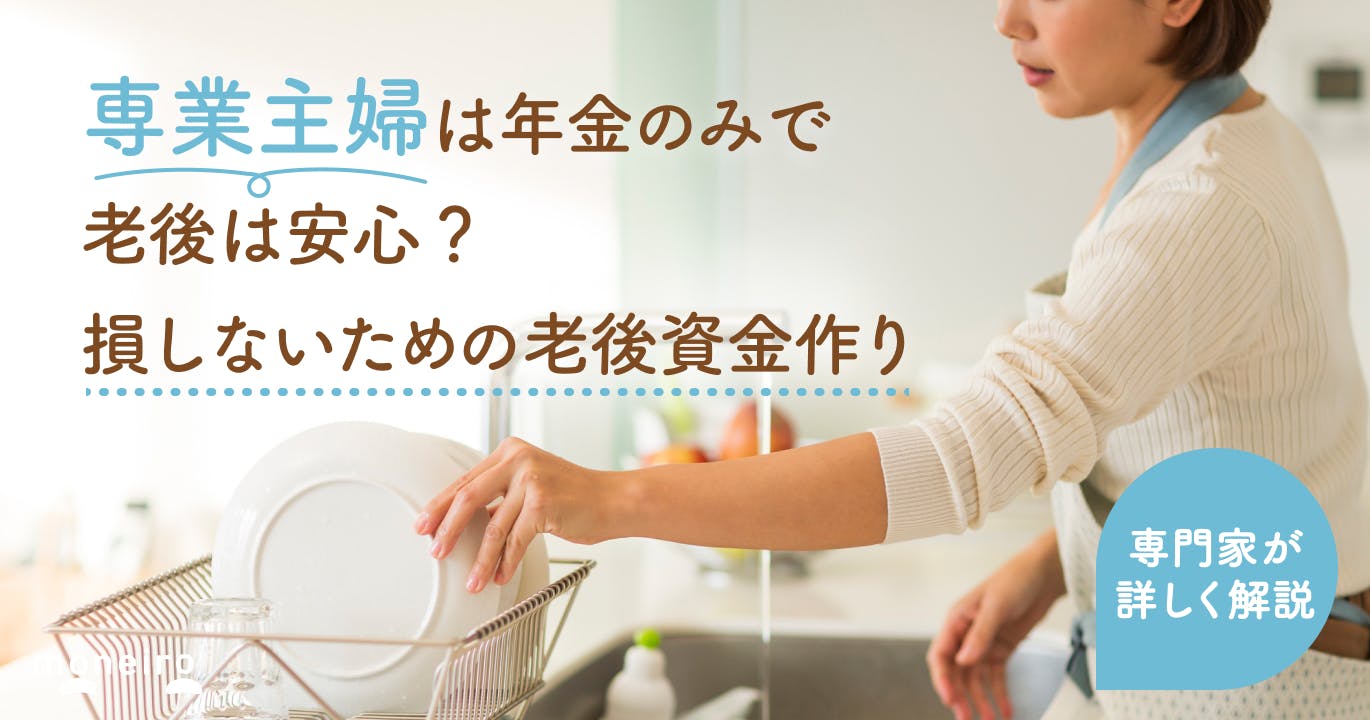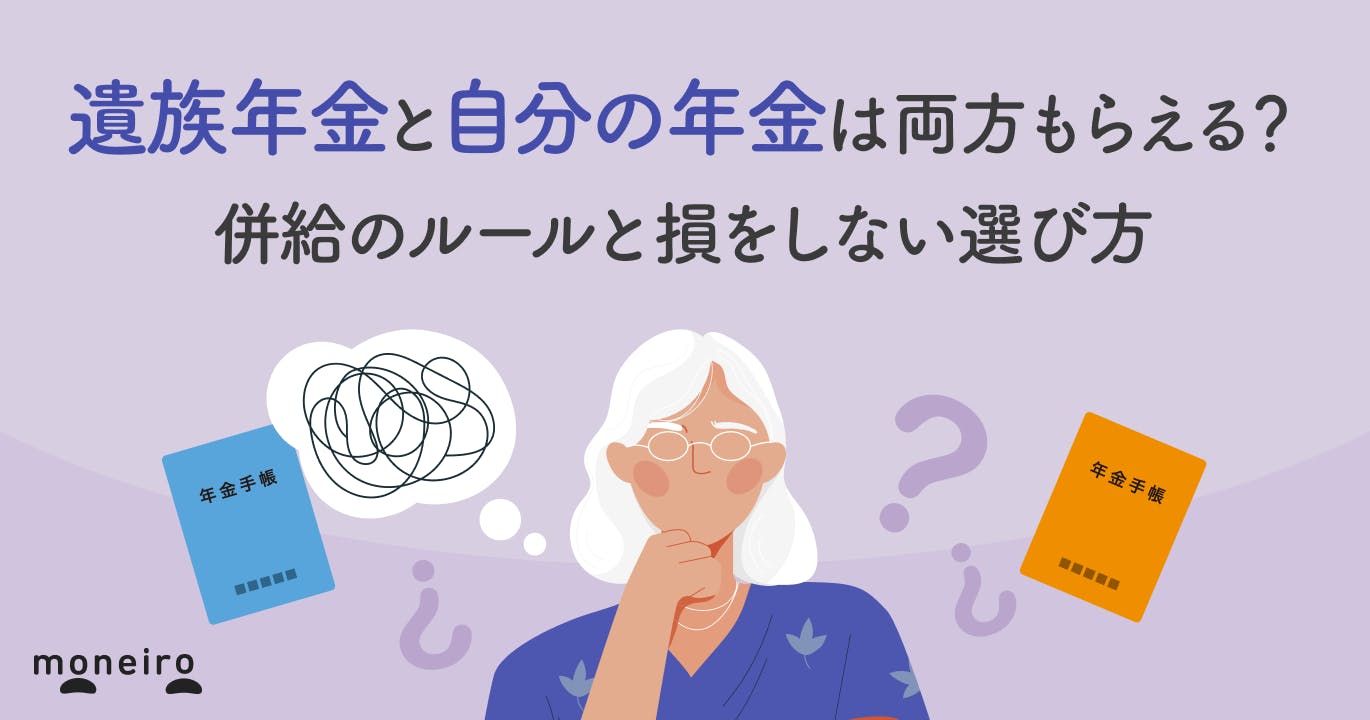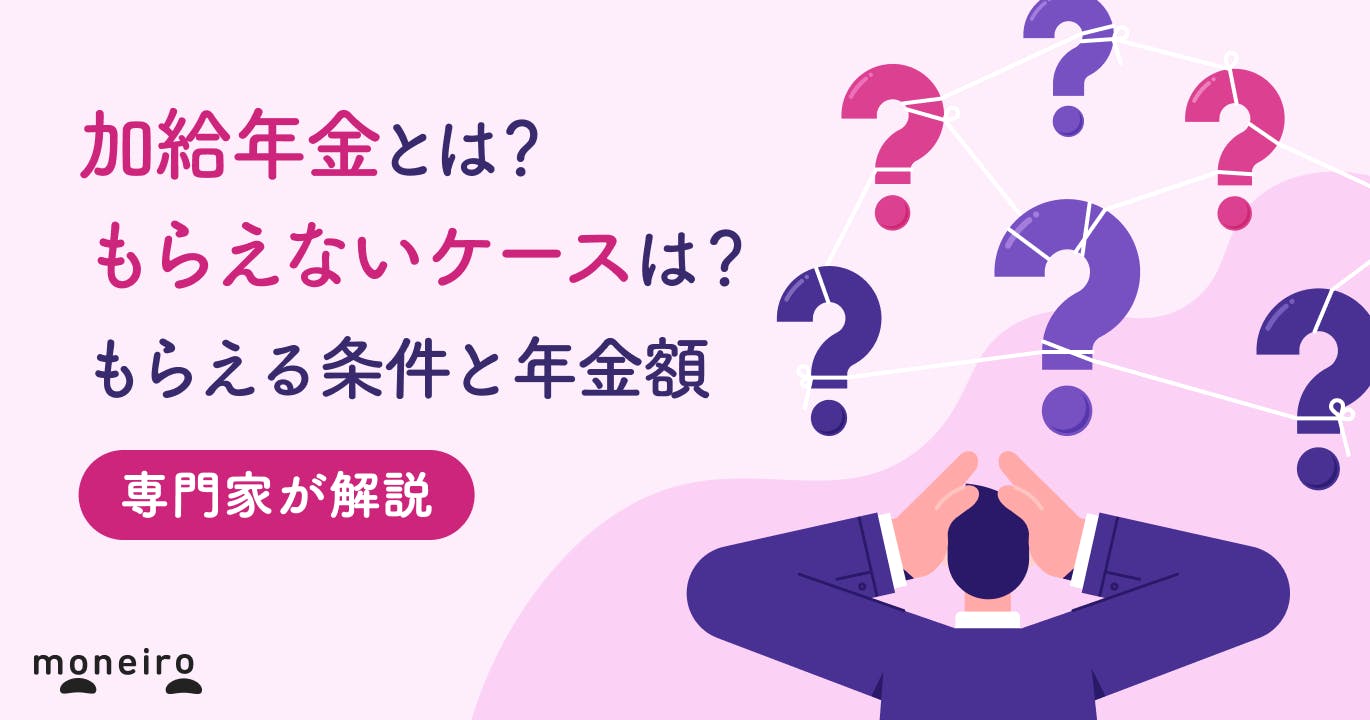
厚生年金に死亡一時金はない?併給可能?もらえないケースと知っておきたい年金の仕組み
»制度だけで足りる?必要な備えを3分で見える化
「厚生年金に加入していた家族が亡くなった時、死亡一時金はもらえる?」と不安に思う人は少なくありません。
死亡一時金は厚生年金ではなく、国民年金にのみ設けられた制度です。そのため厚生年金の加入者が亡くなった場合、遺族が受け取れるのは死亡一時金ではなく、遺族厚生年金や埋葬料(健康保険の給付)など別の給付となります。ただし、条件次第では死亡一時金と遺族厚生年金の併給が可能です。
本記事では「なぜ死亡一時金がもらえないのか」「どのように手続きを進めれば良いのか」を専門家の視点でわかりやすく解説します。
- 死亡一時金は国民年金にのみある制度
- 死亡一時金をもらえないケースは「厚生年金加入者である」「遺族年金や寡婦年金を受給した場合」など
- 遺族厚生年金と死亡一時金の併給できる条件は、「遺族が遺族基礎年金の受給要件を満たさないこと」
年金について知りたいあなたへ
お金の疑問を解決する無料サービスをご利用いただけます
▶老後資金の無料診断:将来の必要額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶老後資金の無料相談会:老後への備えを専門家がアドバイス
死亡一時金は国民年金にのみある制度
死亡一時金は、国民年金独自の給付であり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、納めた保険料が「掛け捨て」にならないよう補償することを目的としています。
死亡一時金を受け取れるのは、亡くなった人が以下の要件を満たす場合です。
- 保険料納付要件:死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した月数が36ヶ月以上あること
- 年金受給歴::老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに死亡したこと
また、遺族は故人と「生計を同じくしていた」ことが必要です。金額は保険料を納めた月数に応じて、12万円から32万円の間で決まります。付加保険料を36ヶ月以上納めている場合は、8000円が加算されます。
(参考:死亡一時金を受けるとき|日本年金機構)
死亡一時金をもらえないケース
死亡一時金は、国民年金制度の特定の条件を満たす場合にのみ支給されるため、他の公的年金給付との関係や個人の状況によって、受給できない場合があります。
厚生年金加入者であるため(制度上対象外)
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として一定期間保険料を納付した方が対象となる給付です。
したがって、会社員として厚生年金にのみ加入していた場合、死亡一時金の支給対象にはなりません。
国民年金保険料の納付要件を満たしていない場合
死亡一時金の請求には、死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した月数が36ヶ月以上あることが必須条件です。
この要件を満たしていない場合は、死亡一時金を受け取ることはできません。
遺族年金や寡婦年金を受給した場合
遺族が遺族基礎年金を受けられる場合、死亡一時金は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合は、どちらか一方を選択して受給することになります。
これは、どちらも国民年金独自の給付であり、目的が重複するためです。
既に老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していた場合
死亡一時金は、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した方に支給される給付です。故人がこれらの年金を既に受給していた場合、遺族は死亡一時金を受け取ることができません。
請求期限(2年)を過ぎた場合
死亡一時金には請求期限があり、故人が亡くなった日の翌日から2年が時効と定められています。この期間を過ぎると、受給する権利は消滅します。
年金について知りたいあなたへ
お金の疑問を解決する無料サービスをご利用いただけます
▶老後資金の無料診断:将来の必要額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶老後資金の無料相談会:老後への備えを専門家がアドバイス
厚生年金加入者の遺族が受け取れる主な給付
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、遺族は主に以下の給付を受け取れる可能性があります。
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者だった人が亡くなった場合に、その遺族の生活を保障することを目的とする年金です。
一家の主たる生計維持者が死亡した場合に、従前の生活水準をある程度維持できるよう所得を保障する仕組みとして機能します。
遺族基礎年金(条件付き)
遺族基礎年金は、18歳到達年度の末日までの子(または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)がいる配偶者や、子本人に支給されます。
子の有無が受給可否の大きな条件となります。
寡婦年金
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者であった夫が、年金を受け取らずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係を継続し、生計を維持されていた妻が受け取れる給付です。
死亡一時金と同様、国民年金独自の制度であり、老齢年金支給開始前の寡婦に対する生活保障と、掛け捨て防止を目的としています。
厚生年金加入者が、以前に国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納付していれば支給される可能性があります。
ただし、遺族年金と併給はできず、どちらかを選択しなければなりません。
健康保険からの埋葬料・埋葬費
被保険者が亡くなった場合、健康保険から埋葬料(または埋葬費)が支給されます。金額は5万円(協会けんぽの場合。埋葬費は5万円の範囲内で実費支給)など、医療保険の制度ごとに異なります。
条件次第で遺族厚生年金と死亡一時金の併給が可能
公的年金は「一人一年金」が原則ですが、遺族厚生年金と死亡一時金は、特定の条件下で併給が可能です。これは、両者が異なる制度(厚生年金と国民年金)から支給されるためです。
最も重要な併給条件は、遺族が遺族基礎年金の受給要件を満たさないことです。遺族基礎年金は、子どもが成長するまでの生活保障を目的とした給付であり、死亡一時金よりも優先順位が高いため、遺族基礎年金が支給される場合は、死亡一時金は支給されません。
したがって、子どものいない共働き世帯で夫が亡くなった場合など、遺族が遺族基礎年金を受け取れないケースでは、遺族厚生年金と死亡一時金の両方を受給できる可能性があります。
自分が受け取れる年金を確認する方法
まずは「自分はどの年金を請求できるのか」を確認しましょう。
最寄りの年金事務所で、死亡一時金や遺族年金の受給可否を確認できます。窓口で被保険者の基礎年金番号を提示すれば、加入記録をもとに制度適用の有無を調べてもらえます。
死亡後の手続きはどこから?期限と必要書類
遺族年金や死亡一時金は、申請しないと支給されません。期限や必要書類を理解しておきましょう。
遺族年金の請求方法
- 請求先:年金事務所または市区町村役場(遺族基礎年金のみの場合)
- 必要書類:年金請求書、死亡診断書、戸籍謄本、住民票、収入証明など
埋葬料・埋葬費の請求方法
- 請求先:加入していた健康保険組合や協会けんぽ
- 必要書類:埋葬料(費)請求書、死亡診断書の写し、葬儀費用の領収書など
時効に注意!請求期限は2年間
死亡一時金・埋葬料のいずれも請求期限は2年です。忘れると受給権が消滅しますので注意しましょう。
まとめ
遺族厚生年金と死亡一時金の併給は、遺族が遺族基礎年金の受給要件を満たさない場合に限り可能です。
これらの給付は、それぞれ目的や制度的基盤が異なるため、個別の状況を正確に把握し、適切な手続きを行うことが大切です。
不明な点があれば、自己判断をせず、年金事務所などの専門機関に相談することをおすすめします。
»制度だけに頼らず、将来に備えたい方へ|診断でわかる将来の備え方
年金について知りたいあなたへ
お金の疑問を解決する無料サービスをご利用いただけます
▶老後資金の無料診断:将来の必要額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶老後資金の無料相談会:老後への備えを専門家がアドバイス
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。