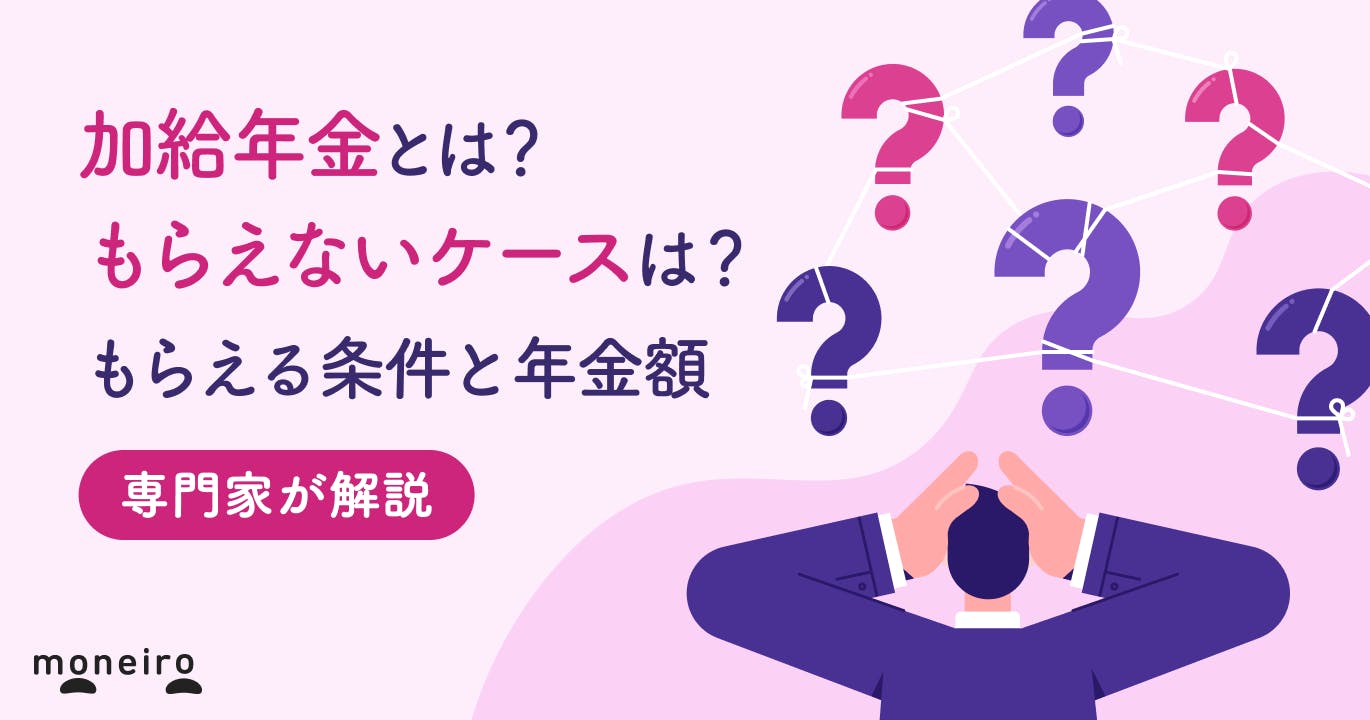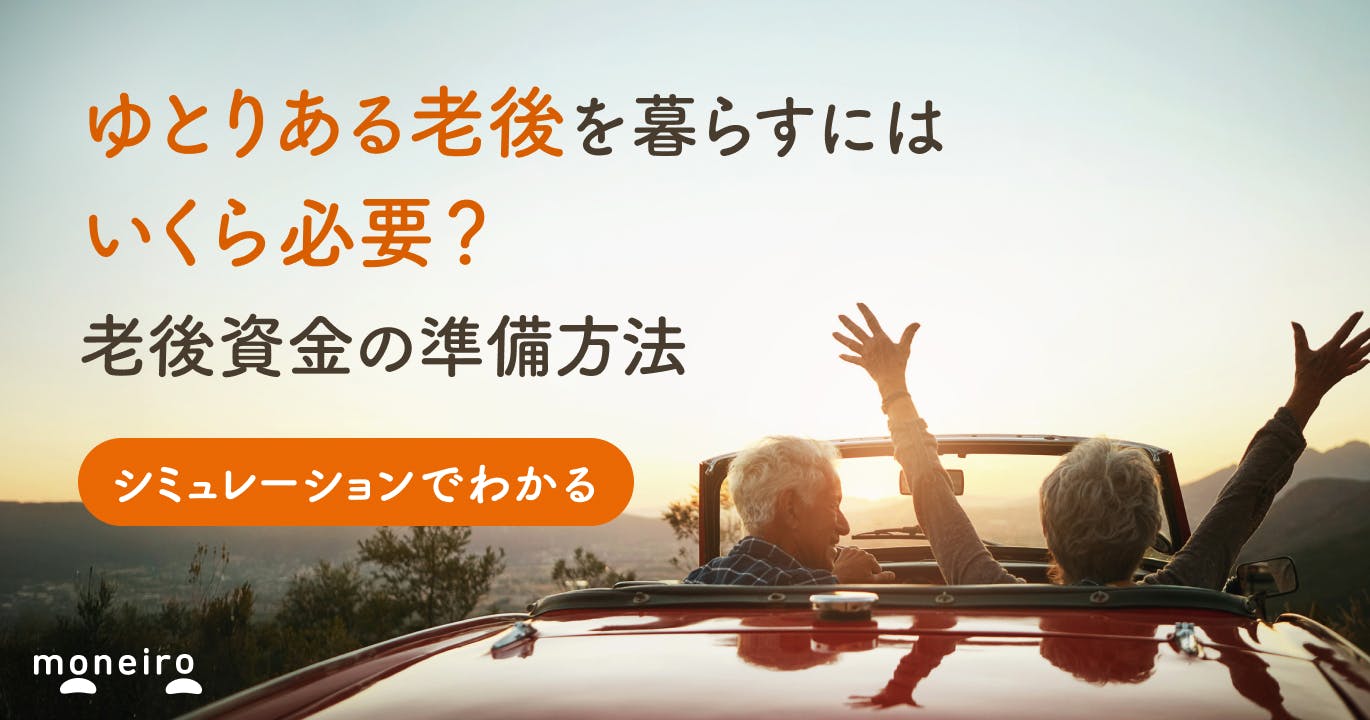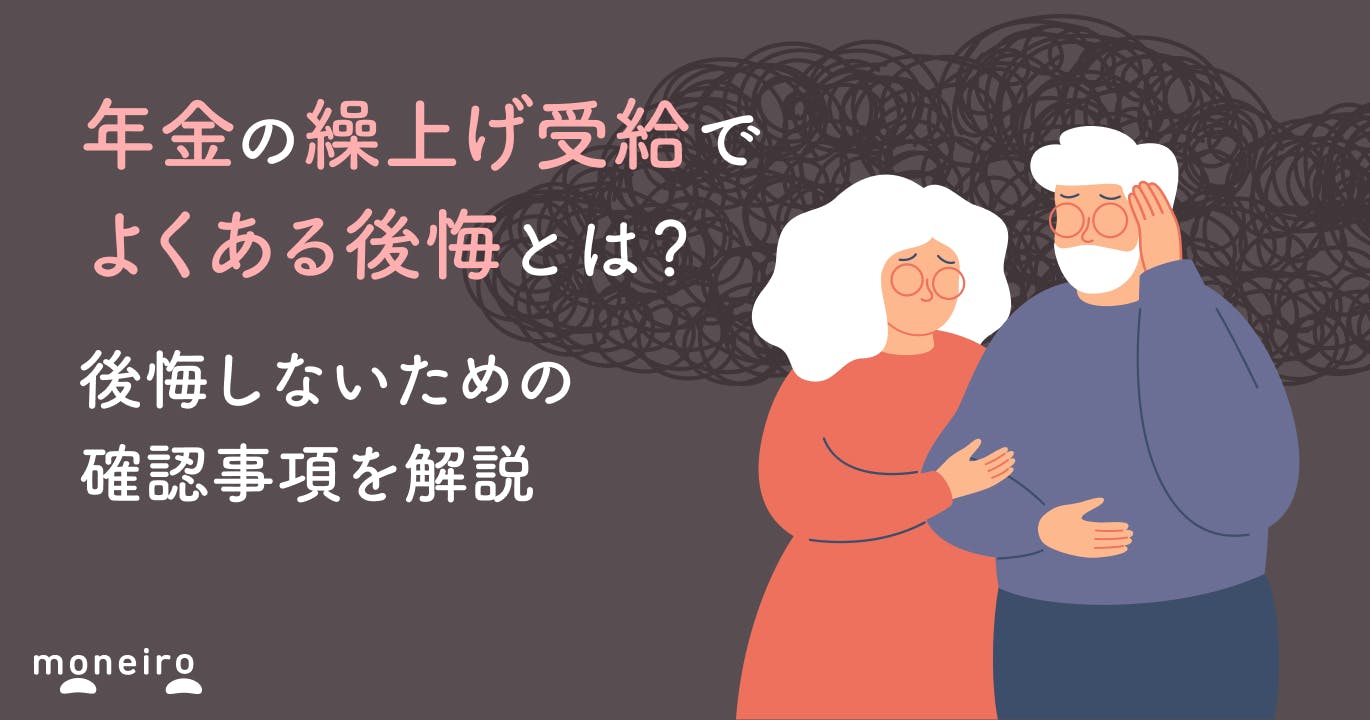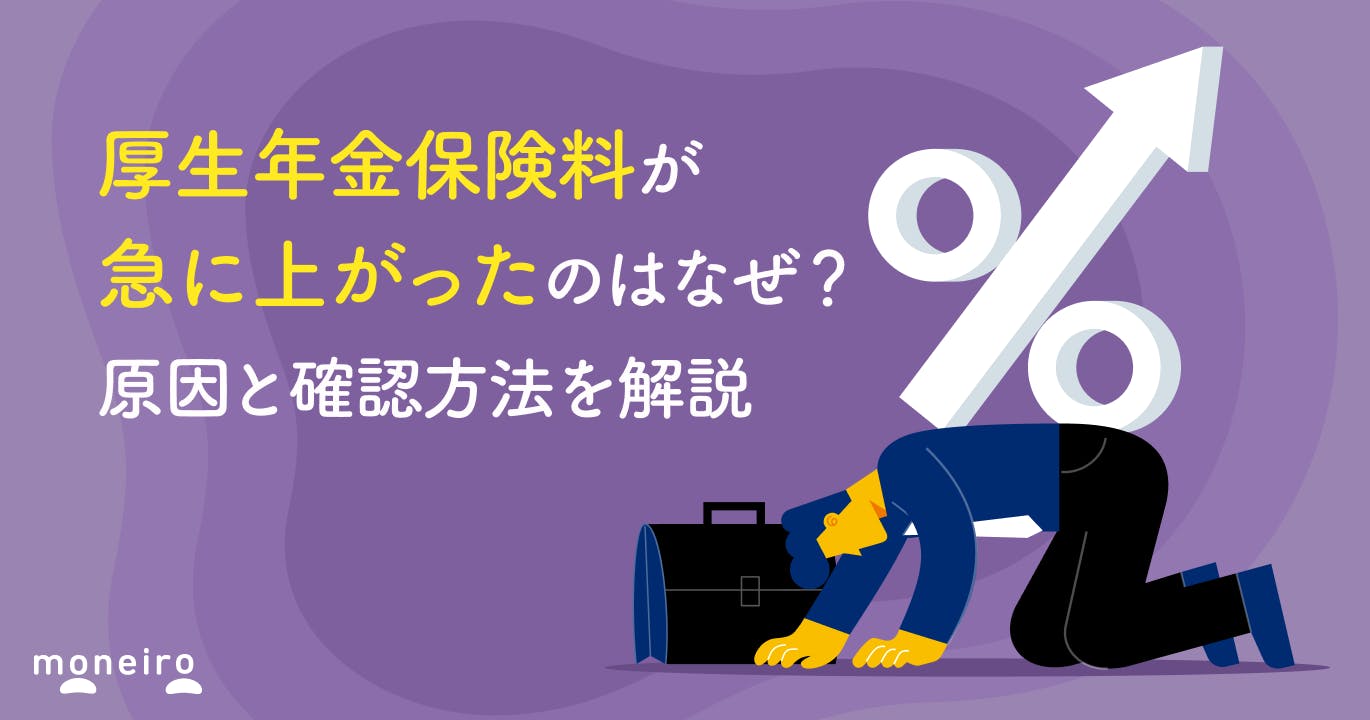
加給年金とは?もらえないケースは?もらえる条件と年金額を専門家がわかりやすく解説
≫年金だけで足りる?あなたの不足額をシミュレーション
加給年金とは厚生年金を受け取る人が、65歳到達時点で生計を維持されている配偶者や子どもの分として上乗せ支給される年金のことをいいます。
配偶者は41万5900円(受給権者が昭和18年4月2日以後生まれ)、1人目・2人目の子どもには各23万9300円で、3人目以降の子は各7万9800円が支給されます(令和7年4月から)。
本記事では、「加給年金とは?もらえる条件と年金額を知りたい」という人に向けて、加給年金の受給要件や支給金額の詳細、加給年金がもらえないケース、振替加算との違いなども専門家がわかりやすく解説します。
(参考:加給年金額と振替加算|日本年金機構)
- 加給年金とは、厚生年金保険の受給者に配偶者や子どもがいる場合に加算される年金のこと
- 加給年金をもらえる条件は「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある」「65歳に到達した時点で、その人に生計を維持されている配偶者、または子どもがいる」
- 加給年金の基本年金額は「配偶者の場合:41万5900円」「子どもの場合:1人目・2人目はそれぞれ年額23万9300円、3人目以降の子どもは年額7万9800円」
将来の年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
加給年金とは
加給年金とは、厚生年金保険の受給者に一定の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に加算される年金です。
いわば「家族手当」のような役割を担っており、主に扶養家族を持つ高齢者の生活支援を目的としています。
加給年金が支給される目的と制度の概要
加給年金は厚生年金の受給者に一定の扶養家族がいる場合、生活費の補助として支給される制度です。
制度の背景には、高齢期における扶養家族の存在による生活負担を軽減するという目的があります。
対象となるのは主に65歳以上の老齢厚生年金受給者で、その配偶者が65歳未満である場合や、一定年齢未満の子どもがいる場合です。
なお、受給には厚生年金の被保険者期間が20年以上必要です。
加給年金と他の年金(基礎年金・厚生年金)との関係
日本の公的年金制度は、国民全員が加入する国民年金(1階部分)と、会社員・公務員が加入する厚生年金(2階部分)の2階建て構造になっています。
基礎年金(1階部分)は国民年金から支給され、
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
があります。
また、老齢厚生年金(2階部分)は厚生年金保険料を支払うことで、
- 老齢厚生年金
- 障害厚生年金
- 遺族厚生年金
が支給されます。
一方、加給年金は「老齢厚生年金」や「障害厚生年金」に上乗せされる形で支給されるため、国民年金だけを受け取っている自営業者などは対象になりません。
加給年金自体は、年金の基本額とは別に支給される点が特徴です。
加給年金をもらうための条件と対象者
老齢厚生年金の加給年金を受け取るためには、年金受給者本人と、加給年金の対象となる配偶者や子どもが、それぞれ特定の要件を満たす必要があります。
加給年金の受給要件
加給年金を受け取るための年金受給者本人の主な要件は、以下の通りです。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある
- 65歳に到達した時点で、その人に生計を維持されている配偶者、または子どもがいる
過去に厚生年金に20年以上加入し、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給している場合は
加給年金が出ませんが、65歳以降に所定の条件を満たせば加給年金の対象となります。
対象となる配偶者・子どもの要件
加給年金の対象となる配偶者や子どもには、以下の要件があります。
【配偶者の場合】
- 年金受給者本人に生計を維持されていること
- 65歳未満であること
- 配偶者自身の老齢厚生年金や障害年金を受給していないこと(または、老齢厚生年金を受給していても厚生年金加入期間が20年未満であること)
【子どもの場合】
- 年金受給者本人に生計を維持されていること
- 18歳になった年度の3月31日までであること
- 障害等級1級または2級の場合は、20歳未満まで対象
- 婚姻していないこと
「生計を維持している」の具体的な判断基準
「生計を維持している」とは、単に同居しているだけでなく、経済的に依存関係にあることを指します。
同居している場合は基本的に生計同一関係が認められます。一方、別居している場合、仕送りをしている、健康保険の扶養に入れている、税法上の扶養親族としている、といった実態があれば認められます。
また、原則として、前年の年間収入が850万円未満(または所得が655万5000円未満)であることが条件です。
共働きの場合でも、この収入基準を満たしていれば対象となります。
Q.パートや年金受給中の配偶者は対象になる?
上記の「生計を維持している」の収入基準(年間収入850万円未満)を満たしていれば、加給年金の対象となります。
ただし、配偶者自身が厚生年金加入期間20年以上の老齢厚生年金や障害年金を受け取っている場合は、加給年金が支給停止となるため注意が必要です。
Q.共働きの場合でも加給年金はもらえる?
共働きの場合でも、前述の受給要件を満たしていれば加給年金はもらえます。
ただし、配偶者が65歳になると、加給年金が停止し、「振替加算」に切り替わることになります。
加給年金の支給額と振替加算の関係
加給年金がいくらもらえるのか、そして振替加算とは何かを理解することは、老後資金計画を立てる上で大切です。
≫年金だけで足りる?あなたの不足額をシミュレーション
加給年金の基本金額(配偶者・子)
加給年金の金額は、対象となる家族によって決まります。
配偶者に対する加給年金は、年額23万9300円(基本額)に年金受給者の生年月日に応じた特別加算額が加算され、現在の配偶者の加給年金額は41万5900円です。
一方、子どもに対する加給年金は1人目・2人目はそれぞれ年額23万9300円、3人目以降の子どもは年額7万9800円です。
Q.加給年金に税金はかかる?
公的年金のうち、障害年金と遺族年金は非課税ですが、加給年金は「公的年金等に係る雑所得」として課税対象になります。
振替加算とは?加給年金からの切り替えと条件
振替加算とは、夫(または妻)の厚生年金に加算されていた加給年金が、配偶者自身が65歳になり、老齢基礎年金を受け取るようになった場合に、その配偶者の老齢基礎年金に加算されるものです。
配偶者が65歳になった際に、加給年金が打ち切られることによる世帯収入の急減を緩和するための経過措置です。
振替加算の金額は 配偶者の生年月日によって異なり、年々少なくなり昭和41年4月2日以降に生まれた配偶者には支給されません。
加給年金→振替加算に切り替わるタイミング
加給年金が振替加算に切り替わるのは、原則として加給年金の対象となっていた配偶者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権が発生した時です。
受給者本人の老齢厚生年金に加算されていた加給年金は停止し、その代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされるようになります。
自動的に切り替わりますが、手続きが必要な場合もあるため、年金事務所に確認が必要です。
将来の年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
加給年金の支給期間と支給停止・終了のケース
加給年金は、一度支給が始まっても、特定の条件を満たさなくなった場合に支給が停止されたり、終了したりします。
いつからいつまでもらえるのか、どのようなケースでもらえなくなるのかを理解しておきましょう。
加給年金の支給開始時期と終了タイミング
原則として、加給年金を受け取る本人が65歳になり、老齢厚生年金の受給が開始された時点から支給されます。
一方、加給年金は、加給年金の対象となっている家族が要件を満たさなくなった時点で支給が終了します。
加給年金が支給停止になる主なケース
以下のような場合には、加給年金の支給が停止・終了となります。
加給年金の対象から外れた場合
加給年金は、家族を扶養していることを前提とした手当のため、扶養対象の家族が以下の状況になった場合、支給が終了します。
【配偶者の場合】
- 離婚または事実上の婚姻関係が解消された時
- 配偶者が死亡した時
- 配偶者が65歳に到達した時(この場合、配偶者自身の年金に「振替加算」として引き継がれる可能性があります)
【子どもの場合】
- 子どもが18歳になった年度の3月31日を迎えた時(障害等級1級または2級の場合は20歳到達時まで)
- 子どもが死亡した時
- 子どもが婚姻した時
配偶者が年金を受け取り始めた時
加給年金の対象となっている配偶者が、自身で厚生年金加入期間20年以上の老齢厚生年金や65歳以降の老齢基礎年金、障害年金を受給するようになった場合、加給年金は支給停止となります。これは、配偶者自身の年金収入で生計が維持できると判断されるためです。
ただし、この際に配偶者の老齢基礎年金に振替加算が引き継がれる可能性があります。
加給年金の具体的な支給例
加給年金の支給額や、振替加算への切り替えタイミングをより具体的にイメージできるよう、代表的なケースでの支給例を見てみましょう。
夫が65歳で会社員、妻が60歳で専業主婦の場合
夫が65歳になると、老齢厚生年金(65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金を除く)の受給が始まり、それに加えて配偶者加給年金も支給されます。ただし、妻が65歳になると、夫の加給年金は支給停止となります。
その代わりに、妻自身の老齢基礎年金の受給が始まり、さらに条件を満たしていれば振替加算が上乗せされます。
振替加算が支給されるのは、妻の厚生年金の加入期間が20年未満の場合に限られます。
夫が65歳で会社員、妻が62歳でパート勤務の場合
夫が65歳になった時、夫の老齢厚生年金の支給が開始されるとともに、配偶者加給年金も加算されます。妻のパート収入が一定基準以下であるため、生計維持関係が認められていることが条件です。
また、妻が65歳になった時、夫に支給されていた配偶者加給年金は停止されます。その代わりに、妻自身の老齢基礎年金の支給が始まり、条件を満たしていれば振替加算が上乗せされます。
夫が65歳で会社員、妻が62歳で会社員
夫が65歳になった時、妻が特別支給の老齢厚生年金の受給権を持っている場合、夫への配偶者加給年金は支給されません。
妻が失業保険を受給している場合や、給与が高い場合などで、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となっていると、加給年金も支給されません。
このように、夫婦それぞれの年金の加入状況や受給年齢によって、加給年金の支給の有無や、支給開始・停止のタイミング、金額が異なる点には注意が必要です。
加給年金の申請手続きの流れ
加給年金を受給するための手続きは、年金事務所で行います。必要書類と手順を確認しましょう。
1.年金請求書を準備: 原則として、年金受給者本人が65歳になり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を請求する際に提出する「年金請求書」に、加給年金の欄を記入します。
2.必要書類の添付: 年金請求書に加えて、加給年金の対象となる配偶者や子どもの情報を証明する書類を添付します。
- 戸籍謄本または戸籍抄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 加給年金の対象となる方の所得証明書または非課税証明書
- その他、必要に応じて診断書(子が障害者の場合)など
ただし、戸籍謄本や住民票、所得証明書などは、マイナンバーのわかる資料を持参すると省略可能です。
3.年金事務所へ提出: 必要書類を揃えて、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
4.審査・支給決定: 提出された書類に基づいて審査が行われ、要件を満たしていれば加給年金の支給が決定されます。
5.支給開始: 原則として、老齢厚生年金の初回支給と合わせて加給年金が支給されます。
手続きには時間がかかる場合があるため、老齢厚生年金の請求手続きと同時に申請を行うようにしましょう。
まとめ
加給年金は、厚生年金に一定期間以上加入した人が、生計を維持している配偶者や子どもがいる場合に、老齢厚生年金に上乗せされる大切な年金です。
配偶者に対しては年額41万5900円、子どもに対しては1人目・2人目が年額23万9300円など、その金額は老後の家計に大きな影響を与えます。
ただし、加給年金をもらうには、受給者本人だけでなく、対象となる家族にも細かな条件があります。
特に、配偶者が65歳になると加給年金が停止し「振替加算」に切り替わる点には注意が必要です。
自身の状況で加給年金がもらえるかどうか、いくらもらえるのかを正確に把握し、老後資金計画に役立てましょう。不明な点があれば、年金事務所などの専門機関に相談することをおすすめします。
≫年金だけで足りる?あなたの不足額をシミュレーション
将来の年金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。