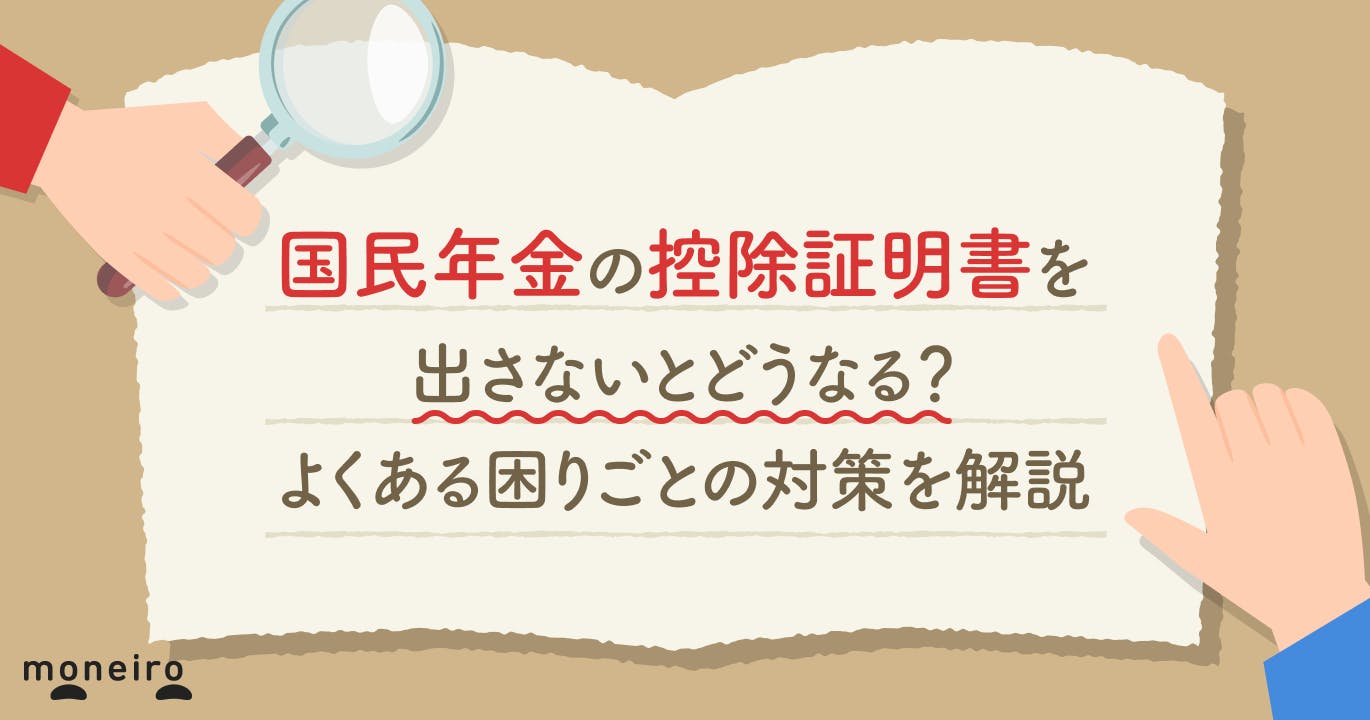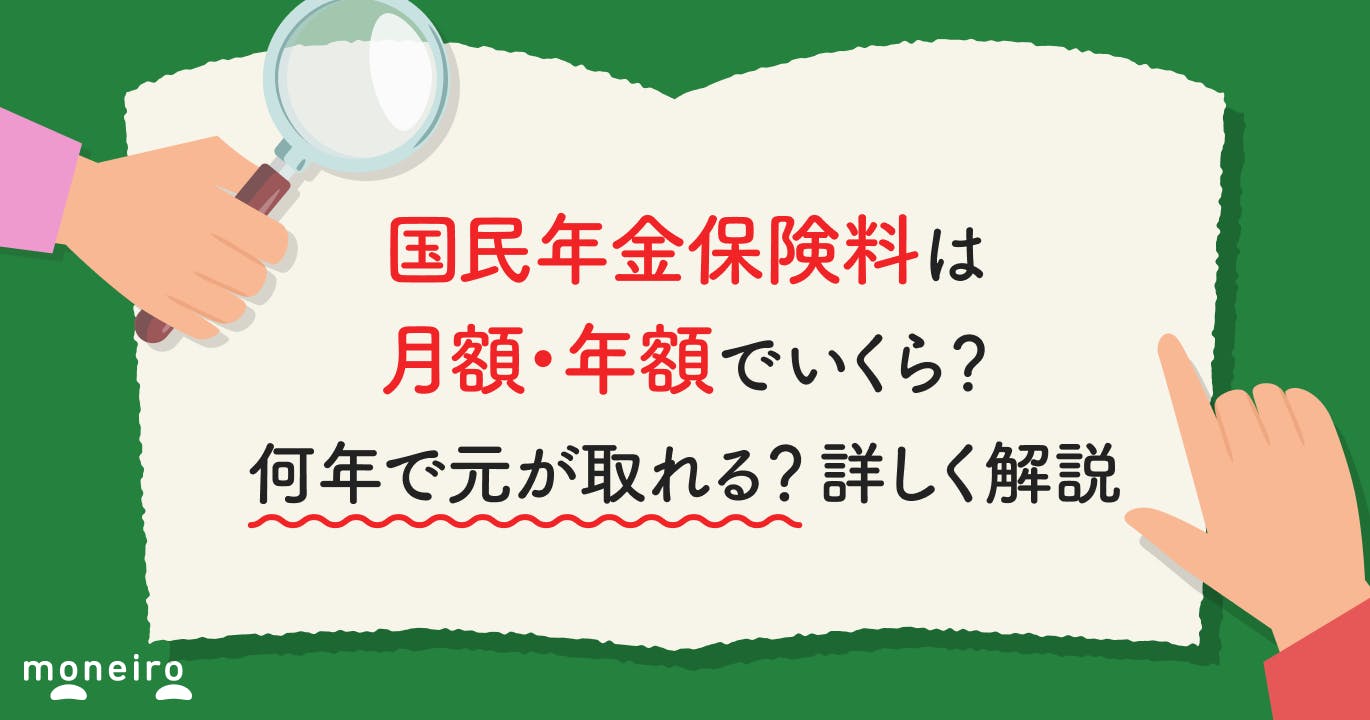
国民年金の控除証明書を出さないとどうなる?よくある困りごとの対策を解説
≫あなたは大丈夫?老後に不足する金額を3分で診断
「国民年金の控除証明書を出さないとどうなる?」と不安に思っていませんか?結論からいうと、提出しないと「社会保険料控除」が受けられず、大きな損につながります。
本記事では、そもそもの控除の仕組みや、いくら税金が戻るかの年収別シミュレーションなどを分かりやすく解説します。控除の重要性をあらためて確認し、確実に提出するようにしましょう。
- 国民年金の控除証明書を提出しない場合に発生する影響
- 年収別のモデルケースでの節税効果
- 控除証明書を紛失・破棄した場合の再発行方法や、届かない場合の対処法
将来の備えが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
国民年金の控除証明書を出さないとどうなる?
国民年金の控除証明書を提出しない場合、もっとも大きな影響は「社会保険料控除」が受けられなくなることです。
社会保険料控除とは、支払った国民年金保険料の全額を所得から差し引くことができる仕組みです。この控除が適用されないと、その分、課税対象となる所得が増加します。結果として、本来減税されるはずだった所得税や住民税の負担が増加し、家計において損をしてしまうことになります。
国民年金保険料の「社会保険料控除」の仕組み
社会保険料控除とは、納税者本人または生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合に適用される所得控除の一つです。国民年金保険料はこの社会保険料に含まれます。支払った国民年金保険料の全額が所得から控除の対象となります。
この控除を適用するためには、年末調整や確定申告の際に、支払いを証明する書類である「国民年金保険料控除証明書」を提出する必要があります。
控除により所得が減ることで、適用される所得税率および住民税率に基づき税負担が軽減されます。
国民年金保険料控除の節税額を年収別に徹底シミュレーション
国民年金保険料控除による節税額は、その人の「課税される所得金額」にかかる所得税率によって大きく変動します。所得税率が高ければ高いほど、節税効果は大きくなります。
ここでは、令和7年度の年間保険料21万120円(月額1万7510円 × 12ヶ月)をベースに、住民税率を一律10%と仮定して、年収別の節税モデルケースをシミュレーションします。
「課税される所得金額」とは、「年収」そのものではなく、年収から給与所得控除や基礎控除、国民年金以外の社会保険料控除などを差し引いた後の、税金計算の基礎となる金額を指します。
年収300万円(所得税率5%)の場合
年収300万円の場合、課税所得の区分は「195万円以下」となり所得税率は5%となります。年間保険料を21万120円とした場合、節税効果は以下の通りです。
- 所得税の軽減額:21万120円 × 5% = 1万506円
- 住民税の軽減額:21万120円 × 10% = 2万1012円
- 合計節税額:3万1518円
この控除手続きを忘れると、3万1518円分が納税額として上乗せされてしまいます。
年収500万円(所得税率10%)の場合
年収500万円の場合、課税所得の区分は「195万1円~330万円以下」となり、所得税率は10%となります。年間保険料を21万120円とした場合の節税効果は以下の通りです。
- 所得税の軽減額:21万120円 × 10% = 2万1012円
- 住民税の軽減額:21万120円 × 10% = 2万1012円
- 合計節税額:4万2024円
年収300万円と比較して節税効果が大きく増加することが分かります。
これは、所得税率が上がるほど、控除による節税効果が大きくなるためです。
年収800万円(所得税率20%)の場合
年収800万円の場合、課税所得の区分は「330万1円~695万円以下」となり、所得税率は20%となります。年間保険料を21万120円とした場合の節税効果は以下の通りです。
- 所得税の軽減額:21万120円 × 20% = 4万2024円
- 住民税の軽減額:21万120円 × 10% = 2万1012円
- 合計節税額:6万3036円
所得税率が高くなる高所得者ほど、控除証明書を提出しないことによる経済的損失は大きくなるため、手続きの漏れがないよう十分な注意が必要です。
将来の備えが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
控除証明書はいつ・どうやって届く?
国民年金保険料の控除証明書は、その年の9月30日までに納付実績がある方と、10月1日以降にその年初めて納付された方で、発送時期が異なります。
一般的に、多くの人の手元には10月末から11月上旬にかけて送付されます。これは、その年の1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料の納付実績がある方が対象です。
この証明書は、年末調整や確定申告を行う際に社会保険料控除を適用するために必須の書類です。
もし控除証明書を紛失・破棄してしまったら?3つの再発行方法
控除証明書を紛失したり、誤って破棄してしまったりした場合でも、再発行手続きを行うことができます。再発行の方法は主に以下の3つがあり、自身の状況に合わせて選択できます。
マイナポータルでダウンロードする
マイナポータルを利用すると、スマートフォンやパソコンから控除証明書情報をダウンロードすることが可能です。これはもっとも手軽な再発行方法の1つです。
マイナポータルで連携手続きを行い、電子データとして取得することで、そのまま確定申告の電子提出に利用することもできます。
日本年金機構に電話する
日本年金機構に電話で再発行を依頼することも可能です。この際、スムーズな手続きのために、基礎年金番号通知書や年金手帳など、基礎年金番号が確認できる書類を事前に用意しておく必要があります。
本人確認後、郵送で自宅に再発行された証明書が送付されます。
年金事務所の窓口に行く
お近くの年金事務所の窓口へ直接出向き、再発行を申請することもできます。窓口で申請する場合は、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
その場で申請書を記入し、手続きが完了すれば、通常その場で証明書を受け取ることができます。
そもそも控除証明書が届かない!考えられる原因と対処法
控除証明書が届くべき時期になっても届かない場合、いくつかの原因が考えられます。
住所変更手続きをしていない
転居した場合などに、日本年金機構に対して住所変更手続きを行っていないと、証明書が旧住所に送られてしまい届かない原因となります。住所が変わった場合は速やかに年金事務所または日本年金機構に届け出を行う必要があります。
もし転居後に証明書が届かない場合は、住所変更手続きを完了させた上で、再発行の手続きを依頼してください。
発送対象の時期ではない
納付時期によっては、発送スケジュールが異なります。特に、10月1日以降にその年初めて保険料を納付した場合、証明書(郵送)が発送されるのは翌年の2月上旬です。
年末調整には間に合わないため、この場合は自分で確定申告を行う必要があります。
電子データでの受け取りを選択している
マイナポータルで「電子データ」での受け取りを希望している場合、証明書(書面)は郵送されません。その場合はマイナポータルにログインし、電子データを確認しましょう。
こんな時はどうする?国民年金保険料控除のよくある困りごと
年末調整や確定申告の時期には、国民年金保険料控除に関してさまざまな疑問や困りごとが発生します。ここでは、特に頻繁に発生するケースとその対処法を解説します。
年末調整で書類を提出し忘れた
会社員の方が年末調整の際に国民年金保険料控除証明書を提出し忘れたとしても、焦る必要はありません。提出忘れそのものに対するペナルティ(罰則)は一切ありません。
会社によっては、年末調整のやり直し(再調整)が可能なケースもありますが、もっとも確実な対処法は自分で「確定申告(還付申告)」を行うことです。
還付申告は、控除を適用することで払いすぎた税金を取り戻す手続きで、申告する年の翌年1月1日から5年間は手続きが可能です。現在はスマートフォンや国税庁のサイトを利用し、比較的簡単に手続きが完了できるようになっています。
過去の未納分を追納した
国民年金保険料は、過去10年以内の未納分を「追納」することができます。この追納した保険料についても、支払った年分の社会保険料控除の対象となります。例えば、2025年に過去2年分をまとめて追納した場合、2025年分の所得からその追納額すべてを控除することができます。
ただし、追納した分もすべて支払った証明が必要となるため、追納分の控除証明書もしっかり保管しておく必要があります。
年の途中で就職・退職した
年の途中で退職し国民年金に加入した場合や、逆に就職して厚生年金に切り替わった場合など、国民年金保険料を支払った期間がある場合は、その支払った分が控除の対象になります。
退職後に国民年金に加入し、その保険料を自分で納付した場合は、その年の年末調整(就職後の会社で行う場合)または確定申告で控除証明書を提出する必要があります。
また、就職前に国民年金を前納していた場合なども、控除額の計算に含めることができます。
国民年金保険料控除に関するよくある質問
ここでは、国民年金保険料控除に関するよくある質問について回答します。
Q. 国民年金の控除証明書は、提出しないと罰則がある?
控除証明書を提出しなかった場合でも、それ自体に罰則やペナルティはありません。
ただし、社会保険料控除が適用されないため、結果として所得税や住民税の納税額が増加し、経済的に損をすることになります。
万が一提出を忘れた場合は、翌年1月1日から5年以内に還付申告を行うことで、税金を取り戻すことができます。
Q. 妻(夫)や子供の国民年金を払った場合も控除できる?
できます。社会保険料控除は、納税者自身が支払った保険料だけでなく、納税者と「生計を一にする」配偶者やその他の親族の国民年金保険料を支払った場合も対象となります。
例えば、20歳以上で学生または無業の子供の国民年金保険料を親が支払った場合などが該当します。この場合、支払ったことを証明する控除証明書を使って、支払った人(親)が所得控除を受けることができます。
Q. 国民年金を前納した場合はどうなる?
前納(数ヶ月分や1年分などをまとめて事前に納付すること)した場合、以下のいずれかの方法で控除を選択できます。
- 納付した年に全額を控除する方法
- 期間に応じて各年に振り分けて控除する方法
一般的には、一度に控除額を大きくできる「納付した年に全額を控除する方法」を選ぶと、その年の節税効果が最大になる傾向があります。
まとめ
国民年金保険料控除証明書は、支払った保険料の全額を所得から控除し、所得税・住民税の負担を軽減するために非常に重要な書類です。提出しないと、年収に応じて数万円から十数万円の税負担が増加し、損をしてしまいます。
もし、年末調整で提出を忘れた場合でも、還付申告によって5年間遡って税金を取り戻すことが可能です。控除証明書が届かない、紛失したといった場合には、マイナポータルや年金機構への連絡を通じて再発行が可能です。必ず手続きを行い、節税の機会を逃さないようにしましょう。
≫あなたは大丈夫?老後に不足する金額を3分で診断
将来の備えが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
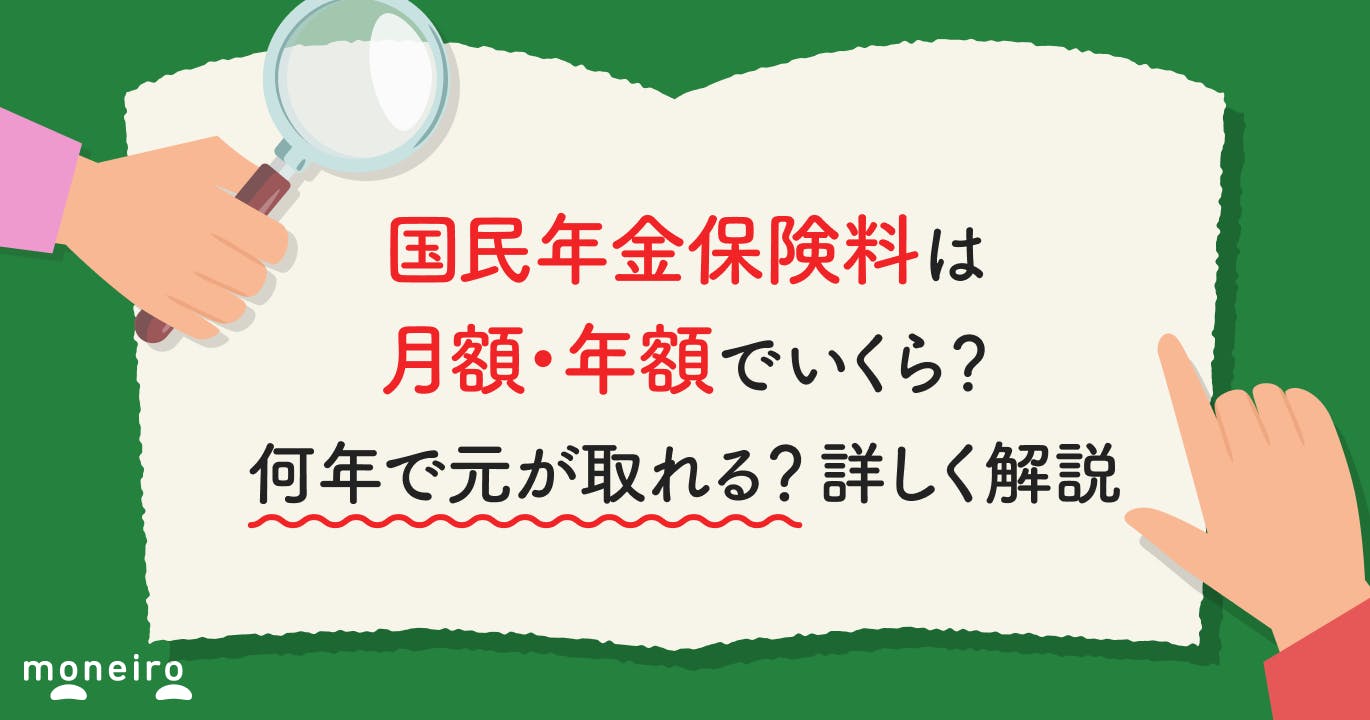
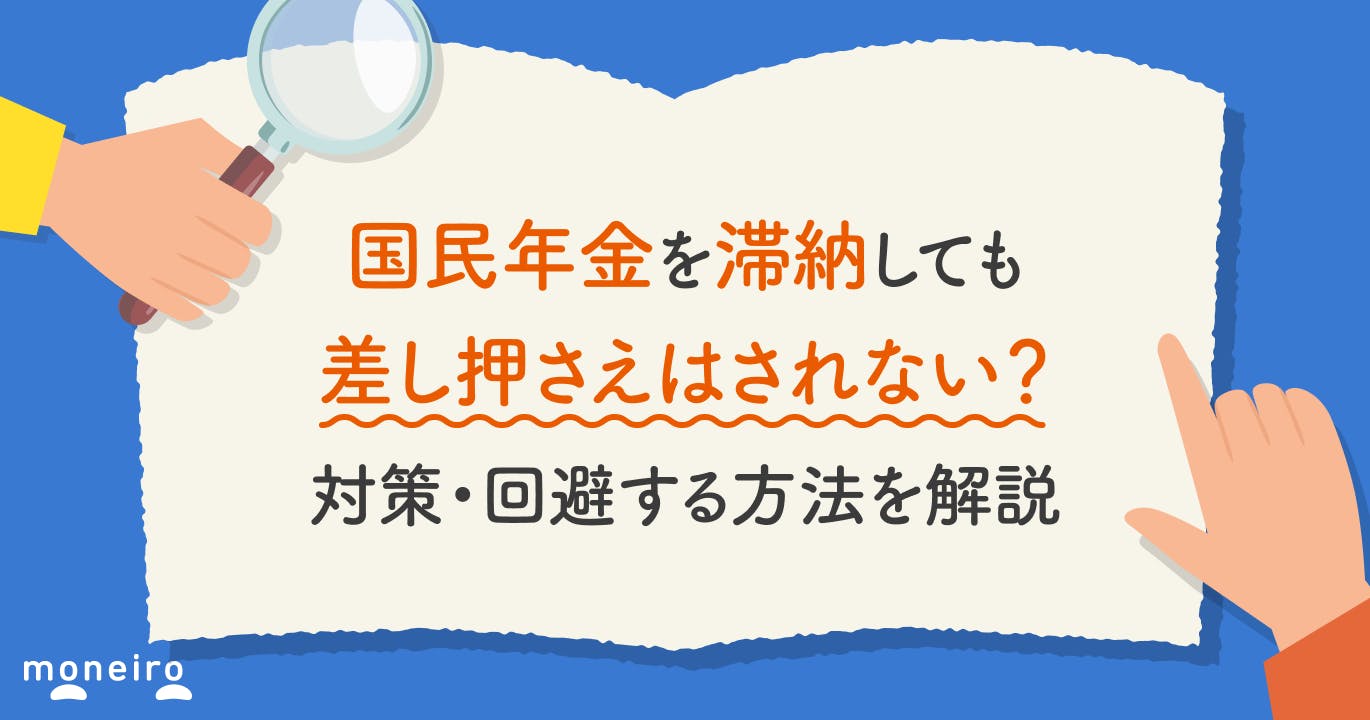
国民年金を滞納しても差し押さえはされない?対策・回避する方法を解説
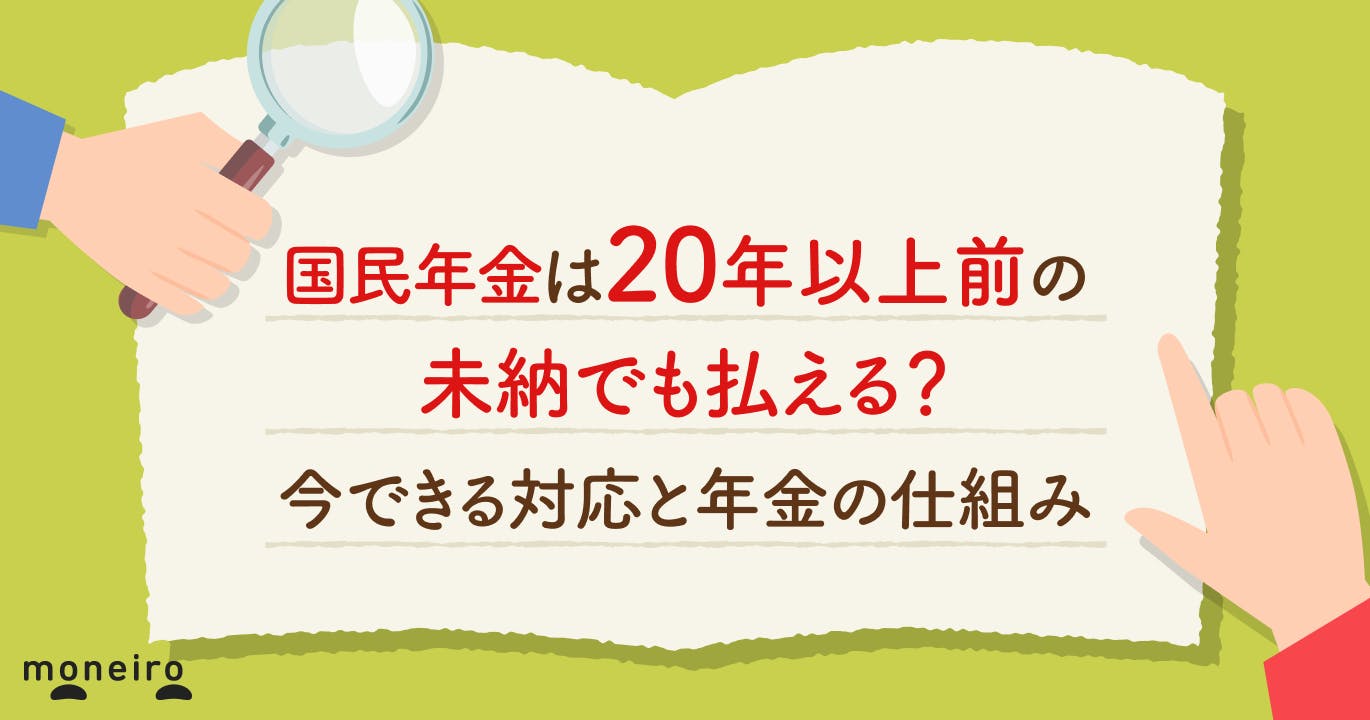
国民年金は20年以上前の未納でも払える?今できる対応と年金の仕組みをわかりやすく解説
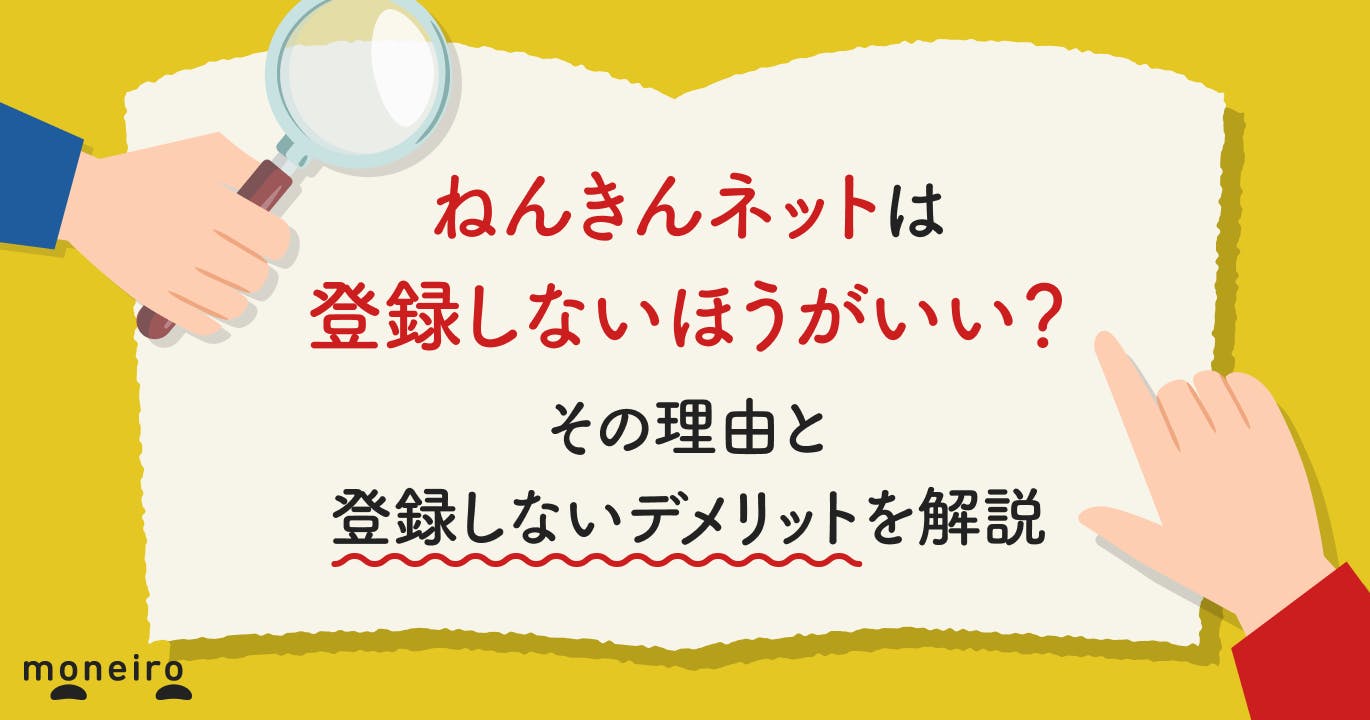
ねんきんネットは登録しないほうがいい?その理由と登録しないデメリットを解説
監修
内山 智絵
- 公認会計士/税理士/AFP
大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所にて約10年間勤務し、上場企業を中心とした法定監査などの業務に携わる。出産・育児を機に監査法人を退職した後、2021年春に個人会計事務所を開業。地域の中小企業や個人事業主の身近な相談役として、法人・個人問わず税務・会計サポートを提供している。2025年夏に株式会社SheBlissを設立。自身の経験や女性起業特有の課題を踏まえ、女性が「やりたい」を形にして続けていけるように、専門性の高いサポートとコミュニティを提供している。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。