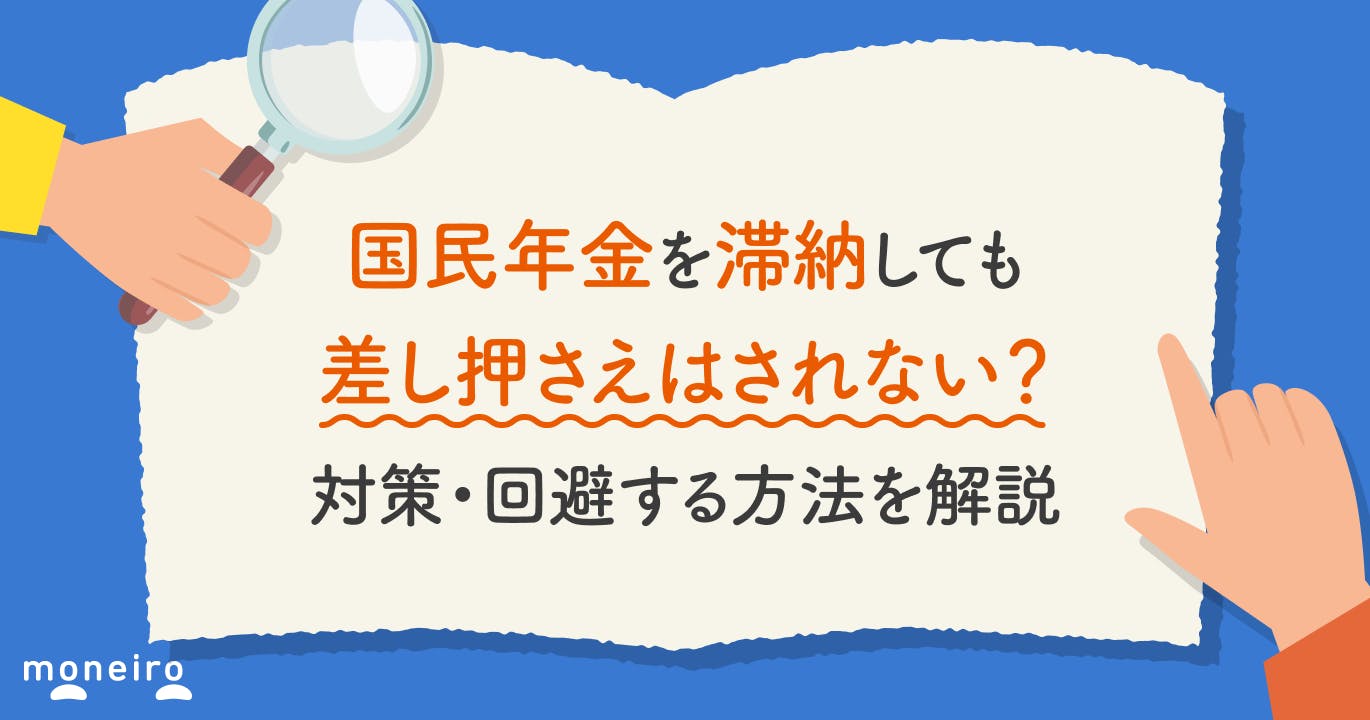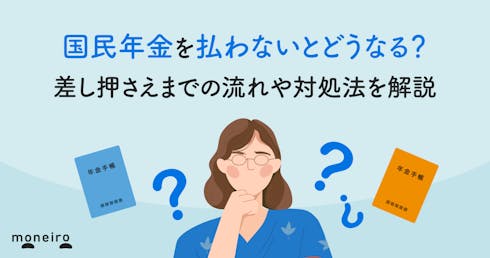
国民年金を滞納しても差し押さえはされない?対策・回避する方法を解説
>>将来の備えは大丈夫?あなたに必要な老後資金をチェック
「国民年金の滞納で、財産が差し押さえられないか不安」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。国民年金保険料には納付義務があり、滞納し続けると最終的に財産が差し押さえられる可能性があります。
本記事では、差し押さえの条件や具体的な流れ、そして万が一滞納してしまった場合に利用できる免除・猶予制度や相談先について詳しく解説します。手遅れになる前に適切な対処法を知り、不安を解消しましょう。
- 国民年金保険料の滞納が差し押さえに至るまでの具体的な流れと条件
- 差し押さえの対象となる財産と、差し押さえから保護される財産の種類
- 差し押さえを回避するための、免除・猶予制度の利用や相談先の情報
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
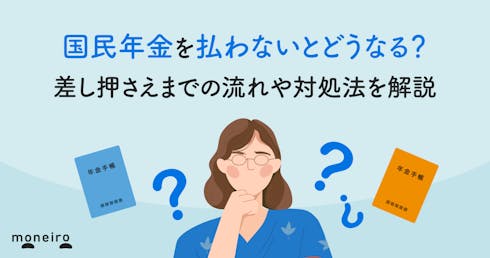
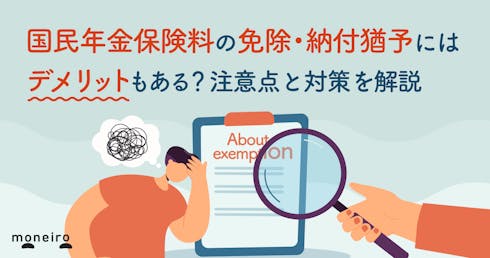
国民年金保険料を滞納し続けると財産が差し押さえられる
国民年金第1号被保険者は、保険料を納付対象月の翌月末日までに納める義務があります 。納付期限を過ぎた場合、督促状などの納付督励が段階的に行われ、それでもなお長期にわたって滞納が続くと、最終的には財産の差し押さえなどの強制徴収措置がとられる可能性があります 。
実際、厚生労働省が発表した「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、令和6年度には2万6797件の強制徴収(財産の差し押さえ)※が実施されています。これは、滞納が続いた結果、日本年金機構による強制徴収措置がとられたことを示しており、決して無視できない問題といえるでしょう。
※控除後所得300万円以上かつ7ヶ月以上保険料を滞納している人が対象
国民年金保険料を滞納するとどうなる?差し押さえまでの流れ
国民年金保険料を滞納すると、いくつかの段階を経て財産差し押さえへと進んでいきます。この流れを理解しておくことで、早めに対処する重要性がわかります。
1.納付勧奨(納付督励)
納付期限までに保険料が納付されない場合、まず日本年金機構から納付を促す「納付勧奨(納付督励)」が行われます。これは電話や文書、時には民間事業者への委託を通じて行われます。令和6年度には、文書による納付督励が4150万件、電話が1904万件実施されています。
2.特別催告状・督促状の送付
再三の納付勧奨にも応じない場合、まず「特別催告状」が送付されます。さらに納付能力があるにもかかわらず納付されない場合には、最終催告状が送付され、指定された期限までに納付がないと「督促状」が送付されます。令和6年度には、最終催告状が16万8456件、督促状が9万9962件送付されています。
3.財産調査と差押予告通知書の送付
督促状で指定された期限までに納付がない場合、日本年金機構は滞納者の財産調査を行います。財産が確認されれば、差し押さえを行う旨の「差押予告通知書」が送付されます。この通知は、滞納処分として実際に差し押さえを行う前の最後の段階です。
この段階へ至る前に、できる限り早く日本年金機構に相談することが重要です。
4.財産差し押さえの実行
差押予告通知書に記載された期限までに納付がない場合、滞納者の財産(預貯金、給与、不動産など)が強制的に差し押さえられます。
被保険者だけでなく、連帯納付義務者である世帯主や配偶者の財産も差し押さえの対象となる場合があります。
国民年金の滞納で差し押さえを受ける条件
国民年金の滞納が差し押さえに至るには、以下の条件が重なることが多いです。これらの条件に該当すると、財産差し押さえの対象となるリスクが高まります。
未納期間が7ヶ月以上ある
日本年金機構は、控除後の所得が300万円以上で、7ヶ月以上保険料を滞納している人を強制徴収の対象とすることを明示しています。長期間の未納が続くことは、納付する意思がないと判断され、差し押さえの対象となる可能性を高めます。
控除後の所得額が300万円以上
一定以上の所得があるにもかかわらず保険料を滞納している場合、日本年金機構が「納付能力あり」と判断するため差し押さえの対象となる可能性が高まります。
より重いケースとして、所得1000万円以上でかつ滞納月数が13ヶ月以上になる場合は、国税庁へ強制徴収委任が行われることもあります。
繰り返しの督促に応じない
度重なる納付勧奨や督促状、最終催告状などの通知を無視し続けることは、日本年金機構が「支払いの意思がない」と判断する要因となります。これにより、強制徴収へと移行する可能性が高まります。
督促に迅速に対応し、相談することが重要です。
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
差し押さえの対象になる財産、ならない財産
財産の差し押さえが行われる場合、どのような財産が対象となり、どのような財産が保護されるのでしょうか。
差し押さえの対象になる主な財産
国民年金保険料の滞納による差し押さえは、滞納者の納付能力に応じて多岐にわたる財産が対象となります。差し押さえの対象となる主な財産は以下の通りです。
- 給与:給与は原則として手取り額の4分の1が差し押さえられます。ただし、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分が全額差し押さえられることがあります。
- 銀行預金:預金口座にある現金は、その全額または一部が差し押さえの対象となります。
- 不動産:土地や建物などの不動産も差し押さえの対象となり、公売によって換金され、滞納保険料に充当されます。
- 動産:高価な自動車や生活必需品ではない高級な家財道具なども、差し押さえの対象となる可能性があります。
これらの財産は、国税徴収法第47条に規定された差し押さえの要件に該当し、徴収の対象となり得ます。差し押さえは、滞納者への事前の通知に基づき、適正な手続きに従って実行されます。
滞納が差し押さえに至る前に、日本年金機構に相談することが重要です。
差し押さえの対象にならない財産
一方で、滞納者の生活を保護するため、差し押さえが禁止されている財産も存在します。国税徴収法第47条には、以下のような差し押さえ禁止財産が定められています。
- 生活に不可欠な財産:衣類、寝具、家具、台所用品、その他の生活に欠かせない器具などは、差し押さえの対象になりません。これは、滞納者およびその扶養親族が通常の生活を送る上で最低限必要な物品が保護されるためです。
- 現金:滞納者とその扶養家族が1ヶ月間の生活に必要な費用として、99万円以下の現金は差し押さえが禁止されています。
これらの差押禁止財産は、国税徴収法第47条に「滞納者及びその者と生計を一にする配偶者(中略)の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具、台所用具、燃料、光熱その他の生活必需品」として明記されています。
国民年金の受給権は差し押さえされない
公的年金の受給権は、民事執行法によって差し押さえが禁止されています。これには、国民年金や厚生年金だけでなく、確定給付企業年金、確定拠出年金、国民年金基金、厚生年金基金なども含まれます。
したがって、将来受け取る年金そのものが、国民年金保険料の滞納によって差し押さえられることはありません。
差し押さえを回避するための具体的な対処法
国民年金保険料の滞納による差し押さえを回避するためには、早期の対応が非常に重要です。以下の対処法を検討しましょう。
滞納分を速やかに納付する
もっとも確実な回避策は、滞納している保険料を速やかに納付することです。口座振替やクレジットカード納付、コンビニ納付、インターネットバンキング、スマートフォン決済アプリなど、さまざまな納付方法が整備されています。
特に口座振替やクレジットカード納付は、自動で納付されるため納め忘れを防ぎ、納付率の向上にも貢献しています。令和6年度には、口座振替の電子申請が開始され、利便性がさらに向上しています。
免除・納付猶予制度の利用
経済的な理由で国民年金保険料の納付が難しい場合、免除制度や納付猶予制度を利用することができます。これらの制度が適用されれば、保険料の納付が免除されたり、後から納付できるよう猶予されたりするため、未納期間が発生するのを防ぐことができます。
所得が少ない場合は全額免除や一部免除の申請が可能なほか、学生であれば学生納付特例制度が利用できます。申請手続きはマイナポータルを利用した電子申請も可能となっており、簡素化が進んでいます。
厚生労働省「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、令和6年度末時点で、全額免除・猶予者の数は合わせて592万人にも上ります。これは多くの方が滞納を避けるためにこれらの制度を活用していることを示しています。
未納のまま放置せず、制度を有効に活用することが、将来の年金受給権を確保するために重要です。
分割納付の相談
すでに滞納が発生してしまっている場合でも、日本年金機構の窓口や電話で相談し、分割納付の相談をすることで、差し押さえを回避できる可能性があります。納付が困難な事情を伝え、具体的な納付計画を立てることで、柔軟な対応をしてもらえることがあります。
まとめ
国民年金保険料の滞納は、納付勧奨から始まり、督促状、最終催告状を経て、最終的には財産の差し押さえに至る可能性があります。特に控除後所得が300万円以上で7ヶ月以上の未納がある場合や、度重なる督促に応じない場合は、差し押さえのリスクが高まります。
しかし、経済的な困難がある場合でも、免除・納付猶予制度の利用や、日本年金機構への分割納付の相談など、差し押さえを回避するための具体的な対処法が用意されています。公的年金受給権は差し押さえの対象外ですが、預貯金や給与、不動産などは対象となり得るため、早めの行動が不可欠です。
もし国民年金保険料の納付に不安がある場合は、一人で抱え込まず、早めに日本年金機構の相談窓口へ連絡し、適切なサポートを受けるようにしましょう。
>>将来の備えは大丈夫?あなたに必要な老後資金をチェック
将来資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
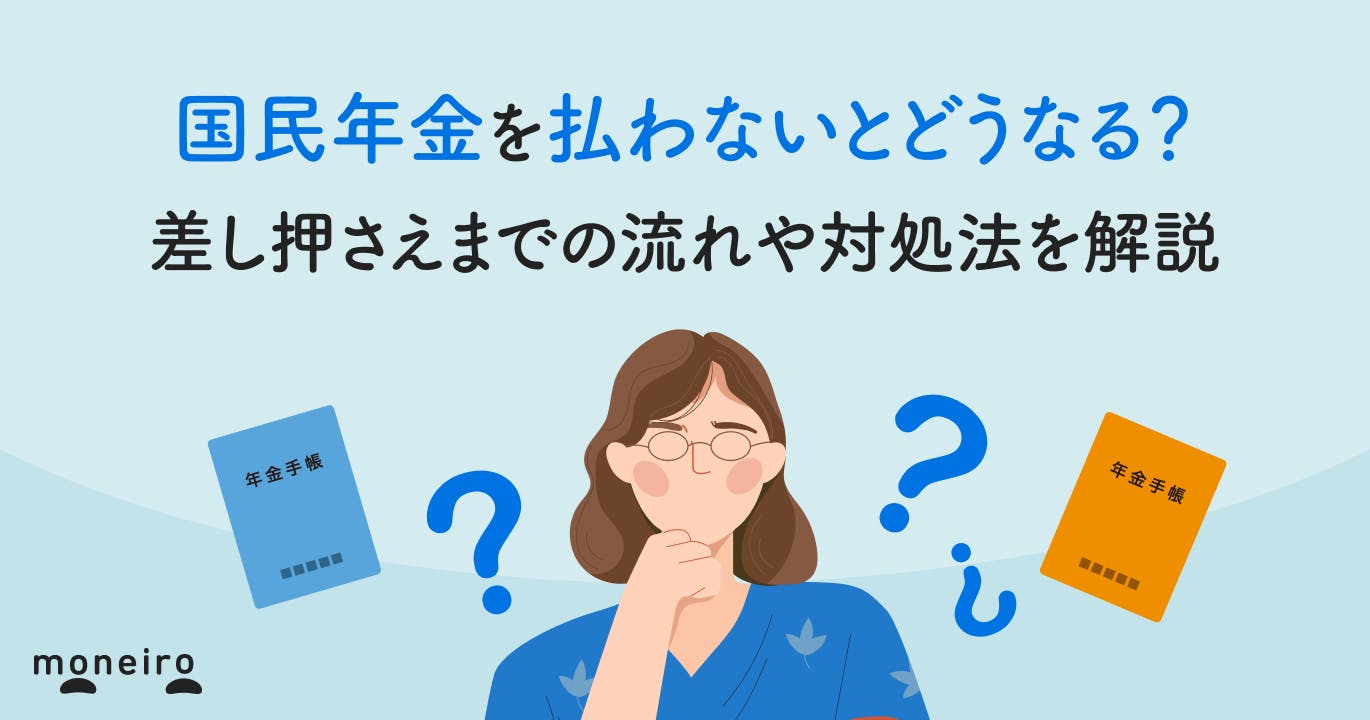
国民年金を払わないとどうなる?差し押さえまでの流れや対処法を解説
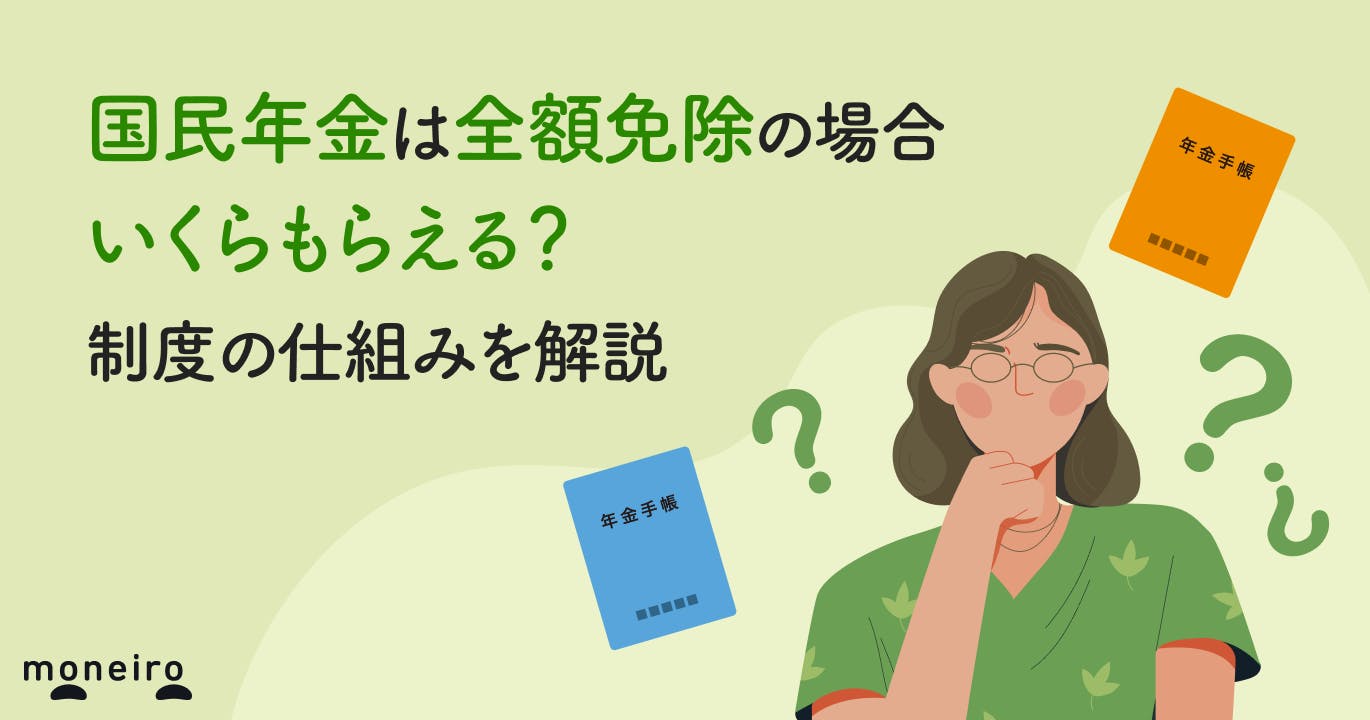
国民年金は全額免除の場合いくらもらえる?免除期間別シミュレーション
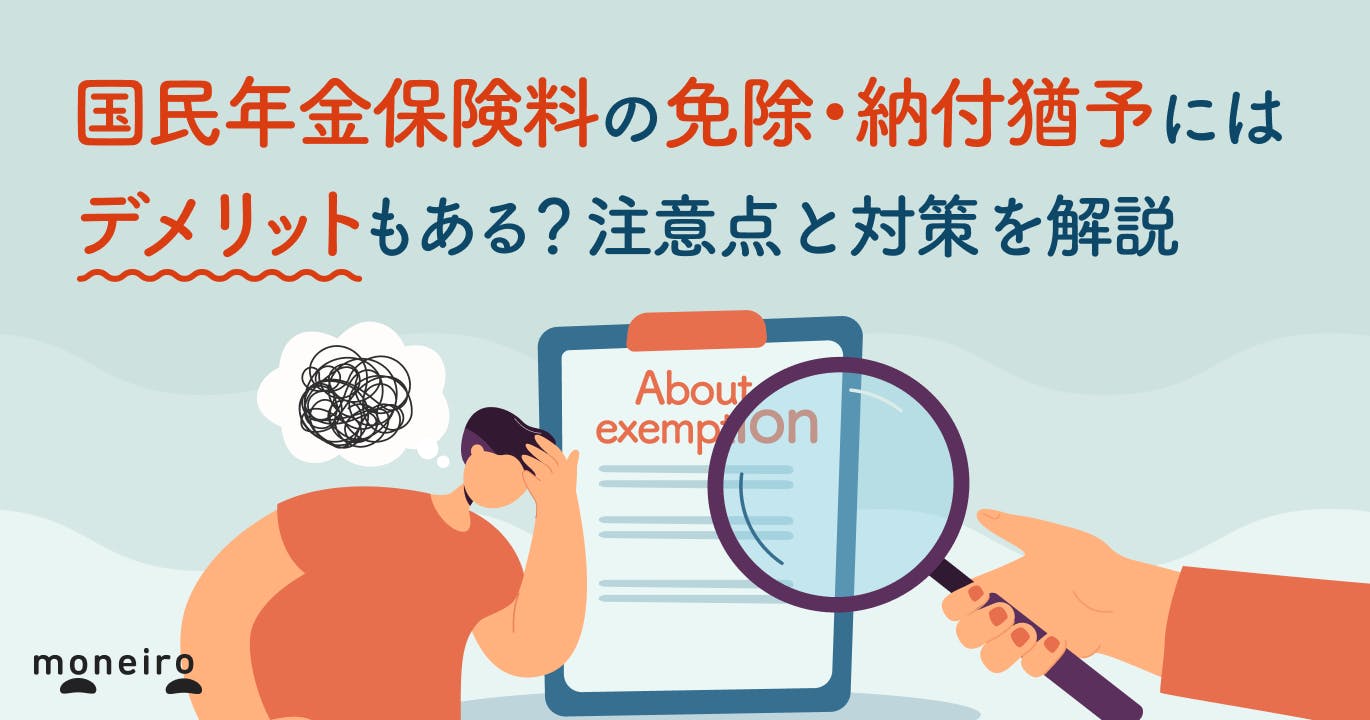
国民年金保険料の免除・納付猶予にはデメリットもある?注意点と対策を解説
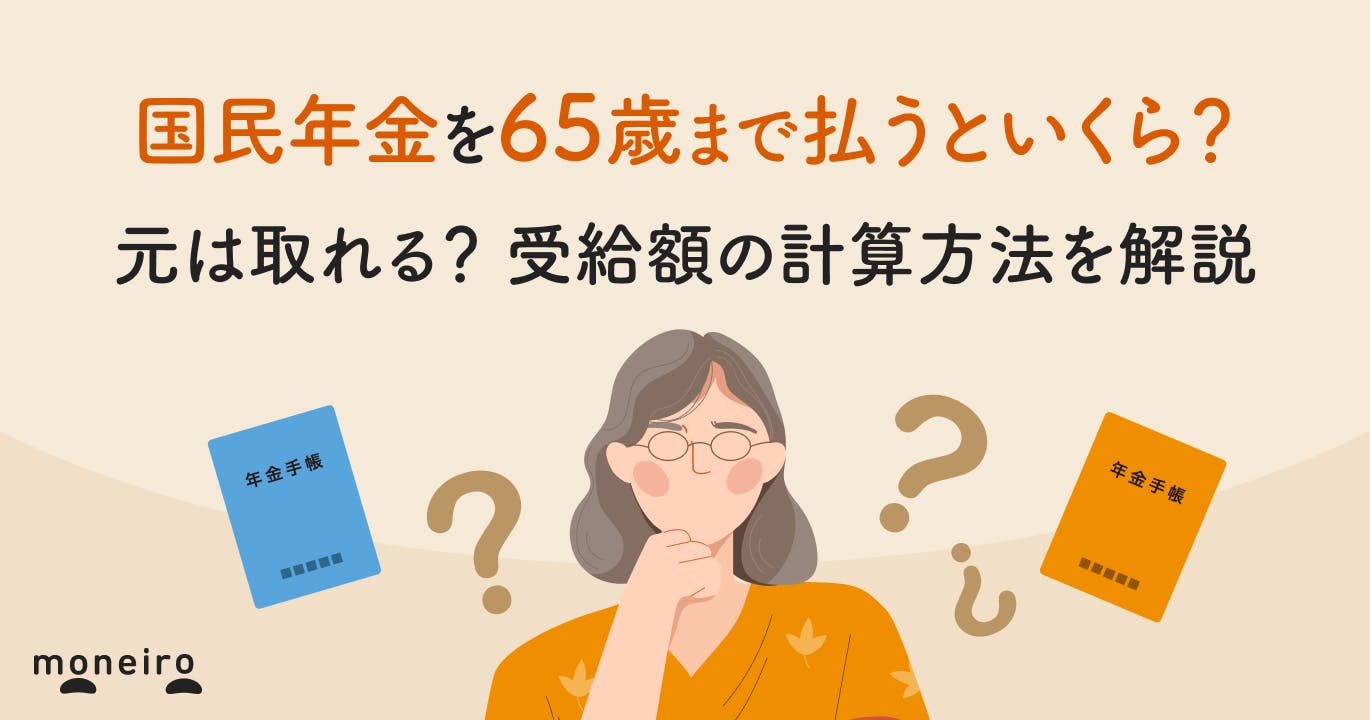
国民年金を65歳まで払うといくら?元は取れる?満額受給額と老後の不足分を徹底解説
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。