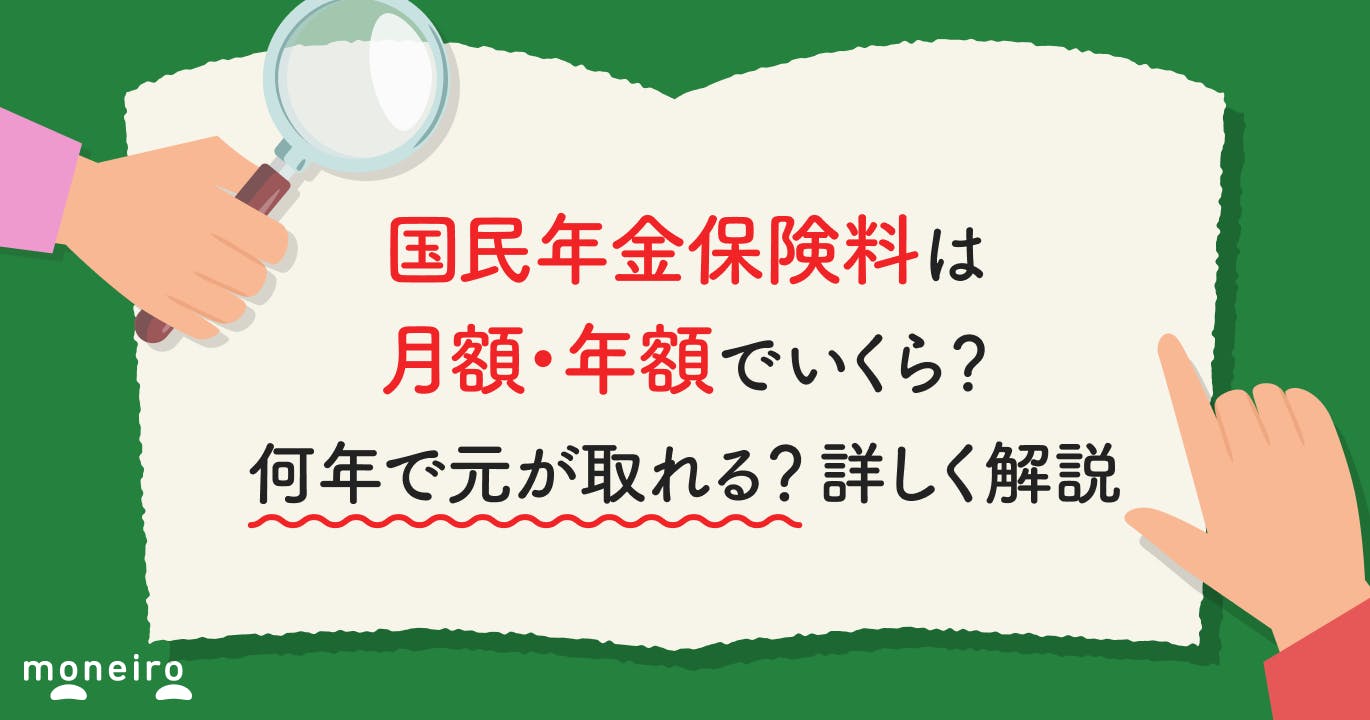国民年金保険料は月額・年額でいくら?何年で元が取れる?詳しく解説
>>年金で足りる?あなたの老後の必要額をチェック
「国民年金保険料は毎月いくら払う?」「将来、払った分はきちんと元が取れる?」そんな疑問をお持ちではありませんか?日本の公的年金制度の基礎となる国民年金ですが、その仕組みや保険料について、実はよく知らないという方も多いかもしれません。
そこでこの記事では、2025年度(令和7年度)の国民年金保険料の具体的な金額から、保険料が決まる仕組み、将来受け取れる年金額、そして何年で元が取れるのかまで、図や表を交えながら分かりやすく解説します。
記事の情報を参考に国民年金に関する疑問を解決し、ぜひ将来のライフプラン作りにお役立てください。
- 2025年度(令和7年度)の国民年金保険料の正確な月額・年額
- 保険料が割引になる「前納制度」や、支払いが困難な場合の「免除・納付猶予制度」
- 将来受け取れる年金額と、支払った保険料の元が何年で取れるかの目安
国民年金のことが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
最新の国民年金保険料はいくら?
2025年度(令和7年度)の国民年金保険料は、月額1万7510円です。2024年度(令和6年度)の月額1万6980円から530円の引き上げとなっています。年額に換算すると保険料の総額は21万120円となります。
なお、厚生労働省の発表により、2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は1万7920円となることが決まっています。
国民年金保険料の基礎知識
国民年金保険料の金額を知ったところで、この制度の仕組みについて、基本的な知識をおさらいしておきましょう。
いつからいつまで、誰が支払う義務があるのか、そして保険料が毎年どのように決まるのかを解説します。
いつからいつまで、誰が払う?
国民年金保険料の納付義務があるのは、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人です。このうち、自分で保険料を納める必要があるのは、主に第1号被保険者に分類される人です。分類は以下のようになっています。
- 第1号被保険者:自営業者、フリーランス、農林漁業者、学生、無職の人など。
- 第2号被保険者:会社員や公務員など、厚生年金に加入している人。保険料は給与から天引きされる厚生年金保険料に含まれています。
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収130万円未満の人。保険料を個別に納付する必要はありません。
なお、国民年金の納付義務期間は、原則として20歳の誕生日の前日が属する月から、60歳の誕生日の前日の属する月までの40年間(480ヶ月)です。
国民年金保険料はどうやって決まる?毎年金額が変わる理由
国民年金保険料が毎年変動するのは、「保険料改定率」を用いて調整されているためです。まず、法律によって基準となる保険料額が定められています。この基準額に、毎年の賃金や物価の変動を反映させた保険料改定率を掛け合わせて、その年度の保険料が決定されます。
計算式: 基準保険料額 × その年度の保険料改定率 = 国民年金保険料
これは、現役世代の負担能力(賃金の伸び)と、年金受給者が受け取る年金額(物価の変動)のバランスを取るための仕組みです。経済状況に合わせて保険料を調整することで、年金制度の公平性と持続可能性を保つことを目的としています。
過去10年間の保険料額の推移
過去10年間の国民年金保険料の推移は以下の通りです。
参照:国民年金保険料の変遷|日本年金機構
推移を見ると、保険料は毎年数百円単位で変動していることが分かります。
今後については、定期的に行われる「財政検証」の結果に基づき、年金制度の健全性を保つための調整が行われます。賃金や物価の上昇、少子高齢化の進展度合いなどが、将来の保険料を左右する重要な要素となります。
40年間で支払う保険料の総額は?
もし、2025年度(令和7年度)の保険料額である月額1万7510円を、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)にわたって支払い続けたと仮定すると、支払う保険料の総額は以下のようになります。
計算式: 1万7510円(月額) × 12ヶ月 × 40年 = 840万4800円
これは、あくまで2025年度の保険料額で固定した場合の試算です。実際には前述の通り、毎年度の保険料は見直されるため、総額は変動します。
将来の生活を支えるための重要な資金として、「大体これくらいの金額を生涯で納めることになる」という目安と考えるとよいでしょう。
国民年金は「いくらもらえる?」受給額のすべて
保険料を納めることで、将来どれくらいの年金を受け取れるのかは、もっとも気になるところでしょう。ここでは、満額の受給額や、支払った保険料の元が何年で取れるのか、さらに受給額を増やす方法について解説します。
40年間保険料を納めた場合の満額受給額
20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、すべての期間で保険料を納付した場合に受け取れる老齢基礎年金を満額と呼びます。
2025年度(令和7年度)の満額受給額は、年額83万1700円(昭和31年4月2日以後生まれの方)です。月額にすると6万9308円となります。
この満額の年金額も、保険料と同様に物価や賃金の変動に応じて毎年改定されます。なお、保険料の未納期間や免除期間がある場合は、その期間に応じて年金額が減額されます。
>>年金で足りる?あなたの老後の必要額をチェック
国民年金は何年で元がとれる?
支払った保険料の元が何年で取れるのかを、2025年度の金額をもとに試算してみましょう。
- 40年間の保険料総額(試算):840万4800円
- 年間の満額受給額(2025年度):83万1700円
計算式: 840万4800円 ÷ 83万1700円/年 ≒ 10.1年
この試算によると、65歳から受給を開始した場合、約10年と1ヶ月後の75歳頃には支払った保険料総額を上回る計算になります。
日本の平均寿命が男女ともに80歳を超えていることを考えると、多くの人が支払った保険料以上の年金を受け取れる可能性が高いといえます。
また、公的年金は終身(亡くなるまで)受け取れるため、長生きするほど総受給総額は増えていくことになります。
国民年金のことが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
国民年金の受給額を増やせる2つの制度
第1号被保険者の方は、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして、将来の年金額を増やすことができる制度が2つあります。より豊かな老後生活を送るため、これらの制度の活用も検討してみましょう。
付加年金
付加年金は、毎月の国民年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めることで、将来受け取る年金額を増やせる制度です。
受け取れる付加年金額は、「200円 × 付加保険料を納めた月数」で計算されます。
例えば、20年間(240ヶ月)付加保険料を納めた場合、
- 支払う付加保険料の総額:400円 × 240ヶ月 = 9万6000円
- 将来上乗せされる年金額(年額):200円 × 240ヶ月 = 4万8000円
この場合、年金を2年間受給すれば、支払った付加保険料の元が取れる計算になります(4万8000円 × 2年 = 9万6000円)。非常に有利な制度ですが、後述する国民年金基金との同時加入はできないため注意が必要です。
国民年金基金
国民年金基金は、自営業者など第1号被保険者のための、老齢基礎年金に上乗せする公的な年金制度です。
付加年金とは異なり、ライフプランに合わせて掛金や給付のタイプを自由に設計できるのが特徴です。掛金は月額6万8000円(iDeCoにも加入している場合は、その掛金と合算しての上限額)が上限で、全額が社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税の節税効果も期待できます。
終身年金が基本で、途中で亡くなった場合でもご家族が一時金を受け取れる保証期間付きのプランもあります。より手厚い老後の備えをしたい方におすすめの制度です。
国民年金保険料の納付方法と知って得する割引制度
国民年金保険料は、毎月忘れずに納付することが大切です。ここでは、基本的な納付方法と、利用することで保険料が安くなるお得な「前納割引制度」について解説します。
基本的な納付方法一覧
保険料の納付方法は、ライフスタイルに合わせて選べるよう、複数用意されています。
- 納付書(現金):日本年金機構から送られてくる納付書を使い、銀行、郵便局、コンビニエンスストアなどで現金で支払う方法です。
- 口座振替:指定した金融機関の口座から、毎月自動的に引き落とされる方法です。納め忘れがなく便利です。
- クレジットカード納付:クレジットカード会社が立て替えて納付し、後日カード利用代金として請求される方法です。カードのポイントが貯まるメリットがあります。
- スマートフォンアプリでの納付:Pay-easy(ペイジー)に対応したスマートフォン決済アプリ(PayPay、au PAY、d払いなど)を使い、納付書のバーコードを読み取って支払う方法です。
保険料が安くなる「前納割引制度」
保険料をまとめて前払い(前納)すると、割引が適用されてお得になります。前納にはいくつかの種類があり、納付方法によって割引額が異なります。
※2年前納の割引額は、令和7年度保険料(1万7510円)と令和8年度見込み保険料(1万7920円)を基に計算されています。
もっとも割引額が大きいのは「2年前納」を「口座振替」で行う方法で、1万7010円お得になります。まとまった資金の準備が必要ですが、将来にわたって必ず支払う保険料なので、可能であれば積極的に活用しましょう。
なお、申し込みには期限があるため、希望する場合は早めに年金事務所や金融機関で手続きを行いましょう。
保険料の支払いが困難な場合の免除・猶予制度
失業や所得の減少など、経済的な理由で保険料を納めることが難しい場合、未納のまま放置してはいけません。
国民年金には、保険料の支払いが免除されたり、先送りにできたりする「免除・納付猶予制度」があります。これらの制度を利用することで、将来の年金受給権を確保することができます。
免除・納付猶予制度の種類と対象者
免除・納付猶予制度には、所得などに応じていくつかの種類があります。
これらの制度を利用するには、お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口や年金事務所で申請手続きが必要です。承認されると、その期間の保険料の納付が免除または猶予されます。
免除・納付猶予期間は年金にどう反映される?
免除や納付猶予が承認された期間は、保険料を納めていなくても、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間(原則10年以上)に算入されます。これが、保険料を未納のまま放置することとの決定的な違いです。
ただし、将来受け取る年金額を計算する上では、「免除」と「納付猶予・特例」で扱われ方が大きく異なります。
- 免除の期間:国の税金負担分(2分の1)が年金額に反映されます。そのため、後から追納しなくても、年金額がまったくのゼロにはなりません。(例:全額免除の場合、満額の2分の1の年金として計算されます)
- 納付猶予・特例の期間:後から保険料を追納しない限り、年金額の計算には一切反映されません(0円)。
追納制度の活用
どちらの制度で承認された期間の保険料も、10年以内であれば後から納付(追納)することが可能です。追納を行うことで、老齢基礎年金の受給額を本来の満額に近づけることができます。
国民年金保険料に関するQ&A
ここでは、国民年金保険料に関してよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 厚生年金と国民年金保険料は両方払うのですか?
いいえ、厚生年金と国民年金は、両方を払うことはありません。日本の公的年金制度は2階建て構造になっています。1階部分が全国民共通の「国民年金(基礎年金)」、2階部分が会社員や公務員が加入する「厚生年金」です。
会社員などの第2号被保険者は、給与から天引きされる厚生年金保険料の中に、1階部分である国民年金保険料も含まれています。そのため、別途国民年金保険料を自分で納める必要はありません。
Q. 保険料を払わないとどうなりますか?
国民年金保険料を払わず放置し続けた場合、将来の年金が受け取れないだけでなく、財産を差し押さえられる可能性もあります。具体的には以下のような重大なデメリットがあります。
- 将来の老齢基礎年金が受け取れない、または減額される
- 病気やけがで障害が残った場合に障害基礎年金を、亡くなった場合に遺族が遺族基礎年金を受け取れない可能性がある
- 納付の督促が行われ、最終的には延滞金が加算されたり、財産(預貯金、給与など)が差し押さえられたりすることがある
支払いが困難な場合は決して放置せず、年金事務所や自治体の窓口などに相談の上、免除・納付猶予制度の申請を検討しましょう。
Q. 学生でも国民年金保険料を払わないといけない?
はい、20歳以上の学生は加入義務があり、原則として保険料を納める必要があります。ただし、学生で所得が一定以下の場合は、「学生納付特例制度」を申請することで、在学中の保険料の納付が猶予されます。
この制度を利用すれば、猶予された期間は年金の受給資格期間に含まれ、障害基礎年金などの保障も受けることができます。10年以内であれば保険料を追納できるので、卒業後に社会人になってから追納することも可能です。20歳になったら、忘れずに手続きを行いましょう。
まとめ
本記事では、2025年度(令和7年度)の国民年金保険料の金額から、将来受け取れる年金額、そしてお得な納付方法や支払いが困難な場合の対処法まで、幅広く解説しました。
- 2025年度の保険料は月額1万7510円、年額21万120円
- 40年間納付した場合の保険料総額は約840万円、年金の受給開始から約10年1ヶ月で元が取れる計算
- 保険料の前納は割引があり、特に「2年前納・口座振替」がもっともお得
- 支払いが困難な場合は、未納で放置せず「免除・納付猶予制度」の申請を検討する
国民年金は、老後の生活だけでなく、万が一の病気やケガ、死亡といったリスクにも備えるための重要な社会保険制度です。自分の納付状況をきちんと把握し、将来のために計画的に保険料を納めていきましょう。
>>年金で足りる?あなたの老後の必要額をチェック
国民年金のことが気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

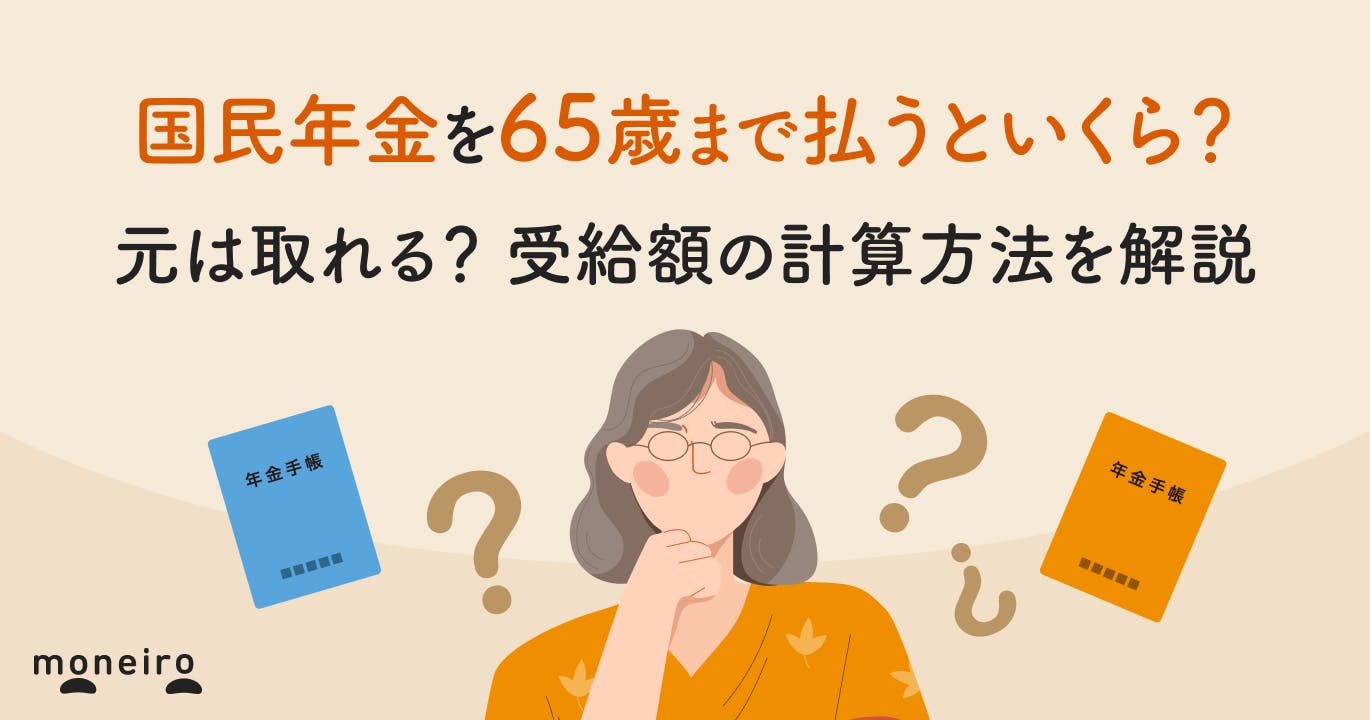
国民年金を65歳まで払うといくら?元は取れる?満額受給額と老後の不足分を徹底解説

国民年金と厚生年金の違いとは?加入条件や受給額、保険料などをわかりやすく解説
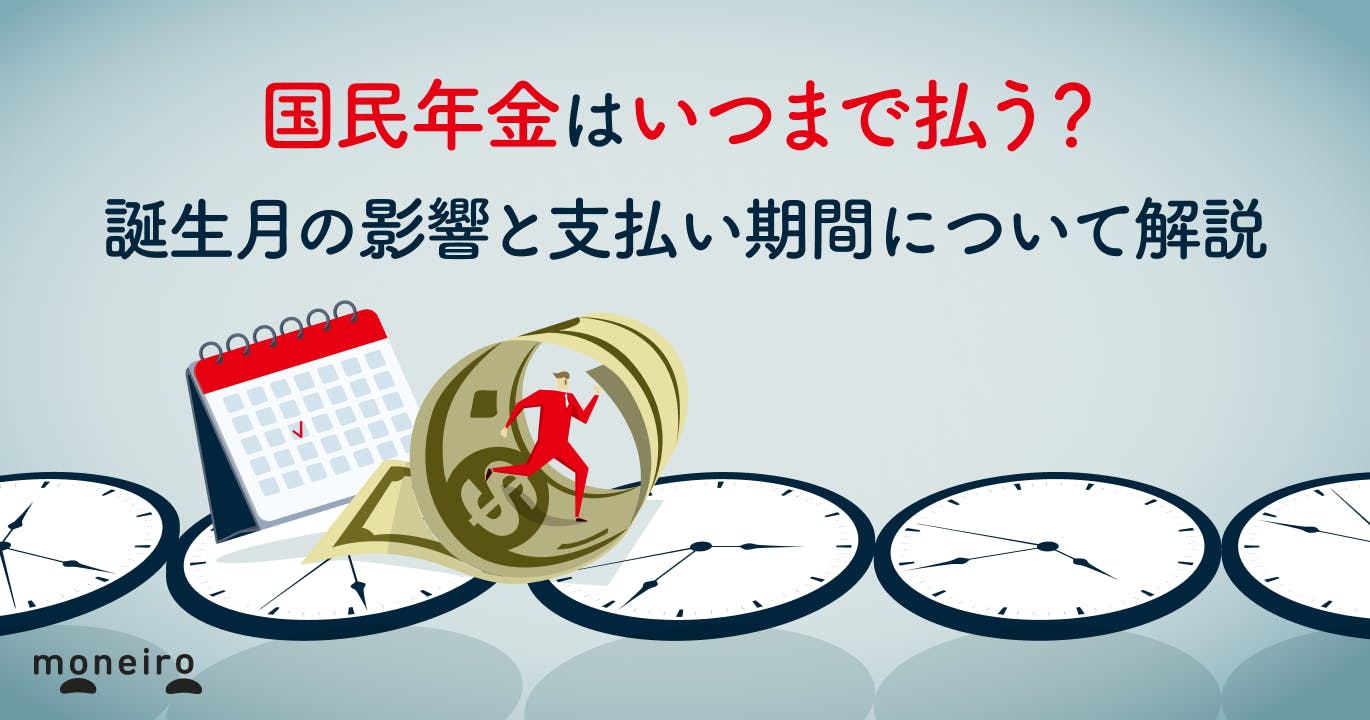
国民年金はいつまで払う?誕生月の影響と支払い期間をわかりやすく解説
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。