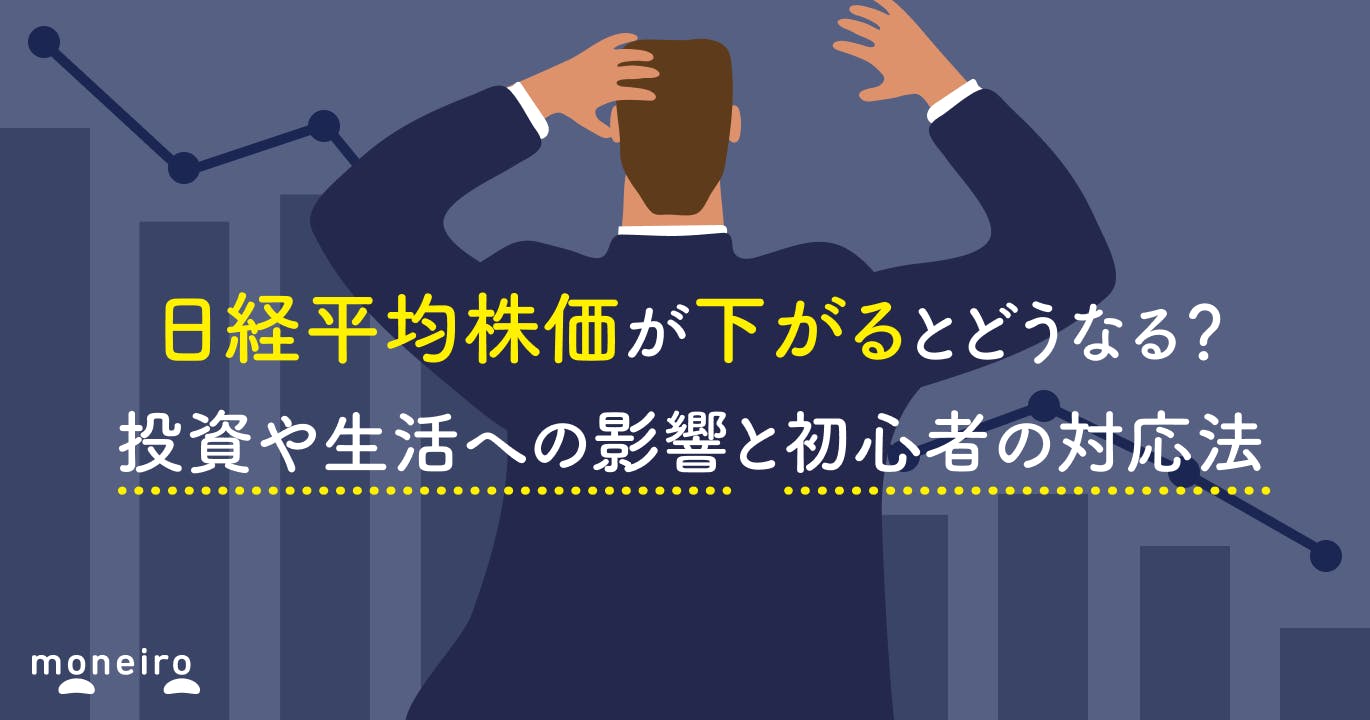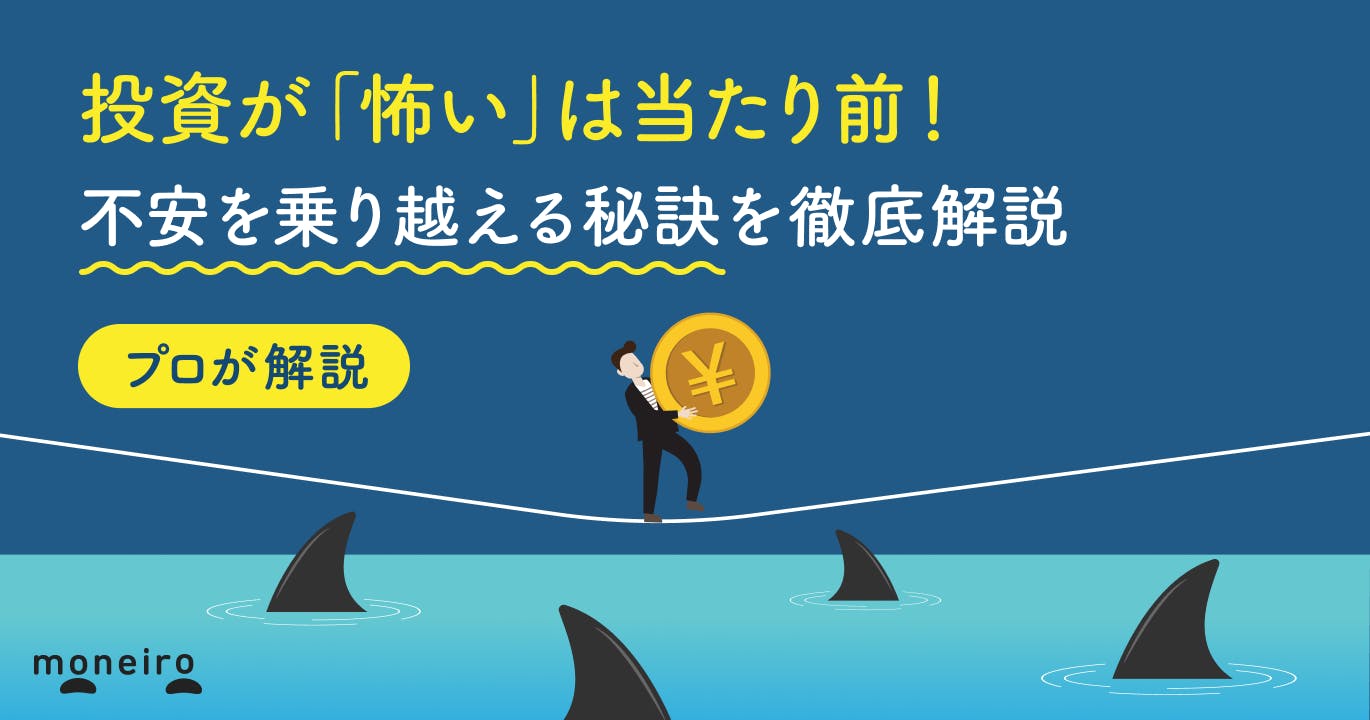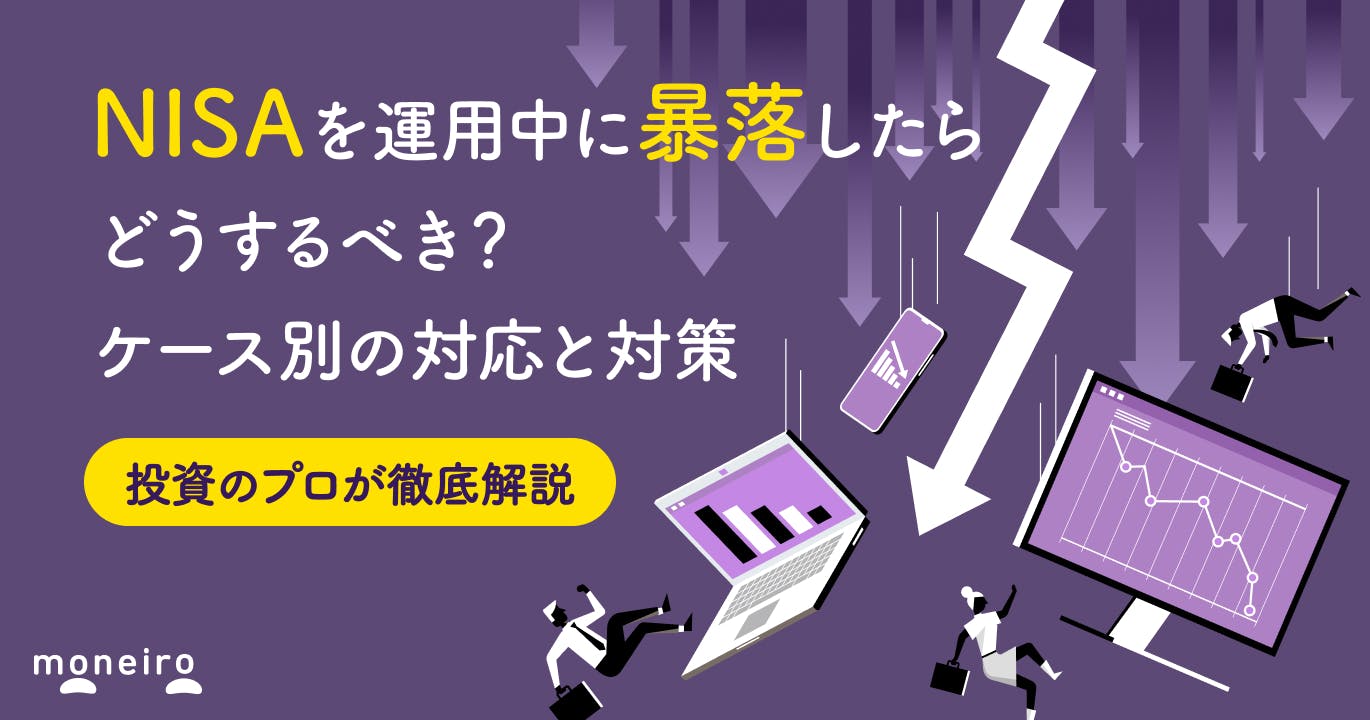日経平均株価が下がるとどうなる?上がる場合は?投資や生活への影響と初心者の対応法
»株価がわかってきた今こそ、投資タイプを診断
ニュースで「日経平均株価が下落」と聞くと、「景気が悪いの?」「自分の投資に影響するの?」と不安になる方も多いでしょう。日経平均株価とは、日本を代表する225銘柄の株価を平均した指数のことで、日本の株式市場の動きを把握できる代表的な指数です。
株価に関する指数なので、短期的に大きく動くことがありますが、一喜一憂する必要はなく、長期的に見れば下落がチャンスになる場合もあります。
本記事では、日経平均が下がると経済や資産にどんな影響があるのか、逆に上がった場合のプラスの影響も整理。初心者が知っておきたい基本知識と、下落局面で取るべき対応を専門的にわかりやすく解説します。
- 日経平均株価が下がる仕組み
- 経済全体や個人資産への具体的な影響
- 株価下落時に取るべき冷静な行動
投資について気になっているあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:将来必要な金額と自分に必要な投資がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:専門家と一緒に考える資産運用
日経平均株価が下がるとはどういうこと?
日経平均株価は、東京証券取引所のプライム市場に上場している企業のうち、日本経済新聞社が選んだ225銘柄の株価をもとに算出される株価指数のことです。
指数は「株価平均型」で算出され、日本の株式市場全体の動きを示す重要な指標として広く知られています。
そのため、日経平均株価の下落が続くと、多くの企業の業績悪化や不景気を連想しがちですが、必ずしも日本経済全体の悪化を示しているわけではありません。
つまり、日経平均株価は景気の悪化以外にも、いくつかの要因によって下落する可能性があります。
株価指数が下がる=経済が悪いとは一概に言えない理由
日経平均株価が下落しても、「日本経済が悪化している」と直ちに判断することはできません。
理由のひとつは、日経平均株価の算出方法にあります。日経平均株価は「値がさ株」と呼ばれる、株価の高い銘柄の影響を受けやすい「平均算出型」が採用されています。
そのため、一部の株価の高い銘柄が下落すると指数全体の押し下げる要因になります。逆も同様です。
また、為替や海外市場の動向、経済状況は、個々の企業の株価や業績にも影響します。とくに為替は海外事業を幅広く展開している企業にとっては、業績が変動する大きな要因となり、株価にも影響します。
程度の差はありますが、これらの要因が日経平均株価の上昇や下落に少なからず関係していると言えます。
参考:TOPIXと日経平均株価の違い
日本を代表する株価指数には、日経平均株価のほかに「TOPIX(東証株価指数)」があります。この2つの指数は以下の点において特徴が異なります。
- 計算対象となる銘柄の範囲
- 算出方法
まず銘柄の範囲ですが、日経平均株価は225銘柄で構成されますが、TOPIXは原則として東京証券取引所プライム市場に上場する全ての銘柄を対象として算出されています。
TOPIXは、日経平均株価より、さらに多くの企業の動きを反映しているので、市場全体の動きをより詳しく把握したい人は、TOPIXも合わせて活用すると良いでしょう。
また、日経平均株価とTOPIXは指数の算出方法が異なります。日経平均株価が「平均株価型」であるのに対し、TOPIXは「時価総額加重型」で算出されます。
日経平均株価が一部の値がさ株の影響を受けやすいのに対し、TOPIXは時価総額の大きい銘柄の影響を受けやすいという違いがあります。
日経平均下落が経済全体に与える影響
日経平均株価の下落が続くことは、多くの企業で株価が下落していることを示し、企業業績が悪化している、あるいは業績見通しが悪くなっている可能性があります。
特に日経平均株価の下落が長期化すると、企業は景気後退を意識するようになり、新たな設備投資を控えたり、資金調達の需要が鈍化したりします。
また、企業の業績不振は、給与や賞与の減少につながり、個人も景気の悪化を実感するようになります。消費マインドが冷え込むと、買い控えも進みやすく、最終的には実態経済にも影響が及ぶことになります。
企業の業績や雇用への影響
日経平均株価が継続的に下落すると、指数に採用されている225銘柄の多くが下落している可能性があります。
企業は自社の株価が低迷すると、資金調達が困難になる恐れがあり、設備投資や新規事業への参入など、事業拡大への投資がやりにくくなるかもしれません。
一方で、株価低迷の原因が業績悪化の場合、給与や賞与のカット、リストラや採用控えにつながり、雇用や賃金へ影響が及びます。
悪循環から抜け出せなければ、業績がさらに悪化する可能性もあるため、投資家は投資対象の選定を慎重に行う必要があるでしょう。
消費マインドや投資家心理への波及
日経平均株価の下落は、個人の消費行動にも少なからず影響します。
日経平均株価の継続的な下落は、景気後退を連想させ、将来不安から支出を控える「逆資産効果」が生じやすくなります。支出控えにもつながり、景気がよりいっそう冷え込む要因になります。
また、投資家心理にもマイナスの影響を与え、特に株価の急落局面では不安から売りが売りを呼ぶ連鎖が起こりやすくなります。このような状況下では、企業業績以上に投資家心理が株価を動かす要因となります。
為替(円高・円安)や海外市場との関係
日経平均株価が下落すると、日本の株式市場は株安の状況なので、理論上は円が売られ、円安方向に進みやすくなります。
ただし、株価の下落にはさまざまな要因が重なっていることがほとんどです。下落したからといって、直ちに円安が進むわけではないことを理解しておく必要があるでしょう。
一方で、日経平均株価は世界経済の動向に大きく左右されます。特に米国株と連動しやすいという特徴があります。
常に連動しているわけではありませんが、米国市場が大幅に下落すると、翌日の東京市場でも売りが先行する傾向があります。
日経平均が上昇した場合の影響
日経平均株価の上昇は、業績の好調さや見通しの明るさを予感させるので、投資家にとっては好材料となります。
取引が活発化し、企業の成長や個人資産の増加を通じて、経済全体に好循環をもたらします。
企業業績・雇用・賃金へのプラス効果
日経平均株価が上昇すると、多くの企業の株価も概ね上昇している状況です。
自社の株価が上がれば、市場からの評価が高まり、企業の信用力が増します。銀行からの融資を受けやすくなったり、株式発行による資金調達が有利になったりします。
それぞれの企業活動が活発になるので、日経平均株価の上昇は経済全体にとって好材料となるでしょう。
調達した資金を元手に、企業は新たな設備投資や研究開発、人材採用を積極的に行えるようになり、事業の成長を加速させることができます。結果として、雇用の創出や賃金の上昇といった形でも、経済全体にプラスの効果をもたらします。
投資信託や株式資産の評価額が上がる
日経平均株価が上昇すると、例えばインデックスファンドなどの投資信託、個別株などの資産価値が増加します。
NISAやiDeCoなどでコツコツと資産形成を行っている人にとっては、資産評価額が上昇することで、安心感にもつながります。
景気回復期待による消費や投資意欲の拡大
株価の上昇は、人々の消費マインドを刺激します。保有する株式や投資信託の評価額が上がることで資産が増加し、将来への安心感から消費意欲が高まる「資産効果」が生まれます。
これにより、高額商品の購入や旅行など、消費が活発になり、経済全体に好循環をもたらすことが期待されます。
また、株価指数は「景気の先行指標」とも言われます。日経平均株価の上昇は、多くの企業の業績見通しが明るいことを市場が織り込んでいる証拠です。
上昇がさらに続けば、これから景気が良くなるだろうという期待感が社会全体に広がり、企業の投資意欲や個人の消費意欲をさらに後押しする効果があります。
投資について気になっているあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:将来必要な金額と自分に必要な投資がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:専門家と一緒に考える資産運用
日経平均株価が下落したら投資にどんな影響がある?
日経平均株価が下落すると、投資信託や株式など、日本株を含む金融資産の評価額も同じように下がります。
また、私たちの老後を支える年金資産の運用にも影響します。ただし、どのような形で資産を保有しているかにより、影響の度合いは異なります。
株式やETFを保有している人への影響
日経平均株価に連動する成果を目指すETF(上場投資信託)を保有している場合、その価格は日経平均とほぼ同じ動きになるので、日経平均株価が下落すれば、同様に下落します。
また、個別株を保有している場合も保有資産の評価額が減少している可能性があり、下落の要因によっては、225銘柄以外の株式も同様に下落しているかもしれません。
したがって、株式や日本株に関連するETFを保有している場合、これら資産の評価額は下がることになるでしょう。
NISA・投資信託の基準価額への影響
NISA口座で運用している資産も、市場の変動と無関係ではありません。日経平均株価やTOPIXなどに連動するインデックスファンドを保有している場合、日経平均株価が下落すれば、それらの基準価額も同様に下落します。
また、日本株を多く組み入れているアクティブファンドなども、市場全体の下落の影響を受ける可能性が高いでしょう。
これは、特定口座で日本株式を投資対象とする投資信託を購入している場合も同様です。
年金や保険資産への影響
直接、投資信託や株式に投資をしていなくても、日経平均株価の下落が私たちの資産に影響を与える場合があります。
例えば、私たちの公的年金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、国内外の株式で資産の一部を運用しています。
そのため、日経平均株価が長期的に低迷すると、GPIFが運用している年金資産にも影響を与えることになります。将来の年金給付水準に影響が及ぶ可能性もゼロではありません。
また、個人で加入しているiDeCo(個人型確定拠出年金)で日本株式を含む投資信託で運用している場合や、変額保険に加入している場合も、株価の下落は運用成績の悪化、つまり資産評価額の減少に直結します。
日経平均株価が下落しても慌ててはいけない理由とは
日経平均株価に連動する成果を目指す投資信託やETF、あるいは個別株に投資をしている人は、保有している資産の評価額が下落すると、このまま保有し続けて良いのか、心配になるものです。
しかし、リスクのある金融商品に投資をした場合、短期的な下落、もちろん上昇も同様ですが、これらは常に起こりうることです。
市場が大きく変動している時こそ、パニックにならず、自身の投資方針を再確認しましょう。長期的な視点と分散投資を心掛けることでリスクを管理し、下落には冷静に対応することが大切です。
株価変動は常に起こる
株式市場において、株価が日々変動することはごく自然なことです。企業業績、金利動向、国内外の政治情勢など、さまざまな要因によって株価は常に上下しています。
時には、予期せぬ出来事によって暴落が起こりますが、投資を行う上では避けられないことです。大切なのは短期的な値動きに一喜一憂せず、冷静に市場と向き合う姿勢です。
多くの株価指数は長期にわたり成長している
歴史を振り返ると、日経平均株価はこれまで数々の暴落を経験してきました。一部を挙げるだけでも1987年のブラックマンデー、2008年のリーマンショック、そして2020年のコロナショックなど、市場が大きく混乱した時期は何度もありました。
しかし、一時的に大きく下落しても、数ヶ月・数年という期間で振り返ってみると、株価はいずれ回復し、長期的には成長を続けていることがわかります。この歴史的な経験則は、下落局面でも冷静さを保つための大きな支えとなります。
長期・分散投資がリスクを軽減する
株価下落時の資産の目減りを抑えるために、資産運用の鉄則とされるのが「分散投資」です。これは、投資先を一つの資産に集中させるのではなく、値動きの異なる複数の資産に分けて投資する手法です。
日本株だけでなく、海外株式や債券、REIT(不動産投資信託)などを一緒に保有することで、ポートフォリオのリスクが小さくなり、ある資産が値下がりしても、他の資産の値上がりでカバーする効果も期待できます。
このようにポートフォリオ全体でリスクを管理することが、安定した資産形成につながります。
下落局面で初心者が取るべき行動
株価下落時は、慌てて売却する「狼狽売り」を避け、積立投資を継続することが基本です。むしろ、優良な資産を安く購入できる好機と捉える長期的な視点が求められます。
一時の感情に流されないようにして、事前に決めた投資ルールに従うことが大切です。
慌てて売却しない
株価が急落した際に最も避けるべき行動が「狼狽売り」です。これは、市場のパニック的な雰囲気にのまれ、冷静な判断を失って保有資産を売却してしまうことです。売却した時点で損失は確定してしまいます。
歴史的に見ても、株価は暴落後に回復するケースが多いため、慌てて売ってしまうと、その後の価格回復による利益を得る機会を自ら手放すことになりかねません。
ちなみに、保有資産の評価額が下がって元本が割れている状況のことを「含み損」と言います。売却しない限り実際の損失にはなりません。
積立投資(ドルコスト平均法)をコツコツ続ける
NISAのつみたて投資枠などで積立投資を実践している場合、下落局面でも投資を中断せずに継続することが大切です。
定期的に一定額を投資し続ける「ドルコスト平均法」は、価格が低い時にはより多くの口数を、価格が高い時には、より少ない口数を購入する投資方法です。
平均購入単価を抑える効果が期待できるだけでなく、下落時に多くの口数が購入できるため、将来、価格が回復した際の利益が大きくなりやすいのが特徴です。
「下落」に対する視点を変える
長期的な視点を持つ投資家にとって、株価の下落は悲観的な出来事ではなく、優良な資産を割安な価格で購入できる絶好の機会と捉えることができます。
「安く買って高く売る」という投資の基本に立ち返れば、市場全体が悲観に包まれている時こそ、冷静に買い向かうチャンスといえるでしょう。
株価下落を正しく理解するための基礎知識
日経平均株価は、日本の経済活動の状況を理解する上で重要な指標です。
日本株を保有している人は、日経平均株価への理解をさらに深めて、下落時にも合理的な判断ができるようになることが望ましいでしょう。
「日経平均=日本経済」ではない
日経平均株価は日本の景気を映す鏡として広く利用される指数ですが、日本経済のすべてを表しているわけではないことを理解しておく必要があります。
あくまで日本経済新聞社が選んだ225社の株価動向を示す指標であり、非上場企業や中小企業の状況は反映されていません。
経済の実態をより正確に把握するには、東証プライム市場の全銘柄を対象とするTOPIXなど、他の指標と合わせて多角的に分析することが必要になります。
海外要因(米国株・金利動向)の影響
日経平均株価の動きを理解する上で、海外、特に米国の政治や経済の動向は無視できません。
米国株市場の動向は、翌日の日本市場に大きな影響を与えます。世界を牽引する海外のリーディングカンパニーや主要セクターの動きにより、日本の関連企業の株価が影響を受け、間接的に日経平均株価が上下する要因になります。
また、米国の政策金利の動向や各種経済指標の発表も重要なイベントになります。とくに昨今は米国の政策金利に注目が集まっています。
米国金利が下がり、日本円の金利が上昇すると、日米の金利差が縮小し、ドルの魅力が相対的に薄れるため、日本の株式市場に資金が集まる可能性があります。そうなると日経平均株価が上昇する要因のひとつとなるでしょう。
銘柄の「定期見直し」の影響
日経平均株価を構成する225銘柄は、固定されたものではなく、定期的に見直し(入れ替え)が行われます。
市場代表性(※)や流動性などを基準に、時代の変化に合わせて銘柄が選定されるので、新しい成長企業が採用されたり、市場での影響力が低下した企業が除外されたりします。
定期見直しは、指数に現代の日本経済の状況を反映させるために行われますが、銘柄の見直し自体が、投資家の売買を誘発し、株価の変動要因となることもあります。
※ここでいう市場代表性とは、構成銘柄が東証プライム市場の特徴を正確に反映している状態かどうかという概念のこと
まとめ
日経平均株価の下落は、経済や個人の資産にさまざまな影響を及ぼしますが、その仕組みを正しく理解することが重要です。指数の背景を知れば、ニュースの裏側まで読み解く力も身につきます。
株価の短期的な変動は避けられないものであり、歴史を振り返れば市場は数々の危機を乗り越えて成長してきました。
長期的な資産形成を目指すのであれば、下落局面に慌てて売却するのではなく、むしろ積立投資を継続し、割安になった資産を購入する好機と捉えることが賢明です。
市場の動きに一喜一憂することなく、自身の投資方針に基づいた冷静な判断を心掛けましょう。
»どんな投資が自分に合う?3分でかんたん診断
投資について気になっているあなたへ
マネイロは働く世代向けにお金の診断・サービスを提供しています
▶3分投資診断:将来必要な金額と自分に必要な投資がわかる
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
▶オンライン無料相談:専門家と一緒に考える資産運用
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
土屋 史恵
- ファイナンシャルプランナー/金融ライター/編集者
神戸市外国語大学卒業後、外資系生命保険会社、都市銀行にてリテール営業、法人営業に携わる。遺言信託など資産承継ビジネスに強み、表彰歴あり。その後は長年の金融機関勤務経験を活かし、金融メディアに転職。記事執筆や編集などを担当。現在はフリーランスとして活動中。AFP、FP2級、証券外務員一種を保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。