30代・40代だからこそつみたてNISAがおすすめ?銘柄の選び方と賢い運用方法
»あなたに合った投資を3分で無料診断
「30代、40代はつみたてNISAを始めた方が良い?」「つみたてNISAをどう活用するべき?」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
つみたてNISAは30代、40代と働き世代の利用者が多い制度のひとつです。
つみたてNISAを利用して将来資金の準備をしたいと考えている人もいるでしょう。
一方で、つみたてNISAでどのように商品を選べば良いか悩むこともあるかもしれません。また、投資の目的によってはつみたてNISAだけではなく、他の制度や金融商品を組み合わせた方が良い場合もあります。
本記事では「つみたてNISAを始めるべき?どう活用した方が良い?」と悩んでいる30代・40代の働き世代に向けて、投資の基本知識とつみたてNISAの商品の選び方について投資のプロが解説します。
※本記事では2023年までのNISA制度を「旧NISA」または「旧制度」、2024年から始まる新しいNISAを「新NISA」または「新制度」と表記しております
※本記事は2023年までの旧制度の内容を中心に記載しています
※旧制度のつみたてNISAの仕組みは新NISA(新しいNISA)のつみたて投資枠へ引き継がれます
※旧制度で新規買付ができるのは2023年末までです。2024年以降は非課税保有期間が終了するまで、資産を非課税で保有することができます
(参考:新しいNISA : 金融庁)
- 30代・40代は働き世代であり、運用期間も長く確保できるため、将来資金を準備するのにベストなタイミング
- つみたてNISAで銘柄を選ぶ時は「ベンチマーク」を参考にする
- つみたてNISAは目的に合わせて「貯蓄型の保険」「銀行預金」「iDeCo」などと組み合わせる
NISAの運用について知りたいあなたへ
マネイロではよりうまくNISAを運用できるよう、さまざまな無料サービスを提供しています。
▶3分投資診断:あなたとNISAの相性がわかる
▶「NISAで始める資産運用の基本」:専門家が基本を30分で解説
▶「成長投資枠の失敗しない銘柄選び」:銘柄選びがわかる30分解説
▶NISAオンライン相談:専門家にスマホで直接相談
つみたてNISAを始める前に:投資の基本
つみたてNISAとは、少額からの「長期・積立・分散投資」を支援するためにスタートした非課税制度です。
毎年40万円を上限として一定の投資信託を積立方式でコツコツ購入すると、購入後最長20年間、保有中に得た分配金や値上がりした後に売却して得た利益に対して非課税で運用することができます。
つみたてニーサの対象商品は、手数料水準が低く(販売手数料がゼロ、信託報酬が一定水準以下)、頻繁に分配金が支払われないなど、長期運用に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されています。
そのため、初心者でも安心して始めやすいように制度設計されていますが、デメリットなどもあります。
ここではつみたてニーサを始める前に知っておきたい投資のポイントをご紹介したいと思います。
①投資先における日本と海外の違い
・為替変動リスクなし
・人口減少で経済縮小が懸念
【海外】
・為替変動リスクあり
・人口増加で経済成長が期待
日本と海外の資産の大きな違いの一つは、「為替変動リスク」があるかどうかです。
為替変動リスクとは、為替相場の変動によって、外貨建て資産を円換算した時に資産の価値が上がったり、下がったりするリスクです。
例えば米ドル建ての金融商品で運用する場合、投資した時より円安・ドル高のタイミングで売却すると利益が見込めますが、円高・ドル安のタイミングで手放すと元本割れをしてしまう可能性があります。
為替変動リスクがあるものの、メリットもあります。
日本は超低金利が続いているため、海外の金利も魅力のひとつといえるでしょう。そして海外資産の最大の魅力は経済成長力です。
日本国内は少子高齢化の影響で労働人口は今後減少していく見込みです。働く人、すなわちお金を稼いで使う人が減ると、経済活動の規模が小さくなり、社会保障費も増大する傾向があります(人口オーナス)。
一方世界に目を向けると、現在人口が増加し、生産力が増加している国がいくつもあります。
国連の予想によると、世界の人口は2020年現在で77億9千万人なのに対し、2060年に101億5千万人に増加することが予想されています。
世界に目を向けると、今後人口が増加し、経済が発展していくことが期待できる国が多くあるでしょう(人口ボーナス)。
海外の成長力を自分の資産運用にも利用したい人は、世界の資産、特に世界株式に投資をすることを検討するのも一案でしょう。
②投資におけるリスク
一般的に投資の世界の「リスク」とは、価格が目減りすることだけを指すのではなく、「価格のブレ幅」のことを指します。
一般的には価格が目減りすることだけを指すと思われがちですが、逆の価格が上にブレる(収益が出る)場合も指します。
また、「リスクが大きい」と言うと、大きく収益が上がる可能性がある反面、大きく損失が出る可能性もあることを指し、「リスクが小さい」と言うと得られる収益は大きくないが、大きな損失が出る可能性も少ないことを指します。
投資の世界では、「ローリスク・ハイリターン」は理論上ありえないというわけです。
そのため、リスクが大きい商品と小さい商品をバランスよく配分することでリスクをできるだけコントロールするために、ポートフォリオを組んだり、定期的に見直しをしているのです。
攻めの運用か、守りの運用か、その時の市場の動向も加味しながら、自分好みにステータスをカスタマイズするイメージです。
③ポートフォリオ
ポートフォリオとは「金融商品の組み合わせ」のことを指します。「ポートフォリオを組む」という表現もよく使われます。
実際にどんな商品を購入しようか、株はどの銘柄を買おうか、何株買おうかなど、を検討して、金融商品を組み合わせることを指します。
ローリスクの商品とハイリスクの商品を、自分のリスク許容度に応じて組み立てていきます。
参考)ポートフォリオのバランス
投資目的や投資スタイル(一括投資か積立投資か)、投資期間によって、そして何より自分の好みによって最適なバランスは異なります。
そのため、それぞれの資産と価格の振れ幅(リスクの大きさ)、資産同士の関係性などを考慮しながら組み立てていきましょう。
例えば、一般的に株式と債券は逆の動きをする傾向があると言われています。
「株価が下がった時に債券が支えてくれる、あるいは債券が下落した時に株価が支える効果」を期待しながら、ポートフォリオを組むことで、リスクをコントロールしようと工夫するわけです。
ただし、リーマンショックの時のような経済危機が起こった場合は、ポートフォリオの工夫も虚しく、ほとんどの資産が一斉に下落する可能性もあります。
元本保証のない投資商品で運用する場合は、これらの工夫をしながら長期間かけてゆっくりと増やしていくようにしましょう。
ちなみに、私たちの年金を運用している年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、外国株式・外国債券・国内株式・国内債券をそれぞれ25%ずつの基本ポートフォリオで運用しています。
④分散投資
- 世界株をコアに、サテライトとして日本株やバランスファンドなどで調整
- より資産を増やしたい人は、変動幅は大きくなるが先進国株や新興国株も
すべての卵を1つのカゴに入れてしまうと、カゴを落としたらすべての卵が割れてしまいます。
しかし、いくつかのカゴに分けて卵を入れておくと、1つのカゴを落としても残りの卵は無事です。
このことから資産運用においては「投資先や投資時期を分散させてリスクも分散させることが重要」と言われています。
30代・40代がつみたてニーサで長期間かけて積立投資をする場合は、「投資時期」を毎月分散しながら運用することができます。
この「長期・積立・分散投資」によりリスクの軽減が期待できると言われています。
「長期・積立・分散投資」で毎月コツコツ運用する場合は、ローリスク・ローリターンの商品をあまり多くしてしまうと、損失が出るリスクは抑えられるでしょうが、反対に収益を得るチャンスも限られてしまいます。
そのため、つみたてNISAで長期間かけて資産運用をする場合は、世界株式などの長期的に成長が期待できる資産をコア(主軸)とし、サテライトとして日本株やバランスファンドなどで調整するのも一案でしょう。
もしくは先進国株式と新興国株式というように組み合わせるのも良いでしょう。
価格変動の幅は大きくなりますが、より資産拡大を目指したい人にはマッチするかもしれません。
このように、老後に向けてより資産形成を狙いたいのなら、ローリスク・ローリターンの商品では「増えないリスク」があることも考慮したいところです。
一点気をつけたいのは、つみたてNISAに固執しすぎないことです。
つみたてNISAは取り組む資産運用のごく一部に過ぎません。つみたてNISAの中で分散しすぎてしまうよりも、つみたてNISAと他に何を組み合わせるかを考えることが大切です。
参考)インデックス(パッシブ)とアクティブの違い
・指標に追随した運用成果を目指しているもの
【アクティブ】
・指標以上の運用成果を目指しているもの
投資信託を運用スタイルで分けるとインデックス(パッシブ)型とアクティブ型があります。
この2種類の運用方法の違いを理解することは、資産運用をスタートするうえで非常に重要です。
多くの投資信託には「ベンチマーク」と呼ばれる指標が存在します。
日本株式なら「日経平均株価」や「TOPIX」、アメリカ株式なら「S&P500」「NASDAQ」「ダウ平均株価」などがあります。
この指標にピッタリ沿うように運用することを目指しているものが「インデックス型」です。
一方で、指標を上回る成果を目指して運用するのが「アクティブ型」です。
一般的にインデックス型の方が、アクティブ型より手数料が安い傾向があります。
つみたてNISAに採用されている銘柄の多くはインデックス型です。
よくインデックス型の方がアクティブ型よりもリスクが低いと思っている人がいますが、決してそうとは言い切れません。
インデックス型はすべて安心だと勘違いしていると、思わぬ失敗を招く危険があるので注意が必要です。
つみたてNISAの銘柄はベンチマークで選ぶ
つみたてNISAの銘柄を選ぶ時、人気ランキングを参考に銘柄を選ぶ人が多いのではないでしょうか。
しかし、投資スタイルによって、最適な投資信託、さらに最適なポートフォリオは異なります。
そこで、ベンチマークを参考に、自分の銘柄を選ぶ方法について解説します。
ポイント①ベンチマーク
投資信託が運用の指標にしている市場の指数のこと
つみたてNISAに採用されている銘柄の多くはインデックス型の投資信託です。
インデックス型の投資信託はベンチマークに沿って運用することを目指すため、運用成果はベンチマークに左右されます。
つみたてNISAを活用して長期・積立・分散投資で資産形成をしたい人は、今後長期間にわたって成長が期待できる市場の指数をベンチマークに設定している投資信託を選ぶ必要があります。
日本の国内株式と言っても、日経平均株価かTOPIXかによって、組み入れられている株式の銘柄や比率が異なるため、運用成果も異なります。
世界株式の投資信託には「先進国株」や「全世界株」あるいは「先進国から日本を除く」など、さまざまなベンチマークがあります。
ベンチマークをしっかり選べると、同じような銘柄を重複して買うことも防ぐことができ、効率的に資産を分散できます。
つみたてNISAの銘柄選びの際はベンチマークをポイントに選びましょう。
参考)ベンチマークの選び方
つみたてNISAの銘柄を見ていると、よく似た名前の商品が多いと感じる人が多いのではないでしょうか。
投資信託も銘柄の名前を見るとどこの運用会社の、どんな資産に投資をする投資信託なのかがわかるものが多くあります。
名前の最初には運用会社名が入るものが多く、その次に何に投資をするのかが入るものが多い傾向です。
例えば「◯◯日経225インデックスファンド」と言えば、日経平均株価をベンチマークに設定しているインデックス型投資信託であることがわかります。
また、「◯◯S&P500インデックスファンド」と言えば、ダウ・ジョーンズ・インデックスが算出しているアメリカの代表的な株式指数「S&P500」をベンチマークに設定しているインデックス型の投資信託であることがわかります。
このように、投資信託の中には名前を見ただけでどのような投資信託かがわかる銘柄が多くあります。
特に、インデックス型の投資信託はベンチマークに設定する指数に連動することを目指して運用しています。
商品を選ぶ際は投資信託の名前から、ベンチマークの商品を選ぶようにするとスムーズでしょう。
NISAの運用について知りたいあなたへ
マネイロではよりうまくNISAを運用できるよう、さまざまな無料サービスを提供しています。
▶3分投資診断:あなたとNISAの相性がわかる
▶「NISAで始める資産運用の基本」:専門家が基本を30分で解説
▶「成長投資枠の失敗しない銘柄選び」:銘柄選びがわかる30分解説
▶NISAオンライン相談:専門家にスマホで直接相談
つみたてNISAのベストな組み合わせ方【30代・40代】
つみたてNISAだけで資産形成が万全かというと、そうとも言い切れません。
旧制度のつみたてNISAは年間40万円(毎月3万3333円)までしか投資できないうえに、非課税で運用できる期間は20年間しかありません。
30代・40代の人には少し物足りないと言えるでしょう。
また、つみたてNISAは投資できる銘柄が金融庁の選定基準を満たした商品に限られています。
いろんな商品の中から商品を選んで運用したいという人や、万が一の時の保障を付けて運用したいという人には物足りないかもしれません。
つみたてNISAと組み合わせて運用するのにおすすめの制度や金融商品を見ていきましょう。
貯蓄型の保険:万が一の保障を準備
30代・40代の人で家庭を持っている人も多いでしょう。
自分に万が一のことがあった時、自分や家族が経済的に困窮しないためにも、リスクに備えた保障を準備しておくことが大切です。
保障が大切なのは家庭を持っている人だけとは限りません。
独身の人でさえも、病気や怪我で働けなくなる、もしくは介護が必要な状態になることも考えられるでしょう。
収入が絶たれてしまい、以前の生活を送れなくなってしまい、途方に暮れてしまうかもしれません。
また、長期積立投資は自分が元気に働き続けられることを前提にした行為なので、前提条件が崩れないように備えるのが大事です。
万が一の時に困らないほど十分な資産を持っている人は良いのですが、そうでない場合は保障を確保しましょう。
特に、30代・40代はまだ資産を形成している途中の段階です。十分な備えを貯蓄で確保できない時こそ、保険で備えておきましょう。
最近では死亡や高度障害に備えながら、投資信託で運用できる貯蓄型の保険も人気があります。
掛け捨ての死亡保障はもったいないと感じる人は貯蓄型保険で備えながら運用すると良いでしょう。
銀行預金:まずは預金で十分な貯蓄を確保
十分な貯蓄がないという人は、つみたてNISAと同時に銀行預金の積立をするべきと言えるでしょう。
突然病気や怪我で働けなくなったり、万一のことが起こった場合、銀行預金があれば当面の生活費に充てることができます。
銀行預金では、金利はほとんど見込めませんが、いつでもキャッシュカードで引き出せるという安心感があります。
つみたてNISAの場合も途中で引き出すことができますが、投資信託は売却の手続きをしてから口座に資金が入金されるまで、1週間程度時間がかかります。
また、基準価額は日々変動しているため、お金が必要な時に元本割れをしていることも想定されます。
その点、預金は元本保証されているため安心でしょう。
まずは万が一の時のために、生活資金6ヶ月分を目指して銀行預金を貯めながら、将来の生活資金はつみたてNISAで積立投資をする、という役割分担でお金を管理すると良いでしょう。
アクティブ投資信託:積極的に投資
「せっかく資産運用をするなら投資商品にとことんこだわりたい」という人はアクティブ投資信託を組み合わせるのも一案です。
特に、iDeCo(イデコ)では毎月の投資金額に上限があってもの足りない、60歳まで引き出せないのを不便と感じる人におすすめです。
また、日本国内には約6000種類の投資信託が存在しますが、つみたてNISAやiDeCoは投資できる商品数に限りがあるため、少し物足りないという人も出てくるでしょう。
投資商品にこだわりたい人は、幅広い商品の中から選べる一般の投資信託がおすすめです。
一方で、課税口座での運用になるため、運用益に対して20.315%課税される点には注意しましょう。
さらに、アクティブ型の投資信託の中には運用成果が上がっていない商品や、手数料が高いだけでインデックス投資信託よりもパフォーマンスが上がっていない商品もあります。
最初は資産運用のプロのアドバイザーと一緒に銘柄を選ぶ良いでしょう。
iDeCo:老後資金をしっかり準備
30代・40代で老後の資産形成を重視したい人は、つみたてNISAとiDeCoを併用した運用も選択肢のひとつでしょう。
iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)とは、任意加入の私的年金制度のことです。
iDeCoのメリットは充実した税制優遇制度です。毎月の掛金が全額所得控除の対象になるだけでなく、運用益も非課税で再投資され、さらに60歳以降で引き出す時も「退職所得控除」や「公的年金等控除」を利用することができます。
税制優遇制度が充実しているiDeCoですが、運用するうえで注意点があります。
原則60歳まで積み立てた資金を引き出すことができないという点です。
つみたてNISAはいつでも投資元本を引き出すことができます。一部売却も全部売却も可能です。
一方、iDeCoは原則60歳まで引き出せないがゆえに、強制的に老後資金を確保できます。
マネイロでは、長期積立投資が重要と考えています。
まずは長期積立投資を行うために、若く健康な時から保障を備えましょう。
保障をきちんと整えたうえで、iDeCoの活用を検討しましょう。
まとめ
30代・40代は、給与収入も安定し、資産運用をスタートする機運が高まる年代です。
また、金融商品の選択肢も多いため、スタート地点でしっかり運用方針を固めることができれば、老後に向けてしっかりとした資産形成ができるでしょう。
30代と40代では、NISAの“適切な積立ペース”や“リスクの取り方”が大きく変わります。収入・貯蓄・老後に必要な金額が年代ごとに異なるため、人気のやり方を真似るだけでは最適な運用にはつながりません。
まずは自身の将来必要額・不足額・許容できるリスクを整理して、無理のない積立計画を立てることが重要です。
3分投資診断なら、年代ごとの特徴を踏まえつつ、あなたに最適な積立額・投資スタイルを自動算出。30代・40代で“どれくらい積み立てるべきか”を明確にできます。
»NISAの最適な積立ペースを3分で診断(無料)
NISAの運用について知りたいあなたへ
マネイロではよりうまくNISAを運用できるよう、さまざまな無料サービスを提供しています。
▶3分投資診断:あなたとNISAの相性がわかる
▶「NISAで始める資産運用の基本」:専門家が基本を30分で解説
▶「成長投資枠の失敗しない銘柄選び」:銘柄選びがわかる30分解説
▶NISAオンライン相談:専門家にスマホで直接相談
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
泉田 良輔
- 証券アナリスト/経営者/元機関投資家
愛媛県出身。慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2018年11月、株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)を共同設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。
執筆
谷口 裕梨
- ファイナンシャルアドバイザー
同志社大学卒。大学卒業後、京都中央信用金庫で投資信託や生命保険などを活用した資産運用アドバイス、相続相談、融資、為替業務などに従事。その後は福知山市役所で主に中小企業支援などに携わる。現在はこれまでの金融商品の知識を生かし、個人向け資産運用のサポート業務を行う。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などを保有。


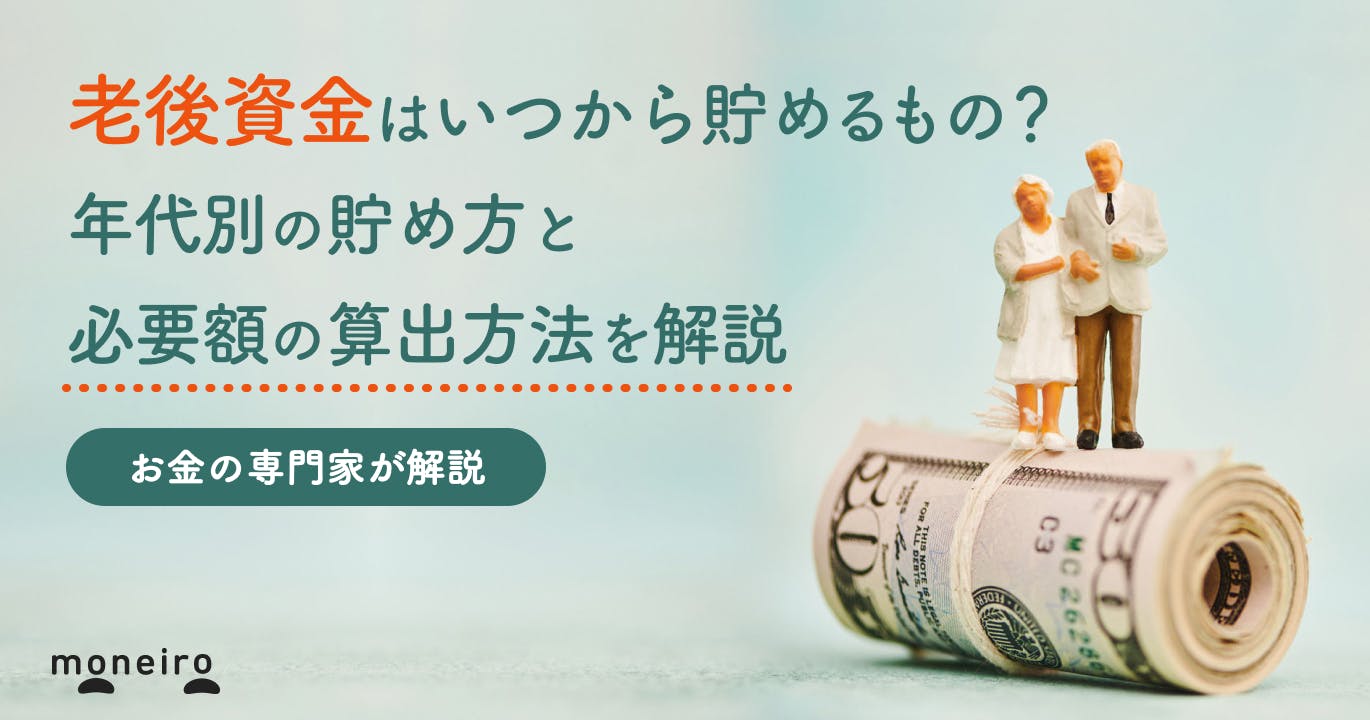
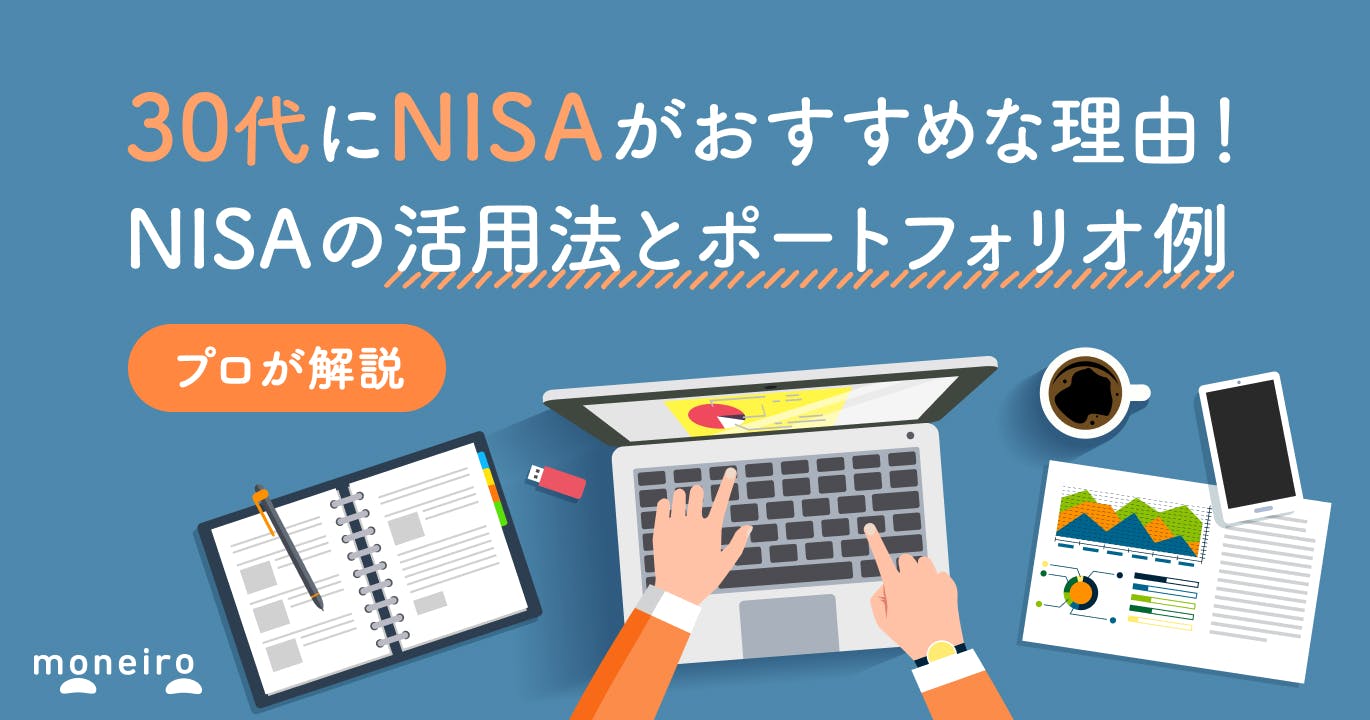
.jpg?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)