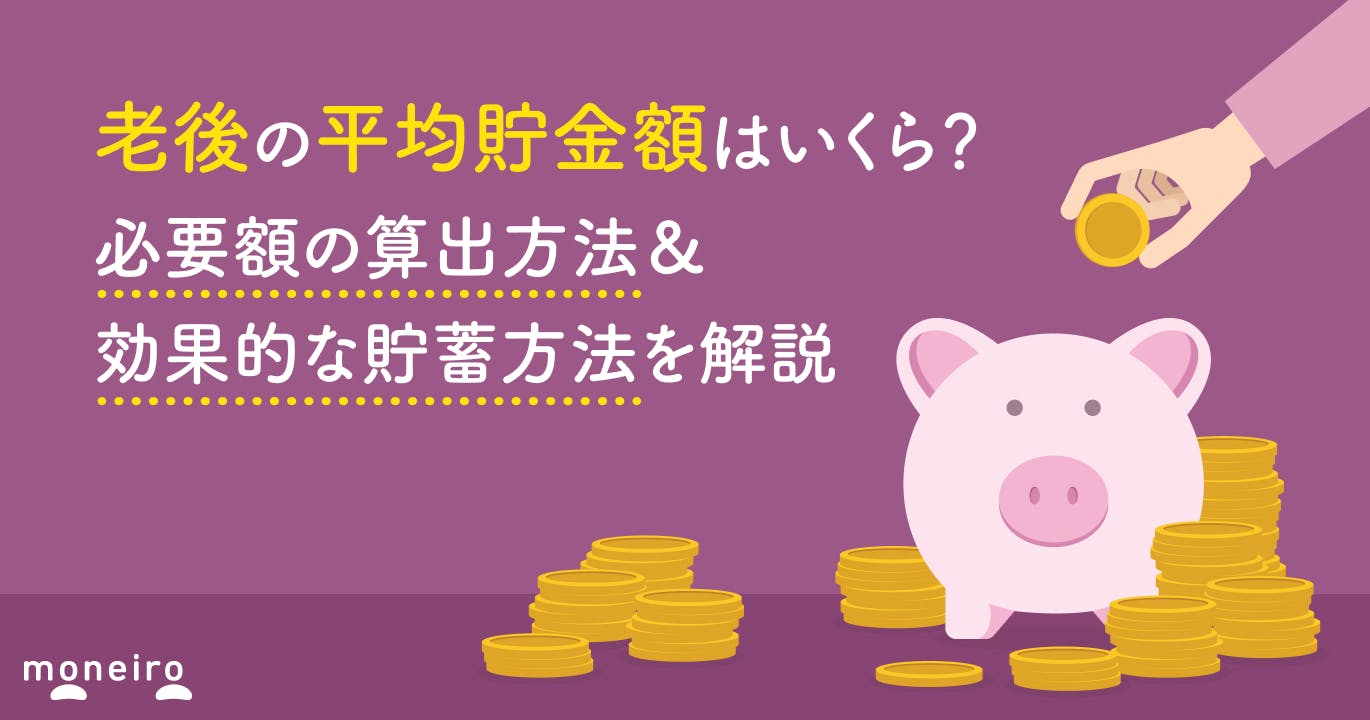老後の平均貯金額はいくら?必要額の算出方法&効果的な貯蓄方法を解説
>>あなたは足りる?老後に必要なお金を3分で診断
「老後の貯金、みんなはいくら持っているのだろう?」「自分にはどれくらい必要なんだろう?」こうした疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。漠然とした不安を抱える一方で、具体的にどれくらいの資金が必要で、どう準備すれば良いのか分からないという声も聞かれます。
この記事では、最新の調査データをもとに、60代・70代の平均貯蓄額や金融資産を保有していない世帯の割合を具体的に解説します。さらに、老後の生活に必要な費用の考え方や、賢く老後資金を準備するための具体的な方法もご紹介しますので、ぜひ老後資金準備の参考にしてみてください。
- 60代・70代の平均貯蓄額と中央値、そして貯蓄ゼロ世帯の割合
- 老後生活に必要な支出を把握し、不足額を考えるための基本的な視点
- 老後資金を準備するための具体的な3つの効果的な貯蓄方法
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
60代以上の平均貯蓄額はいくら?
60代以上の老後世代が実際にどれくらいの金融資産を保有しているのかは、多くの方にとって関心の高い情報です。ここでは、金融広報中央委員会が2024年に実施した「家計の金融行動に関する世論調査」のデータに基づいて、60代および70代の平均貯蓄額と中央値、そして貯蓄ゼロの割合を世帯別に詳しく見ていきましょう。
平均値だけでなく中央値にも注目することで、より実態に近い貯蓄状況を把握することができます。
※本記事では「貯金額=預貯金額」「金融資産保有額=貯蓄額」と表記しています
※貯蓄額は預貯金以外に保険や有価証券なども含んだ金額としています
60代の平均貯蓄額・中央値
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(2024)」によると、60代の金融資産保有額は以下の通りです。
60代2人以上世帯の貯蓄額
60代の2人以上世帯で金融資産を保有している世帯の平均貯蓄額は2581万円、中央値は1140万円です。平均値が中央値を大きく上回っていることから、一部の世帯が高額な金融資産を保有している一方で、多くの世帯は中央値に近い金額に留まっていることが考えられます。
このデータは、世帯ごとの多様な状況を反映したものであり、当然ながら個別の世帯ごとに状況は大きく異なります。そのことを理解した上で、具体的な目標設定を行う際の参考とするとよいでしょう。
60代単身世帯の貯蓄額
60代の単身世帯で金融資産を保有している世帯の平均貯蓄額は2363万円、中央値は960万円です。2人以上世帯と同様に、平均値と中央値に差があることから、単身世帯においても貯蓄額にばらつきがあることがわかります。
単身世帯の場合、すべての生活費や予備費を一人で賄う必要があるため、より計画的な資金準備が求められます。
60代の貯蓄ゼロの割合は?
金融資産を保有していない、いわゆる「貯蓄ゼロ」の世帯の割合も見ていきましょう。
60代の単身世帯では、27.7%が金融資産を保有していません。一方、60代の2人以上世帯では、金融資産を保有していない世帯の割合は20.5%です。
これは、約4~5世帯に1世帯が、現時点での金融資産を持たない状態で老後を迎えている可能性を示しています。貯蓄ゼロで老後を迎えると、その後のライフスタイルに大きな影響を及ぼすことになるため、事前の資金準備は非常に重要だといえます。
70代の平均貯蓄額
次に、70代の平均貯蓄額と中央値、貯蓄ゼロの割合を見ていきましょう。
70代2人以上世帯の貯蓄額
70代の2人以上世帯で金融資産を保有している世帯の平均貯蓄額は2450万円、中央値は1205万円です。60代と比較すると平均額はわずかに減少していますが、中央値は増加しており、より多くの世帯が一定の金融資産を保有していることがうかがえます。
このことから、年金受給が本格化し、現役時代の貯蓄を計画的に取り崩しながら生活していることが考えられます。
70代単身世帯の貯蓄額
70代の単身世帯で金融資産を保有している世帯の平均貯蓄額は2257万円、中央値は1000万円です。60代の単身世帯と比較すると、平均額は減少していますが、中央値は増加しています。これも2人以上世帯の場合と同様に、年金収入と計画的な資産の取り崩しが行われていることが考えられます。
なお単身世帯の場合、サポートしてくれる人が身近にいない分、介護や医療費など不測の事態への備えは一層重要になります。
70代の貯蓄ゼロの割合は?
70代の単身世帯では、27.0%が金融資産を保有していません。これは60代単身世帯とほぼ同じ水準です。一方、70代の2人以上世帯では、金融資産を保有していない世帯の割合は20.8%です。これも60代2人以上世帯とほぼ同じ割合であり、一定数の世帯が金融資産を持たないまま老後を過ごしている実態が浮き彫りとなっています。
老後に必要な貯金はいくら?
老後に必要な貯蓄額は、個々のライフスタイルや価値観、想定する生活水準によって大きく異なります。そのため、万人に当てはまる必要額を一概にいうことはできません。
しかし、いくつかの重要な視点から試算を行うことで、自分の老後資金が「いくらあれば足りるのか」「いくら不足するのか」を大まかに把握することは可能です。以下で老後の必要資金を試算するプロセスについて解説しますので、確認しておきましょう。
老後の支出を把握しよう
老後に必要なお金を算出するには、まず現在の生活費を詳細に把握した上で、老後も継続する支出と変化する支出を明確に区別して計算することが重要です。
老後の生活費は、現役時代とは異なる支出構造になります。現役時代は住宅ローンや教育費などが大きな割合を占めることが多いですが、老後は食費、光熱費、医療費、介護費用、趣味・レジャー費などが主な支出となるでしょう。
現在の支出から、減りそうな費目と増えそうな費目を差し引きして、大まかな老後の生活費を算出してみましょう。
老後の収入を把握しよう
老後に必要な月々の生活費が大体分かったら、次に年金収入を含めた老後の収入を算出しましょう。年金の受給見込み額については、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、確認するとよいでしょう。
なお、厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和5年度)」によると、令和5年度の国民年金(基礎年金部分)の平均年金月額は5万7700円、厚生年金保険(基礎年金を含む)の平均年金月額は14万7360円となっています。
また、退職後も働き続ける予定がある場合は、その労働収入も計算に入れるとよいでしょう。
不足額を計算しよう
最後の不足額の計算です。不足額は、支出と収入との差額から計算します。この不足額が、現役時代に貯蓄すべき目標金額となります。
計算方法は、「(月々の支出 - 月々の収入) × 老後期間(月数)」です。老後も働き続ける場合は、働く予定の期間と、完全にリタイアした後の期間を分けて計算しましょう。
例えば、月々の支出が25万円・収入が22万円で、老後を30年(360ヶ月)とした場合、(25万円 - 22万円) × 360ヶ月 = 1080万円 が不足額(=準備すべき老後資金)ということになります。
老後の必要額診断ツールも活用しよう
老後に必要な金額を知るために、無料でできるマネイロの「3分診断」も活用しましょう。現在の年収や資産額など、簡単な質問に答えていくだけで、あなたの老後に必要なお金や、そのお金を準備するための最適な資産運用の方法を導き出してくれる便利なツールです。
まずは、老後資金準備はまず「知る」ことがスタートです。安心な老後への第一歩として、トライしてみましょう。
>>あなたは足りる?老後に必要なお金を3分で診断
生活費の支出にも備えよう
日々の生活費や趣味・レジャー費用だけでなく、老後には予期せぬ大きな支出が発生する可能性があります。これらの支出に備えることも、老後資金計画の重要な一部です。
特に以下の3つの費用については、あらかじめ備えを検討しておくべきでしょう。
住宅のリフォーム費用
長年住み慣れた自宅で老後を過ごす場合、バリアフリー化や耐震補強、水回りの改修など、住宅のリフォームが必要になることがあります。これらの費用は数百万円単位になることも珍しくありません。
また、高齢になると身体が不自由になり、専門業者に依頼する機会が増えるため、計画的に費用を積み立てておくことが重要です。
自宅の築年数や状態を考慮し、将来的に必要となりそうなリフォーム内容とその概算費用を見積もっておきましょう。
病気やケガの医療費
高齢になると、病気やケガのリスクは高まります。医療費は公的医療保険でカバーされる部分も大きいですが、自己負担分や先進医療、差額ベッド代など、保険適用外の費用も発生する可能性があります。
特に、長期にわたる療養や高額な治療が必要になった場合に備え、一定の貯蓄や医療保険、がん保険などの民間保険への加入も検討しておくとよいでしょう。健康寿命を延ばす努力をしながらも、万が一の事態に備えることは、安心な老後を送る上で不可欠です。
子や孫への援助
老後になっても、子や孫の結婚費用、教育資金、住宅購入資金など、援助を求められるケースは少なくありません。もちろん、援助するかどうかは各家庭の判断によりますが、もし援助を検討するのであれば、老後資金計画に無理のない範囲で予算を組み込んでおく必要があります。
場合によっては、贈与税なども考慮した上で、計画的に準備を進めることが大切です。子や孫への援助は、家族の絆を深める喜びとなる一方で、自身の生活を圧迫しないよう慎重な判断が求められます。
援助を計画する際は、まず自分自身の老後資金が十分に確保されているかを確認し、その上で無理のない範囲で支援額を決定するようにしましょう。
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
老後の貯金を準備する3つの方法
老後資金を効率的に準備するためには、ただ漠然と貯蓄するのではなく、計画的かつ戦略的に取り組むことが重要です。
ここでは、今日から実践できる3つの効果的な貯蓄方法をご紹介します。これらの方法を組み合わせることで、より確実に老後資金を積み上げていくことができるでしょう。
方法1.家計を見直して「貯蓄できる力」をアップ
老後資金準備の第一歩は、現在の家計を把握し、無駄な支出を削減することです。収入を増やすのが難しい場合でも、支出を減らすことで貯蓄に回せる金額を増やすことができます。
まずは、家計簿アプリなどを活用して、毎月の収入と支出を把握しましょう。次に、食費、光熱費、通信費、娯楽費など、項目ごとに支出をチェックし、削減できる部分がないか洗い出します。
特に、固定費(通信費、保険料、サブスクリプションサービスなど)の見直しは、一度見直せば継続的に効果が得られるため、優先的に取り組むのがおすすめです。
方法2.給料日に自動で貯める「先取り貯蓄」を徹底
貯蓄が苦手な方におすすめなのが、「先取り貯蓄」です。これは、給料が入ったらすぐに、あらかじめ決めた金額を貯蓄用口座などに移してしまう方法です。「残ったお金を貯蓄する」のではなく、「先に貯蓄して残ったお金で生活する」という意識に変えることで、自然と貯蓄週間が身につきます。
先取り貯蓄をするには、具体的に以下のような方法があります。
定期預金
積立預金は、貯蓄が苦手な方でも簡単・確実に先取り貯蓄を始められる代表的な方法です。毎月指定した日に、給与振込口座などの普通預金から、決まった金額を自動的に積立用口座へ移してくれます。
金融機関によっては、目標金額や期間を設定できるほか、ボーナス月に積立額を増やすといった柔軟な設定も可能です。一度設定すれば手間がかからないため、着実に貯蓄を続けられるのが大きな魅力です。
財形貯蓄
財形貯蓄は、勤務先を通じて行う先取り貯蓄制度です。毎月の給与やボーナスからあらかじめ設定した金額が天引きされて積み立てられるため、意思の力に関わらず、半ば強制的に貯蓄を進められるのが最大の特長です。
「一般財形」「住宅財形」「年金財形」の3種類があり、特に住宅や年金を目的とするものは、合わせて元利合計550万円まで利子等が非課税になる税制優遇を受けられます。会社によっては、積立額に応じて奨励金が支給されることもあります。
制度を導入している会社の従業員であれば、誰でも利用できる強力な資産形成の手段です。利用を検討したい場合は、勤め先の制度について担当部署(総務部や人事部など)に確認してみるとよいでしょう。
方法3.資産運用で貯金の一部を「育てる」
ただ貯蓄するだけでなく、貯金の一部を「育てる」視点も重要です。低金利の時代において、預貯金だけではお金が増えにくいのが現実です。そこで、少額からでもリスクを抑えつつ資産運用を取り入れることで、効率的に老後資金を増やす可能性が広がります。特に、長期・積立・分散投資を意識することで、リスクを軽減しながら複利効果を最大限に活用することができるでしょう。
資産運用を行う上では、非常に有利な税制優遇を受けられる制度がありますので、チェックしておきましょう。
NISA(少額投資非課税制度)の活用
NISAは、投資で得られた利益(配当金や売却益)が非課税になる制度です。2024年からは制度が恒久化され、非課税期間も無期限となって、より柔軟な資産形成が可能になりました。
NISAには、長期積立に適した「つみたて投資枠(年間120万円まで)」と、個別株などにも投資できる「成長投資枠(年間240万円まで)」の2つの投資枠があります。特につみたて投資枠は老後資金の準備に適した投資枠で、毎月一定額を積立投資することで、時間分散によるリスク軽減効果も期待できます。
金融機関によっては月々100円から積立設定ができるため、まずは少額から始めてみるのもおすすめです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用
iDeCoは、自分で掛金を拠出し、自ら運用商品を選んで運用する私的年金制度です。大きな特徴は、掛金が全額所得控除の対象となるため、所得税・住民税が軽減される税制優遇があることです。また、運用益も非課税で再投資され、受け取る際も公的年金等控除や退職所得控除の対象となるなど、手厚い税制優遇が魅力です。
老後資金の準備に特化した制度であり、原則60歳まで引き出せないことはデメリットですが、逆に強制的に長期的な資産形成ができるという意味ではメリットともいえるでしょう。
iDeCoの活用を検討する際は、自分の職業(会社員、公務員、自営業など)に応じた掛金の上限額を確認し、無理なく継続できる掛金を設定することが重要です。
まとめ
この記事では、老後資金の準備に関して、60代・70代の平均貯蓄額から必要資金の考え方、そして具体的な貯蓄方法までを解説しました。
金融広報中央委員会の調査によると、60代の2人以上世帯の平均貯蓄額は2581万円、中央値は1140万円、単身世帯は平均2363万円、中央値960万円となっています。一方で、60代の単身世帯の27.7%、2人以上世帯の20.5%が金融資産を保有していないという現実も示されています。
老後に必要な貯蓄額は個々人のライフスタイルによって異なりますが、まずは老後の支出を具体的に把握し、年金収入との差額である「不足額」を計算することが重要です。日々の生活費に加え、住宅のリフォーム費用、病気やケガの医療費、子や孫への援助といった予期せぬ大きな支出にも備える計画が必要です。
老後資金の準備は一朝一夕にはできませんが、早めに計画を立て、具体的な行動を始めることで、将来への不安を軽減することができるでしょう。
>>あなたは足りる?老後に必要なお金を3分で診断
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事


老後に必要なお金はいくら?単身・夫婦の世帯タイプ別必要額を解説

老後破産する人の特徴とは?原因や破産しないための対策を解説
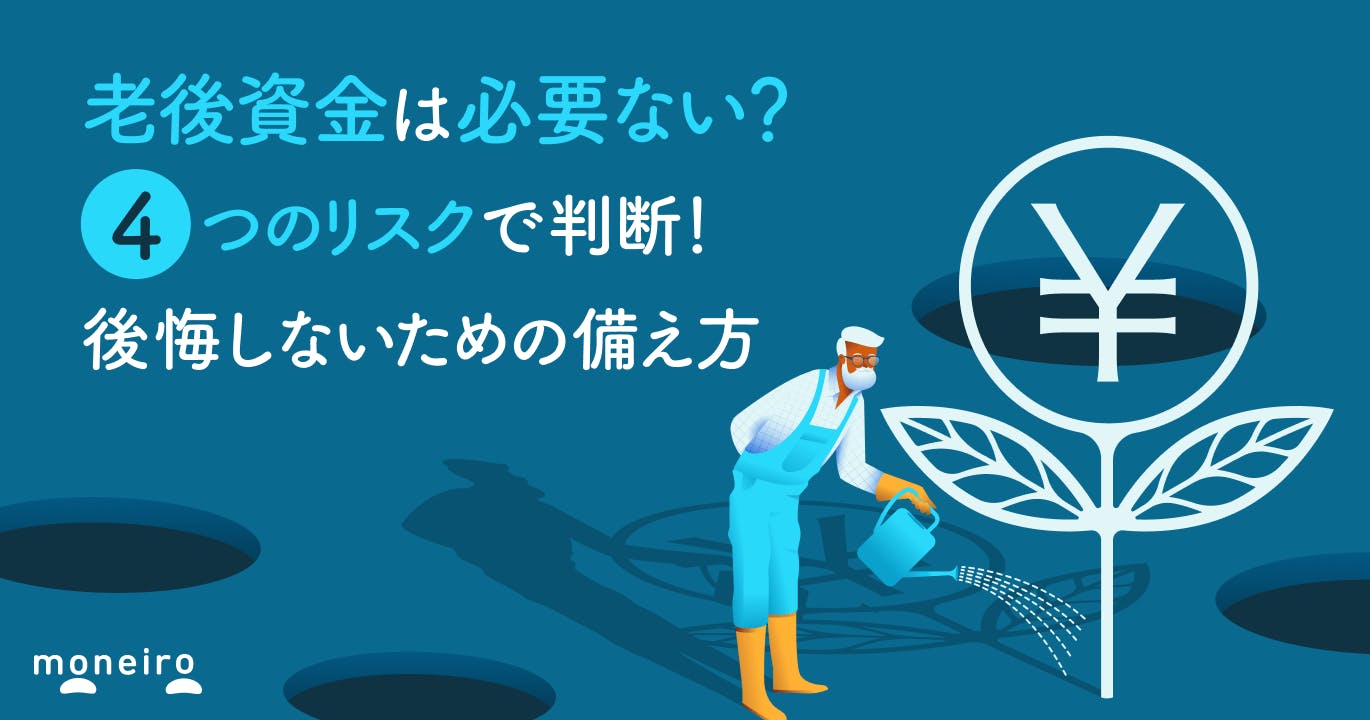
老後資金は必要ない?4つのリスクで判断!後悔しないための備え方と賢い選択肢を解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。