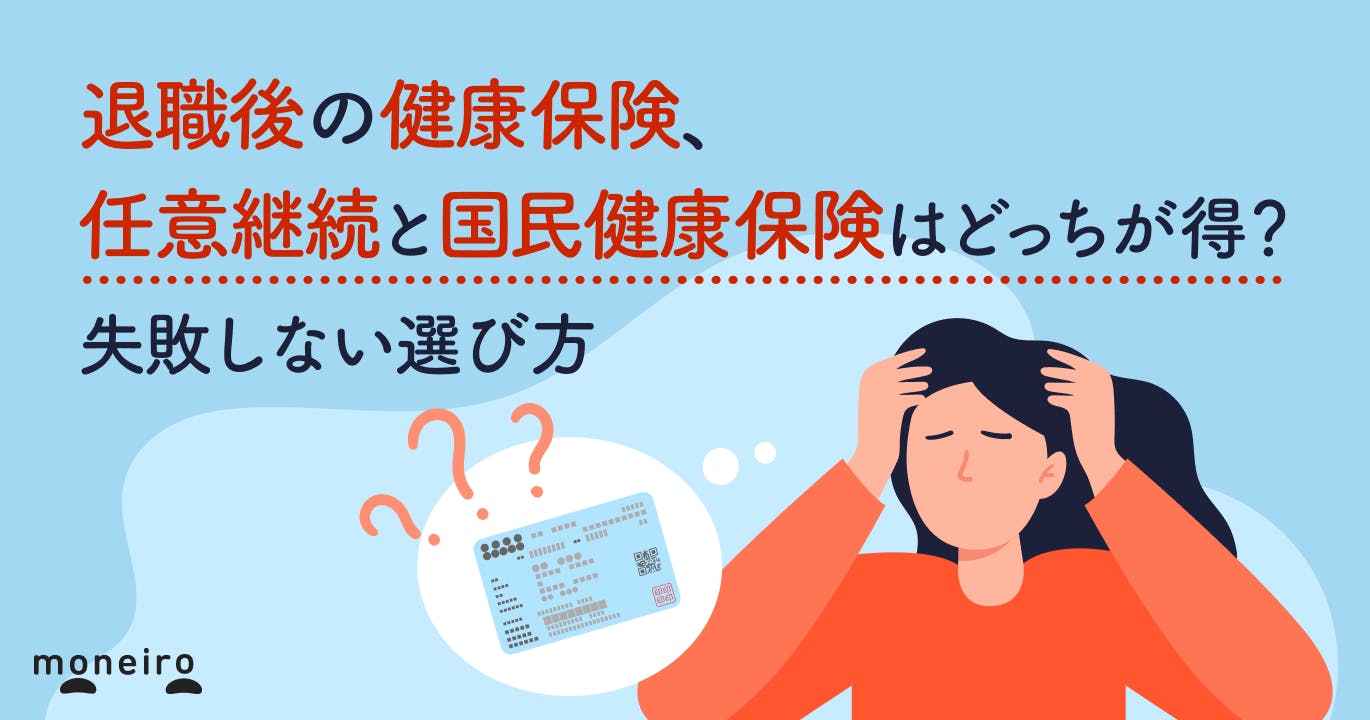退職後の健康保険、任意継続と国民健康保険はどっちが得?失敗しない選び方
【無料】あなたの老後に必要なお金はいくら?3分で診断
退職後の健康保険、任意継続と国民健康保険はどっちが得?そんな疑問をお持ちの方も多いかもしれません。退職後の健康保険選びは、今後の生活に直結する重要な決断です。任意継続、国民健康保険、そして家族の扶養という3つの主要な選択肢の中から、自分の状況にもっとも合ったものを選ぶことで、保険料で損をしない賢い選択が可能になります。
この記事では、各制度の比較ポイントを詳しく解説しますので、どの選択肢が最適かの判断にぜひお役立てください。
- 退職後の健康保険の主要な3つの選択肢と、それぞれの制度の概要
- 任意継続と国民健康保険の保険料計算や給付内容などの違い
- 家族構成や退職後の状況に応じた最適な健康保険の選び方
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
退職後の健康保険3つの選択肢|制度の全体像を理解しよう
退職後、健康保険の選択肢は主に3つあります。それぞれの制度の概要を理解することで、ご自身にとって最適な選択が見えてくるでしょう。
選択肢1.健康保険の任意継続とは?
健康保険の任意継続とは、退職後も以前加入していた会社の健康保険組合や協会けんぽの被保険者資格を、任意で継続できる制度です。
加入条件
退職日(資格喪失日の前日)までに、健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上あることが条件となります。
加入期間
最長で2年間継続して加入することが可能です。この期間が終了すると、原則として他の健康保険に切り替える必要があります。
保険料の決まり方
任意継続では、退職時の標準報酬月額が保険料の計算基準となります。在職中は会社が保険料の半分を負担していましたが、任意継続では会社負担がなくなり、保険料の全額を自己負担することになります。
ただし、標準報酬月額には上限が設けられており、退職前の給与が高い人でも、一定額を超えて保険料が高くなることはありません。
選択肢2.国民健康保険(国保)とは?
国民健康保険(国保)は、会社員として職場の健康保険に加入していない人が対象となる、市区町村が運営する医療保険制度です。
運営主体
国民健康保険は市区町村が運営しており、保険料の金額や具体的な制度内容は、自治体ごとに異なる場合があります。
加入対象者
日本国内に居住するすべての人で、職場の健康保険や後期高齢者医療制度など他の公的医療保険に加入していない人が対象となります。
保険料の決まり方
国民健康保険料は、前年の所得や世帯構成、世帯人数がベースとなり、自治体ごとに定められた計算方法や料率に基づいて算出されます。所得が多いほど、また世帯の加入者が多いほど、保険料は高くなる傾向があります。
選択肢3.家族の被扶養者になる
退職後、ご自身に収入がない、または収入が少ない場合は、配偶者や親など、家族が加入している健康保険の被扶養者になるという選択肢もあります。
条件
主な条件は、年収が130万円未満であること(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)です。加えて、扶養者の年収の2分の1未満であることや、健康保険組合によっては同居が条件となる場合があります。
メリット
もっとも大きなメリットは、ご自身の保険料負担がなくなることです。被扶養者になることで、扶養者の保険料が増えることもありません。
注意点
失業手当を受給する場合、その受給額によっては被扶養者の条件である年収130万円未満(または180万円未満)を超えてしまい、被扶養者になれないことがあります。また、健康保険組合によって扶養の認定基準が異なるため、事前に確認が必要です。
任意継続と国民健康保険を徹底比較
退職後の健康保険選びで迷わないよう、任意継続と国民健康保険の主な違いを確認しましょう。
比較① 保険料の計算方法と上限額
任意継続では、退職時の標準報酬月額が保険料の計算基準です。在職中の保険料は会社と折半でしたが、任意継続では全額自己負担となります。ただし、標準報酬月額には上限額が設定されており、一定以上の給与の人にとっては保険料が抑えられる場合があります。
国民健康保険の場合は、前年の所得や資産、そして世帯の加入者数に応じて保険料が計算されます。自治体ごとに保険料の計算方法や料率が異なり、毎年見直しが行われるのが一般的です。
比較② 扶養家族の扱い
任意継続では、会社員時代の健康保険と同様に「扶養」の概念があります。被扶養者がいる場合でも、その分の追加保険料は不要です。例えば、配偶者や子どもを扶養に入れても、健康保険料は本人分のみで済みます。
一方の国民健康保険には扶養の制度がありません。同じ世帯に加入者が複数いる場合、世帯の加入者数(均等割)に応じて保険料が増える仕組みになっています。そのため、家族が多いと国民健康保険料は高くなる傾向があります。
比較③ 給付内容(傷病手当金・出産手当金)
任意継続では、会社員時代に支給されていた傷病手当金や出産手当金は、原則として支給されません。
ただし、退職前にすでに受給要件を満たしており、かつ継続給付の要件を満たす場合は例外的に支給されることがあります。国民健康保険には、傷病手当金や出産手当金の制度は基本的にありません。
比較④ 付加給付(健保独自のサービス)
任意継続では、加入していた健康保険組合によっては、人間ドック補助、予防接種費用補助、保養施設の利用割引といった独自の「付加給付」やサービスを引き続き利用できる場合があります。これは、国民健康保険にはない任意継続のメリットであり、健康維持に役立つ可能性があります。
一方の国民健康保険には、健康保険組合のような独自の付加給付の制度はありません。基本的な医療給付のみとなります。
比較⑤ 保険料の減免・軽減制度
任意継続では、保険料の減免制度はありません。一度決定された保険料は、保険料率の変動がなければ基本的に変わることはありません。
一方の国民健康保険の場合は、会社の倒産や解雇など、自身の意思によらない非自発的な失業者の場合、国民健康保険料が大幅に軽減される制度があります。
比較⑥ 手続きの期限と方法
任意継続は、退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると、原則として任意継続はできなくなるため、早めの対応が肝心です。
国民健康保険の場合は、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる地域の市区町村役場で手続きを行う必要があります。
比較⑦ 加入期間と脱退の自由度
任意継続は最長で2年間加入することができます。再就職をして新たな健康保険に加入する場合や、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合などには任意継続被保険者の資格を喪失します。
また、途中で国民健康保険に切り替える場合は、任意脱退を希望する旨を健康保険組合、または協会けんぽに届け出ることで資格を喪失します。
一方の国民健康保険は、加入期間に制限はありません。就職などにより職場の健康保険に加入する際も、比較的自由に切り替えが可能です。
任意継続と国民健康保険はどちらが得?ケース別に解説
ご自身の状況によって、任意継続と国民健康保険のどちらがお得かは異なります。具体的なケースを見ていきましょう。
扶養家族がいる場合
扶養家族がいる場合は、任意継続が有利になるケースが多いでしょう。任意継続では、被扶養者が何人いても保険料が追加されることはありません。
一方の国民健康保険では、世帯の加入者数(均等割)に応じて保険料が増えるため、家族が多いほど国民健康保険の保険料が高くなる傾向にあります。
ただし、任意継続の保険料上限額と国保の軽減制度を考慮し、必ずご自身の状況でシミュレーションを行うことが重要です。
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
単身者の場合
単身者の場合は、退職時の給与水準によって有利な選択肢が変わる可能性があります。
給与が低かった場合
退職前の給与が比較的低かった場合、任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額がベースとなるため、保険料が低く抑えられる可能性があります。
国民健康保険も前年の所得に基づいて計算されるため、所得が少なければ保険料も低くなります。両者の保険料を具体的に比較し、より負担の少ないほうを選ぶのが賢明です。
給与が比較的高かった場合
退職前の給与が比較的高かった場合、任意継続の標準報酬月額は上限額があるため、国民健康保険と比較して低くなる可能性があります。
国民健康保険は前年の所得に基づいて計算されるため、退職により所得が大幅に減少した場合は翌年の保険料は抑えられます。
また、非自発的失業者の場合は、国民健康保険の保険料軽減制度が適用される可能性があるため、国保が有利になるケースが多いでしょう。
退職後、すぐに再就職しない(失業保険を受給する)場合
退職後すぐに再就職せず、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する場合、健康保険の選択は複雑です。失業保険の受給額が高いと、家族の被扶養者になれない可能性があります。
国民健康保険には非自発的失業者の保険料軽減制度がありますが、任意継続には減免制度がありません。
そのため、失業保険受給中は、国民健康保険の軽減制度の適用可否を確認し、ご自身にとって有利なほうを選ぶことが重要です。
健康保険の切り替え手続き方法は?
健康保険の切り替えは、期限が設けられているため、速やかに手続きを行うことが重要です。
任意継続の手続き方法
- 提出先:以前勤めていた会社の健康保険組合、または協会けんぽが提出先となります。
- 必要書類:「任意継続被保険者資格取得申出書」のほか、本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類などが必要です。
- 書類の入手方法:通常、退職時に会社から案内されるか、健康保険組合や協会けんぽのWebサイトからダウンロードできます。
- 期限:退職日の翌日から20日以内です。この期限を過ぎると、原則として任意継続は認められません。
国民健康保険の手続き方法
提出先:市区町村役場の国民健康保険担当窓口が提出先となります。
- 必要書類:「国民健康保険異動届出書」「健康保険資格喪失証明書」、本人確認書類、マイナンバーカード(または通知カードと身元確認書類)などが必要です。
- 注意点:「健康保険資格喪失証明書」は、会社を退職した際に会社に発行を依頼する必要がある重要な書類です。退職時に忘れずに発行を依頼しましょう。
- 期限:退職日の翌日から14日以内です。
手続きが遅れるとどうなる?
健康保険の切り替え手続きが遅れると、健康保険の適用が受けられない期間が生じ、その期間に医療費が発生した場合、全額自己負担となる可能性があります。
また、国民健康保険の場合は、保険料を遡って納付しなければならなくなることがあります。健康保険は空白期間なく加入することが原則ですので、期限内の手続きを強く意識しましょう。
まとめ
退職後の健康保険は、任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者の3つの選択肢があり、それぞれに特徴があります。保険料計算、扶養家族の扱い、給付内容、付加給付、減免制度、手続き期限、加入期間などを多角的に比較検討することが大切です。
特に、扶養家族の有無、退職前の給与、再就職の予定など、自身の状況に応じてシミュレーションを行うことが、退職後の選択で失敗しないためのカギとなります。
迷った際は、会社の担当者や市区町村の窓口への相談も検討し、最適な選択をしましょう。
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

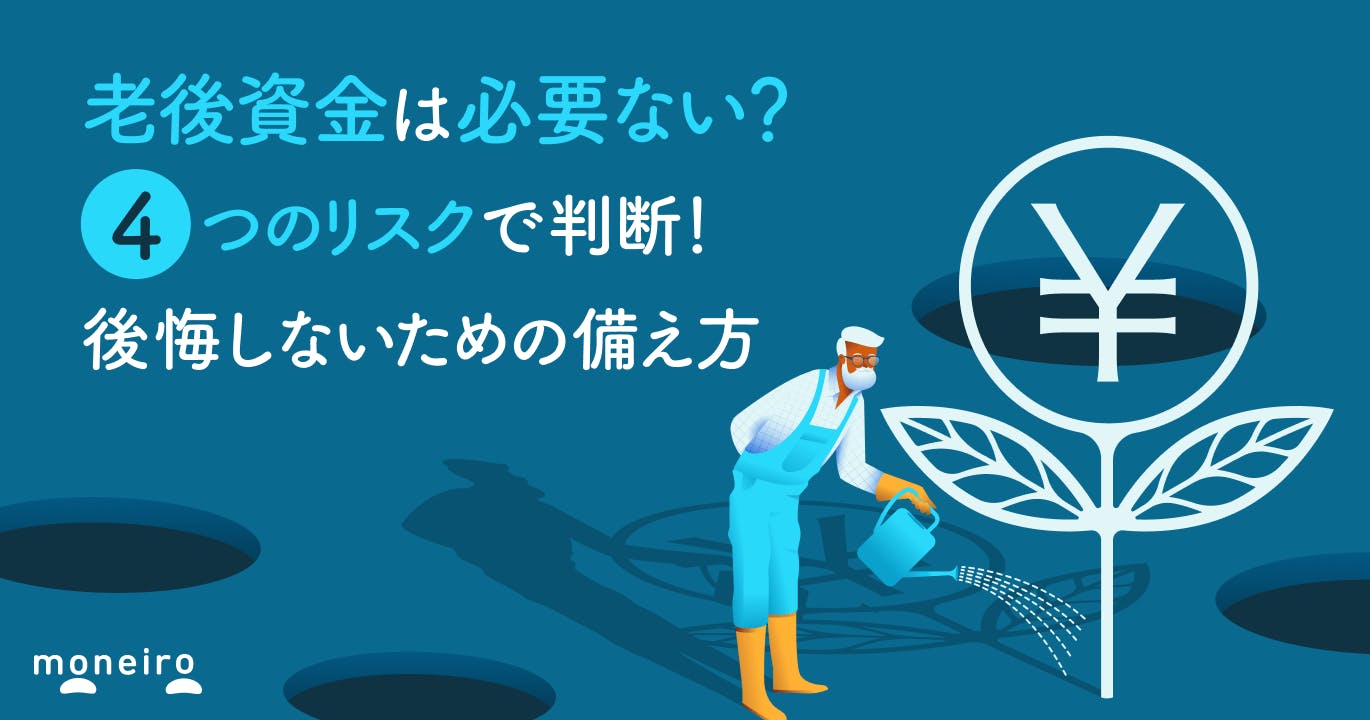
老後資金は必要ない?4つのリスクで判断!後悔しないための備え方と賢い選択肢を解説
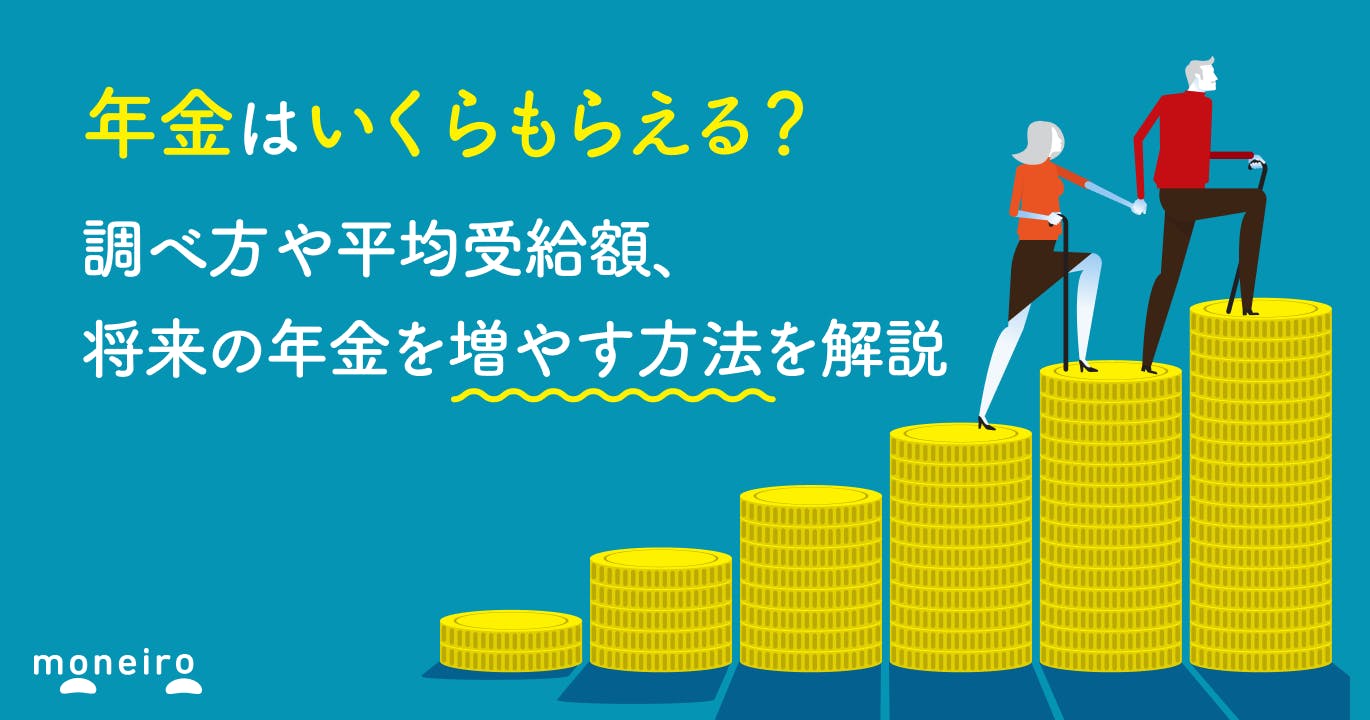
年金はいくらもらえる?調べ方や平均受給額、将来の年金を増やす方法を解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。