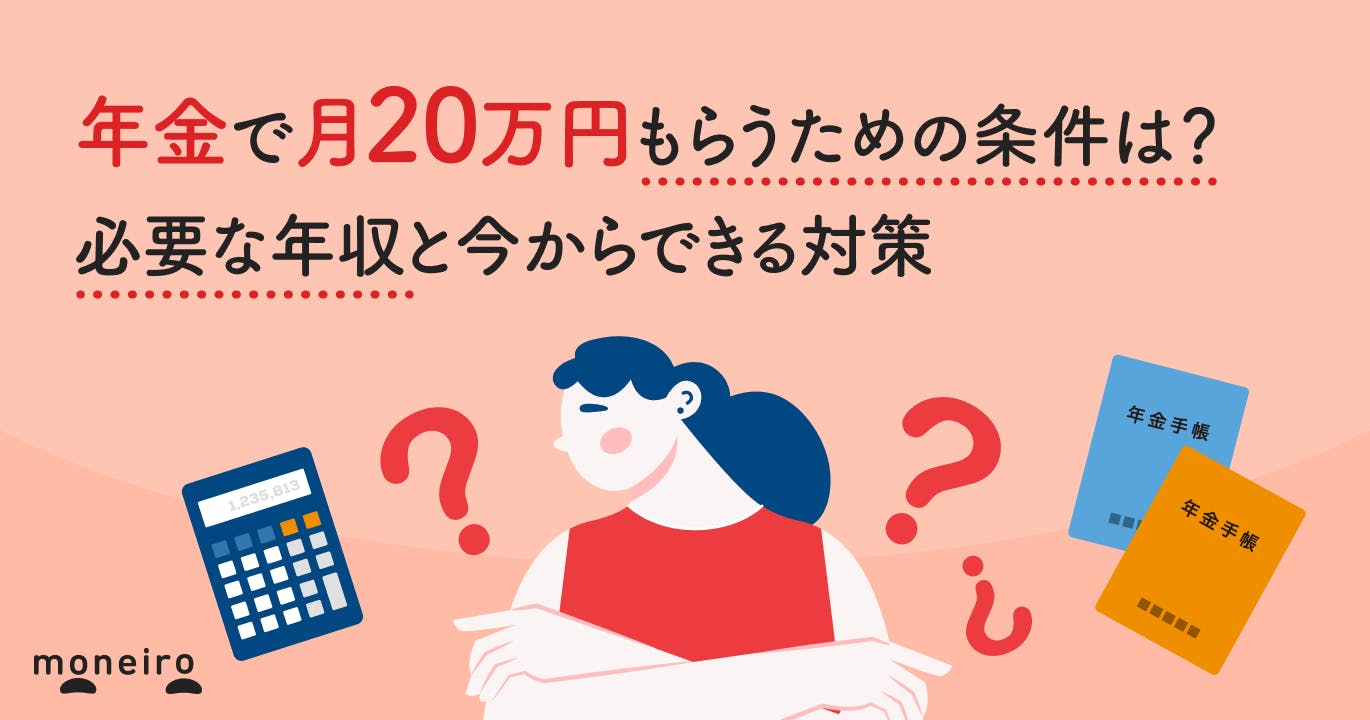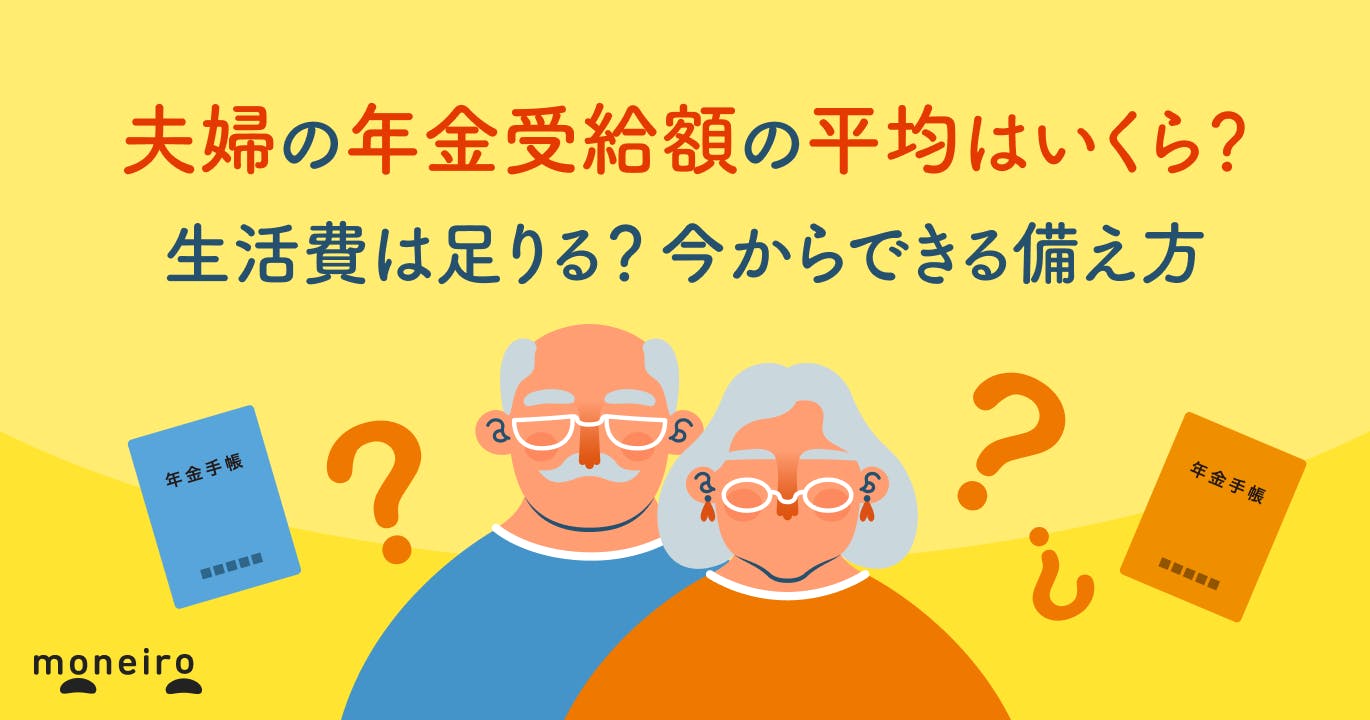
年金で月20万円もらうための条件は?必要な年収と今からできる対策を専門家が解説
»将来に不安を感じたら、3分で老後資金を診断
「老後に月20万円の年金を受け取りたい」と考える人は多いですが、実際にはどの程度の年収・加入年数が必要か気になっている人もいるでしょう。厚生年金と国民年金では仕組みが異なり、同じ年収でも将来の受給額に大きな差が出ます。
本記事では、月20万円の年金を受け取るために必要な年収と加入期間の目安をわかりやすく解説します。さらに、職業別・年代別のケース別に“今からできる増やし方”を紹介します。年金の仕組みを理解すれば、将来の不安を減らし、老後資金づくりの行動計画を立てやすくなります。
- 年金20万円の達成に必要な年収シミュレーション
- 年金の平均受給額と目標とのギャップ
- 今から年金を増やすための5つの具体的な方法
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
月年金20万円は現実的?|受給額の計算方法
将来の年金受給額は、日本の公的年金制度の仕組みによって決まります。主に国民年金と厚生年金の2階建て構造になっており、現役時代の働き方や収入、加入期間が受給額を大きく左右します。
厚生年金と国民年金の仕組みの違い
日本の公的年金制度は、全国民共通の国民年金(基礎年金)を1階部分、会社員や公務員が上乗せで加入する厚生年金を2階部分とする「2階建て」の構造が基本です。
20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金は、保険料を納めた期間に応じて受給額が決まります。
一方、厚生年金は国民年金に上乗せされる形で、現役時代の収入(給与や賞与)に応じた保険料を納めることで、将来の受給額が増える仕組みです。保険料は勤務先と折半で負担します。
平均報酬月額・加入年数が受給額を決める
厚生年金の受給額(報酬比例部分)を決定する主な要素は
- 平均標準報酬額
- 厚生年金の加入期間
「平均標準報酬額」とは、加入期間中の給与や賞与を含めた平均収入のことです。この金額に、定められた乗率と加入月数を掛けることで、年金額が算出されます。
したがって、現役時代の収入が高く、かつ厚生年金への加入期間が長いほど、将来受け取る年金額は多くなります。
なお、平成15年3月以前の加入期間については、賞与から厚生年金保険料が差し引かれていなかったため、賞与を含めない「平均標準報酬月額」を基準に年金額を算出します。
会社員・公務員・自営業の年金の違い
働き方によって加入する年金制度が異なるため、将来の受給額にも差が生じます。
会社員や公務員は、国民年金(1階)と厚生年金(2階)の両方に加入するため、老後は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取れる「2階建て」構造です。
一方、自営業者やフリーランスは国民年金のみに加入するため、受給できるのは老齢基礎年金のみの「1階建て」構造となります。
年金で月20万円もらうにはどれくらいの年収が必要?
月20万円の年金を受給するためには、現役時代に一定以上の年収を長期間にわたって得ている必要があります。
会社員・公務員の場合の必要年収
会社員や公務員が月額20万円の年金を受け取るための一つの目安は、40年間(480ヶ月)厚生年金に加入し、その間の平均年収が約715万円であることです。
このシミュレーションの内訳は、国民年金から支給される老齢基礎年金が満額の約6.9万円、厚生年金から支給される老齢厚生年金が約13.1万円となり、合計で月額約20万円に達するという計算です。
ただし、これは加入期間を通じて一定の収入が続いた場合の単純計算です。
実際には昇給や転職などで収入は変動するため、生涯にわたる平均年収で考えることが重要になります。
自営業の場合は高収入でも満額に届かない理由
自営業者やフリーランスの場合、受給できる年金は国民年金(老齢基礎年金)のみです。そのため、どれだけ高い収入を得ていても、国民年金のみで月20万円を受け取ることは制度上不可能です。
国民年金の受給額は収入額に左右されず、保険料の納付期間によってのみ決まります。40年間すべての保険料を納付した場合の満額でも、月額約6.9万円(2025年度)が上限となります。
このため、自営業者が老後に月20万円以上の生活資金を確保するには、iDeCo(個人型確定拠出年金)や国民年金基金といった私的年金制度を自ら活用し、2階・3階部分を上乗せで準備することが不可欠です。
年収別・加入年数別のシミュレーション表
厚生年金の受給額は、「現役時代の平均年収」と「加入期間」によって決まります。下の早見表では、生涯の平均年収と加入年数ごとの目安額を示しています。
記載している金額は、国民年金の満額(年額83万1700円)に厚生年金を加えた合計額です。
※老齢基礎年金(満額約83万円)を含む概算値
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
年金の平均受給額と20万円とのギャップ
月20万円という目標額は、実際の平均的な年金受給額と比較すると、決して低いハードルではありません。
特に単身世帯の場合、平均受給額と目標額の間には大きなギャップが存在するのが現実です。
夫婦世帯・単身世帯別の平均受給額
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢基礎年金(国民年金)の平均月額は約5万7700円です。
厚生年金受給者でも、国民年金を含めた平均月額は約14万7000円にとどまります。
また、令和7年4月分からの夫婦二人世帯の標準的な年金受給額(1人分の老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金を含む年金額)は23万2784円となっています。
夫婦二人であれば、合計で月20万円前後の年金を受け取れるケースもありますが、単身の場合は生活費をまかなうには厳しい水準といえます。
20万円あっても足りない?老後生活費との比較
月20万円の年金を受け取れたとしても、それが老後の生活に十分な金額であるとは限りません。
総務省の家計調査報告(2024年)によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における1ヶ月の平均的な消費支出は約25.6万円です。
このデータと比較すると、月20万円の収入では毎月約5.6万円の赤字が発生することになります。
持ち家の有無や健康状態、ライフスタイルによって必要な生活費は変動するため、自身の状況に合わせた資金計画が重要です。
年金を増やすために今からできる5つの方法
将来の年金受給額に不安を感じる場合でも、今から対策を講じることで金額を増やすことが可能です。
公的年金の受給額を増やす方法から、私的年金を活用する方法まで、代表的な5つの選択肢をご紹介します。
① 長く働く(加入期間を延ばす)
年金額を増やす最も直接的な方法の一つが、長く働き続けることです。
会社員の場合、厚生年金には最長で70歳まで加入できます。60歳以降も厚生年金に加入して働き続けることで、その分だけ加入期間が延び、将来受け取る老齢厚生年金の額を増やすことができます。
また、国民年金の保険料納付期間が40年(480ヶ月)に満たない場合は、60歳から65歳までの間に任意加入することで、納付期間を延長し、老齢基礎年金を増額させることが可能です。
② 繰下げ受給で受取額を増やす
年金の受給開始時期を遅らせる「繰下げ受給」も、受給額を増やす有効な手段です。
年金は原則として65歳から受給が開始されますが、この開始時期を66歳から75歳までの間で繰り下げることができます。受給開始を1ヶ月遅らせるごとに受給額が0.7%増額され、最大で84%(75歳受給開始の場合)も年金額を増やすことが可能です。
ただし、繰下げ期間中は年金を受け取れないため、その間の生活資金を確保しておく必要があります。
また、増額された年金額は生涯にわたって続くため、長生きするほど有利になりますが、早くに亡くなった場合は総受給額が少なくなる可能性も考慮する必要があります。
③ iDeCo・企業型DCで老後資金を上乗せ
公的年金を補う手段として、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(企業型確定拠出年金)の活用が注目されています。これらは自分で掛金を拠出し、投資信託などで運用して老後資金を積み立てる制度です。
最大のメリットは、掛金が全額所得控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減できる点です。さらに、運用益も非課税で再投資されます。
原則60歳まで引き出せませんが、税制優遇を活かして効率的に老後資金を形成できる、有利な制度といえます。
④ 国民年金基金・付加年金を活用(自営業者向け)
自営業者やフリーランスには、国民年金に上乗せできる独自の制度が用意されています。
国民年金基金は、自営業者などが任意で加入できる公的な年金制度で、国民年金に上乗せして終身年金などを受け取ることができます。掛金は全額が社会保険料控除の対象となり、節税効果も期待できます。
また、付加年金は、毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せして納めることで、将来の年金額を増やせる制度です。「200円 × 付加保険料納付月数」で計算された金額が、老齢基礎年金に加算されます。
2年以上受給すれば元が取れるため、非常に有利な制度と言えます。
ただし、国民年金基金との併用はできません。
⑤ 追納・任意加入制度で未納期間を埋める
過去に国民年金保険料の免除や猶予を受けていた期間がある場合、その分だけ将来の老齢基礎年金が減額されてしまいます。
この減額分を取り戻すために、10年以内であれば保険料を後から納める「追納」が可能です。追納することで、その期間は保険料を納付したものとして扱われ、年金額を満額に近づけることができます。
また、保険料の納付期間が40年に満たないまま60歳を迎えた場合には、60歳から65歳までの間に「任意加入」することで、不足している期間の保険料を納付し、受給額を増やすことができます。
これらの制度を活用し、未納期間をなくすことが年金増額の基本となります。
年代別に見る「今からできる対策」
老後資金の準備は、年代によって取り組むべき対策の優先順位が異なります。自身のライフステージに合わせて、最適な方法を選択することが大切です。
若いうちから始めるほど、時間を味方につけた有利な資産形成が可能になります。
20〜30代|長期運用と積立投資を始めよう
20代や30代の方は、老後まで時間的な余裕があることが最大の強みです。この時期からiDeCoや新NISAのつみたて投資枠などを活用し、少額からでも積立投資を始めましょう。
長期間にわたる運用では、利息が利息を生む「複利効果」を最大限に活かすことができます。複利効果とは、元本に運用益が組み入れられ、その合計額に対してさらに利益が付く仕組みのことです。早く始めるほど、この効果は雪だるま式に大きくなります。
まずは月々数千円からでも、コツコツと資産形成をスタートさせることが、将来の大きな安心につながります。
40〜50代|節税しながら老後資金を積み増し
40代や50代は、収入が安定し、子育てが一段落するなど、家計に余裕が生まれやすい時期です。この年代では、iDeCoの掛金を増額するなどして、老後資金の積立ペースを加速させることが重要になります。
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象となるため、積立額を増やすことは、将来の資産形成だけでなく、現在の所得税や住民税の負担を軽減するという直接的なメリットにもつながります。
また、退職金制度の有無や金額を確認し、不足分を補うための具体的な目標額を設定して、計画的に資産を積み増していきましょう。
60代前後|繰下げ・任意加入で受給額を底上げ
60代前後は、年金の受給開始が目前に迫る時期です。この年代では、公的年金の受給額そのものを増やすための最終調整が重要になります。
健康状態や就労状況に問題がなければ、年金の繰下げ受給を検討しましょう。受給開始を1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ受給額が増え、最大で84%も増額できます。
また、国民年金の納付期間が40年に満たない場合は、任意加入制度を利用して満額に近づけることも有効です。
これらの制度を活用することで、生涯にわたって受け取る年金額を確実に底上げすることができます。
自分の将来の年金額を確認する方法
将来の年金計画を立てる第一歩は、自分の年金見込額を正確に把握することです。日本年金機構の「ねんきんネット」では、これまでの加入記録や将来の受給見込額を24時間いつでも確認できます。
また、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」でも、加入実績や納付状況をチェック可能です。特に50歳以上の人には、60歳まで現在の年金制度に同じ条件で加入し続けた場合の見込額も記載されています。
定期的に確認し、老後資金計画を見直す習慣を持ちましょう。
まとめ
会社員の場合、平均年収約715万円で40年間加入することが月20万円の一つの目安ですが、これはあくまで一例です。多くの場合、目標額と平均受給額にはギャップがあり、自助努力が不可欠となります。
年金を増やすためには、以下の方法が有効です。
- 長く働く
- 繰下げ受給を利用する
- iDeCoや企業型DCを活用する
まずは「ねんきんネット」でご自身の年金見込額を確認し、早期に具体的な対策を始めることが、将来の安心につながります。
年金だけに頼らず、今からできる備えを。
»3分で“必要な老後資金”と“最適な投資プラン”を診断
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
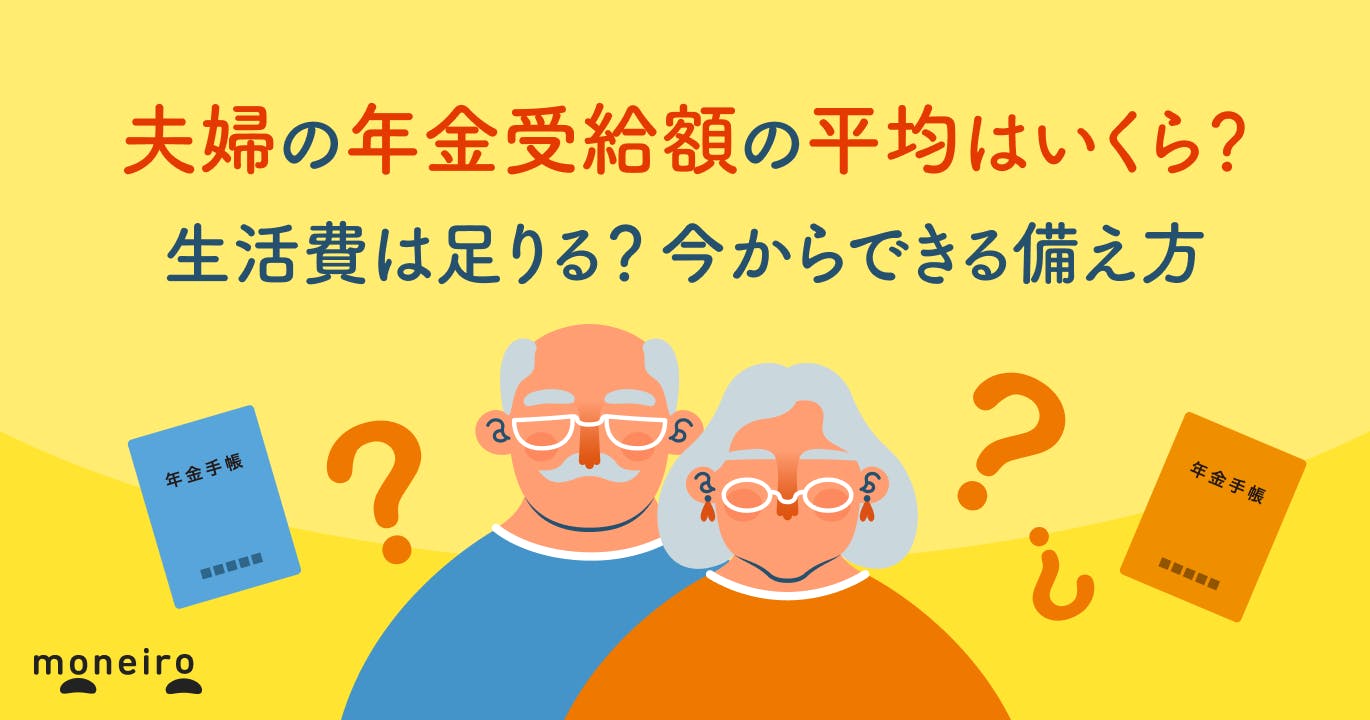
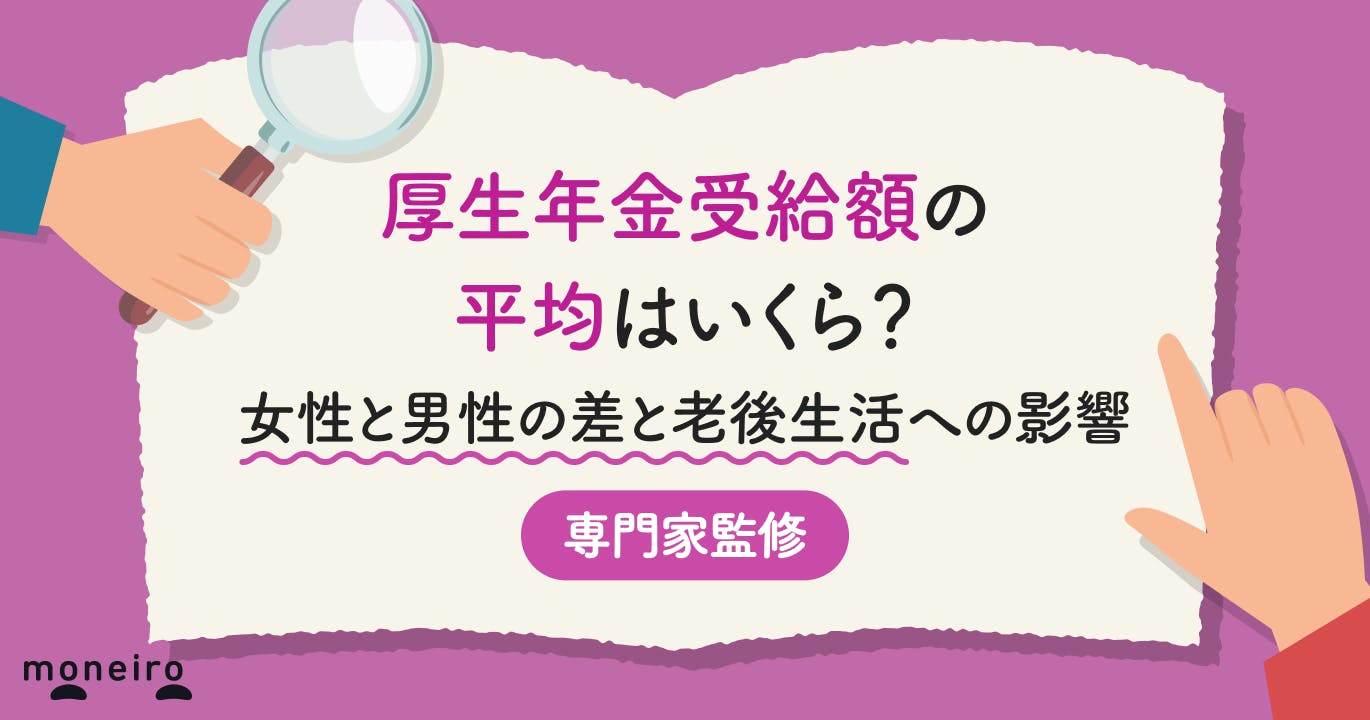
厚生年金受給額の平均はいくら?女性と男性の差と老後生活への影響を徹底解説
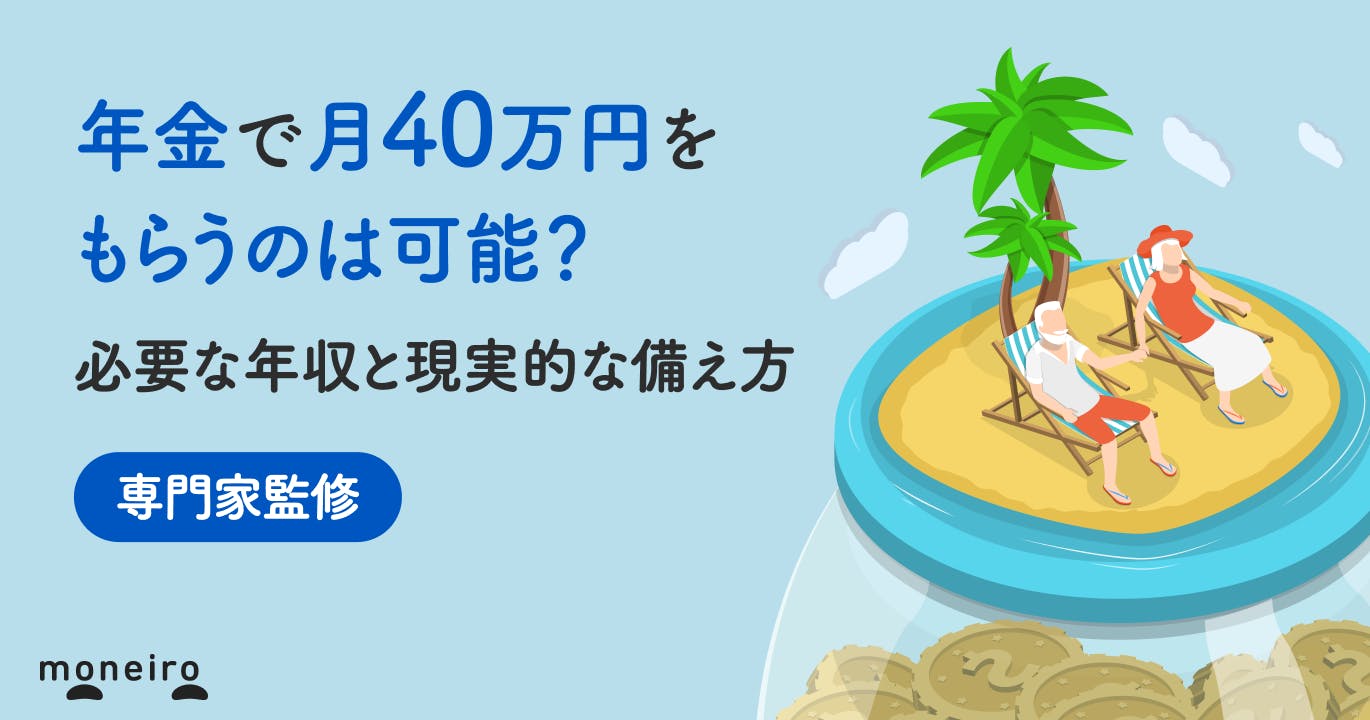
年金で月40万円をもらうのは可能?必要な年収と現実的な備え方を専門家が徹底解説
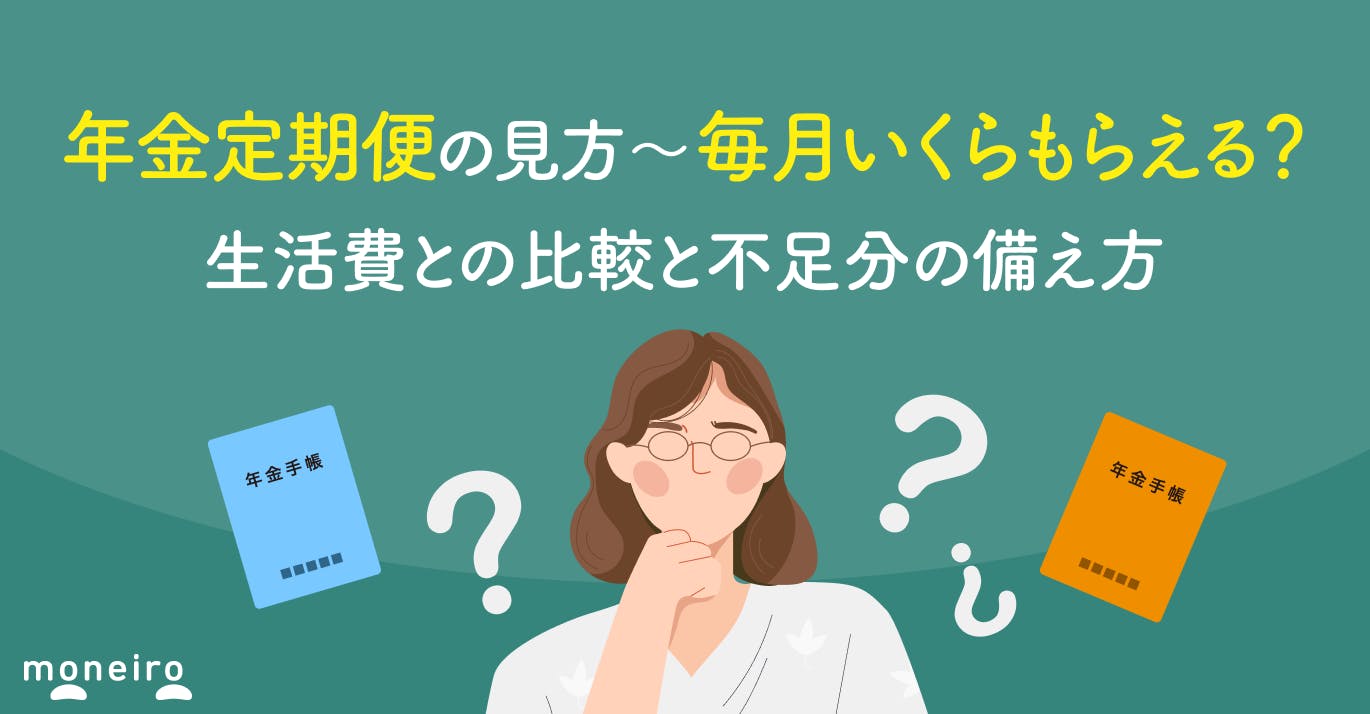
年金定期便の見方~毎月いくらもらえる?生活費との比較と不足分の備え方を徹底解説
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。