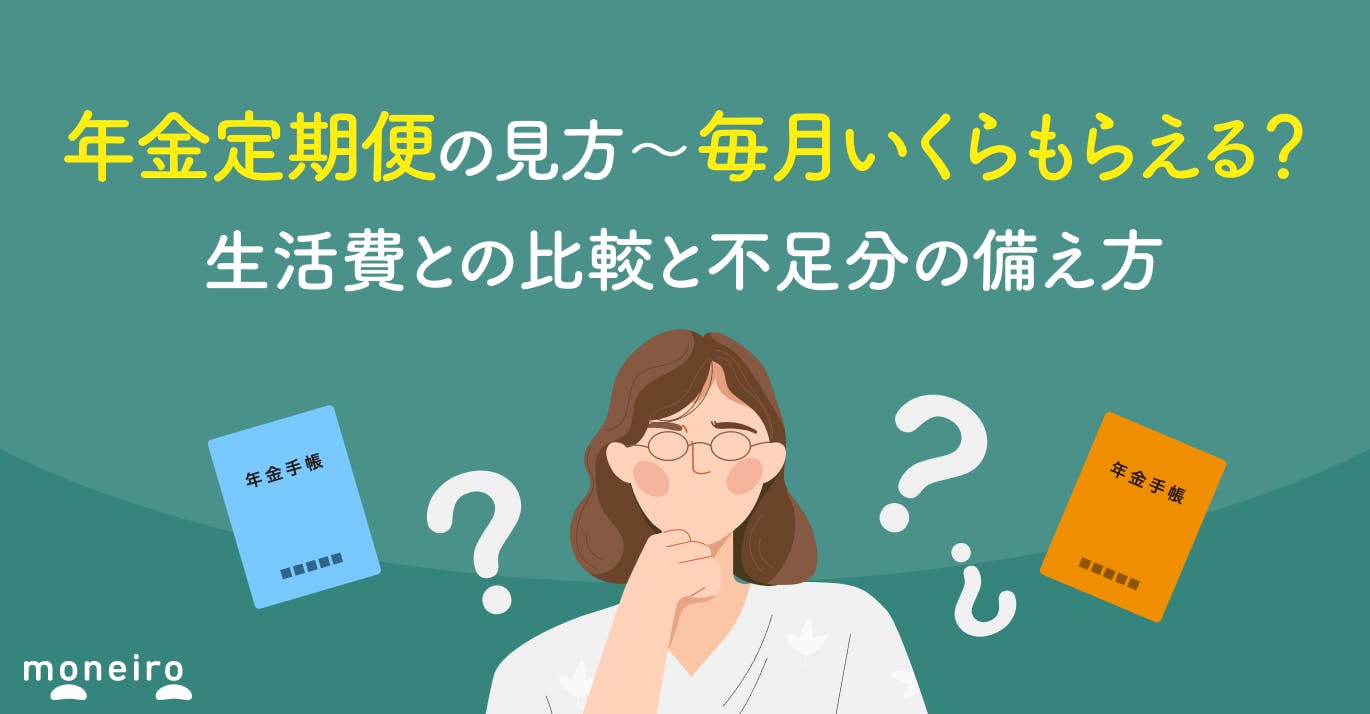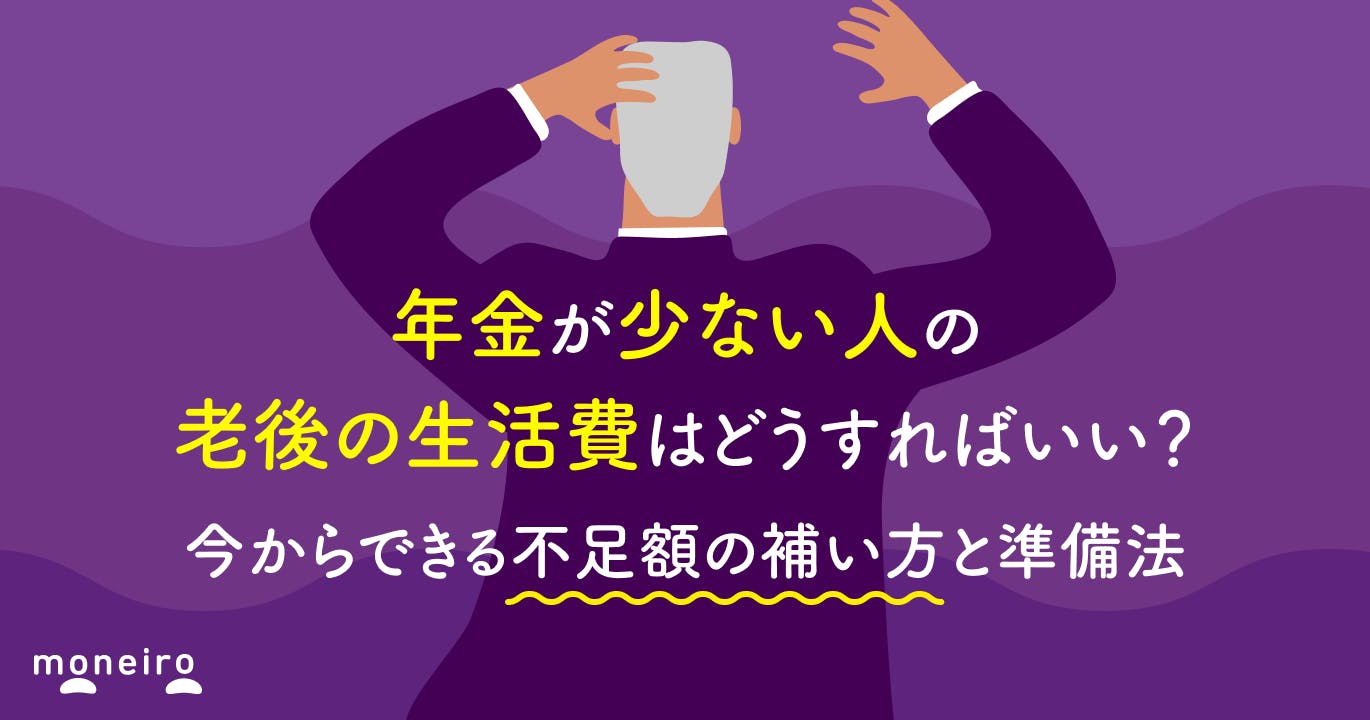
年金定期便の見方~毎月いくらもらえる?生活費との比較と不足分の備え方を徹底解説
≫年金だけで老後は暮らせない?必要資金を無料診断
毎年届く「ねんきん定期便」ですが、書かれている数字を見ても「結局毎月いくらもらえるの?」と疑問を抱く人は多いでしょう。
年金定期便には、これまでの加入実績に基づく年金額が記載されますが、年額表記のため月額に換算する必要があります。また、50歳未満と50歳以上では記載内容が異なる点にも注意が必要です。
本記事では、年金定期便の基本的な見方をわかりやすく解説し、実際に「毎月いくらもらえるのか」を読み解く方法をご紹介します。
さらに平均的な生活費との比較で不足額を明らかにし、NISAやiDeCoなどで備える方法、パートや非正規の方が注意すべきポイントまで、専門家視点で詳しく解説します。
- 年齢によって異なる記載内容の読み解き方
- 年額表示から毎月の受給額を計算する方法
- 将来の年金額を増やすための具体的な対策
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
年金定期便とは?基本の仕組みと注意点
ねんきん定期便は年金加入記録や将来受け取れる年金の見込額を確認できる、日本年金機構から毎年誕生月に送られてくる大切な書類です。
老後の生活設計の基礎となる情報が書かれているため、必ず内容を確認しましょう。
50歳未満と50歳以上で記載内容が異なる
ねんきん定期便に書かれている年金額は、年齢によってその意味が大きく違います。
50歳未満の人に届く通知書に書かれているのは、あくまで作成時点までの加入実績に基づいて計算された年金額です。これは将来受け取る確定額ではなく、今後の働き方や収入によって変わるため、現時点での参考値として考えることが大切です。
一方、50歳以上の人のねんきん定期便には、より具体的な将来の年金見込額が書かれています。
現在の加入条件、働き方や収入が60歳まで続くと仮定して計算された金額であり、老後の生活設計を立てる上での重要な目安となります。
年金額は「年額」で表示されている
ねんきん定期便に書かれている金額は、1年間に受け取れる合計額、つまり「年額」で表示されています。老後の家計をシミュレーションする際には、この年額を12で割って月額に換算する必要があります。
例えば、「これまでの加入実績に応じた年金額」や「老齢年金の種類と見込額」に180万円と書かれていれば、1ヶ月あたりの目安は約15万円となります。
この点を間違えると、将来の収入計画に大きなずれが生じる可能性があるため注意が必要です。
老齢基礎年金と厚生年金の内訳
日本の公的年金制度は、働き方によって加入する制度が違い、2階建て構造になっています。
1階部分にあたるのが「国民年金」です。これは、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、保険料を40年間すべて納付すると65歳から老齢基礎年金を満額受け取れます。
2階部分にあたるのが会社員や公務員が加入する「厚生年金」で、65歳になると老齢厚生年金を受け取れます。こちらは収入や加入期間に応じて受給額が変わる仕組みです。
ねんきん定期便では、2つの年金の内訳と合計額が書かれており、自身の年金構造を理解することができます。
年金定期便から「毎月いくら」もらえるか読み解く
ねんきん定期便に書かれている年金額は年間の合計額です。これを月額に換算し、内訳を正しく理解することで、毎月の収入イメージを具体的に掴むことができます。
特に50歳未満の人の場合は、書かれている金額の意味を正しく理解することが大切です。
年額を12で割って月額を算出
将来の生活をイメージするためには、毎月の収入額を把握することが欠かせません。ねんきん定期便に書かれている年金額は年間の総額であるため、その金額を12で割ることで、1ヶ月あたりの受給額の目安を計算できます。
例えば、年金見込額が240万円と書かれていれば、月額に換算すると20万円となります。
この月額を基に、老後の家計の収支計画を立てることが、具体的な生活設計の第一歩となります。
基礎年金と厚生年金を合算して考える
ねんきん定期便では、1階部分の「老齢基礎年金」と2階部分の「老齢厚生年金」の金額がそれぞれ内訳として書かれています。
会社員や公務員だった場合は、この2つの合計額が老後の収入の柱となります。一方、自営業者やフリーランスの場合は、原則として老齢基礎年金のみとなります。
それぞれの内訳を確認し、働き方に合った年金構造を理解することが大切です。
50歳未満は「これまでの実績分」しか反映されない
50歳未満の場合、ねんきん定期便に書かれている年金額は、あくまで過去に納付した保険料の実績を基に計算された金額です。将来受け取る年金額そのものではありません。
若い世代ほど納付期間が短いため、この金額は少なく表示されますが、心配する必要はありません。今後60歳まで保険料を納め続けることで、この金額は着実に増えていきます。
将来の見込額を知りたい場合は、ねんきん定期便のQRコードからアクセスできる「公的年金シミュレーター」などを活用するのが効果的です。
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
年金額と生活費を比較してみよう
ねんきん定期便で将来の年金見込額を把握したら、次はその金額でどのような生活が送れるのかを具体的にイメージすることが大切です。公的な調査データを参考に、自身の年金額と老後の生活費を比較してみましょう。
(参考:家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要)
≫年金だけで老後は暮らせる?あなたの必要資金をシミュレーション
単身世帯の平均生活費との比較
総務省の家計調査報告によると、65歳以上の単身無職世帯における1ヶ月の消費支出(生活費)の平均は約15万円です。
自身の年金見込額を月額に換算し、この平均的な生活費と比較してみましょう。もし年金額がこの水準を上回っていれば、平均的な生活を送る上では余裕があると考えられます。
一方、下回る場合は、現役時代から計画的に貯蓄をしたり、生活費を見直したりといった対策が必要になります。
夫婦世帯の平均生活費との比較
夫婦2人暮らしの場合、生活費はさらに増加します。同じく総務省の家計調査報告によれば、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における1ヶ月の消費支出(生活費)の平均は約26万円です。
夫婦それぞれの年金見込額を合算した月額が、この平均生活費を上回るかどうかが一つの目安となります。
モデルケースでは、公的年金などの収入から税金や社会保険料を差し引いた可処分所得が約22万円となっており、毎月赤字となる可能性も考慮しておく必要があります。
ゆとりある生活費と最低限の生活費の差
老後の生活に求める水準は人それぞれです。生命保険文化センターの調査によると、老後の最低日常生活費として考えられている金額は月額平均で約23万円です。
一方で、旅行や趣味などを楽しむ「ゆとりある老後生活」を送るためには、月額平均で約38万円が必要とされています。
差額である約15万円を、公的年金以外でどのように準備するかが、豊かな老後を送るための鍵となります。
自身の年金見込額と、理想のライフスタイルに必要な生活費を比較し、具体的な目標額を設定することが大切です。
不足分を補うための対策
公的年金だけでは老後の生活費が不足すると分かった場合でも、早期に対策を始めることで備えることが可能です。
収入を増やす、支出を減らす、資産を増やすという3つの観点から、具体的な方法を検討しましょう。
支出を抑える
老後資金の不足分を補う最も基本的な対策は、支出を見直すことです。特に、毎月決まって支払いが発生する「固定費」の削減は効果が大きいとされています。
具体的には、以下のような項目を見直してみましょう。
- 保険料:保障内容が過剰になっていないか確認し、必要な保障に絞る
- 通信費:スマートフォンの契約プランを、より安価なものに変更する
- サブスクリプションサービス:利用頻度の低いサービスを解約する
これらの見直しは一度実行すれば、節約効果が継続的に続くため、早期に取り組むことがおすすめです。
資産運用で準備
公的年金を補うための資金準備として、資産運用は有効な手段の一つです。特に、税制優遇制度がある「NISA」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の活用がおすすめです。
NISAは、一定額までの投資で得た利益が非課税になる制度です。一方、iDeCoは投資で得た利益が非課税になるだけでなく、掛金が全額所得控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減しながら老後資金を準備できるなど税制メリットが大きい制度です。
ただし、iDeCoは原則として60歳まで資金を引き出せない点に注意が必要です。
国の制度を活用し、長期的な視点でコツコツと資産を育てていくことが、ゆとりある老後につながります。
退職延長やパート勤務で収入を確保
老後の収入を増やす直接的な方法は、できるだけ長く働くことです。定年後も再雇用やパートタイム勤務などで働き続けることで、収入を確保し、貯蓄の取り崩しを遅らせることができます。
さらに、会社員や公務員として働き続ける場合、厚生年金保険に原則70歳まで加入できます。加入期間が延びることで、将来受け取る老齢厚生年金の額を増やすことにもつながります。
健康状態や働きがいを考慮しながら、ライフプランに合った働き方を検討してみましょう。
注意したい年金定期便の読み方【ケース別】
公的年金の仕組みは、働き方によって加入する制度が違います。そのため、ねんきん定期便を確認する際も、自分の状況に合わせたポイントをおさえることが大切です。
ケース別に注意点や確認すべきポイントを解説します。
パート・非正規の人が確認すべきポイント
パートタイムや非正規雇用で働く方は、厚生年金に加入しているかどうかが大きなポイントになります。勤務先の規模や労働時間などの条件を満たせば、パートタイマーでも厚生年金に加入できます。
ねんきん定期便の「最近の月別状況」で、厚生年金保険の欄に加入記録があるかを確認しましょう。加入している場合は、「標準報酬月額」が自身の給与実態と大きく違っていないかもチェックすべき点です。
標準報酬月額は将来の年金額に直結するため、間違いがあれば年金事務所に確認することが重要です。
専業主婦(第3号被保険者)の年金見込み額
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者は、「第3号被保険者」として国民年金に加入します。
第3号被保険者の期間は、自身で保険料を納付する必要はありませんが、保険料を納付したものとして扱われ、将来の老齢基礎年金の額に反映されます。
ねんきん定期便の「最近の月別状況」の国民年金の欄には「3号」と表示されます。この期間が正しく記録されているかを確認しましょう。
配偶者の退職や自身の収入増加により扶養から外れた場合、自身の勤務先の社会保険に入る場合を除き、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
手続きを忘れていると、その期間が未納扱いになってしまうため注意が必要です。
自営業(国民年金のみ)の場合の注意点
自営業者やフリーランスの場合は、国民年金の「第1号被保険者」に該当します。会社員とは違い、年金の2階部分である厚生年金がないため、将来の年金額は老齢基礎年金のみとなります。そのため、会社員と比較して年金受給額が少なくなる傾向にあります。
また、ねんきん定期便では、保険料の「未納」期間がないかを特に注意して確認する必要があります。収入が不安定な時期などに保険料の納付が困難な場合は、未納のまま放置せず、必ず「保険料免除・納付猶予制度」を申請しましょう。
これらの制度を利用すれば、受給資格期間に算入されるため、将来年金を受け取れなくなるリスクを避けることができます。
将来受け取る年金額を増やす方法
公的年金は、老後の生活を支える重要な収入源です。現行の制度をうまく活用することで、将来受け取る年金額を増やすことが可能です。
ここでは、具体的な3つの方法をご紹介します。
受給開始を繰り下げる
年金の受給額を増やす最も代表的な方法が「繰下げ受給」です。これは、原則65歳から受け取れる年金を、66歳以降に遅らせて受け取る制度です。
受給開始を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額され、最大で75歳まで繰り下げると84%も増額されます。
65歳以降も働く予定がある人や、十分な貯蓄がある人にとっては、有効な選択肢となるでしょう。
国民年金の付加年金を利用する
自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者の場合は、「付加年金」を利用することで、将来の年金額を上乗せできます。
毎月の国民年金保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めることで、将来、「200円 × 付加保険料を納付した月数」で計算される金額が老齢基礎年金に加算される制度です。
例えば、10年間(120ヶ月)付加保険料を納めると、年間2万4000円(200円×120ヶ月)が終身で上乗せされます。
住んでいる市区町村役場で簡単に申し込むことができます。
企業年金・iDeCoを組み合わせる
公的年金に上乗せする形で老後資金を準備する私的年金制度の活用もおすすめです。
勤めている会社に企業年金制度(企業型確定拠出年金など)があれば、積極的に活用しましょう。また、個人で加入できる私的年金制度として「iDeCo(個人型確定拠出年金)」があります。
iDeCoは、自分で掛金を拠出し、運用商品を選んで資産を形成する制度です。掛金が全額所得控除の対象になるなど、税制上のメリットが大きいのが特徴です。
これらの制度を公的年金と組み合わせることで、より手厚い老後資金を準備することが可能になります。
まとめ
ねんきん定期便は自身の年金記録を確認し、老後のライフプランを考えるための重要な手がかりです。
特に、50歳未満と50歳以上で記載内容の意味が違う点や、記載されている金額が年額である点を正しく理解することが大切です。
まずはご自身のねんきん定期便を手元に用意し、本記事で解説したポイントに沿って内容を確認してみてください。
そして、将来の年金見込額と理想の生活に必要な費用を比較し、不足分があればiDeCoやNISAなどの資産運用も活用しながら、計画的に準備を進めていきましょう。
≫年金だけで老後資金は足りる?3分でわかる無料診断
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
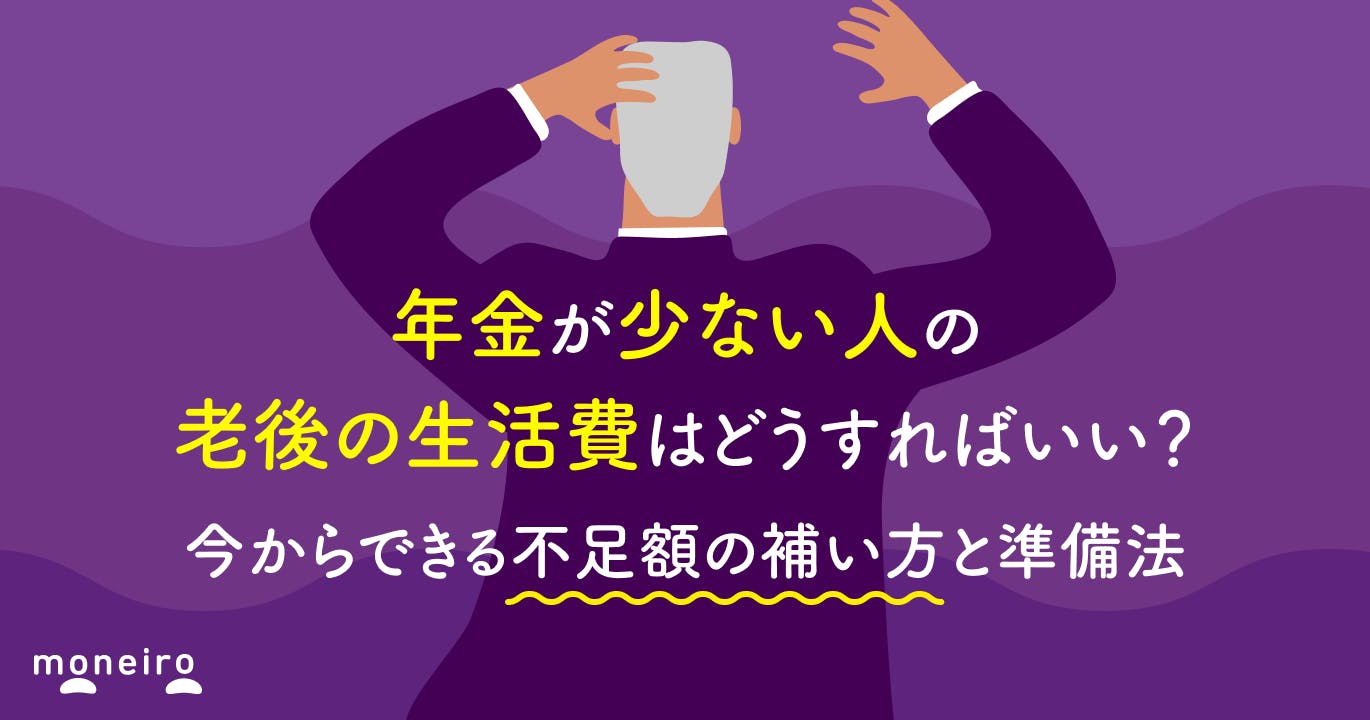
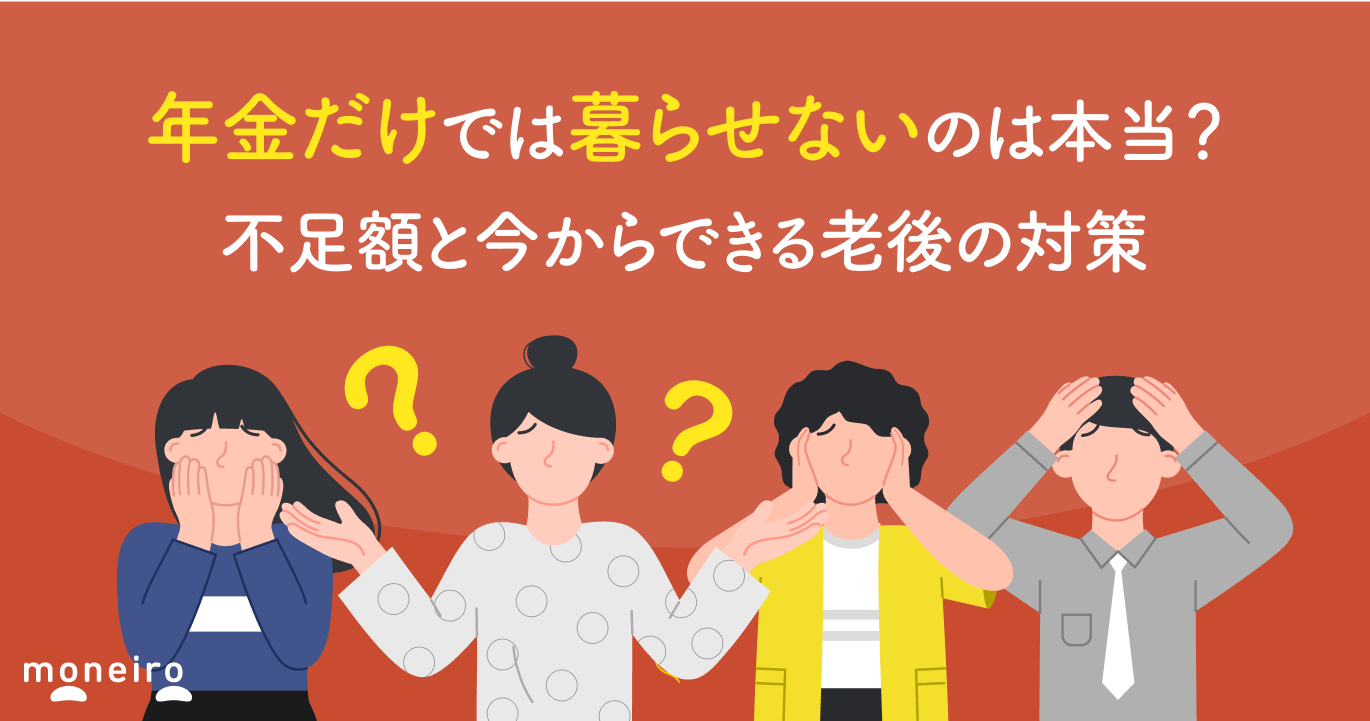
年金だけでは暮らせないのは本当?不足額と今からできる老後の対策をお金の専門家が解説

60歳からの国民年金「任意加入」は得?損?加入すべき人の特徴と年金の仕組み

正直みんな貯金はどのくらいある?年代別・年収別に平均額・中央値を解説
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。