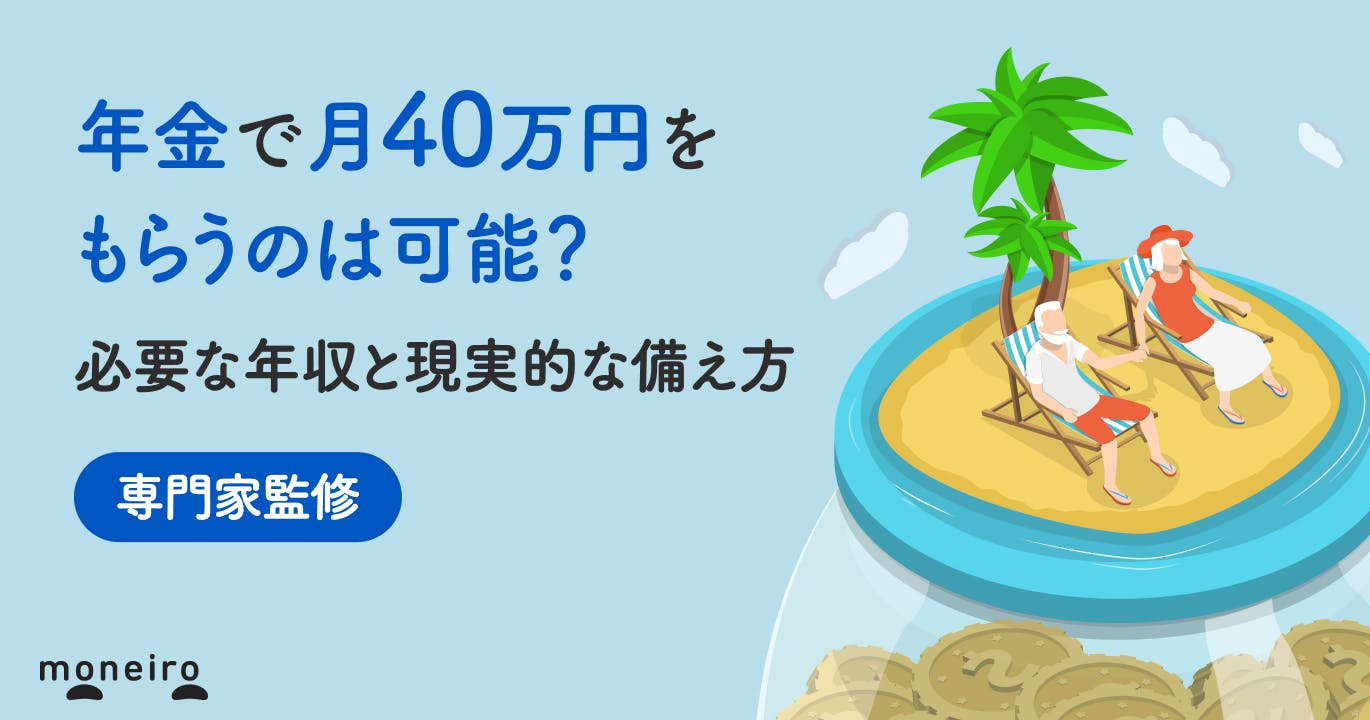年金で月40万円をもらうのは可能?必要な年収と現実的な備え方を専門家が徹底解説
»年金だけで老後は安心?3分でわかる無料診断
「老後は年金だけで毎月40万円ほしい」と考える人も少なくありません。しかし、厚生労働省の統計によると、実際の年金受給額は平均で単身約14万円、夫婦世帯でも22〜23万円程度です。また、公的年金だけで毎月40万円をもらうのは、制度上不可能といえます。
本記事では、年金制度の仕組みや年収ごとに受給できる年金額を整理するとともに、会社員・公務員・自営業での違いを解説します。
さらに夫婦合算で40万円を目指すケースや、退職金・企業年金・iDeCoなどで不足分を補う方法を紹介します。
年金制度の仕組みを正しく理解し、老後の安心につなげるための実践的なヒントをお伝えします。
- 年金40万円の実現可能性
- 目標達成に必要な年収の目安
- 40万円に届かない場合の備え方
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
年金で毎月40万円は実現可能?
「老後を月40万円の年金で豊かに暮らしたい」という理想は、多くの人が抱くものです。
結論から言うと、一人で公的年金だけで毎月40万円をもらうのは、制度上不可能です。しかし、夫婦の年金を合わせる場合には、高収入で長期間厚生年金に入っていれば実現の可能性があります。
平均的な受給額と40万円の差(国の統計データ)
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢基礎年金(国民年金)の平均月額は5万7700円です 。また、厚生年金受給者の平均月額は、国民年金分を含めても14万7360円にとどまります 。
月40万円という目標額との間には、約25万円という大きなギャップが存在しており、この差を埋めるためには自助努力が不可欠であることが明らかです。
単身では不可能、夫婦合算なら可能性あり
後述しますが、単身で公的年金だけで月40万円を達成することは、理論上不可能です。一方で、夫婦2人分の年金を合わせれば、月40万円という目標は現実味を帯びてきます。
例えば、夫婦ともに会社員として長期間働き、それぞれが厚生年金をもらう場合、世帯としての年金収入は大きく増加します。
夫婦の働き方や収入によって達成の難しさは変わりますが、一人の場合と比べて可能性は格段に高まります。
高収入+長期加入者の条件を確認
年金で月40万円を目指すには、「高い収入」と「長い加入期間」の両方を満たす必要があります。
厚生年金は、現役時代の収入(報酬)に比例して受給額が決まる「報酬比例」の仕組みを採用しています。年金額計算の基礎となる報酬には上限があります。しかし、長期間にわたって高い給与や賞与を得て、それに見合った厚生年金保険料を払い続けることで年金額を増やせます。
また、加入期間も重要な要素です。国民年金は40年(480ヶ月)の納付で満額となりますが、厚生年金は70歳に到達するまで加入できます。
70歳まで働くことで加入期間を延ばし、受給額を増やすことも可能です。
つまり、若いうちから高い収入を得て、できるだけ長く厚生年金に加入し続けることが、高額な年金受給への道筋となります。
40万円の年金をもらうにはどのくらいの年収が必要?
年金で月40万円をもらうために必要な年収は、加入する年金制度によって大きく異なります。
特に、会社員・公務員が加入する厚生年金と、自営業者などが加入する国民年金とでは、その構造が全く違うため、必要な年収の考え方も変わってきます。
会社員・公務員の場合
会社員や公務員が一人で毎月40万円(年額480万円)の年金をもらうのは、前述の通り不可能です。
年金額の構成は、定額の「老齢基礎年金」と、収入に比例する「老齢厚生年金」の2階建てです。2025年度の老齢基礎年金の満額は年額約83万円です。したがって、残りの約397万円を老齢厚生年金でもらう必要があります。
ただし、厚生年金保険料を計算する基礎となる標準報酬月額の上限は65万円となっており、月収63.5万円(年収762万円)を超えると、老齢厚生年金は増えない仕組みになっています。
仮に中学卒業後の16歳から70歳までの54年間(648ヶ月)ずっと年収762万円以上を維持したとしても、老齢厚生年金額は約231万円となり、397万円には到達しません。
なお、老齢厚生年金を計算する際には、給料だけでなく賞与も含めます。賞与にも150万円の上限がありますが、上記の給料に加えて150万円の賞与を年3回受け取り続けたと仮定しても、老齢厚生年金額は約364万(月額30万円)です。
つまり、公的年金の理論上の最高月額は老齢基礎年金6.9万円と老齢厚生年金30万円を合わせた36.9万円で、40万円に達することはありません。
自営業者の場合
自営業者やフリーランスが加入する公的年金は、原則として国民年金(老齢基礎年金)のみです。国民年金の受給額は、現役時代の収入の多寡にかかわらず、保険料の納付月数によって決まります。
20歳から60歳までの40年間、保険料をすべて納付した場合でも、2025年度の満額で月額約6.9万円(年額約83万円)です。したがって、自営業の方が公的年金だけで月40万円をもらうことは、どれだけ高い年収を得ていたとしても不可能です。
このため、自営業者は会社員以上に、iDeCo(個人型確定拠出年金)や国民年金基金、個人年金保険などを活用した自主的な老後資金の準備が不可欠となります。
年収と加入年数による受給額のシミュレーション
会社員や公務員の場合、将来の年金受給額は現役時代の平均年収と厚生年金の加入期間によって大きく変わります。
以下の表は、その目安を示したものです。ご自身の状況に近いものを見つけて、将来の受給額をイメージしてみましょう。
【年収・加入期間別 年金受給額の早見表(年額)】
※老齢基礎年金(満額約83万円)を含む概算値
例えば、平均年収700万円で40年間厚生年金に加入した場合でも、年間の受給額は約238万円(月額約19.8万円)となり、一人で月40万円には遠いことがわかります。
老後の生活設計を立てる上で、現実的な受給額を把握しておくことが大切です。
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
夫婦合算で40万円を実現するには
一人での達成が困難な月額40万円の年金も、夫婦の受給額を合わせることで現実的な目標となります。
ただし、世帯の働き方によって、目標達成のために必要な現役時代の世帯年収は大きく異なります。
ここでは、代表的な2つのケースについて見ていきましょう。
共働きフルタイム夫婦のケース
夫婦ともに正社員として長期間働き、それぞれが厚生年金をもらうケースでは、世帯の年金収入は大きく増加します。
これにより、比較的現実的な年収で月40万円の目標を達成できる可能性があります。
夫の平均年収が700万円、妻の平均年収が500万円で、それぞれ40年間厚生年金に加入したと仮定します。この場合、年金受給額の目安は以下のようになります。
- 夫の年金:約238万円/年(月額約19.8万円)
- 妻の年金:約191万円/年(月額約15.9万円)
この2つを合わせると、世帯の年金収入は年間約429万円、月額に換算すると約35.8万円となります。
40万円には届きませんが、夫婦ともにさらに高い収入を維持できれば、目標達成は十分に可能です。
例えば、夫婦ともに平均年収700万円以上を維持できれば、世帯での年金月額40万円が見えてきます。
専業主婦(第3号被保険者)家庭のケース
夫が会社員で、妻が専業主婦(第3号被保険者)という家庭の場合、妻がもらう公的年金は国民年金(老齢基礎年金)のみとなります。
そのため、世帯で月40万円の年金をもらうには、夫が非常に高い年収を長期間維持する必要があります。
妻が国民年金を満額(月額約6.9万円)受給すると仮定すると、夫は残りの約33.1万円(年額約397万円)を自身の年金で賄わなければなりません。
夫の年金のうち、国民年金部分が約6.9万円なので、厚生年金部分で月額約26.2万円(年額約314万円)をもらう必要があります。
ただし、老齢厚生年金は月収63.5万円(年収762万円)を超えるとそれ以上増えません。夫が40年間年収762万円以上を維持したと仮定しても、老齢厚生年金の額は約171万円(月額14.3万円)にしかなりません。そのため、月40万円を達成することは不可能です。
企業年金や退職金を加味した場合
公的年金だけで月40万円を目指すのはハードルが高いですが、企業独自の年金制度や退職金を加味すれば、目標達成はより現実的になります。
多くの企業では、厚生年金に上乗せする形で「企業年金(確定給付企業年金や企業型確定拠出年金など)」を導入しています。
また、退職時にもらう退職一時金も重要な老後資金です。例えば、2000万円の退職金を20年間で取り崩す場合、年間100万円、月額に換算すると約8.3万円を生活費に充当できます。
公的年金の見込み額が月32万円だったとしても、この退職金の取り崩し分を加えれば、月40万円の生活が実現可能です。
勤務先の退職金制度や企業年金について確認し、老後の収入全体を把握することが大切です。
40万円に届かない場合の備え方
シミュレーションの結果、公的年金だけでは月40万円に届かないと分かっても、悲観する必要はありません。
現役時代から計画的に準備を進めることで、不足分を補い、ゆとりある老後生活を実現することは十分に可能です。
公的年金はあくまで老後生活の土台と考え、自助努力による上乗せ部分を構築していきましょう。
退職金・企業年金を活用する
老後資金を考える上で、退職金や企業年金は公的年金と並ぶ重要な収入の柱です。まずは自身の勤務先の制度を確認し、将来もらえるおおよその金額を把握しましょう。
退職金は一時金でもらうか、年金形式でもらうか選択できる場合があります。一時金でもらう場合は、退職所得控除という税制上の優遇措置があり、税負担を抑えられます。
もらった資金を計画的に取り崩していくことで、毎月の生活費を補うことができます。企業年金がある場合は、60歳や65歳から終身または一定期間、公的年金に上乗せして収入を得られます。
これらの制度を最大限活用することで、老後のキャッシュフローは大きく改善します。
iDeCo・NISAで上乗せ資金を準備
国が用意した投資における税制優遇制度であるiDeCo(個人型確定拠出年金)とNISA(少額投資非課税制度)は、公的年金の上乗せ資金を準備するために活用できる制度です。
iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象となるため、現役時代の所得税・住民税を軽減しながら老後資金を積み立てることができます。
運用によって得られた利益も非課税で再投資され、60歳以降にもらう際にも税制上の優遇があります。
一方、NISAは、投資で得られた利益が非課税になる制度です。2024年から新しくなったNISAでは、非課税で投資できる上限額が大幅に拡大し、制度も恒久化され、より柔軟で長期的な資産形成が可能になりました。
iDeCoとNISAを併用することで、効率的に老後の資産を築くことができます。
資産運用や副収入の可能性
iDeCoやNISA以外にも、投資信託や株式投資などを活用した資産運用は、老後資金を増やすための有効な手段です。
長期・積立・分散投資を心掛けることで、リスクを抑えながら着実に資産を育てることが期待できます。
また、定年後も健康であれば働き続けることも有力な選択肢です。厚生年金に70歳まで加入すれば、将来の年金額を増やせます。
さらに、現役時代に培ったスキルや経験を活かして、パートタイムや業務委託で働くことで、年金以外の安定した収入源を確保することも可能です。
これにより、年金の繰下げ受給を選択しやすくなるというメリットも生まれます。
40万円の年金があればどんな生活ができるか
老後に毎月40万円の収入が確保できれば、多くの場合、ゆとりある生活を送ることが可能になります。
国の統計データと比較することで、どの程度の生活水準が期待できるのか、具体的なイメージを持つことができます。
高齢夫婦無職世帯の平均支出との比較
総務省の家計調査によると、2024年における65歳以上の夫婦のみの無職世帯では、1ヶ月の消費支出の平均額は約25.6万円です。
このデータと比べると、毎月40万円の収入があれば、平均的な生活費を支払った後でも、毎月14万円以上の余裕資金が生まれる計算になります。
この余裕資金は、趣味や旅行、孫へのお祝い、将来の医療・介護費用への備えなど、様々な目的に活用することができ、精神的な安心にも繋がります。
(参考:家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要)
ゆとりある老後生活に必要な金額
生命保険文化センターの調査によると、夫婦2人で「ゆとりある老後生活」を送るために必要と考える生活費は、平均で月額37.9万円という結果が出ています。
「ゆとり」には、旅行やレジャー、趣味や教養、人との付き合いなどが含まれています。
この金額と比べても、月40万円の収入があれば、平均的な人が考える「ゆとりある老後」を十分に実現できる水準にあると言えるでしょう。
経済的な心配をせずに、自分たちのやりたいことにお金を使える生活が期待できます。
(参考:生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/2022(令和4)年度)
40万円の生活イメージ
毎月40万円の収入があれば、日々の生活費に加えて、人生を豊かにするための様々な活動にお金を使うことができます。具体的な生活イメージは以下の通りです。
- 旅行・レジャー:年に数回、夫婦で国内の温泉旅行に出かけたり、少し豪華な海外旅行を計画したりすることも可能です
- 趣味・教養:以前から興味があった楽器や絵画を習い始めたり、スポーツジムに通って健康維持に努めたりと、自己投資にも積極的になれます
- 交際費:友人との食事会や、子ども・孫との交流にも気兼ねなくお金を使うことができます
- 医療・介護への備え::平均的な支出を上回る収入があるため、将来の急な入院や介護サービスの利用が必要になった場合でも、貯蓄を大きく取り崩すことなく対応できる安心感があります
このように、月40万円の年金収入は、経済的な制約をあまり感じることなく、アクティブで充実したセカンドライフを送るための強固な基盤となります。
まとめ
結論として、一人で公的年金だけで月40万円をもらうのは不可能ですが、夫婦合算であれば高収入・長期加入を前提に実現の可能性があります。
特に共働きで夫婦それぞれが厚生年金をもらう場合、目標達成はより現実的になります。
シミュレーションの結果、目標額に届かない場合でも、iDeCoやNISAといった税制優遇制度を活用したり、退職金や企業年金を計画的に利用したりすることで、不足分を補うことは十分に可能です。
重要なのは、自身の年金見込み額を早期に把握し、目標との差を埋めるための計画を立て、着実に実行していくことです。
本記事をきっかけに、ご自身の豊かな老後生活に向けた準備を始めてみてはいかがでしょうか。
»今の貯蓄で老後資金は足りる?無料でわかる診断はこちら
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

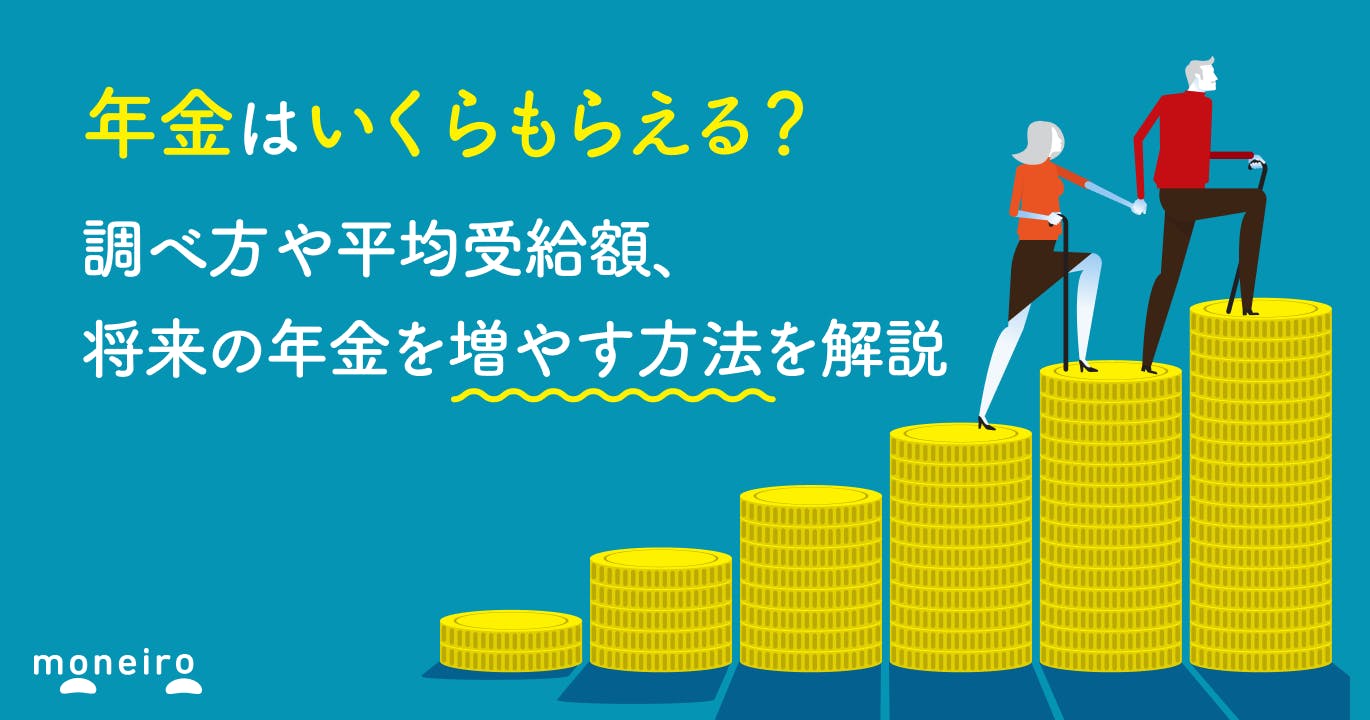
年金はいくらもらえる?調べ方や平均受給額、将来の年金を増やす方法を解説

60歳以上も厚生年金に加入し続けるデメリットは?損しない働き方と制度を解説
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。