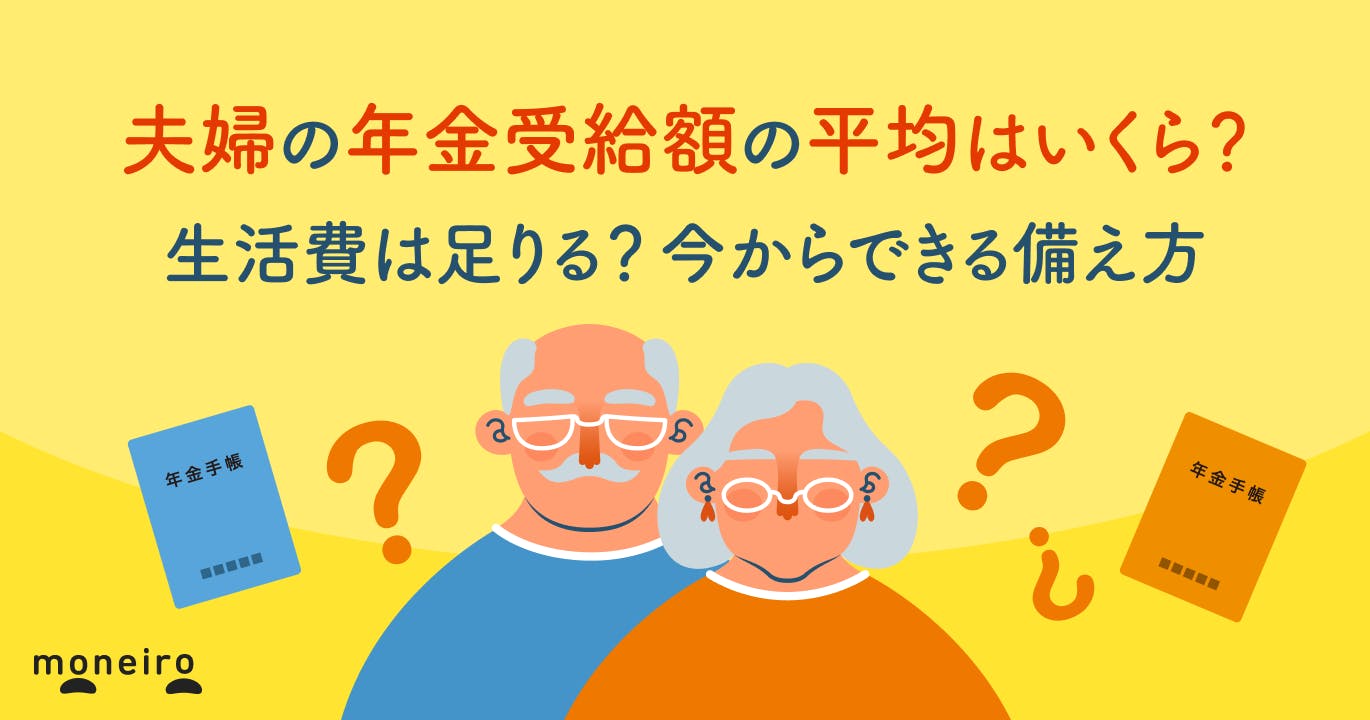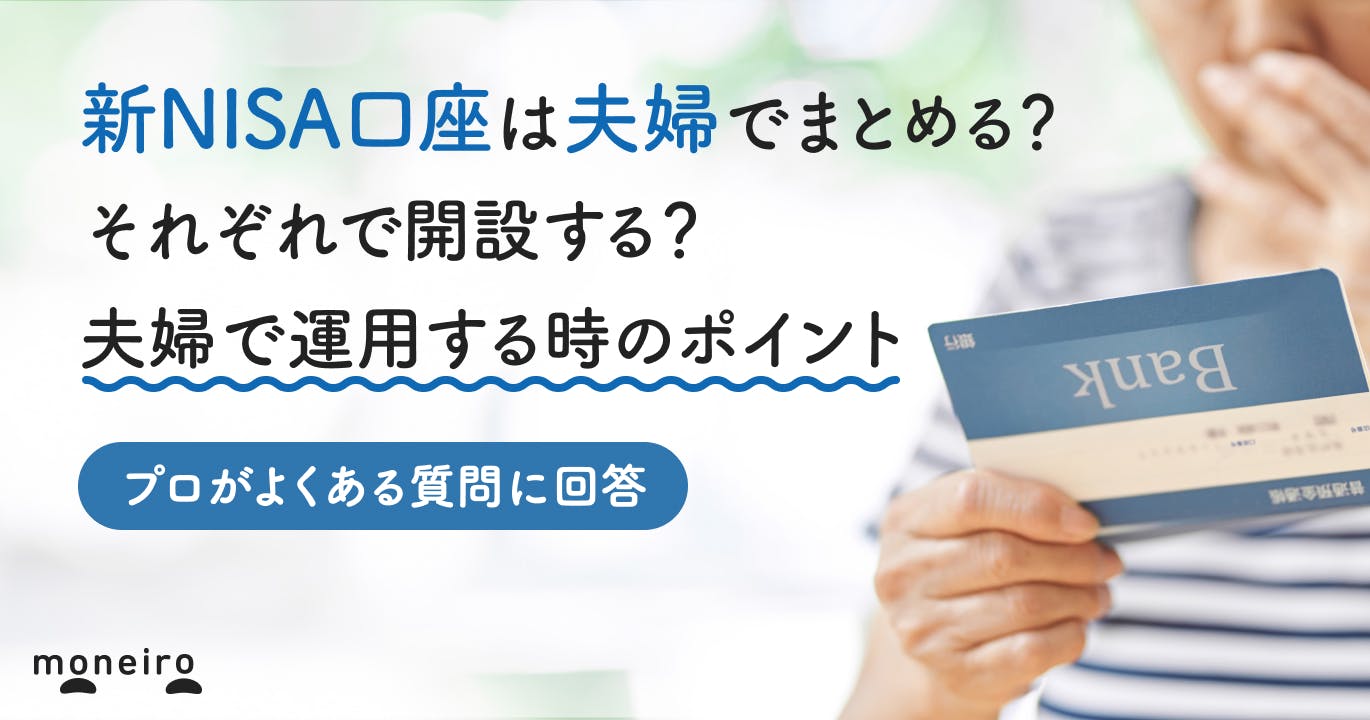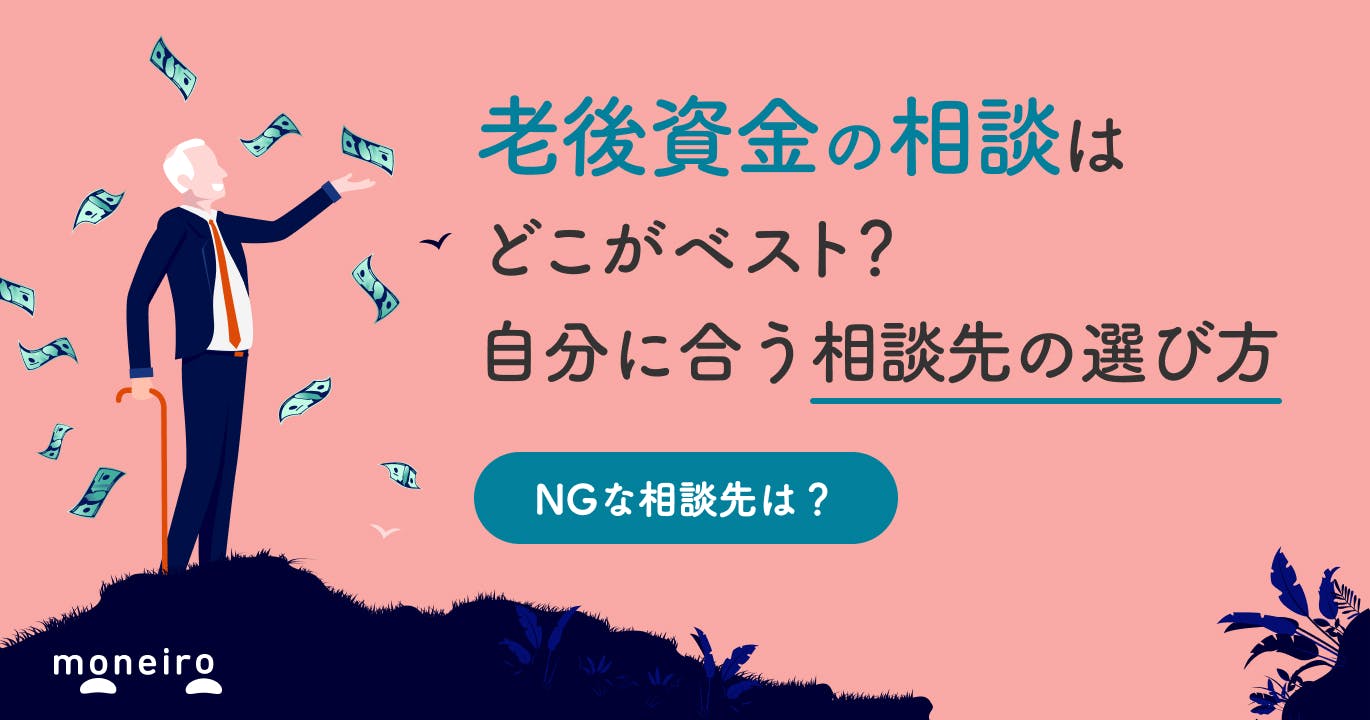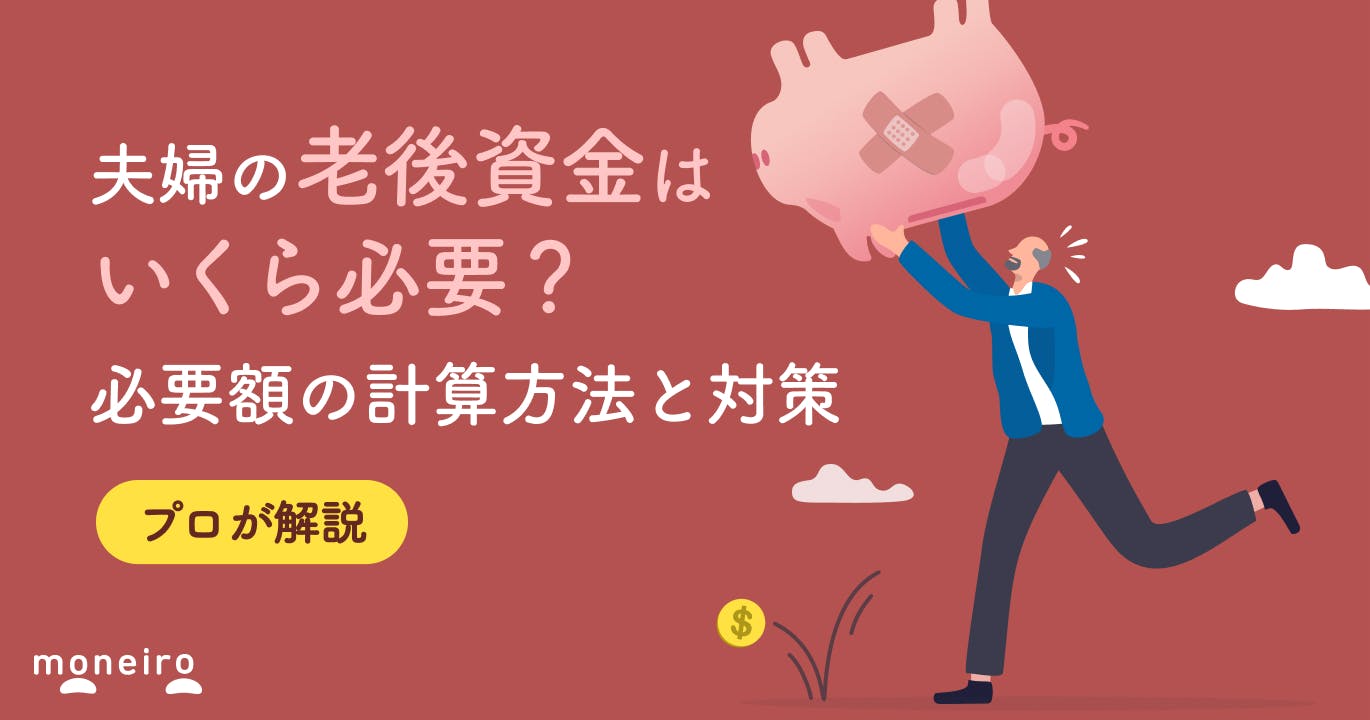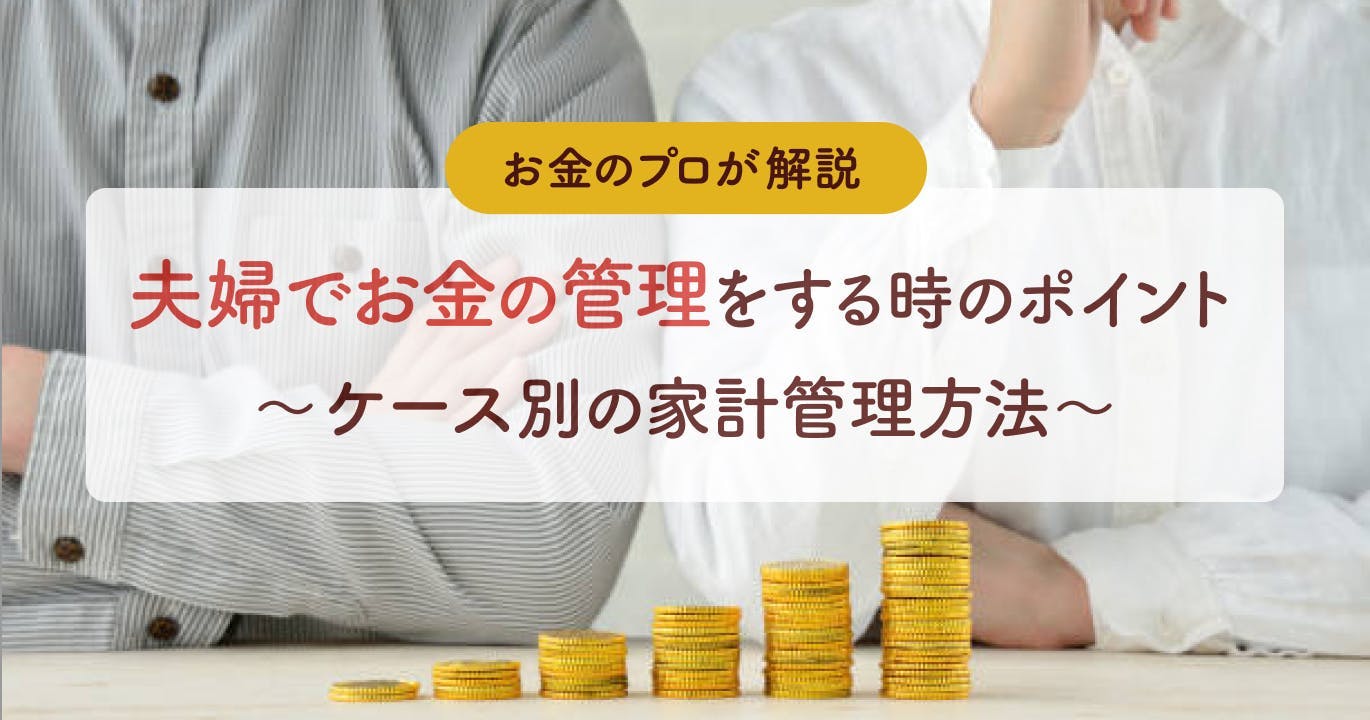夫婦の年金受給額の平均はいくら?生活費は足りる?今からできる備え方を専門家が解説
≫年金で老後資金は足りる?あなたの必要額を診断
「夫婦で年金をもらうと毎月いくらになるのか?」は老後資金を考えるうえで最も気になるポイントです。
厚生労働省が発表しているモデルケースでは、夫婦2人の平均的な年金受給額は約23万円とされています。ただし、実際には共働き世帯か専業主婦世帯か、自営業かによって大きく異なります。
本記事では、夫婦の平均年金額をデータで確認しつつ、働き方別のシミュレーション、老後の生活費との比較、不足分をどう補うかまで専門家視点で解説します。さらに、自分の年金額を調べる方法(ねんきん定期便・シミュレーター)も紹介し、将来設計に役立つ具体的な指針を提供します。
- 夫婦の年金受給額の平均データ
- 老後の生活費と年金の不足額
- 不足分を補うための具体的な準備方法
年金の受給額が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶賢いお金の増やし方入門:将来資金が不安な方におすすめ
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:夫婦でしっかり備える方法
夫婦の年金受給額の平均データ
厚生労働省が発表しているモデルケースでは、夫婦2人分の標準的な年金受給額は月額約23万円とされています。
夫が平均的な収入で40年間会社員として勤務し、その期間、妻が専業主婦であった世帯を想定した金額であり、夫婦2人分の老齢基礎年金と、夫の老齢厚生年金が含まれています。
一方で、個々の加入実績に基づいた実際の平均データを見ると、年金制度ごとの受給額がわかります。
統計によると老齢基礎年金の平均月額は約5.7万円(5万7700円)です。それに対し、会社員や公務員が加入する厚生年金の場合、国民年金分を含めた平均月額は約14.7万円(14万7360円)となっています。
(参考:令和7年4月分からの年金額等について|日本年金機構)
(参考:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況)
夫婦の働き方別|年金受給額のシミュレーション
夫婦の年金受給額は、共働きか片働きか、また会社員か自営業かといった働き方の組み合わせによって大きく変わります。
特に、厚生年金という「2階部分」があるかないかが、世帯の受給総額に大きな差を生みます。
代表的な3つの働き方のモデルケースを基に、具体的な年金受給額をシミュレーションします。
共働きフルタイム(厚生年金+厚生年金)の場合
厚生労働省の統計データに基づくと、厚生年金受給者の平均月額は男性が約16.7万円、女性が約10.7万円です。
これを単純に合算すると、共働き夫婦の世帯としての平均受給額は月額約27.4万円になります。
あくまで平均値であり、夫婦それぞれの現役時代の収入や厚生年金の加入期間によって受給額は変わります。
例えば、夫婦ともに平均以上の収入を得て長期間勤務していた場合、世帯合計で月額30万円を超えることも珍しくありません。
夫が会社員・妻が専業主婦(第3号被保険者)の場合
夫が会社員で妻が専業主婦(第3号被保険者)の場合、夫は自身の加入実績に基づき老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ります。
一方、妻は自身で保険料を納付していませんが、第3号被保険者であった期間が国民年金の納付済期間として算入されるため、老齢基礎年金を受給できます。
厚生年金の男性の平均受給額が約16.7万円、国民年金の平均受給額が約5.7万円とした場合、このモデルケースの世帯における年金受給額の合計は、月額約22.4万円が目安となります。
夫婦共働きで共に厚生年金に加入していた世帯と比較すると、妻の老齢厚生年金がない分、世帯としての受給額は低くなります。
夫婦ともに自営業(国民年金のみ)の場合
夫婦がともに自営業者やフリーランスとして働いている場合、加入する公的年金は国民年金のみとなります。そのため、老後に受け取る年金も夫婦それぞれの老齢基礎年金だけです。会社員世帯にあるような厚生年金という「2階部分」がないため、受給額は相対的に少なくなります。
国民年金の平均受給月額は、約5.7万円です。したがって、夫婦2人分を合わせると、世帯としての平均受給額は月額約11.4万円となります。
仮に夫婦ともに40年間、保険料を一度も欠かさず納付して満額を受給した場合でも、月額合計は約13.8万円(2025年度)が上限です。
この働き方の世帯では、公的年金だけで老後の生活費をすべて賄うのは現実的に困難です。そのため、計画的に上乗せの資産を準備する「自助努力」が重要になります。
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶賢いお金の増やし方入門:将来資金が不安な方におすすめ
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:夫婦でしっかり備える方法
年金額と老後生活費の比較
公的データを用いて老後のリアルな家計状況を分析し、どれくらいの資金が不足するのか、また「ゆとり」のためにはいくら上乗せが必要なのかを具体的に解説します。
高齢夫婦無職世帯の平均支出(総務省家計調査)
総務省の「家計調査報告(家計収支編)2024年(令和6年)」によると、夫婦二人とも65歳以上で無職の場合、1ヶ月あたりの家計は次のようになっています。
- 実収入:25万2818円
- 可処分所得(税金や社会保険料を差し引いた手取り):22万2462円
- 消費支出:25万6521円
- 平均消費性向:115.3%(=消費支出 ÷ 可処分所得 × 100)
毎月約3.4万円の赤字となっています。最低限の生活だけでなく、ゆとりある老後を送るためには、年金以外の資産準備が不可欠と言えます。
(参考:家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要)
ゆとりある老後に必要な金額
日々の生活を賄うだけでなく、旅行や趣味、孫との交流など、人生をより豊かに楽しむための「ゆとり」を求める場合、さらに多くの資金が必要となります。
生命保険文化センターが実施した調査によると、夫婦2人が経済的にゆとりのある老後生活を送るために必要と考える生活費は、月額で平均37.9万円という結果が出ています。
夫婦2人とも65歳以上で無職の場合の実収入、約25万円に加えて、毎月約13万円の上乗せ資金が必要であると多くの人が感じていることを示しています。
この上乗せ資金の主な使い道として挙げられているのは、「旅行やレジャー」「日常生活費の充実」「趣味や教養」「身内との付き合い」などです。
どのような老後を送りたいかを夫婦で具体的に話し合い、目標とする生活レベルに必要な資金を計画的に準備することが、心豊かなセカンドライフを実現するための鍵となります。
(参考:生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/2022(令和4)年度)
≫年金だけで老後資金は足りる?あなたのケースで必要額をシミュレーション
自分の年金額を確認する方法
老後の資金計画を立てる第一歩は、将来自分がいくら年金を受け取れるのか、その見込額を正確に把握することから始まります。
日本年金機構が提供する「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」といった公的なツールを活用すれば、個人の加入記録に基づいた具体的な金額を確認することが可能です。
自分の年金額を正確に確認するための3つの方法について、それぞれの特徴と使い方を分かりやすく解説します。
ねんきん定期便の見方
「ねんきん定期便」は、毎年誕生月に日本年金機構から郵送されてくるハガキまたは封書で、自身の年金記録を確認するための最も基本的なツールです。
これまでの保険料納付状況や加入期間に誤りがないかをチェックする重要な機会となります。
記載内容は年齢によって異なり、50歳未満の人には「これまでの加入実績に応じた年金額」が表示されます。これはあくまで過去の実績に基づく金額です。
一方、50歳以上の場合には、現在の加入条件が60歳まで続くと仮定した場合の「老齢年金の見込み額」が記載され、より具体的な将来の受給額をイメージしやすくなっています。
特に35歳、45歳、59歳の節目の年には、全期間の年金記録が一覧できる封書形式で届きます。
転職経験が多い場合などは、この機会に加入記録に漏れや誤りがないかを詳細に確認することが推奨されます。
ねんきんネットの活用方法
「ねんきんネット」は、インターネットを通じていつでも最新の年金記録を確認できる日本年金機構のオンラインサービスです。
パソコンやスマートフォンからアクセスでき、「ねんきん定期便」に記載されている情報をオンラインで手軽に閲覧できます。
このサービスの大きな利点は、将来の年金見込額を様々な条件で試算できることです。今後の収入の変化や、受給開始年齢を繰り上げた場合・繰り下げた場合など、自身のライフプランに合わせた複数のシナリオでシミュレーションが可能です。
利用にはユーザーIDの取得が必要ですが、マイナポータルと連携することで、より簡単にログインしてサービスを利用できます。年金記録の電子データをダウンロードして保管することも可能です。
公的年金シミュレーターで将来額を試算
厚生労働省の「公的年金シミュレーター」は、IDやパスワードなしで年金見込額を手軽に試算できるツールです。ねんきん定期便のQRコードを読み込めば、自分の年金記録が自動反映されます。スライダー操作で働き方や受給開始年齢を変えると、将来の受給額の変化をグラフで確認可能です。
ただし簡易的な試算のため、加給年金などは反映されません。大まかな見通しに使い、正確な金額は「ねんきんネット」で確認しましょう。
不足分を補うための準備方法
老後の経済的な安心は、公的年金という土台の上に、自分自身で資産を積み上げることでより確かなものになります。
年金の不足分を効果的に補うための具体的な3つの方法について、それぞれの特徴を解説します。
iDeCoやNISAで老後資金を積み立てる
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金の準備に特化した私的年金制度です。最大の特長は、掛金が全額所得控除の対象となるため、現役時代の所得税や住民税を軽減できる高い節税効果にあります。また、運用によって得られた利益も非課税となります。
ただし、積み立てた資産は原則として60歳まで引き出すことができないため、長期的な視点で着実に老後資金を確保したい方に適した制度です。
一方、NISA(少額投資非課税制度)は、年間投資枠内で購入した金融商品から得られる運用益が非課税になる制度です。
iDeCoと異なり、積み立てた資産はいつでも自由に引き出すことができるため、老後資金だけでなく、住宅購入や教育資金など、さまざまなライフイベントに備えるための柔軟な資産形成が可能です。
2024年から新しくなったNISAでは、非課税で投資できる上限額が大幅に拡大し、より積極的な資産運用が可能になりました。
企業年金や退職金制度を活用
会社員や公務員の方にとって、勤務先が用意している企業年金制度は、老後資金を考える上で非常に重要な要素です。これは公的年金に上乗せされる「3階部分」にあたり、老後の収入を大きく左右する可能性があります。
将来の給付額があらかじめ約束されている「確定給付企業年金」や、自分自身で運用を行う「企業型確定拠出年金」など、制度の種類は企業によってさまざまです。まずは自社の制度内容を正確に把握することが第一歩です。
また、退職金も老後資金の大きな柱となり得ます。しかし、退職金制度の有無や給付水準は企業によって大きく異なるため、過度な期待は禁物です。
就業規則や退職金規程などを確認し、自分が将来受け取れる見込み額を把握した上で、老後の資金計画に具体的に組み込むことが大切です。
付加年金・国民年金基金の利用
自営業者やフリーランスなど、国民年金の第1号被保険者の場合は、厚生年金に代わる上乗せの年金制度として「付加年金」と「国民年金基金」が利用できます。
付加年金は、毎月の国民年金保険料に月額400円を上乗せして納めることで、将来「200円×納付月数」で計算される年金額を生涯にわたって受け取れる制度です。
2年間年金を受け取れば支払った保険料の元が取れる計算となり、比較的負担なく年金を増やせる制度と言えます。
一方、国民年金基金は、より手厚い保障を準備できる私的年金制度です。掛金は全額が社会保険料控除の対象となるため、所得税や住民税を節税しながら将来の年金を増やすことができます。掛金の額や給付の型をライフプランに合わせて自分で設計できる柔軟性も魅力です。
ただし、付加年金と国民年金基金を同時に利用することはできないため、どちらか一方を選択する必要があります。
まとめ
夫婦の年金受給額は、共働きで共に厚生年金に加入していた世帯で月額約27.4万円、夫が会社員で妻が専業主婦の世帯で約22.4万円、夫婦ともに自営業の世帯では約11.4万円と、働き方によって大きな差があります。
一方で、高齢夫婦の平均的な生活費は約26万円であり、多くの世帯で年金収入だけでは不足する可能性があります。
この不足分を補うためには、自身の年金見込額を「ねんきんネット」などで正確に把握し、iDeCoやNISAといった制度を活用して計画的に資産形成を進めることが、安心して老後を迎えるための鍵となります。
≫年金で老後資金は足りる?あなたのケースで必要額をシミュレーション
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶賢いお金の増やし方入門:将来資金が不安な方におすすめ
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:夫婦でしっかり備える方法
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。