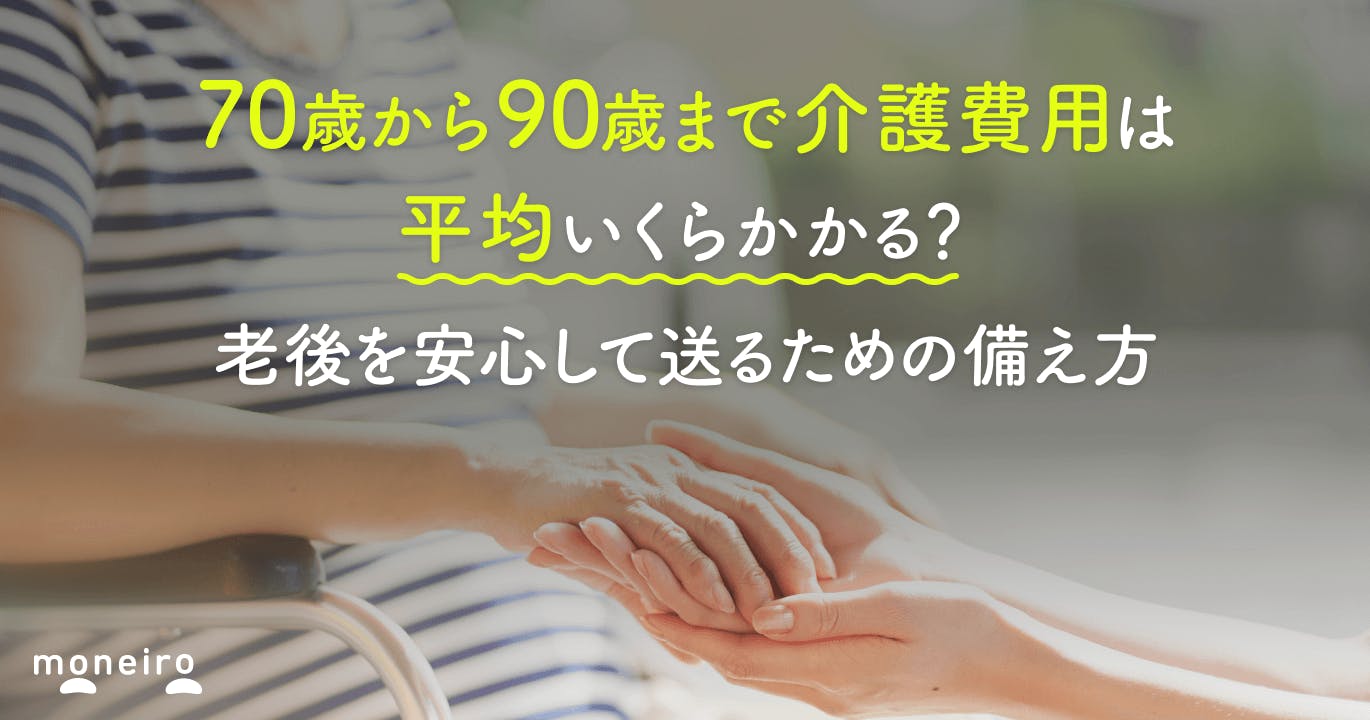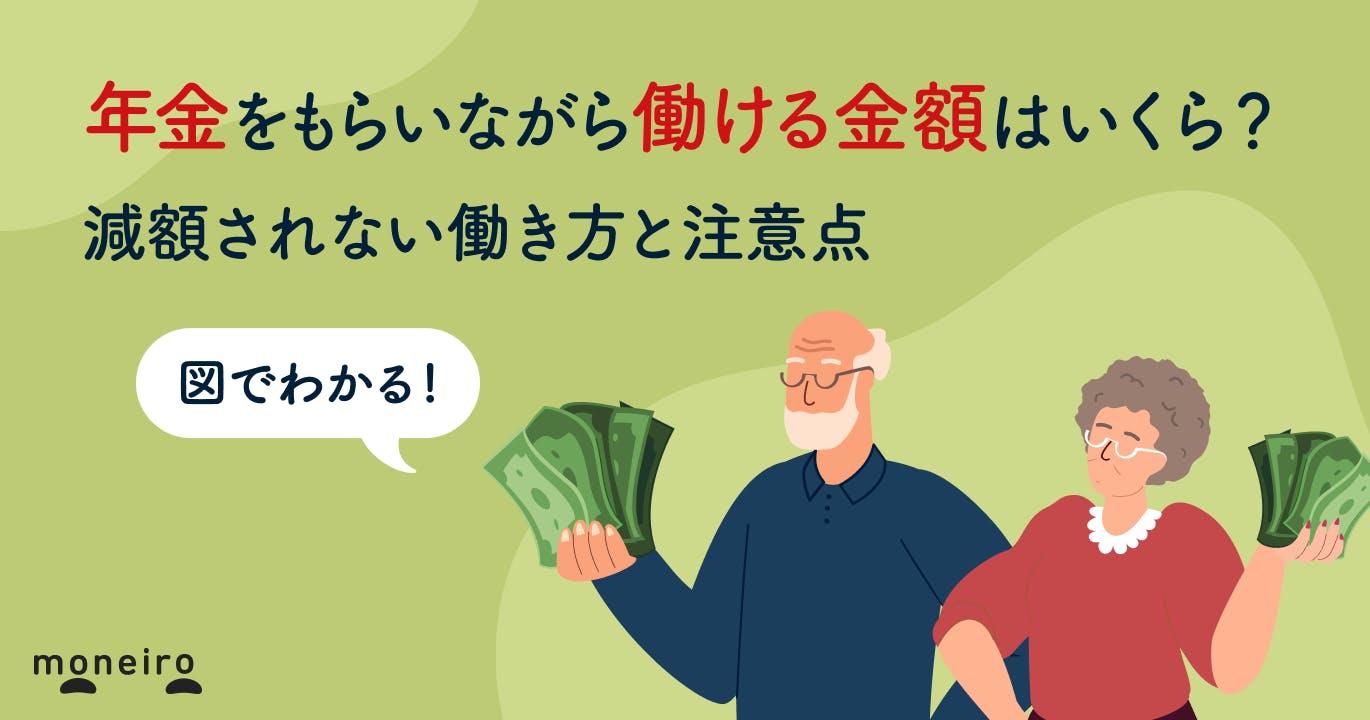60歳からの国民年金「任意加入」は得?損?加入すべき人の特徴と年金の仕組み
≫あなたは年金だけで足りる?将来の必要額を3分で診断
「60歳を過ぎたけれど、年金の未納期間が気になる」「任意加入で元は取れる?」と年金について考えている人は多いでしょう。
国民年金の加入は20歳以上60歳未満とされていますが、未納期間がある場合は60歳を過ぎても加入が可能です。
本記事では、任意加入制度の仕組みや、保険料を払うことで増える年金額の例、損益分岐点の考え方、加入すべきケース・そうでないケースを専門家監修のもと、わかりやすく解説します。
- 60歳以降も任意で国民年金に加入し、将来受け取る年金額を増やすことが可能
- 60歳以降も国民年金に加入できるのは「60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある」「0歳から60歳までの納付済期間が480ヶ月(40年)未満」など
- 保険料の納付1年で増える年金額の目安は毎月約1732円(令和7年度のデータに基づき算出)
年金受給が気になるあなたへ
あなたは年金だけで暮らせる?老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
60歳以降も国民年金に加入できる?任意加入の仕組み
日本の公的年金制度は、老後の生活を支える大切な柱です。原則として国民年金は20歳から60歳未満までが加入期間とされています。
一方、60歳以降も任意で国民年金に加入し、将来受け取る年金額を増やすことができる「任意加入制度」があります。
任意加入制度について、厚生労働省の情報を基に詳しく見ていきましょう。
(参考:任意加入制度|日本年金機構)
国民年金の加入は「60歳未満」まで
国民年金の加入義務があるのは、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人です。
この期間に保険料を納めることで、老齢基礎年金をはじめとする給付を受けることができます。
任意加入の対象者・条件
60歳以降に国民年金に任意加入できるのは、以下すべての条件を満たす人です。
- 60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある
- 老齢基礎年金の繰上げ受給を受けていない
- 20歳から60歳までの納付済期間が480ヶ月(40年)未満
- 厚生年金や共済組合に加入していない
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人
60歳から任意加入すると、年金はいくら増える?
将来受け取る年金額を増やすことを目的に、任意加入制度を利用する人も多いでしょう。具体的にどれくらい年金額が増えるのか、目安を確認しましょう。
保険料の納付1年で増える年金額の目安
国民年金の保険料は毎年見直されますが、令和7年度の月額保険料は1万7510円です。1年間(12ヶ月)保険料を納付すると、年金額は約21万円(1万7510円 × 12ヶ月)の保険料を納めることになります。
満額の老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)、保険料を納付した場合に支給されます。令和7年度の老齢基礎年金満額は年額83万1700円(6万9308円 × 12ヶ月)です。
1年間の国民年金保険料を納付することで増える年金額は、以下の計算式で概算できます。
令和7年度の満額83万1700円で計算すると、1ヶ月分の保険料を納付すると、増加する年金額は83万1700円÷480ヶ月=約1732円です。
したがって、1年間(12ヶ月)任意加入すると、1732円×12ヶ月=2万784円、年金額が増えることになります。
60歳〜65歳まで加入した場合のシミュレーション
60歳から65歳までの5年間(60ヶ月)任意加入した場合、増加する年金額は以下のようになります。
つまり、年間10万3920円、老齢基礎年金が増額されることになります。
5年間で納める保険料の総額は、1万7510円/月×60ヶ月=105万600円です。
参考)年金の損益分岐点
前述のシミュレーションで、5年間任意加入した場合の保険料総額は105万600円、年間増加額は10万3920円でした。この場合、損益分岐点は以下のようになります。
=105万600円÷10万3920円
=10.109……
つまり、年金を受け取り始めてから約10年で、納めた保険料分を回収できる計算になります。
例えば、65歳から年金を受け取るとすると、75歳頃まで生きれば、保険料分を回収できることになります。
任意加入のメリット・デメリット
任意加入を検討する際には、メリットとデメリットを理解しておきましょう。
メリット
任意加入する最も大きなメリットは、将来受け取る老齢基礎年金が増えることです。特に、国民年金の未納期間がある場合や、厚生年金保険の加入期間が短い場合は、年金額を増やす有効な手段となります。
また、老齢基礎年金を受け取るには、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。任意加入により、この期間を満たすことができる場合があります。
さらに、任意加入と同時に「付加年金」に加入することもできます。
付加年金は、月額400円の付加保険料を納めることで、「200円 × 付加保険料納付月数」が年金額に上乗せされる制度です。これにより、年金額を増やすことができます。
デメリット
毎月保険料を支払う必要があるため、経済的な負担が増えます。特に、収入が少ない人にとっては大きな負担となる可能性があります。
また、納めた保険料を年金として回収するまでには、ある程度の期間が必要です。健康状態や平均寿命などを考慮し、損益分岐点を把握することが大切です。
年金受給が気になるあなたへ
あなたは年金だけで暮らせる?老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
任意加入した方が得な人・損な人の違い
任意加入が「得」になるか「損」になるかは、個々の状況によって異なります。
任意加入した方が「得」な可能性が高い人
国民年金に未納期間があり年金額が少ない人にとって、「任意加入」は年金額を増やす有効な手段です。
また、受給資格期間(10年)を満たしていない場合でも、任意加入によって期間を補い、年金を受け取れる可能性があります。
例えば、以下のような人に向いています。
- 経済的に余裕があり、将来の年金を増やしたい人
- 長生きする可能性が高く、年金を長く受け取れそうな人
将来の安心のために、保険料の負担と受給額を比較し、前向きに検討してみましょう。
任意加入した方が「損」になる可能性もある人
以下のような方は任意加入を慎重に検討すべきです。
- 経済的に余裕がない人…保険料の支払いが生活費を圧迫するおそれがあります
- 既に十分な年金が見込まれる人…厚生年金の加入期間が長く、将来の年金額が高い場合、追加で保険料を払っても得られるメリットは少ない可能性があります
- 健康状態に不安がある人…平均寿命よりも早く亡くなるリスクが高い場合、支払った保険料を十分に回収できない可能性があります
無理のない範囲で、将来の見通しとあわせて判断することが大切です。
自分は任意加入すべき?判断の目安【簡単チェック】
任意加入すべきかどうかを判断するための簡単なチェックリストです。
- 現在の年金見込み額に不安がある? (はい / いいえ)
- 国民年金の未納期間がある? (はい / いいえ)
- 60歳以降も経済的に保険料を支払う余裕がある? (はい / いいえ)
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない? (はい / いいえ)
- 長生きする自信がある? (はい / いいえ)
「はい」の数が多いほど、任意加入を検討する価値が高いと言えるでしょう。
最終的な判断は、ライフプランや経済状況、健康状態を総合的に考慮して行ってください。不明な点があれば、年金事務所や街角の年金相談センターに相談することをおすすめします。
任意加入の手続き方法と必要書類
任意加入の手続きは、住んでいる市区町村役場または年金事務所で行います。
【主な必要書類】
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 預貯金通帳および金融機関届出印(口座振替を希望する場合)
- その他、状況に応じて必要となる書類(住民票など)
詳細については、事前に管轄の年金事務所に確認しましょう。
まとめ
60歳以降の国民年金任意加入制度は、将来の年金額を増やし、老後の生活をより安定させるための選択肢の一つです。
年金額の増額、受給資格期間の確保といったメリットがある一方で、保険料の負担や損益分岐点の考慮も必要です。
自身の経済状況、健康状態、将来のライフプランなどを総合的に判断し、必要に応じて専門家のアドバイスも受けながら、最適な選択をしましょう。
≫年金だけで大丈夫?あなたの老後に必要な金額を診断
年金受給が気になるあなたへ
あなたは年金だけで暮らせる?老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
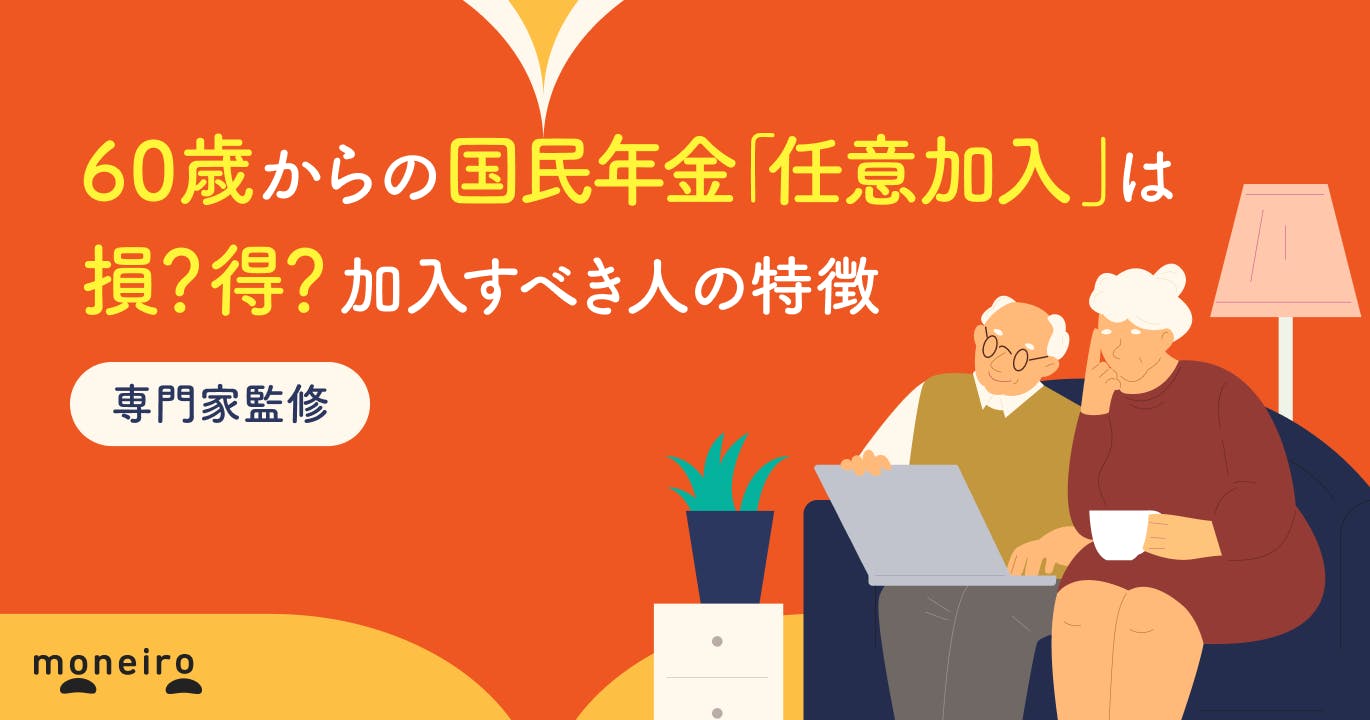
.png?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)