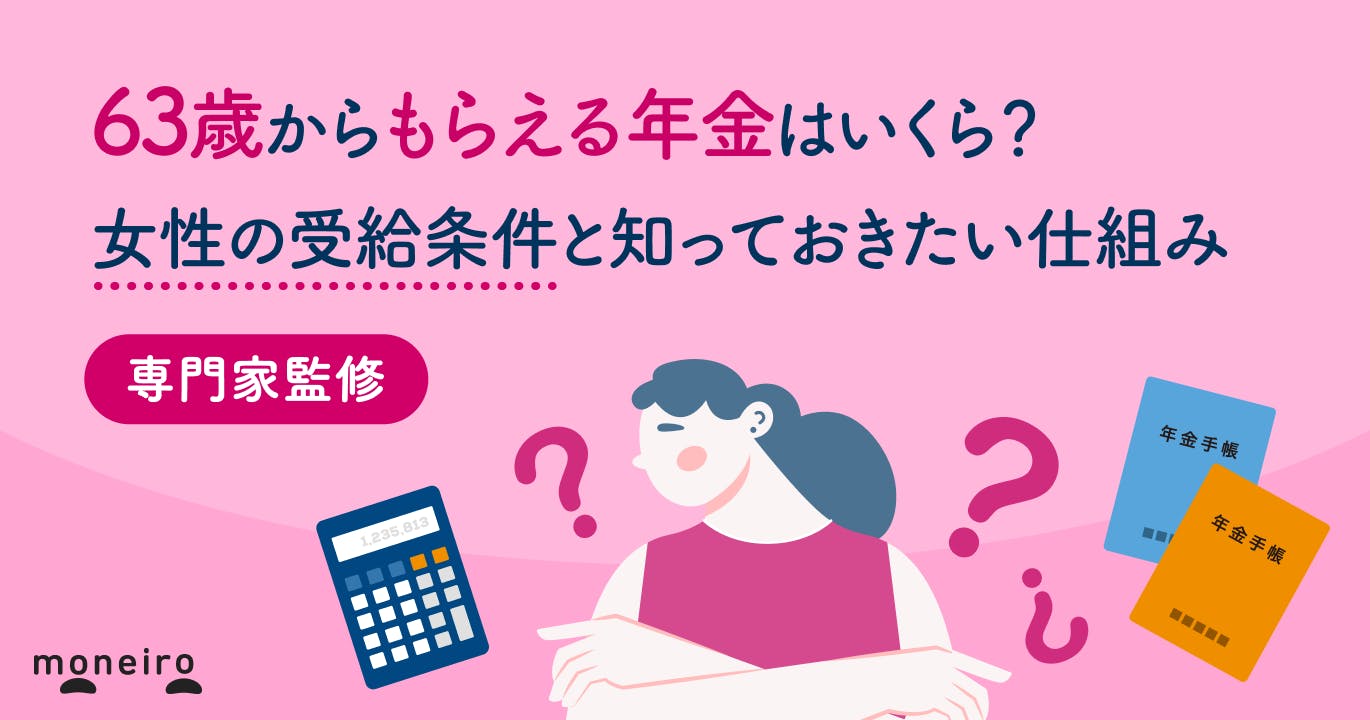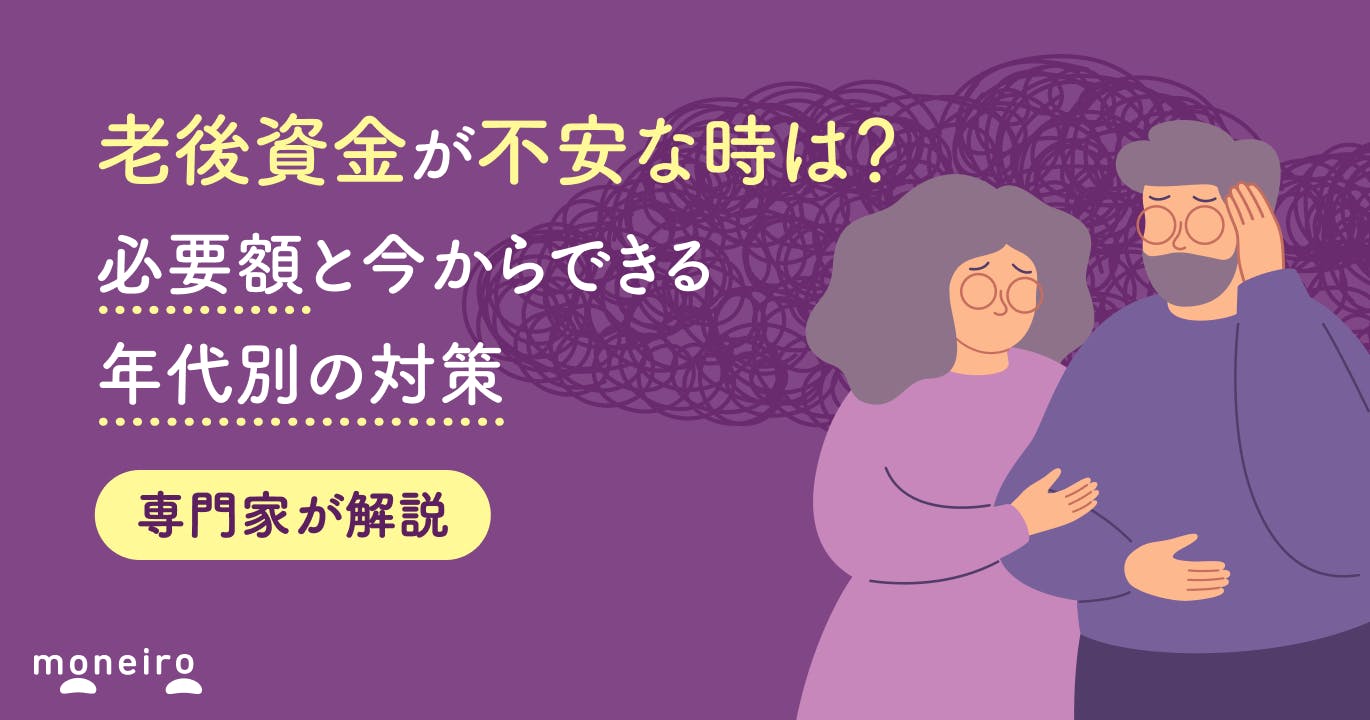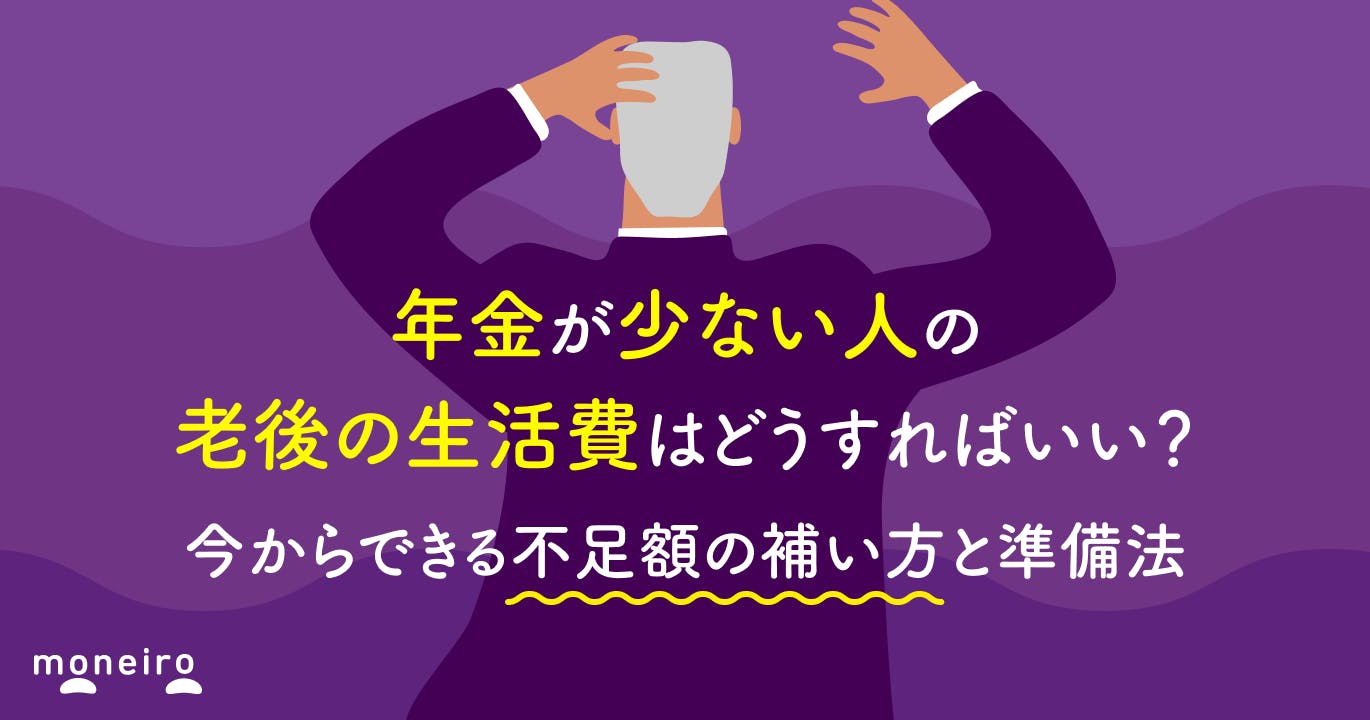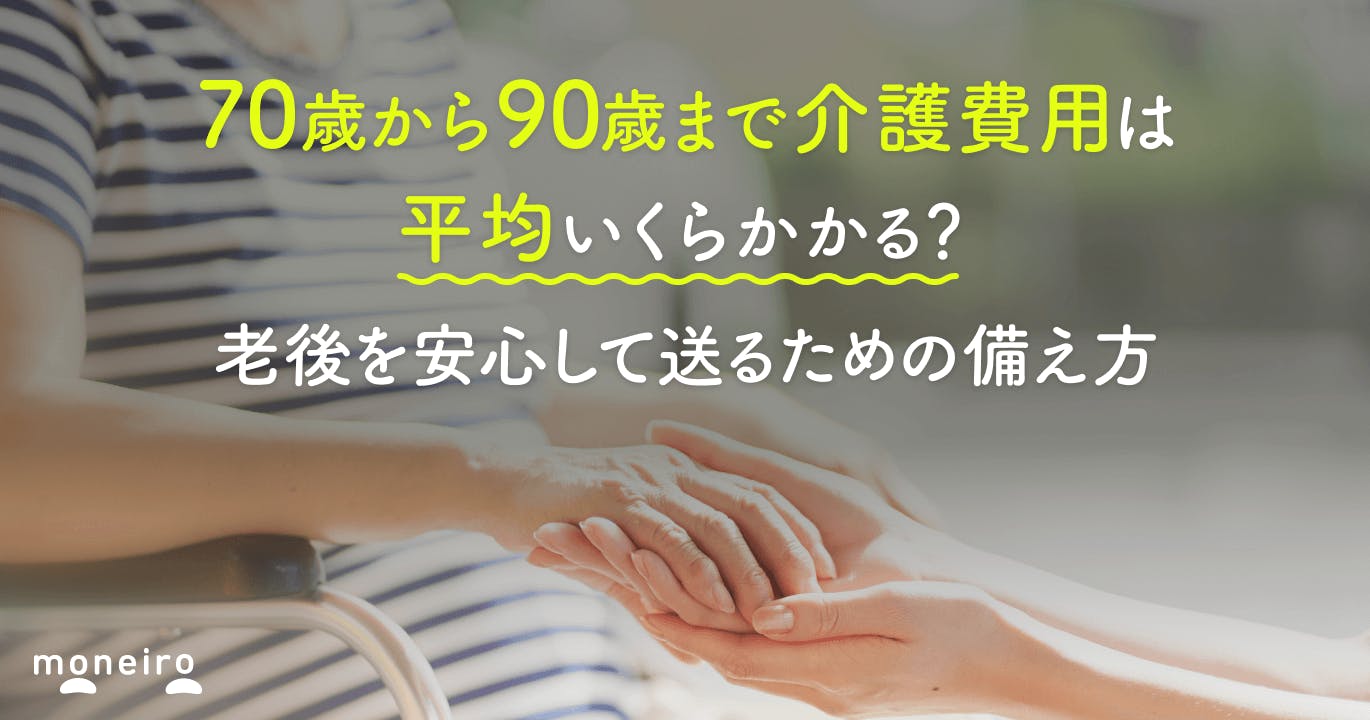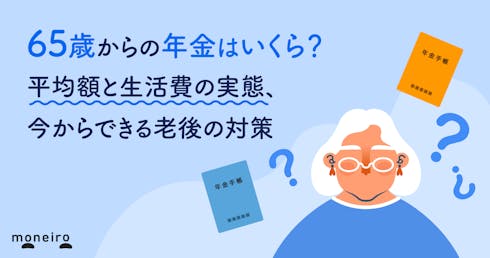
63歳からもらえる年金はいくら?女性の受給条件と知っておきたい仕組みを専門家が解説
»老後に足りないお金はいくら?今すぐ無料診断
「63歳になったら年金はもらえる?」と自身がもらえる年金について調べ始める女性は少なくありません。年金は原則65歳から支給されますが、生年月日や働き方によっては63歳から受け取れるケースもあります。
本記事では、63歳女性がもらえる可能性のある「特別支給の老齢厚生年金」や「繰上げ受給」の仕組みを、年金制度の専門知識をもとにわかりやすく解説します。さらに、もらえる金額の目安・損をしない受け取り方・働きながらの注意点も紹介。退職後の生活資金を不安なく準備するために、63歳からの年金の仕組みを一緒に整理していきましょう。
- 63歳から女性がもらえる年金の種類と条件
- 働き方別の年金受給額モデルケース
- 働きながらもらう場合の注意点(在職老齢年金)
年金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶専門家に無料相談:老後のお金の不安はプロにお任せ
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
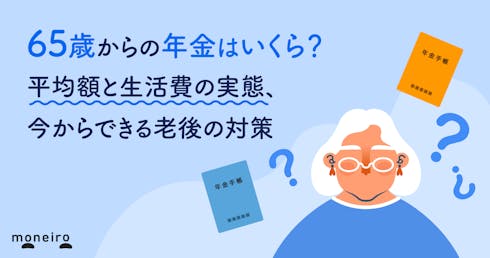
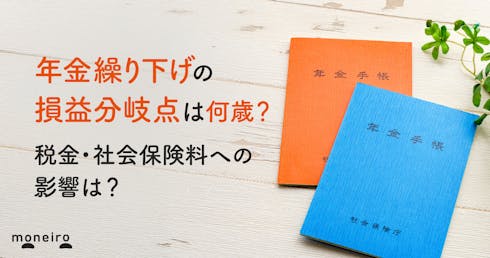
63歳からもらえる年金の種類|女性が知っておきたい基本
63歳の女性が受け取れる可能性がある年金には、主に「特別支給の老齢厚生年金」と「老齢年金の繰上げ受給」の2種類があります。どちらも本来の受給開始年齢である65歳より前に年金を受け取る制度ですが、その仕組みや対象者は大きく異なります。
「特別支給の老齢厚生年金」で63歳から受給できる場合も
日本の公的年金制度では、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金の支給は、原則として65歳からと決められています。これは、すべての加入者に共通する基本ルールです。
しかし、過去の制度改正に伴う経過措置として「特別支給の老齢厚生年金」という制度が存在します。これは、かつて厚生年金の受給開始年齢が60歳だったものが65歳に引き上げられた際に、受給開始年齢の引き上げを円滑に進める目的で設けられました。
この制度の対象となる特定の生年月日の人は、65歳になる前から、段階的に設定された年齢(例えば63歳)から老齢厚生年金を受け取ることが可能です。
これはあくまで期間限定の特別な措置であり、すべての人が対象となるわけではありません。
「国民年金の繰上げ受給」との違い
「特別支給の老齢厚生年金」と混同されやすいのが「繰上げ受給」です。繰上げ受給は、希望すれば誰でも60歳から65歳になるまでの間に年金の受け取りを前倒しできる制度です。老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が対象となります。
しかし、繰上げ受給を選択すると、早めた月数に応じて年金額が減額されます。1ヶ月あたり0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)が減額され、この減額率は生涯にわたって適用されます。一度手続きをすると取り消しはできません。
一方、特別支給の老齢厚生年金は、特定の生年月日の人のみが対象となる経過措置です。こちらは厚生年金部分のみが対象で、繰上げ受給のような減額率の適用はありません。制度の目的そのものが異なる点を理解しておきましょう。
63歳の女性が対象になるかチェック(生年月日早見表)
自身が特別支給の老齢厚生年金の対象となるか、また何歳から受け取れるかは、生年月日によって決まっています。
女性の場合、男性よりも5年遅れて受給開始年齢が引き上げられているのが特徴です。
63歳から受給が開始される女性は、昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた人です。
以下の表で自身の生年月日が該当するか確認してみましょう。
昭和41年4月2日以降に生まれた女性は、特別支給の老齢厚生年金の対象外となり、年金の受給開始は原則通り65歳からとなります。
特別支給の老齢厚生年金とは?制度の仕組み
特別支給の老齢厚生年金は、過去の制度改正における経過措置です。受給するためには生年月日や年金加入期間などの条件を満たす必要があり、年金額は現役時代の収入や加入期間に応じて計算される「報酬比例部分」が基本となります。
受給できる条件
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。一つでも満たしていない場合は受給できません。
- 生年月日:女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれていること。(男性の場合は昭和36年4月1日以前)
- 老齢基礎年金の受給資格期間:国民年金保険料(厚生年金保険料を含む)の納付月数や免除月数などを合算した期間が10年以上あること
- 厚生年金の加入期間:会社員や公務員として厚生年金に1年以上加入していた期間があること
- 受給開始年齢:生年月日に応じて定められた受給開始年齢に達していること
特に重要なのは、厚生年金への加入期間が1年以上必要である点です。例えば、一度も会社員として働いたことがない専業主婦の方などは、他の条件を満たしていてもこの制度の対象にはなりません。
.png?w=490&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)
支給開始年齢の段階的引き上げ
特別支給の老齢厚生年金制度が生まれた背景には、1985年の年金法改正があります。この改正により、老齢厚生年金の受給開始年齢が、それまでの60歳から段階的に65歳へと引き上げられることが決定しました。
変更による影響を緩和し、スムーズな移行を促すために「つなぎ」の制度として設けられたのが、特別支給の老齢厚生年金です。対象者の生年月日を2年ごと(※)に区切り、受給開始年齢を1歳ずつ引き上げるという方法が取られました。
また、この引き上げスケジュールは男女で異なり、女性は男性よりも5年遅れて開始されました。そのため、同じ年齢でも男性と女性で受給開始年齢が異なる場合があります。
この制度は経過措置であるため、昭和36年4月2日以降生まれの男性と昭和41年4月2日以降生まれの女性は対象外となり、制度は間もなくその役割を終えようとしています。
※昭和24年4月2日~昭和28年4月1日に生まれた男性(女性は年遅れ)の人を除く
(参考:特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構)
年金額の内訳(定額部分・報酬比例部分)
特別支給の老齢厚生年金の額は、「報酬比例部分」と「定額部分」という2つの要素で構成されていました。
- 報酬比例部分:厚生年金に加入していた期間の給与や賞与(標準報酬月額・標準賞与額)に応じて計算される部分です。現役時代の収入が高く、加入期間が長いほど金額が大きくなります
- 定額部分:国民年金(老齢基礎年金)に相当する部分で、厚生年金加入期間に応じて計算されます
ただし、制度の段階的な移行に伴い、定額部分の支給はすでに対象者がいなくなり終了しています。そのため、これから特別支給の老齢厚生年金を受け取る方は、原則として「報酬比例部分」のみが支給されることになります。
また、これから受給権の発生する男性については、報酬比例部分の対象となる人はいなくなっているため、特別支給の老齢厚生年金を新たに受給するのは要件を満たす女性だけになります。
報酬比例部分部分の計算式と実際の金額目安
特別支給の老齢厚生年金を構成していた「定額部分」は、老齢基礎年金(国民年金)に相当する部分です。その計算方法は、厚生年金の加入月数に基づいています。
しかし、年金制度の改正に伴い、定額部分の支給開始年齢は段階的に引き上げられ、現在では原則として支給対象となる人はいません。昭和29年生まれの女性が最後の支給対象者でした。
そのため、これから特別支給の老齢厚生年金の受給を迎える63歳の女性の場合、この定額部分が加算されることはありません。
年金額を考える上では、次に解説する「報酬比例部分」がすべてであると理解しておきましょう。
報酬比例部分の計算式と具体例
現在、特別支給の老齢厚生年金として受け取れるのは「報酬比例部分」のみです。この金額は、厚生年金に加入していた期間の収入(給与や賞与)と加入月数に基づいて計算されます。
計算式は、賞与からの老齢厚生年金保険料徴収が始まった2003年(平成15年)4月を境に異なります。
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 加入月数
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
年金額は、AとBを合計した金額となります。「平均標準報酬月額」とは加入期間中の給与の平均額、「平均標準報酬額」は給与と賞与を合わせた平均収入額と考えると分かりやすいでしょう。
【例】昭和41年4月1日生まれの女性が、22歳から32歳までの10年間(120ヶ月)会社員として勤務し、その間の平均給与(平均標準報酬月額)が20万円だった場合を考えてみましょう。この方の加入期間はすべて2003年3月以前のため、計算式Aを適用します。
この女性は、64歳から65歳になるまでの1年間、約17万円の特別支給の老齢厚生年金を受け取れる計算になります。
63歳の女性はいくらもらえる?モデルケースで金額を比較
63歳から受け取れる年金額は、これまでの働き方によって大きく異なります。特に、厚生年金への加入期間が受給資格と金額を左右する重要なポイントです。
いくつかのモデルケースを基に、受給できる年金額の目安を比較してみましょう。
専業主婦(厚生年金なし)の場合
一度も会社員や公務員として働いた経験がなく、厚生年金に加入した期間が全くない、あるいは1年未満の専業主婦の場合、特別支給の老齢厚生年金は受給できません。
この制度は、あくまで厚生年金保険の加入期間が1年以上あることが受給の必須条件となっているためです。したがって、生年月日などの他の条件を満たしていても、この条件をクリアできなければ対象外となります。
ただし、63歳から老齢基礎年金(国民年金)を「繰上げ受給」することは可能です。その場合、本来65歳で受け取る額から、繰り上げた月数に応じて減額された金額を生涯受け取ることになります。
パート勤務で厚生年金加入ありの場合
パートタイマーとして働き、厚生年金に1年以上加入していた期間がある女性は、特別支給の老齢厚生年金の受給対象となる可能性があります。年金額は、加入期間中の平均収入(平均標準報酬額)と加入月数によって決まります。
例えば、昭和36年生まれの女性が、パートで10年間(120ヶ月)厚生年金に加入し、その間の平均月収が10万円だったと仮定します。この場合、年金額の概算は以下のようになります。
このケースでは、63歳から65歳になるまで、年間約6万5千円が支給される計算です。パート勤務であっても、厚生年金の加入実績があれば、65歳前の収入の支えとなり得ます。
単身女性・正社員歴が長い場合
正社員として長期間勤務し、相応の収入を得てきた単身女性の場合、特別支給の老齢厚生年金はより大きな金額が期待できます。年金額は現役時代の収入と加入期間に比例するため、その影響が顕著に現れます。
例えば、昭和36年生まれの女性が、22歳から60歳までの38年間(456ヶ月)正社員として勤務し、全期間の平均年収が480万円(平均標準報酬額40万円)だったと仮定します。
計算を簡略化するため、全期間が2003年4月以降の加入として計算すると、年金額の概算は以下のようになります。
このケースでは、63歳から65歳になるまで、年間約100万円、月額にして8万円以上の年金が支給される計算です。これは65歳までの生活を支える上で、非常に大きな助けとなるでしょう。
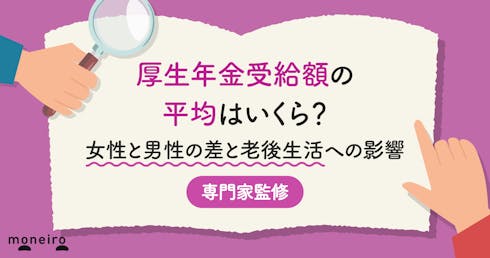
平均受給額の目安と実際の生活費との比較
厚生労働省年金局の調査によると、令和5年度の厚生年金受給権者の平均年金月額は全体で約14.6万円です。ただし、これは国民年金部分を含んだ金額であり、また男女差も大きい点に注意が必要です。
一方で、総務省の2024年(令和6年)の家計調査報告によると、高齢単身無職世帯(65歳以上)の1ヶ月の平均的な消費支出は、約15万円でした。この数字と比較すると、平均的な年金額だけでは生活費を賄うのがやっと、あるいは少し不足する可能性が見えてきます。
特別支給の老齢厚生年金は、あくまで65歳までの「つなぎ」の収入です。63歳から受給できる場合でも、その金額だけで生活が成り立つとは限りません。
この期間の働き方や、それまでに築いた貯蓄をどう活用するかなど、総合的な資金計画を立てておくことが大切です。
(参考:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局)
(参考:家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要)
働きながらもらうとどうなる?在職老齢年金の仕組み
63歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら、会社員として厚生年金に加入して働き続ける場合、「在職老齢年金」という制度が適用されます。
これは、老齢厚生年金の月額と給与・賞与の合計額が一定の基準を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。
収入によって減額されるルール
在職老齢年金制度では、年金が減額されるかどうかの基準となる「支給停止調整額」が定められています。2025年度現在、この金額は51万円です。
具体的には、以下の2つの合計額が51万円を超える場合に、年金が調整(減額)されます。
- 基本月額:特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
- 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額(月給)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12)
合計額が51万円以下であれば、年金は全額支給されます。しかし、51万円を超えた場合は、超えた金額の半分の年金が支給停止されます。
どのくらい働くといくら減る?収入別シミュレーション
在職老齢年金による減額の仕組みを、具体的にシミュレーションしてみましょう。
計算式は以下のとおりです。
ケース1:年金が減額される
- 年金の基本月額:10万円
- 給与・賞与の月額(総報酬月額相当額):45万円
この場合、合計額は55万円となり、基準額51万円を4万円超過します。
支給される年金額:10万円 - 2万円 = 8万円
毎月2万円の老齢厚生年金が支給停止されます。
ケース2:年金が全額支給停止になる
- 年金の基本月額:15万円
- 給与・賞与の月額(総報酬月額相当額):70万円
合計額は85万円となり、基準額51万円を34万円超過します。
調整額(17万円)が基本月額(15万円)を上回るため、この場合、老齢厚生年金は全額支給停止となります。
このように、収入によっては老齢厚生年金が全く受け取れない状況も起こり得ます。
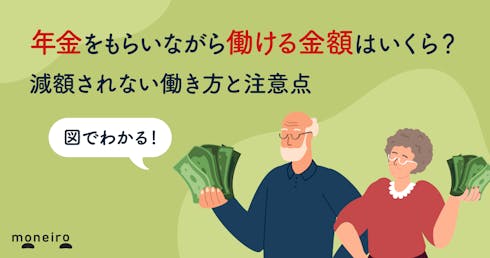
年金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶専門家に無料相談:老後のお金の不安はプロにお任せ
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
63歳からもらうと損?65歳まで待つとどう違う?
63歳から年金を受け取る選択は、特別支給の老齢厚生年金だけでなく、誰でも選択可能な「繰上げ受給」という方法もあります。
しかし、早く受け取ることは必ずしも得策とは限りません。繰上げ受給のデメリットと、逆に65歳以降に受け取りを遅らせる「繰下げ受給」のメリットを比較し、どちらがご自身のライフプランに適しているか慎重に判断する必要があります。
繰上げ受給の減額率と一生続く影響
老齢年金を65歳より前に受け取る「繰上げ受給」を選ぶと、1ヶ月早めるごとに年金額が0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの人は0.5%)減ります。
例えば63歳から受け取る場合、2年(24か月)早まるため、年金は9.6%減額されます。
注意すべきなのは、この減額が一生続く点です。65歳になっても元の金額には戻らず、一度手続きすると取り消しや変更もできません。
また、繰上げ受給をすると国民年金の任意加入ができなくなったり、障害基礎年金(事後重症請求の場合)を受け取れなくなったりするなど、公的保障にも制限がかかります。
目先の収入だけでなく、将来を見据えた慎重な判断が必要です。
(参考:年金の繰上げ受給|日本年金機構)
繰下げ受給の増額率と長生きリスク
「繰下げ受給」とは、65歳で年金を受け取らずに、66歳以降へ受給開始を遅らせることを指します。1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増え、その増額は一生続きます。
最大で75歳まで繰り下げることができ、その場合は年金額が84%増となります。健康で長く働ける人や、65歳以降も収入がある人にとっては、将来の年金を増やす有効な方法です。長生きするほど、総受給額は65歳から受け取るより多くなります。
一方で、受給開始後まもなく亡くなった場合などは、結果的に受け取る総額が少なくなる可能性があります。健康状態や生活設計を踏まえ、慎重に判断することが大切です。
損益分岐点は何歳?ライフプラン別の判断例
年金の受給開始時期を考える上で重要な指標となるのが「損益分岐点」です。これは、繰上げ受給や繰下げ受給をした場合の累計受給額が、65歳から受給を開始した場合の累計額を上回る(または下回る)年齢を指します。
例えば、63歳から繰上げ受給(9.6%減額)を開始した場合、65歳から受給を開始した人に比べて累計受給額で損をしないためには、約84歳より前に亡くなる必要があります。逆に言えば、84歳以上長生きすると、65歳から受給した方が総額は多くなります。
一方、70歳まで繰下げ受給(42%増額)をした場合、損益分岐点は約82歳です。82歳以上長生きすれば、65歳から受給するよりも総額が多くなります。
最終的には、ご自身の健康状態、貯蓄額、働き方の意向など、総合的なライフプランに基づいて判断することが最も重要です。
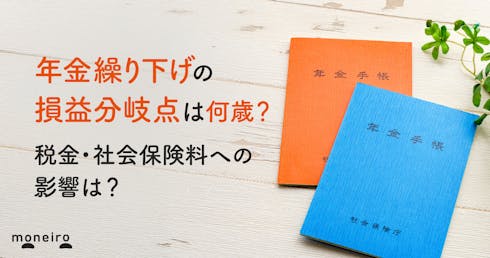
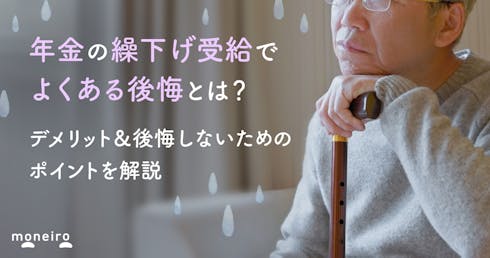
ライフプラン別の判断例
- 健康に不安があり、長生きできるか心配な場合:65歳になるのを待たずに早めに受け取る「繰上げ受給」も一つの選択肢です
- 65歳以降も働く予定で、当面の生活資金に余裕がある場合:将来の受給額を増やす「繰下げ受給」を検討する価値があります
- 貯蓄が少なく、60歳で退職後の収入が途絶える場合:「特別支給の老齢厚生年金」や「繰上げ受給」で当面の生活費を確保することも考えられます
63歳からの年金を上手に活かすための3つの見直し
63歳からの年金受給は、老後生活のスタートラインです。しかし、公的年金だけで全ての生活費を賄うのは難しい時代になっています。
年金収入を一つの柱としながらも、「働き方」や「資産運用」を組み合わせ、総合的に家計を支える視点を持つことが、豊かなセカンドライフを送るための鍵となります。
「年金+働き方+資産運用」で生活を支える考え方
60代以降の生活設計は、「年金・働き方・資産運用」の3つの要素をバランス良く組み合わせることが重要です。
まず、公的年金は終身で受け取れる安定した収入源であり、生活の土台となります。ご自身の年金見込み額を正確に把握することが老後計画の第一歩です。
次に、年金だけでは不足する分を補うために、働き方を考えます。在職老齢年金の仕組みを理解し、年金が減額されない範囲で働く、あるいは専門性を活かして厚生年金に加入しない形で働くなど、多様な選択肢があります。
そして、これまでの貯蓄をただ取り崩すだけでなく、資産運用で増やしながら使うという視点も不可欠です。手元にある資産の一部を投資に回すことで資産寿命を延ばすことが可能になります。
この3つを一体で考えることで、より安心で豊かな老後生活を実現できるでしょう。

まとめ
63歳から年金をもらえるかどうかは、生年月日・加入期間・働き方によって大きく変わります。
特別支給の老齢厚生年金や繰上げ受給を活用すれば、65歳を待たずに年金を受け取ることも可能ですが、減額率や働き方とのバランスには注意が必要です。
「早くもらうか」「待って増やすか」は、寿命・健康・家計状況・仕事の有無など、人それぞれの答えがあります。大切なのは、「なんとなく」で決めずに、制度を理解したうえでライフプランに合った選択をすることです。
老後の安心は、年金だけではなく、貯蓄や運用、働き方の組み合わせで支える時代です。まずは、自分がいつ・いくら・どう受け取るのが最適かを確認し、老後資金の見直しを始めてみましょう。
年金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶専門家に無料相談:老後のお金の不安はプロにお任せ
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。