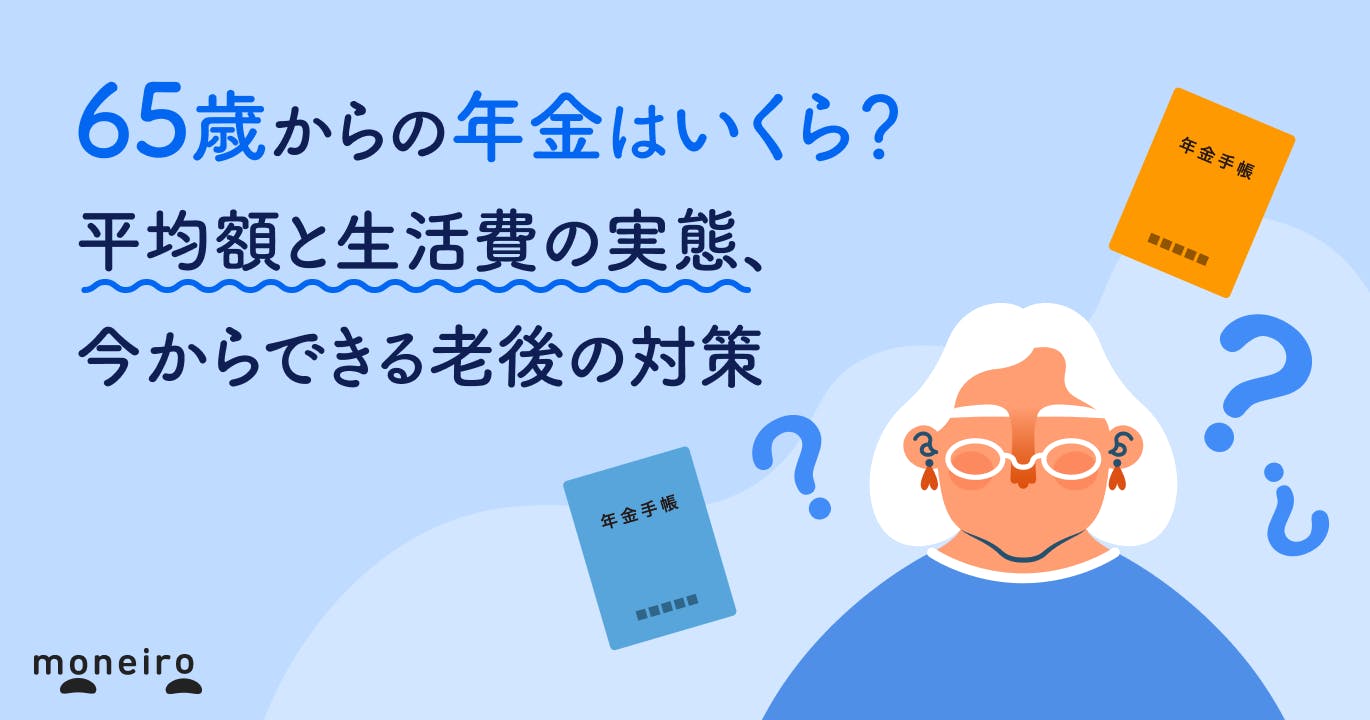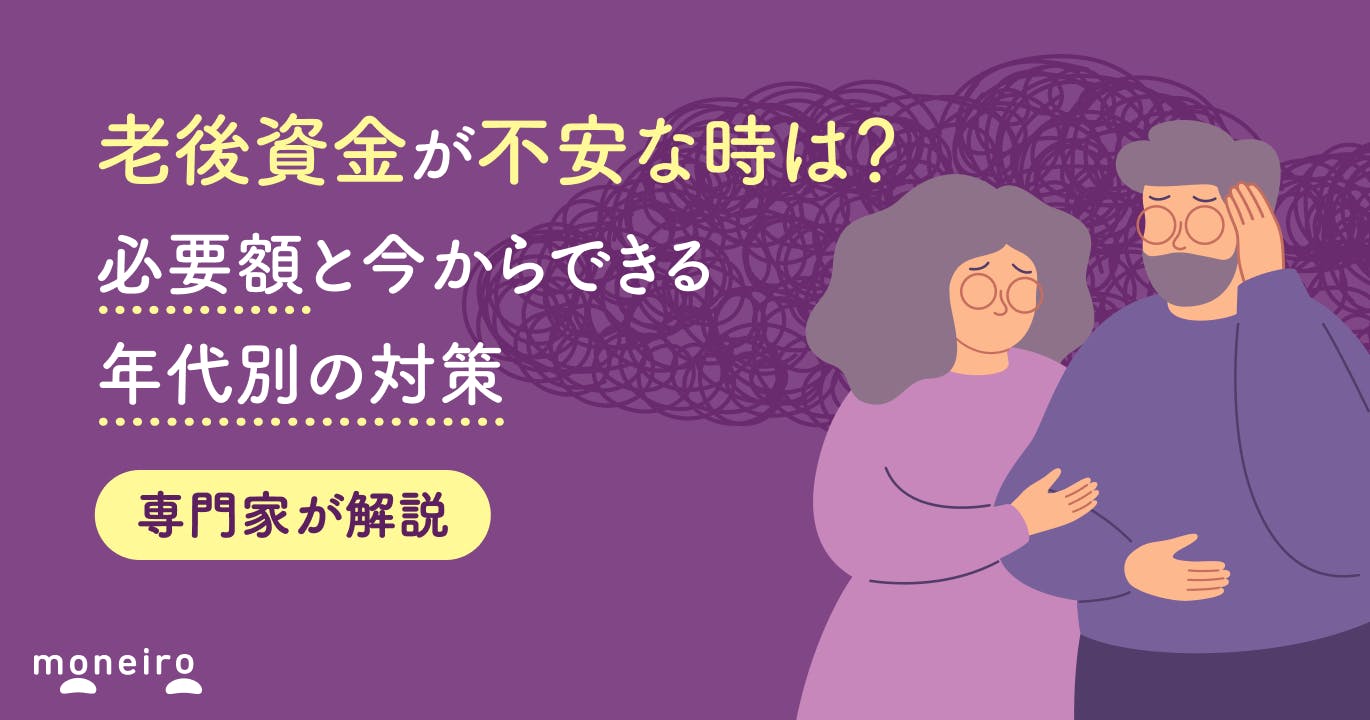65歳からの年金はいくら?平均額と生活費の実態、今からできる老後の対策を徹底解説
»年金で老後は暮らせる?簡単診断はこちら
65歳から年金を受け取ると、実際に毎月いくらになるのでしょうか。
厚生労働省や日本年金機構の公表データによれば、老齢基礎年金の満額は月額約6.9万円(令和7年4月分からの年金額)、厚生年金を含めた平均受給額は単身で約14万円、夫婦で約23万円程度とされています。ただし、働き方や加入期間によって金額は大きく異なります。
本記事では、最新の年金額データをもとに、65歳から受け取れる年金の平均額や男女差、夫婦世帯のケースを解説します。さらに、老後の生活費との比較で不足分を明らかにし、繰下げ受給やiDeCoなどによる上乗せ対策まで、専門家視点でわかりやすくまとめます。
- 65歳から受け取れる年金の基本構造
- 最新の平均受給額と老後の生活費との比較
- 自分の年金額を確認する方法と増やすための工夫
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
65歳から受け取れる年金の基本
65歳から受け取れる公的年金は、全国民共通の「老齢基礎年金」と、会社員などが上乗せで受け取る「老齢厚生年金」の2階建て構造が基本です。
日本の公的年金制度は、働き方や加入状況によって受け取れる年金の種類が異なります。1階部分にあたる老齢基礎年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入する国民年金の給付です。2階部分の老齢厚生年金は、会社員や公務員などが加入する厚生年金から支給されます。
さらに、特定の条件を満たす場合には、配偶者や子がいる場合に加算される「加給年金」なども存在します。
老齢基礎年金の満額(月額約6.9万円:令和7年度)
日本国内に住む20歳から60歳未満のすべての人が加入する国民年金からは、原則65歳から老齢基礎年金が支給されます。保険料の納付済期間などが10年以上あることが受給の条件です。
20歳から60歳までの40年間、保険料をすべて納付した場合に受け取れる満額は、令和7年度(2025年度)で年額83万1700円(昭和31年4月2日以後生まれの方の場合)です。
月額に換算すると約6.9万円となります。
老齢厚生年金の仕組みと受給額の目安
老齢厚生年金は、会社員や公務員などが加入する厚生年金から支給される、老齢基礎年金に上乗せされる2階部分の年金です。国民年金のみに加入している自営業者などと比較して、手厚い保障が受けられます。
また、老齢厚生年金の受給額は、現役時代の収入(正確には標準報酬月額・標準賞与額)と厚生年金への加入期間に応じて決まります。収入が高く、加入期間が長いほど、受け取れる年金額は多くなるのが特徴です。
計算式は複雑ですが、基本的には「平均標準報酬額 × 給付乗率 × 加入月数」で算出される報酬比例部分が中心となります。
例えば、平均年収400万円の人が40年間厚生年金に加入した場合、老齢厚生年金部分だけで年額約88万円が上乗せされ、老齢基礎年金と合わせると合計で年額約171万円(月額約14万円)が受給額の目安となります。
加給年金・振替加算の概要
加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給される制度です。「年金の家族手当」とも呼ばれます。
配偶者が65歳になるまでの期間限定の加算ですが、老後の家計を支える重要な役割を果たします。
配偶者が65歳になり加給年金が終了した後、一定の条件を満たす配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるのが振替加算です。
これは、加給年金の対象であった配偶者が、自身の国民年金加入期間が短い(※)ために老齢基礎年金が少なくなることを補うための制度です。
対象となるのは、昭和41年4月1日以前に生まれた配偶者に限られます。
※第3号被保険者制度が設けられたのは1986年4月からですが、それ以前の専業主婦は強制加入ではなく任意加入でした。そのため、任意加入せずに加入期間の短い専業主婦(または専業主婦だった人)が一定数います
(参考:Q&A|日本年金機構)
65歳からの年金はいくら?最新の平均受給額
年金の受給額は世帯構成や性別、現役時代の働き方によって大きく異なります。例えば、夫婦世帯か単身世帯か、また会社員だったか自営業だったかによって、受給額には差が生じます。
単身世帯の平均年金額
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、65歳以上の受給者の平均受給月額は以下の通りです。
- 国民年金(老齢基礎年金)のみの場合: 5万7700円
- 厚生年金(老齢基礎年金含む)の場合: 14万7360円
国民年金のみの自営業者などであった場合、生活費を年金だけで賄うのは厳しい状況が想定されます。
一方、厚生年金に加入していた会社員などであれば、ある程度の収入が見込めますが、それでも現役時代の収入と比べると大きく減少することを念頭に置く必要があります。
(参考:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局)
夫婦世帯の平均年金額
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータに基づくと、主なパターン別の平均月額は以下のようになります。
夫婦ともに厚生年金に加入している共働き世帯が最も受給額が多くなります。一方で、夫婦ともに国民年金のみの自営業世帯では、受給額が比較的少なくなる傾向にあります。
世帯の働き方の組み合わせが、老後の収入に直接影響を与えることがわかります。
男女差による違い
年金の受給額には男女差があり、特に厚生年金でその差が大きく表れています。令和5年度のデータによると、男性の平均月額は約17万円、女性は約11万円で、およそ6万円の差があります。
この背景には、出産や育児によるキャリアの中断、さらに賃金格差といった要因が影響していると考えられます。
年金額と老後の生活費を比較
多くの世帯で、公的年金収入だけでは老後の生活費を完全に賄うことは難しく、不足分を貯蓄などで補う必要があります。
総務省の家計調査によると、高齢者世帯の平均的な支出は年金収入を上回る傾向にあります。特に、趣味や旅行などを楽しむ「ゆとりのある生活」を送るためには、さらなる資金が必要となります。
年金収入と想定される支出の差額を具体的に把握することで、老後までに準備すべき自己資金額の目標を立てやすくなります。
高齢単身世帯の平均支出
総務省の「家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要」によると、65歳以上の単身無職世帯の消費支出は月平均14万9286円、可処分所得(税金や社会保険料を差し引いた手取り)は12万1469円です。毎月およそ2.8万円の赤字が発生している状況です。
特に住居費や食費、光熱費など、ひとり暮らしでも固定的にかかる支出が大きな負担となっています。
高齢夫婦無職世帯の平均支出
同調査では、65歳以上の夫婦無職世帯の消費支出は月平均25万6521円、可処分所得は22万2462円です。毎月約3.4万円の赤字が生じています。
夫婦二人分の生活費が必要になる一方で、年金収入だけでは十分にカバーできていない実態が浮き彫りになっています。
自分の年金額を確認する方法
老後の生活設計を立てるには、まず自分が将来どのくらい年金を受け取れるのかを把握することが欠かせません。確認方法には大きく3つあります。
- ねんきん定期便:毎年誕生月に届く通知で、これまでの加入実績や将来の年金見込額が記載されています
- ねんきんネット:日本年金機構の公式サイトで、最新の年金記録や見込額のシミュレーションをいつでも確認可能です
- 公的年金シミュレーター:厚生労働省提供のツールで、働き方や受給開始年齢を変えた場合の将来の年金額を簡単に試算できます
まずは上記の方法を活用して現状を把握し、老後資金の不足額や必要な準備を明確にすることが大切です。
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
65歳からの年金を増やすための工夫
公的年金の受給額は、受け取り方や現役時代の工夫次第で増やすことが可能です。特に「繰下げ受給」は、受給開始を遅らせることで年金額を大きく増やせるため、有力な選択肢となります。
また、国民年金の加入期間が短い人向けの制度や、iDeCoといった税制優遇のある私的年金制度を活用することも、老後の収入を厚くするために有効です。
これらの方法を組み合わせることで、より安心して老後を迎えるための準備ができます。
繰下げ受給のメリット・デメリット
繰下げ受給は、年金の受け取り開始を66歳以降75歳までの間に遅らせることで、受給額を増やす制度です。
メリットは、1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増額される点です。例えば70歳まで繰り下げると42%、75歳まで繰り下げると最大で84%も年金額が増え、増額した年金は一生涯受け取れます。
長生きするほど総受給額が多くなるため、健康に自信があり、65歳以降も収入が見込める方には非常に有利な制度です。
一方、デメリットは、繰り下げている期間は年金を受け取れないこと、そして早くに亡くなった場合に総受給額が65歳から受け取り始めるよりも少なくなる可能性があることです。
また、年金額が増えることで税金や社会保険料の負担が増加する点にも注意が必要です。
任意加入制度・付加年金の活用
国民年金の受給額を増やす方法として、任意加入制度と付加年金があります。
任意加入制度は、60歳時点で老齢基礎年金の満額(40年)に満たない場合や、受給資格期間(10年)を満たしていない場合に、60歳から65歳までの間、国民年金保険料を納付できる制度です。
これにより、満額に近づけたり、受給資格を得たりすることができます。
付加年金は、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者が、定額の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めることで、将来の年金額を上乗せできる制度です。
受け取れる付加年金額(年額)は「200円 × 付加保険料納付月数」で計算され、2年以上受け取れば支払った保険料以上の年金を受け取ることができます。
iDeCoやNISAなどを活用した資産運用
公的年金だけでは老後資金が不安な場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)を活用して、自分で「3階部分」の年金や資産を準備することが大切です。
iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税になるなど、税制上のメリットが大きい私的年金制度です。原則60歳まで引き出せないため、着実に老後資金を準備できます。
一方NISAは、年間投資枠内で得られた運用益が非課税になる制度です。iDeCoと異なり掛金の所得控除はありませんが、いつでも自由に資産の引き出しが可能です。老後資金だけでなく、さまざまなライフイベントに備える資金としても活用できます。
ライフプランに合わせて制度を活用することで、公的年金を補う自分年金を効率的に作ることが可能です。
年金以外で確保できる老後の収入源
公的年金は老後の収入の柱ですが、それだけで生活を賄うのが難しい場合、他の収入源を確保することが必要になります。
退職金・企業年金の活用
退職金や企業年金は、公的年金を補完する重要な老後資金です。退職金は、長年の勤務に対する功労報奨的な意味合いを持つ一時金であり、まとまった金額を受け取れるため、住宅ローンの完済やリフォーム費用などに充てることができます。
また、企業年金は、企業が従業員の老後のために設ける私的年金制度です。確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(企業型DC)などがあり、公的年金に上乗せして定期的に収入を得ることができます。
勤務先の制度を確認し、退職金や企業年金がいくら受け取れるのかを把握しておくと良いでしょう。
シニア世代の就労による収入
近年は高年齢者雇用安定法の改正により、企業には70歳までの就業機会確保が努力義務とされるなど、シニア世代が働きやすい環境が整備されつつあります。
働くことで得られる勤労収入は、年金だけでは不足しがちな生活費を補うだけでなく、貯蓄の取り崩しを遅らせる効果もあります。
また、厚生年金に加入して働けば、70歳までに将来の年金額をさらに増やすことも可能です。体力や希望に合わせて、パートタイムや短時間勤務など、多様な働き方を選ぶことができます。
まとめ
65歳から受け取れる年金額は、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の2階建てが基本です。
平均受給額は、国民年金のみで月5万7700円、厚生年金加入者で月14万7360円(令和5年度の調査)ですが、働き方や世帯構成で大きく異なります。
多くの世帯で年金収入だけでは生活費が不足するため、現役時代からの準備が不可欠です。 ご自身のおおまかな年金見込額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。
老後資金を増やすには、繰下げ受給やiDeCo・NISAの活用が有効です。 公的年金への理解を深め、計画的な資産形成を行うことで、安心して老後を迎えましょう。
»年金以外にいくら必要?簡単無料診断はこちら
将来資金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
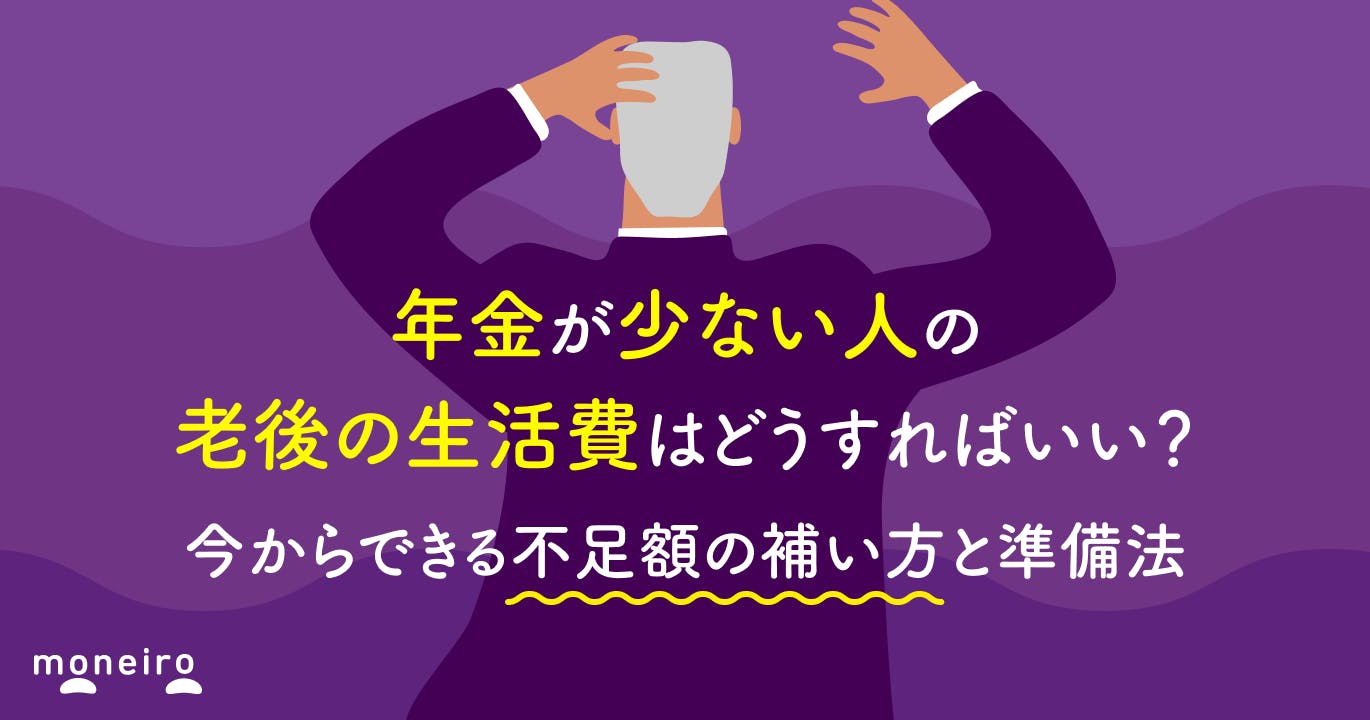
年金が少ない人の老後の生活費はどうすればいい?今からできる不足額の補い方と年代別の準備法
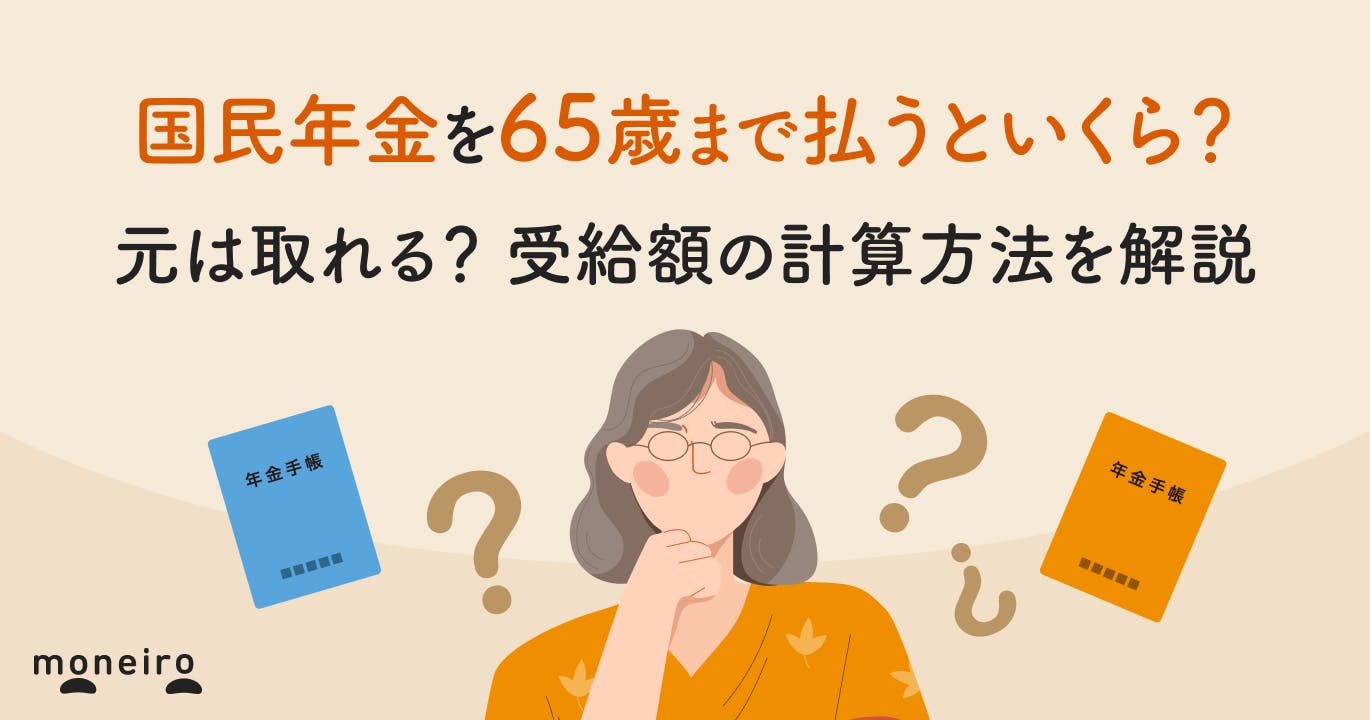
国民年金を65歳まで払うといくら?元は取れる?満額受給額と老後の不足分を徹底解説

老後破産する人の特徴とは?原因や破産しないための対策を解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。