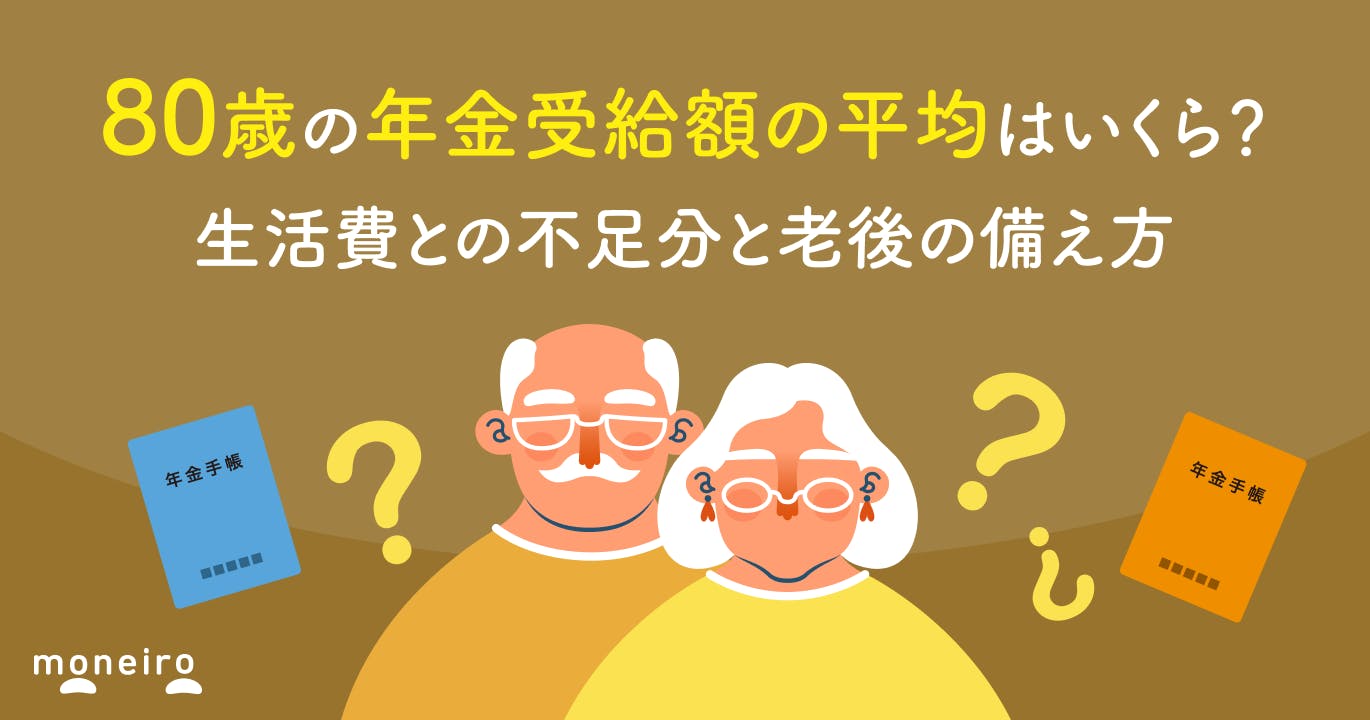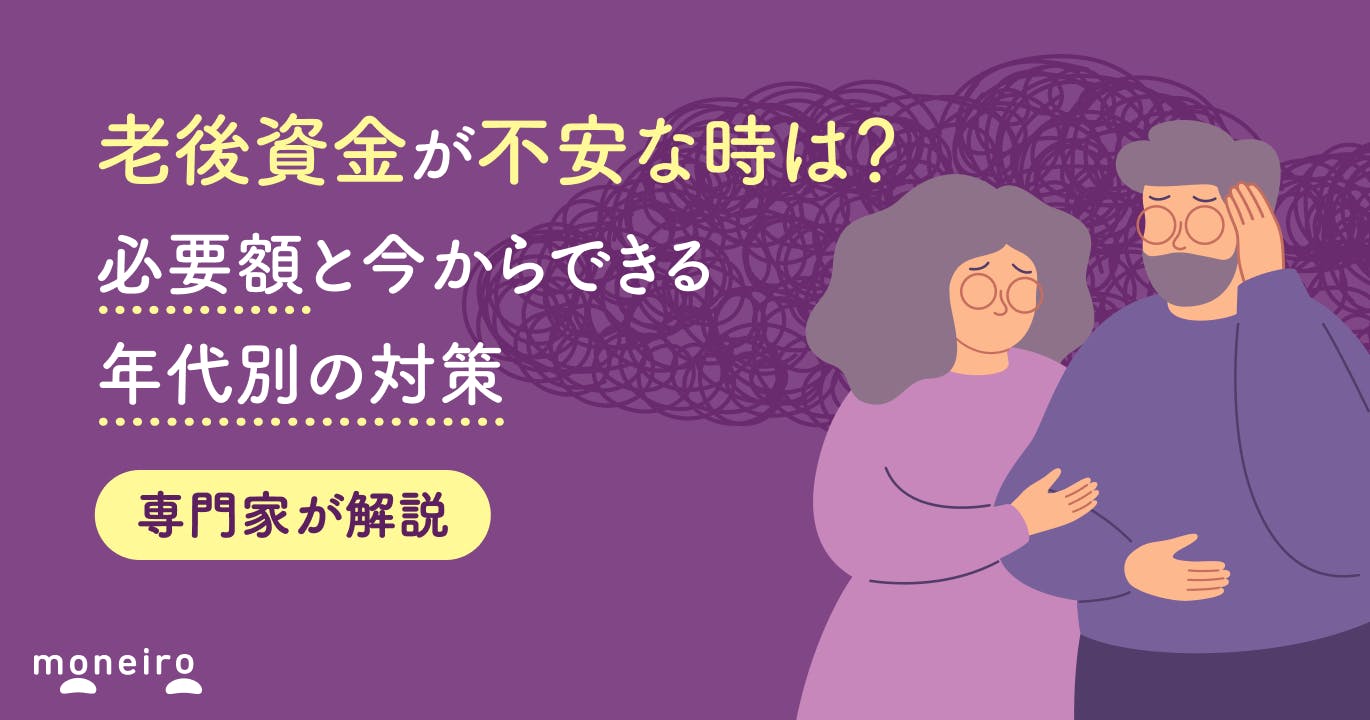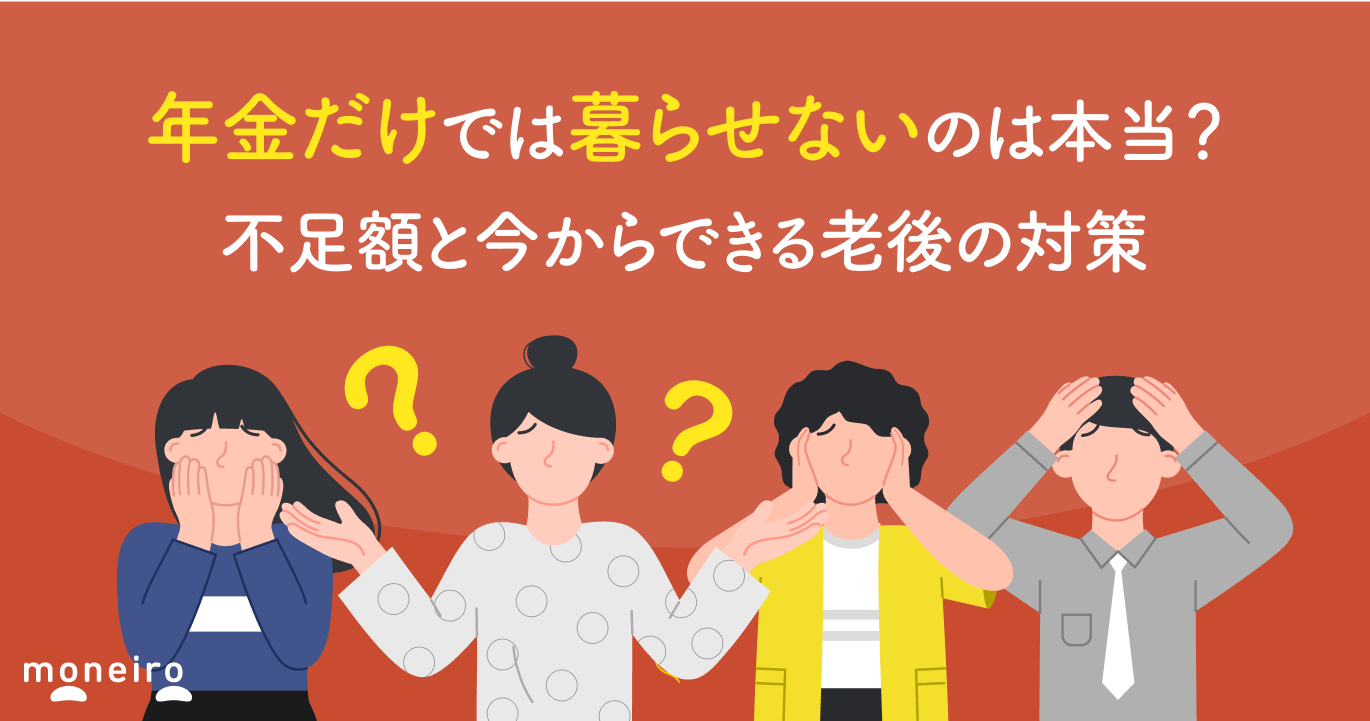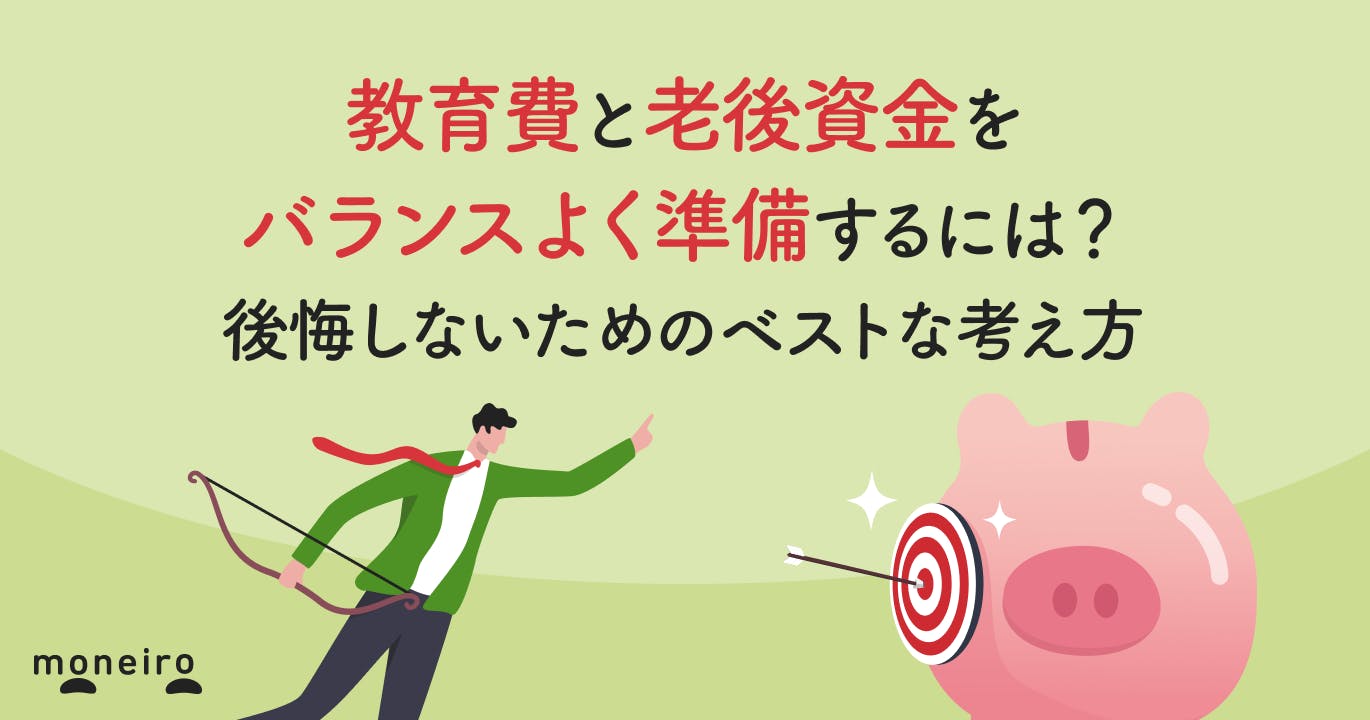80歳の年金受給額の平均はいくら?生活費との不足分と今からできる老後の備え方
»年金だけで暮らせる?将来資金を無料診断
80歳を迎えた時、年金だけで安心して暮らせるのか、と不安に思っている人も多いのではないでしょうか。
本記事では公的データをもとに80歳世代の平均年金受給額を解説します。単身・夫婦、男女別に見る年金額の実態と、医療費や介護費を含めた生活費とのバランスを確認しながら、不足しやすい金額を明らかにします。また、繰下げ受給を選んだ場合に80歳でどのくらい増えるのか、将来世代が知っておきたい備え方についても見ていきます。
親世代の生活を支える立場の方から、自分の老後を見据える50代・60代まで、専門的かつわかりやすく整理しました。
- 単身・夫婦・男女別の平均受給額
- 生活費とのバランスと不足額を補う方法
- 将来の年金見通しと今からできる備え
老後資金が気になるあなたへ
老後を豊かに暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
80歳で受け取れる平均年金額
80歳で受け取れる年金額は、現役時代の働き方や年金制度への加入状況によって大きく異なります。
まずは、単身・夫婦、男女別、そして加入制度による平均受給額の違いを把握し、自身の状況と照らし合わせてみましょう。
平均受給額
単身世帯の場合、受給できる年金は主に国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)です。自営業やフリーランスの場合は国民年金のみ、会社員や公務員の場合は国民年金に加えて厚生年金が支給されます。
2024年の年金受給額に関する情報は以下のとおりです。
2024年(令和5年度)国民年金・厚生年金の概況(受給権者)
(参考:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局)
国民年金の満額は年度により異なり、2025年度の場合は満額で月額6万9308円です。
夫婦世帯では、世帯の合計受給額で生活を考えることが重要です。働き方の組み合わせによって、受給額は大きく変動します。
上記の2024年(令和5年度)国民年金・厚生年金の概況(受給権者)のデータに基づくと、主なパターン別の平均月額は以下のようになります。
例えば、夫が会社員で妻が専業主婦だった世帯では、合計で月額20万円程度が目安です。
一方で、夫婦ともに会社員として働いていた共働き世帯の場合、合計で月額29万円程度と、受給額は高くなる傾向にあります。
夫婦ともに自営業だった場合は、国民年金のみの受給となるため、合計で月額約11万円程度が目安です。
80歳の生活費と年金のバランス
年金だけで生活できるかどうかを判断するには、家計の支出状況を把握することが不可欠です。
生命保険文化センターが実施した「生活保障に関する調査(2022年度)」によると、夫婦2人で老後に必要となる生活費は、最低限で平均23.2万円という結果が出ています。
この金額を年金の平均受給額と比較すると、夫が会社員で妻が専業主婦だった世帯の年金受給額(約22万円)では約5.2万円赤字となります。
また、夫婦ともに自営業だった世帯の平均(約12万円)では、毎月10万円以上の不足が生じる計算になります。
さらに、同調査ではゆとりのある老後生活を送るためには、月額で約37.9万円が必要というデータもあります。この水準になると、夫婦共働きで厚生年金を受給していた世帯(平均約27万円)であっても、毎月10万円程度の不足が見込まれます。
これらのデータから、多くの世帯において、公的年金収入だけで生活を維持するのは容易ではなく、現役時代からの計画的な貯蓄や資産形成が極めて重要であることがわかります。
老後資金が気になるあなたへ
老後を豊かに暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
不足を補うための代表的な手段
年金収入だけでは生活費が不足する場合、その差額を補うための手段をあらかじめ準備しておくことが重要です。
代表的な方法としては、現役時代に築いた貯蓄を取り崩すことが挙げられますが、それ以外にもさまざまな選択肢があります。
公的年金に上乗せする形で老後資金を準備する制度として、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や「国民年金基金」があります。
iDeCo・国民年金基金
iDeCoは、自分で掛金を設定し、運用商品を選んで資産を形成する私的年金制度です。掛金が全額所得控除の対象になるなど、税制上の優遇措置が大きな魅力です。
また、国民年金基金は、自営業者など国民年金の第1号被保険者が、老齢基礎年金に上乗せして加入できる制度です。
NISA
税制優遇を受けながら資産運用を行う方法として「NISA」も有効です。特に「つみたて投資枠」は、長期・積立・分散投資に適した制度設計となっており、老後資金を着実に準備する手段として注目されています。
これらの制度をライフプランに合わせて活用し、公的年金だけではない、複数の収入の柱を築いておくことが、安心して80歳代を迎えるための鍵となります。
70歳・75歳まで繰下げた場合の80歳時点の年金額
人生100年時代において、長生きすること(長寿リスク)に備える資金計画は不可欠です。その有効な手段の一つが、公的年金の「繰下げ受給」です。
受給開始を遅らせることで年金受給額を増やせるこの制度は、長生きするほど有利になります。
繰下げ受給の具体的な効果と、選択する上での注意点を解説します。
繰下げ受給した場合のシミュレーション
年金の繰下げ受給は、受給開始を1ヶ月遅らせるごとに受給額が0.7%ずつ増額される仕組みです。この増額率は生涯にわたって適用されます。受給開始は66歳から最大で75歳まで遅らせることが可能です。
仮に、65歳から月額15万円の年金を受け取れる人が繰下げ受給を選択した場合、80歳時点での月額年金額は以下のようになります。
80歳時点の月額:15万円×1.42 = 21.3万円
80歳時点の月額:15万円×1.84=27.6万円
75歳まで繰り下げると、本来の受給額の2倍近い金額を生涯受け取れることになり、長生きした場合の経済的な安定に大きく寄与します。
長生きした場合に繰下げ受給が有利になるケース
繰下げ受給が本当に有利になるかどうかは、65歳から受給を開始した場合との「損益分岐年齢」を考えることで判断できます。
繰下げ受給で増額された年金の累計受給額が、65歳から受給を開始した場合の累計額を上回る年齢のことです。
一般的に、70歳まで繰り下げた場合の損益分岐年齢は81歳頃、75歳まで繰り下げた場合は86歳頃とされています。
つまり、この年齢よりも長生きすれば、繰下げ受給を選択した方が生涯で受け取る年金の総額は多くなります。
自身の健康状態、そして65歳から受給開始までの生活資金をどう確保するかを総合的に考慮し、繰下げ受給を検討することが重要です。
デメリットや注意点(受給開始前に亡くなった場合など)
繰下げ受給は長生きした場合のメリットが大きい一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。
最も大きなリスクは、年金受給開始後すぐに亡くなってしまうケースです。この場合、受給期間が短くなるため総受給額は65歳受給開始した場合と比べて大きく減少します。
また、税金や社会保険料への影響も考慮が必要です。年金額が増えると、それに伴い所得税や住民税、国民健康保険料や介護保険料の負担も増加する可能性があります。額面上の年金額は増えても、手取り額の増加はそれほど大きくならない場合があるため注意が必要です。
さらに、厚生年金に長期間加入している人に一定要件を満たす配偶者がいる場合に支給される「加給年金」は、繰下げ待機期間中は支給が停止されます。加給年金は金額が大きいため、対象となる方は特に慎重な判断が求められます。
これらのデメリットを理解した上で、自身のライフプランに合った選択をすることが大切です。
親が80歳の時に備えておきたいこと
自分の老後だけでなく、親が80歳を迎えるにあたり、子世代として準備しておくべきこともあります。
特に介護の問題は、経済的にも精神的にも大きな負担となり得ます。事前に知識を得て、家族で話し合っておくことが、いざという時の助けになります。
介護費用や施設入居費の目安
生命保険文化センターの「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、介護費用(月額)の平均は9.0万円でした。
また、介護費用は、在宅で介護サービスを利用するのか、あるいは老人ホームなどの施設に入居するのかによって大きく異なります。
介護費用月額
(参考:2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査|生命保険文化センター)
在宅介護の場合、住宅改修や介護用品の購入などの初期費用に加え、介護保険サービスを利用した際の自己負担分が月々の費用としてかかります。
一方、施設に入居する場合は、入居時に支払う「入居一時金」と、毎月の「月額利用料」が必要です。施設の種類や立地、提供されるサービス内容によって費用はさまざまですが、有料老人ホームなどでは高額になるケースも少なくありません。
親の貯蓄や年金収入でこれらの費用を賄えるのか、不足する場合は誰がどのように負担
するのかを、親子間で事前に話し合っておくことが、将来のトラブルを避けるために不可欠です。
(参考:2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査|生命保険文化センター)
親の年金が不足する時、子世代の支援方法
親の年金収入だけでは生活費や介護費をまかなえない場合、子ども世代による支援が必要になることがあります。
金銭面では、毎月一定額を仕送りする方法や、医療費・介護施設費などの発生時に都度負担する方法が考えられます。支援の金額や分担方法については、兄弟姉妹がいる場合も含め、家族間でしっかり話し合い合意しておくことが大切です。
一方で、買い物や通院の付き添い、身の回りの世話といった生活サポートも重要な支援です。遠方に住んでいる場合は、定期的な連絡や訪問に加え、配食サービスや見守りサービスの利用を検討するのも有効です。
仕送り・生活援助の税制上の扱い
親へ金銭的な支援をする際には、税金の仕組みを理解しておくと安心です。
原則として個人間で財産を渡すと贈与税の対象になりますが、親子間の仕送りで生活費や教育費など「通常必要と認められる範囲」であれば、贈与税はかかりません。
ただし、仕送りされたお金を親が貯蓄や投資に回した場合は、贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
さらに、親の年収など一定の条件を満たせば、親を税法上の「扶養親族」とすることで、自身の所得税や住民税を軽減できる「扶養控除」を受けられる場合があります。
同居していなくても、生活費の援助を継続している事実があれば対象となることがあります。
具体的な要件や有利な支援方法については、税務署や税理士などの専門家へ確認することをおすすめします。
年金制度の今後の課題と見直し動向
日本の公的年金は、現役世代の保険料で高齢者を支える「賦課方式」で運営されています。しかし、少子高齢化により支える人が減り、受け取る人が増えるという課題を抱えています。
そこで導入されたのが「マクロ経済スライド」です。物価や賃金が上がっても年金額の伸びを抑えることで、年金財政の安定を図る仕組みです。
ただし、その結果として将来の年金の実質的な価値が目減りする可能性があります。今後も制度改正が進むと見られるため、公的年金に加えて、自助による資産形成がより重要になっています。
まとめ
80歳時点の年金額は、働き方や性別によって大きく差があり、年金だけで生活を支えるのは難しいのが実情です。
繰下げ受給は長寿への備えとして有効ですが、デメリットも踏まえた判断が欠かせません。将来世代にとっては、公的年金に加えて、iDeCoや新NISAなどを活用した自助努力が重要になります。
まずは「ねんきんネット」で自分の年金見込額を確認し、具体的な老後資金計画を立てることが安心への第一歩です。計画的な資産形成を進め、80代を自分らしく過ごせる備えを始めましょう。
»年金だけで暮らせるか、簡単無料診断でチェック
老後資金が気になるあなたへ
老後を豊かに暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。