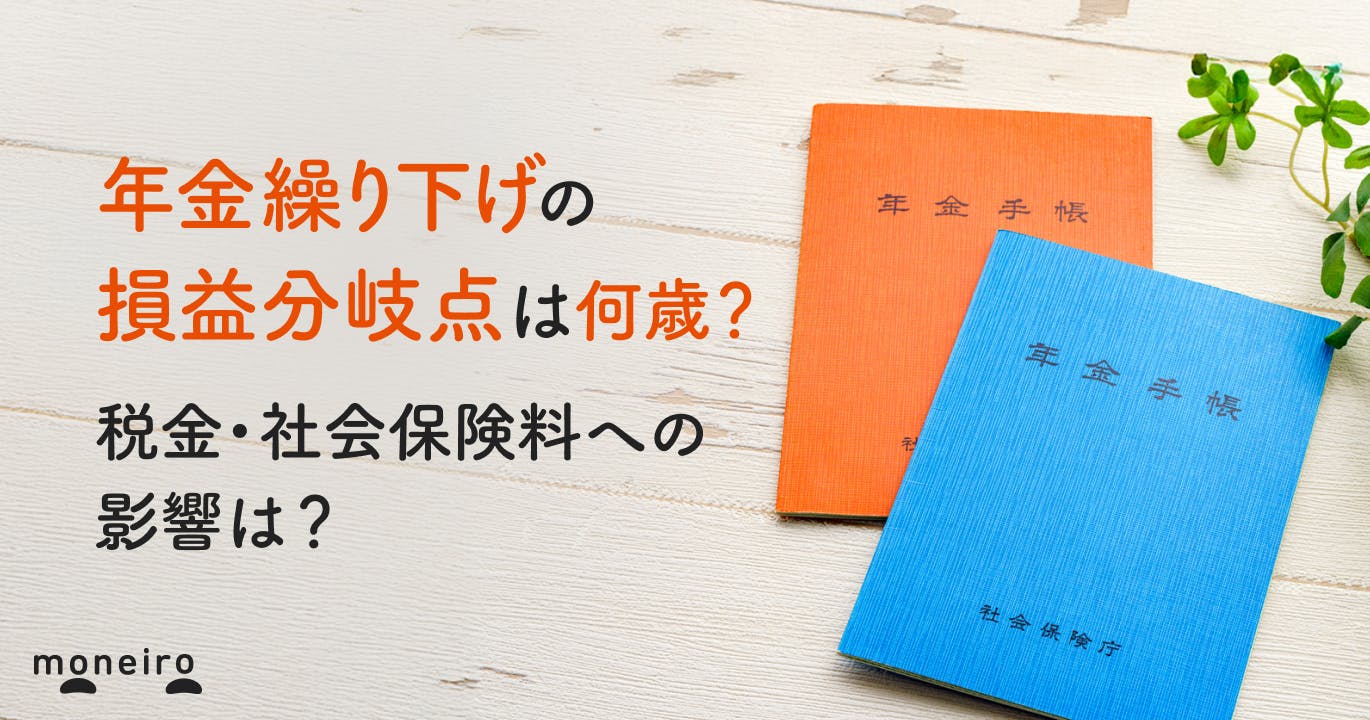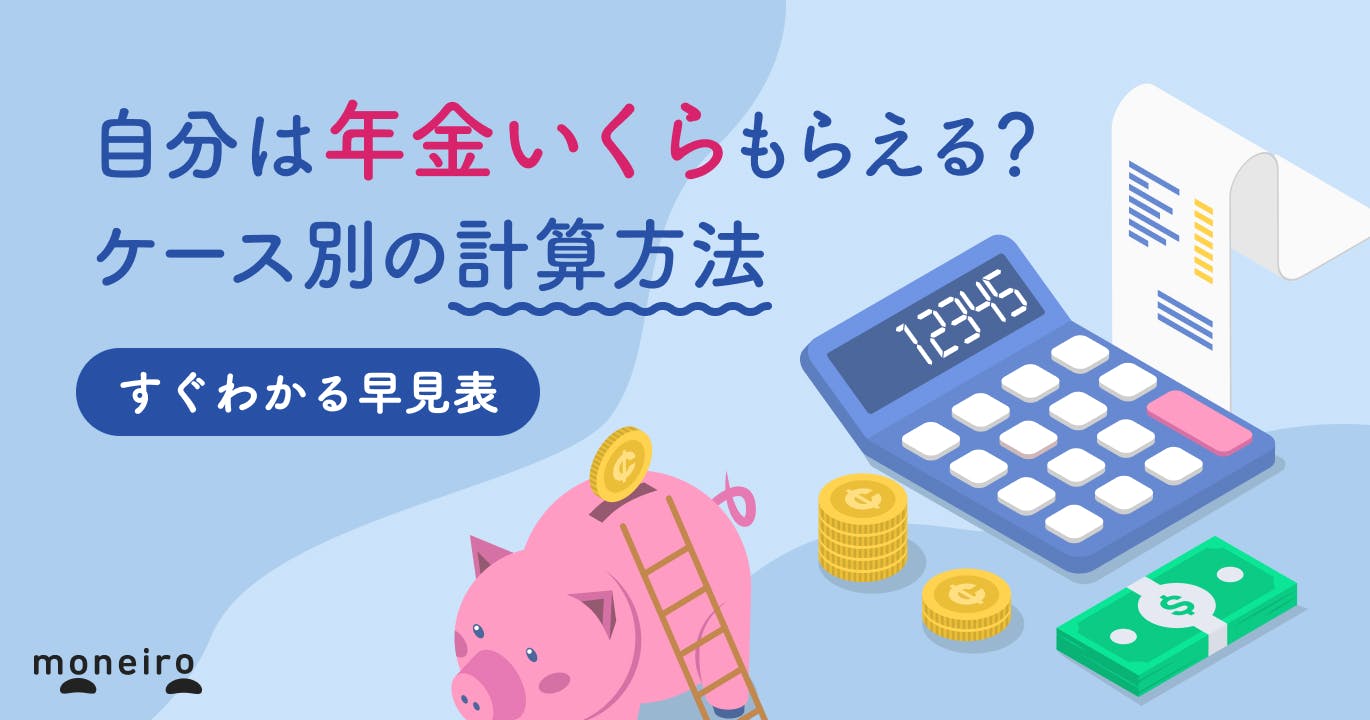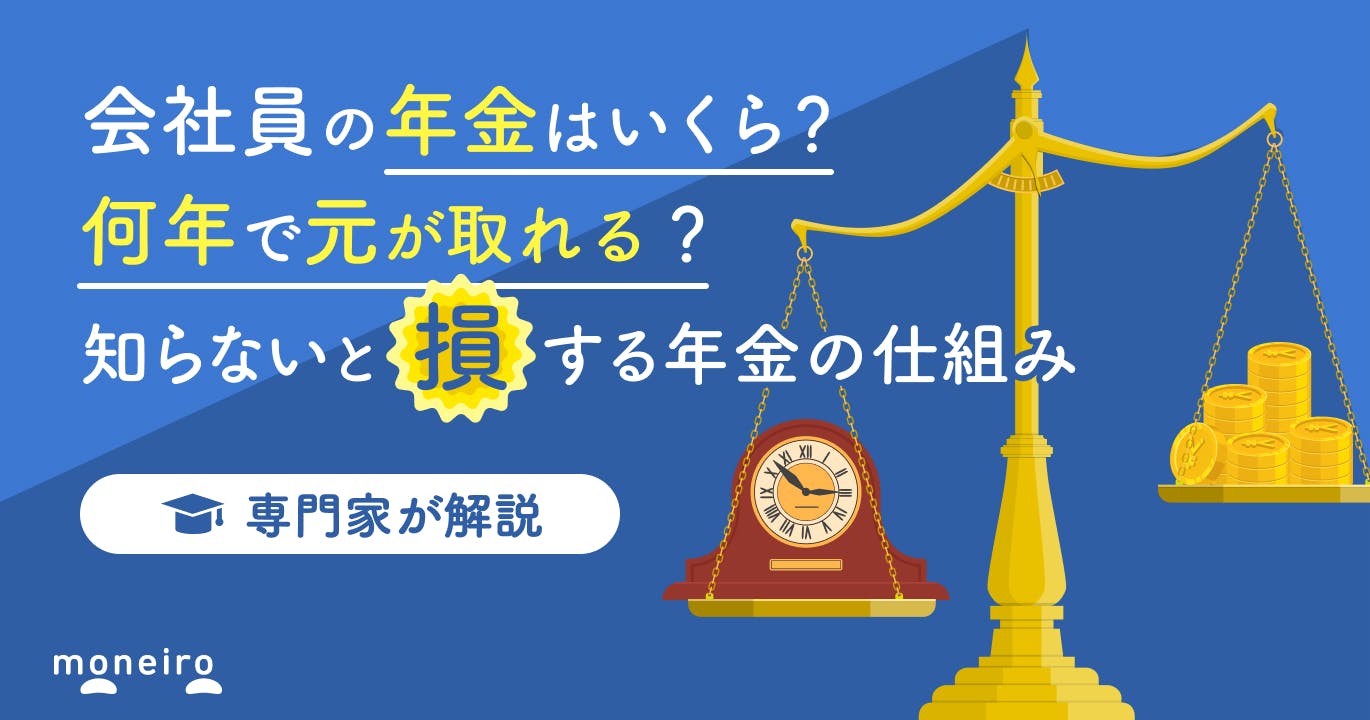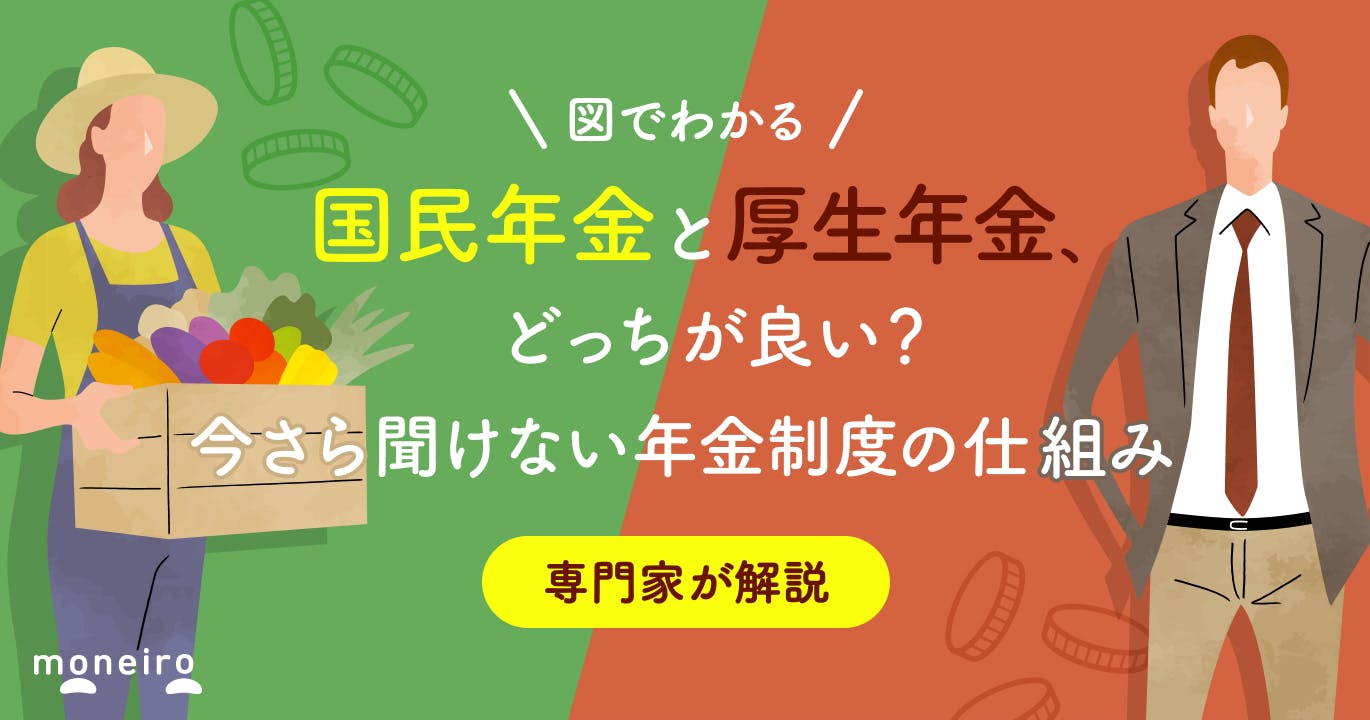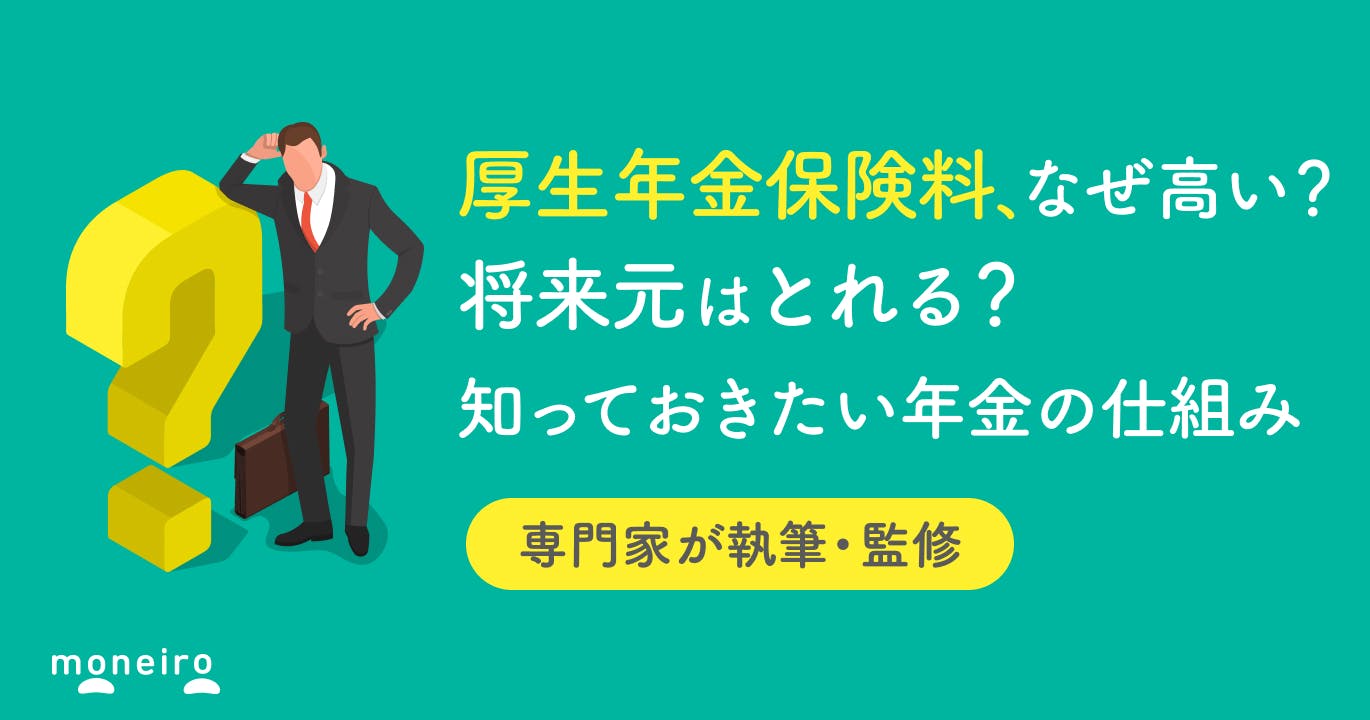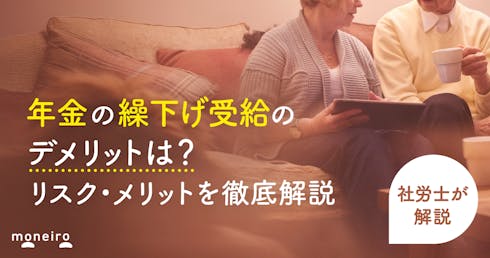
年金繰下げの損益分岐点は何歳?税金・社会保険料増のデメリットも解説
»年金以外でいくら必要?無料診断はこちら
公的年金は、老後生活を支える収入源です。公的年金の繰下げ受給を選択すると、受給額を増やせるメリットがあります。
しかし、受給できない期間が発生するため、「何歳まで生きれば得になるのか?」という損益分岐点を知りたい方もいるのではないでしょうか。
老後生活における経済的な安心を得るためには、自身のライフプランに適したタイミングで、年金の受給を開始する必要があります。この記事では、繰下げ受給の損益分岐点や受給するタイミングの考え方などを解説します。
- 長生きリスクに備えるために、繰下げ受給は有効な対策となる
- 70歳から繰下げ受給をした場合の損益分岐点は81歳11カ月、75歳の場合は86歳11カ月
- 税金や社会保険料も増えるため、増額分をまるまる受け取れるわけではない
老後資金が気になるあなたへ
老後の不安をなくすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
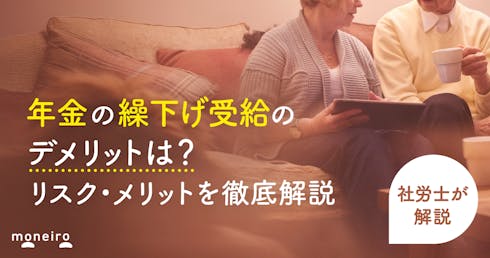

年金の繰下げ受給とは?制度の基本と仕組み
年金の繰下げ受給とは、年金の受け取り開始時期を66歳以降に繰り下げることを指します。自分自身の寿命よりも「資産の寿命」が先に尽きてしまうリスクを軽減するうえで、繰下げ受給は有効な対策です。まずは、年金受給の選択肢とそれぞれの特徴について解説します。
年金受給の3つの選択肢
年金は65歳を基準として、3つの受給方法があります。それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
1.通常受給
通常受給とは、65歳から年金を受給することを指します。現行制度において、年金を受け取る基準となる年齢は65歳であり、65歳に到達する3ヶ月前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
64歳以前に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する人は、受給権発生の3カ月前に届きます。
通常受給をするには、届いた請求書に必要事項を記載したうえで、受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金事務所へ提出します。一定の要件を満たしている方は、電子申請も可能です。
また、65歳より前に特別支給の老齢厚生年金を受給している人には、65歳の誕生月に日本年金機構より「年金請求書(はがき型)」が送付されます。通常受給するには、はがきに氏名や住所などを記載して返信します。
2.繰上げ受給
繰上げ受給とは、60歳から65歳になるまでの間に年金を受給することです。65歳よりも早いタイミングで年金を受給できますが、以下のように繰上げ受給の請求をした年齢に応じて減額(1カ月あたり0.4%または0.5%)され、減額された金額が一生涯続きます。
【昭和37年4月1日以前生まれの方(1カ月あたりの減額率は0.5%)】
【昭和37年4月2日以降生まれの方(1カ月あたりの減額率は0.4%)】
老齢年金を繰上げ請求した後に、請求の取り消しはできません。繰上げ請求の手続きを行った時点で、減額率が決まります。
繰上げ受給の申請手続きは、繰上げ受給を希望する時期に「年金請求書」と「繰上げ請求書」を、年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。
原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は、同時に繰上げ請求をする必要がある点に留意しましょう。
3.繰下げ受給
繰下げ受給とは、66歳以後75歳までの間に年金を受給開始することです。繰り下げた期間に応じて、以下のように年金額が増額(1カ月あたり0.7%)されます。
増額された年金額は一生涯変わらないため、「できるだけ受給額を増やしたい」という方は、繰下げ受給を検討するとよいでしょう。
繰り下げている期間は年金を受給できません。そのため、生活するために働いて収入を得たり生活費として取り崩すための資産を用意したりする必要があります。
老後資金が気になるあなたへ
老後の不安をなくすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
繰下げ受給の対象となる年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げることができます。「老齢基礎年金を繰り下げ、老齢厚生年金は65歳から受給する(あるいはその逆)」という対応が可能です。
ただし、老齢厚生年金に関しては、65歳以降に在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象外です。65歳以降になっても働く予定の方は、注意しましょう。
また、年下の配偶者がいるときに支給される「加給年金額」や、加給年金の支給終了後に配偶者の老齢基礎年金に上乗せされる「振替加算額」も、増額の対象外です。
年金繰下げ受給の「損益分岐点」とは?
年金には繰上げ受給による減額、繰下げ受給による増額という仕組みがあるため、「何歳から受け取るのが得なのか」という議論がしばしば起こります。
そこで、具体的に繰下げ受給をしたときの「損益分岐点」は何歳なのかを見ていきましょう。
年金における損益分岐点の考え方
繰上げ受給をすると、65歳よりも早いタイミングから年金を受け取れる一方で、減額された年金額が一生涯続きます。通常受給または繰下げ受給をしたときと比較すると、長生きをするほど損をしてしまいます。
一方、繰下げ受給をすると、受け取るタイミングは遅くなる一方で、増額された年金額が一生涯続きます。そのため、通常受給または繰上げ受給をした場合に対し、どこかのタイミングで繰下げ受給をしたときの総受給額が逆転することになります。
長寿化が進んでおり、何歳まで生きるかわからない点を考えると、繰下げ受給を選択したほうが得をする可能性も十分に考えられます。
繰下げ期間別の損益分岐点は何歳?
年金を何歳から受け取るのが得なのかは、寿命を予測できない以上、事前に知ることはできません。
しかし、「何歳まで生きれば得をする」というイメージを持っておくと、より自身の老後生活に適した受給の選択ができるでしょう。そこで、以下4つのパターンを比較し、損益分岐点を図表化しました。
- 60歳から繰上げ受給したとき
- 65歳から通常受給したとき
- 70歳から繰下げ受給したとき
- 75歳から繰下げ受給したとき
65歳での通常受給開始と比較したとき、それぞれの損益分岐点は以下のようにまとめられます。
- 60歳から繰上げ受給した場合、80歳10カ月より長く生きると損をする
- 70歳から繰下げ受給を開始した場合、81歳11カ月より長く生きると得をする
- 75歳から繰下げ受給を開始した場合、86歳11カ月より長く生きると得をする
厚生労働省の「令和5年簡易生命表」によると、男性の平均寿命は81.09年、女性の平均寿命は87.14年となっています。
一方で、65歳時点での平均余命は、男性が19.52年、女性が24.38年となっています。つまり、65歳まで生きた男性は平均84歳まで、女性なら平均89歳まで生きるという統計データが出ています。いずれのデータでも女性のほうが長生きする可能性が高いことが示されています。
「平均寿命」が、ある年に生まれた人が平均して何年生きるかを示す推定値で、「0歳時点での期待寿命」であるのに対し、「平均余命」は、ある年齢に達した人が「あと何年生きると期待されるか」を示します。年金受給の検討においては、平均余命を参考にしたほうが、繰下げ受給などの判断をより適切に行える可能性があります。
繰上げ受給・繰下げ受給の利用状況
実際に年金を受給している方々は、どの程度の割合で繰上げまたは繰下げ受給を選択しているのでしょうか。厚生労働省の「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の繰上げ・繰下げ受給の割合は以下のとおりです。
このように、繰下げ受給を選択する方の割合は、かなり低いことがわかります。
「特別支給の老齢厚生年金」は繰り下げできない
なお、「特別支給の老齢厚生年金」は繰り下げできません。同年金の受給者は、65歳に到達した際に、その時点から受け取る資格が発生する「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」については繰下げ受給を選択することができます。
特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が65歳に引き上げられたことを受け、受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたものです。対象者は65歳より前から年金を受給することになります。
年金繰下げ受給による税金・社会保険料への影響
年金の繰下げ受給を選択すると、生涯の総支給額が増えるメリットがあります。しかし、課税所得が増えることにより税金や社会保険料も増えることになるため、しっかり確認しておきましょう。
税金への影響
公的年金は、所得税法上「雑所得」に分類されます。雑所得は他の所得と合算して総所得金額を計算するため、年金額が増えるほど納付する所得税や住民税は増える点に注意が必要です。
公的年金には課税所得を抑える仕組みとして「公的年金等控除」が適用され、控除しきれなかった分は所得となります。
給与所得や事業所得など他の所得と合算して税額を計算するため、「思ったよりも最終的な手取り額が増えない」という可能性も十分あり得ます。
社会保険料への影響
税金だけでなく、社会保険料へ与える影響も把握しておきましょう。
国民健康保険料
勤務先の健康保険に加入しない方や、就職していない方が加入する公的医療保険が国民健康保険です。国民健康保険料は「均等割額」と「所得割額」で構成されており、所得割額は前年の所得の影響を受けます。
繰下げ受給によって年金の受給額が増加すると、所得が増えます。その結果、国民健康保険料が高くなる点に注意しましょう。
後期高齢者医療保険料
75歳以上の方または65歳以上で一定の障害がある方は、後期高齢者医療保険に加入します。後期高齢者医療保険料も、国民健康保険料と同様に「均等割額」と「所得割額」で構成されています。
つまり、年金の繰下げ受給により所得が増えるほど、保険料も高くなることを認識しておきましょう。
介護保険料
介護保険料は、40歳以上65歳未満の「第二号被保険者」と、65歳以上の「第一号被保険者」に分かれます。介護保険料額は自治体ごとの「基準額」に保険料率を乗じて算出し、前年の所得が多いほど、保険料が高くなる仕組みです。
そのため、繰下げ受給により年金の受給額が増加すると、介護保険料も高くなる可能性があります。
繰上げ受給・繰下げ受給を判断するポイントは?
年金は60歳から75歳までの間であれば、都合がよいタイミングで受給を開始できます。つまり、ある程度の柔軟性があります。
年金・給与収入や平均寿命・平均余命、 健康状態、資産状況などを総合的に鑑みたうえで、自身に適した受給タイミングを探っていきましょう。
平均寿命・平均余命から判断する
年金を繰上げ受給するか繰下げ受給するかの判断において、1つの判断基準となるのが平均寿命・平均余命です。厚生労働省によると、2022年における日本の平均寿命は男性で約81歳、女性で約87歳、また平均余命をもとに考えると男性は平均で約84歳、女性は平均で89歳まで生きることが期待されます。
この平均余命のデータに当てはめると、男性の場合は70歳から、女性は75歳から受給開始したほうが得をする可能性が考えられます。
ただし、平均寿命はあくまで統計上の数字であり、当然ながら寿命には個人差がある点にも留意しましょう。あくまでも参考程度にとどめ、自身の健康状態や資産状況なども加味するべきです。
健康状態で判断する
健康に不安がある場合は、医療費・介護費を工面するために、繰上げ受給が一つの選択肢となります。
現在は健康でも、家系的に短命の傾向がある場合や生活習慣病のリスクが高い場合も、繰上げ受給を検討する余地はあるでしょう。
一方で、健康状態が良好な方や健康意識が高い方は、繰下げ受給を検討してみてもよいかもしれません。長生きする可能性が高いと考えれば、生涯にわたって支給される年金を増やすことで、経済的な安心を得られるでしょう。
健康状態は時間とともに変化します。定期的な健康診断を行い、結果に応じて最適な判断をしていきましょう。
経済状態で判断する
仕事をリタイアしたあとに十分な貯蓄がない場合は、早めに受給開始する選択肢があります。生活費を工面するために安定した収入が必要な場合は、減額を受け入れてでも繰上げ受給をするとよいでしょう。
生活費以外にも、医療費や介護費のような資金が必要になった場合も、繰上げ受給は有力な選択肢です。
一方で、経済的に余裕がある場合は繰下げ受給を検討する手もあります。退職金や企業年金で当面の生活費を工面できる場合や、不動産所得や配当所得などの収入がある場合も、年金を繰下げても問題ないケースが考えられます。
不動産所得や配当所得などの収入や資産が十分にある場合は、逆に繰上げ受給をするという選択肢も出てきます。将来の受給額を増やす必要がなく、むしろ「比較的身体が健康なうちに使えるお金を増やしたい」というケースでは、繰上げ受給をすることで充実した老後を送れる可能性があります。
働き方で判断する
「何歳まで働くのか」も、年金を受給するタイミングに影響します。例えば60歳でリタイアし、その後働く予定がない場合は、繰上げ受給が選択肢の一つになります。
一方で、65歳以降も継続して働き、勤労収入で生活費を工面できる場合は、年金を繰り下げても問題ないでしょう。働けなくなったときに備えて、できるだけ年金を繰り下げて増額させる方法があります。
60歳以降に独立し、自営業者・フリーランスになる場合は、収入の不安定性に留意する必要があります。収入が不安定な場合は生活費を確保するために繰上げ受給を検討し、事業が安定している場合は繰下げ受給を検討する、という方法が考えられるでしょう。
ライフプランで判断する
60歳以降、どのようなライフプランを想定しているのかによって、適した受給方法は異なります。
- 退職金はいくらもらえるのか
- 企業年金はあるか、ある場合は何歳から何歳まで受給できるのか
- 何歳まで働くつもりか
- 自分の金融資産がどれくらいあるか
以上のように、勤務先の退職金制度や資産状況、働き方を踏まえて「60歳以降、どのように生活するか」を考える必要があります。
どのような生活を送りたいかを具体的に考えた上で、実現するために最適なタイミングで年金受給を開始するとよいでしょう。
どちらかが亡くなったときのことを考えておく
夫婦の場合はどちらか一方が先に亡くなったとき、残された側が問題なく生活できるかどうかを考える必要があります。
平均寿命は女性のほうが長く、また現役時に専業主婦世帯だった場合は妻の年金額が少額になるため、妻の生活をきちんと考えなければなりません。
この場合、夫の年金は65歳から受給し、妻の年金はできるだけ繰り下げる方法が考えられます。これにより、妻の年金収入を手厚くでき、経済的な不安を軽減できるでしょう。
老後に必要な資金をシミュレーションしておこう
老後に必要な資金が気になる方は、事前にシミュレーションしておくと資金の準備や目標設定に便利です。
マネイロの「3分投資診断」なら、現在の収入・支出や資産状況から将来の老後に必要な資金を算出し、その目標に向けた適切な資産運用方法が、たった3分、無料で診断できます。
老後生活を豊かに、楽しく過ごせるよう、まずは現状を知るところから始めてみましょう。
»老後に必要な資金はいくら?無料の3分診断
まとめ
年金は65歳からの通常受給のほか、60歳からの繰上げ受給と66〜75歳からの繰下げ受給を選択できます。65歳時点と比較したときの、受給開始年齢が「60歳」「70歳」「75歳」の損益分岐点は、それぞれ以下のとおりです。
- 60歳から繰上げ受給した場合、80歳10カ月より長く生きると損をする
- 70歳から繰下げ受給を開始した場合、81歳11カ月より長く生きると得をする
- 75歳から繰下げ受給を開始した場合、86歳11カ月より長く生きると得をする
特に女性は男性よりも平均寿命・平均余命が長いことから、繰下げ受給を選択すると有利な可能性があります。
ただし、最適な受給方法は平均寿命・健康状態・資産状況・働き方・ライフプランなどを総合的に判断して決めるべきです。理想としている老後生活をイメージしたうえで、何歳から年金を受け取るのが最適なのかを考えてみるとよいでしょう。
»まずは年金だけで暮らせるか、無料診断してみませんか?
老後資金が気になるあなたへ
老後の不安をなくすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶賢いお金の増やし方入門:30分の無料オンラインセミナー
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。