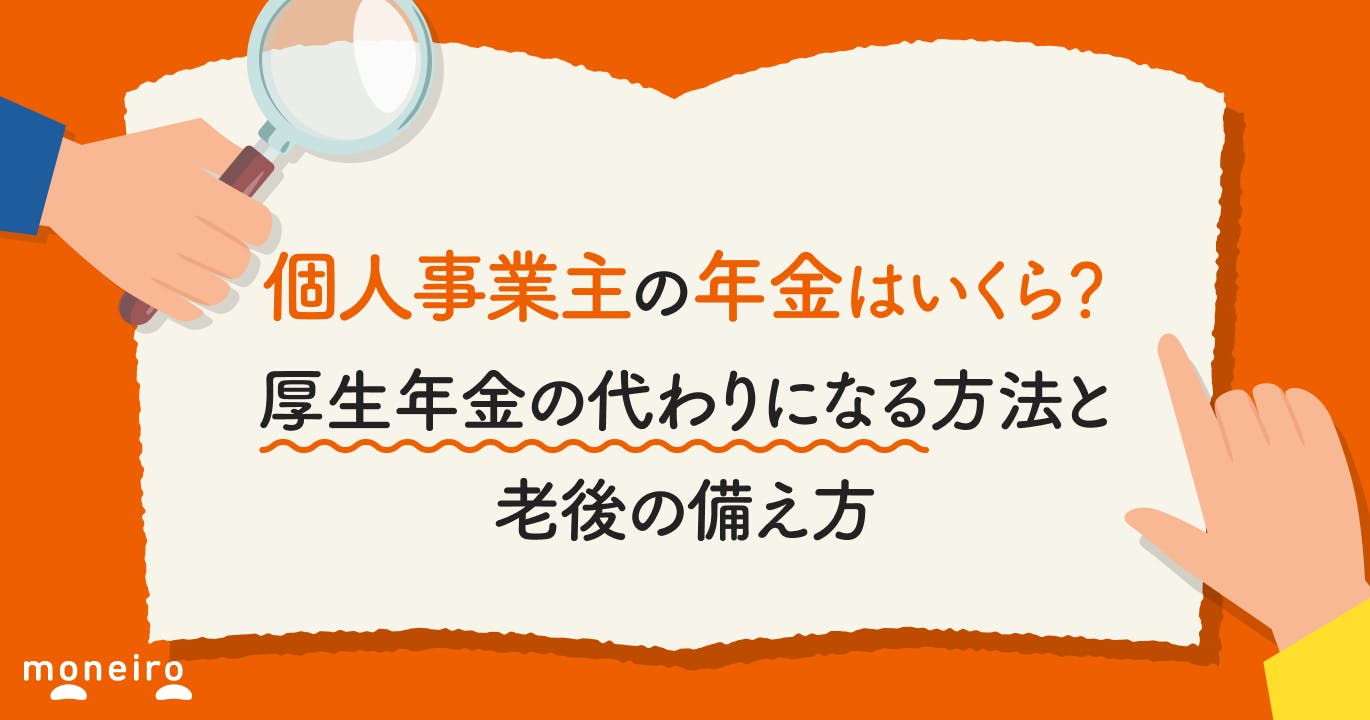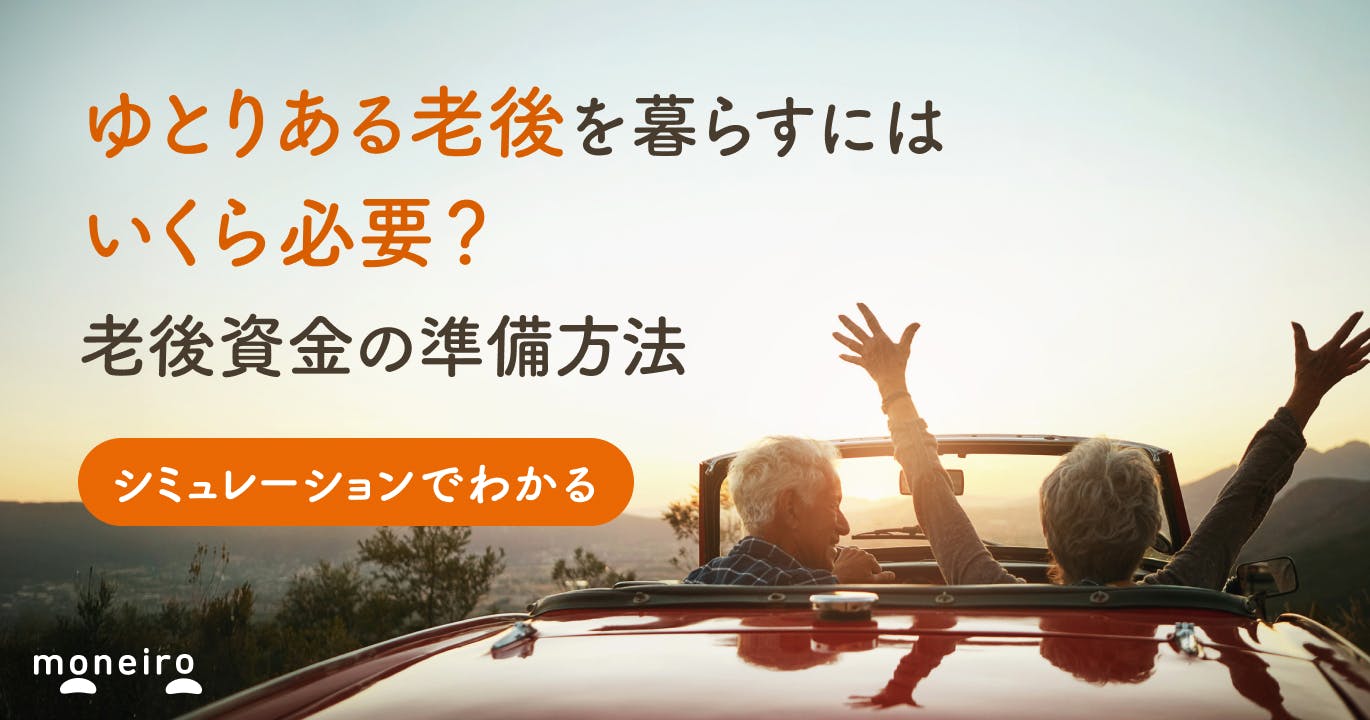個人事業主の年金はいくら?厚生年金の代わりになる方法と老後の備え方を専門家が解説
»年金だけで暮らせる?簡単診断
個人事業主は厚生年金に加入できず、基本的に「国民年金(老齢基礎年金)」のみを受給します。そのため、会社員に比べて将来の年金額が少なくなる傾向があります。
実際、厚生労働省の統計によれば、国民年金の平均受給額は月額5万7700円にとどまり、厚生年金加入者の平均と大きな差があります。では、個人事業主は老後にどう備えれば良いのでしょうか。
本記事では、個人事業主の平均年金額や会社員との違いを解説し、自分の年金額を確認する方法を紹介します。そのうえで、国民年金基金・付加年金・iDeCo・小規模企業共済などを組み合わせる具体的な対策を専門家視点で整理し、老後資金準備の実践的な指針を提供します。
- 個人事業主が加入する年金制度の基本
- 会社員との年金額の比較
- 年金額を増やすための上乗せ制度
老後資金が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶教育・住宅・将来資金の賢い準備方法:スマホで見られる30分セミナー
▶50代からの老後資金作り:スマホで見られる30分セミナー
個人事業主がもらえる年金とは
個人事業主が加入する公的年金は、原則として国民年金(老齢基礎年金)のみです。会社員が加入する厚生年金には加入できないため、将来の備えを自分で考える必要があります。
日本の公的年金制度は2階建て構造になっています。1階部分が全国民共通の「国民年金」、2階部分が会社員や公務員向けの「厚生年金」です。個人事業主は「第1号被保険者」として、この1階部分である国民年金にのみ加入します。
そのため、会社員と比べて将来受け取る年金額が少なくなる傾向にあります。この差を埋めるために、任意で加入できる様々な上乗せ制度が用意されています。
国民年金(老齢基礎年金)が基本
日本の公的年金制度の根幹をなすのが国民年金(老齢基礎年金)です。これは、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての国民に加入が義務付けられている制度です。
個人事業主やフリーランスは、国民年金に「第1号被保険者」として加入することになります。
公的年金の加入者は働き方によって区分されています。会社員や公務員は「第2号被保険者」、その被扶養配偶者は「第3号被保険者」となります。
個人事業主は第1号被保険者として、自分の国民年金保険料を全額自分で支払う点が特徴です。
厚生年金に加入できない理由
個人事業主が厚生年金に加入できないのは、厚生年金が法人や常時5人以上の従業員がいる個人事業所など、適用事業所に勤務する会社員や公務員を対象とした制度であるためです。
自営業者や個人事業主、フリーランスは、この加入要件を満たしません。
個人事業主の年金平均額と会社員との比較
個人事業主と会社員では、年金の受給額に大きな差があります。
国民年金の平均受給額(月額約5.8万円)
個人事業主が主に受け取ることになる国民年金(老齢基礎年金)の平均受給額は、月額でおおよそ5万円台です。厚生労働省の統計によると、令和5年度の平均月額は5万7700円となっています。
これはあくまで平均値であり、保険料を40年間満額納付した場合の受給額(令和7年度で月額約6.9万円)とは異なる点に注意が必要です。
実際の受給額は、個人の保険料納付期間や免除期間などによって変わります。
(参考:令和7年4月分からの年金額等について|日本年金機構)
(参考:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局)
厚生年金加入者の平均(月額約14.7万円)
一方で、会社員などが加入する厚生年金の平均受給額は、国民年金部分を含めて月額14万円台となっています。令和5年度の統計では、平均月額は14万7360円です。
この金額には、1階部分である老齢基礎年金が含まれています。厚生年金保険料は収入(標準報酬月額)に応じて決まり、その半分を勤務先が負担してくれるため、個人事業主が加入する国民年金のみの場合と比べて、将来の受給額が有利になる傾向があります。
夫婦世帯での受給額の違い
夫婦世帯で考えると、年金額の差はさらに大きくなる可能性があります。
会社員の配偶者で一定年収未満の場合、「第3号被保険者」として国民年金保険料を自分で納付することなく、将来、老齢基礎年金を受け取ることができます。
一方、個人事業主の配偶者は第3号被保険者にはなれず、自分も「第1号被保険者」として国民年金保険料を納付する必要があります。
そのため、世帯全体の保険料負担や将来の年金受給額を考える際には、制度の違いを理解しておくことが大切です。
自分の年金額を確認する方法
将来の年金額は、「ねんきん定期便」や「公的年金シミュレーター」で簡単に確認できます。さらに詳しい試算をしたい場合は、「ねんきんネット」の利用がおすすめです。
- ねんきん定期便:毎年誕生月に届くハガキや封書で、加入実績や将来の見込み額を確認可能
- ねんきんネット:日本年金機構の公式サイトで、最新の年金記録や見込額シミュレーションをいつでも確認できる
- 公的年金シミュレーター:厚生労働省提供のツールで、働き方や収入の変化に応じた将来の年金額を簡単に概算できる
自分の年金額を把握することが、老後資金対策の第一歩です。定期的に記録をチェックする習慣を持ちましょう。
個人事業主が利用できる年金の上乗せ制度
個人事業主は
- 国民年金基金
- 付加年金
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 小規模企業共済
といった制度を活用することで、国民年金に上乗せして将来の受給額を増やせます。
それぞれ特徴や節税効果が異なります。自分の事業状況やライフプランに合わせて、適切に組み合わせることが、賢い老後資金準備の鍵となります。
国民年金基金:会社員の厚生年金に近い仕組み
国民年金基金は、個人事業主やフリーランスといった国民年金の第1号被保険者のために作られた、公的な上乗せ年金制度です。
国民年金基金に任意で加入し掛金を納めることで、将来の年金額を増やし、会社員の厚生年金との格差を是正することを目的としています。
大きなメリットは、支払った掛金が全額「社会保険料控除」の対象となり、所得税や住民税の節税につながる点です。
また、1口目は終身年金ですが、2口目以降は有期年金も選択できます。老後の生活設計に合わせた年金受給が可能です。
一方で、一度加入すると原則として自己都合での脱退はできません。掛金の口数を減らすことは可能ですが、将来の計画を慎重に立てた上で加入を検討する必要があります。
付加年金:月400円で将来上乗せ
付加年金は、手軽に始められる年金の上乗せ制度です。毎月の国民年金保険料に月額400円の付加保険料を追加で納めるだけで、将来の年金額を増やすことができます。
受給額(年額)は「200円 × 納付月数」で計算され、この金額が毎年、老齢基礎年金に加算されます。計算上、2年間年金を受け取れば支払った保険料の元が取れるため、非常に有利な制度といえるでしょう。
ただし、国民年金基金に加入している場合は、付加年金を利用することはできません。どちらか一方を選択する必要があるため、自分の状況に合わせて検討しましょう。
iDeCo:掛金が全額所得控除で節税効果が高い
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し、投資信託などの金融商品を選んで運用する私的年金制度です。運用成果によって将来の受取額が変わるのが特徴で、老後の資産形成の有力な選択肢となります。
iDeCoの最大の魅力は、さまざまな税制優遇にあります。まず、支払った掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
次に、運用によって得られた利益(分配金や譲渡益)は非課税で再投資されます。さらに、60歳以降に受け取る際も、一時金なら「退職所得控除」、年金形式なら「公的年金等控除」が適用され、税負担が軽くなるように設計されています。
一方で、運用商品によっては元本割れのリスクがある点や、原則として60歳まで資金を引き出せないという制約も理解しておく必要があります。
小規模企業共済:廃業・引退時の退職金代わり
小規模企業共済は、国の機関である中小企業基盤整備機構が運営する、個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。
毎月掛金を積み立て、事業を廃業した際や役員を退任した際に、共済金として一括または分割で受け取ることができます。
掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になるため、高い節税効果が期待できます。また、納付した掛金の範囲内で事業資金などを低金利で借り入れできる貸付制度も用意されており、万一の際の資金繰りにも役立ちます。
一方、納付期間が20年(240ヶ月)未満で任意解約した場合は、受け取れる金額が掛金の合計額を下回る元本割れのリスクがあります。
また、加入から12ヶ月未満での任意解約は掛け捨てとなるため、長期的な継続が前提の制度です。
老後資金が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶教育・住宅・将来資金の賢い準備方法:スマホで見られる30分セミナー
▶50代からの老後資金作り:スマホで見られる30分セミナー
どの制度を優先すべき?組み合わせ方の考え方
自分の収入やリスク許容度、将来設計に合わせて制度を活用しましょう。
最低限おさえるべき「国民年金基金または付加年金」
個人事業主の年金上乗せの基本としてまず検討したいのが、国民年金基金または付加年金です。これらは公的な制度であり、将来の生活設計の土台となります。
付加年金は月々400円という少額の保険料で、将来の年金額を確実に増やせる制度です。一方、国民年金基金はより大きな金額を積み立てることができ、終身年金などプランの選択肢も豊富です。
ただし、この2つの制度は併用することができません。どちらか一方を選択する必要があります。
手軽に始めたい場合は付加年金、より手厚い保障を求めるなら国民年金基金、というように自分のニーズに合わせて選びましょう。
余裕があれば「iDeCoや小規模企業共済」
国民年金基金や付加年金で基礎を固めた上で、さらに資金に余裕があればiDeCoや小規模企業共済の活用を検討しましょう。
これらの制度は、掛金が全額所得控除の対象となるため、高い節税効果が期待できます。
iDeCoは自分で金融商品を選んで運用するため、将来の受給額は運用成績次第ですが、大きなリターンも狙えます。
一方、小規模企業共済は個人事業主の退職金制度という位置づけで、事業資金の貸付制度も利用できるなど、経営者にとってのメリットも大きいのが特徴です。
国民年金基金とiDeCoは併用可能ですが、掛金の上限額は合算して月額6.8万円(※)となります。小規模企業共済はこれらの制度とは別枠で加入できるため、節税効果を最大化したい場合は積極的に活用を検討すべきです。
※2027年度から7.5万円(予定)
個人事業主の老後資金シミュレーション
国民年金(老齢基礎年金)のみでは、多くの世帯で老後の生活費を賄うのは困難です。上乗せで活用する制度の内容で受給額は大きく変わるため、不足額を把握し計画的に備える必要があります。
国民年金基金やiDeCoを活用した場合の上乗せ額
国民年金基金やiDeCoといった上乗せ制度を活用することで、将来の受給額を大幅に増やすことが可能です。
例えば、国民年金基金では、加入時の年齢や選択するプランによって受給額が決まります。公式サイトのシミュレーションなどを活用すれば、具体的な上乗せ額を試算できます。
また、iDeCoの場合、受給額は自分の掛金額と運用成績によって変わります。個人事業主は最大で月額6.8万円(2027年1月から7.5万円に増額予定)まで拠出できるため、長期的に運用することで大きな資産形成が期待できます。
これらの制度は掛金が所得控除になるため、節税しながら将来の備えを厚くできるのが大きな利点です。
老後生活費との不足額と備え方
生命保険文化センターの調査(2022年度)によると、夫婦2人が老後生活を送る上で必要と考える最低日常生活費は平均で月額23.2万円、ゆとりある生活を送るには月額37.9万円が必要とされています。
国民年金の満額受給額(令和7年度:月額約6.9万円)だけでは、最低限の生活費にも遠く及ばないことがわかります。
仮に夫婦2人とも国民年金を満額受給しても月額約13.8万円であり、それでも不足します。
不足額を補うためには、国民年金基金やiDeCo、小規模企業共済といった上乗せ制度を計画的に活用することが不可欠です。
自分の事業収入やライフプランと照らし合わせ、どの制度をどのくらい利用するかを早期に検討し、実行に移すことが大切です。
(参考:「生活保障に関する調査」/2022(令和4)年度|生命保険文化センター)
まとめ
個人事業主は、会社員と異なり公的年金が国民年金のみとなるため、将来の備えを自分で計画的に行う必要があります。
- 基本は国民年金: 個人事業主の公的年金は国民年金(老齢基礎年金)が土台です
- 会社員との差: 厚生年金がない分、平均的な受給額は会社員より少なくなります
- 上乗せ制度の活用: この差を埋めるために、国民年金基金、iDeCo、小規模企業共済などの制度が用意されています
- 節税メリット: 上乗せ制度の多くは、掛金が全額所得控除になるなど、高い節税効果も兼ね備えています
まずは「ねんきんネット」などで自分の将来の年金見込額を確認し、どのくらいの上乗せが必要かを把握することから始めましょう。
そして、それぞれの制度の特徴を理解し、ご自分の事業状況やライフプランに合った最適な組み合わせを見つけることが、安心して老後を迎えるためのポイントです。
»年金以外でいくら必要?簡単診断はこちら
老後資金が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶教育・住宅・将来資金の賢い準備方法:スマホで見られる30分セミナー
▶50代からの老後資金作り:スマホで見られる30分セミナー
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。