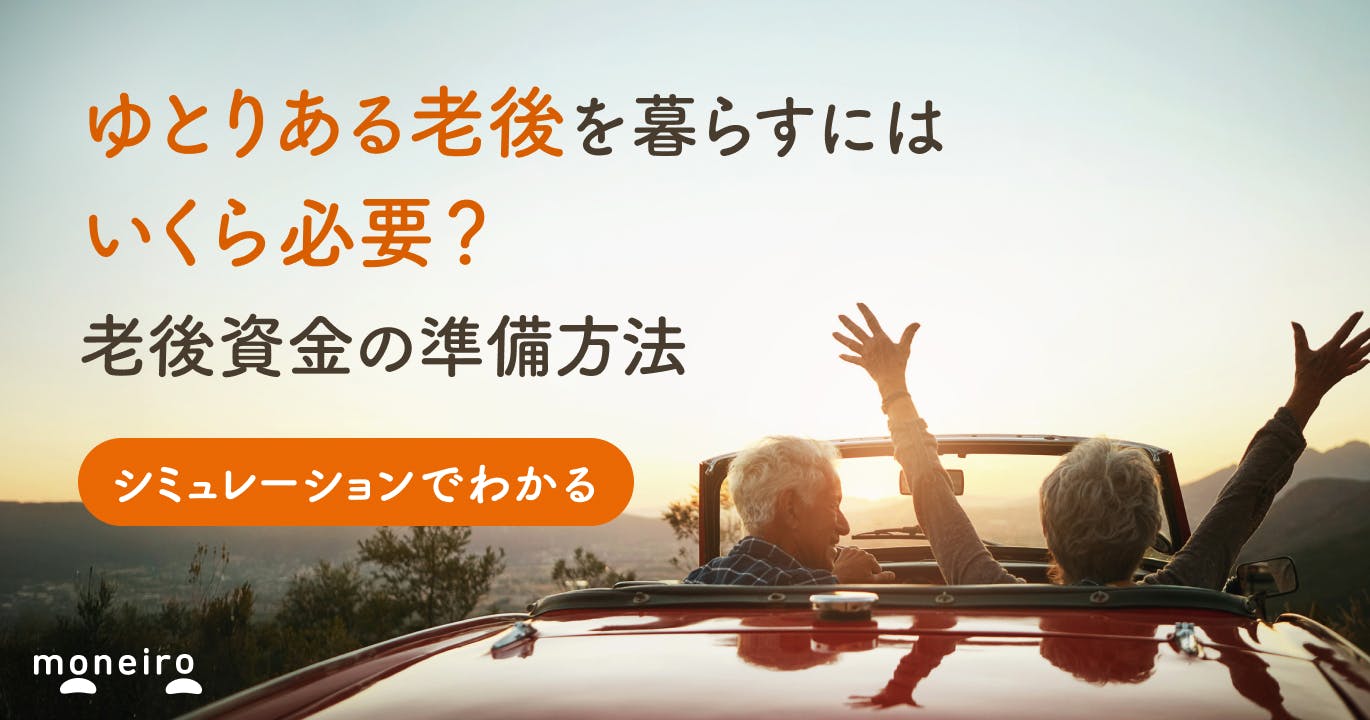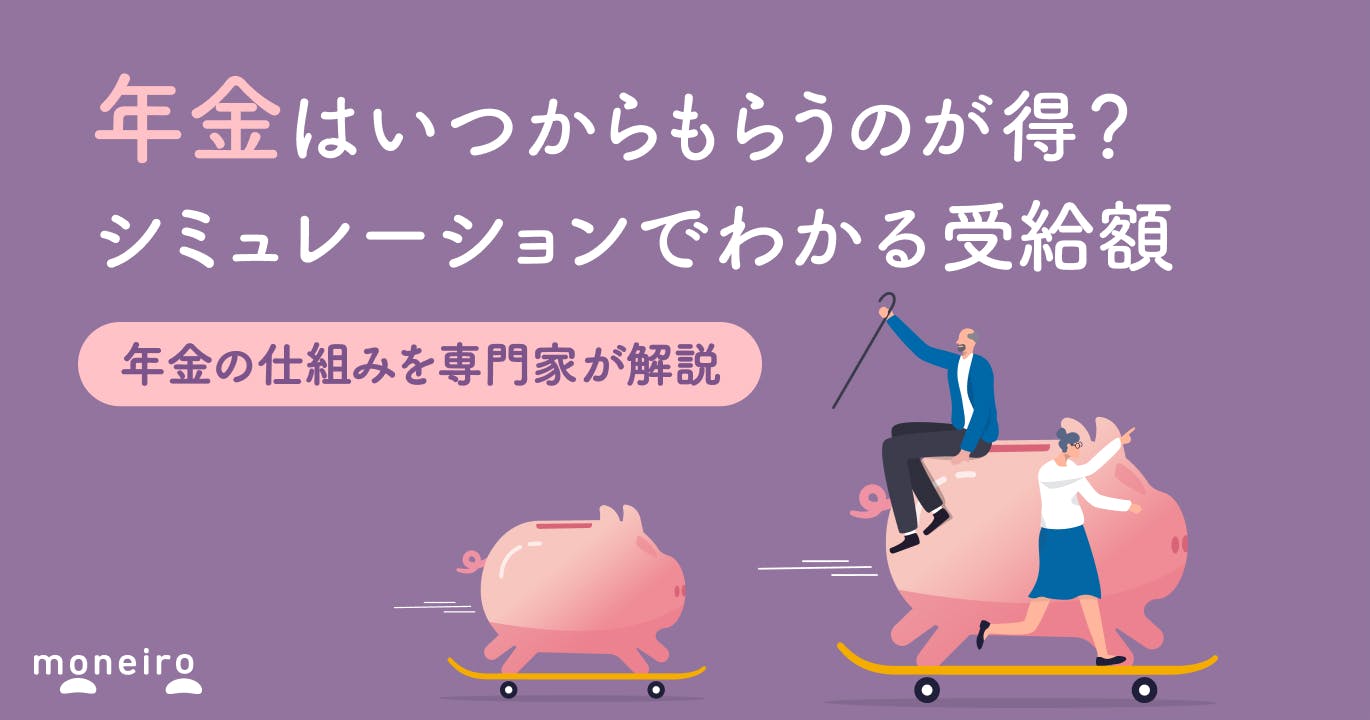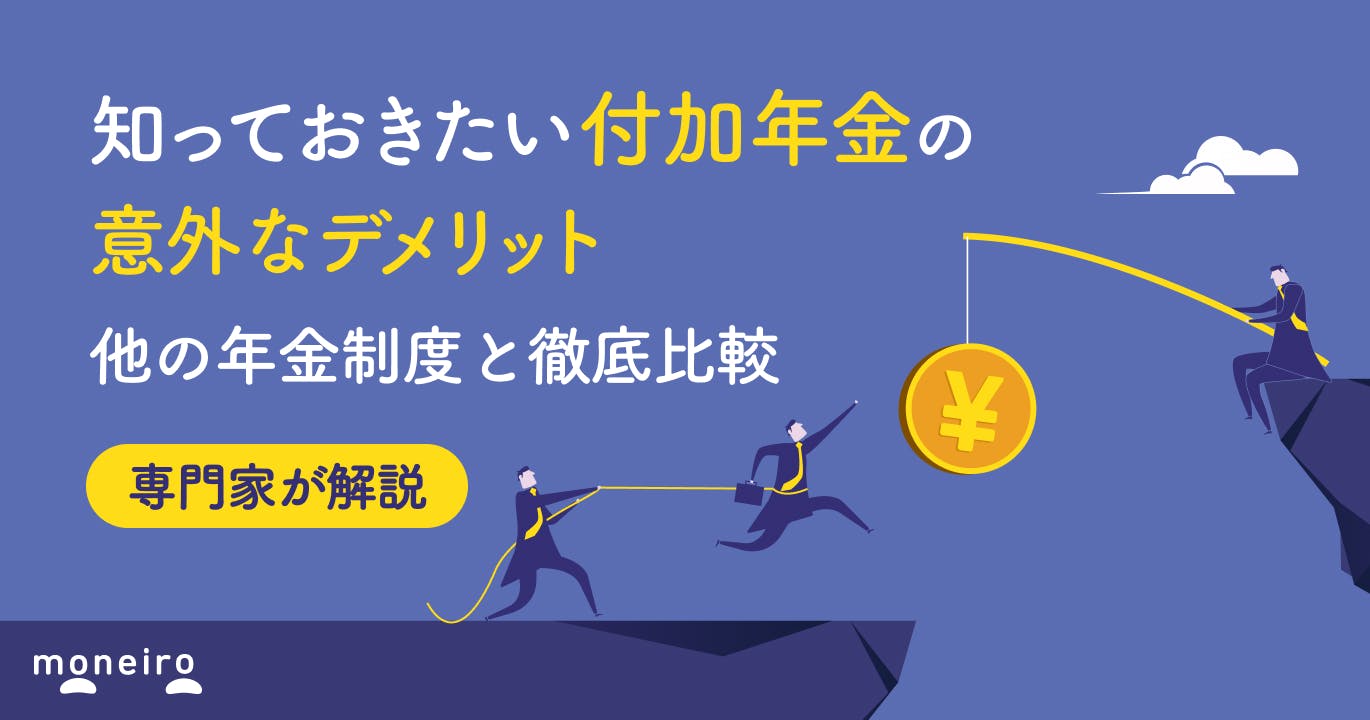小規模企業共済のデメリットとは?専門家が3つの注意点と活用法をわかりやすく解説
無料診断:将来必要な金額がわかる
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者などのための退職金制度として人気ですが、「元本割れするって本当?」「解約すると損する?」と不安を感じて検索している人も多いのではないでしょうか。
制度には途中解約リスクや資金の流動性の低さといったデメリットがありますが、活用法次第で将来の備えとして大きな味方になります。
本記事では、小規模企業共済の主なデメリットと注意点、やめた方がいいケース、さらにメリットを活かすための活用のコツまで、専門家がわかりやすく解説します。
- 小規模企業共済の主なメリット・デメリットと向かない人
- 小規模企業共済とiDeCoの比較と併用のメリット
- 小規模企業共済を賢く活用するコツ
将来のお金が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
小規模企業共済とは
小規模企業共済は「個人事業主」や「小規模企業の経営者、役員」のための、独立行政法人中小企業基盤整備機構が設けている退職金制度です。
将来の廃業時や引退時、あるいは事業を継承する際に、これまでの積み立てに応じた共済金を受け取ることができます。
個人事業主や小規模企業の役員等には会社員のような退職金制度がありません。そのため、小規模共済が老後の生活資金として大きな役割を果たします。
小規模企業共済の目的
小規模企業共済の主な目的は、個人事業主や小規模企業の経営者、役員が、廃業や退職後の生活の安定を図ることです。
積み立てた掛金が老後の生活資金になったり、万が一事業を廃止した場合は新規事業の開業資金に充てたり、途中解約して事業資金に充てることもできます。
小規模企業共済の加入資格
小規模企業共済に加入できるのは、原則として以下の条件を満たす方です。
法人の役員:常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人の役員
協業組合の役員:事業を行う協業組合の役員
従業員数に制限があるため、中小企業の中でも特に小規模な事業者や、役員の方が対象となります。
小規模企業共済の主なメリット
小規模企業共済は個人事業主や小規模企業の経営者、役員にとって、税制面で非常に大きなメリットを持つ制度です。
掛金が全額所得控除になる
支払った掛金(月額1000円〜7万円)が全額、所得控除の対象になります。これにより、課税所得を減らすことができ、所得税・住民税の負担を軽減できます。
共済金受取時は退職金扱いになる
将来、共済金を受け取る際にも税制上の優遇があります。
共済金は、一括で受け取る場合は「退職所得」として扱われ、年金形式で受け取る場合は「公的年金等の雑所得」として扱われます。
どちらの受け取り方でも、退職所得控除や公的年金等控除といった優遇措置が適用されるため、税負担を抑えることができます。
低金利の貸付制度を利用できる
小規模企業共済の加入者は、積立掛金の範囲内で、低金利で事業資金等の貸付制度を利用できます。
急な資金繰りが必要になった際でも、金融機関から借り入れるよりも有利な条件で資金を調達できる場合があります。
小規模企業共済の主なデメリット・注意点
小規模企業共済はメリットが大きい一方で、資金の流動性や途中解約時には注意すべきデメリットがあります。
任意解約時の元本割れリスク
小規模企業共済は自己都合で任意解約した場合に、解約手当金が掛金合計額を下回る元本割れのリスクがあります。
加入期間が12ヶ月未満で任意解約すると、掛金は全額掛け捨てとなり、解約手当金は一切受け取れません。
また、掛金納付月数が20年未満で任意解約すると、支払った掛金の合計額を下回る金額しか解約手当金として受け取れません。
元本割れを避けるには、原則として20年以上掛金を払い続けるか、廃業・引退など共済金が満額支給される事由が発生するまで継続する必要があります。
共済金受給時に課税される
掛金が全額所得控除されるメリットがある一方、共済金を受け取る際には課税される可能性があります。
退職所得控除や公的年金等控除が適用されるとはいえ、他の退職金や年金収入との兼ね合いによっては税負担が発生するため注意しましょう。
資金の流動性が低い
小規模企業共済に積み立てた資金は原則として廃業、引退、または役員退任などの請求事由が発生するまで引き出すことができません。
急にまとまったお金が必要になったとしても、任意解約をすれば元本割れのリスクを負うことになります。
小規模企業共済があまり向かない人
小規模企業共済は、節税メリットが魅力ですが、すべての人に適しているわけではありません。
以下に該当する場合は加入を慎重に検討しましょう。
収入が不安定で支払いを続けられるか不安な人
小規模企業共済は、長期的な支払いの継続が前提となる制度です。事業の収入が不安定で、毎月の掛金支払いが困難になる可能性がある場合、任意解約のリスクが高まり、元本割れにつながる可能性があります。
掛金は減額することも可能ですが、無理なく続けられる範囲で設定することが大切です。
事業の継続性や将来性が見通せない人
事業の立ち上げ期で将来が見通しにくい場合や、短期間での廃業・業態変更の可能性が高い場合は、小規模企業共済が向かないことがあります。
事業の廃業・解散以外の自己都合による任意解約では元本割れリスクがあるため、事業が不安定なうちは注意が必要です。
急な資金ニーズに備えて資金を流動的に使いたい人
生活防衛資金(※)が足りない人や、近い将来に住宅購入の頭金などを使う予定がある人には、小規模企業共済は向いていません。資金が長期間引き出せないためです。
まずは生活防衛資金をしっかり確保し、近い将来使うお金は流動性の高い預貯金などで準備しましょう。
※予期せぬトラブルが発生した際に、当面の生活を維持するために使うお金のこと
小規模企業共済とiDeCoは併用可能
小規模企業共済とiDeCo(個人型確定拠出年金)は、どちらも自営業者向けの税制優遇のある制度です。
小規模共済とiDeCoは併用することが可能です。それぞれの違いについて理解して活用しましょう。
小規模企業共済とiDeCoの主な違い
小規模企業共済とiDeCoの違いは以下のとおりです。
小規模企業共済とiDeCoの併用のメリット
小規模企業共済とiDeCoは、それぞれ異なる強みを持つため、両方を活用することで、より手厚く、かつ柔軟性も考慮した老後資金準備が可能になります。
どちらも掛金が全額所得控除になるため、併用することで節税メリットを最大限に享受できます。
また、小規模企業共済の資産運用は中小機構任せ、iDeCoは自身で運用商品を選択するため、運用先の分散による投資リスクの軽減が期待できます。
そして、小規模企業共済は運用利回りは低めですが共済金額が事前に確定している一方、iDeCoは運用方法次第で高い利回りが期待できるため、両方を組み合わせることで、多角的な老後資金対策が可能です。
小規模企業共済を賢く活用するコツ
小規模企業共済のデメリットを理解した上で、制度を最大限に活用するためのポイントを解説します。
廃業・引退まで継続前提で加入する
小規模企業共済のデメリットのひとつに、任意解約時の元本割れリスクがあります。
このリスクを避けるためには、原則として廃業や引退といった共済事由が発生するまで、掛金を払い続けることが大切です。
長期的な視点で継続できることを前提に加入を判断しましょう。
貸付制度を活用して資金拘束リスクを補う
小規模企業共済は資金の流動性が低いというデメリットがあります。しかし、貸付制度を活用することで、一時的な資金ニーズに対応できる場合があります。
万が一、事業で急な資金が必要になった際に、低金利で融資を受けられる制度を活用することで、資金拘束リスクを補うことが可能です。
毎年の掛金控除を節税に活かす
小規模企業共済の掛金は全額所得控除になるため、毎年、所得税や住民税の負担軽減効果があります。
節税メリットを最大限に活かすために、無理のない範囲で、かつ将来必要となる退職金の目標額を見据えた掛金設定をしましょう。
掛金は年1回など、まとめて支払うことも可能です。
まとめ
小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者、役員にとって、退職金の準備と節税を両立できる有効な制度です。
掛金が全額所得控除になるほか、共済金の受取時にも税制優遇があり、低金利での貸付制度が利用できる点も魅力です。
一方で、任意解約では元本割れのリスクがあり、資金の流動性が低いというデメリットもあります。特に、収入が不安定な場合や、近い将来まとまった資金が必要になる場合は注意しましょう。
小規模企業共済を賢く活用するには、廃業や引退まで続ける前提で加入することが大切です。また、必要に応じて貸付制度を活用しながら、毎年の節税メリットを最大限に活かしましょう。
iDeCoとの併用も検討し、自身の事業やライフプランに合った老後資金の準備を進めることがポイントです。
将来のお金が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。