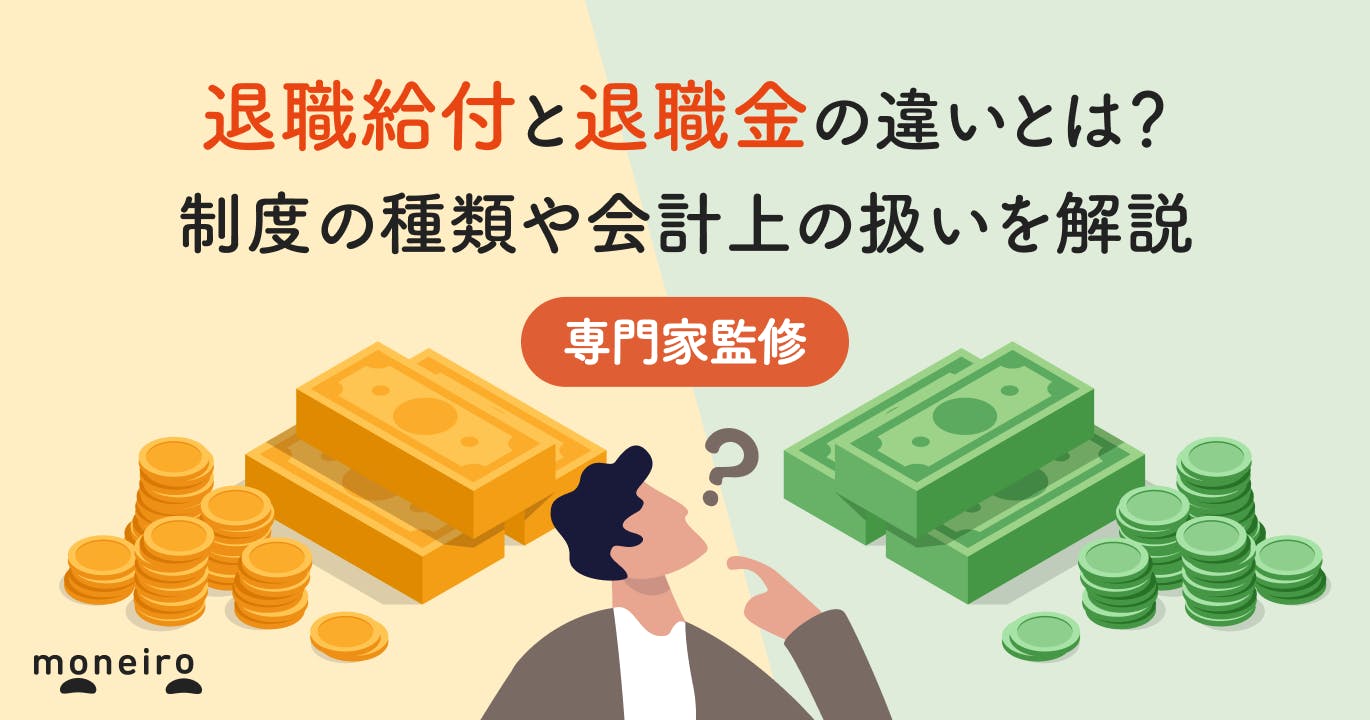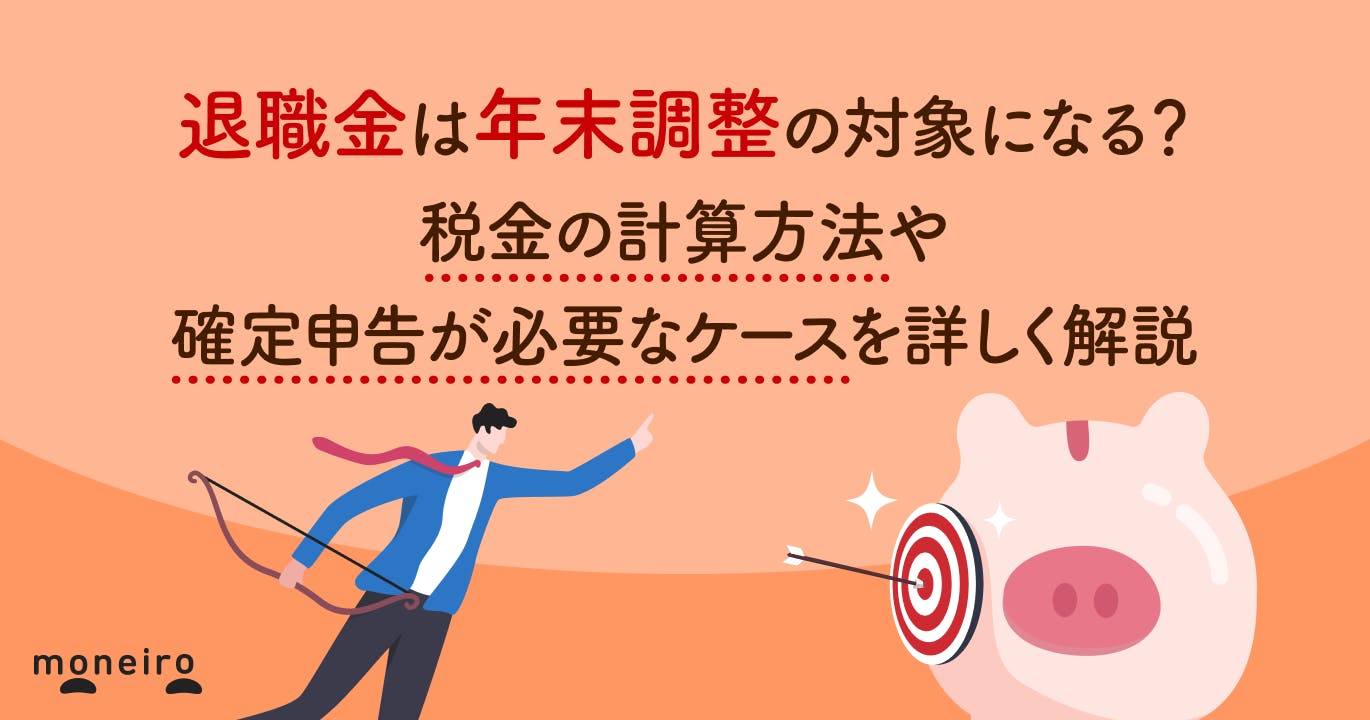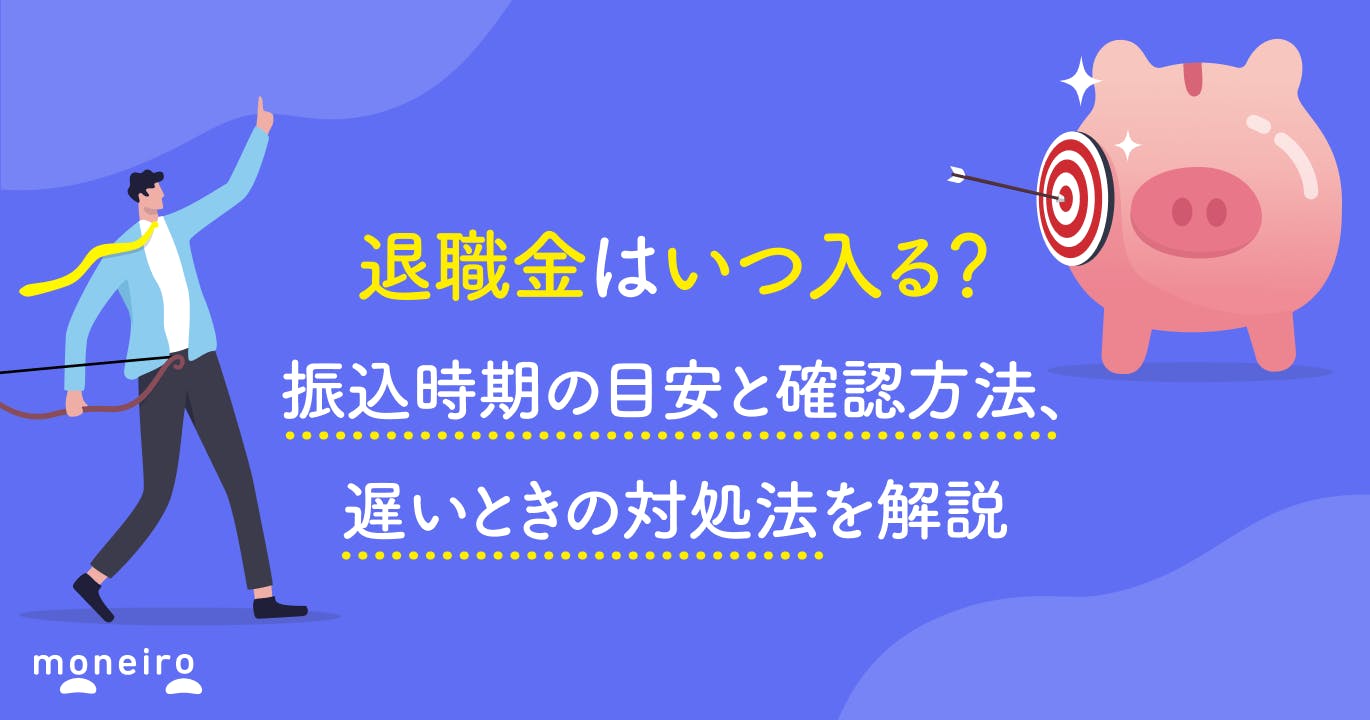
退職金は年末調整の対象になる?税金の計算方法や確定申告が必要なケースを詳しく解説
≫退職金で足りる?あなたの老後の不足額をシミュレーション
退職金は長年の勤務に対する対価として支給される大切な資金ですが、「年末調整の対象になるのか」「税金はいくらかかるのか」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、退職金にかかる税金の基本的な仕組みから、年末調整との関連、所得税・住民税の計算方法、そして確定申告が必要なケースと不要なケースまで、退職者が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
- 退職金が年末調整の対象外である理由
- 退職金にかかる税金の仕組みと優遇措置
- 自分で確定申告をすべきケース
老後資金が気になるあなたへ
老後を豊かに暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法を学ぶ
▶資産500万円からの債券投資の基本:30分の無料オンラインセミナー
そもそも年末調整とは?
年末調整とは、毎月の給与やボーナスから天引きされた源泉所得税の1年間の合計額と、本当に払うべき源泉所得税の差額を調整する手続きです。
多くの会社員は、この年末調整を勤務先が行うため、個人で確定申告をする必要がありません。
年末調整の対象となるのは、「給与所得」です。1年間の給与の総額が決まる年末に、生命保険料控除や扶養控除などの各種控除を反映させて、最終的な所得税額を計算し、過不足を調整します。
退職金は年末調整の対象になる?
結論からいうと、退職金は年末調整の対象にはなりません。
その理由は、退職金が「給与所得」ではなく「退職所得」という別の所得の種類に分類されるためです。所得税法では、所得の種類に応じて税金の計算方法が決められています。
- 給与所得:毎月の給与やボーナスなど。他の所得と合わせて税額を計算する「総合課税」の対象。
- 退職所得:退職時に受け取る一時金など。他の所得とは分けて税額を計算する「分離課税」の対象。
このように、退職金は給与とは別に税金が計算されるため、年末調整のプロセスには含まれません。
退職金(一時金)にかかる税金の仕組み
退職金は年末調整の対象外ですが、税金が全くかからないわけではありません。しかし、長年の勤務の対価であり、老後の生活保障という性質から、税負担が大幅に軽くなる退職所得控除が設けられています。
所得税と住民税がかかる
退職金には、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の2種類の税金がかかります。これらは給与やボーナスにかかる税金と同じ種類ですが、計算方法が大きく異なります。
退職金は、他の所得とは合わせずに税額を計算する分離課税という方式が使われています。これは、退職金のような一時的に大きな金額の所得が他の所得と合計されると、累進課税によって税率が急激に高くなってしまうのを防ぐための配慮です。
この分離課税のおかげで、税負担が軽くなる仕組みになっています。
退職所得控除で税負担を軽減できる
退職金にかかる税金を計算する上でもっとも重要なのが退職所得控除です。これは、退職金が過去の長年の勤務の対価であるために税制上優遇措置されているからです。
この控除額は勤続年数に応じて大きくなるため、長く勤めるほど税制上有利になります。退職金の額がこの控除額の範囲内であれば、所得税や住民税はかかりません。
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額は、勤続年数によって計算方法が違います。具体的な計算式は以下の通りです。
ポイントは、勤続年数に1年未満の端数がある場合、切り上げて1年として計算する点です。例えば、勤続年数が15年2ヶ月の場合は16年として計算します。
これにより、例えば勤続20年であれば800万円、勤続35年であれば1850万円もの控除が受けられます。
勤続年数5年以下の「短期退職手当等」に注意
勤続年数が5年以下の役員以外の従業員が受け取る退職金(短期退職手当等)については、税金の計算方法が一部違います。
具体的には、退職金から退職所得控除額を差し引いた金額のうち、300万円を超える部分については、税金がかかる所得を計算する際の「2分の1」計算が適用されません。
これは、短期間で会社を移りながら退職金を繰り返し受け取ることで、税負担を軽くすることを防ぐための措置です。勤続年数が5年以下で退職する場合には、この点に注意が必要です。
老後資金が気になるあなたへ
老後を豊かに暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法を学ぶ
▶資産500万円からの債券投資の基本:30分の無料オンラインセミナー
退職金(一時金)で確定申告は必要?不要なケースとすべきケース
退職金(一時金)を受け取った際、確定申告が必要かどうかは多くの方が疑問に思う点でしょう。基本的には不要ですが、状況によっては確定申告が必要になったり、した方が有利になったりする場合があります。
原則として確定申告は不要
退職金(一時金)については、原則として確定申告は不要です。これは、退職者が勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、勤務先側が正しい税額を算出し、退職金から天引きして納税を済ませるためです。
この手続きにより、退職金に関する税金の関係は完結するため、受け取った本人が改めて申告する必要はありません。
この申告書は通常、退職手続きの際に会社から案内がありますので、忘れずに提出しましょう。
確定申告が必要、またはしたほうがよいケース
原則不要である一方、以下のようなケースでは確定申告が必要になるか、または確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
- 年の途中で退職し、その後再就職していない場合
- 生命保険料控除など、控除を適用したい場合
- 退職した年に給与以外の所得が20万円を超える場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職所得控除が適用されず、退職金の支払額に対して一律20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の所得税および復興特別所得税が天引きされます。
この税率は、本来の税額よりも高くなることが多く、確定申告を行うことで、正しく計算された税額との差額が還付されます。
「退職所得の受給に関する申告書」を未提出の場合は、必ず確定申告を行いましょう。
年の途中で退職し、その後再就職していない場合
年の途中で退職し、その年内に再就職しなかった場合、退職するまでにもらった給与について税金の精算がされていません。
毎月の給与から天引きされる所得税は、各種控除が反映されていない概算の金額であるため、通常は本来の税額より多くなっています。年末調整が行われないと、その年の所得に対する税額の精算がされないままになります。
そのため、確定申告によって所得税を精算する必要があります。
退職した会社から発行される「給与所得の源泉徴収票」を使って、忘れずに確定申告をしましょう。
生命保険料控除など、控除を適用したい場合
年末調整で申告できる生命保険料控除や地震保険料控除などを申告し忘れた場合や、そもそも年末調整では適用できない控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。年末調整で適用できない控除の代表例は以下の通りです。
- 医療費控除:年間の医療費が高額になった場合に適用
- 寄附金控除:ふるさと納税などが対象
- 雑損控除:災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に適用
- 住宅ローン控除(1年目):住宅ローンを組んで家を購入した初年度
これらの控除を適用することで、所得税の還付を受けられる可能性があります。退職した年にこれらの支出があった場合は、確定申告を検討しましょう。
退職した年に給与以外の所得がある場合
退職した年に、給与や退職金以外の所得がある場合は、確定申告が必要です。対象となる所得には、以下のようなものがあります。
- 事業所得・不動産所得:個人事業やアパート経営などによる所得
- 雑所得:公的年金以外の年金、副業による所得(原稿料など)
- 一時所得:生命保険の一時金など
- 譲渡所得:株式や不動産の売却による所得
これらの所得がある場合は、退職金の手続きとは別に自身で所得を計算し、確定申告を行う義務がありますので注意しましょう。
退職金(一時金)にかかる税金の計算方法
退職金(一時金)にかかる税金は、3つのステップで計算できます。退職所得控除が組み込まれているため、一見複雑に見えますが、順を追って計算すれば理解しやすくなります。ここでは、具体的な計算手順を解説します。
1.退職所得控除額を計算する
まずは、税金の計算から差し引くことができる退職所得控除額を、以下の計算式で求めます。
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年)
2.課税退職所得金額を計算する
次に、実際に税金がかかる対象となる「課税退職所得金額」を計算します。計算式は以下です。
課税退職所得金額 = (退職金の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
まず、退職金の総額からステップ1で計算した退職所得控除額を差し引きます。そして、その残りの金額をさらに半分(2分の1)にします。この「2分の1にする」措置が、退職金の税負担を大きく軽くする重要なポイントです。
3.所得税額と住民税額を計算する
最後に、ステップ2で算出した課税退職所得金額をもとに、所得税と住民税の額を計算します。
- 所得税額の計算 課税退職所得金額に応じて決められた所得税率を掛け、控除額を差し引いて計算します。税率は5%から45%までの累進課税となっています。算出した所得税額に、さらに2.1%の復興特別所得税が上乗せされます。
- 住民税額の計算 課税退職所得金額に、一律10%(都道府県民税4%、市区町村民税6%)の税率を掛けて計算します。
これらの計算を経て、最終的に退職金から天引きされる税金の総額が決まります。
退職金の税金に関するよくある質問
退職金の税金に関するよくある疑問についてQ&A形式で解説します。
Q. 退職金の年末調整をしないとどうなる?
退職金はそもそも年末調整の対象外であるため、「年末調整をしない」ことによる不利益は何もありません。退職金は給与とは別の「退職所得」として、会社が支払い時に天引きという形で税金を納めます。したがって、自身で特別な手続きをする必要はありません。
まとめ
この記事では、退職金と年末調整の関係、かかる税金の仕組みと計算方法、そして確定申告が必要になるケースについて解説しました。
- 退職金は「退職所得」であり、年末調整の対象外
- 「退職所得控除」により税負担は大幅に軽減される
- 原則確定申告は不要だが、退職所得の受給に関する申告書を勤務先に未提出の場合、年末調整(給与所得)が未済で各種控除を受けたい場合は確定申告の必要がある
退職金は、過去の長年の勤労の対価です。税金の仕組みを正しく理解し、損のないように手続きを進めることが重要です。自分の状況に合わせて、必要であれば確定申告を行い税金の精算をしましょう。。
≫退職金で足りる?あなたの老後の不足額をシミュレーション
老後資金が気になるあなたへ
老後を豊かに暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法を学ぶ
▶資産500万円からの債券投資の基本:30分の無料オンラインセミナー
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
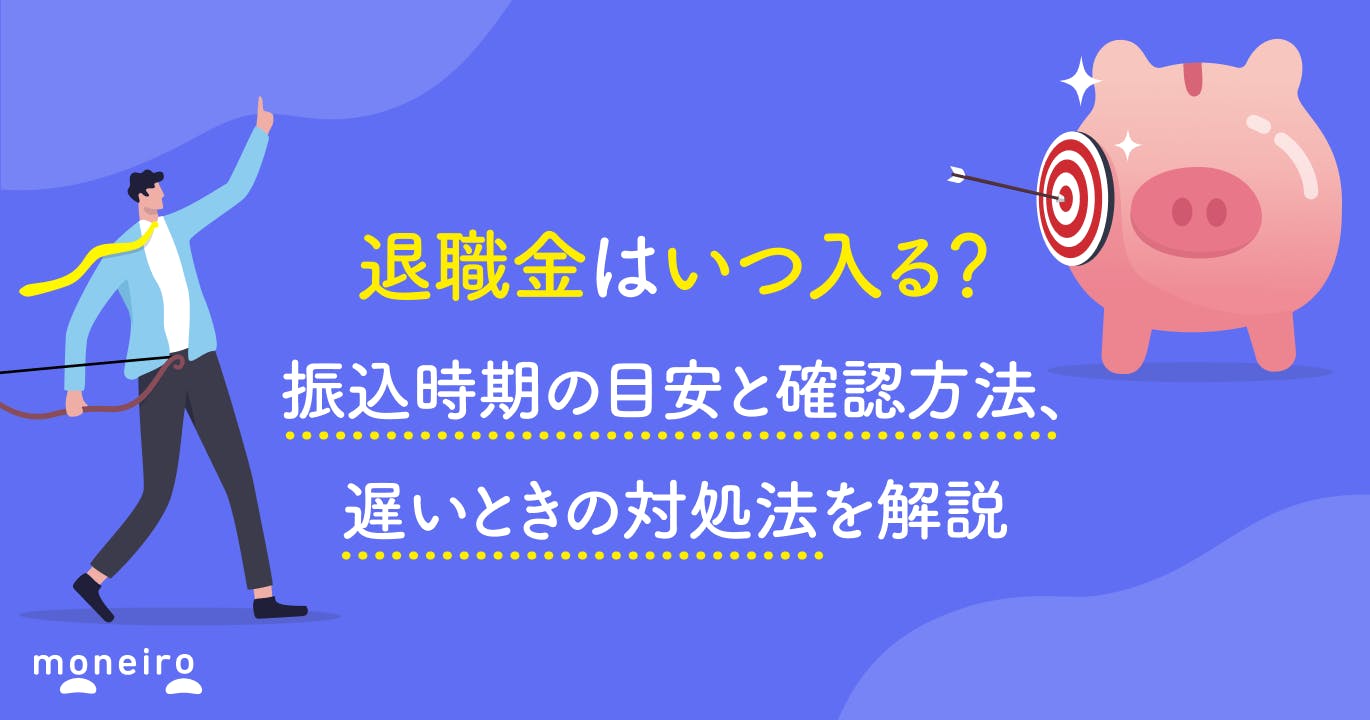
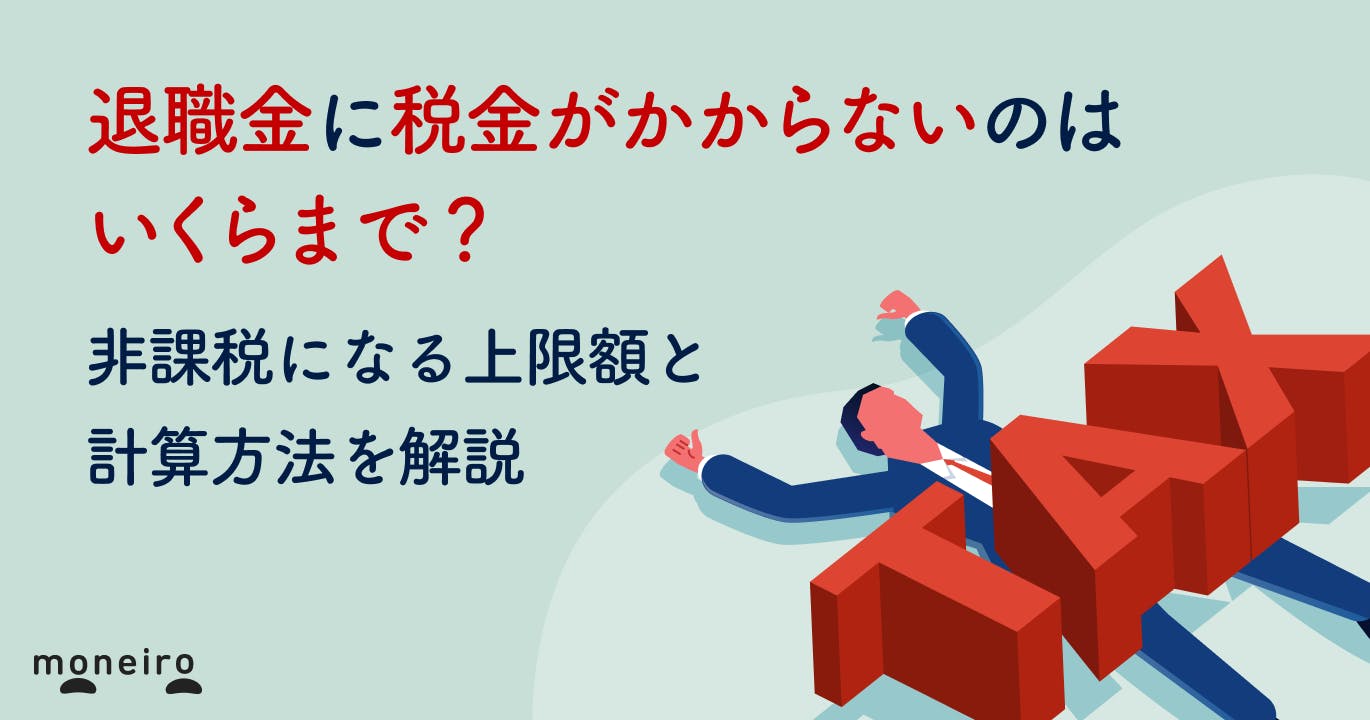
退職金に税金がかからないのはいくらまで?非課税になる上限額と計算方法を解説