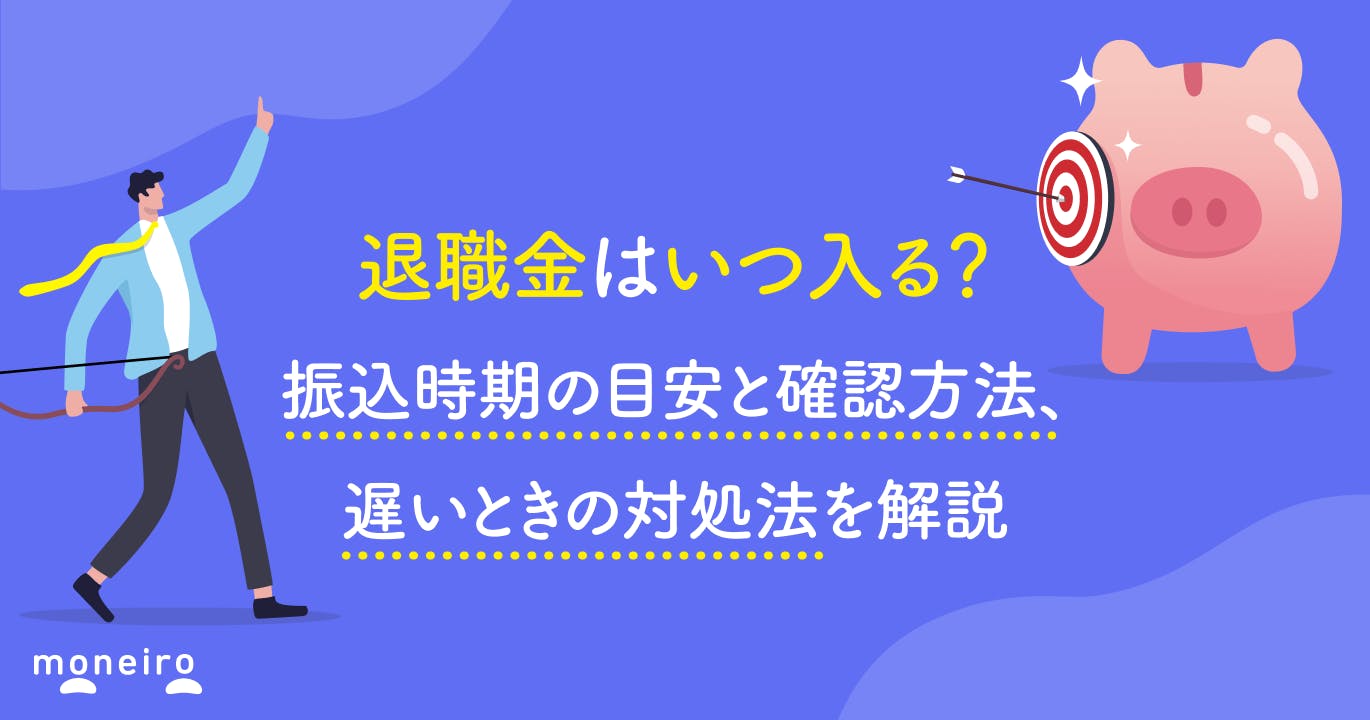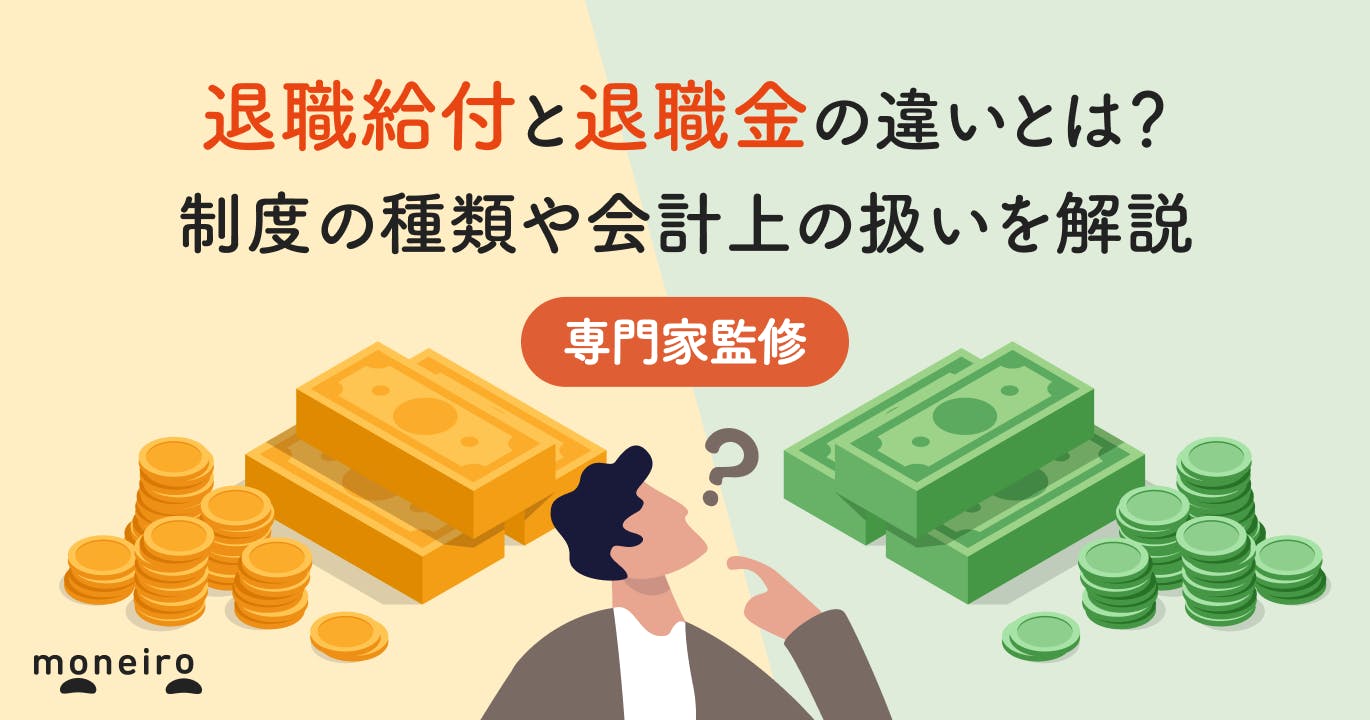
退職金はいつ入る?振込時期の目安と確認方法、遅いときの対処法を解説
≫退職金はどう運用する?あなたに最適な資産運用を診断
「退職金はいつ入る?」退職後の大切な資金計画を立てる上で、この疑問は非常に重要です。
この記事では、退職金の一般的な振込時期から、勤め先の会社の支給日を正確に確認する方法、万が一入金が遅れたり、振り込まれなかったりした場合の具体的な対処法まで、必要な情報を詳しく解説します。退職後の生活を安心して送るための準備として、ぜひご活用ください。
- 退職金の一般的な振込時期(会社員のケース/公務員のケース)
- 振込時期を正確に知るための確認方法
- 支払いが遅い場合の法的な対処ステップ
退職金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
退職金はいつ入る?
退職金の振込時期は法律で一律に決められているわけではなく、企業によって対応が異なりますが、退職後1〜2ヶ月以内に支払われるケースが一般的です。
また、「退職日から1ヶ月以内に支払う」といったように、就業規則や退職金規程において支払時期を明確に定めているケースもあります。
退職者が集中する年度末(3月)や、会社の決算期などは、人事・経理部門の手続きが混み合い、通常よりも時間がかかる可能性があります。退職後の資金計画を円滑に進めるためにも、まずは勤め先の規定を事前に確認しておくことが重要です。
公務員の場合は?
国家公務員の退職手当は、「国家公務員退職手当法」という法律に基づき、原則として退職後1ヶ月以内に支払われることが決められています。これにより、退職後の生活への移行がスムーズに行えるよう、法的な裏付けがなされています。
地方公務員の退職手当についても、多くの場合、国家公務員の制度に準じた条例が各自治体で決められています。そのため、基本的には国家公務員と同様に、退職から1ヶ月以内が支給の目安となります。
ただし、退職者が集中する時期など、事務処理の都合で多少前後する可能性も考慮しておくとよいでしょう。
退職金がいつ振り込まれるか正確に知るための3つの確認方法
退職は今後のライフプランに大きく関わる重要なイベントです。憶測で判断するのではなく、以下の方法で退職金の入金時期に関する正しい情報を把握し、安心して次のステップに進めるように準備しましょう。
- 就業規則・退職金規程の確認
- 人事・総務部への問い合わせ
- 中小企業退職金共済(中退共)制度の確認
就業規則・退職金規程を確認する
企業における退職金の支払時期や計算方法といったルールは、就業規則や、より詳細を決めた「退職金規程」に明記されているのが基本です。これはもっとも信頼性が高い情報源であり、退職を考え始めた際に最初に確認すべき書類です。
これらの書類には、支払時期のほかにも、支給対象となる最低勤続年数や、自己都合・会社都合といった退職理由による支給率の違いなども記載されています。
また、就業規則は、法律によって従業員がいつでも閲覧できる状態にしておくことが義務付けられています。社内の共有フォルダやイントラネットで公開されているか、書面で保管されている場所を確認し、必ず内容に目を通しておきましょう。
人事・総務などの担当部署に問い合わせる
就業規則を読んでも不明な点がある場合や、ご自身の個別の状況について正確な情報を知りたい場合は、人事部や総務部など、労務管理を担当する部署へ直接問い合わせるのが確実です。
担当者は退職手続きの実務を熟知しているため、具体的な振込予定日や手続きの進捗状況について回答を得られるでしょう。
問い合わせのタイミングとしては、退職の意思を正式に伝えた後、具体的な退職手続きを進める中で行うのがスムーズです。
その際、退職金の支給額や振込時期だけでなく、受け取りに必要な書類や手続きの流れについても併せて確認しておくと、その後の段取りを円滑に進められるでしょう。
中小企業退職金共済(中退共)に加入している場合
中小企業に勤めている場合、会社独自の制度ではなく、国の中小企業退職金共済制度(中退共)に加入しているケースがあります。これは、企業が外部機関である中退共に掛金を積み立て、退職時にはその機関から直接、退職者に退職金が支払われる公的な仕組みです。
中退共からの退職金は、退職者本人が請求手続きを行ってから約4週間で振り込まれるのが標準的なスケジュールです。ここで重要なのは、支払いの起算点が「退職日」ではなく「請求を受け付けた日」であるという点です。退職後に会社から「退職金共済手帳」を受け取り、速やかに自身で請求手続きを進める必要があります。
ただし、支払いが遅れる可能性もあります。中退共は、会社が退職月分の掛金を納付したことを確認してから支払手続きを開始します。
そのため、会社の事務処理の都合で掛金の納付が遅れると、退職金の振り込みもそれに伴って遅れ、2ヶ月以上かかる場合もあることを念頭に置いておきましょう。
退職金の振り込みが遅い・振り込まれない場合の4つのステップ
万が一、決められた時期を過ぎても退職金が支払われない場合、まずは社内での確認から始め、解決しなければ公的機関や専門家への相談へと段階的に対応を進めることが重要です。
支払いの遅延は単なる事務手続きの遅れであることも多いですが、意図的な不払いである可能性もゼロではありません。冷静かつ着実に行動するために、以下のステップを確認しておきましょう。
ステップ1.まずは会社の担当部署に状況を確認する
約束の時期を過ぎても退職金が振り込まれない場合、最初の行動は会社の担当部署(人事部や総務部)への連絡です。まずは感情的にならず、事務的な確認として「退職金の振込状況についてお伺いしたいのですが」と冷静に問い合わせましょう。
単なる事務処理の遅延や、手続き上の単純なミスである可能性も十分に考えられます。退職者が多い時期には、手続きに時間がかかっているだけかもしれません。
この段階で、いつ、誰と話したのか、そしてどのような回答を得たのかをメモしておくことが重要です。もし明確な回答が得られなかったり、不誠実な対応をされたりした場合には、次のステップに進む準備が必要になります。
ステップ2.内容証明郵便で支払いを請求する
担当部署に問い合わせても解決しない、あるいは支払いを明確に拒否されるような状況であれば、次の手段として内容証明郵便を利用して、書面で正式に退職金の支払いを請求します。
内容証明郵便は、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。これにより、「退職金を正式に請求した」という事実を法的な証拠として残すことができます。
この書面が会社に届くことで、会社側も事態の重要性を認識し、支払いに応じるケースが多くあります。請求書には、支払われるべき退職金の額、支払いを求める期限、そして「期限までに支払いがない場合は法的措置も検討する」という旨を明確に記載します。
これは、次のステップである公的機関への相談や訴訟に進む前の、重要な意思表示となります。
ステップ3.労働基準監督署に相談する
内容証明郵便を送付しても会社が支払いに応じない場合は、公的機関である労働基準監督署に相談することを検討します。労働基準監督署は、労働基準法などの法令に基づき、企業が労働条件を遵守しているかを監督する行政機関です。
就業規則で決められた退職金は法律上の「賃金」と見なされるため、その不払いは労働基準法違反に該当する可能性があります。労働基準監督署に相談すると、担当官が事実関係を調査し、法違反が確認されれば会社に対して是正勧告や指導を行ってくれます。
この行政指導には直接的な強制力はありませんが、多くの企業は監督署からの指導を重く受け止め、支払いに応じる傾向があります。相談に行く際は、就業規則の写し、給与明細、内容証明郵便の控えなど、これまでの経緯がわかる資料を持参すると、話がスムーズに進みます。
ステップ4.弁護士に相談し、法的措置を検討する
労働基準監督署の指導にもかかわらず会社が支払いに応じない場合、最終的な手段として弁護士に相談し、法的手続きを検討することになります。弁護士は法律の専門家として、あなたの代理人となり、会社との交渉から法的な手続きまでを一貫してサポートしてくれます。
具体的な法的措置としては、比較的短期間(原則3回以内の期日)で解決を目指す「労働審判」や、より正式な裁判手続きである「民事訴訟」などがあります。どちらの手続きが適しているかは、未払い額の大きさや事案の複雑さによって異なります。
費用は発生しますが、専門家が介入することで、これまで停滞していた問題が大きく前進する可能性があります。
多くの法律事務所では初回無料相談を実施しているため、まずは状況を説明し、今後の見通しや費用についてアドバイスを求めることから始めるとよいでしょう。
退職金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
事前に知っておきたい・退職金に関する基礎知識
退職金の支払時期は法律で厳密に決められていませんが、労働基準法には労働者の権利を守るための金品返還の義務が存在します。
退職金をいつ、どのように受け取るかは、退職後のライフプランに直結する重要な問題です。後悔のない選択をするために、以下の基礎知識をしっかりと押さえておきましょう。
退職金の支払時期は法律で決まっている?
労働者の権利を守る労働基準法第23条には、労働者が退職した際に請求があった場合、会社は7日以内に賃金をはじめとする労働者の権利に属する金品を返還しなければならない、という重要な規定があります。就業規則で決められた退職金も、この「金品」の一種と解釈されます。
しかし、退職金の支払い時期に関しては、この原則に特例が認められています。行政解釈により、あらかじめ就業規則や退職金規程で「退職後〇ヶ月以内に支払う」といった具体的な支払時期が決められている場合は、その規定された時期に支払えばよいとされています。
したがって、退職金の支払時期は必ずしも請求から7日以内とは限らず、まずは会社のルールが優先されるのが一般的です。この点が、毎月の給与支払いとは異なる大きな特徴です。
退職金の受け取り方は大きく3つ
退職金の受け取り方には、主に以下の3つの方法があり、どの方法を選択できるかは会社の制度によって異なります。それぞれの特徴を理解し、ご自身のライフプランに合った方法を選びましょう。
一時金受け取り
退職金を一括で受け取るもっとも一般的な方法です。住宅ローンの完済、繰り上げ返済やリフォーム、事業資金など、まとまったお金が必要な場合に適しています。税制面では「退職所得控除」という大きな優遇措置が受けられます。
年金受け取り
退職金を分割して、公的年金のように定期的に受け取る方法です。安定した収入を長期間確保できるため、老後の生活費として計画的に使いたい方に向いています。ただし、税務上は「雑所得」として扱われ、社会保険料の負担にも影響する場合があります。
一時金と年金の併用
上記2つの方法を組み合わせた柔軟な受け取り方です。一部を一時金として受け取り、残りを年金形式で受け取ることができます。当面の大きな支出に備えつつ、将来の安定収入も確保したいというニーズに応えられます。
退職金にかかる税金について
退職金には所得税や住民税がかかりますが、長年の功労に報いるという性質から、税制面で大きな優遇措置が設けられています。
特に一時金で受け取る場合、「退職所得控除」が適用されます。この控除額は勤続年数に応じて大きくなり、税金の計算対象となる金額(課税退職所得金額)を大幅に圧縮できます。具体的な計算方法は以下の通りです。
退職所得控除額を計算する
まずは、退職所得控除額を以下の計算式で算出します。退職所得控除額は、勤続年数によって計算方法が異なります。
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
課税退職所得金額を計算する
次に、上で出した退職所得控除額をもとに、課税退職所得金額を算出します。計算には以下の計算式を用います。
- (退職金額 - 退職所得控除額) × 1/2
上記の計算式からもわかるように、まず控除額が非常に大きく、さらに控除されない部分についても半分になるため、給与所得に比べて税負担がかなり軽減される仕組みになっています。
退職金の請求手続きの流れ
退職金を受け取るためには、会社が決める手続きを適切に行う必要があります。一般的には、退職の意思を伝えた後、人事・総務担当者から手続きに関する案内があります。
もっとも重要な書類が「退職所得の受給に関する申告書」です。この申告書を会社に提出することで、前述の「退職所得控除」が適用され、適切な税額が源泉徴収されます。
もしこの書類を提出しないと、退職金額に対して一律20.42%という高い税率で源泉徴収されてしまい、後で自身で確定申告をして還付を受ける手間が発生します。
会社によっては、独自の退職金請求書や、振込先口座を指定する書類の提出を求められることもあります。退職日が近づいたら、担当部署に必要な書類と提出期限を必ず確認し、漏れなく手続きを進めるようにしましょう。
退職金に関するよくある質問
退職金に関するよくある質問にお答えします。
Q. 退職金は勤続何年からもらえる?
法律上の決まりはなく企業によって異なります。自分が勤続何年から退職金をもらえるかを確認したい場合は、勤め先の就業規則や退職金規程で支給条件を確認することがもっとも確実です。
Q. 自己都合退職の場合、退職金はいつもらえる?
自己都合退職であっても、会社都合退職であっても、退職金の支払時期に違いはないのが一般的です。通常、退職後1〜2ヶ月以内に支払われますが、正確な時期は会社の就業規則で決められているのが一般的です。なお、支給額については自己都合の場合、減額されるケースが多い点には注意が必要です。
Q. 退職金を受け取るための必要書類は?
もっとも重要な書類は「退職所得の受給に関する申告書」です。この書類を会社に提出することで、適切な税額控除(退職所得控除)が適用されます。
提出しないと高い税率で源泉徴収されてしまい、後日、自分で確定申告をして還付を受ける手間が発生してしまうため、必ず提出しましょう。
まとめ
この記事では、退職金がいつ振り込まれるかという疑問について、多角的に解説しました。
退職金の振込時期は、一般的に退職後1〜2ヶ月が目安ですが、法律で決められているわけではなく、最終的には企業の就業規則や退職金規程によります。公務員の場合は法律に基づき、原則1ヶ月以内に支払われます。
正確な支払い時期を知るためには、まず就業規則を確認し、不明な点は人事・総務部へ問い合わせるのが確実です。万が一、支払いが遅れたり、支払われなかったりした場合は、担当部署への確認から始め、内容証明郵便の送付、労働基準監督署への相談、最終的には弁護士への相談と、段階的に対応を進めましょう。
退職金は、長年の勤務に対する大切な対価です。当記事の内容を参考に、受け取り方や税金の仕組みなど基本的な知識を身につけ、退職後のライフプランの計画にお役立てください。
≫退職金はどう運用する?あなたに最適な資産運用を簡単診断
退職金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
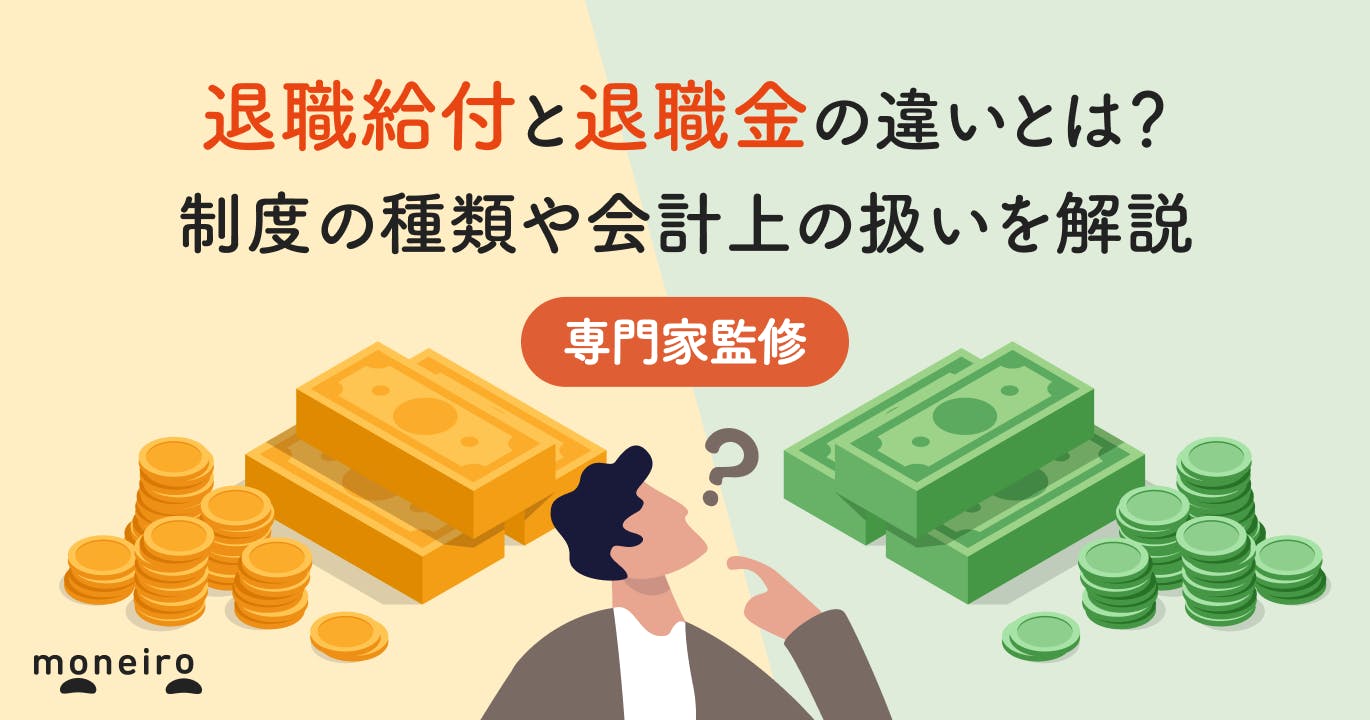

公務員の退職金はいくら?平均額や算定方法、税金の仕組みを解説

中小企業の退職金平均はいくら?勤続年数・学歴・退職理由別の相場を解説
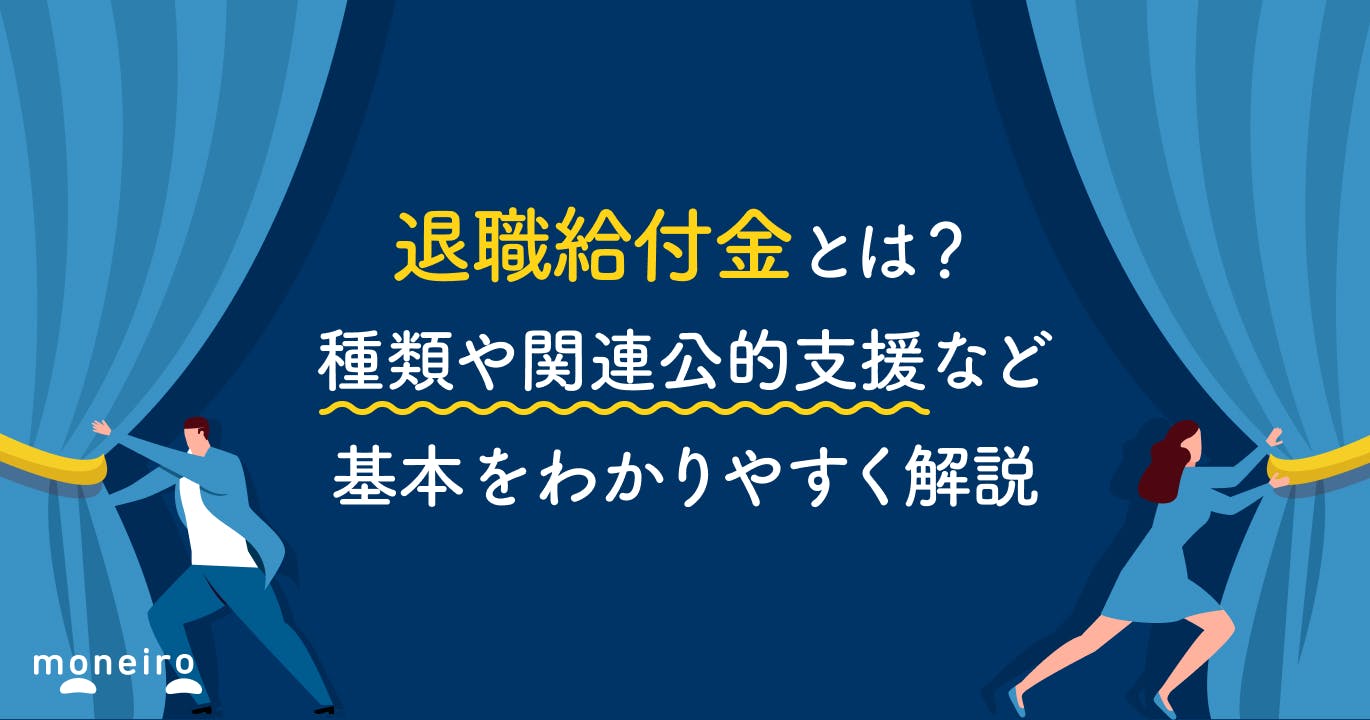
【社労士監修】退職給付金とは?種類や関連の公的支援など基本をわかりやすく解説
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。