
持ち家がない人の老後はどうなる?賃貸派の生涯コストと賢い準備を解説
>>あなたの老後は大丈夫?将来必要な資金を今すぐ診断
持ち家がない人が抱える老後にはどんなリスクや心配事が待ち受けているのでしょうか?
この記事では、賃貸派が直面する家賃負担や契約継続の課題といった老後のリスクや、住み替えの自由度などのメリットを解説します。さらに、持ち家の有無による貯蓄額の差を具体的なデータで比較し、安心して老後を送るためのヒントをご提案します。
- 持ち家がない人が老後に直面する可能性のある4つのリスク
- 持ち家の有無によって、金融資産の平均額・中央値にどれだけの差が出るか
- 老後の不安を解消するための具体的な住まい選びの戦略
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
持ち家がない人の老後にはどんなリスクがある?
持ち家がない場合、老後に向けて、資金や住居の確保など、さまざまなリスクが生じる場合があります。各課題について、具体的に確認していきましょう。
家賃負担の継続と家計への影響
持ち家がない最大の課題は、生涯にわたって家賃の支払いが続くことです。高齢になり収入が途絶えても、家賃の負担はなくならないため、継続的に家計を圧迫することになります。
例えば、老後も現役時代と同水準の家賃(月10万円と仮定)を支払う賃貸生活を続けた場合、65歳から95歳までの30年間支払うと、それだけで3600万円のコストとなります。
このコストは、持ち家であれば住宅ローン完済後に発生しない、賃貸特有の大きな「住居費」リスクであり、老後資金計画に深刻な影響を与えます。
賃貸派は、この将来の家賃支払い総額を見越した上での資金準備が必須です。
賃貸契約の継続性・住居確保のハードル
高齢者が直面しやすいのが、賃貸契約の継続性の問題です。貸主側は、孤独死のリスクや認知症によるトラブル、または保証人を見つけにくいといった理由から、高齢者との新規契約や更新を拒否するケースが多くあります。特に単身世帯の場合、緊急時の対応や万が一の事態を懸念され、住居確保のハードルが高くなる傾向があります。
高齢者が安心して住み続けられる住居を確保するためには、高齢者を受け入れる公的住宅や、保証人不要の物件を早期から探すなど、戦略的な準備が必要です。契約更新の制限や保証人問題は、老後の住まいの安定性を脅かす主要なリスクです。
介護・医療・住環境の課題
持ち家がない場合、住環境が介護や医療のニーズに合わない可能性があります。老後に向けてバリアフリー対応が必要になることがありますが、賃貸住宅では入居者の都合による大規模なリフォームは一般的に困難です。
また、訪問医療や介護サービスを受けやすい立地、あるいは将来的に介護施設に近接した場所への住み替えが必要になった際、希望の条件を満たす賃貸物件がすぐに見つからなかったり、住み替えに伴う契約手続きの負担が生じたりする課題があります。
健康状態の変化に合わせた柔軟な住環境の選択が、賃貸では制限される可能性があります。
孤立・安全・生活の質の低下リスク
賃貸住宅は流動性が高く、長期間同じ場所に定住することが少ないため、地域コミュニティとの関係性が希薄になりやすいのもデメリットです。持ち家であれば長年住み続けたことで自然に形成される近隣住民との「見守り」の関係が、賃貸では築きにくい場合があります。特に高齢の単身世帯では、地域から孤立し、緊急時の対応が遅れるリスクもあります。
この孤立は、生活の質の低下や精神的な不安につながるため、住居選びだけでなく、自治体のサービスを利用したり、積極的に地域活動に参加するなどの対策を通じて、安全確保と生活の質の維持に努めることが重要です。
持ち家なしにはメリットも
賃貸生活はリスクばかりではありません。持ち家を持たないことで享受できるメリットも存在します。併せてチェックしておきましょう。
住み替えの自由度が高い
賃貸の最大のメリットは、ライフステージの変化や健康状態、家族構成の変化に合わせて、自由に住まいを移転できることです。
例えば、現役時代は都心の広い部屋に住んでいても、退職後は生活費を抑えるために郊外の小さな物件へ、介護が必要になればバリアフリー対応の住宅へと、物件の売買の手間なく迅速に住み替えが可能です。これにより、その時の生活に最適な立地や住環境を、大きなコストや時間的制約なしに選び続けることができます。これは、持ち家にはない決定的な強みです。
固定資産税や修繕費などが不要
持ち家の場合、毎年固定資産税や都市計画税といった税金が発生するほか、建物や設備の老朽化に伴う大規模修繕費用や設備の交換費用が突発的に発生します。特に大規模修繕は、築年数に応じて数百万単位の出費となることが一般的です。
賃貸であれば、これらの固定資産税や大規模修繕にかかる費用を自己負担する必要がありません。
毎月の家賃は発生しますが、突発的な高額出費の心配がなく、計画的に資金管理を進められる点は、賃貸の大きな利点です。メンテナンスや管理の手間から解放されることもメリットです。
相続トラブルの心配がない
持ち家は重要な資産である一方で、相続時には「分けにくい資産」として、相続人同士のトラブルの原因となることがあります。特に不動産の評価額や、誰がその家に住み続けるかといった点で揉めるケースは少なくありません。
賃貸であれば、そもそも不動産を所有しないため、将来的に子世代に相続させる際の資産分割の心配がなく、スムーズに財産を整理することができます。これは、家族間の争いを避けたいと考える人にとって、非常に大きなメリットとなります。
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
持ち家の有無で貯蓄はどれくらい違う?
賃貸派が老後に向けて必要な資金を考える上で、持ち家世帯と非持家世帯の金融資産の状況を比較することは極めて重要です。ここでは、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(2024)」のデータを用いて、世帯別の金融資産保有額の平均値と中央値を確認してみましょう。
単身世帯の場合
金融資産を保有している単身世帯において、持ち家世帯と非持家世帯では大きな資産差があります。
持ち家世帯の金融資産保有額の平均は2442万円、中央値は1000万円です。一方、非持家世帯の平均は881万円、中央値は270万円となっており、平均で1561万円、中央値で730万円もの差が見られます。
特に中央値が低い非持家世帯は、多くの世帯が老後資金として十分な貯蓄を確保できていない可能性が高く、計画的な資産形成の緊急性が高いことを示しています。
「平均値」は、一部の富裕層によって引き上げてしまう可能性が高いため、「中央値(データを小さい順に並べたとき、ちょうど真ん中に位置する値)」のほうが、より実感に近い数値になりやすいといえます。
2人以上世帯の場合
2人以上世帯においても、金融資産保有額に持ち家の有無で顕著な差があります。
持ち家世帯の金融資産保有額の平均は2056万円、中央値は983万円です。これに対し、非持家世帯の平均は1254万円、中央値は400万円であり、平均で802万円、中央値で583万円の差があります。
単身世帯同様、2人以上世帯でも非持家世帯の中央値は持ち家世帯の半分以下であり、老後の生活資金を確保するための貯蓄努力が特に求められることが、データからも明らかです。
>>あなたの老後は大丈夫?将来の必要資金を今すぐ診断
生活費でも大きな差に
金融資産の保有額だけでなく、毎月の「住居費」の消費支出も、持ち家の有無で大きく異なります。
「家計調査(家計収支編2024)」によると、ローンの支払いが終わった持家世帯と、民営借家に住む世帯を比較すると、住居費(家賃地代と設備修繕・維持の合計)には以下のような差が見られます。
持ち家世帯はローンの支払いが終わっていれば、毎月の住居費負担が大幅に軽減されることがわかります。この毎月の生活費の差が、毎月の貯蓄額に直結し、結果として金融資産保有額の大きな差を生み出す主要因の1つになると考えられます。
高齢で持ち家を検討する手もある?デメリット・注意点を確認
老後の家賃負担を解消するため、高齢になってから持ち家の購入を検討する人もいます。しかし、若年層とは異なり、高齢での住宅取得には多くの課題が伴います。ここでは、高齢になってから持ち家を取得する際の主なデメリットと注意点について解説します。
審査が厳しく、借入期間が短くなる
住宅ローンは完済時の年齢を80歳程度に定めているため、高齢になってからの借入は審査が非常に厳しくなります。
例えば、完済年齢を80歳とすると、60歳で借り入れを始めた場合、返済期間は最長で20年となります。返済期間が短くなれば、その分月々の返済額が大きくなり、退職後の年金収入で賄うのが難しくなる可能性があります。
結果として、希望する借入額を確保できない、あるいは借入自体を断られるケースが増えます。
借り入れが可能でも、家計を圧迫しない返済計画を立てることが極めて重要です。
団体信用生命保険(団信)に加入できない可能性
ほとんどの住宅ローンでは、契約者が死亡または高度障害になった際に残債が保険で弁済される団体信用生命保険(団信)への加入が必須です。しかし、高齢者は健康状態に関するリスクが高くなるため、団信の審査に通りにくい、あるいは持病がある場合は加入を拒否される可能性があります。
団信に加入できなければ、原則として民間の住宅ローンを利用することができません。団信なしで利用できる住宅ローン(例:フラット35の一部)もありますが、金融機関の選択肢が限られ、老後の資金計画の自由度が低下します。健康状態が借入の大きな障壁となることを認識しておくべきです。
退職金や貯蓄を減らしてしまう可能性
高齢での持ち家購入は、住宅ローンを利用できない場合や利用額が少ない場合、退職金やこれまでの貯蓄を頭金として大きく切り崩す必要が生じます。老後生活を支えるための貴重な資金を不動産に固定してしまうと、急な医療費や介護費用が発生した際に資金繰りが難しくなるリスクがあります。
老後資金は、生活費だけでなく、予想外の出費に備える流動性の高い資産を残しておくことが大切です。
住宅購入に充てる資金と、手元に残しておくべき流動性のある資金のバランスを慎重に検討しなければ、老後破産につながりかねません。
継続的な維持費がかかる
高齢になって持ち家を取得した場合でも、その家を維持するための費用は継続的に発生します。具体的には、固定資産税や火災保険料、そして物件の老朽化による修繕費用です。特に築年数の古い物件を購入した場合、予想外の修繕コストが発生し、年金生活の家計を圧迫する可能性があります。
また、住まいが過大であった場合、光熱費なども増加し、トータルで賃貸に住み続けた場合と比較して経済的なメリットが出ない可能性も考慮しなければなりません。計画外の維持費は老後の予算を狂わせる原因となります。
ライフステージの変化に対応しにくい
高齢になって持ち家を取得しても、将来的に介護が必要になったり、身体機能が低下したりした場合に、住環境を容易に変更できないというリスクがあります。介護施設へ入居する、あるいはよりコンパクトな住居へ移る必要が生じた際、持ち家は売却手続きに時間と費用がかかります。
また、市場状況によってはすぐに売却できない、あるいは希望価格で売れない可能性もあり、老後の柔軟な生活設計の足かせとなる可能性があります。住み替えの自由度が高い賃貸のメリットが、持ち家では失われてしまうことに注意が必要です。
持ち家がない人が老後を安心させるための具体的な対策
賃貸派が老後の不安を解消するためには、生涯続く家賃負担のリスクを軽減する戦略と、計画的な資産形成を並行して進めることが重要です。具体的な対策として、資金計画と住居確保の両面から確認していきましょう。
家賃を抑える住まい選び・住み替え戦略
老後の家賃負担を軽減するためには、早い段階で家賃の安いエリアや物件への住み替えを検討することが効果的です。特に、UR賃貸住宅は、礼金・仲介手数料・更新料が不要で、保証人も原則不要であるため、高齢者にとって契約のハードルが低い選択肢の一つとなります。
また、高齢者向けの優遇制度が用意されている自治体の住宅制度を活用することも有効です。地方移住やコンパクトな住居へのダウンサイジングも有効な戦略です。住居費を削減することで、その分を医療費や介護費用などのための貯蓄に回すことができます。
サービス付き高齢者向け住宅の利用
高齢者向けの住まいとして、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の利用も選択肢に入ります。サ高住はバリアフリー設計で、安否確認や生活相談サービスが提供されるため、高齢者が安心して暮らすための住環境が整っています。
家賃の他にサービス費用が発生しますが、介護や医療のニーズが高まる将来を見越して、サ高住を検討しておくことで、従来の賃貸契約拒否のリスクや孤立のリスクを低減できます。
特に単身で生活の安全に不安を感じる方にとって、有力な選択肢となります。
公的制度・補助金・支援サービスの活用
経済的に困窮した場合や、住居の確保が難しい場合に備えて、公的な制度を理解しておくことが重要です。例えば、低所得者向けの家賃補助制度や、高齢者や障害者に対する住まい確保の支援サービスなどが地方自治体や国によって提供されています。
これらの制度は、万が一の事態におけるセーフティネットとして機能し、老後の生活を支える基盤となります。自治体の窓口や社会福祉協議会に相談し、利用可能な制度や補助金について事前に情報収集をしておくとよいでしょう。
資金計画と資産形成の工夫
持ち家世帯と非持家世帯の金融資産の大きな差を埋めるため、計画的な資産形成が不可欠です。特に、賃貸派は退職金や年金に加えて、生涯の家賃負担をカバーするための十分な金融資産が必要となります。
資産形成の手段としては、税制優遇制度のあるNISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を積極的に活用し、できるだけ早い段階から長期的な視点で資産運用を進めることが賢明です。これらの制度は、老後資金の準備を効率的に進めるために国が推奨している制度であり、非課税メリットを最大限に活用することで資産形成をスムーズに進めることができます。
まとめ
持ち家がない人の老後には、生涯続く家賃負担や、高齢による賃貸契約拒否、地域からの孤立など、固有の大きなリスクが存在します。
データによると、非持家世帯の金融資産の中央値は、持ち家世帯と比較して低い傾向があり、賃貸派は老後の生活費と住居費を賄うための資金計画を特に早期から確立する必要があります。
一方で、賃貸には住み替えの自由度や固定資産税・修繕費が不要というメリットもあります。これらのメリットを活かしつつ、UR賃貸住宅やサ高住などの住まいの選択肢を検討するとともに、できるだけ早い段階からの計画的な資産形成を通じて、老後の安心を確保していくことが大切です。
>>あなたの老後は大丈夫?将来の必要資金を今すぐ診断
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは現状を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額を3分で診断
▶夫婦で考えるお金の基本セミナー:ライフステージごとのお金の管理がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

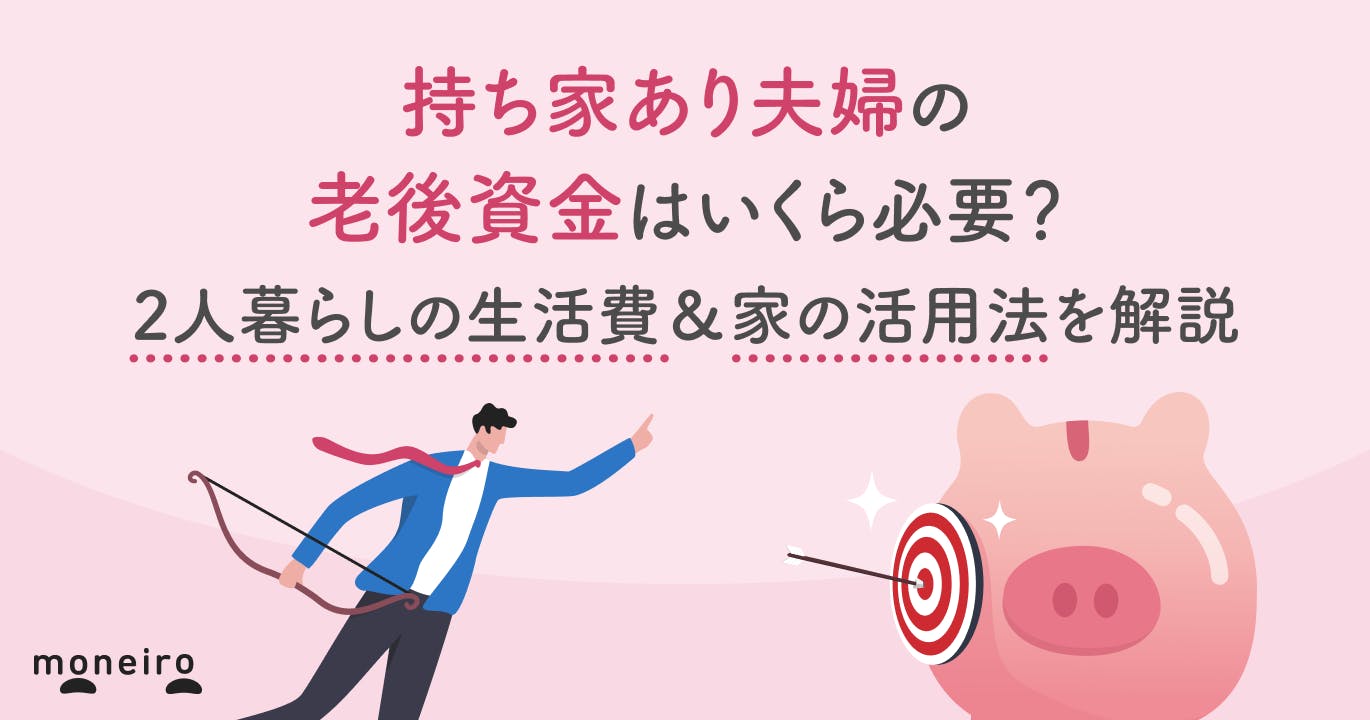
持ち家あり夫婦の老後資金はいくら必要?2人暮らしの生活費&家の活用法を解説
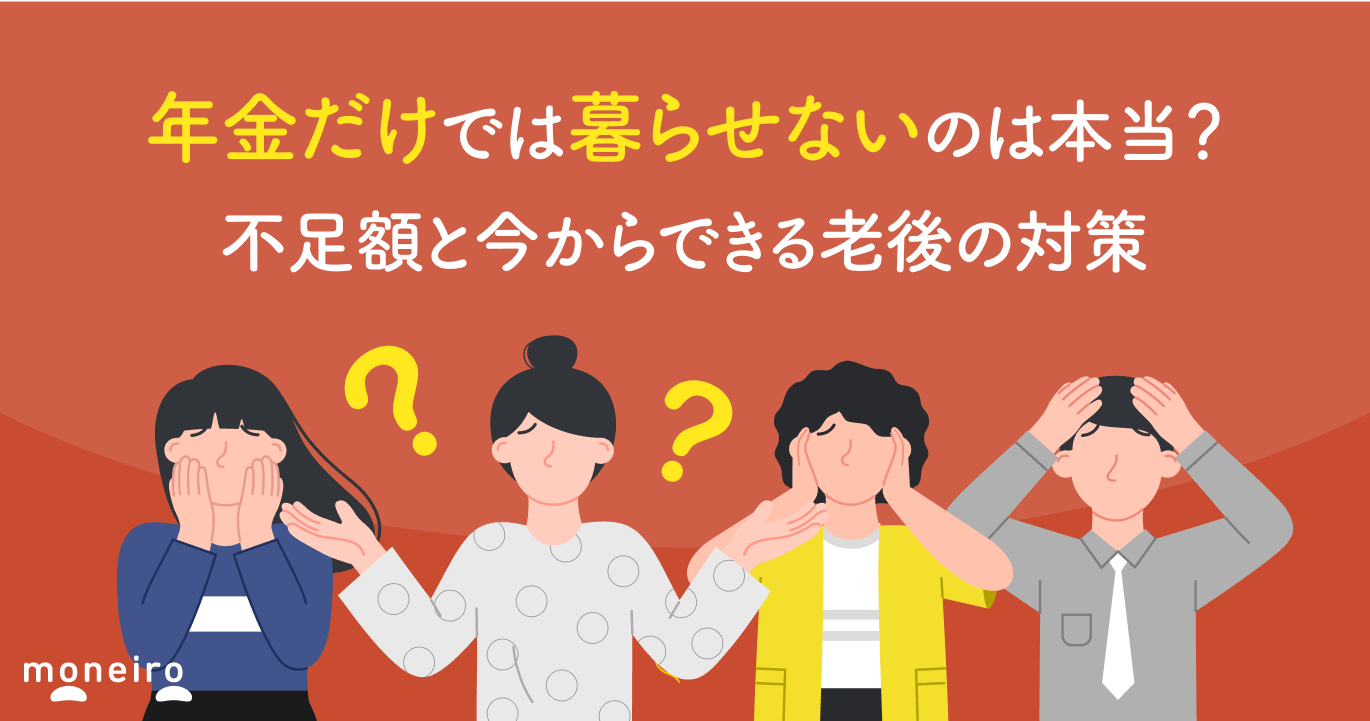
年金だけでは暮らせないのは本当?不足額と今からできる老後の対策をお金の専門家が解説
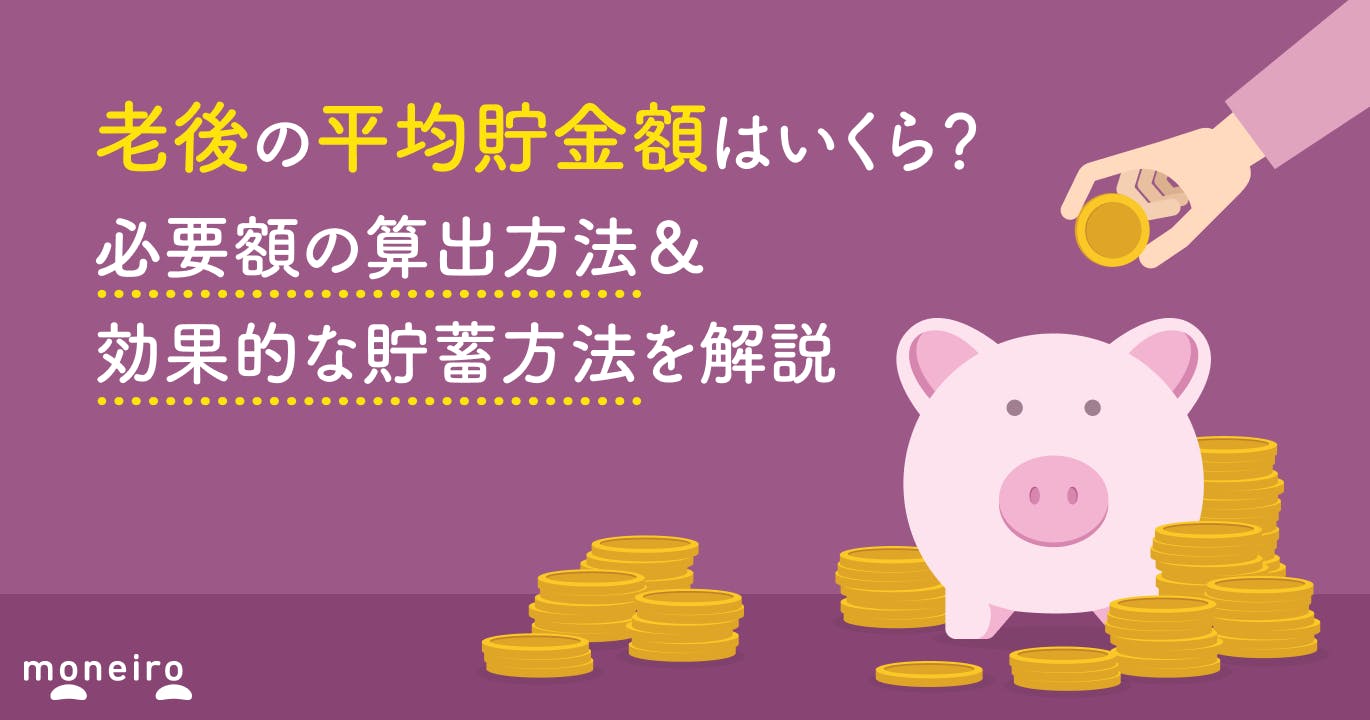
老後の平均貯金額はいくら?必要額の算出方法&効果的な貯蓄方法を解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
