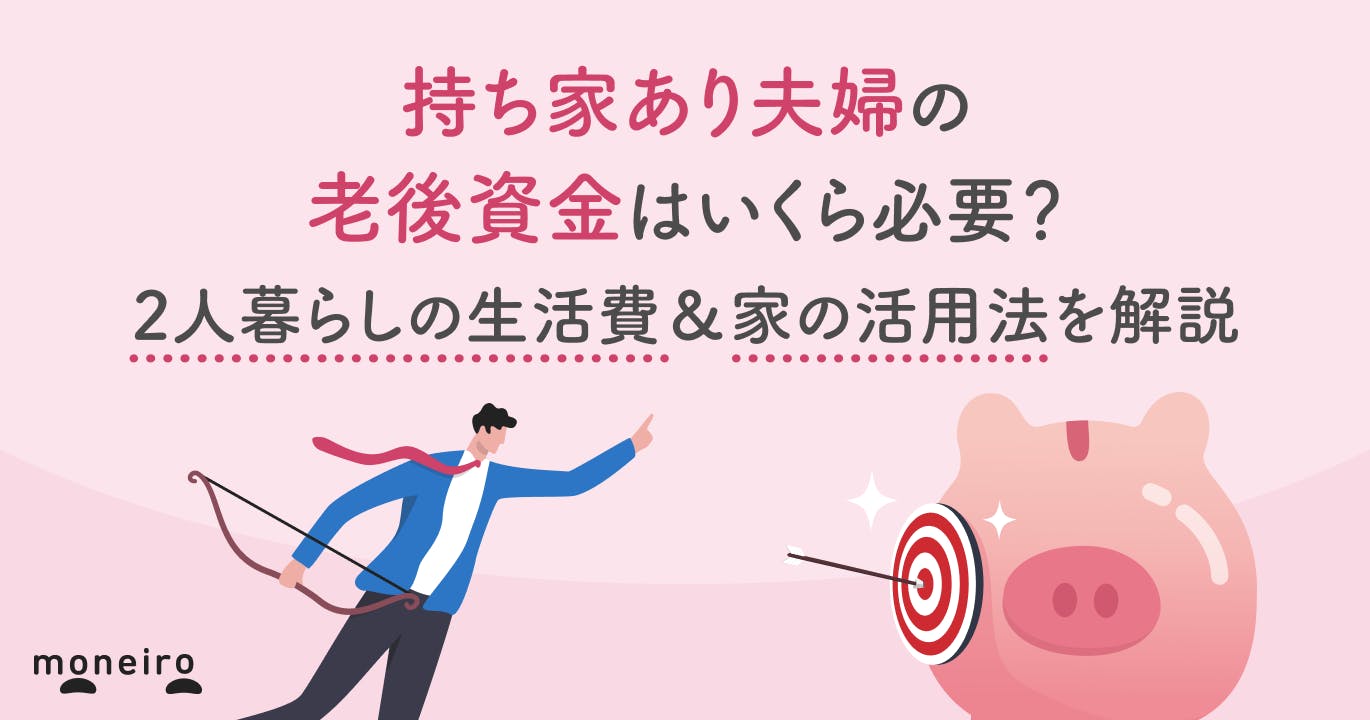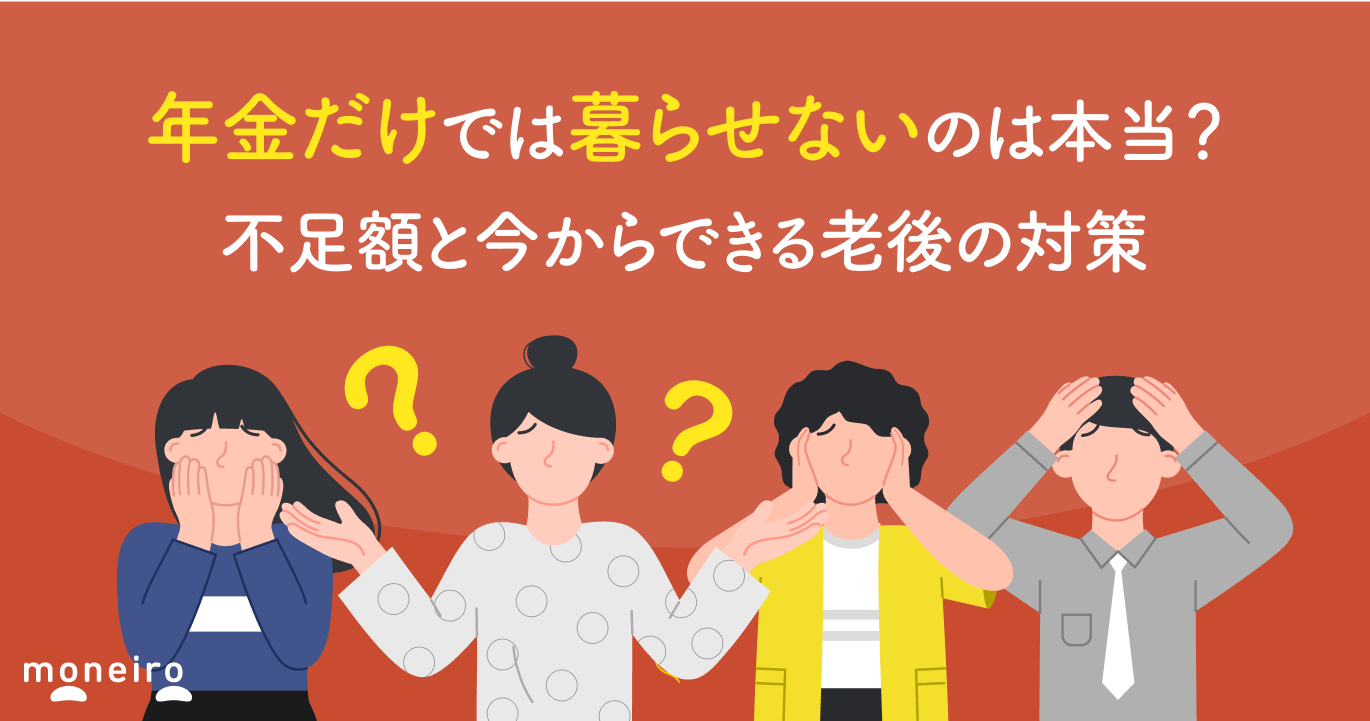
持ち家あり夫婦の老後資金はいくら必要?2人暮らしの生活費&家の活用法を解説
>>あなたに必要な老後資金はいくら?3分で診断
持ち家がある夫婦にとって、老後資金はどれくらい必要になるのでしょうか?
この記事では、公的なデータに基づき、持ち家のある高齢夫婦2人暮らしの平均的な生活費を紹介します。さらに、状況に合わせた老後資金の計算方法や、持ち家を将来にわたって賢く活用するための方法まで、具体的な情報を詳しく解説します。
- 高齢夫婦2人暮らしの平均的な生活費と持ち家だからこそかかる費用
- 老後資金の具体的な計算ステップと準備方法
- 持ち家を資産として活用する多様な選択肢
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
高齢夫婦2人暮らしの持ち家あり割合は96.5%
総務省「家計調査(家計収支編/2024年)」の「1世帯当たり1ヶ月間の収入と支出(高齢者のいる世帯)世帯主の就業状態別」をもとに、データを見ていきましょう。
高齢夫婦世帯(無職世帯)※の持家率は96.5%に達しており、持ち家を所有している割合は非常に高い水準にあります。これは、ほとんどの高齢夫婦世帯が、家賃や地代といった住居費の負担が少ない、あるいはまったくない状態で生活していることを示しています。
そのため、老後の生活設計を考える上で、住居費の割合を低く見積もることができる可能性があります。
※高齢夫婦世帯……夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦1組のみの世帯
高齢夫婦2人暮らしの平均生活費はいくら?
では実際に、住居費も含めた高齢夫婦世帯の生活費はどのくらいになるのでしょうか。同じく総務省の「家計調査 家計収支編(2024)」から詳細を見ていきましょう。
高齢夫婦世帯(無職世帯)における1ヶ月あたりの消費支出は25万8621円です。これは、食料、住居、光熱・水道、交通・通信、教養娯楽といった日常生活を送る上で必要なさまざまな費用を合計した金額です。
以下で細かな内訳を確認しましょう。
生活費の内訳
高齢夫婦世帯(無職世帯)の消費支出25万8621円の内訳は以下の通りです。
この内訳を見ると、食料費がもっとも大きな割合を占め、次いで交通・通信費、教養娯楽費、その他の消費支出が続くことがわかります。
住居費については、ほとんどの世帯が持ち家ありとなっていることもあり、平均値としては低く抑えられています。
持ち家だからこそかかる費用も
持ち家を所有している場合でも、老後にかかる費用はゼロではありません。「家計調査 家計収支編(2024)」のデータでは、住居費の項目として「設備修繕・維持」に1万4734円が計上されています。
これは、家の経年劣化に伴う修繕やメンテナンスなどの維持費用が含まれるものです。
老後も住み慣れた家で快適に過ごすためには、こうした持ち家特有の費用も計画的に準備しておくことが重要です。
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
持ち家あり夫婦に必要な老後資金を3ステップで計算
持ち家がある夫婦にとって、老後資金の必要額を把握することは非常に重要です。ここでは、老後資金の不足額(準備すべき金額)を計算するための3つのステップを解説します。自身の状況に合わせて確認しながら、明確な目標額を設定しましょう。
ステップ1.老後の支出を把握する
老後資金の計算を始める上で、最初に行うべきは、将来の支出を具体的に把握することです。先ほど紹介した平均的な生活費はあくまで目安であり、実際の生活費は家庭ごとに大きく異なります。
現在の生活費を参考にしつつ、老後に不要になるもの(住宅ローン返済など)や、逆に新たにかかる可能性のある費用(医療費、介護費用、旅行費など)を考慮して、より具体的な支出を想定しましょう。
目指すライフスタイルごとに支出を想定しておこう
どのような老後を送りたいか、どのような生活レベルを望むかによって、必要な支出は変わってきます。そのため、老後の支出を把握する際には、「最低限の生活」と「ゆとりある生活」という2つの異なるライフスタイルを想定して支出額を見積もるのがおすすめです。
「最低限の生活」は、日々の衣食住や医療費など、生活する上でどうしても必要な費用に焦点を当てたものです。一方、「ゆとりある生活」では、趣味やレジャー、旅行、社会貢献活動、孫への支援など、精神的な豊かさを追求するための費用も加味します。
両方を想定することで、老後資金の目標額に幅を持たせることができ、柔軟な資金計画を立てやすくなります。
ステップ2.老後の収入を把握する
次に、老後に見込まれる収入を具体的に把握します。主な収入源として挙げられるのが、公的年金(国民年金、厚生年金)です。年金受給額は、現役時代の加入期間や報酬額によって個人差があるため、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」などで想定される受給額を確認しておきましょう。
ステップ3.差額から不足額(準備すべき金額)を割り出す
最後に、ステップ1で把握した「老後の支出総額」から、ステップ2で把握した「老後の収入総額」を差し引いて、老後資金の不足額を割り出していきます。
例えば、老後の生活が20年間続くと仮定した場合、1ヶ月あたりの不足額に12ヶ月を掛け、さらに20年を掛けることで、総額の不足額が算出できます。
この不足額が、現役時代に準備すべき老後資金の目標額となります。
平均値で試算すると?
「家計調査 家計収支編(2024)」のデータで試算してみましょう。データによると、高齢夫婦世帯(無職世帯)の1ヶ月あたりの可処分所得22万4221円に対し「消費支出」は25万8621円となっています。これを差し引きすると毎月3万4400円の赤字となります。
仮に老後が20年続くとすると、「3万4400円 × 12ヶ月 × 20年 = 825万6000円」となり、約825万円を老後までに用意しておく必要がある、ということになります。
老後資金を準備するための方法
老後資金の不足額が明確になったら、次はその目標額を達成するための具体的な準備方法を検討しましょう。
家計の見直し&「先取り貯蓄」の実践
老後資金準備の第一歩として、現在の家計を見直し、無駄をなくすことが重要です。支出を最適化し、浮いたお金を「先取り貯蓄」に回すことで、着実に貯蓄を増やしていくことができます。
固定費の見直し
家計を見直す上で、まず着手すべきなのが固定費です。固定費は一度見直せば継続的に節約効果が得られるため、非常に効果的です。
例えば、携帯電話のプランやインターネット回線の見直し、利用していないサブスクリプションサービスの解約、保険料の見直しなどが挙げられます。これらは実行するときには手間がかかるように思えますが、一度行えば効果が持続するため、長期的な視点で見ると大きなメリットがあります。
変動費の見直し
固定費の見直しと並行して、変動費の見直しも行いましょう。変動費は、食費、交際費、趣味・娯楽費など、月によって支出額が変わる費用です。変動費の見直しは、日々の意識が重要になります。
例えば、外食を減らして自炊の回数を増やす、不必要な買い物を控える、安価なレジャーに切り替えるなどが考えられます。家計簿アプリなどを活用して、自分の変動費の傾向を把握し、無理のない範囲で節約を習慣化することが大切です。
先取り貯蓄の実践
家計の見直しで浮いたお金は、意識的に貯蓄に回す「先取り貯蓄」を実践しましょう。先取り貯蓄とは、給料が入ったらまず貯蓄分を別の口座に移す、または自動積立定期預金などを活用して、強制的に貯蓄する仕組みです。
「残ったお金」で生活することに慣れていくことで、使いすぎが減り、着実に貯蓄額を増やしていくことができます。
資産運用でお金を育てる
貯蓄だけでなく、資産運用によってお金を「育てる」ことも、老後資金準備の強力な手段となります。現在は資産運用に有利な税制優遇制度がありますので、ぜひ活用していきましょう。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、投資で得た利益(運用益や配当金など)が非課税になる制度です。通常、投資の利益には20.315%の税金がかかりますが、NISA口座内で投資を行えば、上限1800万円の非課税投資枠の範囲内で利益が非課税となります。
NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの投資枠があり、特につみたて投資枠は長期目線での資産形成に適しています。
40代、50代という年代からでも、コツコツと積立投資を行うことで、非課税や複利の恩恵を享受しながら老後資金の準備を進めることができます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で掛金を出して自分で運用する私的年金制度です。掛金は全額が所得控除の対象となるため、所得税や住民税の負担を軽くできるのが大きな魅力です。さらに、運用益も非課税で再投資され、受け取るときにも退職所得控除や公的年金等控除といった優遇を受けられます。
ただし、原則60歳までは引き出せないため、資金の自由度は低いのがデメリットです。
自由に使えるお金を増やしたいならNISA、節税しながら老後資金をしっかり準備したいならiDeCo、というように目的に合わせて選ぶのがよいでしょう。
個人年金保険
個人年金保険は、生命保険会社が扱う私的年金の一つで、毎月一定の保険料を積み立てていき、契約時に決めた年齢(たとえば60歳や65歳)から年金として受け取れる仕組みです。
公的年金にプラスして老後資金を準備できるほか、条件を満たす契約であれば「個人年金保険料控除」が適用され、所得税や住民税の軽減につながるのもメリットです。受け取り方も確定年金や終身年金などから選べるため、ライフプランに合わせて設計できます。
ただし、途中解約では元本割れする可能性があったり、インフレに弱いといったデメリットもあるので注意が必要です。
定年以降も働くことを検討
老後資金を確保するための有効な選択肢の1つとして、定年以降も働き続けることを検討することも挙げられます。収入を得ることで、年金だけでは不足しがちな生活費を補うことができ、貯蓄を取り崩すペースを遅らせることが可能です。また、社会とのつながりを持ち続けることで、心身の健康維持にもつながるというメリットもあります。
長く働ける場合は年金の繰下げ受給も検討できる
もし健康状態が良好で、定年以降も長く働き続けることが可能であれば、公的年金の「繰下げ受給」を検討するのも選択肢に入ります。
年金は原則として65歳から受給できますが、希望すれば66歳以降に繰り下げて受け取ることもできます。年金額は1ヶ月繰り下げるごとに0.7%増額され、最大75歳まで繰り下げると、年金額が最大で84%も増えることになり、その後の生活の大きな助けになります。
持ち家を資産として活用する方法も
老後資金の準備には、現在お住まいの持ち家を「資産」として活用するという選択肢もあります。住宅ローンを完済していれば、住居費の負担を大きく軽減できるだけでなく、必要に応じて持ち家から資金を得ることも可能です。ここでは、持ち家を活用する主な方法を3つご紹介します。
売却して住み替える
持ち家を資産として活用するもっとも直接的な方法が、現在の家を売却し、よりコンパクトな住居や、生活費の安い地域に住み替えることです。売却によって得た資金を老後資金に充当できるほか、住居費(固定資産税や維持費など)も軽減できる可能性があります。
特に、都心部に大きな家を持っている場合や、子どもの独立によって広い家が不要になった場合などに有効な選択肢となるでしょう。
住み替え先の検討はもちろん、売却にかかる費用や税金、そして売却益の活用計画を事前にしっかり立てることが重要です。
リースバック
リースバックとは、持ち家を不動産会社などに売却した後も、賃貸契約を結んでそのまま住み続けられる仕組みです。売却によってまとまった資金を確保しつつ、住み慣れた家で生活を続けられるため、「住まいを手放したくないが現金が必要」という場合に役立ちます。
売却後は家賃の支払いが必要になりますが、固定資産税や修繕費などの維持管理費は不要になるほか、契約によっては将来的に買い戻せるオプションが設けられている場合もあります。
ただし、売却価格が市場価格より低めに設定されることや、家賃が相場より高くなるケースもあるため、利用の際は契約条件をよく確認することが大切です。
リバースモーゲージ
リバースモーゲージは、自宅を担保にすることで、住み続けながら生活資金を融資として受け取れる仕組みです。返済は契約期間中は利息のみを支払い、元金は契約者が亡くなった際や契約終了時に、自宅を売却して一括返済するのが一般的です。これにより、自宅を手放さずに老後の生活費などをまかなえる可能性があります。
ただし、担保となる不動産の評価額や契約者の年齢に制限が設けられている場合が多く、金利の変動や不動産価格の下落によっては利用できる金額が減るリスクもあります。
老後の必要額が分かる診断ツールを活用しよう
老後資金の必要額や、その準備方法について具体的なイメージを持つためには、診断ツールを活用するのも効果的です。マネイロの「老後の必要額診断」では、簡単な質問に答えていくだけで、老後に必要となる資金の概算や、そのお金を用意するための適切な運用方法などを知ることができます。
無料で手軽に利用できるので、まずは一度、現在の状況を踏まえて診断してみるとよいでしょう。
>>あなたの不足額はいくら?老後の必要額を診断する
まとめ
持ち家がある夫婦にとって、老後資金の計画は、住居費が抑えられる分、賃貸世帯とは異なる特徴があります。しかし、「家計調査 家計収支編(2024)」が示すように、高齢夫婦世帯(無職世帯)では、は平均して月々3万4000円程度の不足が生じている現状があります。そのため、老後に向けて計画的な準備が必要です。
老後資金の準備においては、以下のステップと方法を検討することが重要です。
- 支出の把握:目指すライフスタイル(最低限の生活からゆとりある生活まで)に合わせた老後の支出額を具体的に想定
- 収入の把握:年金受給額をはじめ、退職金や個人年金、定年後の収入など、老後に見込まれる収入源を確認
- 不足額の算出:支出と収入の差額から、準備すべき老後資金の目標額を明確に
目標額達成のためには、家計の見直しによる「先取り貯蓄」の実践や、NISA・iDeCoといった「資産運用」でお金を育てること、そして定年後も働き続けることや年金の「繰下げ受給」を検討することが有効です。
また、リースバックやリバースモーゲージなど、持ち家を活用するという手段も知っておくことで「いざ」という時の選択肢になります。自分自身の状況に合った最適な老後資金計画を立て、安心で豊かなセカンドライフを目指しましょう。
>>あなたの老後に必要な金額はいくら?3分で診断する
老後資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
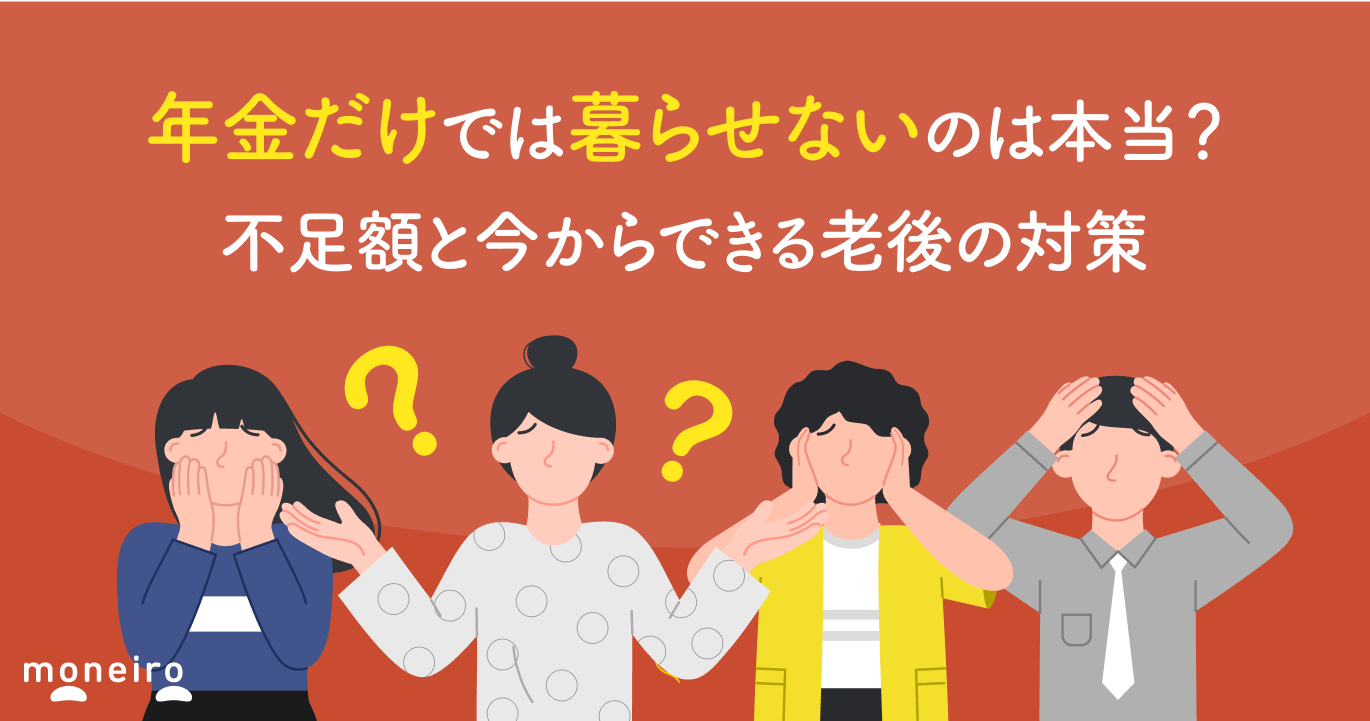
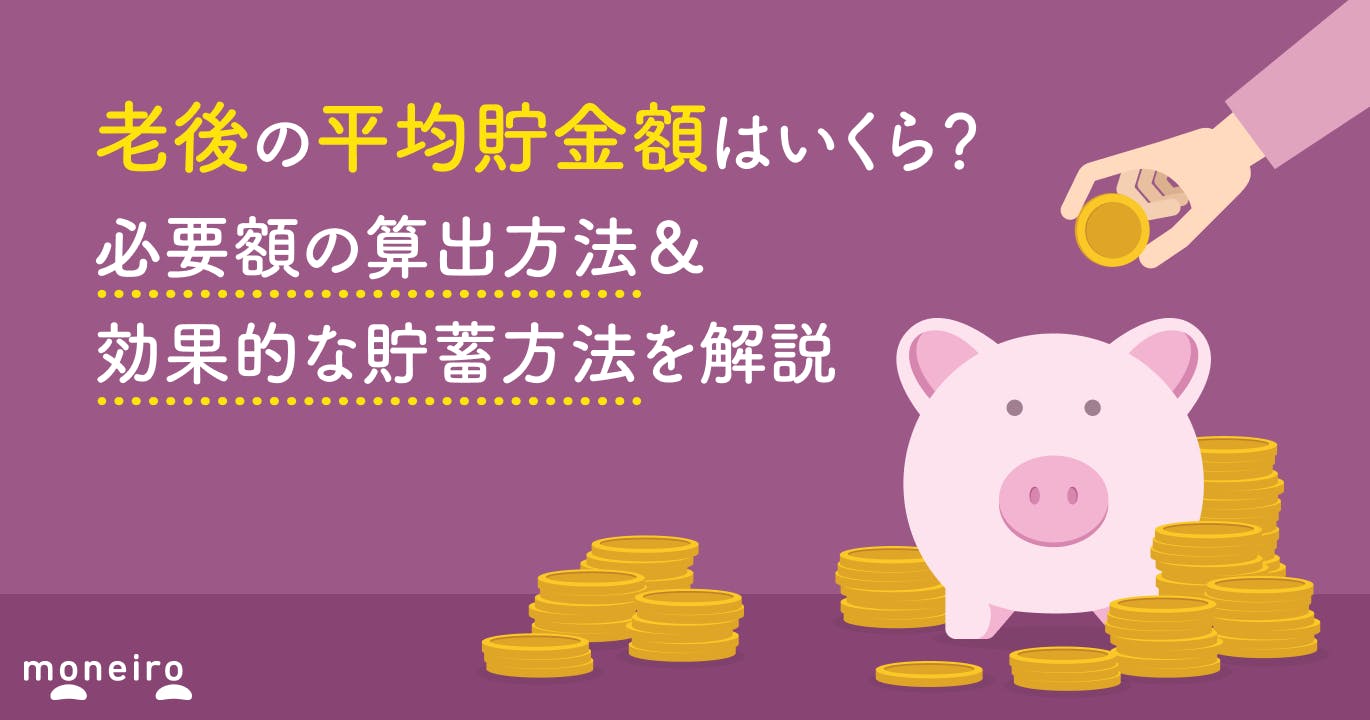
老後の平均貯金額はいくら?必要額の算出方法&効果的な貯蓄方法を解説

老後に必要なお金はいくら?単身・夫婦の世帯タイプ別必要額を解説

老後の生活費はいくらかかる?一人暮らし・夫婦の平均は?データをもとに解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。