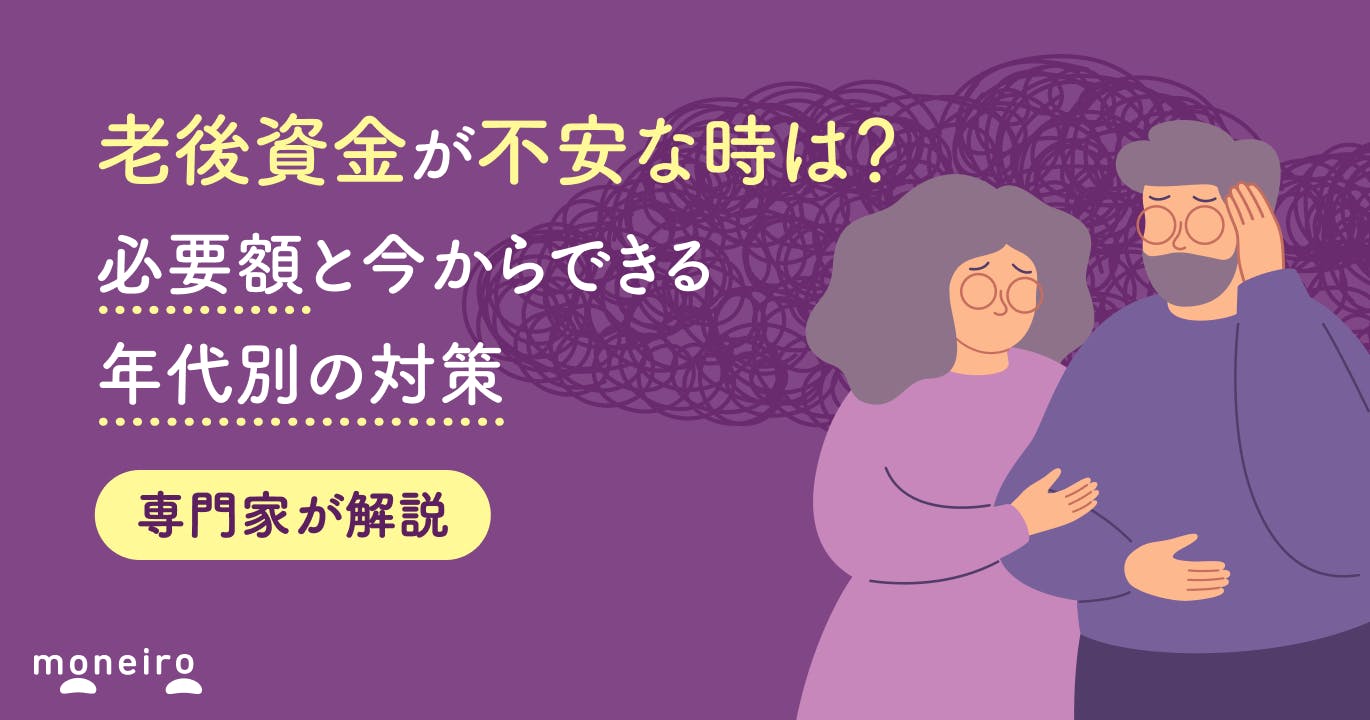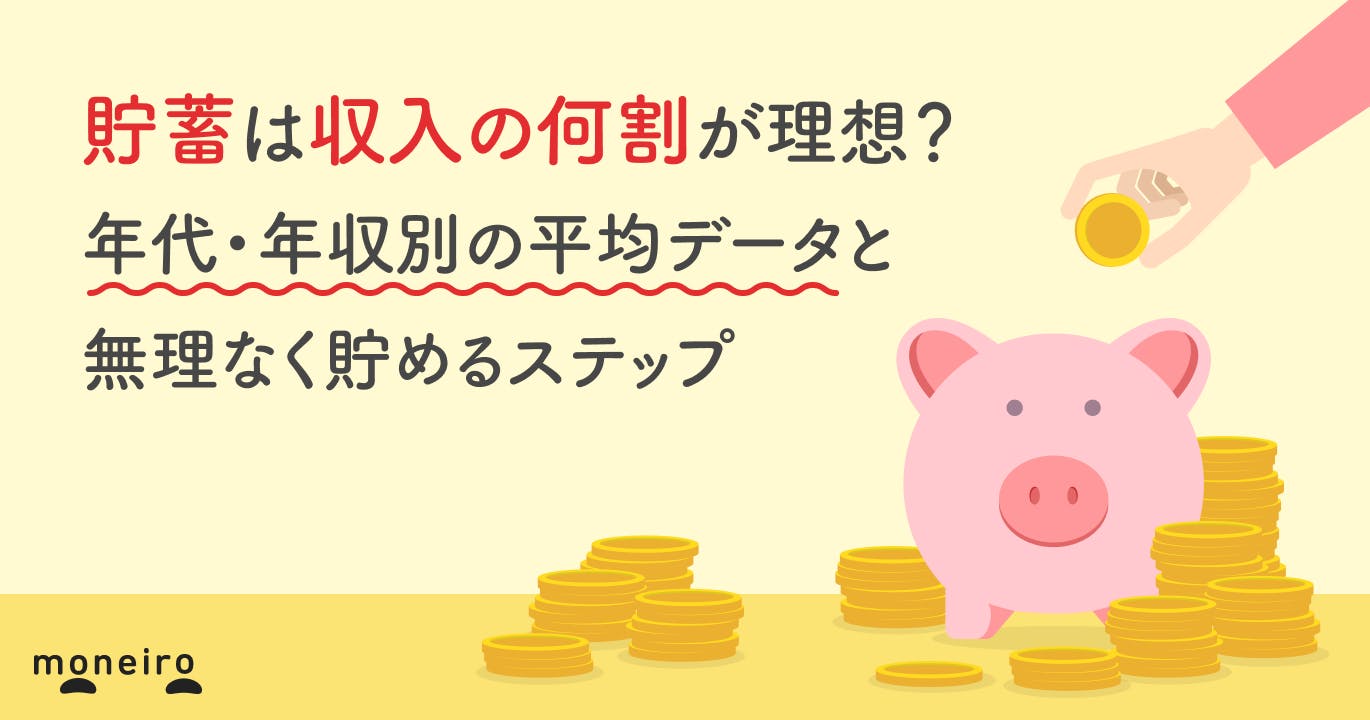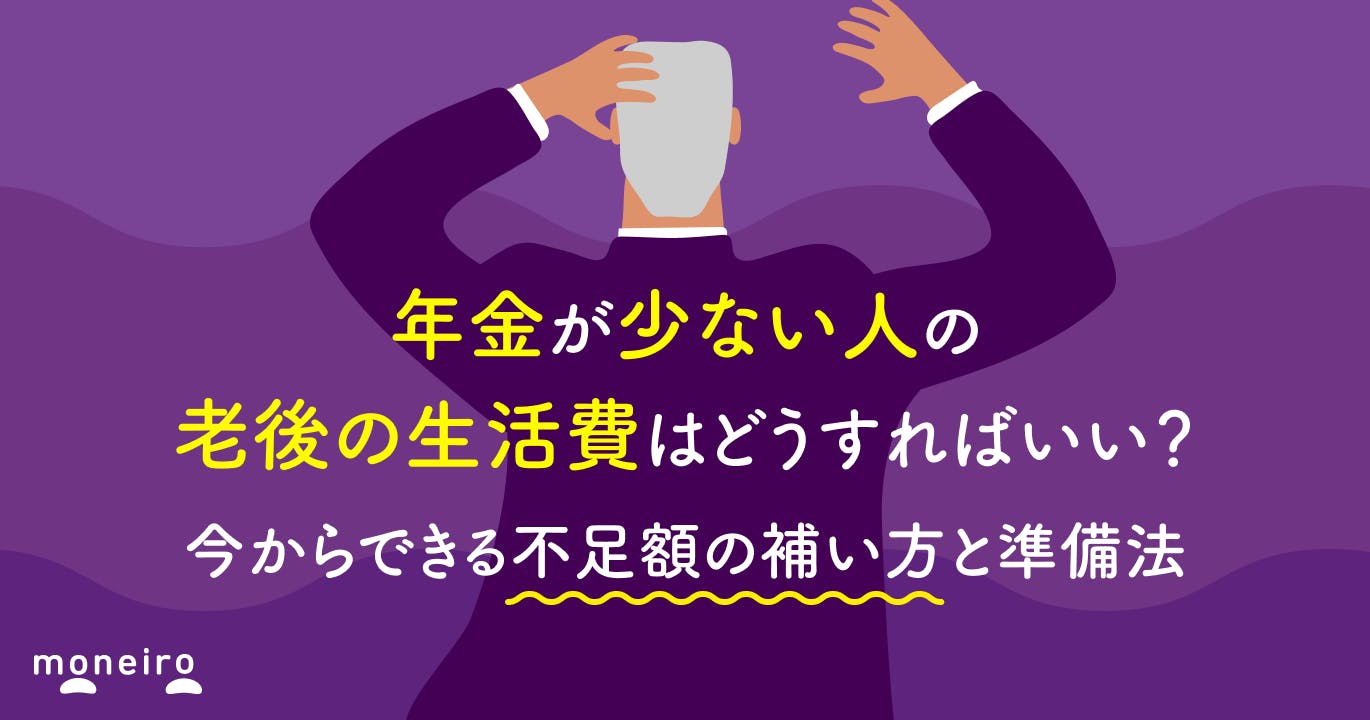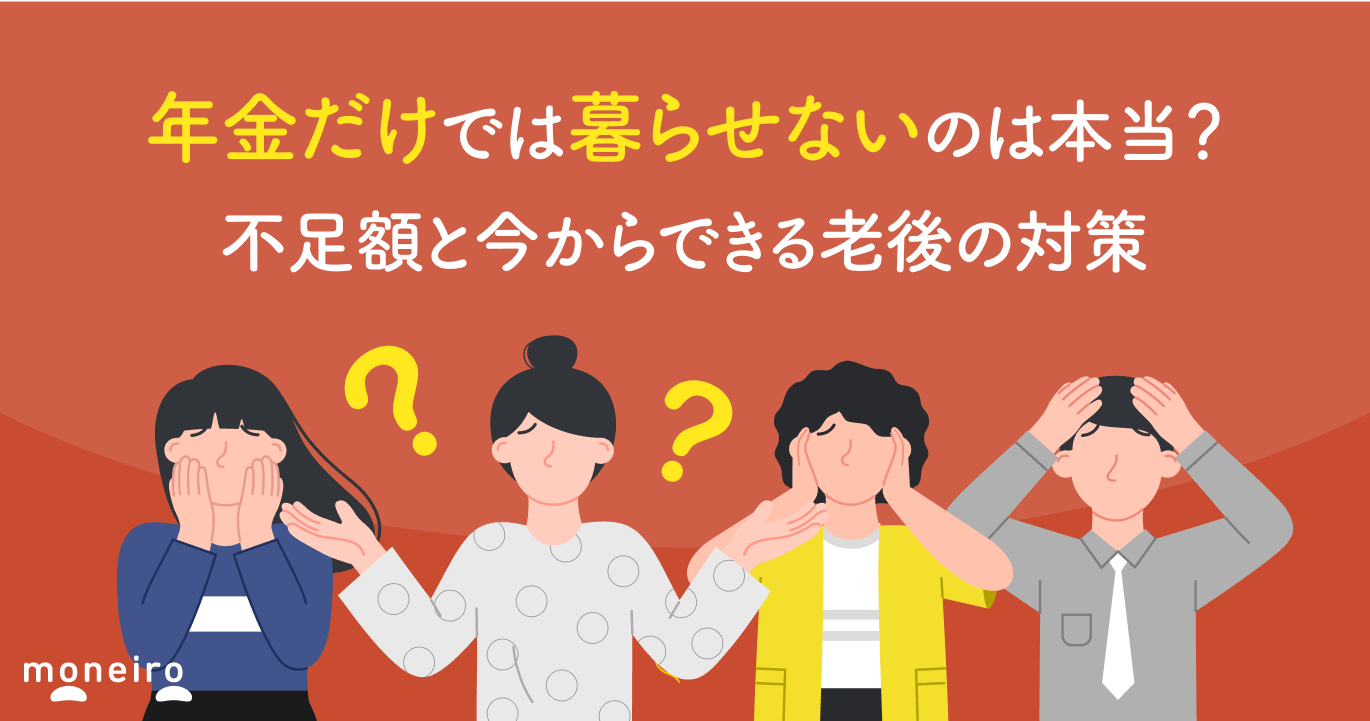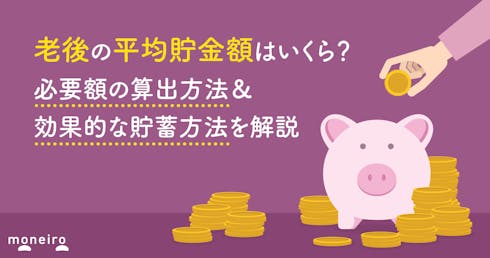
老後資金はどうやって準備する?必要資金の計算方法と準備方法を解説
>>あなたの老後に必要な金額はいくら?3分で診断
「人生100年時代」ともいわれる現代において、老後を安心して暮らすためには、公的年金に加えて自分自身で老後資金を準備することが重要です。
この記事では、老後資金準備の必要性、必要な金額の目安、そして具体的な準備方法を分かりやすく解説します。早めの計画で、豊かな老後を実現するための第一歩を踏み出しましょう。
- 老後資金の準備が必要な3つの理由
- 公的年金や老後の平均生活費の目安
- 老後資金を効率的に準備するための具体的な方法
老後資金の準備が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、今から準備を始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶40代からの老後資金作り:40代が目指すリスクとリターンのバランスとは?
▶50代からの老後資金作り:50代からでも間に合う?堅実な資産の増やし方
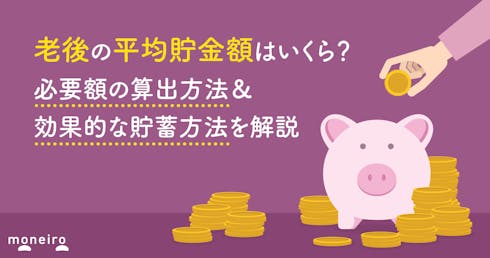

なぜ老後資金の準備が必要?3つの理由
老後資金の準備は、現代社会を生きる私たちにとって避けては通れない課題です。その背景には、主に以下の3つの理由が挙げられます。これらの理由を理解することで、老後資金準備の重要性をより深く認識できるでしょう。
理由1.公的年金だけでは生活費を賄えない可能性がある
多くの人が頼りにしている公的年金だけでは、老後の生活費を十分に賄うことが難しくなっているのが現状です。
これは、少子高齢化の進展や社会保障制度の持続可能性が課題となっているためです。年金がいくらもらえるのか、そしてどれくらい生活費が不足するのかを具体的に見ていきましょう。
年金はいくらもらえる?
公的年金は、主に国民年金と厚生年金の2種類があり、加入期間や収入によって受給額は異なります。厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢基礎年金の平均月額は5万7700円(年額69万2400円)、老齢厚生年金(老齢基礎年金含む)の平均月額は14万7360円となっています。
夫婦2人世帯で、夫が老齢基礎年金を、妻が国民年金を受給するモデルケースで見てみましょう。65歳以上の男性の老齢厚生年金の平均月額は16万9484円、国民年金の平均月額は月額5万7700円です。これを合計すると22万7184円となり、これが公的年金で得られる収入の目安となります。
これらの金額は、あくまで平均であり、実際の額は個々人の状況によって大きく異なります。将来のシミュレーションを行う場合は必ず自身の年金見込み額を確認するようにしましょう。
不足する生活費はいくら?
総務省の「家計調査(家計収支編/2024年)」によると、夫65歳以上・妻60歳以上の夫婦の「高齢夫婦世帯(無職世帯)」の1ヶ月あたりの消費支出は25万8621円となっています。これを上記の年金収入の例と合わせて考えると、以下のような計算式になります。
(収入)22万7184円 - (支出)25万8621円 =(不足する額)-3万1437円
年額にすると上記の12ヶ月分で37万7244円、老後が25年あると仮定すると、943万1100円が老後に必要な金額であると算出できます。
>>あなたの老後に必要な金額はいくら?3分で診断
理由2.「人生100年時代」で老後が長期化
現代は「人生100年時代」と呼ばれるほど、平均寿命が伸びてきています。老後が長期化するということは、それだけ長く生活費が必要になるということです。
例えば、65歳で引退し、90歳まで生きると仮定すると、25年間の老後生活を送ることになります。さらに長生きして100歳まで生きるなら、35年間の老後生活を送ることになり、その分、準備すべき資金も増加します。長寿化は喜ばしいことですが、その分、計画的な資金準備がより一層求められることになります。
理由3.物価上昇によるお金の価値の目減り
老後資金を準備する上で見落としがちなのが、物価上昇のリスクです。物価が継続的に上昇していくと、お金の価値は相対的に下がっていきます。
実際に多くの人が実感している通り、日本でも近年物価上昇が続いています。総務省が発表する「消費者物価指数」によると、2020年を100としたときの2025年7月の総合指数は、111.9となっており、5年間で約12%もの物価上昇があったことを示しています。
貯金としてただお金を置いておくだけでは、将来的にその購買力が低下してしまうリスクがあることを認識しておく必要があるでしょう。特に老後資金は、使うまでに長い年月があるため、このインフレによる影響を特に大きく受けます。
そのため、単に貯蓄するだけでなく、インフレに負けないように、お金の価値を維持・増加させるための対策も考える必要があります。
老後資金の準備はいつから始めるべき?
老後資金の準備は「早ければ早いほどよい」 といえます。
まず、早く始めれば始めるほど、目標とする老後資金を達成するために必要な毎月の積立額を少なくすることができます。これにより、現在の生活を圧迫することなく、無理なく老後資金を準備することが可能になります。
また、早くから準備を始めることで、月々の貯蓄額を少なく抑えながら資産形成を進めることができます。また、資産運用を行う場合には、早く始めることによって複利効果の恩恵を最大限に受けることが可能になります。
投資で得た利益を元本に加えて再度投資することで、雪だるま式に資産が増えていく効果を指します。運用期間が長ければ長いほど、この複利効果は大きくなります。
例えば、毎月3万円を年利3%で積み立て運用した場合、20年間では元本720万円に対し、約263万円の運用益が期待できますが、30年間では元本1080万円に対し、約668万円の運用益が期待でき、運用益が倍以上になることがわかります。
※シミュレーション参照:つみたてシミュレーター|金融庁
40代・50代でも遅くはない
40代や50代で、「今から準備を始めても遅いのでは」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、40~50代からでも「遅すぎる」ということはありません。むしろ収入のピークを迎え、教育費や住宅ローンの負担が一段落し始める世代だからこそ、老後資金に本格的に取り組みやすい時期です。
効率よく老後資金を準備していくため、次の項目で解説する方法を取り入れながら、着実な資産形成を目指していきましょう。
老後資金の準備が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、今から準備を始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶40代からの老後資金作り:40代が目指すリスクとリターンのバランスとは?
▶50代からの老後資金作り:50代からでも間に合う?堅実な資産の増やし方
今から始める!老後資金を準備する方法
老後資金を準備する方法は多岐にわたりますが、ここでは特におすすめの具体的な方法をいくつかご紹介します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の状況に合った方法を選びましょう。
先取り貯蓄・財形貯蓄
老後資金準備の基本となるのが「先取り貯蓄」です。これは、給与が支給されたら、まず一定額を貯蓄用口座に移し、残ったお金で生活するという方法です。「給与天引き」や「自動積立」の設定をすることで、意識せずとも着実に貯蓄が増えていきます。
また、会社員で制度を利用できる場合は「財形貯蓄制度」の活用も検討してみましょう。財形貯蓄には、住宅購入を目的とした「財形住宅貯蓄」と、老後資金を目的とした「財形年金貯蓄」があります。これらは一定の要件を満たせば、両者を合わせて 550万円までの利子等が非課税 となるメリットがあります。
さらに、給与からの天引きで自動的に積み立てられるため、貯蓄が苦手な人でも無理なく継続できるのが特徴です。
退職金や年金制度の活用
老後資金の大きな柱となり得るのが、退職金や公的年金制度の賢い活用です。特に公的年金の受給開始時期を調整することで、生涯にわたる受給額に大きな影響を与えることがあります。
繰上げ受給
公的年金の繰上げ受給とは、本来の年金受給開始年齢である65歳よりも早く(60歳から64歳までの間に)年金を受け取り始める制度です。早い段階から生活費等の資金を確保したい場合に有効です。
ただし、早く年金を受け取れるというメリットがある一方で、繰り上げた月数に応じて年金額が減額されるというデメリットがある点には注意が必要です。減額率は1ヶ月の繰上げあたり0.4%で、例えば60歳で受給開始した場合、最大で24%(昭和37年4月2日以降生まれの場合)の減額となります。減額された年金額は生涯変わらないため、慎重な検討が必要です。
繰下げ受給
公的年金の繰下げ受給とは、本来の年金受給開始年齢である65歳よりも遅く(66歳以降に)年金を受け取り始める制度です。この制度を利用すると、繰り下げた月数に応じて年金額が増額されるという大きなメリットがあります。
増額率は1ヶ月の繰下げごとに0.7%となっており、最大75歳まで繰り下げた場合、月額84%の増額になります。この増額率は生涯適用されるため、長生きするほど総受給額が増えていくことになります。健康状態に自信がある人や、年金受給まで別の収入や貯蓄で生活を賄える人に向いている制度です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金制度です。自分で掛金(拠出金)を積み立てて運用し、その運用成果によって将来受け取る年金額が決まる制度です。 iDeCoの最大のメリットは、以下のような税制優遇が受けられることです。
- 掛金が全額所得控除の対象:毎年支払う掛金が全額所得控除となるため、所得税・住民税が軽減されます。
- 運用益が非課税:通常、投資の運用益には20.315%の税金がかかりますが、iDeCoで得た運用益は非課税です。
- 受給時にも控除あり:老齢給付金を受け取る際にも、公的年金等控除や退職所得控除が適用されます。
ただし、原則60歳まで資金を引き出せないというデメリットもある点には注意が必要です。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、投資から得られる利益(売却益や配当金)が非課税になる制度です。iDeCoと同様に、税制優遇を受けながら資産形成ができるため、老後資金準備にも活用できます。
NISAには、年間投資枠が設定されており、その範囲内で投資を行った場合、得られた利益は非課税となります。2024年からの新しいNISAでは年間投資枠が大幅に拡大され、非課税保有限度額も増えました。非課税保有期間も無期限化され、より長期的な資産形成に適した制度となっています。
税制優遇の面ではiDeCoのほうが優れていますが、NISAには、「いつでも資金を引き出せる」というメリットがあります。自由度の高い資産運用ができるため、老後資金形成に有効な手段の1つといえるでしょう。
個人年金保険
個人年金保険は、保険会社に保険料を積み立て、老後に年金として受け取る民間の保険商品です。公的年金だけでは不足しがちな老後資金を補う手段として利用されています。
メリットは「計画的に老後資金を準備できること」と「税制優遇を受けられること」です。定期的に保険料を支払う仕組みにより強制的に貯蓄でき、将来の年金額があらかじめ確定しているタイプなら、老後の資金計画を立てやすくなります。さらに、所定の要件を満たせば個人年金保険料控除の対象となり、所得税や住民税の負担を軽減できます。
一方で、途中解約による元本割れのリスクもあります。そのため契約時には、各保険会社や商品の特徴を比較し、自身のライフプランに合ったものを選ぶことが大切です。
>>あなたに向いている資産形成方法は?簡単な質問に答えてサクッと診断
老後も働き続ける
老後資金の準備として、貯蓄や投資だけでなく、「老後も働き続ける」という選択肢も有効です。
老後も働き続けるメリットは、「収入を得ることで生活費の不足を補える」ことと、「年金の受給開始を繰り下げることができ、将来受け取る年金額を増額できる」ことです。
また、働くことで社会参加の機会が得られ、生きがいや健康維持にもつながるでしょう。自身の健康状態や体力、これまでの経験などを考慮し、無理のない範囲で働き続けることを検討してみるのもよいでしょう。
老後資金準備でよくある質問
老後資金準備に関して、よくある質問や注意点をまとめました。不安や疑問を解消し、よりスムーズに準備を進めるための参考にしてみてください。
Q. 貯金がまったくない場合はどうすればいい?
貯金がまったくない場合でも、老後資金の準備は今すぐに始めることができます。まずは、以下のステップで現状を把握し、対策を立てましょう。
- 家計の現状を把握する:毎月の収入と支出を詳細に記録し、何にいくら使っているかを把握します。家計簿アプリなどを活用すると便利です。
- 無駄な支出を見直す:固定費(通信費、保険料など)や変動費(食費、娯楽費など)から、削減できる項目がないか検討します。例えば、格安SIMへの変更や、不要なサブスクリプションの解約などが考えられます。
- 少額からでも積立を始める:まずは月5000円や1万円といった無理のない金額からでも、先取り貯蓄やiDeCo、NISAでの積立を始めましょう。早く始めることで複利効果の恩恵を受けやすくなります。
- 収入を増やす方法を検討する:副業やスキルアップによる昇給、転職など、収入を増やす選択肢も視野に入れます。
- 専門家に相談する:必要に応じて、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、具体的なアドバイスを受けることも有効です。
Q. 老後の平均貯蓄額はどれくらい?
金融広報中央委員会が2024年に実施した「家計の金融行動に関する世論調査」によると、60代の2人以上世帯で金融資産を保有している世帯の平均貯蓄額は2581万円、中央値は1140万円で、単身世帯の場合は平均貯蓄額が2363万円、中央値は960万円となっています。
また、70代では、2人以上世帯の平均貯蓄額は2450万円、中央値は1205万円で、単身世帯では平均貯蓄額が2257万円、中央値は1000万円となっています。
平均値と中央値に大きな差がありますが、一部の富裕層が平均値を引き上げている可能性が高く、中央値のほうがより多くの世帯の実情に近いと考えられます。
また、この平均値や中央値はあくまで目安であり、自分自身のライフスタイルや理想とする老後生活に必要な金額を計算することが重要です。
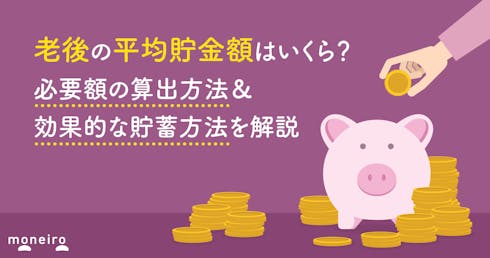
Q. 老後にかかる生活費はいくらくらい?
総務省の「家計調査(家計収支編/2024年)」によると、老後にかかる生活費は、単身世帯で月14万9286円、夫婦2人世帯で25万8621円となっています。ただし、これは平均値であり、持ち家の有無や、介護・医療費の大小、老後にどれくらいゆとりをもって暮らすかによっても変わってきます。
上記の金額を参考にしつつ、現在の生活費も考慮して、実際に老後にどれくらいの生活費が必要かを自分でシミュレーションしてみることが大切です。
まとめ
「人生100年時代」において、老後資金の準備は誰もが直面する重要な課題です。公的年金だけでは生活費を賄いきれない現実、長期化する老後、そしてインフレによるお金の価値の目減りという3つの理由から、自助努力による資金準備が不可欠です。
老後資金の準備は、早く始めれば始めるほど複利効果の恩恵を受け、無理のない積立で大きな資産形成が期待できます。40代や50代からでも、家計の見直しや働き方の検討、税制優遇のあるiDeCoやNISA、個人年金保険の活用、そして公的年金(繰上げ受給・繰下げ受給)の賢い選択など、多様な方法で今からでも十分に対応可能です。
まずは、ご自身の老後生活の目標を明確にし、必要な老後資金を計算してみましょう。そして、この記事で紹介した具体的な準備方法の中から、自分の状況に合ったものを選択し、今日から一歩を踏み出すことが大切です。老後資金準備は、未来の自分への大切な投資です。計画的に取り組むことで、安心して豊かな老後を迎えることができるでしょう。
>>あなたの老後に必要な金額は?3分で診断
老後資金の準備が気になるあなたへ
老後にお金で困らないために、今から準備を始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶40代からの老後資金作り:40代が目指すリスクとリターンのバランスとは?
▶50代からの老後資金作り:50代からでも間に合う?堅実な資産の増やし方
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。