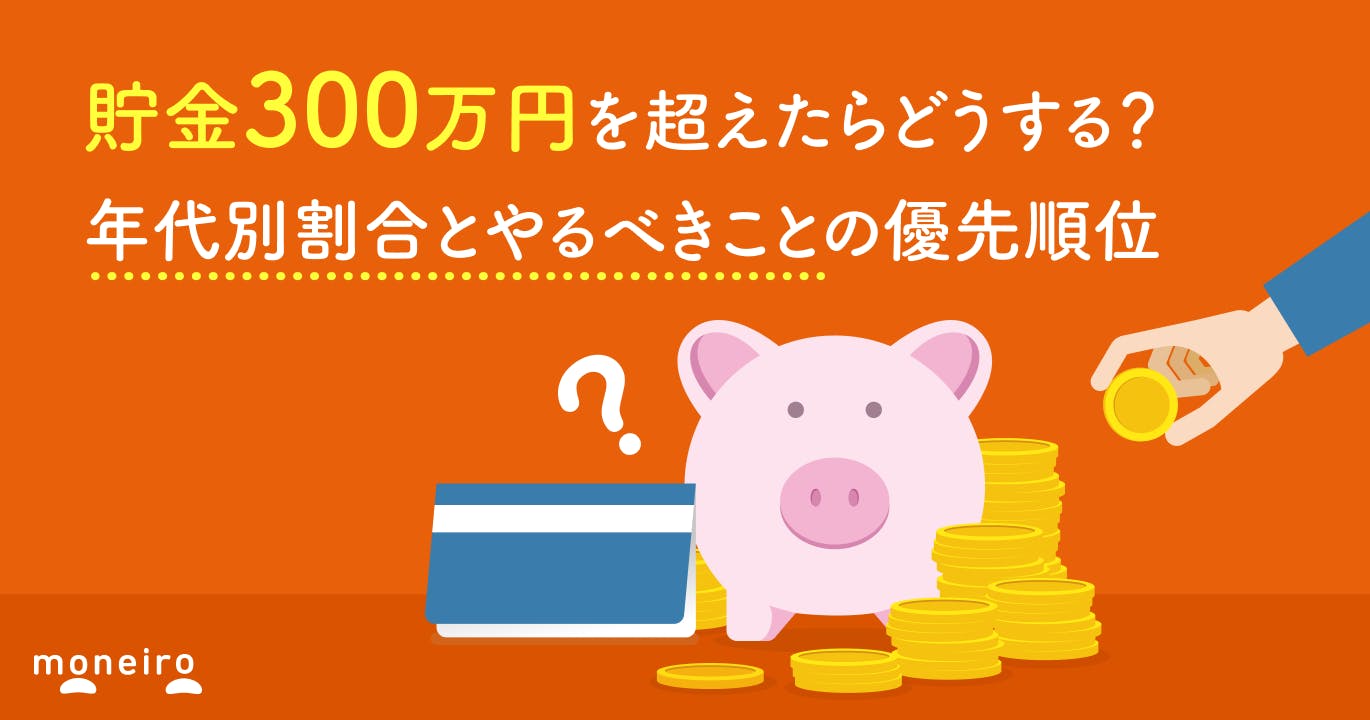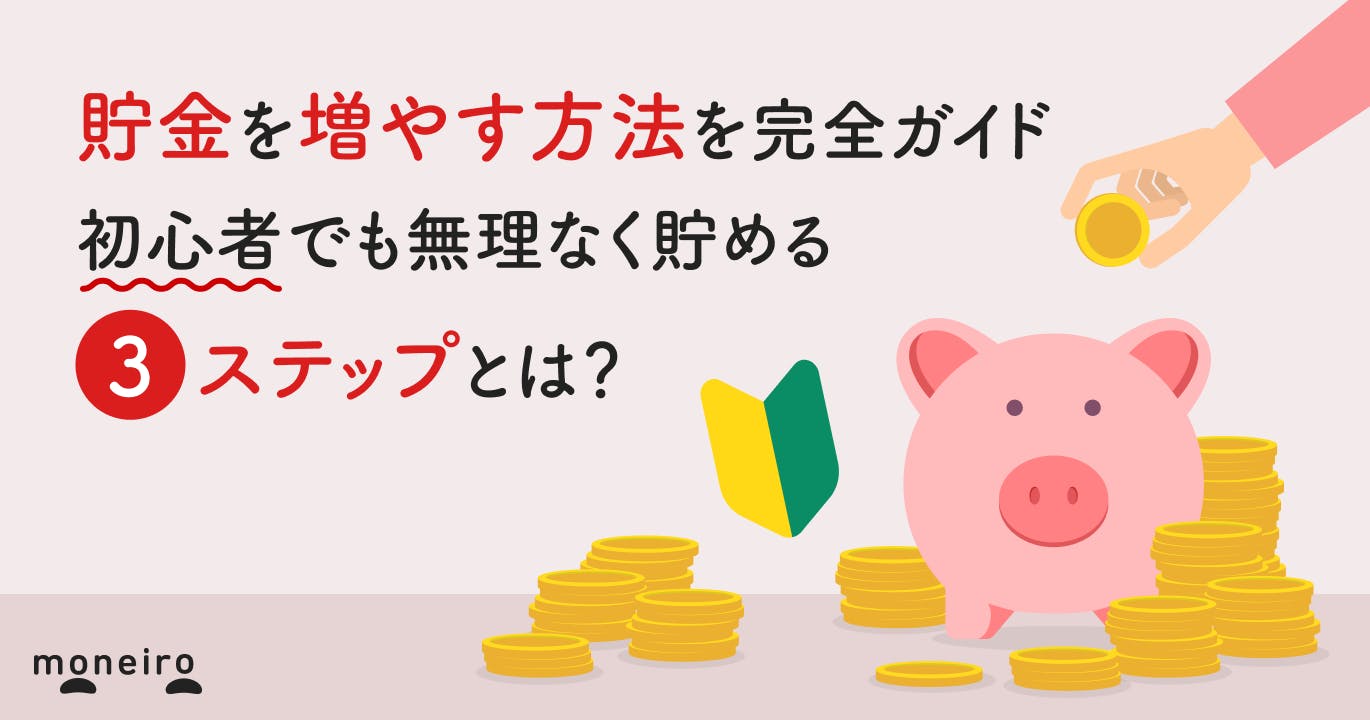
貯金300万円を超えたらどうする?年代別割合とやるべきことの優先順位
≫今の貯金で足りる?あなたの将来の不足額をチェック
貯金が300万円を超えたら、「次に何をすべきか」悩む方も多いでしょう。300万円は、資産形成における重要な通過点であり、ここからが本格的な資産運用のスタートラインです。
本記事では、まず金融広報中央委員会のデータに基づき、年代別の平均貯金額と比較して「貯金300万円の現在地」を確認します。次に、資産を守り、増やすための具体的な優先順位や、さらに次の目標・1000万円への道筋を解説します。
- 年代別の金融資産300万円以上を保有する世帯割合
- 貯金300万円達成後、次に取るべき行動と優先順位
- 1000万円という次の目標を目指すための資産運用戦略
将来の資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
貯金300万円は多い?少ない?年代・世帯別の平均貯金額と比較
貯金300万円という金額が、自身の年代や世帯構成において「多い」のか「少ない」のかを把握することは、次の資産運用戦略を立てる上で重要です。金融広報中央委員会が公表した「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」のデータをもとに、単身世帯と2人以上世帯の状況を比較してみましょう。
※なお、当調査における「金融資産」には、現金の他、株式や投資信託、債券、生命保険などの資産が含まれます
単身世帯
単身世帯における金融資産保有額(金融資産を保有していない世帯を含む)を見ると、全体の平均値は989万円、中央値は100万円です。平均値が中央値を大きく上回っていることから、一部の富裕層が平均値を押し上げていることが分かります。貯金300万円という金額は、中央値と比較すると高い水準にあるといえるでしょう。
また、年代別に見ると、金融資産保有額が300万円以上の単身世帯の割合は以下の通りです。
これを見ると、20歳代の単身世帯で300万円以上の資産を保有しているのは2割以下で少数派であることが分かります。
また、30~50歳代でも、大体3人に1人の割合となっています。また、中央値を見ると、50歳代までは100万円以下の金額となっており、300万円は十分に上位の資産であることが分かります。
2人以上世帯
2人以上世帯では、金融資産保有額の全体平均値は1374万円、中央値は350万円です。単身世帯と比較して、平均値・中央値ともに高くなる傾向があります。貯金300万円は、この世帯の中央値(350万円)にほぼ近い、重要な水準です。
年代別の300万円以上の金融資産を保有する割合は以下の通りです。
2人以上世帯では、全体的に300万円以上の資産を保有する世帯が多くなります。30歳代から50歳代にかけては、約4割から5割の世帯が300万円超の金融資産を保有しています。
さらに上の世代ではより多くの資産額になっていくことを考えると、貯金300万円は、多くの世帯で資産形成を次のフェーズに進めるきっかけとなる金額であるといえるでしょう。
≫今の貯金で足りる?あなたの将来の不足額をチェック
貯金300万円を超えたらやるべきこととは?
300万円という貯蓄を効果的に活用し、1000万円という目標を目指すためには、資産の配分と優先順位付けが重要です。
1.生活防衛資金を確保する
まず最優先で確認すべきは、「生活防衛資金」の確保です。これは、リストラ、病気、怪我など予期せぬ事態が発生し、収入が途絶えた際に、生活を維持するために必要な資金です。
一般的に、生活防衛資金の目安は毎月の生活費の3~6ヶ月分程度とされています。すでに300万円の貯金がある場合、この一部または全額が生活防衛資金として機能するかを確認します。もし、目安に対して不足している場合は、投資などのリスク資産形成よりも先に、生活防衛資金の確保を優先しましょう。
この資金は、すぐに引き出せるよう流動性の高い普通預金やネット銀行の預金に置いておくのが鉄則です。また、生活防衛資金は、その月に使う生活費とは別で用意することが大切です。
2.目的別にお金を分ける
生活防衛資金を確保できたら、残りの資産を「使う」「守る」「増やす」の3つの目的に明確に分け、資産形成の優先順位をつけます。
使うお金(短期資金)
数年以内に使用予定のある資金です。例として、教育費の一部、車の買い替え費用、近いうちの旅行費用などが該当します。これらは元本割れしては困るため、現金や普通預金で保有します。なお、日々の生活費はここには含みません。
守るお金(ペイオフ・インフレ対策)
リスクを抑えて確実に守りたい資金であり、主にペイオフやインフレ対策のために分散させます。インフレ対策としては、現金を多額に持ちすぎず、個人向け国債などの安全性の高い金融商品で保有することが考えられます。
増やすお金(長期資金)
使うのが10年以上先である長期資金です。老後資金や遠い将来の教育資金などが該当し、NISAやiDeCoなどを活用して積極的に運用する対象となります。
資産形成において、「守る」と「増やす」のバランスと優先順位付けが、次の1000万円という目標達成において非常に重要になります。
3.積立投資を始める
「増やすお金」として運用に回せる資金を特定できたら、資産運用をスタートします。まとまった資金を一度に投資するよりも、毎月定額を積み立てる「積立投資」から始めるのが、リスクを抑える上で有効です。
これは、価格が高い時も安い時も一定額を買い続けることで、購入価格を平均化し、価格変動リスクを平準化するドルコスト平均法の恩恵を受けることができるためです。
NISA(少額投資非課税制度)を活用
積立投資を始める上で、もっとも優先して利用すべき制度がNISA(少額投資非課税制度)です。NISAの最大のメリットは、投資によって得られた配当金や売却益が非課税になることです。通常、投資の利益には20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかりますが、NISA口座を活用すれば、この税金が免除されます。
2024年からスタートした新しいNISAでは非課税保有期間が無期限となり、生涯の非課税限度額も大幅に拡充されました。具体的には、安定的な積立投資に適した「つみたて投資枠」(年間120万円)と、まとまった資金での投資や個別株投資も可能な「成長投資枠」(年間240万円)の2つの枠があります。
まずは「つみたて投資枠」で、手数料の安い投資信託を毎月コツコツ積み立てることから始めるのが王道です。
将来の資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
貯金300万円を1000万円にするには?
300万円という土台をもとに、次の目標である1000万円を達成するには、漫然と貯金を続けるのではなく、具体的な運用戦略が必要です。以下で達成までのステップを確認していきましょう。
Step1.全財産を棚卸し、「お金の地図」を作成する
まずは現在の金融資産300万円を含めた全財産を可視化します。預金、保険、年金、投資信託など、保有する資産すべてを一覧にし、それぞれの資産が「日々の生活費」「生活防衛資金」「短期利用」「長期運用」のどの目的に割り当てられているかを明確にします。
この棚卸しによって、資産の偏りや、運用に回せる余剰資金の正確な規模を把握でき、これが今後の運用方針の基盤となる「お金の地図」となります。資産を視覚化することで、現在の生活に影響を与えずに投資に回せる額を冷静に判断できるようになります。
≫今の貯金で足りる?あなたの将来の不足額をチェック
Step2.自分の「リスク許容度」を正確に把握する
資産運用戦略を立てる上で欠かせないのが、「リスク許容度」です。これは、資産価格が一時的に下落した際に、経済的・精神的にどれだけ耐え、運用を続けられるかを示すものです。
リスク許容度は、年齢、収入の安定性、資産規模、そして個人の性格や投資経験によって決定されます。
例えば、若年層で投資期間が長く取れる方はリスク許容度が高く設定でき、より積極的な運用が可能です。
リスク許容度を超えた運用は、市場下落時にパニック売却(狼狽売り)を招き、損失を確定させるリスクを高めるため、運用方針を決定する前に必ず自己分析を行いましょう。
Step3.具体的な資産運用戦略を立てる
リスク許容度に基づき、具体的な資産の組み合わせ(ポートフォリオ)を構築していきましょう。代表的な例を以下に挙げてみましょう。
【積極型】
高いリターンを求め、値動きのブレ(リスク)を許容できる方向けの戦略です。資産の大部分を、成長性の高い市場をカバーする全米株式インデックスファンドや全世界株式インデックスファンドなど、多くの株式銘柄に分散投資できるファンドを中心に組み入れます。
さらに、人によっては高いリターンを期待できる米国ハイテク株ファンドなども部分的に追加し、全体の収益率向上を目指します。この戦略は、短期間で大きなリターンを目指すものではなく、長期的な複利効果を最大限に引き出すためのものです。
【バランス型】
株式による成長性と、債券による安定性を両立させたい方向けの王道プランです。自動で資産配分の調整(リバランス)を行ってくれるバランス型ファンドを中心に据えるのが有効です。
多くの投資家にとって精神的負担が少なく、長期継続しやすい基本戦略となります。この組み合わせは、リスクとリターンのバランスが取れており、迷ったらまず選ぶべき選択肢です。
【保守型】
元本割れのリスクを極力避け、資産の値動きをマイルドにしたい方向けの戦略です。株式の比率を抑え、比較的安全性が高いとされる国内債券ファンドもポートフォリオに組み入れます。
これにより、市場の大きな変動時でも資産の減少幅を抑えることを優先し、安定性を最重視します。リターンは穏やかになりますが、精神的な安心感を重視し、着実に資産を守りながら増やすことを目指します。
Step4.「ほったらかし」と「年1回の見直し」で着実に育てる
一度最適な運用戦略とポートフォリオを決定したら、市場の短期的な変動に惑わされず、頻繁な売買を避けて「ほったらかし」を基本とします。長期・積立・分散投資の最大の利点は、時間による複利効果を最大限に享受することにあります。
ただし、年に一度は必ずポートフォリオの「見直し(リバランス)」を行いましょう。これは、運用によって株式の比率が高くなりすぎた場合など、リスク許容度と現状の資産配分にズレが生じていないかを確認し、必要に応じて修正するためです。
リバランスを怠ると、いつの間にか高リスクな状態になっている可能性があるため、この「年に一度の点検」は非常に重要です。
貯金300万円に関するQ&A
貯金300万円を達成し、資産運用へ進む段階でよく抱かれる疑問についてお答えします。
Q. 貯金300万円で何年暮らせる?
何年暮らせるかは、毎月の支出額に大きく依存します。仮に、現在貯金が300万円あり、その他の収入がゼロになったと仮定します。毎月の生活費が20万円の場合、単純計算で15ヶ月(1年3ヶ月)暮らせる計算になります。
生活費が30万円の場合は、10ヶ月分の生活費に相当します。この期間は、もしもの時にどれだけ時間稼ぎができるかを示す、生活防衛資金の目安を考える上でも重要な指標となります。
Q. 貯金が1000万円を超えると銀行が破綻した場合どうなる?
銀行が破綻した場合、預金者を保護する「預金保険制度(ペイオフ)」があります。この制度により、普通預金や定期預金といった「決済用預金ではない一般預金等」は、1つの金融機関につき元本1000万円とその利息が保護されます。
したがって、貯金が1000万円を超えた場合、超過分は保護の対象外となります。ペイオフ対策およびインフレ対策として、1000万円を超える資金は、複数の金融機関に分散して預け入れる、あるいはNISAなどを活用して預金以外の資産(投資信託等)で保有することが推奨されます。資産を分散させることで、1つのリスクが全体に与える影響を軽減できます。
Q. 貯金300万を超えたら税務署にバレる?
単に預金口座の残高が300万円を超えたという理由だけで、銀行が個人の預金残高を逐一税務署に報告する義務はありませんので、自動的に税務署に「バレる」ことはありません。
ただし、多額の贈与があった場合や、資産が急激に増加した場合(例:不動産の高額売却、巨額の投資利益など)には、税務署が職務権限に基づき金融機関に照会をかけることは可能です。特に年間110万円を超える贈与があった場合は贈与税の申告が必要です。健全な資産形成のためにも、不審な資金移動がないように注意し、贈与や相続については適切に手続きを行うことが重要です。
まとめ
貯金300万円は、特に若年層や資産形成初期の方にとって、次のステージへ進むための確かな土台です。
この段階で最優先すべきは、まず生活防衛資金を確保することです。それが済んだら、残りの資金を「守る」資産と「増やす」資産に明確に分けます。特に「増やす」資金については、NISAを最大限に活用した長期・積立・分散投資をすぐに始めることが、次の大きな目標・1000万円達成へのもっとも着実な道筋です。
まずは自分の「お金の地図」を作成し、リスク許容度に基づいた計画的な資産運用戦略を立てながら、さらに大きな資産を育てていきましょう。
≫今の貯金で足りる?あなたの将来の不足額をチェック
将来の資金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
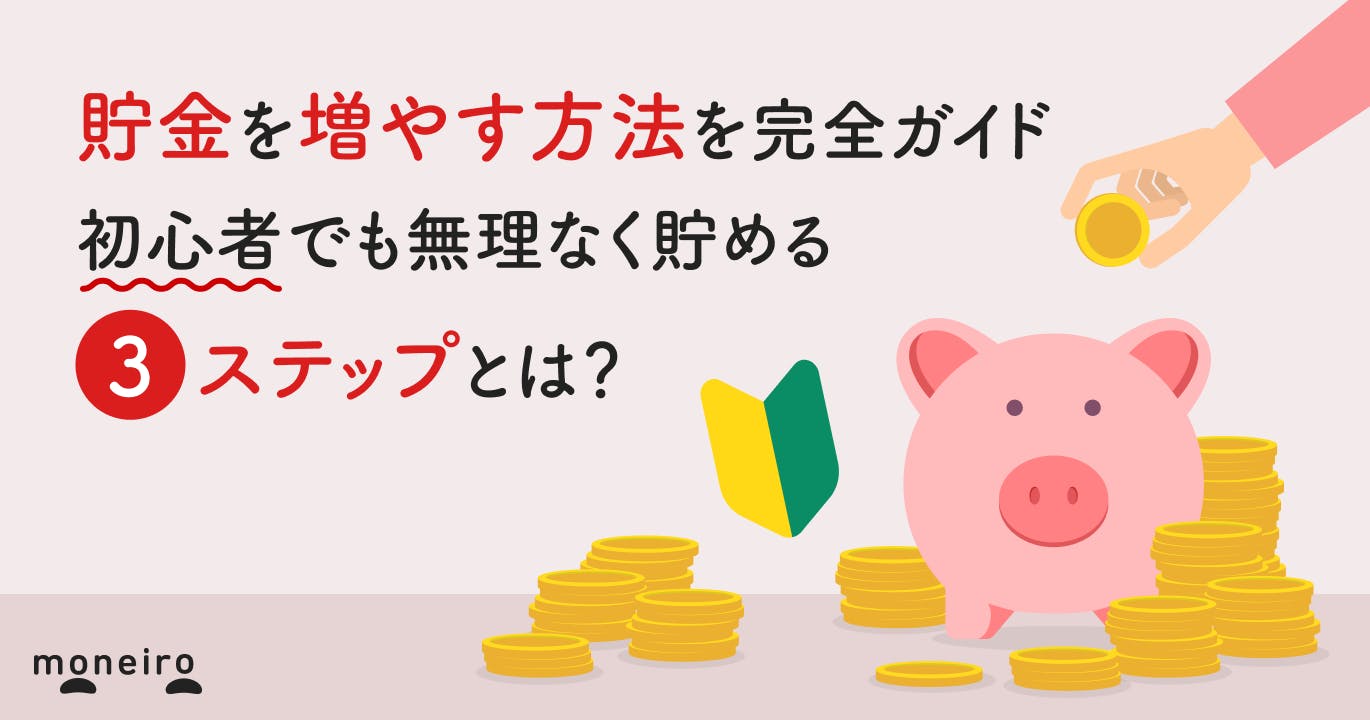

貯金1000万円はすごい?年代別の割合&達成方法・達成後の注意点を解説
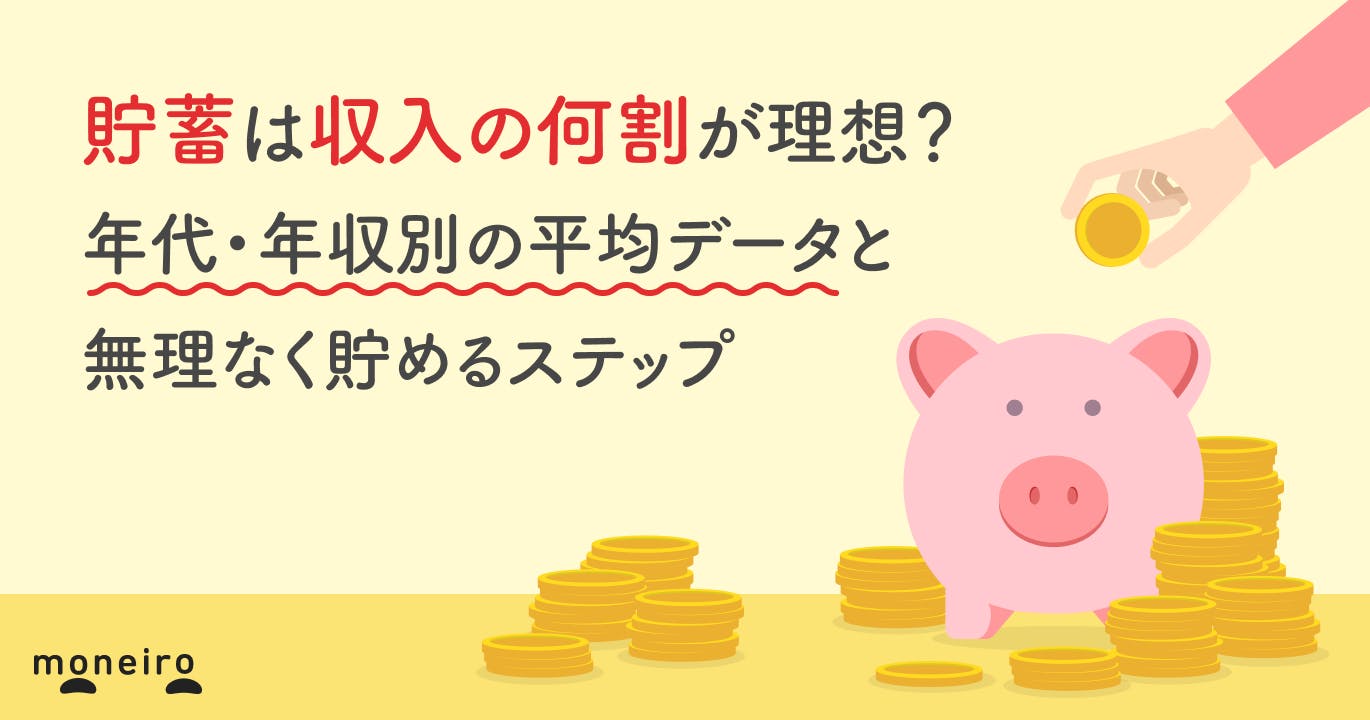
貯蓄は収入の何割が理想?年代・年収別の平均データと無理なく貯めるステップ
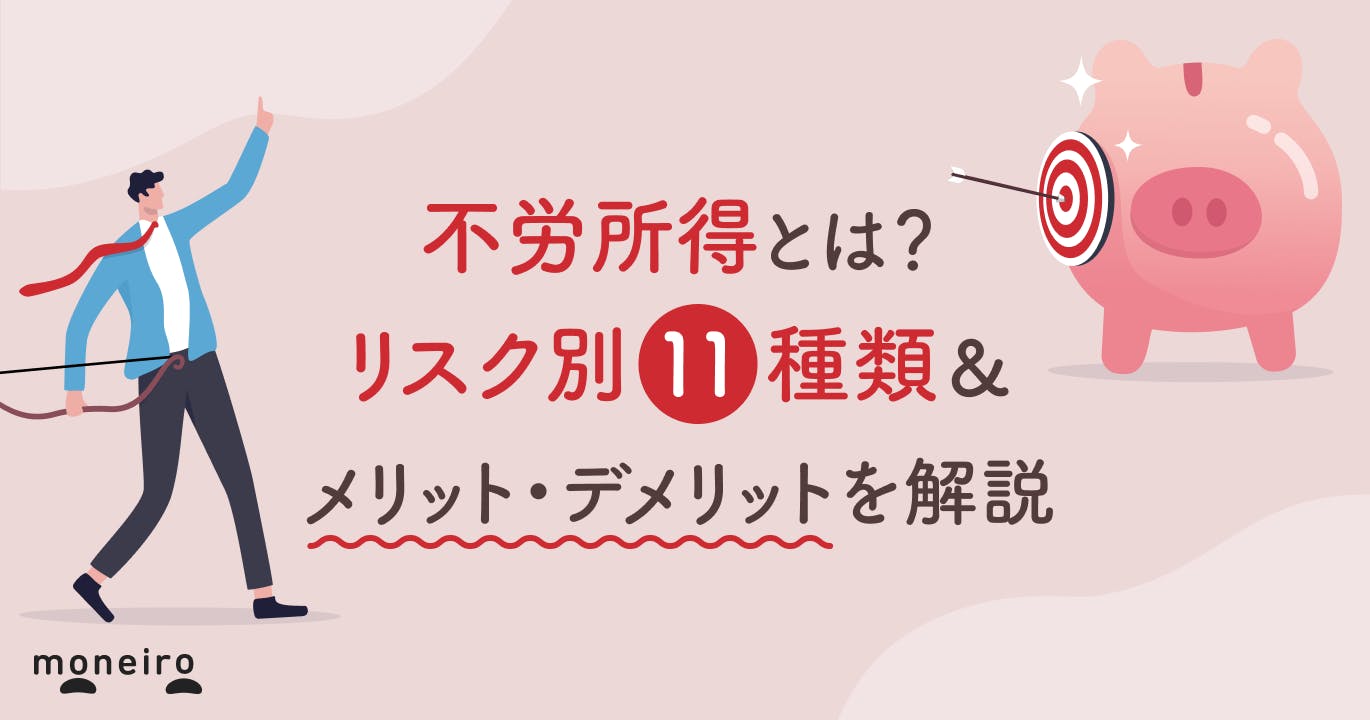
不労所得とは?リスク別11種類&メリット・デメリットを解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。