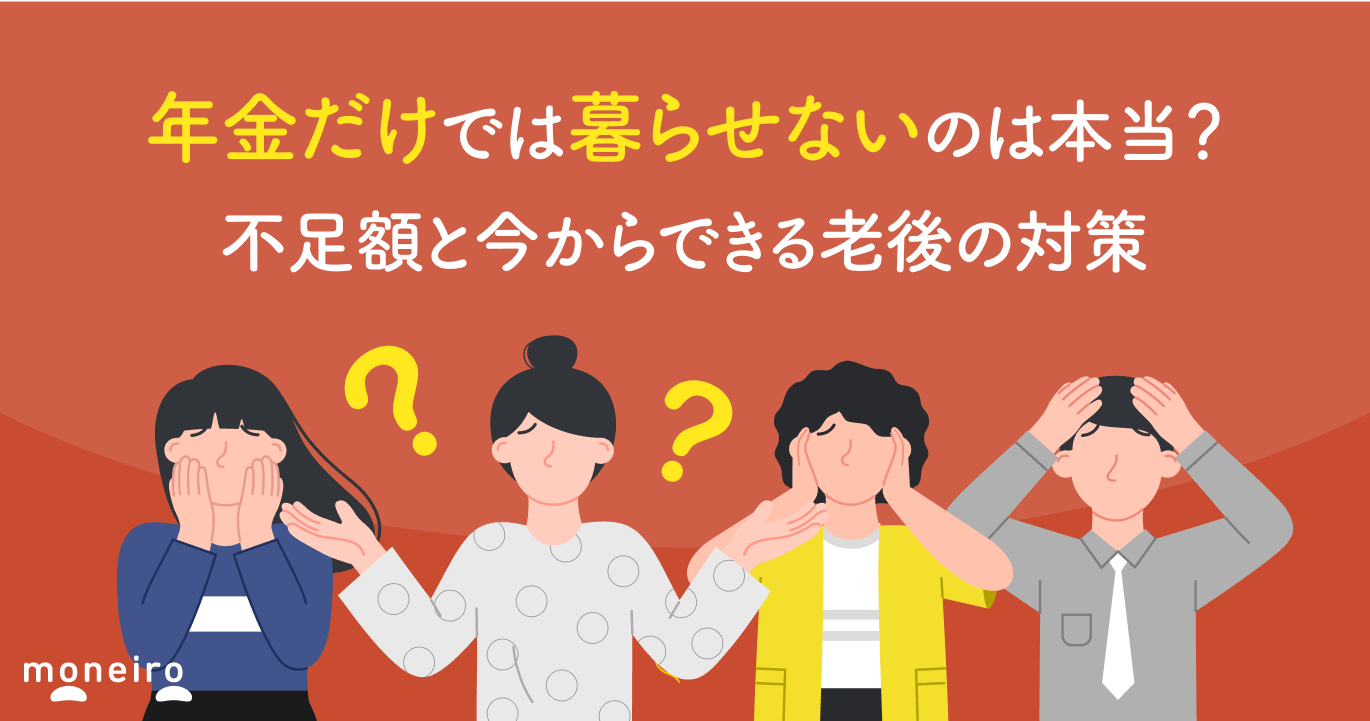
70代の平均貯蓄額はいくら?中央値や貯蓄ゼロの割合、資金不足時の対策を解説
>>老後のお金は大丈夫?あなたの必要資金を3分で診断
70代になると、多くの方が年金生活に入り、現役時代とは異なる家計の管理が求められます。老後の生活を安心して送るためには、現在の貯蓄状況を把握し、将来に備えることが重要です。
そこでこの記事では、最新の調査データに基づき、70代の平均貯蓄額や中央値、さらに貯蓄がない世帯の割合などを、2人以上世帯と単身世帯に分けて詳しく解説します。自身の状況と照らし合わせて、今後の生活設計や資金計画の参考にしてみてください。
- 70代の平均貯蓄額と中央値、金融資産を保有していない世帯の割合
- 70代の平均的な生活費と、将来必要となる資金の考え方
- 貯蓄が少ないと感じた場合に実践できる具体的な対策
この先のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
70代の平均貯蓄額と中央値
70代の貯蓄状況を把握する上で、「平均値」と「中央値」の両方を確認することが重要です。平均値は一部の高額な貯蓄を持つ世帯に引き上げられる可能性があるため、より実態に近い「中央値」も参考にすることで、ご自身の状況を客観的に判断できます。
2人以上世帯の貯蓄額(平均・中央値)
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024)」によると、二人以上世帯における70歳代の金融資産保有額は以下の通りです。
・中央値:800万円
・金融資産非保有世帯(貯蓄ゼロ世帯)の割合:20.8%
平均貯蓄額を見ると、2000万円に迫る金額となっていますが、これは上述の通り、一部の高額な貯蓄を持つ世帯が平均値を引き上げている可能性が高いといえます。
中央値の800万円のほうが、より多くの世帯の実情に近いでしょう。
また、このデータから約5世帯に1世帯が金融資産をまったく保有していないことが分かります。
保有資産額の分布
2人以上世帯の70歳代における金融資産保有額の分布は以下の通りです。
分布を見ると、平均値や中央値では分かりにくい実態も見えてきます。
割合としては、いわゆる「貯蓄ゼロ世帯」がもっとも多い20.8%となっていますが、一方で3000万円以上の資産を保有する世帯もそれに迫る19%となっており、二極化していることが分かります。
保有資産の内訳
2人以上世帯の70歳代(金融資産非保有世帯を含む)における平均金融資産1923万円の内訳は以下の通りです。
圧倒的に多くの割合を占めるのが預貯金で、次いで株式、生命保険、投資信託となっています。
単身世帯の貯蓄額(平均・中央値)
同じく「家計の金融行動に関する世論調査(2024)」によると、単身世帯における70歳代の金融資産保有額は以下の通りです。
・中央値:475万円
・金融資産非保有世帯(貯蓄ゼロ世帯)の割合:27.0%
単身世帯の場合も同様に、平均値よりも中央値のほうが多くの世帯の実情を表していると考えられます。
単身世帯のほうが貯蓄ゼロ世帯の割合が高く、約4世帯に1世帯以上が金融資産を保有していない状況となっています。
保有資産額の分布
単身世帯の70歳代における金融資産保有額の分布は以下の通りです。
金融資産非保有世帯(貯蓄ゼロ世帯)がもっとも多く、次に3000万円以上の資産を保有する世帯が多い点については、単身世帯と同様の傾向が出ています。
ただし、1000万円以上を保有する世帯の割合は2人以上世帯で44.7%であるのに対し、単身世帯では35.6%と、やや少なめとなっています。
保有資産の内訳
単身世帯の70歳代(金融資産非保有世帯を含む)における平均金融資産1634万円の内訳は以下の通りです。
資産の内訳を見ると、2人以上世帯のケースと同様に預貯金がもっとも多くの割合を占めます。
一方で、2人以上世帯と比較すると、単身世帯では、株式が394万円、投資信託が267万円とリスク資産をより多く保有している実態が見えてきます。
この先のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
70代の平均的な生活費と将来に必要な額は?
70代の貯蓄状況を確認した後は、具体的な生活費と将来必要となる資金についても把握しておきましょう。
年代別の平均生活費
総務省の「家計調査(家計収支編/2024)」によると、高齢者世帯の1ヶ月間の消費支出の平均は以下の通りです。
・高齢単身世帯のうち無職世帯:14万9286円
この消費支出には、食料、住居、光熱・水道、保健医療、交通・通信、教養娯楽など、日常生活に必要な費用全般が含まれています。
将来に必要な額は?
老後の生活で不足する資金は、「(生活費-収入)× 老後の想定年数」という計算式で概算できます。
総務省の家計調査によると、夫婦高齢者世帯のうち無職世帯の1ヶ月間の可処分所得は22万2462円、消費支出は25万6521円です。この場合、毎月3万4059円の赤字となります(25万6521円 - 22万2462円 = 3万4059円)。
また、高齢単身世帯のうち無職世帯の1ヶ月間の可処分所得は12万1469円、消費支出は14万9286円です。この場合は、2万7817円の赤字となります(14万9286円 - 12万1469円 = 2万7817円)。
不足額を計算
仮に、夫婦高齢者世帯がこの赤字額で20年間生活すると想定した場合、不足する資金は「3万4059円 × 12ヶ月 × 20年 = 817万4160円」となります。
単身世帯の場合は「2万7817円 × 12ヶ月 × 20年 = 667万6080円」となります。
ただし、これらの不足額はあくまで平均値であり、個々人の生活スタイルや健康状態、想定される老後の年数によって大きく異なります。
自身の年金受給額やその他の収入、現在の生活費を正確に把握し、上記の計算式に当てはめて、具体的な不足額を計算することが重要です。
貯蓄が少ないと感じる場合の対策は?
70代で貯蓄が平均より少ない、あるいは生活費が収入を上回る状況にあると感じる場合は、以下のような対策を講じることをおすすめします。
対策1.家計を見直して支出を減らす
もっとも基本的な対策は、現在の家計を見直し、無駄な支出を削減することです。
固定費の削減
毎月決まって発生する固定費は、一度見直せば継続的な節約効果が期待できます。
・保険料の見直し:加入している保険の内容が現在のライフスタイルに合っているか確認し、不要な保障を削減する。
・住居費の見直し:持ち家であれば住宅ローンの借り換えを検討する、賃貸であれば家賃の安い住居への引っ越しを検討する。
変動費の削減
毎月の変動費も意識的に削減することで、支出を抑えることができます。
・水道光熱費の節約:省エネ家電への切り替え、節水・節電を心がける、暖房の設定温度を調整するなど。
・娯楽費の削減:趣味にかける費用を見直し、無料または安価で楽しめる活動に切り替える。
対策2.健康なら働くという選択肢も
身体が健康であれば、70代でも働くことで収入を増やすことができます。
・再就職支援の活用:ハローワークや自治体の高齢者向け就職支援サービスを利用する。
・経験やスキルを活かす:これまでの職務経験や趣味で培ったスキルを活かせる仕事を探す。
働くことは収入が増えるだけでなく、社会とのつながりを維持し、生きがいを感じる上でも有効な手段となります。
対策3.公的制度を活用する
国や自治体には、高齢者の生活を支援するためのさまざまな公的制度があります。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金(老齢・障害・遺族)を受け取っている人のうち、所得が一定基準以下の人に支給される制度です。パート収入などがある場合でも、所得基準を満たしていれば対象になることがあります。
支給額や、対象になるかどうかは、年金の種類や所得状況によって変わるため、年金事務所、年金生活者支援給付金の専用ダイヤル(0570-05-4092)などで確認するとよいでしょう。
高齢者向け公営住宅
家賃負担を抑えたい場合には、自治体が運営する高齢者向けの公営住宅を検討する方法もあります。入居には所得や年齢、家族構成などの要件があり、募集数も限られますが、条件を満たせば民間賃貸よりも低い家賃で住まいを確保できる可能性があります。
地域の福祉サービス
自治体によっては、日常生活の支援や介護予防、健康増進など、高齢者向けの多様な福祉サービスを提供しています。食料品の宅配サービス、外出支援、相談窓口など、地域の状況に応じてさまざまな支援が受けられるケースがあります。まずは居住地の自治体の窓口で、どのようなサービスがあるか相談してみましょう。
生活保護制度
自助努力や他の公的支援を利用しても、日々の生活を維持するのが難しいときには、生活保護制度を利用できる場合があります。これは、すべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活」を送れるように支え、自助や他の制度によっても生活が成り立たない場合に最後のセーフティネットとして機能します。
申請には資産や収入の状況、扶養義務の条件など複数の要件がありますが、本当に困窮している場合は、遠慮せず自治体の窓口で相談する価値のある制度です。
対策4.持ち家を活用する
持ち家がある場合は、その資産価値を現金化する形で活用することも選択肢の1つです。
リバースモーゲージ
リバースモーゲージとは、自宅を担保に金融機関から融資を受け、自宅に住み続けながら生活資金などを受け取れる制度です。契約者が亡くなった後は、自宅を売却して返済に充てるか、相続人が一括返済して完済する仕組みになっています。自宅を手放さずに現金を得られるため、住み慣れた家で老後を過ごしたい人に向いています。
ただし、以下のような注意点もあるため、事前に確認しておきましょう。
・金利変動型の商品が多いため、将来的に返済額が増えるリスクがある
・相続人が自宅を相続したい場合には、一括で返済する必要がある
リースバック
自宅を売却してまとまった資金を一括で受け取り、同時にその家を賃貸契約で借り直して住み続ける仕組みです。持ち家を現金化しつつ、住み慣れた家に住み続けられる点が大きなメリットです。まとまった資金が必要な場合や、将来の住居費を見通しやすくしたい場合に活用できます。
ただし、リースバックの場合にも以下のような注意点があります。
・契約条件によっては長く住み続けられない可能性がある
・売却価格は市場価格より低く設定されることが多い
まとめ
70代の平均貯蓄額は、2人以上世帯で1923万円、単身世帯で1634万円ですが、中央値はそれぞれ800万円と475万円となっています。また、金融資産を保有していない世帯も2人以上世帯で20.8%、単身世帯で27.0%存在しており、多くの金融資産がない世帯も少なくないことが分かります。
また、平均的な生活費を見ると、夫婦高齢者世帯の無職世帯では平均で月25万6521円、高齢単身世帯の無職世帯では平均で月14万9286円の消費支出があり、年金収入だけでは不足する傾向が見られます。
もし現在の貯蓄額に不安がある場合は、家計の見直しによる支出削減や、健康であれば働くことによる収入増加、さらに年金生活者支援給付金や高齢者向け公営住宅といった公的制度の活用も視野にいれることで、不安を解消できる可能性があります。
老後のお金に関する不安は、多くの人が抱える共通の課題です。まずは自分自身の現在の状況を正しく把握した上で、計画的に対策を講じることが、安心して充実した老後を送るためのカギになるでしょう。
>>老後のお金は大丈夫?あなたの必要資金を3分で診断
この先のお金が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
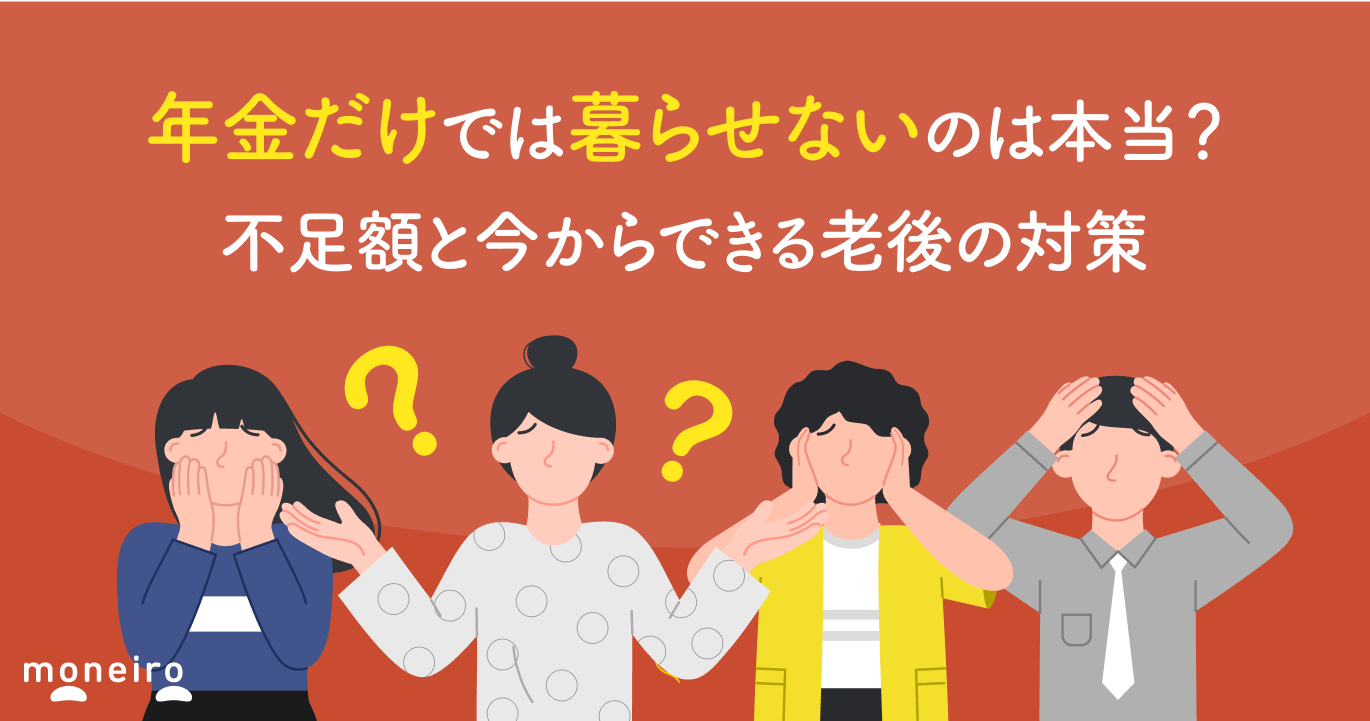

老後の生活費はいくらかかる?一人暮らし・夫婦の平均は?データをもとに解説

老後に必要なお金はいくら?単身・夫婦の世帯タイプ別必要額を解説

老後資金は平均いくらあれば安心?必要額をケース別に計算!今からできる7つの準備方法
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
