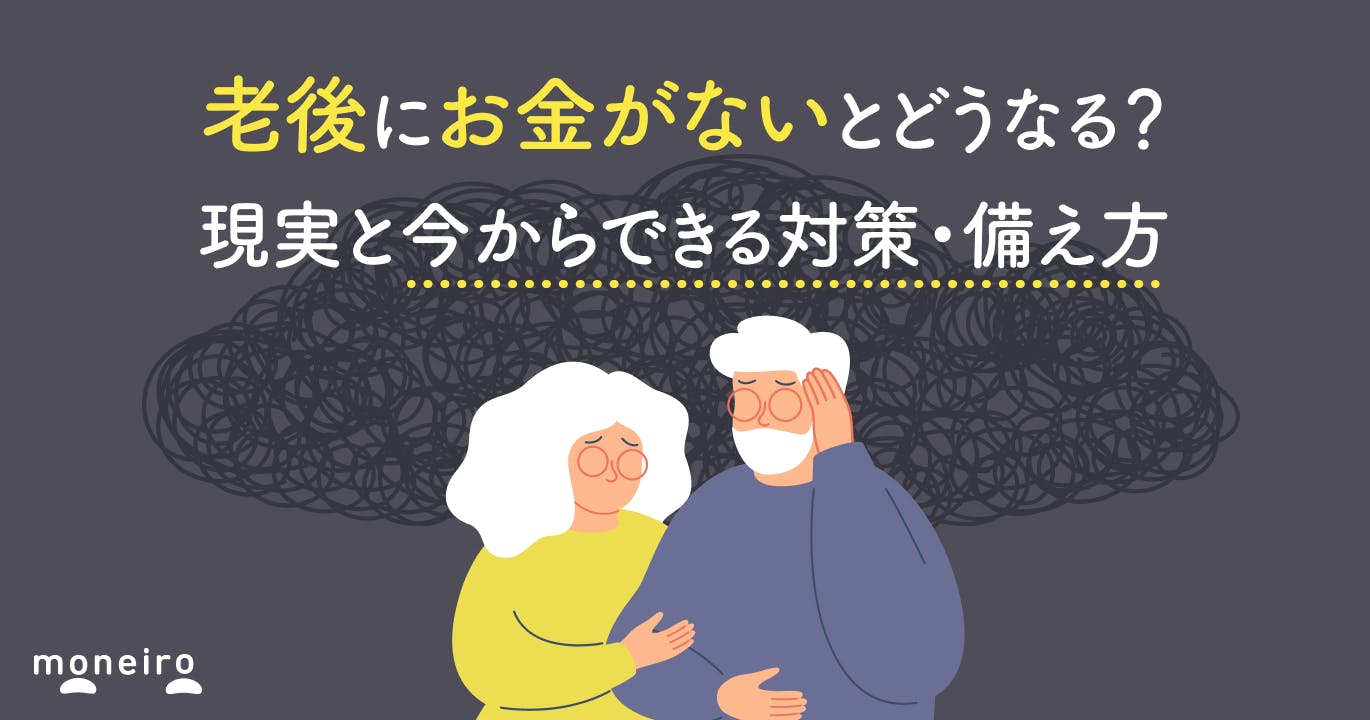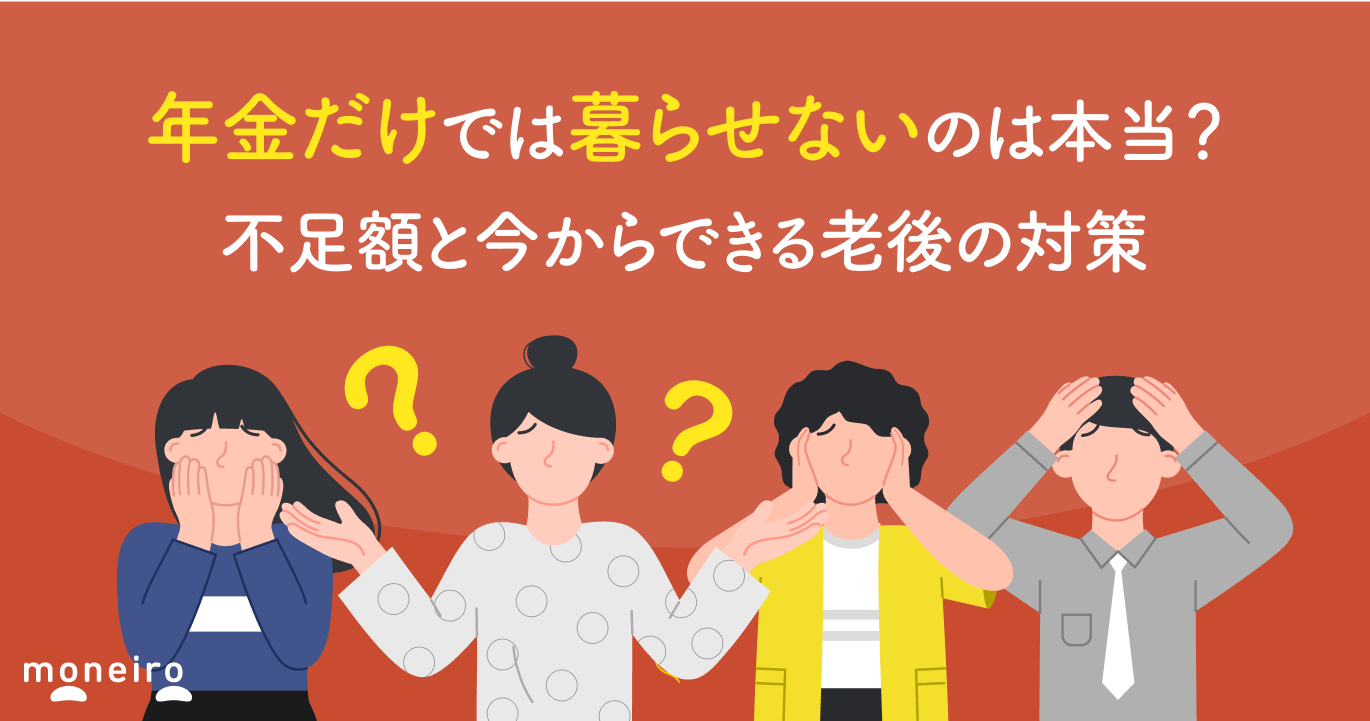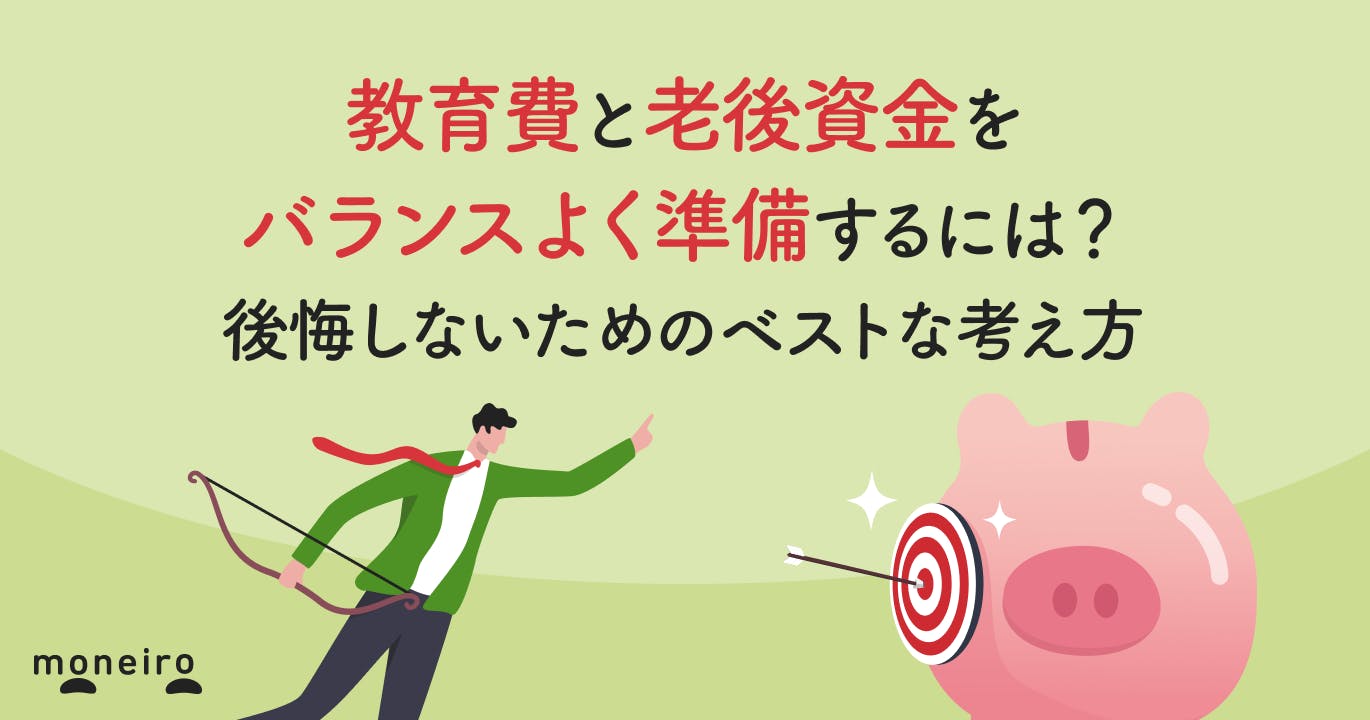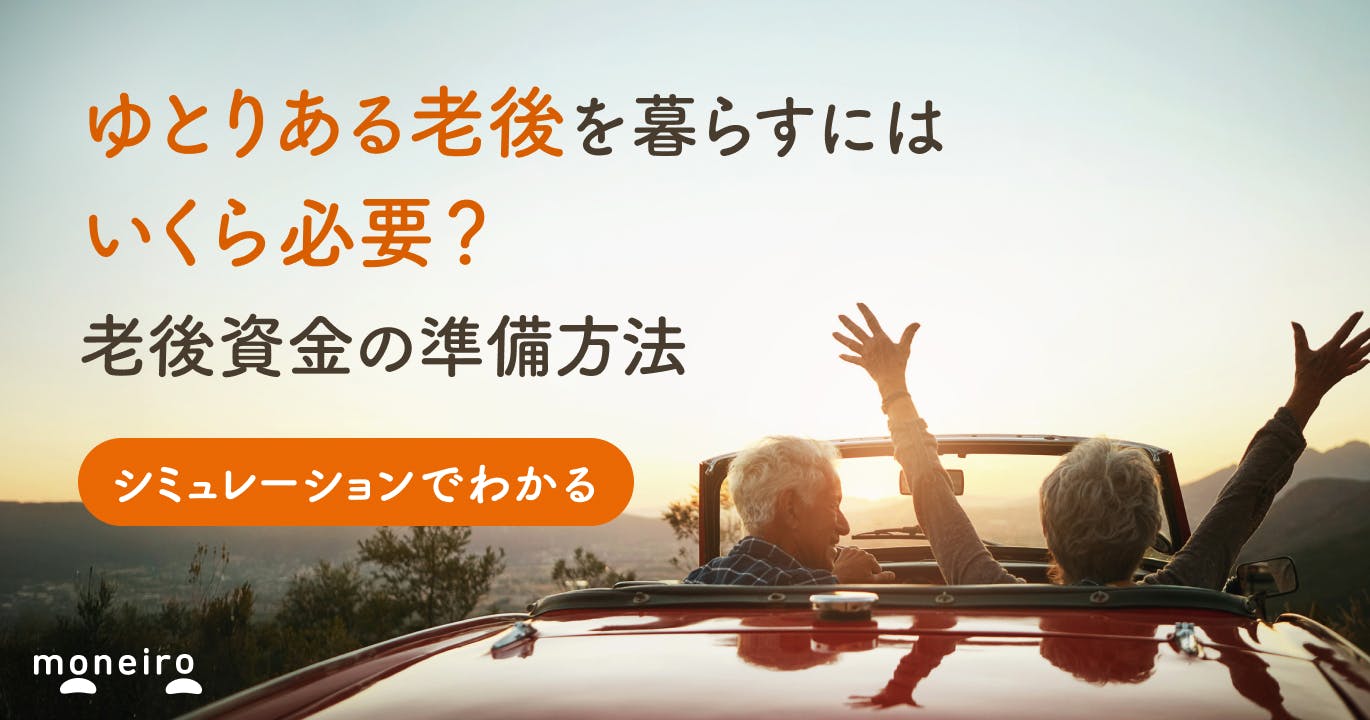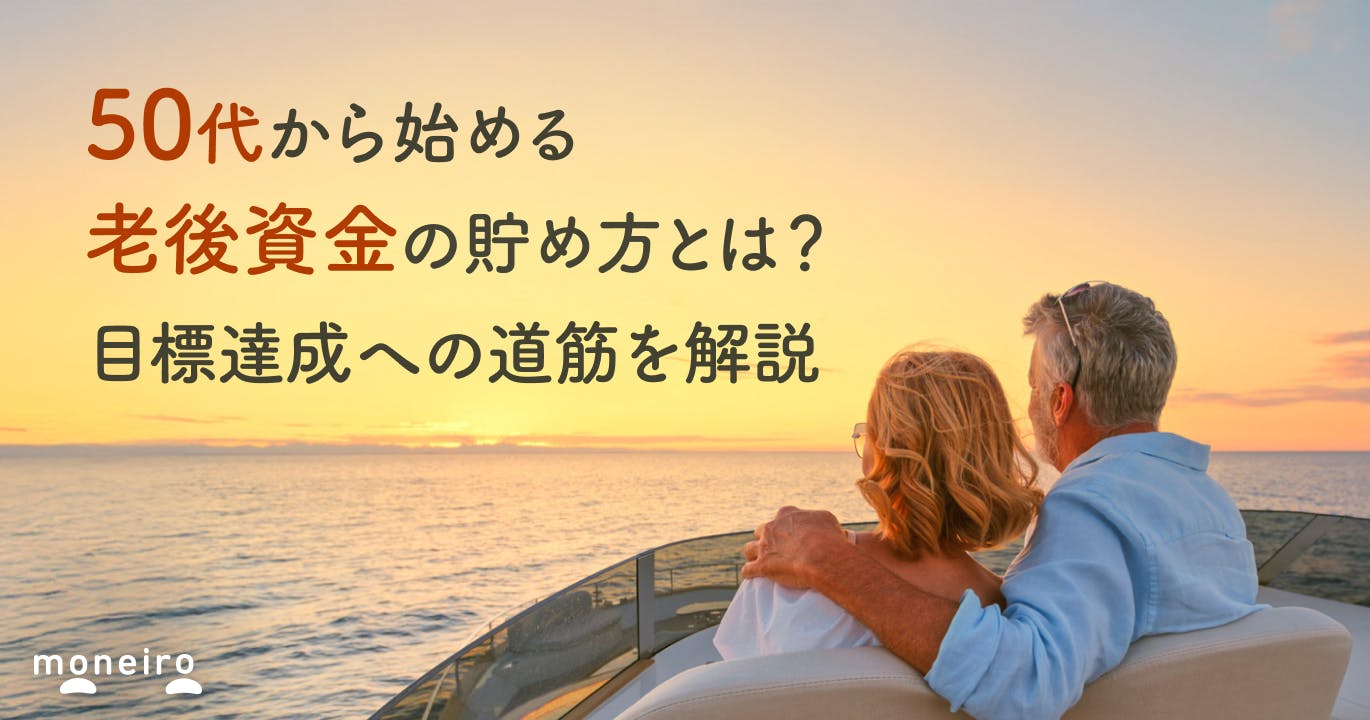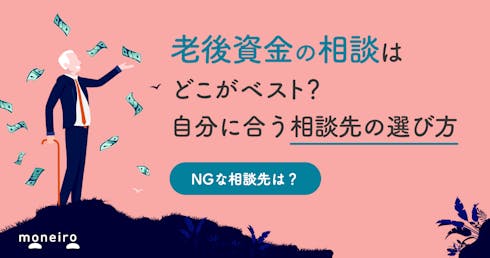
老後にお金がないとどうなる?現実と今からできる対策・備え方をお金のプロが徹底解説
»今から間に合う対策がわかる!無料診断
「老後にお金がなくなったらどうなる?」「老後のためのお金が準備できなかったら?」と、老後資金について誰もが一度は不安に感じるのではないでしょうか。実際、年金だけでは生活が苦しい世帯も多く、老後資金の不足は現実的な課題になっています。
しかし、“お金がない=破綻する”とは限りません。生活を立て直すための制度や支援も整っており、今からの行動で老後破産は防げます。
本記事では、老後にお金が足りなくなった時に起こる現実的な問題、起こりやすい人の特徴、そして今日からできる対策を専門家の視点で解説します。また、不安を安心に変える「現実的な老後の備え方」をわかりやすくご紹介します。
- 老後にお金がない場合に起こる現実
- 老後破産を招く5つの原因
- 今からできる具体的な資金不足への対処法
老後破産が気になるあなたへ
老後もお金の不安なく暮らすために、将来の必要資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
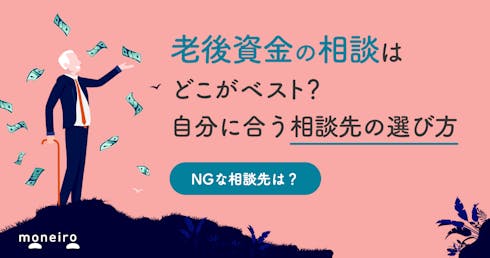

老後にお金がないとどうなる?現実に起こること
老後にお金がない場合、年金収入だけでは生活が苦しくなり、貯蓄を切り崩す生活が続きます。趣味や娯楽を我慢するだけでなく、医療や介護が必要になった際に対応できず、最悪の場合は「老後破産」や「生活保護」に至るリスクがあります。
年金だけでは生活が苦しくなるケースも多い
老後の主な収入源となる公的年金ですが、その受給額だけでゆとりある生活を送るのは難しいのが現実です。年金の受給額は、現役時代の働き方や加入期間によって大きく異なります。
厚生労働省の令和5年度の調査によると、厚生年金受給者の平均年金月額は約14.7万円です。一方で、自営業者などが中心の国民年金(老齢基礎年金)の平均受給額は月額約5.8万円に留まります。
これに対し、総務省の令和6年度の家計調査では、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における1ヶ月の平均消費支出は約25.6万円、単身無職世帯では約15万円となっています。
(参考:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局)
(参考:家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要)
生活費を削る・貯金を切り崩す生活が続く
年金収入だけでは生活費が不足する場合、多くの人はまず支出を切り詰めることから始めます。食費や光熱費を節約し、趣味や旅行、友人との交際といった娯楽費を削る生活が続くことになります。このような我慢を重ねる生活は、精神的な豊かさや生きがいを損なうことにも繋がりかねません。
節約だけでは追いつかなくなると、次に手をつけるのがこれまで蓄えてきた貯金の切り崩しです。しかし、人生100年時代と言われる現代において、長生きすればするほど貯蓄が底をつくリスクは高まります。
特に、突発的な病気や怪我による医療費、あるいは家族の介護費用といった想定外の大きな出費が発生すると、貯蓄は一気に減少してしまいます。
お金が減っていくことへの不安や、やりたいことを我慢し続けるストレスは、社会的な孤立感を深める一因ともなり、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
最悪の場合は「老後破産」「生活保護」のリスクも
貯蓄が尽き、年金収入だけでは生活費や医療費を賄えなくなった状態が「老後破産」です。これは単にお金に困るだけでなく、借金の返済が不可能になり、自己破産などの法的手続きに至る深刻な事態を指します。自己破産をすると、持ち家や車など生活に最低限必要な範囲を超える資産は手放さなければならなくなります。
老後破産に陥った場合の最終的なセーフティーネットとして「生活保護制度」があります。しかし、生活保護を受給するためには、預貯金や不動産といった活用できる資産は原則すべて生活費に充てることが求められるなど、厳しい条件を満たす必要があります。
受給できる金額も、あくまで「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する水準です。
そのため、趣味や旅行といった活動は大きく制限され、これまで通りの生活を送ることは困難になります。長年住み慣れた家や築き上げてきた資産を失うことは、経済的な困窮以上に大きな精神的打撃となるでしょう。

実際に困窮する高齢者世帯のデータ・事例
老後の経済的困窮は、決して他人事ではありません。日本弁護士連合会が公表した「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、自己破産を申し立てた人のうち、60代が16.71%、70代以上が11.84%を占めています。
これは、破産者全体のおよそ3割が高齢者であることを示しており、老後破産が深刻な社会問題となっている現実を浮き彫りにしています。
老後破産を招く主な原因5つ
老後破産は特別な人だけの問題ではなく、誰にでも起こり得る現実です。現役時代の生活習慣や想定外の出費など、いくつかの要因が重なることで家計が破綻に向かうこともあります。
ここでは主な5つの原因を紹介します。
現役時代の支出レベルを変えられない
収入が減った後も現役時代の生活レベルを維持しようとすると、家計は赤字に転落しやすくなります。
外食や旅行など「少しくらい大丈夫」という意識が、貯蓄を急速に減らす原因になります。退職後は収入に見合った支出へ早めに切り替えることが大切です。
貯蓄・退職金が少ない
教育費や住宅ローンの負担で老後資金の準備が遅れ、貯蓄が少ないまま退職を迎えるケースも多く見られます。
近年は退職金の水準も下がっており、想定より少ない金額で老後資金計画が崩れることもあるでしょう。退職金に頼らず、現役時代からの積立が欠かせません。
医療・介護費の負担が増える
高齢になると病気や怪我のリスクが増え、医療費や介護費が家計を圧迫します。
生命保険文化センターの令和6年度の調査によると、介護費用は平均で一時費用約47万円、月約9万円が必要と言われています。こうした想定外の支出が、老後資金を一気に減らす要因になります。
(参考:2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査|生命保険文化センター)
住宅ローンや子どもの支援が続く
現役時代には問題なく返済できていた住宅ローンも、定年退職して収入が減少すると、家計を圧迫する重い負担に変わります。
特に、ローンの完済時期を定年後に設定している場合、年金収入からの返済は生活費を切り詰める原因となり、老後破産のリスクを高めます。
また、晩婚化や非正規雇用の増加といった社会背景から、親が定年を迎えても子どもの教育費や生活費の援助が続くケースも増えています。子どもの大学の学費や仕送り、独立できない子どもの生活費などを親が負担し続けることで、本来自分たちの老後のために使うはずだった資金が失われていきます。
子どもへの支援は親心からくるものですが、過度な援助は自身の老後を危険にさらし、結果的に家族全体が共倒れになるリスクもあります。
詐欺・投資トラブルに遭う
高齢期には、これまで築き上げた資産を狙った詐欺や不適切な投資勧誘のリスクが高まります。特に、まとまった退職金を受け取った直後は注意が必要です。
「元本保証で高利回り」といったうまい話を鵜呑みにし、金融知識が不十分なままハイリスクな投資商品に手を出してしまい、大切な老後資金を大幅に失ってしまうケースが後を絶ちません。
また、近年巧妙化している「振り込め詐欺」や「還付金詐欺」などの特殊詐欺、悪質な訪問販売なども深刻な問題です。警察庁の統計によれば、特殊詐欺の被害者の多くは高齢者であり、被害額も高額化する傾向にあります。
判断力が低下しがちな高齢期に、一瞬の油断で長年かけて築いた財産を失ってしまうことは、老後破産の直接的な引き金となり得ます。
老後破産が気になるあなたへ
老後もお金の不安なく暮らすために、将来の必要資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
あなたは大丈夫?老後資金不足の危険サイン
老後破産は、ある日突然訪れるわけではありません。日々の生活の中に、将来の資金不足につながる危険なサインが隠れていることがあります。自分は大丈夫だと思っていても、気づかぬうちにリスクを高めているかもしれません。
ここで挙げる4つのサインに当てはまらないか、自己チェックしてみましょう。
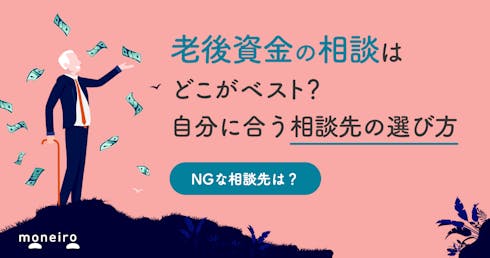
貯蓄が1000万円未満で退職を迎える予定
老後資金の目安として「2000万円」という数字が話題になりましたが、これはあくまで平均的なモデルケースです。しかし、退職時点で貯蓄が1000万円に満たない場合、危険信号と捉えるべきでしょう。
退職後は収入が公的年金中心となり、現役時代のように貯蓄を増やすことは難しくなります。そのような状況で、病気や怪我による急な医療費、自宅の修繕、介護費用の発生など、まとまった出費が必要になった場合、1000万円未満の貯蓄では対応しきれない可能性が高いです。
貯蓄額が少ないということは、予期せぬ事態に対する備えが脆弱であることを意味します。一つのトラブルが引き金となり、一気に生活が困窮するリスクを抱えている状態だと言えるでしょう。
生活費の内訳を把握していない
毎月の収入と支出を正確に把握していない、いわゆる「どんぶり勘定」の状態は非常に危険です。何にいくら使っているかが分からなければ、無駄な出費を減らすことも、計画的に貯蓄することもできません。
「毎月なんとなくお金が足りなくなる」「ボーナスで赤字を補填している」といった状況は、家計管理ができていない証拠です。現役時代はそれでも乗り切れるかもしれませんが、収入が限られる老後においては、このどんぶり勘定が命取りになります。
まずは家計簿アプリなどを活用し、最低でも数ヶ月間、自分のお金の流れを「見える化」することが第一歩です。支出の内訳を把握することで、初めて具体的な節約や資金計画を立てることができます。
年金見込み額を確認していない
老後の生活設計の土台となるのが、公的年金の受給額です。年金の受給額は、加入期間や現役時代の収入によって一人ひとり大きく異なります。
毎年誕生月に日本年金機構から送られてくる「ねんきん定期便」や、いつでもオンラインで確認できる「ねんきんネット」を活用すれば、自身の年金見込み額を簡単に確認できます。
まずはこの金額を正確に把握し、それを基に老後の生活費を賄えるのか、不足分はいくらで、それをどう補うのかを考えることが、現実的な老後計画のスタートラインとなります。
退職後の支出を現役時代と同じだと考えている
「退職すれば、仕事関係の付き合いや通勤費がなくなるから支出は減るはず」と安易に考えていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
一部の支出は減少しますが、一方で、在宅時間が増えることによる水道光熱費の増加、健康維持のための費用、趣味や旅行など自由に使える時間が増えることによる娯楽費の増加など、現役時代にはなかった新たな支出が発生します。
また、加齢に伴う医療費や介護費の負担は、年々重くなる傾向にあります。退職後の支出構造は、現役時代とは大きく異なることを理解し、具体的なシミュレーションを行うことが不可欠です。
老後資金が足りない時の現実的な対処法
老後資金が不足している、あるいは将来不足しそうだと気づいた場合でも、悲観する必要はありません。
現状を正確に把握し、現実的な対処法を組み合わせることで、状況を改善することは可能です。ここでは、今から取り組める3つの具体的な方法を紹介します。
① 生活費を見直す
最も基本的かつ効果的な対策は、家計の支出を徹底的に見直すことです。まずは家計簿などをつけてお金の流れを「見える化」し、どこに無駄が潜んでいるかを把握しましょう。
特に効果が大きいのが、通信費、保険料、サブスクリプションサービスなどの固定費の削減です。一度見直せば、その効果が継続的に続くため、優先的に取り組むべき項目です。
また、食費や娯楽費などの変動費についても、外食を減らして自炊を心がける、お金のかからない趣味を見つけるなど、生活の満足度を大きく損なわない範囲で工夫することが大切です。
子どもの独立などを機に、住居をダウンサイジング(より小さな住居へ移る)して住居費を抑えるのも有効な手段です。
② 収入を増やす
支出を減らす努力と同時に、収入を増やす方法を検討することも重要です。定年後も健康で働く意欲があるなら、再雇用制度やシニア向けの求人を活用して働き続けるのが最も確実な方法です。厚生年金に70歳まで加入すれば、将来受け取る年金額を増やすこともできます。
フルタイムで働くのが難しい場合でも、パートタイムやアルバイト、あるいは自身のスキルや経験を活かした在宅ワークやフリーランスといった多様な働き方があります。働くことは収入確保だけでなく、社会とのつながりを保ち、健康維持にも繋がるというメリットもあります。
また、公的年金の「繰下げ受給」も収入を増やす有効な手段です。年金の受給開始を65歳から遅らせることで、1ヶ月あたり0.7%ずつ受給額が増額され、75歳まで繰り下げれば最大で84%も年金額を増やすことができます。
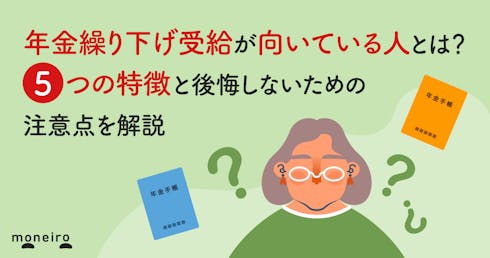
③ 資産を運用する
預貯金だけで資産を持っていると、インフレ(物価上昇)によってお金の実質的な価値が目減りしてしまうリスクがあります。そこで、資産の一部を運用に回し、「お金に働いてもらう」という視点も大切です。
特に、税制優遇を受けながら長期的な資産形成が可能な「NISA」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、老後資金作りの有力な選択肢です。これらの制度を活用し、投資信託などで長期・積立・分散投資を行うことで、リスクを抑えながら複利効果を活かした資産成長が期待できます。
投資には元本割れのリスクが伴いますが、生活防衛資金(生活費の半年〜1年分程度)を預貯金で確保した上で、余剰資金を適切なリスク許容度の範囲で運用することが重要です。
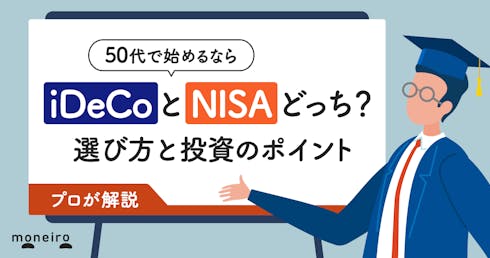
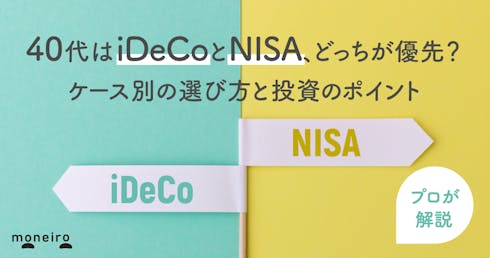
老後に“お金を生み出す仕組み”を持つことが大切
老後の経済的な安定を確保するためには、公的年金だけに依存するのではなく、それ以外の収入源、つまり「お金を生み出す仕組み」を現役時代から構築しておくことが極めて重要です。年金はあくまで生活の土台であり、ゆとりや不測の事態への備えは、自ら作り出す必要があります。
例えば、不動産投資による家賃収入や、株式投資による配当金・分配金といった金融資産からのインカムゲインは、安定した不労所得となり得ます。
また、現役時代に培った専門知識やスキルを活かして、コンサルティングや小規模な事業を始めることも一つの方法です。
現役のうちから、将来の自分を助けるお金の仕組みづくりを意識することが、安心して老後を迎えるための鍵となります。
今からできる対策がわかる|無料診断(サンプル)
「将来に向けて、今何をすればいい?」
マネイロの「3分無料診断」なら、目指す老後に必要なお金と、自分に合った対策がすぐにわかります。
※3分投資診断結果イメージ
面倒な計算は不要。まずは無料診断から始めてみましょう。
老後にお金が尽きた時に使える公的制度
万が一、老後にお金が尽きてしまった場合でも、セーフティーネットとなる公的制度が存在します。これらの制度は、国民が最低限の生活を送るための権利として保障されています。
いざという時に慌てないためにも、どのような制度があるのかを事前に知っておくことが大切です。
主な公的制度の概要と活用法を解説します。
生活保護・年金生活者支援給付金の仕組み
生活保護制度は、資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、国が健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を助けるための制度です。生活費、住宅費、医療費などが給付されますが、受給には預貯金や不動産などの資産がないこと、働く能力がある場合は働くことなど、厳しい要件があります。
年金生活者支援給付金制度は、公的年金などの収入額が一定基準額以下の方を対象に、年金に上乗せして支給される給付金です。老齢・障害・遺族の各基礎年金受給者で、所得要件などを満たす場合に支給されます。
年金収入だけでは生活が苦しい場合の支援策として、重要な役割を担っています。これらの制度を利用するには、住んでいる自治体の福祉担当窓口への相談が必要です。
医療・介護費を抑える高額療養費制度・介護保険制度
高齢期に家計を圧迫する大きな要因が医療費と介護費です。これらの負担を軽減するための公的制度もしっかりと活用しましょう。
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、1ヶ月で上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。上限額は年齢や所得に応じて定められており、高額な医療費がかかった際の家計へのダメージを抑えることができます。
介護保険制度は、要介護・要支援認定を受けた方が、少ない自己負担(原則1割、所得に応じて2〜3割)で介護サービスを利用できる制度です。こちらも、1ヶ月の自己負担額には所得に応じた上限(高額介護サービス費)が設けられており、負担が過重にならないよう配慮されています。これらの制度を正しく理解し利用することで、老後の大きな支出リスクに備えることができます。
自治体・社会福祉協議会などの相談窓口を活用する
経済的な問題や生活上の困りごとを一人で抱え込む必要はありません。各自治体には、生活に困窮している人のための相談窓口が設置されています。市役所や区役所の福祉課などが、利用できる制度の案内や専門機関への橋渡しを行ってくれます。
また、民間の非営利組織である社会福祉協議会も、地域住民の福祉を支える重要な役割を担っています。生活福祉資金貸付制度など、一時的に生活資金が必要な場合の貸付制度を運営しているほか、さまざまな生活相談に応じてくれます。
これらの相談窓口は、プライバシーを守りながら無料で相談に乗ってくれる心強い存在です。「誰に相談していいかわからない」と感じたら、まずは住んでいる地域の相談窓口に連絡してみましょう。専門家が状況を整理し、解決への道筋を一緒に考えてくれます。
40代・50代からでも間に合う!老後破産を防ぐ備え方
「もう40代・50代だから、今から老後資金の準備をしても手遅れだ」と諦めてしまうのは早計です。
定年までにはまだ時間があり、この時期からの行動が将来を大きく左右します。むしろ、子育てが一段落し、自身のキャリアや収入がある程度見通せる40代・50代は、老後準備を本格化させる絶好のタイミングです。
現実的な計画を立て、着実に実行することで、老後破産のリスクは十分に回避できます。
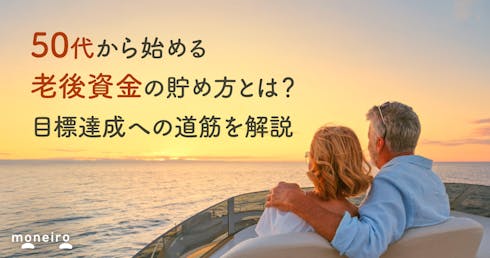

今からできる5つの行動
老後破産を防ぐためには、多角的な視点からのアプローチが不可欠です。以下の5つの行動を今日から始めましょう。
- 家計の見える化と固定費削減:まずは家計簿アプリなどを活用し、収支を正確に把握します。特に通信費や保険料といった固定費は、一度見直すだけで継続的な節約効果が期待できます
- 年金見込み額の確認と繰下げ検討:「ねんきんネット」で将来の受給額を確認し、老後の生活設計の土台とします。収入状況によっては、受給額を増やせる「繰下げ受給」も視野に入れましょう
- 税制優遇制度を活用した資産運用:NISAやiDeCoといった制度を最大限に活用し、長期・積立・分散投資を始めましょう
- 保険の棚卸しと見直し:現在加入している保険の内容をすべて確認し、保障が重複していないか、今のライフステージに合っているかを見直します
- セカンドキャリアの計画:定年後も働き続けることを前提に、自身のスキルや経験をどう活かせるかを考え始めましょう
貯蓄と投資のバランスを整える
老後資金を準備する上で、貯蓄(預貯金)と投資のバランスを考えることはとても大切です。すべての資産を預貯金で持っていると、インフレによってお金の価値が目減りするリスクがあります。一方で、すべての資産を投資に回すのは、価格変動リスクが大きすぎます。
基本的な考え方として、まずは生活費の半年から1年分程度の「生活防衛資金」を、いつでも引き出せる預貯金で確保しましょう。これは、急な失業や病気など、不測の事態に備えるための安全資金です。
その上で、当面使う予定のない余剰資金を投資に回します。40代・50代であれば、まだ20年以上の運用期間が見込めるため、NISAやiDeCoを活用した積立投資が有効です。
年齢やリスク許容度に応じて、株式や債券などを組み合わせたバランスの取れたポートフォリオを構築し、長期的な視点で資産を育てていくことが賢明です。
目的別に考える老後資金づくり
「老後資金」と一括りにするのではなく、その使い道を「基本的な生活費」「医療・介護への備え」「趣味や旅行などの余暇費」の3つに分けて考えると、目標設定がしやすくなります。
- 基本的な生活費:これは、年金収入で賄うことを基本目標とします。年金見込み額を確認し、不足するようであれば、その差額を補うための資産(iDeCoや個人年金保険など)を準備します
- 医療・介護への備え:予期せぬ大きな出費に備える資金です。高額療養費制度などを考慮しつつも、数百万円単位のまとまった資金を、預貯金や換金しやすい金融資産で確保しておくと安心です。民間の医療保険や介護保険で備えるという選択肢もあります。
- 趣味や旅行などの余暇費:老後の生活を豊かにするための資金です。これは、NISAなどを活用した資産運用で積極的に増やしていく部分と考えられます。目標額を設定し、それに向けて計画的に運用を進めましょう。
このように目的別に資金を色分けすることで、それぞれに適した準備方法を選択でき、より効率的で現実的な資金計画を立てることが可能になります。
老後資金が心配な時はプロに相談して現状を見える化
老後資金に関する漠然とした不安を抱えているなら、お金の専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、多くのメリットが得られます。
まず、客観的な視点で家計の収支バランスを分析し、どこに改善の余地があるかを的確に指摘してもらえます。自分では気づかなかった無駄な支出や、より効果的な節約方法が見つかるかもしれません。
次に、自身の希望するライフプランに基づき、将来必要となる資金額を具体的にシミュレーションしてくれます。「老後2000万円」といった一般的な数字ではなく、自分自身の状況に合わせた「自分ごと」の目標額が明確になります。
さらに、NISAやiDeCo、保険など、数ある金融商品の中から、あなたに最適な活用法を中立的な立場でアドバイスしてくれます。
一人で悩みを抱え込まず、プロの力を借りて現状を「見える化」することが、不安を安心に変え、具体的な行動を起こすための第一歩となります。
まとめ
「老後にお金がないとどうなるか」という不安は、多くの人にとって現実的な問題です。年金だけでは生活が苦しくなる可能性が高く、貯蓄を切り崩す生活の先には「老後破産」という深刻な事態も待ち受けています。
その原因は、現役時代の生活習慣、予期せぬ医療・介護費、住宅ローンなど様々ですが、決して他人事ではありません。しかし、危険サインに早く気づき、40代・50代からでも対策を始めれば、未来は大きく変えられます。
まずは、老後にいくら必要で、年金と今の資産でどれくらい足りるのかを把握することが重要です。
マネイロの3分投資診断では、老後に必要な金額と現在の状況から、お金が足りなくなるリスクと、今から取れる選択肢を整理できます。
最悪のケースを避けるための、現実的な第一歩になります。
»必要な老後資金と今からでも間に合う対策を無料診断
老後破産が気になるあなたへ
老後もお金の不安なく暮らすために、将来の必要資金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶50代からの老後資金作り:まだ間に合う。50代からの資産形成が30分でわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。