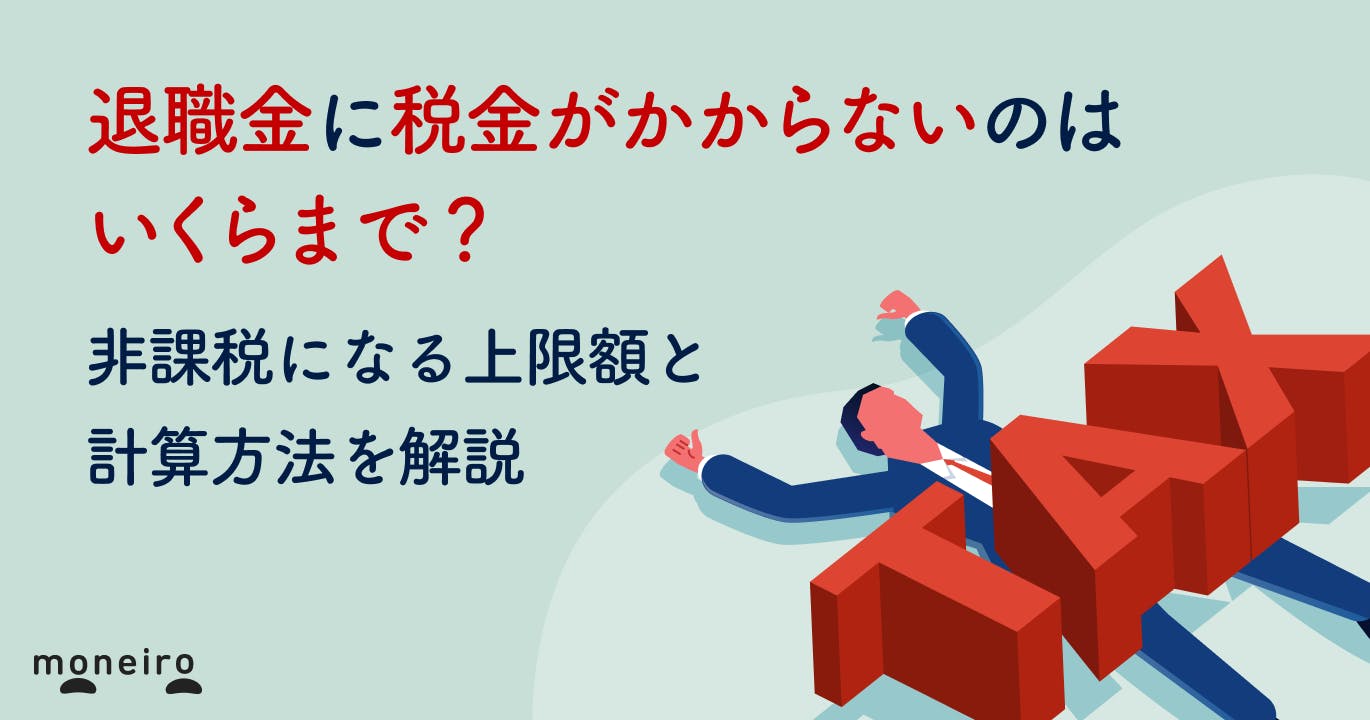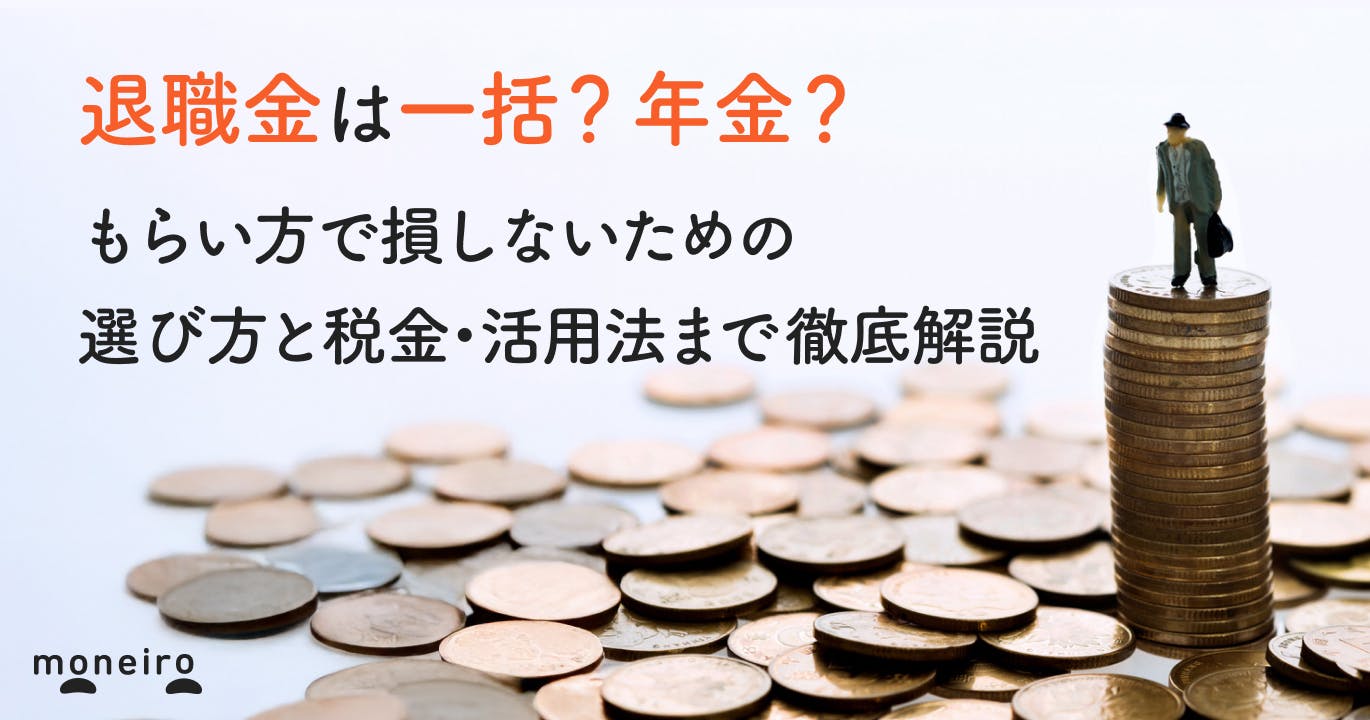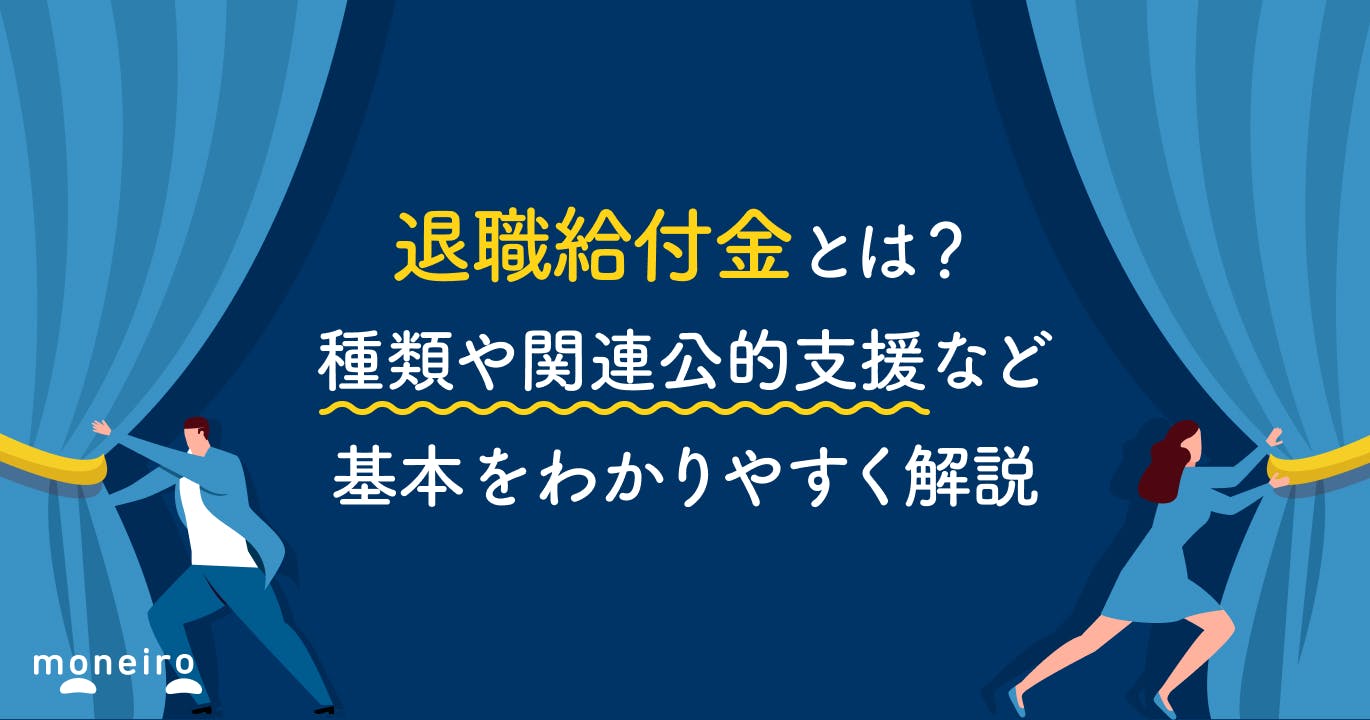
中小企業の退職金平均はいくら?勤続年数・学歴・退職理由別の相場を解説
≫退職金で足りる?あなたの老後に必要な金額を3分で診断
「自分が勤めている中小企業では、退職金はいくらもらえるのだろう?」と、疑問や不安をお持ちではありませんか?
この記事では、最新の調査データを基に、中小企業の退職金に関する実態を解説します。さらに、退職金の税金の仕組みや退職金の有効な活用方法まで詳しく紹介します。この記事を参考に退職金への理解を深め、抱えている不安を解消しましょう。
- 勤続年数や学歴別のリアルな退職金相場
- 退職金にかかる税金の仕組みと計算方法
- 代表的な退職金制度の種類と特徴
退職金が気になるあなたへ
これからの人生をお金の不安なく暮らすために、老後資金の準備は大切です。マネイロでは、将来資金を賢く準備するための無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
中小企業の退職金の平均額はいくら?
中小企業の退職金平均額は、大企業と比べると少ない金額になりますが、学歴や勤続年数によって大きく変わります。自身の状況と比べながら、だいたいの相場を知ることが大切です。
退職金制度のある中小企業の割合
東京都産業労働局が発表している「令和6年版 中小企業の賃金・退職金事情」によると、調査対象の「東京都内にある常用労働者数10人以上299人以下の中小企業」659社のうち、423社が退職金制度を有しているとされています。
このことから、調査対象企業における退職金制度の導入率が約64%に上ることが分かります。
なお、このデータはあくまで東京都内の企業を対象としたデータである点に留意しておく必要があります。
【学歴別】中小企業の退職金の平均額は?
次に、中小企業の学歴別の退職金の平均額を見ていきましょう。自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で大きく異なるため、それぞれのケースも併せて確認していきます。
最終学歴が高校卒の場合
東京都産業労働局の調査によると、高校卒の場合のモデル退職金は以下のようになっています。
勤続年数が長くなるほど退職金が多くなるのが分かります。また、自己都合退職と比較すると会社都合退職は1~2割程度高くなる傾向があります。なお、定年の場合は必ず会社都合退職となるため、自己都合退職の金額は示されていません。
最終学歴が高専・短大卒の場合
東京都産業労働局の調査によると、高専・短大卒の場合のモデル退職金は以下のようになっています。
全体的に、高校卒と同様の傾向が見て取れますが、定年退職時の退職金は、高専・短大卒の場合のほうが18万円ほど高いという結果となっています。
最終学歴が大学卒の場合
東京都産業労働局の調査によると、大学卒の場合のモデル退職金は以下のようになっています。
大学卒の場合では、定年退職のケースで退職金が1000万円を大幅に超えており、他の学歴のケースと比較して、圧倒的に多額の退職金を得られる可能性が高いことが分かります。
≫退職金で足りる?あなたの老後に必要な金額を3分で診断
退職金が気になるあなたへ
これからの人生をお金の不安なく暮らすために、老後資金の準備は大切です。マネイロでは、将来資金を賢く準備するための無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
自分の退職金額を確認する方法
自分の退職金額を正確に知るためには、まず勤務先のルールを確認することが必要です。退職金は法律で決められた制度ではないため、支給条件や計算方法は企業ごとに違います。以下の方法で確認しましょう。
就業規則(退職金規程)を確認する
退職金に関する決まりは、基本的に就業規則や、独立した「退職金規程」に記載されています。まずはこれらの書類を確認することが第一歩です。規程には、以下の内容が書かれているのが一般的です。
・計算方法: 退職金をどのように計算するか(例:基本給連動型、ポイント制など)
・支給率: 勤続年数や退職理由によって変わる係数
・支給時期: 退職後、いつ支払われるか
これらの規程は、従業員がいつでも見ることができる場所に保管されているはずです。まずは自社のルールを正確に理解しましょう。
人事・総務担当者に問い合わせる
就業規則や退職金規程を読んでも計算方法が複雑で理解が難しい場合や、個別の事情に応じた具体的な金額を知りたい場合は、人事部や総務部といった担当部署に直接聞くのが確実な手段です。
会社によって対応は異なる可能性がありますが、問い合わせることで、現時点での退職金見込額や、今後のキャリアプランによる変動の可能性など、より詳しい情報を得られる場合があります。
退職金にかかる税金の計算方法
退職金は給与所得などとは別に計算されるため、税制面で大きく優遇されています。その中心となるのが「退職所得控除」です。この仕組みを理解することで、手取り額が大きく変わる理由がわかります。
退職金が優遇される「退職所得控除」とは?
退職所得控除とは、長年の勤労に対する報奨という退職金の性質を考慮し、税負担を軽くするために設けられた特別な控除です。この控除額は勤続年数に応じて大きくなります。具体的な計算方法は以下の通りです。
さらに、退職金からこの控除額を差し引いた金額を1/2にしたものが課税対象額となります。
例えば、勤続35年で退職金が1800万円の場合で計算すると、「800万円 + 70万円 × (35年 - 20年)」で、控除額は1850万円です。
退職金額が控除額を下回るため、このケースでは所得税はかからないことになります。この手厚い控除制度が、退職金の手取り額を多くする大きな理由です。
中小企業の代表的な退職金制度
中小企業では、自社で退職金を積み立てるだけでなく、外部の共済制度や年金制度を活用して退職金制度を作っているケースが多く見られます。代表的な制度を知ることで、自社の制度への理解も深まります。
企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が掛金を出し、従業員自身が運用商品を選んで資産を作っていく年金制度です。
従業員は、企業が提示する投資信託や保険商品などのラインナップから、自分のリスク許容度に応じて運用方法を決めます。そのため、将来受け取る金額は運用結果によって変わるのが大きな特徴です。
運用によって得られた利益は非課税となるため、効率的な資産形成が期待できます。資産形成への意識を高めるきっかけにもなる制度といえるでしょう。
確定給付企業年金(DB)
確定給付企業年金(DB)は、企業が従業員に対して将来の給付額をあらかじめ約束する制度です。掛金の拠出は企業が行い、その運用責任も企業が負います。
従業員にとっては、将来受け取れる金額が決まっているため、老後の資金計画を立てやすいという大きなメリットがあります。企業型DCとは対照的に、市場の変動リスクを企業側が負担する仕組みです。
受け取り方法は、一時金として一括で受け取るか、年金として分割で受け取るかを選択できるのが一般的です。
中小企業退職金共済(中退共)
中小企業退職金共済(中退共)は、国が運営する中小企業向けの退職金制度です。単独で退職金制度を設けることが難しい中小企業を支援することを目的としています。
企業は毎月、従業員ごとに掛金を金融機関に納付します。その掛金は勤労者退職金共済機構によって管理・運用され、従業員が退職した際には、機構から直接従業員に退職金が支払われる仕組みです。
掛金は全額を損金として計上できるため、企業側の税務上のメリットもあります。
企業の倒産といった万一の場合でも、従業員は退職金を受け取れるため、安心感の高い制度といえます。
特定退職金共済(特退共)
特定退職金共済(特退共)は、商工会議所などが実施している地域や業種ごとの中小企業向けの退職金制度です。中退共と同様に、企業が掛金を拠出し、従業員が退職する際に共済団体から退職金が支払われます。
制度設計は中退共と似ていますが、地域の実情に合わせた運用がなされることが多い点が違いとして挙げられます。企業が加入することで、従業員の福利厚生の充実と、離職率の低下に貢献することが期待されます。
退職金を有効活用する方法は?
退職金は老後の生活を支えるための大切な資金です。受け取ったまとまったお金を無計画に使ってしまうと、将来困ってしまうリスクがあります。ライフプランに基づき、「守る」「増やす」「使う」のバランスを考えた計画的な活用が求められます。
今後のライフプランと収支を明確にする
退職金を有効に活用するための第一歩は、退職後の人生設計、つまりライフプランを具体的に描くことです。いつまで働き、どのような生活を送りたいのか、趣味や旅行、住まいのリフォームなど、将来やりたいことをリストアップしてみましょう。
それらの実現にいくら費用がかかるのかを計算し、公的年金の受給見込額と照らし合わせることで、退職金からいくら補う必要があるのか、収支の全体像が明確になります。この作業を通じて、退職金をどのように配分すべきかの指針が立てられます。
生活費と当面の予備資金を確保する
退職金を手にしたら、まず当面の生活費と、万一の事態に備えるための予備資金を確保することが最優先です。年金の受給開始時期によっては、退職後に無収入の期間が生じることもあるため、できれば生活費を数年分、普通預金など流動性の高い口座に確保しておけると安心です。
また、病気やケガによる入院、家族の介護など、予測できない出費に備えるための予備資金も別途用意しておくことも大切です。これらの資金を確保した上で、残りの余裕資金をどのように活用するかを検討するのが賢明な方法です。
資産を「守る」運用戦略
老後のための資金は、元本割れのリスクを低く抑えなながら、安全性を最優先で管理することが求められます。このような「守る」運用に適しているのが、定期預金や個人向け国債です。
定期預金は、預金保険制度の対象となり、金融機関が破綻した場合でも元本1000万円とその利息が保護されます。個人向け国債は国が発行するため信用度が高く、元本割れのリスクがほぼありません。
金利はそれほど高くありませんが、インフレに対応できる変動金利タイプもあります。大切な資金を確実に守りたい場合に適した選択肢です。
資産を「増やす」運用戦略
生活費や予備資金を確保した上で、さらに余裕のある資金については、インフレに負けないよう「増やす」ことを目的とした資産運用を検討する価値があります。代表的な方法が、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用した投資信託などでの運用です。
NISAは、投資で得た利益が非課税になる制度で、2024年に制度が刷新され、より柔軟な投資が可能になりました。iDeCoは、掛金が全額所得控除になるなど税制優遇が大きく、老後資金作りに特化した制度です。これらの制度を活用し、複数の資産に分散投資することで、リスクを抑えながらも効率的な資産の成長が期待できます。
資産を「使う」計画も大切
老後においては、資産を「守る」「増やす」ことと同時に、「どのように使っていくか」という計画も非常に重要です。資産寿命を延ばすためには、計画的な取り崩しが不可欠です。
例えば、「毎年〇〇万円を取り崩す」「毎年、資産の◯%ずつを取り崩す」といったルールを決めることで、資産の枯渇を防ぎやすくなります。
また、旅行や趣味など、人生を豊かにするための大きな支出は、あらかじめ計画に組み込んでおくことが大切です。
資産をただ持っているだけでなく、計画的に活用して充実したセカンドライフを送るための「出口戦略」を立てましょう。
退職金の運用で不安な場合は専門家へ
退職金の運用は、老後の生活を左右する重要な決断です。しかし、金融商品の知識が少ない中で、自分だけで最適な運用方法を見つけるのは簡単ではありません。
もし少しでも不安を感じるなら、お金の専門家への相談も検討しましょう。銀行や証券会社などの金融機関に相談するのも1つの手ですが、おすすめはIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談することです。
IFAは特定の金融機関に所属していないため、中立的な立場からアドバイスを受けることができます。
マネイロは運用サポートまで行うIFA
マネイロは、はたらく世代向けのお金の診断・相談サービスです。担当者である各マネイロコンシェルは銀行・証券会社・保険会社などで実績を挙げたアドバイザーです。
個人のライフプランや家計状況を総合的に判断し、最適な掛金額や運用ポートフォリオについて客観的なアドバイスの提供が可能です。
また、運用は一度始めたら終わりではなく、定期的な見直しが大切 です。マネイロなら運用後の相談も何度でも無料で対応。長期的なサポートを受けながら資産形成を進めることができます。
▽早速 空いている日程から相談予約してみる▽
まとめ
この記事では、中小企業の退職金平均額について、勤続年数や学歴、退職理由といったさまざまな角度から解説しました。
退職金は、一般的に勤続年数や自己都合か会社都合かによって金額が大きく変わります。さらに学歴によっても差が生まれることが東京都産業労働局の調査から明らかになっています。
とはいえ、退職金の額は、会社の規約や個人の状況で大きく変わります。勤め先の会社に退職金制度があるかどうか、また自身の退職金額の目安などを確認するには、まずは会社の就業規則などをチェックすることから始めるとよいでしょう。
また、退職金を有効活用するためには、生活費と予備資金をしっかり確保した上で、「守る」運用と「増やす」運用をバランスよく検討することが大切です。そして、必要に応じて専門家にアドバイスを仰ぐことで、より安心して退職金を活用し、豊かな退職後の人生を送るための準備を進めることができるでしょう。
≫退職金で足りる?あなたの老後に必要な金額を3分で診断
退職金が気になるあなたへ
これからの人生をお金の不安なく暮らすために、老後資金の準備は大切です。マネイロでは、将来資金を賢く準備するための無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。