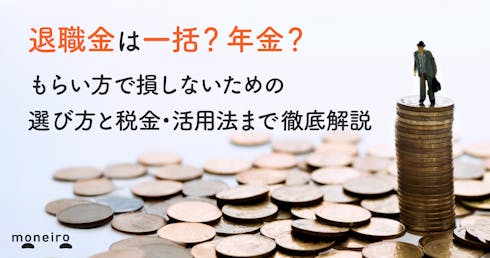
【社労士監修】退職給付金とは?種類や関連の公的支援など基本をわかりやすく解説
≫あなたの老後は大丈夫?将来の必要資金を3分で診断
退職後の生活設計を考える上で、退職給付金は非常に重要です。しかし、「どんな種類がある?」「自分の場合はいくらもらえる?」など、具体的な内容について不安を感じていませんか?
この記事では、退職給付金や、退職後に受けられる公的な支援制度に関する基本的な知識から、具体的な種類まで詳しく解説します。退職給付金の知識を深め、不安のない将来に向けた準備を進めましょう。
- 退職給付金の基本的な仕組みと種類
- 退職後に利用できる公的な支援制度
- 退職給付金にかかる税金の重要ポイント
退職金が気になるあなたへ
これからの人生をお金の不安なく暮らすために、老後資金の準備は大切です。マネイロでは、将来資金を賢く準備するための無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
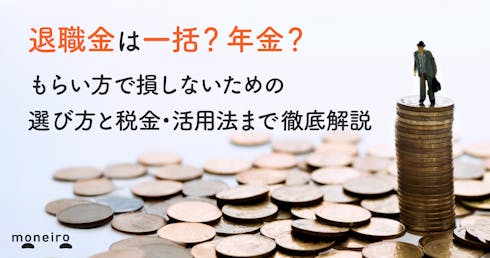

退職給付金とは?基本をおさらい
退職給付金とは、会社を辞める時に、勤め先からもらえるお金の総称です。長年働いてくれたことへの感謝の気持ちを込めて支払われ、退職後の生活を支える大切な資金となります。
もらい方には、一度にまとめて受け取る「退職一時金」と、分割して受け取る「退職年金」の2つの主要な方法があります。
ただし、法律で「必ず支払わなければならない」と決められているわけではないため、すべての会社に退職給付金の制度があるわけではありません。
制度があるかどうか、どのような内容なのかは、会社の就業規則や退職金規程で決められていますので、事前に就業規則などで確認しておくことが重要です。
退職給付金の種類
退職給付金は、大きく「退職一時金」「退職年金」に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分のライフプランに合った受け取り方を考えることが大切です。
退職一時金:退職時に一括で受け取る給付金
退職一時金は、従業員が退職する際に、企業から一括で支払われる退職金です。これは、退職後の生活資金として活用されることが多く、その後のライフプランの選択肢を広げる上で重要な役割を果たします。
退職一時金の決定方法
退職一時金の決定方法は企業によってさまざまですが、一般的には以下の要素が考慮されます。
・退職時の基本給:退職時の基本給をベースに計算されるケースが多いです。
・退職理由:自己都合退職か会社都合退職かによって支給率が異なる場合があります。
・功績加算:会社への貢献度に応じて、加算される場合があります。
具体的な計算式は、企業の退職金規程に明記されています。例えば、「退職時の基本給 × 勤続年数に応じた支給率」といった形式が一般的です。
退職年金:退職後に年金として分割受け取りする制度
退職年金は、退職後に年金として分割して受け取る制度です。これにより、退職後も一定期間にわたって安定した収入を得ることができ、長期的な生活設計に役立てることができます。退職年金制度には、主に「確定給付企業年金(DB)」と「企業型確定拠出年金(企業型DC)」の2種類があります。
確定給付企業年金(DB)
企業が将来の給付額をあらかじめ約束する年金制度です。企業が掛金を拠出し、運用リスクを負うため、従業員は将来の受給額を予測しやすいという特徴があります。
DBでは、事前に定められた計算式に基づき、勤続年数や退職時の給与などによって受給額が決まります。企業が運用責任を負うため、運用実績が悪化しても、原則として約束された給付額が支払われます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業(または個人)が掛金を拠出し、従業員自身が運用を行う年金制度です。運用成果によって将来の受給額が変動するため、従業員自身が運用リスクを負うことになりますが、運用の自由度が高いという特徴があります。個人型確定拠出年金(iDeCo)も企業型DCと同様、運用成果によって受給額が変動します。
企業型DCでは、掛金の拠出額と運用成果によって受給額が変動します。
運用がうまくいけば受給額が増える可能性がありますが、運用に失敗すると受給額が減るリスクもあります。
退職金が気になるあなたへ
これからの人生をお金の不安なく暮らすために、老後資金の準備は大切です。マネイロでは、将来資金を賢く準備するための無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
退職金共済制度:会社に退職金制度がない場合に
退職金共済制度は、中小企業を中心に導入されている退職年金制度です。外部の共済制度を利用して退職金を積み立て、支払う仕組みです。特に、自社で退職金制度を設けることが難しい中小企業にとって、従業員の福利厚生を充実させる上で有効な制度です。
代表的なものとして、中小企業退職金共済制度(中退共)があります。企業が掛金を拠出し、従業員は退職時に共済機構から直接退職金を受け取ります。
退職金共済制度はいくらもらえる?
退職金共済制度の受給額は、掛金月額と掛金納付月数(勤続年数)などによって決まります。制度ごとに定められた計算方法に基づいて支給額が算定され、運用利回りも考慮される場合があります。
≫あなたの老後は大丈夫?将来の必要資金を3分でシミュレーション
【その他】退職後に受けられる公的な支援・給付金
上で紹介した退職給付金以外にも、退職後の生活を支える国の支援制度がいくつもあります。失業した場合や病気で働けない場合など、状況に応じて活用できる制度を知っておきましょう。
失業保険
一般的に「失業保険」と呼ばれるのは、「雇用保険制度の基本手当」のことを指します。
この給付は、失業した方が生活を安定させながら再就職を目指すことを目的としており、会社を辞めて次の仕事を探す間の大切な生活資金となります。
受給には条件があり、単に仕事を辞めたからといって自動的にもらえるわけではありません。ハローワークで求職の申込みを行い、受給資格が認められる手続きを経て支給が始まります。
失業保険の支給要件
失業保険(基本手当)をもらうには、原則として辞める日より前の2年間に、雇用保険に入っていた期間が合計で12ヶ月以上必要です。
ただし、会社の倒産や解雇といった、やむを得ない理由で辞めることになった「特定受給資格者」などに該当する場合は、辞める日より前の1年間に雇用保険に入っていた期間が合計6ヶ月以上あれば条件を満たします。
また、単に会社を辞めただけでなく、「失業の状態」にあることも条件です。「失業の状態」とは具体的には、就職する積極的な気持ちと、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、実際に仕事を探しているにもかかわらず、仕事に就けない状態を指します。
参照:離職されたみなさまへ|厚生労働省
傷病手当金
傷病手当金は、業務外の病気やケガで休業した場合に、本人と家族の生活を支えるために健康保険から支給される給付金です。会社から給与が十分に支払われないときに、生活保障として一定期間受け取ることができるお金のことを指します。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金をもらうためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
・仕事に就くことができない状態であること:医師の意見などを基に判断されます。
・連続する3日間を含む4日以上休んでいること:最初の3日間は「待期期間」となり、4日目からもらえるようになります。
・休業期間中に給与の支払いがないこと:給与が支払われても、傷病手当金の額より少なければ差額がもらえます。
一定要件を満たせば、退職後も傷病手当金を継続して受給できます。
求職者支援制度
求職者支援制度は、雇用保険をもらえない求職者の方を対象とした国の支援です。再就職やスキルアップを目指す方が、無料の職業訓練を受けながら、一定の条件を満たせば月10万円の給付金をもらって生活の支援を受けられる仕組みになっています。
求職者支援制度の支給要件
求職者支援制度の給付金をもらうには、主に以下の条件を満たす必要があります。
・資産の条件:世帯全体の金融資産が300万円以下であること
・出席の条件:訓練実施日のすべてに出席すること(やむを得ない理由がある場合でも8割以上の出席が必要)
その他、ハローワークが職業訓練の支援を行う必要があると認めたことなどが条件となります。
参照:求職者支援制度のご案内|厚生労働省
求職者支援金融資制度
求職者支援金融資制度は、求職者支援制度の職業訓練受講給付金だけでは生活費が足りない方を対象とした貸付制度です。
訓練期間中の生活を支えるため、労働金庫(ろうきん)からお金を借りることができます。あくまで貸付のため、返済する義務があります。
求職者支援金融資制度の支給要件
この融資制度を利用するには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
・ハローワークで「求職者支援資金融資要件確認書」の交付を受けていること
求職者支援資金融資要件確認書は、お金を借りたい理由が妥当であり、返済する意思があるとハローワークに認められた場合に交付されます。
広域求職活動費
広域求職活動費は、雇用保険をもらっている方が、ハローワークの紹介で遠くの会社へ面接などに行く際に支給される手当です。交通費や宿泊費の一部が補助され、遠方での就職活動を経済的に支援することを目的としています。
広域求職活動費の支給要件
広域求職活動費をもらうには、いくつかの条件があります。
もっとも重要なのは、移動距離の条件です。現在手続きをしているハローワークから、面接先企業の所在地を管轄するハローワークまでの往復距離が、原則として200km以上ある必要があります。
その他、ハローワークが紹介した常用求人であることなども条件となります。
参照:「広域求職活動費」と「移動費」のご案内|厚生労働省
就職促進給付金
就職促進給付は、失業保険(基本手当)をもらう資格がある方が、早期に再就職した場合に支給される手当の総称です。
代表的なものに「再就職手当」があり、これは安定した職業に早く就くことを応援し、お祝い金のような形で支給されるものです。
就職促進給付金の支給要件
就職促進給付の代表である再就職手当をもらうには、いくつかの条件を満たす必要があります。
特に重要なのが支給残日数です。就職日の前日時点で、失業保険の支給日数が所定給付日数の3分の1以上残っていることが必須条件となります。
また、7日間の待期期間が満了した後の就職であることなども求められます。
参照:就職促進給付金について|厚生労働省
未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度は、勤め先の会社が倒産したことによって、給与や退職金が支払われないまま退職せざるを得なくなった労働者を救済するための制度です。
国(労働者健康安全機構)が事業主に代わって、未払い賃金の一部を立て替えて支払います。
未払賃金立替払制度の支給要件
この制度を利用するには、まず勤め先の会社が倒産状態であることが大前提です。具体的には、法律上の倒産(破産など)や、労働基準監督署が認定する事実上の倒産が該当します。
また、労働者自身も、倒産の申立てなどが行われる6ヶ月前の日から2年の間にその会社を退職している必要があります。
参照:未払賃金の立替払制度の概要|厚生労働省
特例一時金
特例一時金は、季節的な仕事に従事する方や、短期間の雇用を繰り返す「短期雇用特例被保険者」が失業した場合に支給される手当です。通常の失業保険(基本手当)とは異なり、一時金として支払われるのが特徴です。
特例一時金の支給要件
特例一時金をもらうための主な条件として、まず被保険者期間が挙げられます。辞める日より前の1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が、合計して6ヶ月以上必要です。
加えて、通常の失業保険と同様に「失業の状態」にあることが求められます。これは、就職への積極的な意思と能力があり、実際に仕事を探しているにもかかわらず、就職できていない状態を指します。
参照:離職されたみなさまへ <特例一時金のご案内>|厚生労働省
退職給付金にかかる税金3つのポイント
退職給付金には所得税と住民税がかかりますが、税負担を軽くするための優遇措置が設けられています。
退職給付金にかかる税金を理解する上で重要なのは、退職所得控除、受け取り方による課税方式の違い、そして確定申告の要否の3点です。これらを把握することで、手取り額を最大化するための計画を立てやすくなります。
1.退職所得控除による大幅な税負担軽減
退職給付金は「退職所得」として扱われ、他の所得とは分離して課税される「分離課税」の対象となります。
また、退職所得には「退職所得控除」という特別な控除が適用されるため、税負担が大幅に軽減されます。
さらに、課税所得は退職所得(控除後の金額)の1/2であるため、給与所得などと比較して所得税は大幅に軽減できます。
勤続年数20年を境にした控除額の計算方法
退職所得控除の計算方法は、勤続年数が20年を超えるかどうかで異なります。
・勤続年数20年超の場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
勤続年数が20年を超えると1年あたりの控除額の増額幅は70万円にアップします。
2.退職一時金と退職年金で異なる課税方式
退職給付金は、退職一時金として一括で受け取るか、退職年金として分割で受け取るかによって課税方式が異なります。
・退職年金の場合:公的年金等と同様に「雑所得」として総合課税されます。公的年金等控除が適用されますが、退職一時金と比べると、税負担は重くなる傾向があります。
3.確定申告が不要になるケースと必要なケース
退職給付金を受け取る際、原則として「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、会社が所得税・住民税を計算し、源泉徴収してくれるため、確定申告は不要です。
ただし、次の場合は確定申告が必要になることがあります。
・2社以上から退職給付金を受け取った場合
・年金形式で退職給付金を受け取り、他に所得がある場合
退職給付金に関するよくある質問
退職給付金に関するよくある質問にお答えします。
退職給付金は必ずもらえるもの?
いいえ、必ずもらえるわけではありません。
退職給付金制度は法律で義務付けられていないため、制度自体がない会社もあります。支給の有無や条件は、勤め先の就業規則や退職金規程によって定められているため、事前に確認することが重要です。
また、退職後に受けられる公的な支援についても、それぞれに要件があるため、確認しておくとよいでしょう。
パートや契約社員でも退職給付金は受け取れる?
勤め先の退職金規程によって異なります。規程にパートタイマーや契約社員も支給対象と明記されていれば、受け取ることが可能です。
近年は、同一労働同一賃金の考え方から、非正規雇用の従業員にも退職金を支給する企業が増えています。まずは、勤めている会社の就業規則や退職金規程を確認しましょう。
退職給付金を受け取る際に必要な手続きはありますか?
会社によって異なりますが、退職届の提出と同時に、退職金の請求手続きに関する書類(振込先口座の指定など)を提出するのが一般的です。
まとめ
退職給付金は、退職後の生活を支える重要な資金です。本記事では、その基本から種類、公的な支援制度、税金のポイントまでを解説しました。
主な退職給付金には「退職一時金」「退職年金(DB・企業型DC)」「退職金共済制度」があり、それぞれ特徴が異なります。
また、失業保険や傷病手当金といった公的な支援も、退職後には大きな助けとなります。これらの制度は自ら申請する必要があるため、条件に当てはまるかを確認し、早めに手続きを行いましょう。
まずは、勤めている会社の退職給付金制度の内容を就業規則で確認した上、今回紹介した情報を将来に向けた計画的な資産形成にお役立てください。
≫あなたの老後は大丈夫?将来の必要資金を3分で診断
退職金が気になるあなたへ
これからの人生をお金の不安なく暮らすために、老後資金の準備は大切です。マネイロでは、将来資金を賢く準備するための無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
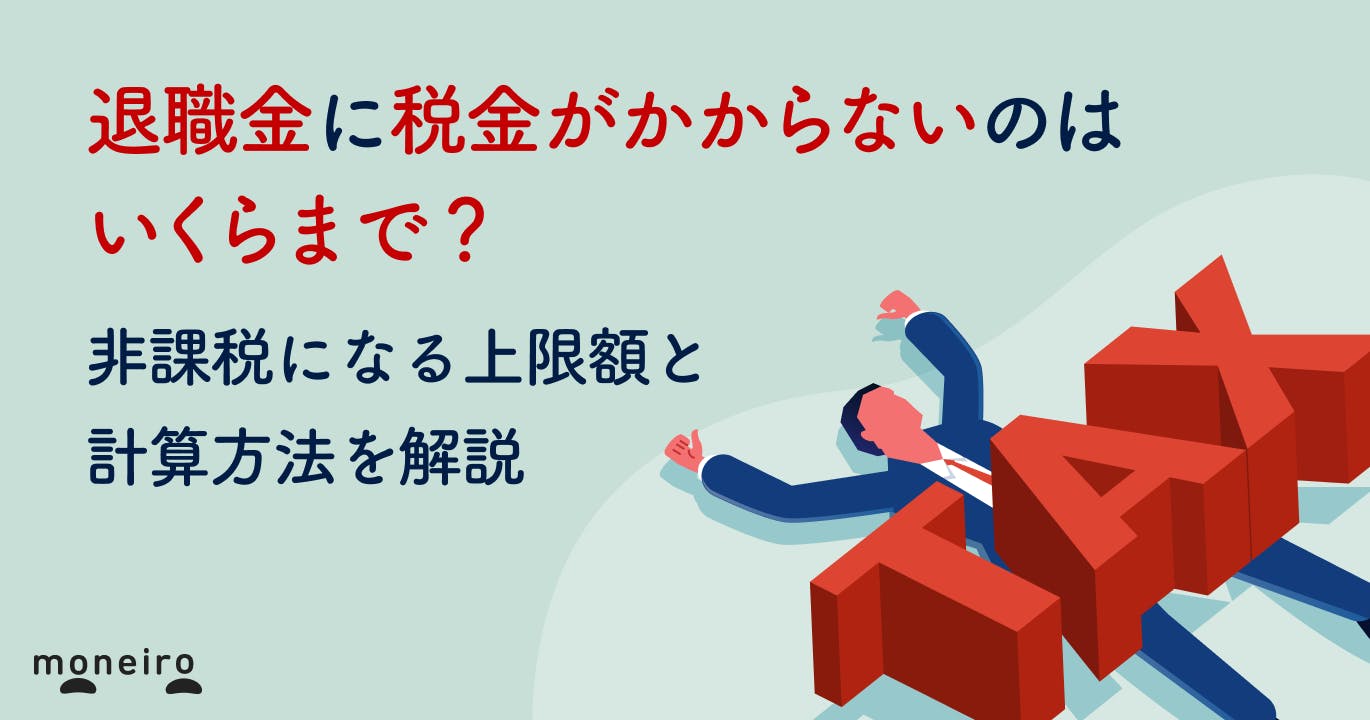
退職金に税金がかからないのはいくらまで?非課税になる上限額と計算方法を解説
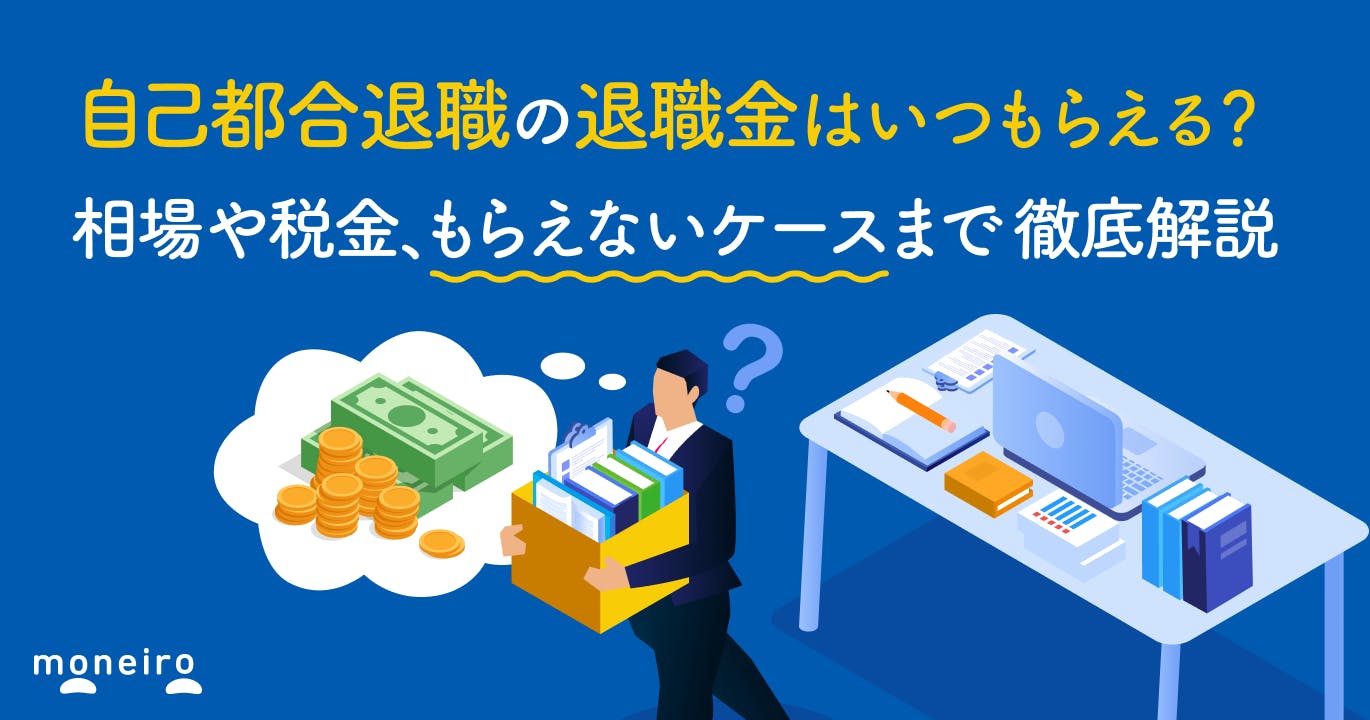
自己都合退職の退職金はいつもらえる?相場や税金、もらえないケースまで徹底解説

早期退職すると退職金はどうなる?公務員や自衛隊の場合は?相場を詳しく解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
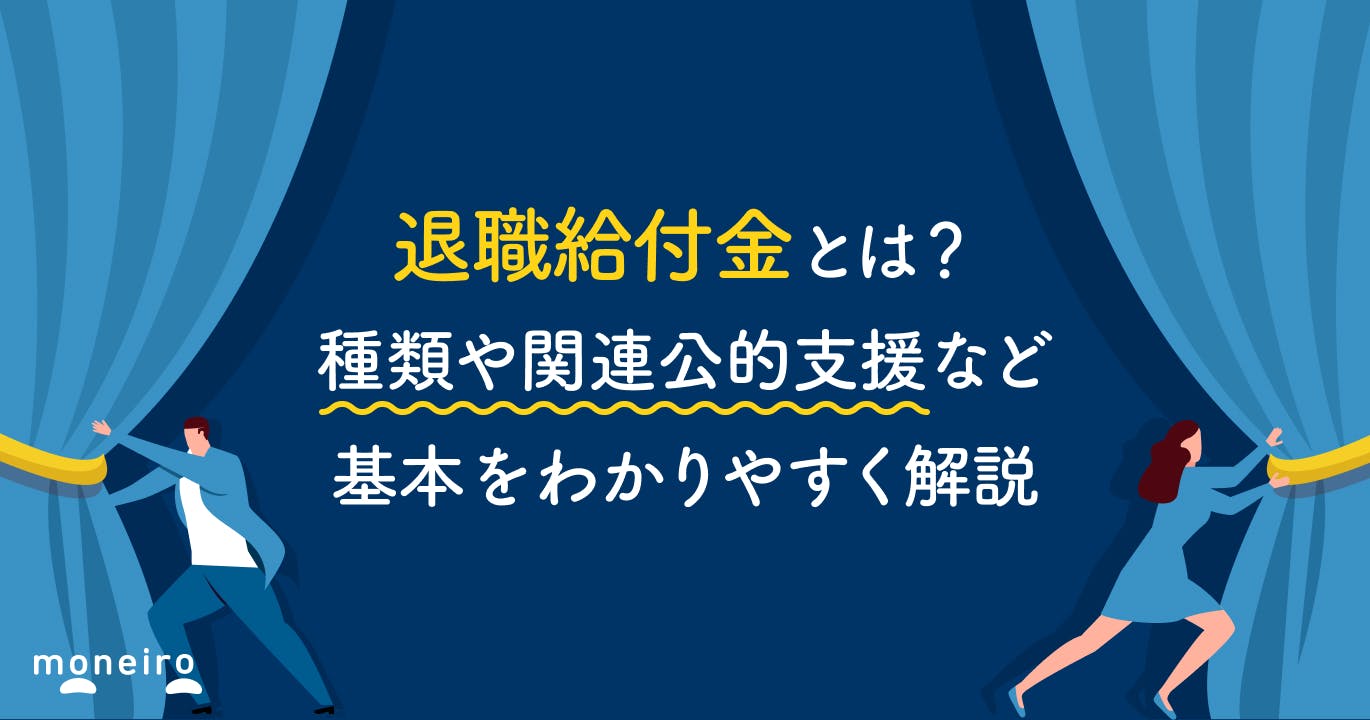
.png?w=1370&h=720&fit=crop&crop=faces&auto=compress,format)