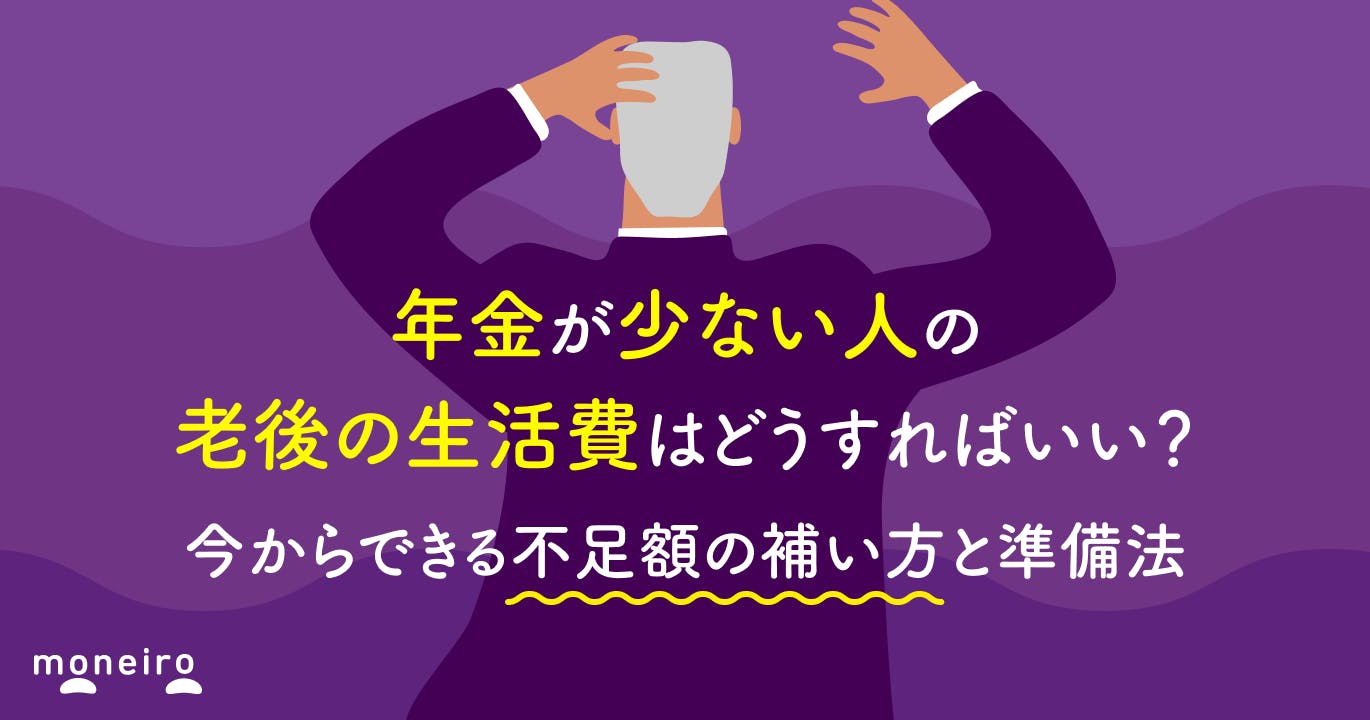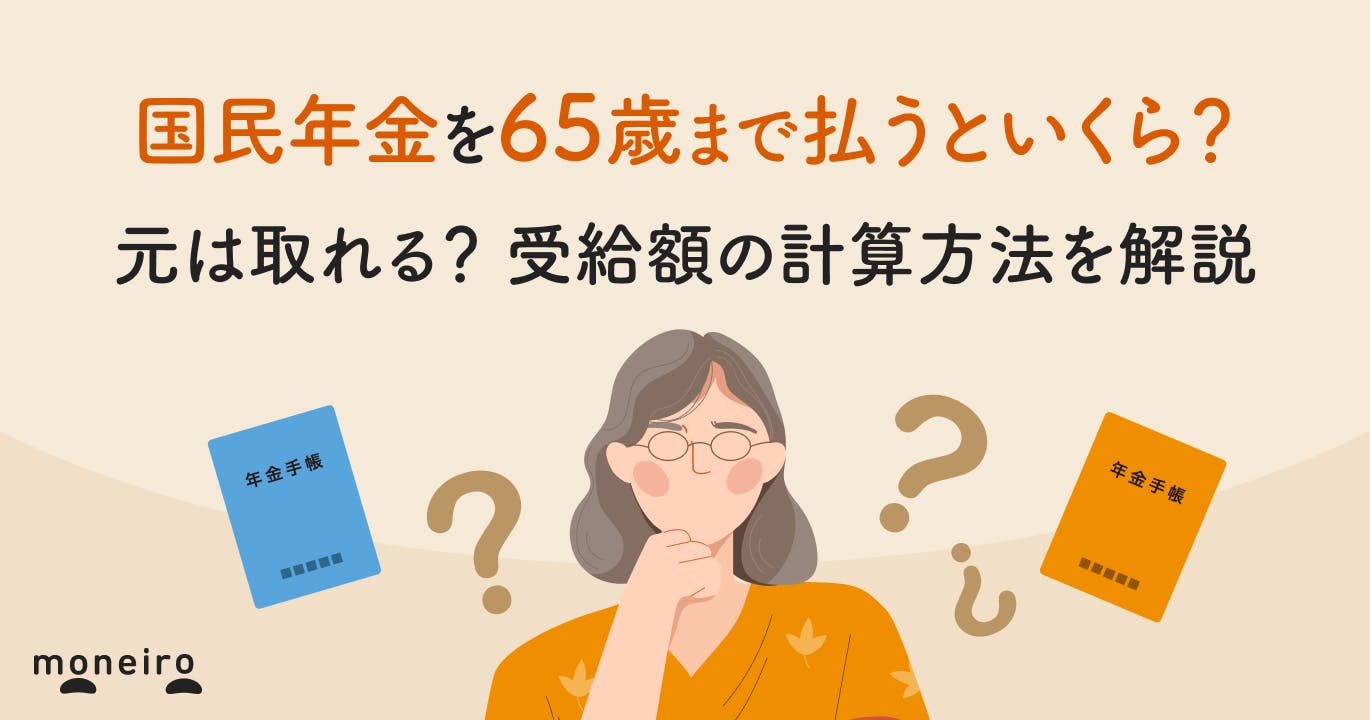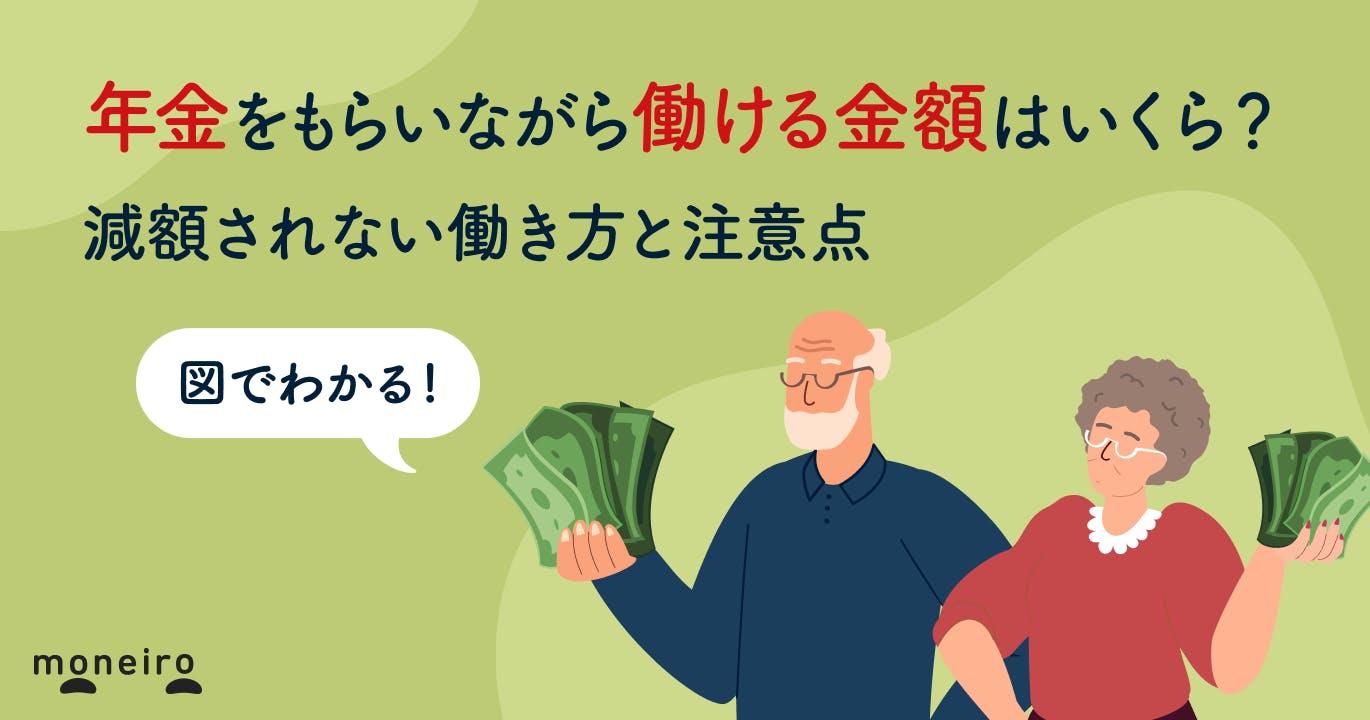特別支給の老齢厚生年金のデメリットや注意点は?制度の特徴・手続きを解説
≫あなたの老後は大丈夫?将来の必要額を3分で診断
特別支給の老齢厚生年金は、65歳を待たずに年金を受け取れる制度ですが、「もらって大丈夫?」「繰上げ受給とは違う?」といった不安や疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、特別支給の老齢厚生年金のデメリットや注意点など、請求前に知るべき注意点を解説します。ぜひ自身の状況に合わせて、受給の判断をする際の参考にしてみてください。
- 特別支給の老齢厚生年金の基本的な概要と支給要件
- 受給時に特に知っておくべきデメリットと注意点
- 年金請求の手続きの主な流れと必要な添付書類
年金の受給額が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる

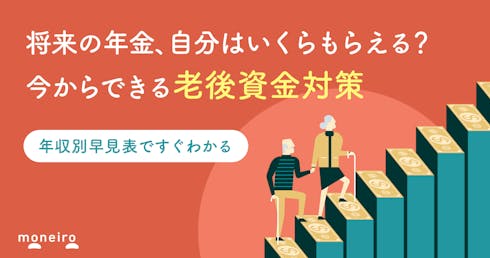
特別支給の老齢厚生年金とは?
特別支給の老齢厚生年金とは、昭和60年の法律改正により厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴い、段階的かつスムーズな移行のために設けられた制度です。
この年金には、「報酬比例部分」と「定額部分」があり、生年月日と性別に応じてそれぞれの受給開始年齢が異なります。
画像参照:特別支給の老齢厚生年金|日本年金機構
特別支給の老齢厚生年金の支給要件
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・女性の場合:昭和41年4月1日以前に生まれたこと
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
なお、在職中の方は、報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。
特別支給の老齢厚生年金のデメリット・注意点
特別支給の老齢厚生年金の受給を検討する際には、いくつかの注意点やデメリットを理解しておくことが重要です。
在職老齢年金制度による減額
特別支給の老齢厚生年金を受け取りながら働き続ける場合、勤務先からの報酬や年金額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。これを「在職老齢年金制度」と呼びます。
雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受けている場合も、65歳までに支給される老齢厚生年金の全部または一部が受け取れません。
税金の負担が増える
特別支給の老齢厚生年金は所得として扱われるため、受給額によっては所得税や住民税の課税対象となります。
特に、働きながら年金を受け取る場合、給与と年金が合算され、課税所得が増加し、税負担が重くなる可能性があります。
≫老後は大丈夫?あなたが将来に必要な金額を3分で診断
繰下げ受給ができない
特別支給の老齢厚生年金は、65歳からの老齢年金とは異なり、「繰下げ制度」がありません。つまり、請求を遅らせても年金額が増額することはありません。
そのため、受給権が発生した場合は速やかに請求手続きを行うことが推奨されています。
請求しないともらえない
特別支給の老齢厚生年金は、受給資格を満たしたからといって自動的に支給が始まるものではなく、受給には「年金請求書」を提出する手続きが必要です。
年金を受け取れるようになった日から5年を過ぎると、法律に基づき、5年超過分については時効によって受け取れなくなるため、早めに手続きをすることが重要です。
年金の受給額が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
特別支給の老齢厚生年金のメリットもチェック
デメリットだけでなく、特別支給の老齢厚生年金にはメリットもあります。
65歳を待たずに現金収入が得られる
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年以上)を満たしている、といった所定の要件を満たす人は、原則65歳から受け取れる老齢厚生年金よりも早く、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
これにより、65歳を待たずに収入源を確保できるというメリットがあります。
もらっても65歳からの本来の年金額は減らない
通常、年金は繰上げ受給すると年金額が減額されますが、特別支給の老齢厚生年金は経過措置として設けられた制度であり、受給しても65歳以降の年金に影響を与えません。
これにより、早期に収入を得ながら、将来の年金受給額を維持できます。
【よくある誤解】繰上げ受給とは違うの?
特別支給の老齢厚生年金は、65歳より前から受け取れる場合がありますが、これは年金制度でいう「繰上げ受給」とはまったく異なります。
繰上げ受給は、本来の支給開始年齢より前に受け取る代わりに、受給額が請求月に応じて減額され、その減額が一生続く仕組みです。一方の特別支給の老齢厚生年金は、制度移行期の一時的な措置として設けられた制度です。そのため、65歳より前から受給したとしても減額はありません。
特別支給の老齢厚生年金の支給手続き
特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、日本年金機構への請求手続きが必要です。手続きの流れは以下の通りです。
1.請求書の事前送付
日本年金機構では、特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対し、受給開始年齢に到達する3ヶ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、年金加入記録が印字された「年金請求書(事前送付用)」と手続き案内が郵送されます。
2.請求書の提出
請求書は、受給開始年齢(誕生日の前日)に到達した後、提出が可能となります。受給開始年齢になる前に提出された場合は、受け付けられませんので注意が必要です。
提出は、年金事務所や街角の年金相談センターの窓口へ持参するか、年金事務所へ郵送することも可能です。窓口での手続きは予約相談の利用が推奨されています。
なお、年金請求書の審査結果は、受け付けから1〜2ヶ月程度で「年金証書・年金決定通知書」などにより通知されます。
必要書類
年金請求に必要な主な添付書類は以下の通りです。ただし、マイナンバーを年金請求書に記入することで、戸籍、住民票、所得証明書などの添付を省略できる場合があります。
・年金の受取口座を確認する書類(金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー)
・雇用保険に関する書類
・生年月日を確認する書類(戸籍抄本、戸籍謄本、住民票のいずれか)
・戸籍謄本や住民票、所得証明書など(配偶者や子がいる場合
・その他(年金手帳、年金加入期間確認通知書など)
特別支給の老齢厚生年金に関するQ&A
特別支給の老齢厚生年金に関するよくある質問にお答えします。
Q. 受給の申請を忘れていた場合、どうすればいい?
特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分については時効により受け取れなくなります。
そのため、申請を忘れていた場合は、できるだけ早く年金請求の手続きを行う必要があります。
Q. 働きながら特別支給の老齢厚生年金を受け取ることはできる?
はい、働きながらでも特別支給の老齢厚生年金を受け取ることは可能です。
しかし、厚生年金保険に加入中の方の場合、勤務先からの報酬と年金額の合計額によっては、年金の一部または全部が支給停止されることがあります。また、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受けている方は、65歳までに支給される老齢厚生年金の全部または一部が減額されます。
まとめ
特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢を65歳に引き上げる際の経過措置として設けられた制度です。65歳を待たずに年金を受け取ることができるため、老後の生活を送る上で非常に重要な制度です。
ただし、受給にあたっては、在職中の報酬による年金額の減額(在職老齢年金制度)や、「繰下げ受給ができない」という特性を理解しておくことが重要です。
また、年金は自動的に支給されるものではなく、自身で請求手続きを行う必要があります。受給開始年齢到達後は速やかに手続きを行い、5年の時効で年金を受け取れなくなる事態にならないよう注意しましょう。
まずは自身の状況を確認した上で、必要に応じて日本年金機構のWebサイトや年金事務所の相談窓口などを利用しながら、適切なタイミングでの手続きを検討しましょう。
≫老後は大丈夫?あなたが将来に必要な金額を3分で診断
年金の受給額が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
.png?auto=format,compress&fit=max&w=3840)