
証券会社の資産が1000万円以上になったら分けるべき?銀行ペイオフとの違いを解説
≫将来の資産は大丈夫?あなたの必要資金を計算
証券会社の口座資産が1000万円以上になったとき、銀行の預金保険制度(ペイオフ)のように「資産を分けるべきか」と不安に感じる方は多いでしょう。しかし、証券会社における資産保護の仕組みは銀行とは根本的に異なり、「分別管理」という仕組みがその根幹です。
本記事では、証券会社が破綻しても資産が守られる仕組みや投資者保護基金の役割、そして口座を分けるべきかの判断基準を詳しく解説します。
- 銀行のペイオフ制度と、証券会社の資産保護の仕組みである「分別管理」の違い
- 証券会社が破綻した場合でも顧客資産が保護される「二重構造」の仕組み
- 資産を複数の証券会社に分けることのメリット・デメリット
資産管理が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
「証券会社の1000万円」は分けるべき?
結論からいうと、証券会社に資産が1000万円以上になったとしても、原則として銀行預金のように緊急に資産を分ける必要はありません。
この違いは、銀行と証券会社のビジネスモデルに起因します。銀行は預金者から預かった預金を「会社の資産」として貸付などで運用しますが、破綻した場合は預金が返せなくなるリスクがあるため、1000万円までの保険(ペイオフ)が必要です。
一方、証券会社は顧客の資産(株や投資信託など)を「預かっているだけ」で、それは証券会社自身の資産とは明確に区別されます。そのため、証券会社が破綻しても、顧客の資産はそのまま返すのが原則となります。
そもそも銀行の預金保険制度(ペイオフ)とは?
証券会社の保護制度をより深く理解するために、まずは銀行の預金保険制度、通称「ペイオフ」について確認しておきましょう。銀行は預かったお金を運用することで利益を得るため、万が一経営破綻した場合、預金が全額戻らないリスクがあります。
このリスクをカバーするために存在するのがペイオフ制度です。ペイオフ制度では、1金融機関あたり、預金者1人につき「一般預金等」(定期預金や普通預金など)は元本1000万円とその利息までが保護の対象となります。一方、「決済用預金」(無利息、要求払い、決済サービスを提供できることの3要件を満たす預金)は、全額保護の対象となります。
この上限があるため、多くの資産を保有している場合、リスク管理のためにペイオフの上限を超えないよう複数の銀行に資産を分散させることが大切です。
証券会社の資産を守る鉄壁の「二重構造」
証券会社に預けた顧客の資産は、銀行のペイオフ制度に依存するのではなく、むしろさらに強力な「二重構造」によって守られています。
この二重構造は、「分別管理」と「投資者保護基金(JIPF)」の2つの仕組みから成り立っています。ほとんどの場合、第1の壁である分別管理が機能することで、資産は保全されます。第2の壁である投資者保護基金は、分別管理が何らかの理由で機能しなかった例外的なケースでのみ発動する、万が一の補償制度であることを理解しておく必要があります。
第1の壁:顧客資産の「分別管理」(資産そのものを守る)
証券会社の資産保護においてもっとも重要な仕組みが、顧客資産の「分別管理」です。これは、金融商品取引法によってすべての証券会社に厳格に義務付けられている制度です。分別管理では、顧客から預かった資産は、証券会社の固有資産とは完全に区別して保管されます。
具体的には、分別管理は以下のように行われます。
- 有価証券(株式・投資信託など):顧客ごとに明確に区分し、証券会社の固有資産とは別に保管されます。
- 現金(預り金・MRFなど):顧客分別金として信託銀行などに「信託」され、証券会社の資産とは完全に分離されます。
この分別管理が徹底されていれば、仮に証券会社が破綻したとしても、顧客の資産は全額(1000万円以上でも)保全され、顧客にそのまま返還されるか、または他の証券会社へ円滑に移管されることになります。
第2の壁:「投資者保護基金(JIPF)」(万が一の補償)
証券会社に預けた資産を守るための第2の壁が「投資者保護基金(Japan Investor Protection Fund, JIPF)」です。これは、不測の事態により顧客の財産が被害を受けた場合に、1人あたり1000万円を上限に損失を補償する制度です。
JIPFが発動するのは、具体的には証券会社の経営破綻により、顧客から預託された金銭及び有価証券の返還が困難になった場合です。これは、分別管理が適切に行われなかったことによる資産の欠損など、第一の壁が破られた場合の最後のセーフティネットとして機能します。
投資者保護基金は、投資元本そのものや、市場価格の変動によって生じた損失を補償するものではありません。
【重要】1000万円以上で「保護されない」2つの落とし穴
証券会社の資産は原則「全額保護」ですが、特定のサービスを利用しているがゆえに、保護対象外のリスクが発生するケースがあります。
1. 「銀行連携口座(スイープ)」はペイオフ対象
多くのネット証券では、証券口座と銀行口座を連携させ、資金を自動で移動させる「スイープサービス(例:SBIハイブリッド預金、マネーブリッジなど)」を提供しています。非常に便利ですが、この連携口座にある資金の実体は「銀行預金」です。
証券会社の画面で残高を確認できても、法的には銀行に預けている状態となるため、連携先の銀行が破綻した場合はペイオフ制度(元本1000万円まで)の対象となります。「証券口座に入れているつもり」で1000万円以上を置いておくと、万が一の際にカットされるリスクがあります。
2. 「貸株サービス」中の株は保護対象外のリスク
保有している株を証券会社に貸し出して金利を得る「貸株サービス」というものがあります。この利用中、株の所有権は一時的に証券会社に移転しています。
そのため、多くの証券会社では「貸株中の株式は分別管理および投資者保護基金の対象外」としています。もし貸株中に証券会社が破綻した場合、貸していた株は戻ってこない(一般債権者としての請求になる)可能性があります。大口資産家の場合は、貸株設定のオン・オフを慎重に判断する必要があります。
資産管理が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
【実例】過去、証券会社が破綻した時、顧客の資産はどうなったのか?
実際に証券会社が経営破綻した場合、前述した二重構造の保護制度がどのように機能したのか、具体的な事例を通じて確認してみましょう。
ケース1:山一證券の自主廃業(1997年)
1997年、日本の証券業界で大きな衝撃を与えたのが、山一證券の自主廃業です。山一證券は、簿外債務の存在が明らかになり、経営破綻に追い込まれましたが、このケースでは、顧客資産の分別管理が適切に行われていました。
顧客が預けていた株式や投資信託などの有価証券、および預り金は、証券会社自身の資産とは明確に区別されていたため、資産そのものは保全されました。
その後、顧客の資産は速やかに他の証券会社への移管などの手続きを通じて対応され、投資者保護基金が発動することなく、顧客資産は保護されました。これは、分別管理という第一の壁が有効に機能した事例の1つといえます。
ケース2:リーマン・ブラザーズ証券の経営破綻(2008年)
2008年、米国本社のリーマン・ブラザーズが経営破綻(リーマン・ショック)し、その影響は世界中の金融市場に波及しました。これに伴い、日本で証券業務を行っていたリーマン・ブラザーズ証券(日本法人)も連鎖的に経営破綻に陥りました。
この際、金融庁は直ちに業務停止命令と資産国内保有命令を発令し、顧客から預かっていた現金・有価証券の流出を阻止しています。その結果、国内保管資産は速やかに返還され、海外保管資産も数ヶ月以内にほぼ全額が顧客に還付されています。決済不履行(DVP)リスクも発生せず、顧客が元本を失う事例は実質ゼロでした。
このケースは、大規模破綻でも分別管理が機能すれば投資者保護基金の補償を必要としないことを示す、制度の成功例として評価されています。
制度は万全…それでも資産を分けるべき4つのメリット
証券会社の保護制度は万全であると理解できたとしても、資産を複数の口座に分けることには、運用上の利便性やリスク管理の観点から、以下のようなメリットが存在します。
1. システム障害・メンテナンス時の取引機会損失を防ぐ
資産を1つの証券会社に集中させている場合、その会社の取引システムに大規模な障害が発生したり、長時間のメンテナンスが実施されたりすると、一時的に取引ができなくなります。特に市場が大きく変動しているタイミングで売買ができなくなると、意図しない損失が発生したり、利益を得る機会を逃したりする可能性があります。
複数の証券会社に口座を持っていれば、一方のシステムがダウンしても、もう一方の口座で代替の取引を行うことができ、取引機会の損失を防ぐことができます。
2. 証券会社破綻時の資産凍結期間を乗り切る
仮に分別管理が徹底されていても、証券会社が破綻した際には、顧客資産の保全や他の証券会社への移管手続きには、数週間から数ヶ月の時間(資産凍結期間)がかかる場合があります。この期間中、顧客は資産にアクセスし、売買を行うことができなくなります。
すぐに現金が必要になった場合や、重要な投資判断を下す必要が生じた際に、資産の一部が凍結されてしまうリスクは無視できません。複数の証券会社に資産を分散させておけば、凍結の影響を受ける資産を一部に留めることができます。
3. 商品・ツール・サービスを戦略的に使い分ける
証券会社ごとに、取り扱っている金融商品や提供されている取引ツール、およびサービス内容には大きな違いがあります。
例えば、A社は特定のアメリカ株の取り扱いが豊富である、B社はIPOの抽選に強い、C社はロボアドバイザーの機能が優れている、というような特性があります。
資産を複数に分けることで、それぞれの証券会社の「強み」を活かし、自分の投資戦略に応じて商品・ツール・サービスを使い分けることが可能になります。
4. 不正アクセス・出金リスクを分散する
インターネットを通じて取引を行うオンライン証券において、セキュリティ対策は非常に重要ですが、不正アクセスやサイバー攻撃のリスクはゼロではありません。万が一、一つの口座が不正アクセスの被害に遭い、顧客資産が不正に出金されてしまうような事態が発生した場合、被害は当該口座の資産全体に及ぶ可能性があります。
複数の証券会社に資産を分散させておくことは、この不正アクセスや出金のリスクを物理的に分散させることに繋がり、リスクヘッジとなります。
証券会社を分ける前に知るべきデメリットと注意点
資産を分けることにはメリットがある一方で、手間やコストが増えるというデメリットも存在します。戦略的な分散投資を行う前に、以下の注意点を把握しておきましょう。
1. 資産管理が煩雑になる(対策あり)
複数の証券会社で取引を行うようになると、管理すべき口座数が増えるため、資産全体の把握が煩雑になります。どこの口座にどれだけの資産があるのか、全体の損益がどうなっているのかを把握しにくくなる可能性があります。
対策としては、証券会社が提供している資産管理ツールや、外部の資産管理アプリなどを活用し、全資産を一覧できる環境を構築することが有効です。
2. 確定申告の手間が増える可能性がある(損益通算)
複数の証券会社で取引を行っていて、源泉徴収なしの特定口座や一般口座を利用している場合、確定申告の手間が増える可能性があります。特に、複数の口座で利益と損失が発生している場合、税負担を最適化するために損益通算を行う必要があり、その計算や書類作成が複雑になることがあります。
特定口座(源泉徴収あり)を選んでいれば原則として確定申告は不要となりますが、複数の源泉徴収ありの特定口座間で損益通算をする場合は、やはり確定申告が必要になるため注意が必要です。
3. 資産の移管には手数料と時間がかかる
現在持っている資産を1つの証券会社から別の証券会社へ移管する場合、移管元の証券会社や移管する銘柄によっては手数料が発生する場合があります。
また、移管手続きには通常、数日から数週間程度の時間がかかり、その間は当該資産の売買取引ができなくなる点も注意が必要です。
資産の分散を考える際は、将来的な移管の可能性も含めて、初期段階からどの資産をどの口座で保有するかを慎重に計画することが大切です。
証券会社と1000万円にまつわるQ&A
証券会社の資産保護や1000万円の壁に関して、よくある質問にお答えします。
Q. 証券会社が破綻しそうな兆候は分かるもの?
証券会社が破綻する兆候を事前に把握することは容易ではありません。とはいえ、大手証券会社であれば、金融当局による監督や監査を受けているため、突然の破綻は稀です。
破綻が表面化する前には、格付け機関による格付けの引き下げ、市場での株価の急落、特定のビジネスモデルからの撤退、または不祥事の報道など、何らかの経営上の危機を示す情報が流れる可能性があります。日頃から利用している証券会社のニュースや財務状況を注意深くチェックしておくことが重要です。
Q. NISA口座の資産も1000万円を超えたら分けるべき?
NISA口座(少額投資非課税制度)で保有している資産についても、通常の特定口座や一般口座と同様に、分別管理の対象となります。したがって、NISA口座の資産が1000万円を超えたとしても、保護の観点から緊急に口座を分ける必要は基本的にありません。
なお、NISA口座は1人1口座という制約があるため、複数の証券会社で同時にNISA口座を開設することはできません。複数の証券会社を利用したい場合は、特定口座や一般口座を利用して資産を分散させることになります。
Q. 証券口座の預り金(現金)が1000万円以上ある場合でも大丈夫?
証券口座内の純粋な「預り金」や「MRF」であれば、分別管理されているため1000万円以上でも原則として全額保護されます。しかし、「銀行連携口座(自動スイープ)」を利用している場合、その現金は「銀行預金」として扱われます。そのため、連携先の銀行が破綻した場合には、銀行ペイオフ制度の上限である1000万円までしか保護されません。
預けている現金が、証券会社の「預り金」にあるのか、連携先の「銀行預金」にあるのか、管理画面の設定をよく確認しておくことが重要です。
まとめ
証券会社の資産が1000万円以上になったからといって、銀行のペイオフのように緊急に資産を分ける必要は原則としてありません。
これは、証券会社が採用している「分別管理」という制度によって、顧客資産が証券会社自身の資産から完全に分離され、全額保全される仕組みが法律で義務付けられているからです。さらに、「投資者保護基金」による補償もありますが、これは分別管理に不備があった場合の例外的なセーフティネットであるといえます。
証券会社の資産は十分な保全性がありますが、システム障害対策や取引機会の確保、不正アクセス対策といった運用上のリスク分散の観点から、複数の証券会社を戦略的に使い分けることには、多くのメリットがあります。そのため、自身の投資スタイルやリスク許容度に合わせて、口座を分けるべきかを総合的に判断するとよいでしょう。
≫将来の資産は大丈夫?あなたの老後の必要資金をチェック
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

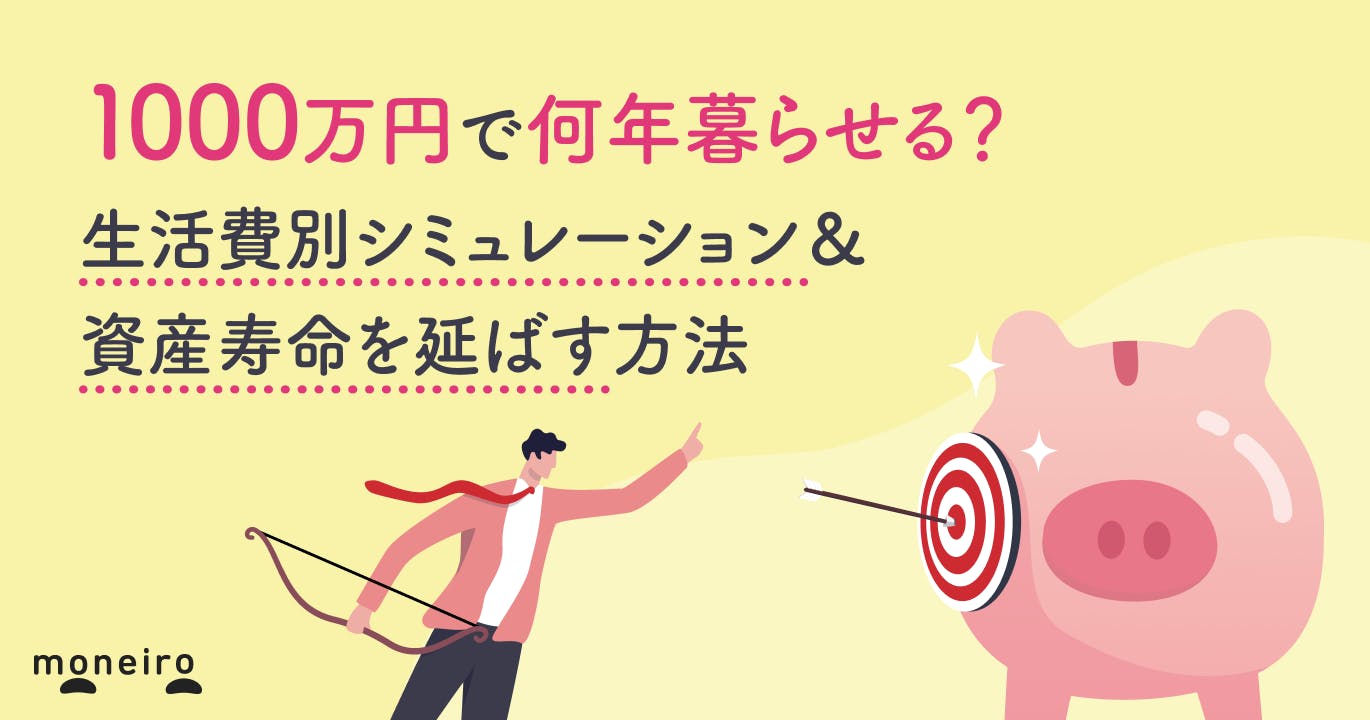
1000万円で何年暮らせる?生活費別シミュレーション&資産寿命を延ばす方法
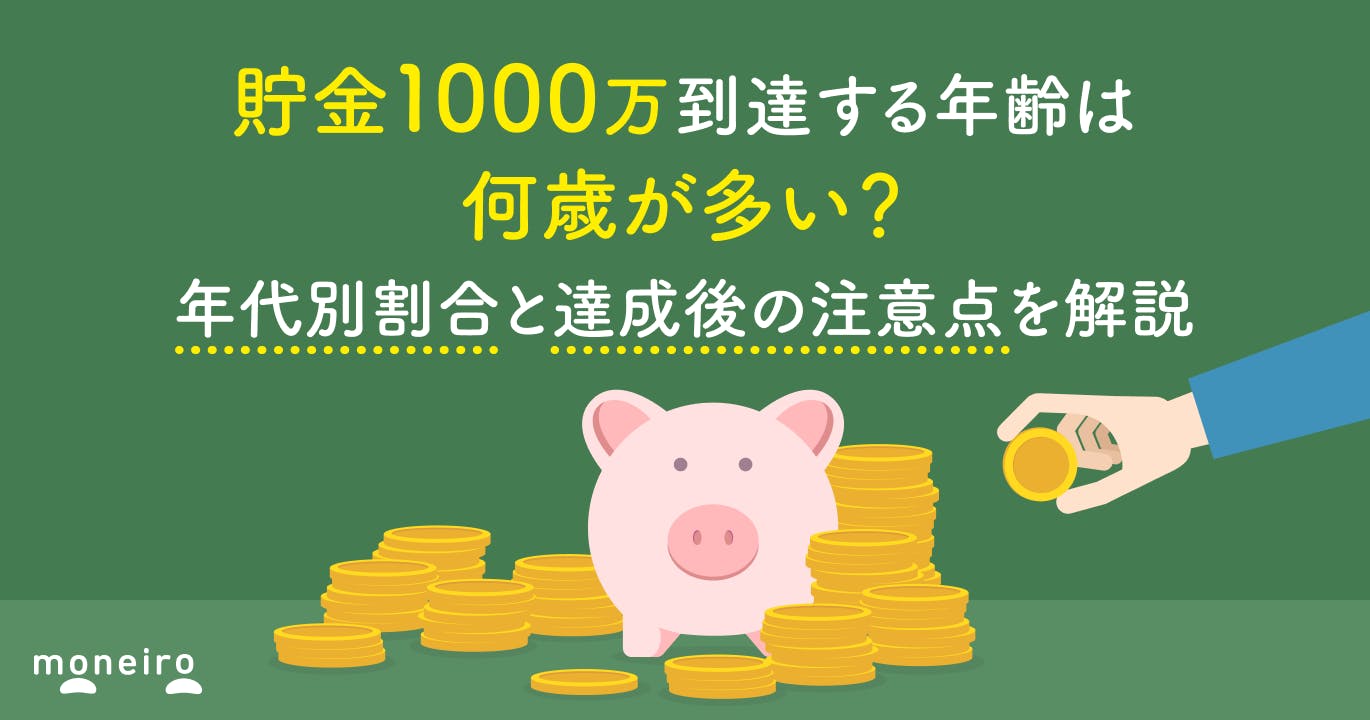
貯金1000万到達する年齢は何歳が多い?年代別割合と達成後の注意点を解説

貯金1000万円はすごい?年代別の割合&達成方法・達成後の注意点を解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。
