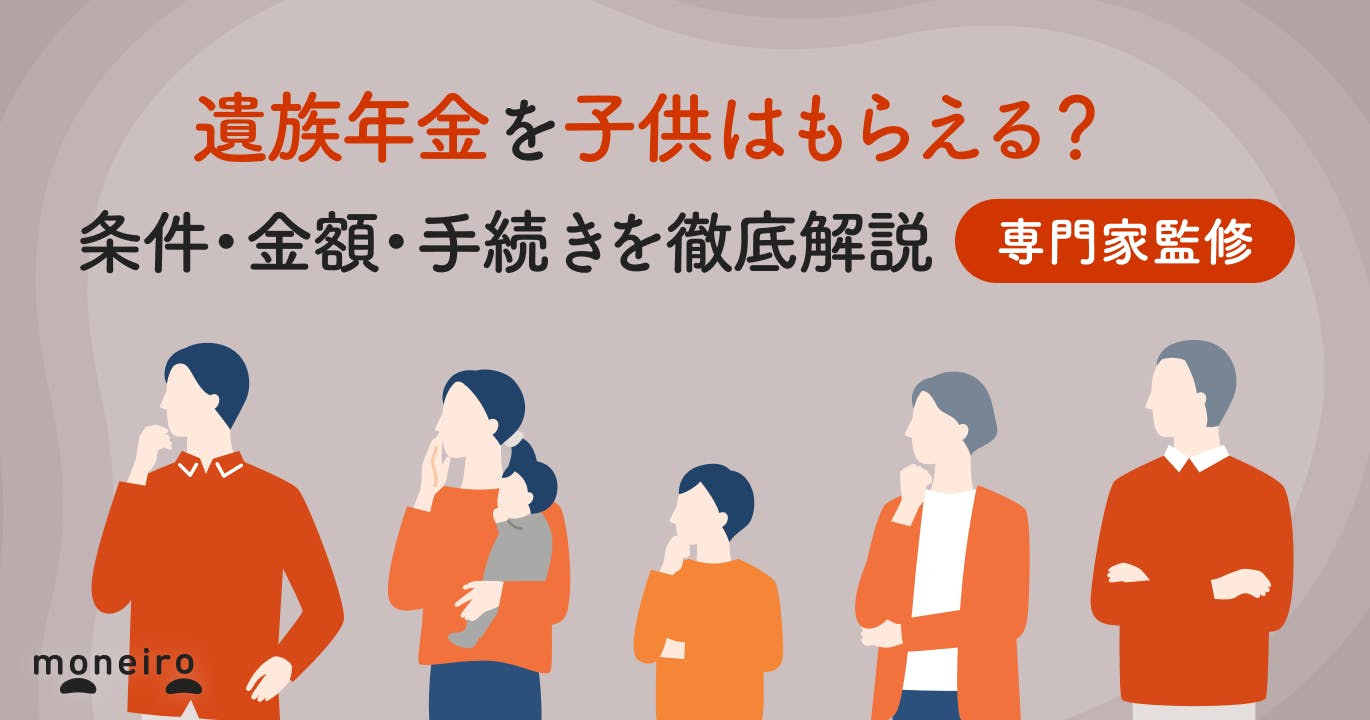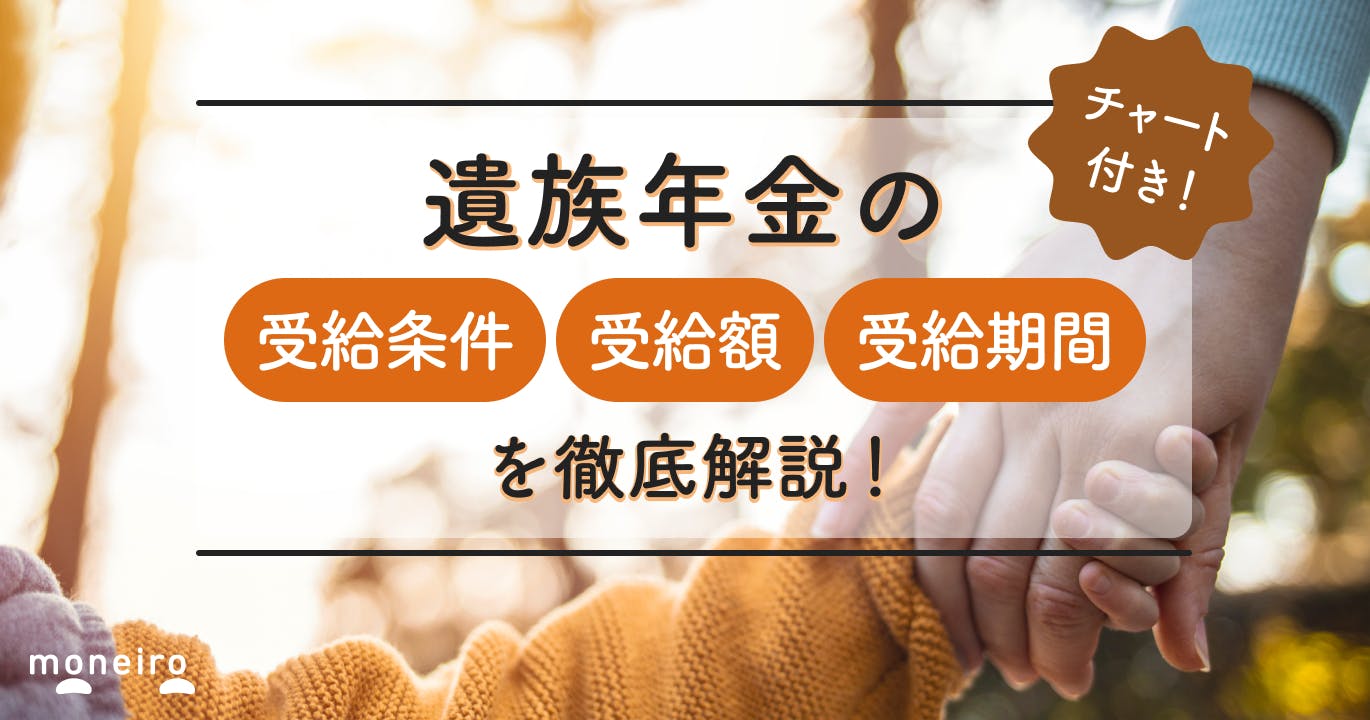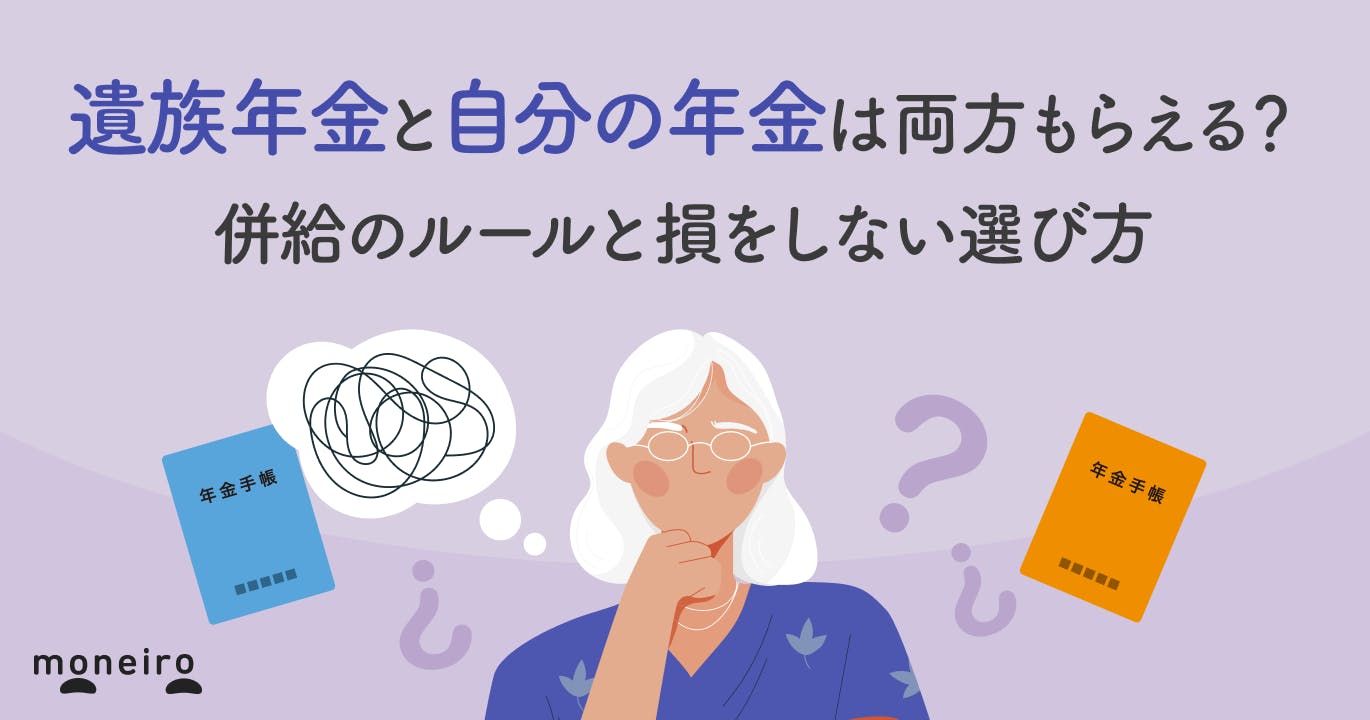
遺族年金を子供はもらえる?専門家が条件・金額・手続きをわかりやすく解説
≫「もしも」の備えは大丈夫?将来の必要額を診断
遺族年金は、親を亡くした子供やその家族の生活を支える大切な制度です。
しかし、「子供はいつまで受け取れるの?」「金額はいくら?」「手続きはどうする?」といった疑問や不安を抱く人は少なくありません。
本記事では、子供が遺族年金を受け取れる条件や対象範囲、もらえる金額の目安、申請手続き、支給が止まるタイミングまでをわかりやすく解説します。父子家庭・母子家庭・再婚などのケース別対応や他の手当との併用可否もご紹介していきます。
- 遺族年金について、親がいる場合は配偶者が受給者となり、子供分は加算額として上乗せされる
- 親がいない場合は子供自身が直接遺族年金を受給する
- 親がいる場合は「子供の加算額」「中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算」など、子供の人数に応じて受け取れる金額が変わる
将来の備えについて知りたいあなたへ
お金の疑問を解決する無料サービスをご利用いただけます
▶老後資金の無料診断:将来の必要額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶老後資金の無料相談会:老後への備えを専門家がアドバイス
子供は遺族年金をもらえる?基本の仕組み
遺族年金は、亡くなった人に生計を維持されていた家族を支える制度です。特に子供のいる家庭では重要な役割を果たします。
ただし、子供自身が直接受け取る場合と、親が受け取って子供の加算額が含まれる場合に分かれるため、仕組みを正しく理解することが大切です。
遺族年金は2種類
- 遺族基礎年金:国民年金加入者が亡くなった場合に支給
- 遺族厚生年金:厚生年金加入者が亡くなった場合に支給
※厚生年金加入者が亡くなった場合、要件を満たす子供がいれば遺族基礎年金も同時に受給できます
対象となる子供は、どちらも18歳到達年度の末日まで(高校3年生の3月末まで)です。障害等級1級または2級に該当する場合は、20歳まで対象となります。
親が受給するケースと子供が直接受給するケースの違い
- 親がいる場合:配偶者が受給者となり、子供分は加算額として上乗せされる
- 親がいない場合:子供自身が直接遺族年金を受給する
遺族年金の受給資格がある親がいる場合、子供の分の加算額を含めて親が遺族年金を受給することになります。この場合、子供が直接遺族年金を受け取ることはできません。
一方、子供が直接遺族年金を受け取れるのは、亡くなった人の配偶者に受給資格がない場合に限られます。
具体的には、両親が2人とも亡くなった場合や、親が離婚している場合などがこれに該当します。
遺族年金を受け取るための条件|親がいる場合
親がいる場合は親が遺族年金を受け取ります。この場合、子供の人数に応じた加算がつきます。
遺族基礎年金:子供の加算額
遺族基礎年金は、受給者(親)の基本額に子供の加算額が加わった金額が支給されます。2025年時点での基本額は、受給者の生年月日に応じて83万1700円(昭和31年4月2日以後生まれ)または82万9300円(昭和31年4月1日以前生まれ)です。
子供の加算額は、1人目と2人目がそれぞれ23万9300円、3人目以降が7万9800円となります。
例えば、配偶者と子供2人の場合は 83.1万円+23.9万円×2=約131万円/年 となります。
加算が停止するケース
親が遺族年金を受給している場合でも、子供と生計同一の関係がなくなると、遺族基礎年金はなくなります。
また、子供が結婚や養子縁組をした場合も、支給が停止されます。
遺族厚生年金:中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算
遺族厚生年金は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額が基準です。
また、遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算といった特別な制度があり、一定の条件を満たす配偶者(夫または妻)が遺族年金を受給する場合に加算されます。
- 中高齢寡婦加算:夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満の妻などが対象
- 経過的寡婦加算:旧制度と比較して不利になる人への経過措置
将来の備えについて知りたいあなたへ
お金の疑問を解決する無料サービスをご利用いただけます
▶老後資金の無料診断:将来の必要額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶老後資金の無料相談会:老後への備えを専門家がアドバイス
遺族年金を受け取るための条件|親がいない場合
両親ともに亡くなっている、あるいは配偶者として遺族年金を受け取れる人がいない場合、子供が直接「遺族基礎年金」(受給要件を満たせば「遺族厚生年金」と併せて)を受給することができます。
どちらを受け取れるかは、亡くなった人が国民年金加入者か、厚生年金加入者かなどによって異なります。
遺族基礎年金:子供が受け取れる条件
遺族基礎年金は、亡くなった人の配偶者に受給権がない場合、生計を維持されていた子供が直接受け取ることができます。
対象となる「子供」は、18歳に到達した年度末(高校3年生の3月末)までです。
ただし、障害等級が1級または2級に該当する場合は、20歳まで受給できます。実子だけでなく、法律上の養子や、亡くなった人と生計を同一にしていた連れ子も対象に含まれます。
支給が開始されるのは、親に受給資格がない場合、つまり親が既に亡くなっていたり離婚している場合などです。
遺族厚生年金:子供が受け取れる条件
子供が直接、遺族厚生年金を受け取る場合も、遺族基礎年金と同様に18歳到達年度末まで、または障害がある場合は20歳までが対象となります。
遺族基礎年金との大きな違いは、亡くなった人の要件です。遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金の被保険者または受給資格者であった場合などに支給されます。
支給される金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額となります。
≫「もしも」の備えは大丈夫?将来の必要額を診断
遺族年金の申請方法と必要書類
亡くなった人が国民年金のみの加入者だった場合は、市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所等に申請します。
厚生年金に加入していた場合は、年金事務所または年金相談センターに申請します。
【必要書類の例】
- 年金請求書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー
- 請求者の収入を証明する書類
- 子供の在学証明書(高等学校等在学中の場合)
- 預金通帳など振込先がわかる書類
必要書類を揃えて申請先へ提出します。不備があると支給が遅れるため、記載漏れや証明書類の有効期限に注意が必要です。
なお、マイナンバーカードを持参すれば省略できる書類もあるため、年金事務所等で確認しましょう。
年金の受給権は、年金支払日の翌日から5年を過ぎると時効となり、受給できなくなります。しかし、5年前までの分は遡って請求することが可能です。
遺族年金の支給が止まるタイミング
遺族基礎年金は、受給資格者が一定の条件を満たさなくなった場合に支給が停止されます。ただし、死亡者の配偶者が受給している場合、遺族厚生年金は継続して支給されるケースもあります。
- 子供が18歳到達年度末(障害がある場合は20歳)になった時
- 子供が結婚した時
- 子供が養子縁組により、遺族年金の受給資格を喪失した時
- 年金受給者である配偶者が再婚した時 など
他の手当との併用可否
他の手当と遺族年金の併用可否について、詳しく見ていきましょう。
児童扶養手当との関係
遺族年金と児童扶養手当は、併用が可能です。ただし、遺族年金を受給すると、児童扶養手当の支給額は調整されます。
生活保護や医療費助成との関係
遺族年金は、生活保護の受給額を計算する際の収入とみなされます。そのため、遺族年金を受け取ることで、生活保護の受給額が減額されます。
医療費助成に関しても、遺族年金が収入とみなされ、助成の対象外となるケースがあります。
まとめ
遺族年金は、生計の主体者などが死亡した場合、残された子供たちの生活を守るために欠かせない制度です。特に、遺族基礎年金は子供の人数によって金額が変動するため、しっかりと把握しておくことが大切です。
制度の改正も予定されており、特に若い世代は今後の制度変更にも注意しましょう。
≫「もしも」の備えは大丈夫?あなたの将来の必要額を診断
将来の備えについて知りたいあなたへ
お金の疑問を解決する無料サービスをご利用いただけます
▶老後資金の無料診断:将来の必要額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:30分の無料オンラインセミナー
▶老後資金の無料相談会:老後への備えを専門家がアドバイス
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
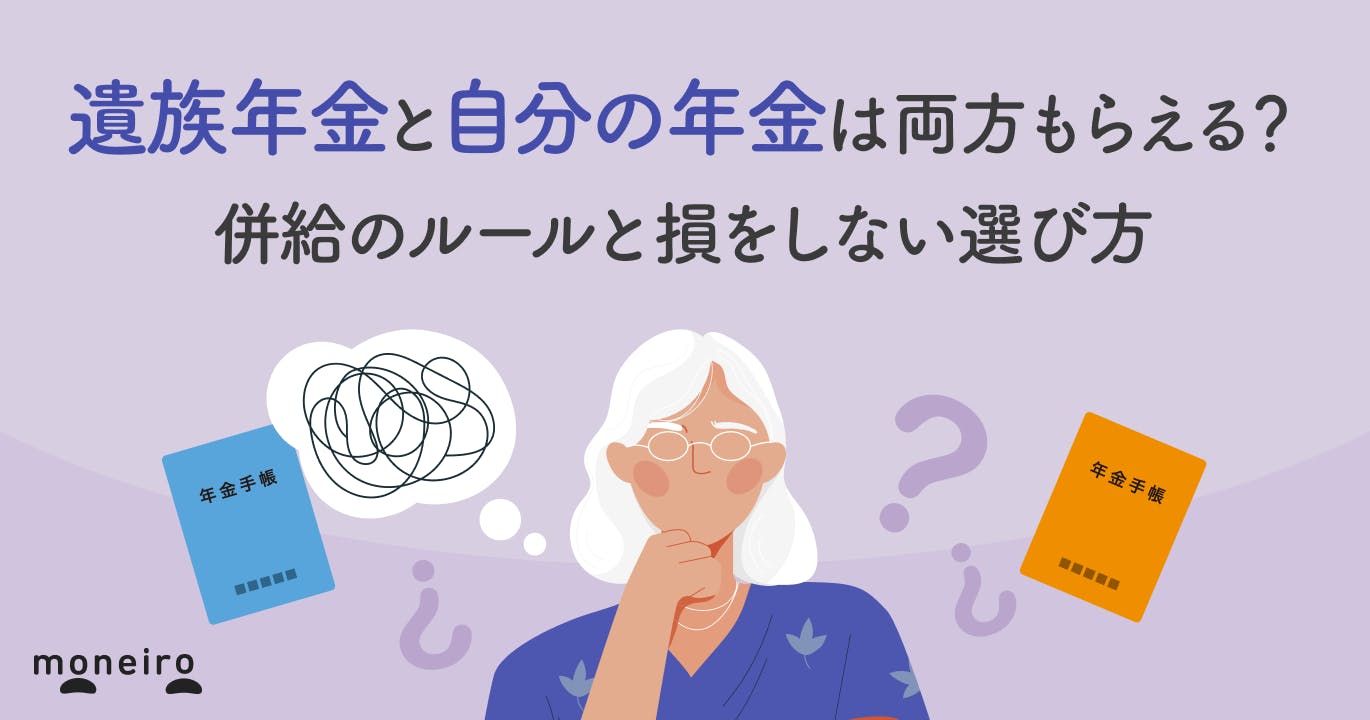
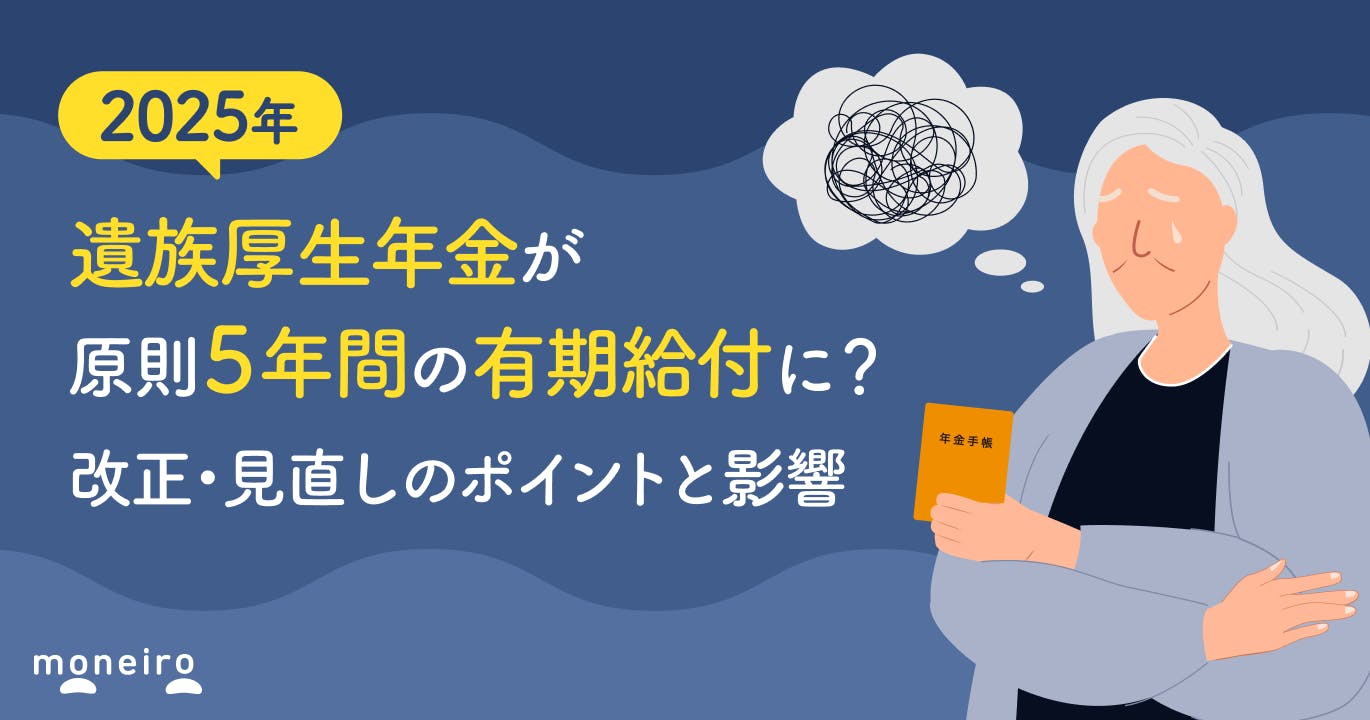
遺族厚生年金が改正で原則5年間の有期給付に?2025年制度見直しのポイントと影響

老後に必要なお金はいくら?単身・夫婦の世帯タイプ別必要額を解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。