
超富裕層とは?日本・海外の定義の違い、増え続ける背景まで徹底解説
>>あなたに最適な資産運用は?年収・資産から3分で診断
「超富裕層ってどんな人?」「定義は?」と気になっている人もいるかもしれません。実はあります。
この記事では、日本でも増加傾向にある超富裕層について解説します。野村総合研究所のデータに基づいた超富裕層の定義から、富裕層との違い、さらに日本や世界の超富裕層の現状と、彼らが増え続けている背景までを詳しく解説していきます。
- 野村総合研究所による日本の超富裕層の定義&富裕層との違い
- 日本や海外における超富裕層の世帯数や割合&
- 富裕層が増え続けている背景や「純金融資産」について
お金のことが気になるあなたへ
将来を豊かに暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶資産500万円からの債券投資の基本:まとまった資金の最適な運用法は?
▶“世界株”だけに頼らないリスク分散の投資術:適切な分散を実現する「オルカン」以外の選択肢とは?

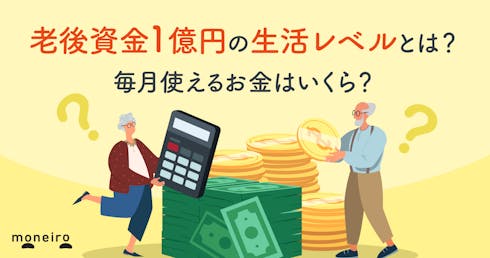
超富裕層とは?富裕層との違い
まずは超富裕層・富裕層についての基本知識を押さえておきましょう。
純金融資産で分類される「5つの資産階級」
日本において「超富裕層」や「富裕層」といった資産階級を定義する際、広く用いられているのが野村総合研究所(NRI)の調査データです。NRIは、個人が保有する純金融資産の額に基づいて、世帯を以下の「5つの資産階級」に分類しています。
- 超富裕層:純金融資産5億円以上
- 富裕層:純金融資産1億円以上5億円未満
- 準富裕層:純金融資産5000万円以上1億円未満
- アッパーマス層:純金融資産3000万円以上5000万円未満
- マス層:純金融資産3000万円未満
この定義によると、超富裕層は純金融資産が5億円を超える世帯を指し、富裕層は純金融資産が1億円以上5億円未満の世帯とされています。この両者の区分けが、日本の富裕層ビジネスや経済分析において重要な指標となっています。
【重要】定義の基準「純金融資産」とは?
超富裕層や富裕層を分類する上では、基準となる「純金融資産」とは、具体的にどのようなものを指すのかを理解しておく必要があります。
純金融資産とは、預貯金、株式、債券、投資信託、生命保険、個人年金などの「金融資産の合計額」から、住宅ローンや不動産購入目的以外の借入金などの「負債の合計額」を差し引いた金額を指します。
重要なのは、不動産などの実物資産は含まれない点です。
これは、不動産は流動性が低く、すぐに現金化して投資や消費に回すことが難しいため、実際の経済活動に影響を与える「自由に使える資産」の指標として、純金融資産が用いられることが多いためです。
例えば、金融資産の合計額が5500万円ある一方で、住宅ローンの残債が3000万円ある場合は、純金融資産は「5500万円 - 3000万円 = 2500万円」となり、分類上では「マス層」となります。
日本の超富裕層の世帯数・割合
次に、日本において超富裕層がどれくらいいるのか、その世帯数や割合について見ていきましょう。
各資産階級の世帯数と割合
野村総合研究所の調査(2025年2月発表)によると、2021年における日本の各資産階級の世帯数と割合は以下の通りです。このデータは、日本の富裕層や超富裕層の現状を理解する上で非常に重要です。
画像参照:純金融資産保有額の階層別にみた保有資産規模と世帯数
日本における超富裕層の世帯数は11.8万世帯であり、全世帯のわずか0.21%で、およそ500世帯に1世帯と非常に少ないことが分かります。また、富裕層と合わせても、日本の全世帯の約2.97%に過ぎません。
超富裕層と富裕層の資産総額
超富裕層と富裕層の世帯数は全体の2.97%に過ぎませんが、彼らが保有する純金融資産総額は非常に大きいという実態があります。
野村総合研究所の同調査によると、超富裕層が保有する純金融資産総額は135兆円、富裕層が保有する純金融資産総額は334兆円に達しています。これらを合わせると469兆円という莫大な金額となり、これは日本の個人金融資産総額約1795兆円の約26%を占める計算になります。
この数字は、一部の超富裕層と富裕層に富が集中している現状を示しています。
少数の世帯が日本の個人金融資産の大きな部分を占めていることは、経済格差の拡大や社会全体への影響を考える上で重要な視点となります。
お金のことが気になるあなたへ
将来を豊かに暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶資産500万円からの債券投資の基本:まとまった資金の最適な運用法は?
▶“世界株”だけに頼らないリスク分散の投資術:適切な分散を実現する「オルカン」以外の選択肢とは?
海外での富裕層・超富裕層の定義と実態
ここまで、日本における富裕層・超富裕層の実態について見てきましたが、海外ではまた違った定義や実態があります。以下で詳しく解説します。
海外での定義
海外において富裕層や超富裕層を定義する際も、純金融資産(または投資可能資産)が基準となりますが、多くの場合、米ドル建てで定義されます。「キャップジェミニ(Capgemini)」「ナイトフランク(Knight Frank)」といった主要なコンサルティングファームでは以下のように定義されています。
- 富裕層(High Net Worth Individuals: HNWIs):100万米ドル以上の投資可能資産または純資産を保有する個人
- 超富裕層(Ultra High Net Worth Individuals: UHNWIs):3000万米ドル以上の投資可能資産または純資産を保有する個人
これらの定義は、世界的な富の状況を把握するために広く利用されています。特に超富裕層は、日本の定義が純金融資産5億円以上であるのに対し、海外の超富裕層の定義は3000万米ドル(1ドル=150円換算で45億円)以上と、より高額な基準が設定されている点に大きな違いがあります。
主要国の富裕層・超富裕層の実態
世界の富裕層・超富裕層の動向は、国際的な経済状況や地域ごとの経済成長を反映しています。
世界における富裕層(HNWIs)の動向
Capgeminiの「World Wealth Report 2025」によると、2024年の世界のHNWIs(富裕層)人口は2023年から2.6%増加し、資産額も4.2%増加しました。これは、堅調な株式市場の成長が経済の変動を支えた影響によるもので、多様な地域トレンドが人口成長をやや鈍化させたものの、全体として持続的な拡大を示しています。
世界における超富裕層(UHNWIs)の動向
Knight Frankの「The Wealth Report 2025」によると、2024年には世界の1000万米ドル以上の資産を持つ個人の人口は4.4%増加しています。
また、UBSの「Global Wealth Report 2025」では、2024年には世界の総個人資産が4.6%増加したことが報告されています。特に米国は世界の富裕層の約40%を占めるなど、グローバルな富の蓄積を主導していることが示されています。
日本で富裕層・超富裕層が増加している背景
日本で富裕層や超富裕層が増加している背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。これらは、経済状況の変化、資産市場の動向、そして社会構造の変化に起因しています。
株価上昇による資産価値の増加
近年の日本における株価の上昇は、富裕層・超富裕層の資産増加に大きく貢献しています。アベノミクス以降の金融緩和政策や、企業業績の改善、円安などが複合的に作用し、日経平均株価やTOPIXは高水準で推移しました。
特に、以前から株式や投資信託などの金融資産を多く保有していた層は、株価の上昇によってその資産価値が大幅に増加しました。これは、資産が資産を生むという「富める者がさらに富む」メカニズムを加速させる要因となっています。
円安による資産価値の増加
円安もまた、富裕層の資産増加に大きな影響を与えています。特に、ドル建て資産やその他の外貨建て資産を保有している富裕層にとって、円安は保有資産の円換算価値を大きく押し上げる要因となります。
例えば、米ドル建ての株式や債券、海外不動産などを保有していた場合、為替レートが円安に振れることで、それらの資産を円に換算した際の価値が自動的に増加します。
グローバルな投資を行っている富裕層ほど、この円安の恩恵を享受しやすいため、資産拡大の背景として非常に重要です。
事業承継や相続による資産の世代間移転
事業承継や相続を通じた資産の世代間移転も、日本の富裕層・超富裕層の増加に寄与しています。特に、中小企業の経営者が高齢化する中で、M&Aによる事業売却や、子息への事業承継によって、巨額の資産が動くケースが増えています。
また、親世代から子世代への相続においても、不動産や金融資産が受け継がれることで、新たな富裕層が誕生したり、既存の富裕層がさらに資産を拡大したりする現象が見られます。
相続税対策の一環として生前贈与が行われることもあり、計画的な資産移転が富裕層形成の一因となっています。
新興テクノロジーやビジネスの成功者(ニューリッチ)の台頭
近年、IT、Web3.0、AIなどの新興テクノロジー分野や、新しいビジネスモデルを確立したスタートアップの成功者たちが、「ニューリッチ」として台頭しています。彼らは従来の資産家とは異なり、短期間で巨額の富を築くケースが多く、若い世代にも富裕層が拡大する要因となっています。
株式公開(IPO)やM&Aによる企業売却で短期間に大きなリターンを得た人々や、暗号資産をはじめとするデジタル資産への早期投資で大きな利益を上げた「クリプト富裕層」などが、日本の超富裕層・富裕層層を厚くしています。これは、経済の構造変化が富の再分配に影響を与えている一例といえるでしょう。
まとめ
この記事では、超富裕層の定義から、日本および世界の現状、そしてその増加の背景までを詳細に解説しました。
野村総合研究所の定義によると、日本では純金融資産5億円以上が「超富裕層」とされ、純金融資産1億円以上5億円未満が「富裕層」と分類されます。2023年時点の日本の超富裕層は11.8万世帯、富裕層は153.5万世帯であり、これらの層が日本の個人金融資産の約26%を保有しているという富の集中が起きていることが明らかになっています。
一方の海外では、富裕層(HNWIs)が100万米ドル以上、超富裕層(UHNWIs)が3000万米ドル以上の純資産を持つ個人と定義されており、日本と比較してより高額な基準が設けられています。
日本をはじめとした世界各国で富裕層は増加傾向にありますが、特に日本の富裕層・超富裕層が増加している背景としては、株価上昇と円安による資産価値の増加、事業承継や相続を通じた資産の世代間移転、そして新興テクノロジーやビジネスの成功者である「ニューリッチ」の台頭といった複数の要因が挙げられます。
これらの要素が、日本の経済構造と富の状況を形作っているといえるでしょう。今回紹介したような超富裕層の実態を理解することは、現代社会の経済動向を把握する上でも非常に重要です。ぜひ、自身の資産形成戦略を立てる上でも参考にしてみてください。
>>あなたに最適な資産運用は?年収・資産から3分で診断
お金のことが気になるあなたへ
将来を豊かに暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をスムーズに進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶資産500万円からの債券投資の基本:まとまった資金の最適な運用法は?
▶“世界株”だけに頼らないリスク分散の投資術:適切な分散を実現する「オルカン」以外の選択肢とは?
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
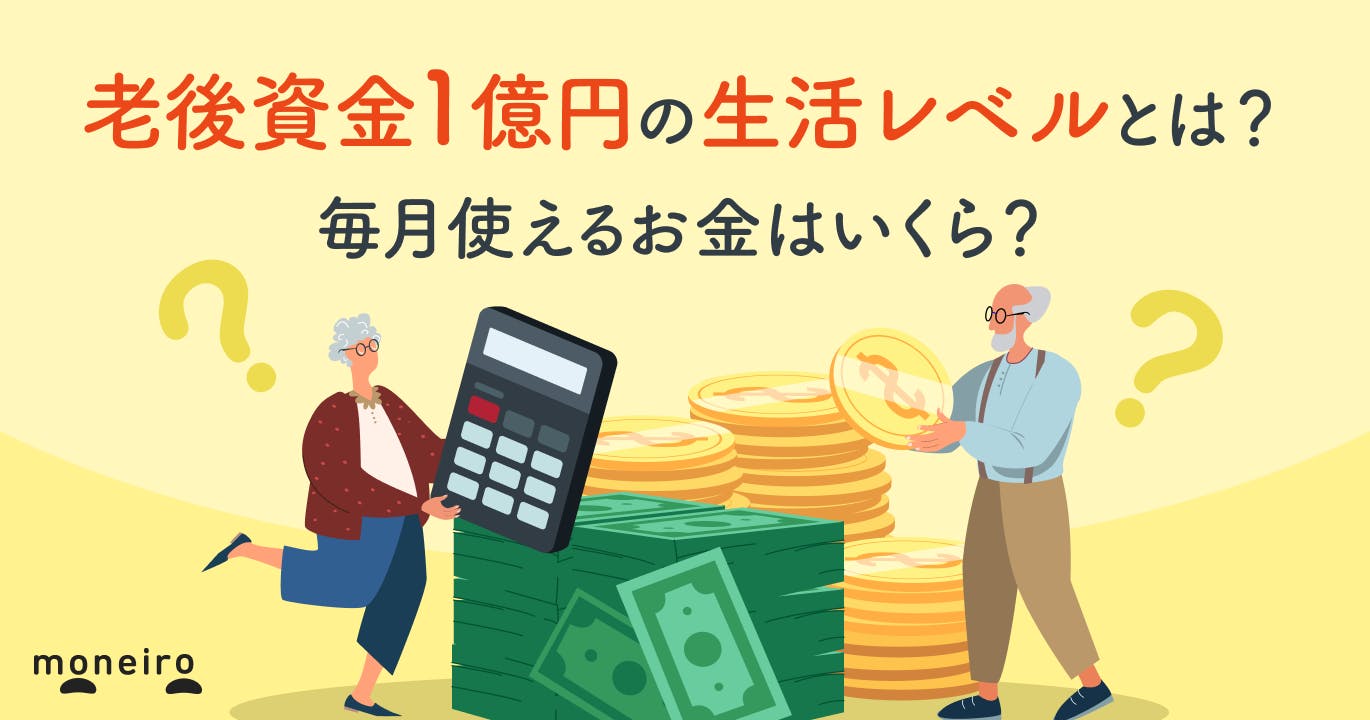
老後資金1億円の生活レベルとは?毎月使えるお金はいくら?

正直みんな貯金はどのくらいある?年代別・年収別に平均額・中央値を解説

世帯年収の平均・中央値は?年代別・世帯の種類別のリアルな年収データを解説
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。

