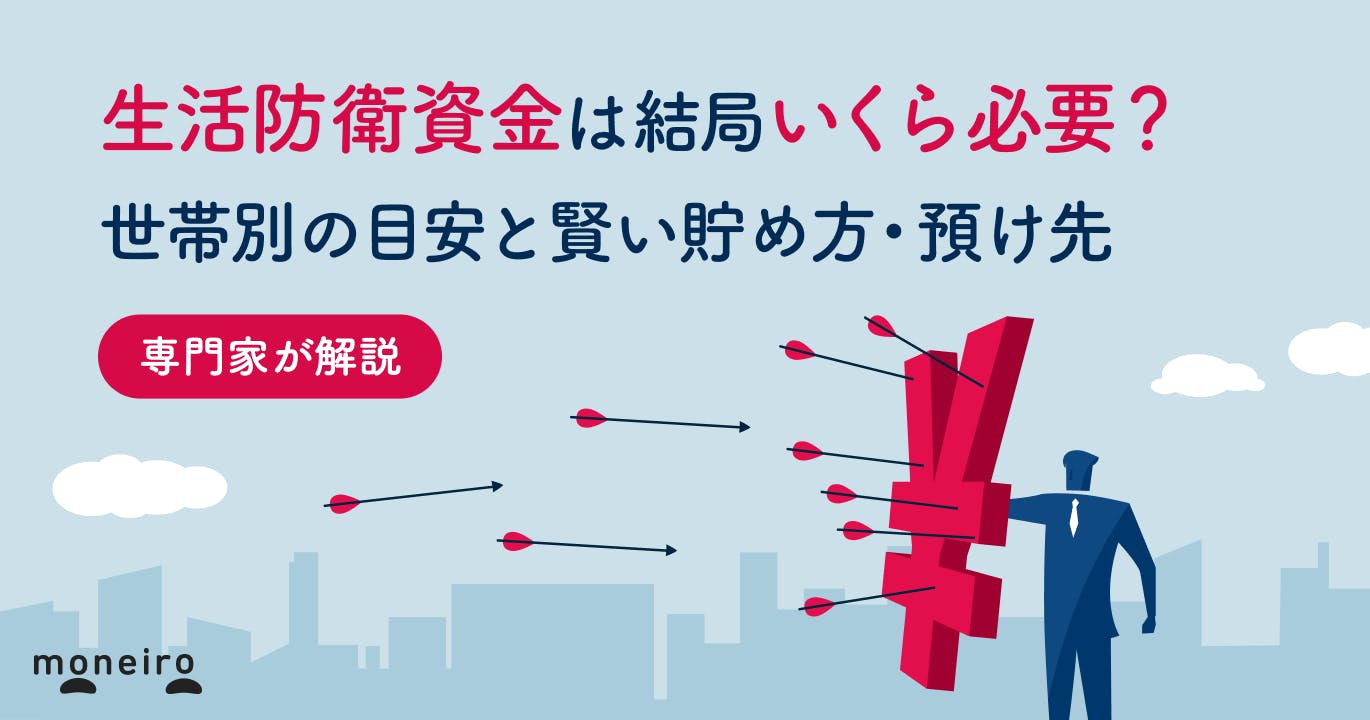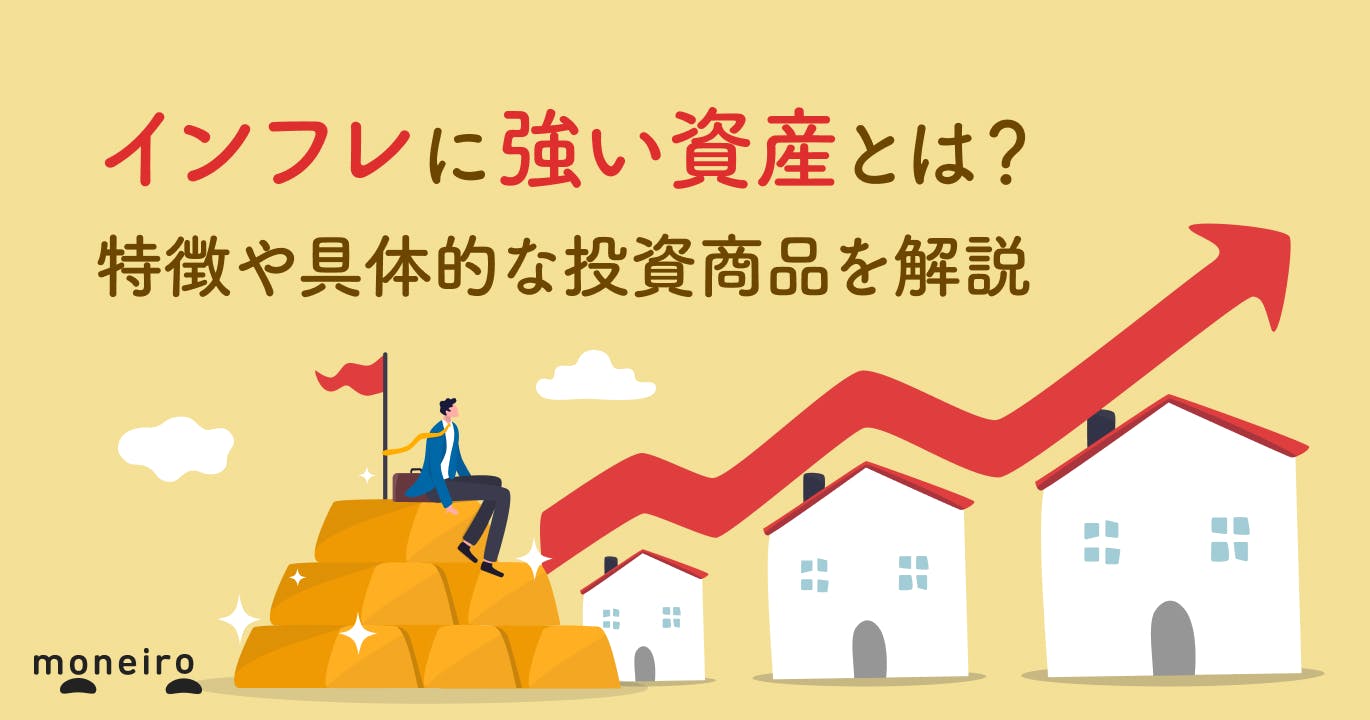日本で物価高が進むのはなぜ?主な原因やトランプ関税の影響について解説
【無料】あなたのお金は足りる?収入・資産から将来に必要な金額を診断
近年、日本では急速に物価高が進行しています。スーパーでの買い物や光熱費の請求書を見ると、以前より出費が増えたと感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、なぜ日本で物価高が進んでいるのか、その主な原因・背景について詳しく解説します。さらに、いわゆる「トランプ関税」が日本の物価に与える影響や、政府が検討している物価高対策についても紹介します。
- 近年の日本における物価高の現状
- 日本で物価高が進行している主な理由・背景
- 「トランプ関税」によって懸念される日本の物価への影響
物価高と将来の生活が気になるあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、将来の生活に必要な金額を把握して早めに準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
【データ】近年、日本は急激な物価高に
総務省統計局が公表する消費者物価指数(CPI)を見ると、日本の物価は近年、顕著に上昇しています。2020年を基準(100)とした総合指数は、2024年平均で108.5(前年比2.7%上昇)、2025年5月には111.8(前年同月比3.5%上昇)と、着実に上昇傾向にあります。
また、生鮮食品を除く総合指数は2025年5月に111.4(前年同月比3.7%上昇)、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は110.0(前年同月比3.3%上昇)と、幅広い品目で物価高が進んでいることが分かります。
2022年以降で物価上昇が顕著に
参照:総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)5月分」
上記は、2022年以降の消費者物価指数を示した図です。2022年以降では物価上昇率が大きく、消費者にとって生活費の負担が増していることがわかります。
特に物価上昇が著しい品目は?
データによると、物価上昇が特に顕著な品目は以下です。
食料品
エネルギー価格の高騰や円安により、輸入小麦や食用油、肉類などの価格が上昇。また、国内で大きな騒動となった米の価格上昇もあり、2020年を100としたときの2025年5月の消費者物価指数は124.4となっています。
水道・光熱費
水道・電気・ガス料金は、国際的な原油価格や天然ガスの高騰により、2020年比の消費者物価指数で121.2と、こちらも大幅な上昇となっています。
輸入品
衣料品や家電製品など、輸入依存度の高い品目は円安の影響を強く受け、価格が上昇傾向にあります。
【参考】物価高とインフレの違い
物価高とインフレは混同されがちですが、厳密には異なります。物価高は、特定の品目やサービス価格が上昇し、生活費の負担が増える現象を指します。一方のインフレは、経済全体の物価水準が継続的に上昇する状態を指し、貨幣価値の低下を伴います。
現在の日本は、特定の要因(円安や原材料高)による物価高が主で、持続的なインフレには至っていないとされています。ただし、この物価高が長期化すれば、インフレへの移行も懸念されます。
なぜ日本で物価高が進む?3つの主な原因
日本の物価高の背景には、複数の要因が絡み合っています。以下に3つの主要な原因を解説します。
1.円安による輸入コストの上昇
2022年以降、円安が急速に進行しました。2022年の年初は1ドル=115円程度でしたが、2024年6月には1986年12月以来37年半ぶりとなる160円台まで下落。2025年7月現在では140円台半ばを推移していますが、依然として円安水準が続いています。
円安は、輸入品の価格を押し上げ、食料品やエネルギー、工業製品など幅広い品目のコスト上昇を招きます。さまざまな分野で輸入品への依存度が高い日本では、円安による物価への影響はかなり大きいといえます。
2.ロシアのウクライナ侵攻の影響
2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻は、グローバルなサプライチェーンに深刻な影響を与えました。ウクライナは小麦やトウモロコシの主要輸出国であり、侵攻による供給減少は世界的な食料価格の上昇を引き起こしました。
また、ロシアからのエネルギー供給の不安定化は、原油や天然ガスの価格高騰を招き、日本の電気・ガス料金やガソリン価格にも大きな影響を及ぼしています。さらに、鉄鋼や化学製品などの原材料価格も高騰し、製造業のコスト増につながっています。
原材料のコストは最終的に製品の価格に転嫁され、結果として消費者物価の押し上げにつながっていきます。
3.人件費の増大
人手不足による人件費の上昇も、物価高の一因といえます。少子高齢化や労働力人口の減少により、特にサービス業や物流業界で人手不足が深刻化しています。
また、2025年春闘の平均賃上げ率は5.25%で、33年ぶりの高水準を記録した2024年の5.10%をさらに上回っています。こうした賃上げに伴い、企業は人件費を価格に転嫁する動きを見せており、物価上昇の要因となっています。
【2025】「トランプ関税」による物価高への影響は?
2025年、ドナルド・トランプ米大統領は自国の「経済政策の柱」として、世界各国に対し大胆な関税引き上げを実施しています。これによる物価への影響について解説します。
「トランプ関税」とは?
「トランプ関税」とは、トランプ米大統領が推進する高関税政策のことを指します。
トランプ氏はこの関税強化措置を活用することで米国が抱える巨額の貿易赤字の縮小を目指し、米国に有利な二国間貿易協定の締結を推進しようとしています。
そこで、2025年4月2日に「相互関税」を公表し、大半の国に一律10%の基本税率を課すほか、国や地域別にさらに税率を上乗せするとしました。
日本に対する関税はどうなる?
上記の「上乗せ分」については一旦、2025年7月9日まで一時停止となっていましたが、この期日を目前にした日本時間の2025年7月8日未明、トランプ氏は自身のSNSで、日本に対する新たな関税率を通知する書簡を公開しました。
書簡では、「8月1日から、日本からの輸入品に25%の関税を課す」としており、さらに、日本が関税を引き上げる場合は関税を上乗せする可能性も示唆しています。
一方で、米国に対する関税や非関税障壁を撤廃する場合には、今回の関税について調整を検討する可能性があるとし、交渉次第では関税措置を見直す考えもあることを表明しています。
見方を変えれば、「8月1日まで交渉期間が伸びた」とも考えることができます。トランプ関税の行方については引き続き注視が必要です。
日本の物価への影響
もしこのままトランプ関税が導入された場合、日本の物価に以下のような影響が考えられます。
輸出企業の収益悪化
日本企業の対米輸出品(自動車や機械など)に高関税が課されると、収益が圧迫され、国内での価格転嫁が進む可能性があります。
また、収益悪化によって今後の賃上げ率が鈍化するリスクも指摘されています。そうなると、物価高が家計の購買力をさらに圧迫し、消費停滞を招く可能性があります。
輸入品の価格上昇
米国からの輸入品(食料品やエネルギー関連)も関税の影響を受け、価格が上昇する可能性があります。特に、米国産の牛肉や穀物は日本市場で重要であり、価格上昇は食卓に直接影響します。
円安の加速
トランプ関税による貿易摩擦の激化は、日本の貿易赤字拡大や日米金利差の拡大によって円安を加速させるリスクがあります。円安が進めば、輸入品のさらなる価格上昇要因となります。
企業の対応は?
日本の各企業は、トランプ関税への対応として以下のような対応を迫られています。
- 生産拠点の移転:関税を回避するため、米国での現地生産を強化する動きが加速。自動車メーカーは米国工場の拡大を始めています。
- 価格転嫁:コスト増を吸収しきれず、国内での製品価格を引き上げる企業も増える可能性があります。
- 代替市場の開拓:米国以外の市場(東南アジアやEU)への輸出シフトを模索する企業も出てきています。
検討されている物価高対策
物価高への対応として、政府は以下のような対策を検討しています。
以下は、2025年参議院選挙・投開票前の情報です。詳細については最新の情報をご参照ください。
給付金の支給
物価高による家計負担の軽減策として、現政権(2025年7月時点)の自民党では給付金の支給が検討されています。ただし、財源などについては議論が続いているほか、野党からは効果の持続性に対する懐疑的な声も挙がっています。
消費税の減税
野党からは、物価高対策として食料品などの消費税減税の案が挙がっています。消費税減税のほうがより持続的で広範な効果が期待できるとしています。
所得を増やす政策
物価高騰を乗り越えるためには、持続的な賃上げが不可欠との認識は与野党で共通しており、その実現方法を巡って論戦が交わされています。
具体的には、最低賃金の引き上げや、税金・社会保険料の負担軽減による手取り増といった政策が挙げられます。
まとめ
日本の物価高は、円安やエネルギー・原材料の高騰、ロシアのウクライナ侵攻、人件費増大といった複数の要因が絡み合って進行しています。
また、日本のみならず世界各国で動向が注視されている「トランプ関税」は、輸出企業の収益悪化や輸入品の価格上昇を通じて、物価高を加速させるリスクがあります。
政府では物価高対策を検討していますが、効果の持続性や財源の確保といった課題は依然として残っている状況です。今後、物価高が家計や経済に与える影響を最小限に抑えるため、消費者としては節約や購買行動の最適化など、影響を軽減する工夫が一層重要となるでしょう。
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。