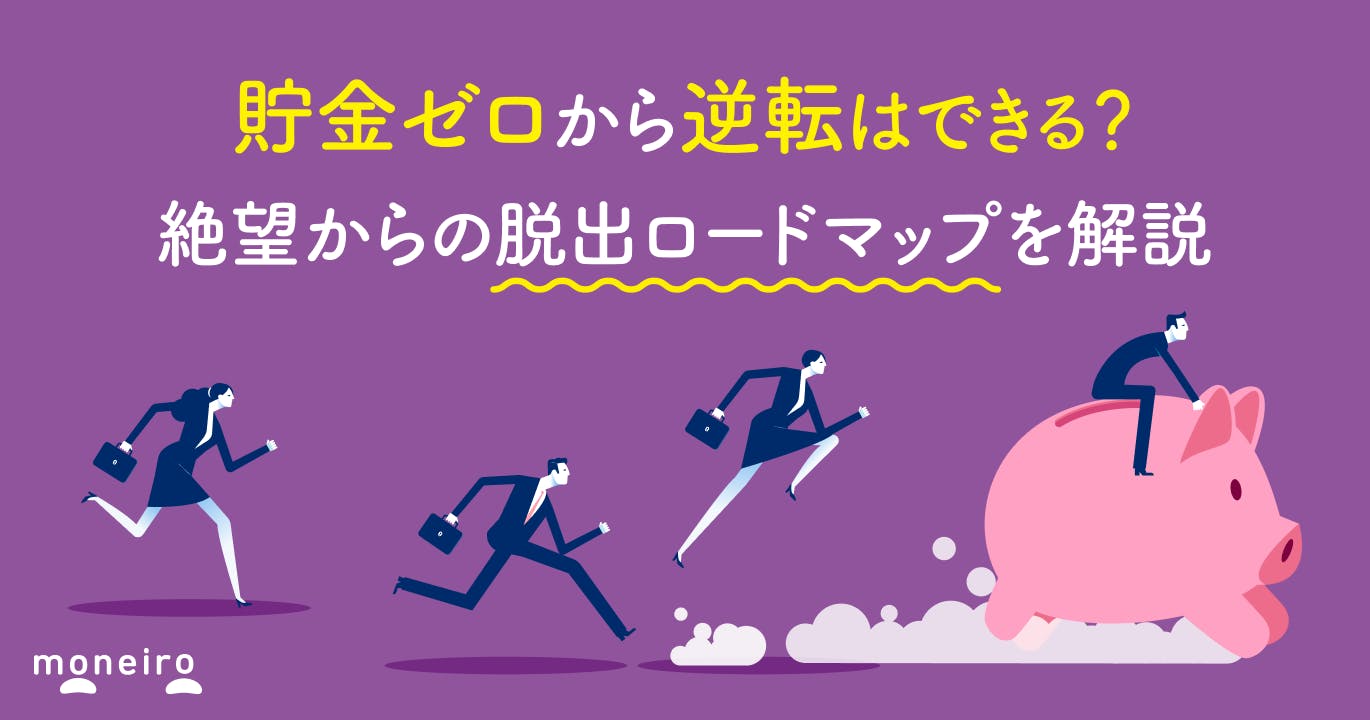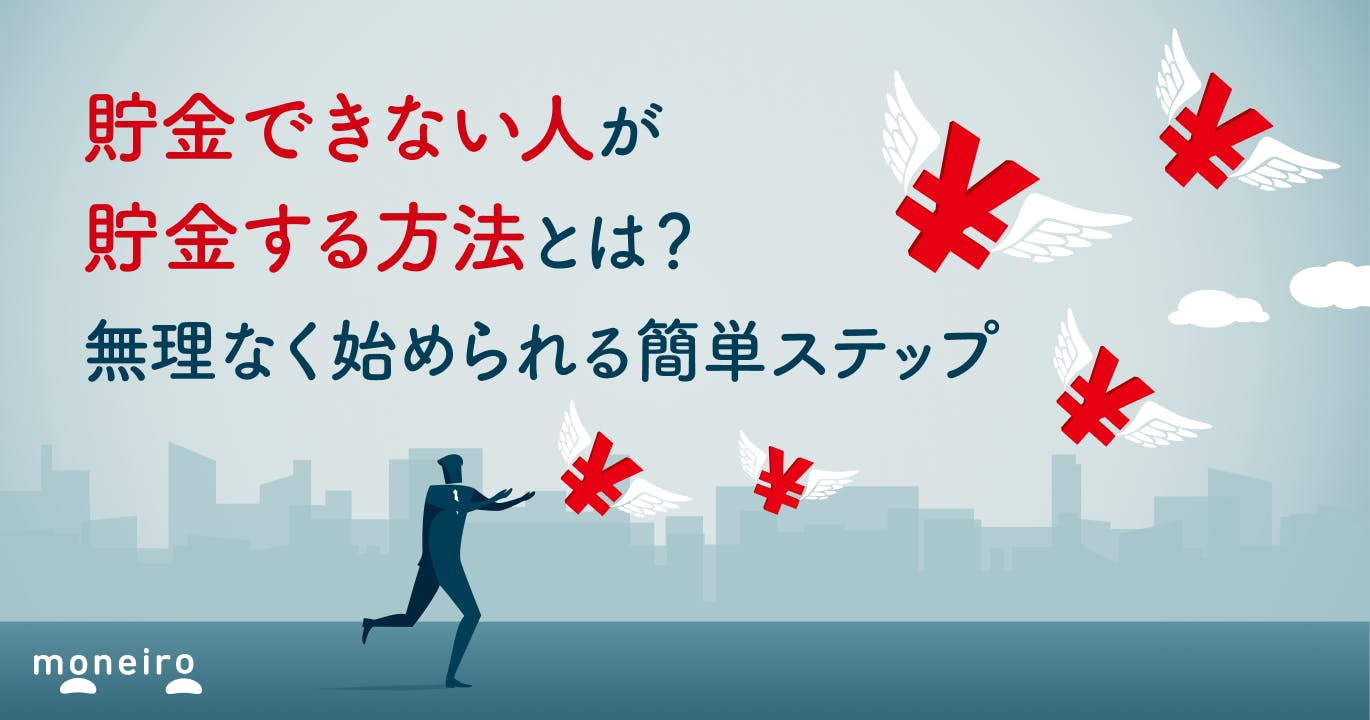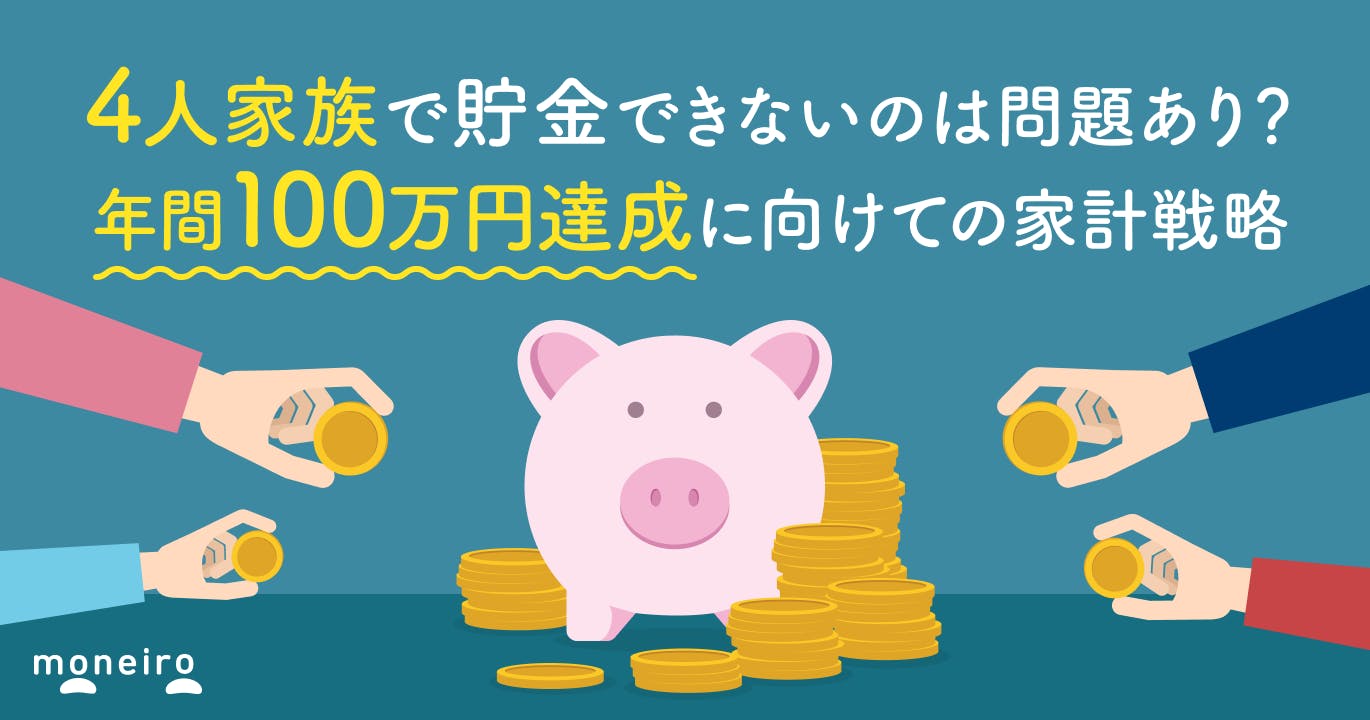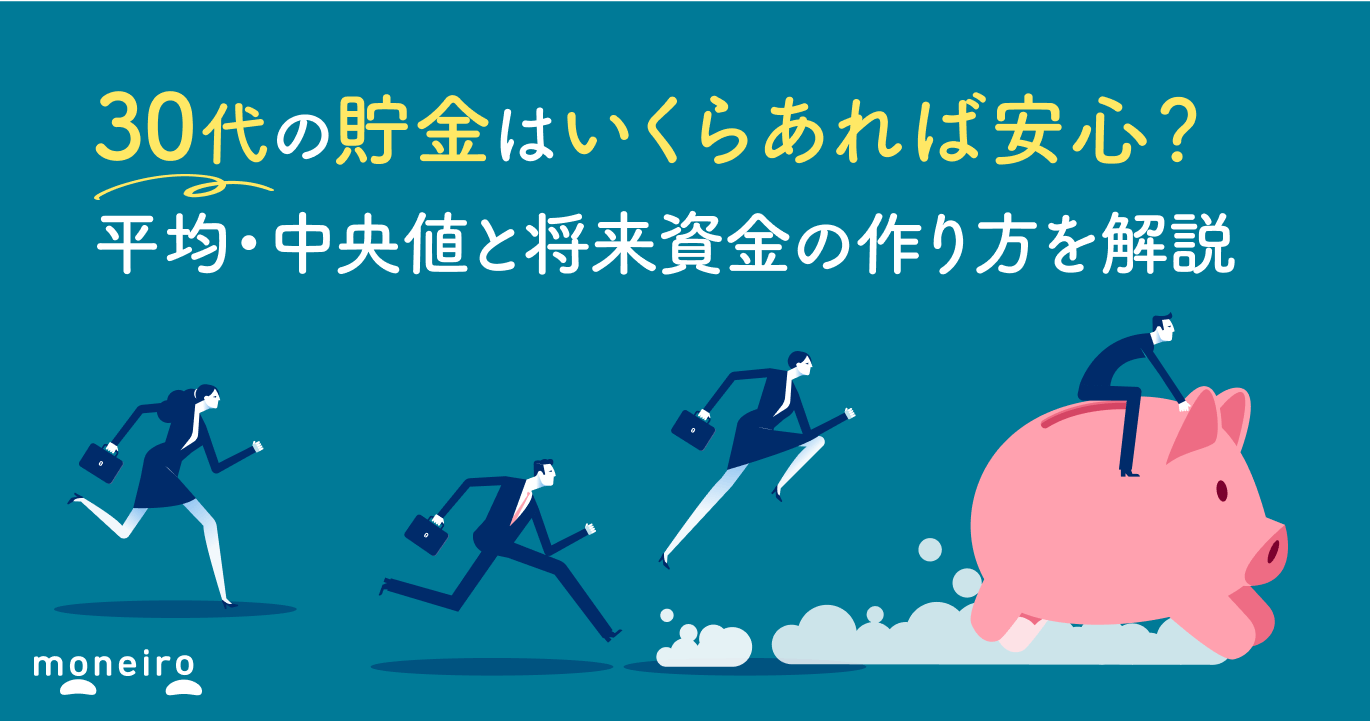貯金ゼロから逆転はできる?絶望からの脱出ロードマップを解説
≫将来に必要なお金はいくら?不足額を3分で診断
「貯金ゼロ」で将来に漠然とした不安を抱えている方は実は少なくありません。そこで本記事では、専門家の視点から、年代別の貯金ゼロ世帯のリアルな割合や、貯金できない人の根本的な原因を解説します。
さらに、今日から実践できる具体的な貯金術と家計改善のステップを紹介し、絶望的な状況から資産形成へと踏み出すためのサポートをいたします。
- 貯金ゼロ世帯の具体的な割合と、貯金ゼロを放置する深刻なリスク
- 貯金ができない3つのタイプ別原因と、負債がある場合の最優先事項
- 即効性のある家計改善の4ステップと具体的な貯蓄戦略
将来が不安なあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
貯金ゼロの人はどれくらいいる?
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、金融資産を保有していない(貯金ゼロ)世帯は決して少なくありません。
全国平均では、単身世帯の32.8%、2人以上世帯の24.0%が金融資産を保有していません(ここでの「金融資産」は、現金の他、株式や投資信託、債券といった有価証券も含みます)。
具体的に年代別の金融資産がない世帯の割合を見ていきましょう。
単身世帯の貯金ゼロの割合(年代別)
単身世帯でもっとも貯金ゼロの割合が高いのは50歳代で40.2%、次いで20歳代が36.6%となっています。50歳代では約4割が、老後資金の準備を急ぐべきタイミングで貯金がないという現実が見えてきます。
2人以上世帯の貯金ゼロの割合(年代別)
2人以上世帯でも、単身世帯と同様に50歳代が29.2%ともっとも高い割合を示しています。50歳代は子供の教育費や住宅ローンの支払いが重なるケースも少なくなく、この時期に貯金がない場合、生活に大きなプレッシャーがかかる可能性があります。
貯金ゼロを放置する「本当のリスク」とは?
貯金ゼロの状態を放置することは、短期的な不安だけでなく、生活基盤を揺るがす深刻なリスクを伴います。突然の事態に対応できなくなり、最悪の場合、負債の連鎖に陥る危険性があります。
リスク1:病気・ケガ|「傷病手当金」だけでは足りない理由
病気やケガで長期間働けなくなった場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。これは「給与(標準報酬月額)の約3分の2」が「最長で通算1年6ヶ月」支給される制度です。
しかし、手当金では給与の全額分を賄えないため、不足する生活費を補う貯金が必要です。さらに、手当金受給中であっても、社会保険料(健康保険料や年金保険料)や住民税の支払いは免除されません。結果として、手取りが大幅に減少し、生活費が足りなくなるリスクが高まります。
また、医療費については、自己負担額に上限がある高額療養費制度がありますが、それでも自己負担分の一時的な支払いが発生する可能性はあります。
≫あなたの将来に必要なお金はいくら?不足額を3分で診断
リスク2:失業|「失業手当」は満額ではない
失業時には雇用保険から基本手当(失業手当)が支給されますが、給付日数には90日〜といった上限があり、金額も離職前の賃金の約50〜80%に留まります。
もっとも注意すべき盲点は、自己都合退職の場合です。基本手当を受け取るまでに、まず待機期間(7日間)があり、その後さらに企業都合退職よりも長い給付制限(原則1ヶ月)が設けられます。この間は収入がゼロとなるため、生活を維持するため、貯金が非常に重要になります。
リスク3:突発的な高額支出(冠婚葬祭・家電故障など)
貯金ゼロの世帯にとって、大きなリスクになり得るのが突発的な高額支出です。
例えば、冷蔵庫や給湯器、エアコンといった生活必需品の故障(買い替え費用)、急な親族の冠婚葬祭(慶弔費)、子どもの進学準備費用など、10〜30万円単位の支出は日常的に発生し得ます。
これらに対応できる生活防衛資金がない場合、緊急性を要する支出に対して、手軽な反面、金利が高いカードローンやリボ払いに頼らざるを得なくなります。これが借金が借金を呼ぶ「負債の連鎖」の始まりとなり、家計を決定的に悪化させます。
リスク4:老後破綻|「年金だけ」では生活できない現実
公的年金は老後の生活を支える重要な資金源ですが、「年金だけ」でゆとりある生活を送るのは現実的ではありません。
経済的に不安なく老後生活を送るためには自助努力が求められており、一般に言われる「老後資金2000万円問題」の必要性を改めて認識する必要があります。
貯金ゼロの状態を放置し、現役世代のうちに資産形成の準備ができない場合、老後破綻のリスクは高いといえます。
なぜ貯金がゼロになる?3つのタイプ別「貯まらない」原因
貯金ができない原因は、個人の行動様式や収入構造によって異なります。自分がどのタイプに当てはまるかを知ることで、効果的な対策を講じるための足がかりとなります。金ゼロに陥る人は大きく3つのタイプに分類できます。
タイプ1:支出管理不能型(どんぶり勘定)
このタイプは、収入に対して極端に支出が多いわけではないのに、なぜか月末になると手元にお金が残らないという特徴を持ちます。
根本的な原因は、支出全体を正確に把握できていない「どんぶり勘定」にあります。特に、現金を使わないキャッシュレス決済が普及した現代では、決済のたびにお金が減っている感覚が希薄になり、「気づかないうちに使いすぎている」状況が発生しやすくなっています。家計簿をつけていない、あるいはつけていても管理が曖昧な場合に陥りやすいタイプです。
タイプ2:収入不足型(手取りが少ない)
節約意識はあるにもかかわらず、最低限の生活費を支払うだけで精一杯になってしまうのがこのタイプです。
主な原因は、基本給の低さや非正規雇用といった「収入構造の問題」にあります。また、額面(総支給額)から引かれる過度な社会保険料や税金の負担が手取りを圧迫しているケースも少なくありません。
まずは、給与明細を確認し、額面と手取り(差引支給額)の違い、そして控除(社会保険料、所得税、住民税)の内訳を正しく理解することが、家計改善の第一歩として重要です。
タイプ3:優先順位混乱型(見栄・ストレス消費)
貯金が将来的に必要であることは頭では理解しているものの、目の前の快楽や見栄、ストレス発散のための支出を優先してしまうタイプです。高価な趣味や頻繁な交際費、ブランド品の購入などが典型例です。
このタイプの根底には、「給料が余ったら貯金しよう」という「余ったら貯金」の思考があります。しかし、人間は基本的に際限なくお金を使ってしまうため、この思考方法では、お金は絶対に余らず、いつまで経っても貯金体質にはなれません。
【重要】借金(リボ・カードローン)がある場合の鉄則
貯金ゼロの状況にある方の中には、すでにリボ払いやカードローンといった負債を抱えているケースも少なくありません。この状況での最優先事項は、新たな貯蓄を始めることではなく、「高金利の借金返済」を最優先することです。
理由として、一般的な貯蓄の利息がほとんど0%に近いのに対し、リボ払いやカードローンの年利は15%といった高金利になるため、借金の利息(マイナス)が貯蓄の利益を遥かに上回ります。利息を払い続けている限り、資産は永久に増えません。
もし自力での返済が困難な場合は、債務整理(任意整理、個人再生など)も選択肢に入れ、早急に弁護士や司法書士といった専門家に相談することを強く推奨します。
将来が不安なあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
貯金ゼロ脱出ロードマップ|即効性のある4ステップ
貯金ゼロを脱出し、安定した貯蓄体質になるためには、意志の力ではなく、「仕組み化」が不可欠です。以下の即効性のある4ステップロードマップを実行することで、上記のタイプ別原因を克服し、確実に成果を出しましょう。
ステップ1:家計の「見える化」と「仕分け」
まず、支出管理不能型(タイプ1)の方は特に、現状把握が不可欠です。家計簿アプリなどを導入し、銀行口座やクレジットカード、電子マネーと連携させることで、最低1ヶ月間の支出をすべて自動で「見える化」しましょう。
次に、支出を「固定費」(家賃、保険料、通信費など)と「変動費」(食費、娯楽費など)に明確に仕分けます。この仕分けが、続く固定費の見直しにおいて、どこから手をつけるべきかを明確にする土台となります。
ステップ2:【最優先】固定費の見直し
家計改善においてもっとも効果が大きく永続するのが、毎月の固定費の見直しです。支出から聖域を設けず、徹底的に見直しましょう。
特に、以下の4項目は最優先で削減を検討しましょう。
- 通信費: 大手キャリアから格安SIMへ乗り換えるだけで、大幅な削減が可能です。
- 保険料: 不要な保障(特に高額な貯蓄型保険)がないかを確認し、見直しを行いましょう。
- 家賃: 収入に対する割合が高い場合は、引っ越しも視野に入れます。
- サブスクリプションサービス: 利用頻度の低い動画配信やアプリの定期購入は解約しましょう。
ステップ3:「先取り貯蓄」の仕組み化
優先順位混乱型(タイプ3)の原因であった「余ったら貯金」の思考を完全に捨てる必要があります。
給料が入ったらすぐに貯蓄分を移動させる「先取り貯蓄」を仕組み化しましょう。具体的な方法としては、勤務先に制度があれば、天引きで貯蓄できる財形貯蓄の利用がもっとも強力です。
もし制度がない場合でも、銀行の自動積立定期預金を設定したり、毎月決まった額を給与振込口座とは別の貯蓄専用口座へ自動で振り込む設定を行うなど、物理的にお金に手をつけられない環境を必ず作りましょう。
ステップ4:予算管理ルールの導入(50/30/20ルール)
貯蓄体質を維持するためには、シンプルで明確な予算ルールが必要です。
アメリカで考案された家計管理のフレームワークで、手取り収入を「生活必需費(50%)」、「娯楽費(30%)」、「貯蓄・投資(20%)」に自動的に振り分ける管理方法です。
このルールを導入することで、支出管理不能型や優先順位混乱型の消費を抑制できます。貯蓄・投資の20%は、まず緊急事態に備えるための「生活防衛資金」(少なくとも生活費の3ヶ月分、できれば6ヶ月分)を貯めることを最優先目標としましょう。
【年代別】貯金ゼロからの処方箋(20代・30代・40代・50代)
年齢が上がるにつれてライフイベントの重さや老後資金までの時間が変化するため、年代ごとに貯蓄の優先順位と戦略が変わってきます。
20代:少額でも「先取り貯蓄」の習慣化を
20代の単身世帯は36.6%が貯金ゼロであり、収入がまだ低い傾向にあります。しかし、この時期にもっとも重要なのは、金額の多寡にかかわらず「先取り貯蓄」を習慣化し、貯蓄体質を作り上げることです。
収入不足型(タイプ2)の根本解決のため、貯蓄と並行して、将来的な収入アップにつながる自己投資(勉強や資格取得)も積極的に行いましょう。
30代:ライフイベントと「つみたて投資」の開始
30代の貯金ゼロの割合は単身世帯で33.4%、2人以上世帯で24.5%です。この年代は、結婚、出産、住宅購入といった大きなライフイベントが集中するため、具体的な支出に備えた貯蓄計画が必須です。
生活防衛資金が貯まったら、資産運用のスタートを検討しましょう。老後資金準備に向けて、非課税制度であるNISA(つみたて投資枠)を利用した長期・積立・分散投資がおすすめです。
40代:教育費・住宅ローンと老後資金の並行準備
40代は、子供の教育費の本格化や住宅ローンの支払いにより、家計の支出がもっとも増大する時期です。貯金ゼロを脱出するためには、ステップ2の固定費の見直しを再度徹底することが極めて重要です。
教育費は児童手当を全額貯蓄に回すなど、計画的に準備を進めましょう。同時に、老後資金の準備として、節税効果の高いiDeCo(個人型確定拠出年金)の活用も視野に入れ、教育費と老後資金の準備を並行して進める必要があります。
50代:【まだ間に合う】老後資金のラストスパート
50代で貯金ゼロの割合は単身世帯で40.2%と最多ですが、まだ手遅れではありません。この年代は退職金に依存せず、老後資金のラストスパートをかける必要があります。
節税メリットが大きなiDeCoは、制度改正により、会社員や自営業者であれば原則65歳まで拠出が可能になりました。残された時間を最大限活用し、可能であれば満額拠出を目指しましょう。
そして、将来の老後生活レベルを想定した支出のダウンサイジング(生活費の削減)を今から実践し、年金生活に備えた家計体質へと移行することも老後の生活維持に有効です。
≫あなたの将来に必要なお金はいくら?不足額を3分で診断
貯金ゼロに関するQ&A
貯金ゼロに関する、よくある疑問と専門家の回答をまとめました。
Q. 貯金ゼロの人はどのくらいいる?
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」によると、金融資産非保有(貯金ゼロ)の世帯は、全体で単身世帯が32.8%、2人以上世帯が24.0%に上ります。
単身世帯では50歳代がもっとも多く40.2%となっており、40歳代も33.3%と約3分の1を占めています。貯金ゼロは決して珍しい状況ではありませんが、だからといって放置すべきではありません。
Q. なぜ貯金がゼロになるのですか?
貯金がゼロになる原因は、主に「支出管理不能型(どんぶり勘定)」、「収入不足型(手取りが少ない)」、「優先順位混乱型(ストレス消費)」の3つのタイプに分けられます。
根本的な問題は、貯金に対する優先順位が低い「余ったら貯金」という誤った考え方や、家計の「見える化」ができていないことにあります。収入の多寡に関わらず、まずは固定費の削減と「先取り貯蓄」の仕組み化によって、貯蓄に対する優先順位を上げることが解決の糸口となります。
Q. 50歳で貯金ゼロだと、もう手遅れ?
50歳で貯金ゼロであっても、決して手遅れではありません。この年代は収入のピークを迎える可能性が高く、固定費の見直しや支出のダウンサイジングによって大きな効果が見込めます。
ただし、時間の猶予は限られているため、税制優遇の大きいiDeCoの満額拠出(原則65歳になるまで拠出可能)や、NISAを活用した資産運用を直ちに開始し、老後資金の準備を最優先でラストスパートをかける必要があります。退職金に頼るのではなく、今すぐ具体的な行動を開始することが大切です。
まとめ
貯金ゼロという状況は、病気や失業、老後破綻といった深刻なリスクを伴います。しかし、重要なのは、自分がどのタイプの原因で貯金できないのかを理解し、意志に頼らない「仕組み化」を実行することです。
固定費の徹底的な見直しと「先取り貯蓄」の導入により、確実に貯蓄体質へと移行できます。その後、年代に合わせた資産形成の優先順位付け(生活防衛資金の確保からNISA・iDeCoへ)を行うことで、ゼロからの逆転は可能です。本記事のアドバイスを活用し、今日から脱出ロードマップのステップを踏み出してください。
≫あなたの将来に必要なお金はいくら?不足額を3分で診断
将来が不安なあなたへ
将来、お金の不安なく暮らすために、老後の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備を便利に進められる無料ツールを利用できます。
▶将来資金の無料診断:将来必要になる金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資で賢く増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。