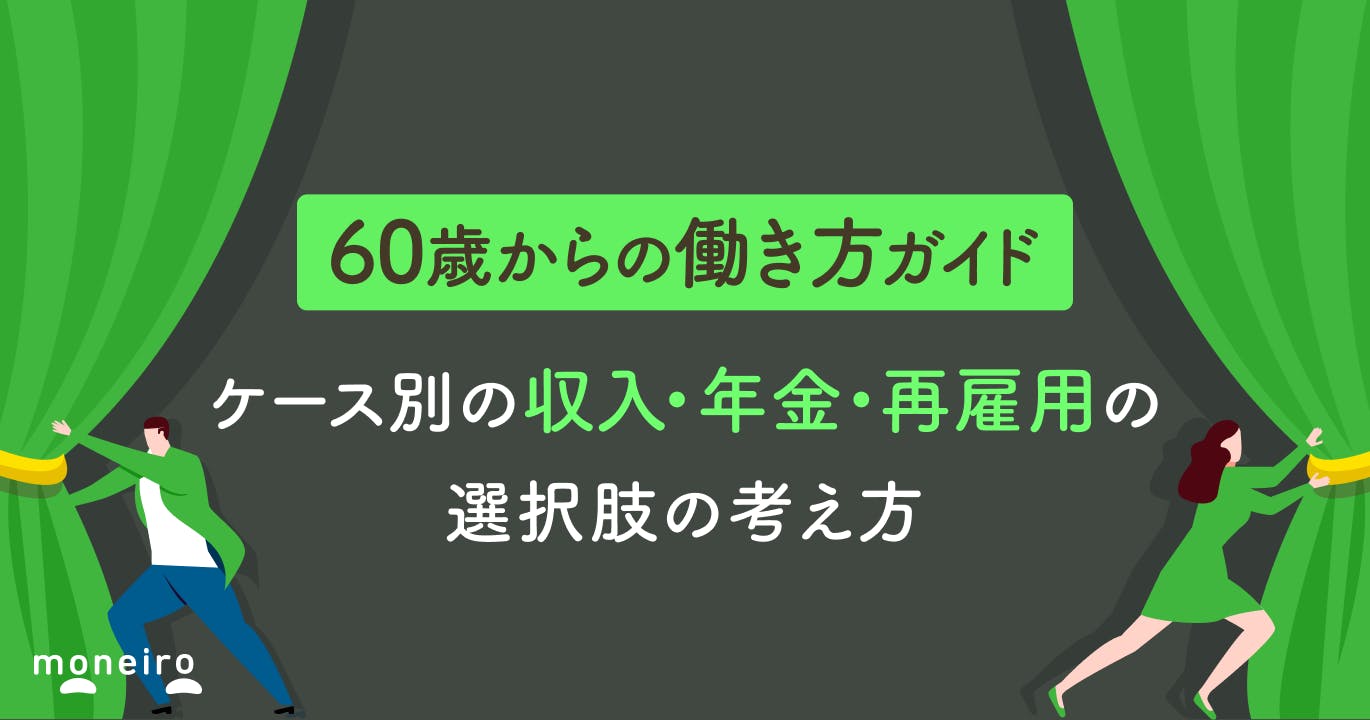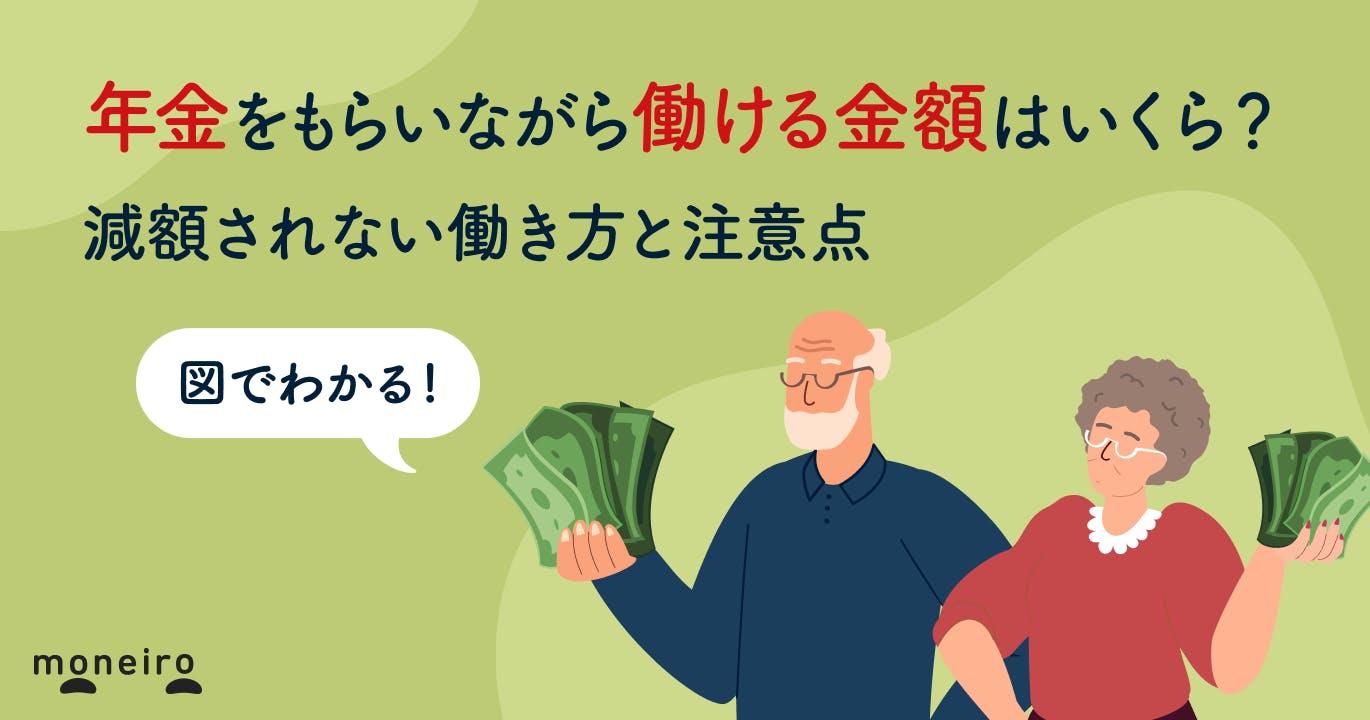60歳からの働き方ガイド|ケース別の収入・年金・再雇用の選択肢の考え方を徹底解説
»60歳からの暮らしに必要な金額をいますぐチェック
60歳を迎えると、再雇用の給与が大きく下がる、年金の受給調整が必要になるなど、働き方に関する判断が複雑になりやすいです。さらに、在職老齢年金や高年齢雇用継続給付など「働くと年金がどう変わるか」を正しく理解せずに働いてしまうと、受給額が減ってしまうなどの損失につながる可能性があります。
本記事では、60~65歳の働き方を「収入」「制度」「キャリア」の3軸でわかりやすく整理し、再雇用・転職・フリーランスの選択肢についてわかりやすく解説します。
- 60歳以降の働き方の主な選択肢とそれぞれの特徴
- 年金や給付金制度と収入のバランスを取る方法
- 60代が採用されやすい仕事と具体的な選び方
老後のお金が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
60歳以降の働き方の選択肢
60歳以降の働き方には、主に「再雇用」「転職」「フリーランス」そして「定年延長」といった選択肢があります。
高年齢者雇用安定法の改正により、企業には70歳までの就業機会を確保する努力義務が課されており、シニア世代が働き続けやすい環境が整いつつあります。
それぞれの働き方にはメリットとデメリットがあるため、自身のライフプランや価値観に合わせて最適な選択をしましょう。
働き方3パターンの比較表
「再雇用」「転職」「フリーランス」の3つの働き方を、収入の安定性、自由度、環境の変化、仕事探しの手間の4つの観点で比較してみましょう。
①再雇用
再雇用制度は、定年退職した従業員を、企業が再び雇用する制度です。最大のメリットは、慣れ親しんだ職場で働き続けられる安心感と、仕事探しをする手間がかからない点です。
一方、企業によって大きく異なりますが、給与水準が低下するというデメリットもあります。正社員として再雇用された場合は定年前の7,8割程度もらえることもあれば、契約社員などで再雇用された場合、定年前の半分を下回ることもあります。
仕事内容は同じでも責任範囲が軽くなることが多く、以前の部下が上司になるといった人間関係の変化が生じる可能性もあります。
②転職
転職(再就職)は、定年退職後に新たな会社で働く選択肢です。これまでのキャリアにとらわれず、全く新しい仕事に挑戦できる点が大きな魅力です。新しい環境で人間関係が広がり、65歳以降も継続して働ける職場に出会える可能性もあります。
しかし、60代向けの正社員求人は少なく、多くの場合は契約社員やパートタイムといった非正規雇用となります。そのため、給与や待遇などの雇用条件が前職より劣るケースが多いのが実情です。
また、希望通りの仕事がすぐに見つからず、再就職先が決まるまでブランクが生じる可能性も考慮しておく必要があります。
③フリーランス
フリーランス(個人事業主)という形で働くことも、60歳からの有力な選択肢です。これまでのキャリアで培ったスキルや人脈を活かし、自分の裁量で仕事を進められるのが最大のメリットです。
働く時間や場所を自由に決められるため、趣味や家族との時間を大切にしながら収入を得ることができます。
ただし、会社員と違って収入が保証されていないため、継続的に仕事を得るための営業活動が不可欠です。収入が不安定になるリスクも考慮しなければなりません。
近年では、インターネットを通じて仕事を受発注できるクラウドソーシングサイトも充実しており、少ないリスクで始められる仕事も増えています。
定年延長と再雇用の現状
2013年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、「65歳までの雇用確保」を企業の義務としました。
これを受け、多くの企業がシニア世代の雇用確保に取り組んでいます。
具体的な措置としては、以下の3つが主流です。
- 定年を65歳以上に引き上げる
- 定年制を廃止する
- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)を導入する
厚生労働省の調査によると、継続雇用制度を導入している企業が最も多く、全体の7割以上を占めています。これにより、希望すれば65歳まで同じ会社で働き続けることが可能になりました。
さらに、2021年4月には「70歳までの就業確保」が企業の努力義務とされ、シニアが長く活躍できる環境が整備されつつあります。
60歳以降の収入と公的制度 ― 損しない働き方の設計
60歳以降の働き方を考える上で、年金や給付金といった公的制度との関係を理解することは不可欠です。
社会保険や税金の扱いも変わるため、収入と支出のバランスを総合的に設計することが「損しない働き方」の鍵となります。
働きながら年金を受け取る仕組み(在職老齢年金)
60歳以降も厚生年金に加入しながら働くと、給与(総報酬月額相当額)と年金(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)の合計額に応じて年金の一部または全額が支給停止されることがあります。
これを在職老齢年金制度といいます。
2025年現在、給与と年金の合計額が51万円を超えた場合、超えた額の半分が年金から減額されます。例えば、合計額が55万円だった場合、超過分の4万円の半額である2万円が、毎月の年金額から差し引かれます。
この制度は、高収入を得ながら年金も満額受け取ることを調整するための仕組みです。
働きながら年金受給を考えている場合は、給与と年金額から、支給調整が行われるかどうかを事前に確認しておきましょう。
高年齢雇用継続給付の「もらえる人・もらえない人」
60歳以降の賃金が定年前と比べて大幅に低下した場合、その減少分を補うために雇用保険から給付金が支給される制度があります。これが「高年齢雇用継続給付」です。
この制度には、働き方に応じて2つの種類があります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 対象者:定年後、退職せずに同じ会社で再雇用され、賃金が60歳時点の75%未満に低下した人
- 条件:雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
- 高年齢再就職給付金
- 対象者:60歳以降に一度退職し、失業保険を受給した後に再就職して、賃金が退職前の75%未満になった人
- 条件:失業保険の支給残日数が100日以上あること
雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
いずれも、低下した賃金の最大15%が支給されます。
ただし、この制度は段階的に縮小・廃止される方針が示されているため、今後の動向に注意が必要です。また、高年齢雇用継続給付を受給しながら老齢年金を受給する場合、年金は給付金額の4割程度の金額が支給停止となります。
60歳以降で年金繰下げをした場合の損得
公的年金は原則65歳から受給開始ですが、希望すれば60歳から受け取る「繰上げ受給」や、66歳以降に遅らせて受け取る「繰下げ受給」が選択できます。
- 繰上げ受給:1ヶ月早めるごとに0.4%(1962年4月1日以前生まれの人は0.5%)減額されます。60歳から受給を開始すると、本来の額から24%減額された年金額を生涯受け取ることになります
- 繰下げ受給:1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額されます。75歳まで繰下げが可能で、最大で84%増額された年金額を生涯受け取れます
どちらが得かは、個人の健康状態や寿命、そして60歳以降の収入状況によって異なります。一般的に、長生きするほど繰下げ受給が有利になりますが、60代で十分な収入がない場合は繰上げ受給も選択肢となります。
ライフプランと資金計画を基に、慎重に判断することが大切です。
「働きながら繰下げ」が向いている人
年金の繰下げ受給は65歳以降も働き続け、十分な収入が見込める人に向いています。繰下げ期間中の生活費を給与で賄えるため、増額された年金を将来の備えとして最大化できます。
具体的には、以下のような特徴を持つ人が「働きながら繰下げ」を選択するメリットが大きいです。
- 健康で体力に自信があり、長く働き続けたい意欲がある
- 再雇用や転職により、現役時代に近い安定した収入を確保できる
- 住宅ローンや教育費などの大きな支出が既に終わっている
- より豊かな老後生活のために、将来の年金額を増やしたいと考えている
社保・税金はどう変わる?
60歳以降の働き方は、社会保険や税金の負担にも影響します。
社会保険については、定年後に同じ会社で再雇用される場合、一度社会保険の資格を喪失し、再取得する手続きを行うのが一般的です。
これにより、再雇用後の低い給与水準に基づいた「標準報酬月額」が設定され、毎月の健康保険料や厚生年金保険料の負担が軽減されます。
税金の面では、特に退職金の受け取り方が重要です。退職金を一度に受け取る「一時金」形式は、「退職所得控除」という大きな税制優遇が適用されるため、分割で受け取る「年金」形式よりも手取り額が多くなることが多いです(ケースによって異なります)。
退職金制度を確認し、最適な受け取り方を検討しましょう。
(参考:60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。|日本年金機構)
老後のお金が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
60代が採用されやすい仕事と選び方
60代の仕事探しでは、これまでの経験を活かせる職種や、人手不足で未経験者を歓迎している業界が中心となります。
また、体力的な負担を考慮し、無理なく長く続けられる仕事を選ぶ視点も重要です。
60代の採用が多い職種
60代の求人は、性別によって需要が高い職種に違いが見られます。男性は経験や体力を活かせる仕事、女性はコミュニケーション能力や家事スキルが役立つ仕事が多い傾向にあります。
60代男性には、これまでの社会経験や責任感を活かせる仕事や、体力的に無理のない範囲で働ける職種が人気です。
- 警備員・マンション管理人
- 設備管理
- ドライバー
- 工場作業員 など
また、60代女性には、これまでの家事や育児の経験、コミュニケーション能力を活かせる仕事が多くあります。
- 介護補助・保育スタッフ
- 事務職
- 販売・接客
- 家事代行・清掃員
- 在宅ワーク
- コールセンター など
正社員・パート・業務委託の比較
60歳からの働き方は、雇用形態によって収入の安定性や自由度が大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の希望に合った形態を選びましょう。
安定した収入を最優先するなら正社員が理想ですが、60代からの転職は経験者採用が中心となります。
一方、プライベートの時間を重視するならパート・アルバイト、スキルを活かして自由に働きたいなら業務委託というように、ライフスタイルに合わせて選択することが重要です。
60代で独立する時の注意点
60代からの独立は、自由な働き方を実現できる魅力的な選択肢ですが、いくつかの注意点があります。
第一に、収入が不安定であることを念頭に置く必要があります。会社員のように毎月決まった給与が保証されるわけではないため、仕事がなければ収入はゼロになります。
第二に、退職金を安易に開業資金に充てないことです。事業が軌道に乗るまでには時間がかかることが多く、生活費を圧迫するリスクがあります。
まずは現役時代に副業として小さく始め、収入の見通しが立ってから本格的に取り組むのが賢明です。
健康・体力と働き方の相関
60歳を過ぎると、若い頃と同じように働くのは難しくなります。健康状態や体力は個人差が大きいため、ご自身の身体と相談しながら無理なく続けられる働き方を選ぶことが何よりも重要です。
体力に自信がない場合は、フルタイム勤務にこだわらず、週数日のパートタイムや短時間勤務が可能な仕事を選ぶのが賢明です。事務職やマンション管理人、清掃員などは、比較的身体的な負担が少なく、シニア世代に人気があります。
一方、適度に体を動かすことが健康維持につながると考える人には、軽作業や販売職なども良い選択肢です。
いずれにせよ、万が一身体を壊してしまうと働けなくなるリスクがあるため、きつすぎる仕事は避け、自身のペースで働ける環境を優先しましょう。
60歳から後悔しないための準備【40代・50代向け】
充実したセカンドキャリアを送るためには、40代や50代からの準備が鍵となります。現役のうちから将来を見据え、自身の市場価値を高めるためのスキルアップや、老後の生活設計を具体的に描いておくことが、60歳以降の選択肢を大きく広げます。
早めに準備を始めることで、年収の減少を最小限に抑え、経済的な不安なく新しいステージに進むことができます。
スキル・資格で年収の落差を小さくする方法
定年後の再雇用や転職では、多くの場合、年収が大幅に下がります。この収入の落差を少しでも小さくするためには、専門的なスキルや資格を身につけておくことが有効です。
特に、年齢に関わらず需要のある「業務独占資格」(その資格がないと仕事ができない資格)は、60代からのキャリアにおいて大きな武器となります。
【シニアのキャリアに役立つ資格の例】
- マンション管理員を目指すなら:管理業務主任者
- 介護業界で働くなら:介護福祉士
- 不動産業界で働くなら:宅地建物取引士
現役のうちから、自身のキャリアに関連する分野や、興味のある分野で資格取得を目指す「リスキリング(学び直し)」に取り組むことで、60歳以降も即戦力として評価され、より良い条件で働くことが可能になります。
60歳以降の生活費と年金のギャップを把握する
60歳からの働き方を計画する上で、まずやるべきことは「老後にどれくらいのお金が必要か」を具体的に把握することです。年金収入だけで生活が成り立つのか、それとも働く必要があるのかを判断するための第一歩となります。
まずは現在の家計簿をもとに、定年後の生活で変動する支出(食費、交際費、住居費など)をシミュレーションしてみましょう。
そして、日本年金機構から毎年送られてくる「ねんきん定期便」で将来の年金受給見込額を確認し、不足額(ギャップ)がいくらになるかを計算することが重要です。
この不足額が、60歳以降に働くことで得るべき収入の目安となります。
まとめ
60歳からの働き方は、定年前のキャリアの延長線上だけにあるわけではありません。再雇用で慣れた環境を選ぶ道、転職で新たな挑戦をする道、そして独立して自分らしい働き方を追求する道など、選択肢は多岐にわたります。
重要なのは、ご自身の健康状態、経済状況、そして「これからどんな人生を送りたいか」という価値観を基に、最適なバランスを見つけることです。
年金や給付金といった公的制度を賢く活用し、無理なく長く続けられる仕事を選ぶことが、充実したセカンドキャリアの鍵となります。
また、現在40代、50代の方は今のうちからスキルアップや資産形成などの準備を始めることで、60歳を迎えた時の選択肢はさらに広がります。
本記事を参考に、ぜひご自身の理想の働き方を見つけてください。
»将来必要額と最適なプランを3分で確認(無料)
老後のお金が気になるあなたへ
マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
▶退職金を“減らさず使う”100歳までの資産活用術:資産を長持ちさせる方法がわかる
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事


60歳以上も厚生年金に加入し続けるデメリットは?損しない働き方と制度を解説

定期預金より堅実なお金の増やし方をプロが厳選!賢くお金を増やす方法を徹底解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。