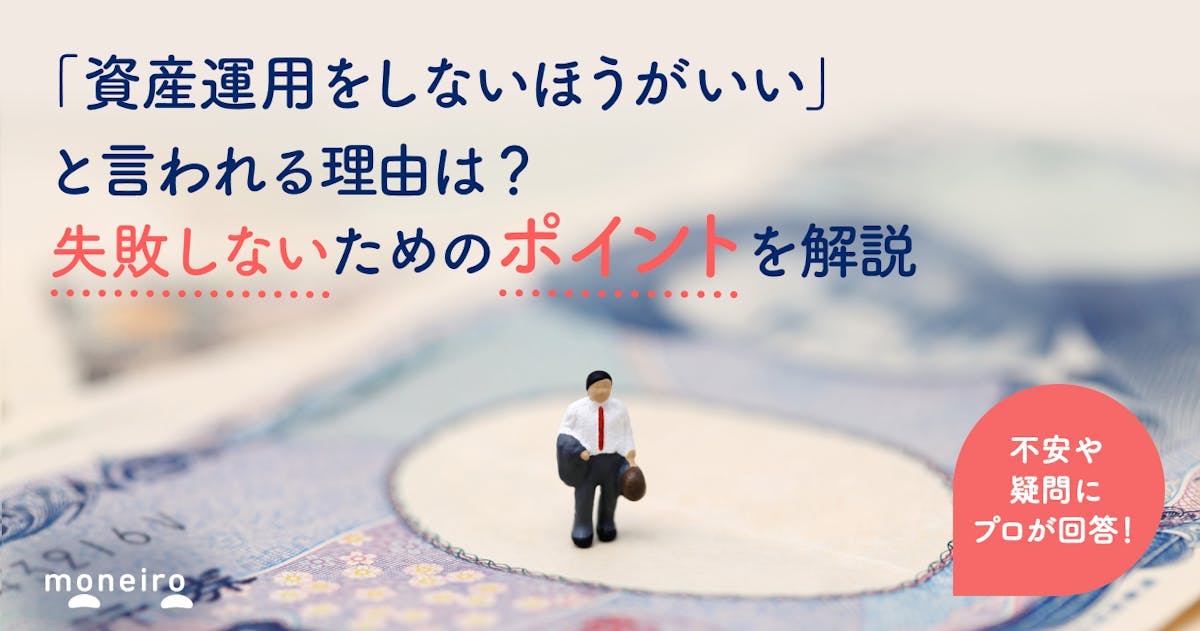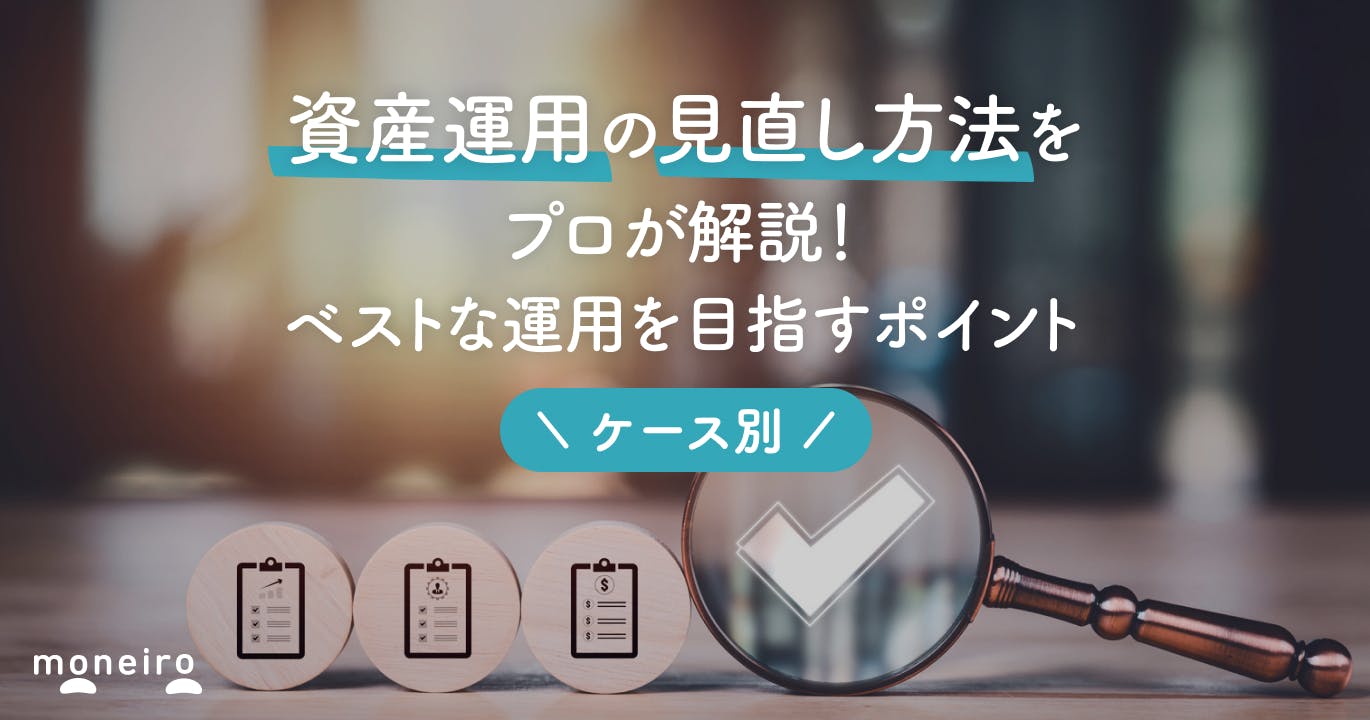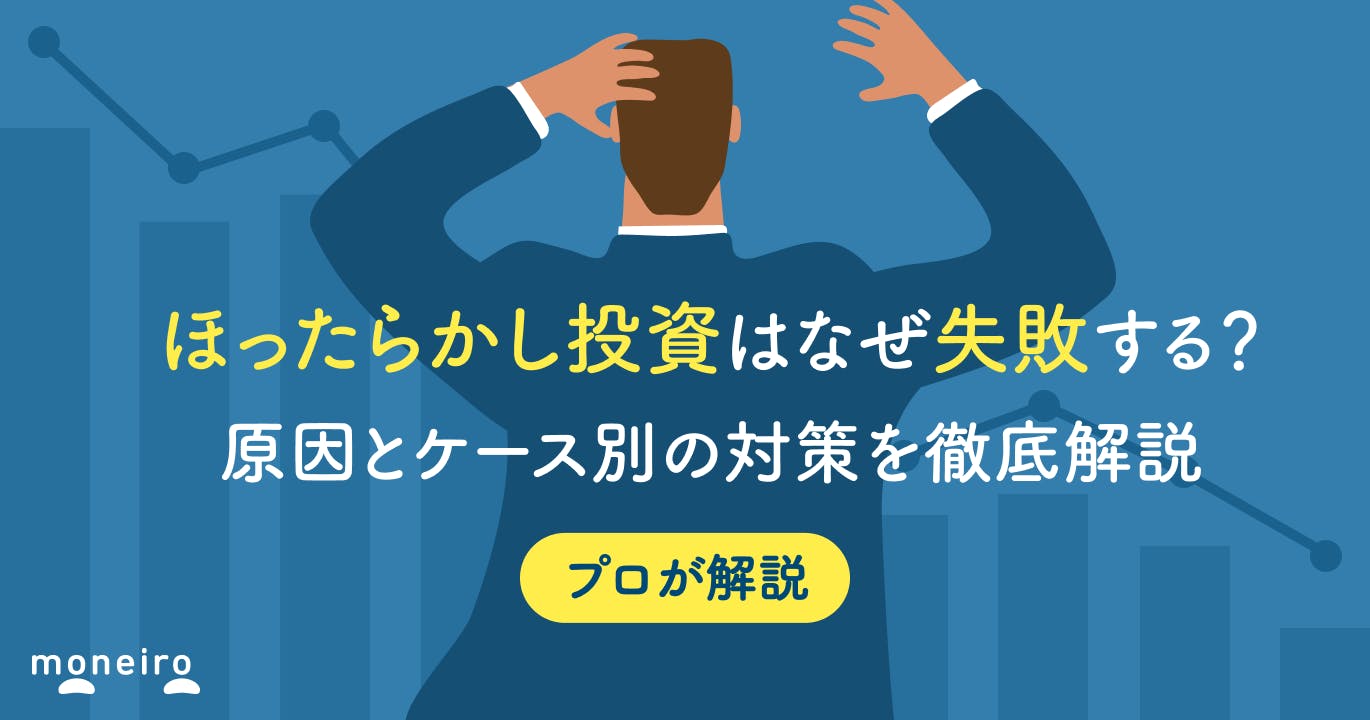資産運用はしないほうがいい?そういわれる理由&「しないことのリスク」を解説
≫あなたは資産運用するべき?最適な運用を3分で診断
「資産運用はしないほうがいい」という意見を耳にすることがあるかもしれません。その背景には、投資に対する元本割れへの恐れや、投資詐欺のイメージがあります。
本記事では、専門家監修のもと、「資産運用をしないほうがいい人」の特徴や、何もしないことによるリスク、そしてリスクを抑えながら資産運用を行うための運用術を解説し、元本割れが怖い方や、損をしたくない方へ、最適な資産管理のヒントをお伝えします。
- 「資産運用をしないほうがいい」といわれる理由・3つのリスク
- 資産運用をしないほうがいい人の特徴
- 元本割れが怖い人でもリスクを抑えて始めるための「守りの運用術」
「資産運用はしないほうがいい」といわれる理由・3つのリスク
資産運用は、必ずしもすべての人にとって必須ではありません。しかし、近年の「みんなやったほうがいい」と推奨する論調に対して不信感を持つ人がいることも事実です。投資はあくまで目的を達成するための「手段」であり、個々のライフプランや経済状況に応じて、取り組むべきかどうかを判断する必要があります。
ここでは、まず「資産運用をしないほうがいい」といわれる根本的な理由と、その背景にある具体的なリスクを確認しておきましょう。
元本割れリスク
資産運用をしないほうがいいといわれる最大の理由は、投資した元本が減ってしまう元本割れリスクが存在するからです。預貯金は元本が保証されていますが、株式や投資信託などの金融商品は、市場の変動により価値が常に上下します。
特に、短期間で大きなリターンを狙おうと売買を繰り返した場合、市場のタイミングによっては大きく元本を毀損する可能性があり、これが「資産運用は怖い」というイメージを助長しています。元本割れのリスクを避けるためには、商品の特性を理解し、長期・分散投資の視点を持つことが不可欠です。
資産の流動性リスク
資産の流動性リスクとは、必要な時にすぐに換金できない可能性を指します。例えば、不動産投資のように売却活動に時間を要するものや、特定の未公開株など、取引市場が小さく買い手を見つけるのが困難な資産はその最たるものです。
そうでない一般的な投資信託でも、売却から口座へ入金されるまで3~5営業日程度かかるため、急な出費やライフイベントで資金が必要になった時に、すぐさま現金化できず、生活設計に支障をきたす恐れもゼロではありません。資産運用においては、流動性を意識して、現預金や売買しやすい金融商品とのバランスを確保することが肝心です。
詐欺・高コスト商品リスク
資産運用に対する不信感が生まれる背景には、悪質な詐欺や高コスト商品が市場に存在することが挙げられます。特に投資初心者や金融知識が十分でない人をターゲットにした、高利回りを謳う怪しい投資スキームや、販売手数料が非常に高く、投資家にとって不利な条件の金融商品(高コスト商品)が残念ながら流通しています。
こうした商品によって損失を被ると、「資産運用=危険・やらないほうがいい」という先入観が強く残ってしまいます。
信頼できる金融機関を選び、国や政府が提供する非課税制度(NISAやiDeCo)など、安全性が高く、透明性の確保された経路を利用することが、このリスクを回避するために重要です。
資産運用を「しないほうがいい人」の5つの特徴
投資にはリスクが伴います。そのため、すべての人に無条件に推奨されるものではありません。以下の5つの特徴に当てはまる場合は、資産運用を始める前に、まず自身の財務基盤を強化するか、生活状況を見直すことをおすすめします。
1. 生活防衛資金が確保できていない人
資産運用で使う資金は、あくまで「近い将来に使う予定のない余剰資金」であることが大前提です。万が一、病気や失業、大規模災害など予期せぬ事態が発生した際に、すぐに引き出して生活費に充てられる「生活防衛資金」が不足している状態で投資を始めると非常に危険です。
市場が下落しているタイミングで急な資金需要が発生した場合、損を確定させて売却せざるを得なくなる可能性が高まります。生活防衛資金は、月々の生活費の6ヶ月分程度を目安に、現預金として確保しておくとよいでしょう。
2. 数年以内に使う予定の資金(教育費・住宅資金)を増やそうとしている人
投資によるリターンは、一般的に長期運用を行うことで安定し、元本割れのリスクが軽減される傾向にあります。しかし、数年以内といった短期的な運用期間では、市場の変動によって必要な時期に資金が目減りしているリスクが非常に高くなります。
例えば、2〜3年後に必要となる子供の教育資金(大学の入学金など)や、数年後の住宅購入の頭金など、使用時期が確定している資金は、リスクの高い投資に回すべきではありません。これらの資金は、「元本保証」を優先し、流動性の高い預貯金などで管理することが賢明です。
3. カードローンやリボ払いなどの高金利な負債がある人
負債、特にカードローンやリボ払いのように、金利が年率10%を超えるような高金利な負債を抱えている場合は、投資を始めることよりも負債の返済を最優先すべきです。
一般的に、株式や投資信託などの資産運用で期待できる年間利回り(例えば、年3~5%)は、高金利な負債の支払い金利を大きく下回ります。そのため、投資で得られる期待収益よりも、負債の利息支払いによって手元から減る金額のほうが大きくなります。高金利な負債を完済することが、もっともリスクが低く、かつ利回りの高い「運用」と考えるべきです。
4. 「利益」や「節税」よりも「元本保証」を優先したい人
資産運用において、どれだけリスクを許容できるか(リスク許容度)は人によって異なります。「リスクを取ってでも節税効果や大きな利益を追求したい」という人もいれば、「精神的な安心を最優先し、絶対に元本を減らしたくない」という人もいます。
もし、多少の利益を得る機会を逃したとしても、元本が保証されている状態を何よりも優先したいのであれば、株式や投資信託など、元本割れリスクがある商品には手を出すべきではありません。この場合は、預貯金や個人向け国債など、安全性の極めて高い資産での管理を選択するのが適切です。
5. 日々の値動きが気になって仕事や睡眠に支障が出る人
資産運用は、運用している資金が多ければ多いほど、市場の変動による精神的な影響が大きくなります。特に下落局面では、不安感から売買を繰り返して損失を確定させたり、日々の値動きが気になって集中力を欠き、仕事や睡眠などの日常生活に悪影響を及ぼすことがあります。
投資は、日常生活に支障をきたさない範囲で行うべきです。もし、値動きに過度に反応してしまう傾向がある場合は、資産運用を避けるか、値動きの小さい商品を選ぶのが賢明でしょう。
「資産運用をしない」ことによるリスクも知っておこう
資産運用には元本割れリスクがありますが、実は、「何もしない」という受動的な選択もまた、別の形で大きな経済的リスクに直面することがあります。この「資産運用をしないリスク」は、特に長期的な資産形成の視点で見ると、無視できない重大な脅威となり得ます。
インフレリスク:現金の価値は実質的に目減りする
近年、国内外でインフレ(物価の上昇)が続いています。インフレとは、モノやサービスの価格が全体的に上がり続ける現象です。インフレが進行すると、相対的にお金の価値は下落します。
2024年のマイナス金利解除以降、金利のある世界へと移行しつつありますが、2025年12月現在においても銀行の普通預金金利(メガバンクで年利0.2%程度)は、物価上昇率に対して低水準に留まっています。
そのため、現金をただ保有しているだけでは、実質的に購買力が目減りしていくことになり、将来的に生活必需品やサービスを購入する能力が低下してしまいます。これが、資産運用をしないことによる、もっとも深刻なリスクの1つです。
機会損失:NISA・iDeCoという「強力な非課税枠」を捨てることに
資産運用をしないという選択は、国が用意した優遇税制であるNISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)という「強力な非課税枠」を活用する機会を失うことを意味します。
通常、投資によって得た利益(配当金や売却益)に対しては20.315%の税金が課されます。しかし、NISAやiDeCoといった制度を利用して運用することで、この運用益が非課税になります。
これは、資産が加速度的に増えていく複利効果を最大限に享受できることを意味し、長期的な資産形成において大きなメリットです。この強力な税制優遇を活用しないという選択は、重大な「機会損失」になり得ます。
老後資金不足:公的年金のマクロ経済スライドへの対抗策欠如
日本の公的年金制度は、将来的な財政健全性を保つため、「マクロ経済スライド」という仕組みによって給付水準が自動的に調整されるようになっています。これは、現役世代の減少や平均寿命の伸びに応じて、年金の給付額が実質的に抑制されていく仕組みです。
今後、少子高齢化がさらに進むにつれて、公的年金のみで老後の生活費をすべて賄うことが難しくなる可能性が非常に高くなっています。
資産運用をまったくしない場合、年金給付水準の抑制(実質的な目減り)に対して、自力で購買力を維持・向上させるための有効な対抗策を持たないことになります。計画的な長期積立投資は、公的年金の不足分を補うための、現実的で重要な対策です。
≫あなたは資産運用するべき?最適な運用を3分で診断
それでも不安な人へ、リスクを軽減する「守りの運用術」
「何もしないリスク」は理解できたが、やはり投資への不安が拭えず、元本割れが怖いという方もいるでしょう。ここでは、リスクを極限まで軽減し、心の平穏を保ちながら安全に資産運用を始めるための「守りの運用術」を解説します。
税制優遇(iDeCo)を「リターン」と捉える
税制優遇制度のメリットは、非課税による運用益の増加だけではありません。特にiDeCo(個人型確定拠出年金)の場合、拠出した掛け金全額が所得控除の対象となります。所得控除とは、課税対象となる所得を減らす仕組みであり、結果的に支払う所得税や住民税が減少します。
例えば、所得税率が20%の方が年間24万円(月2万円)をiDeCoに拠出した場合、所得税(20%)だけでなく住民税(一律10%)も軽減されるため、合わせると約30%の節税効果が生まれます。金額にすると年間7万2000円もの税金が戻ってくる計算です。
これは、運用そのもののリターンとは別に、投資初年度に30%もの確実な利益(コスト削減)を得たと見なすことができます。所得税率が低い場合(5%)でも、住民税と合わせて最低15%のリターンが確約される点は、他の金融商品にはない大きな強みです。
この税制優遇による節税効果を、運用益とは別の「リターン」として捉えることで、元本割れリスクに対する心理的な不安を大きく軽減し、投資への一歩を踏み出しやすくなります。
債券・バランス型ファンドを活用した低ボラティリティ運用
高いリターンを狙う株式市場中心の運用は、ボラティリティ(価格変動幅)が高く、元本割れリスクも高まります。リスクを最小限に抑えたい場合は、値動きの穏やかな債券や、株式と債券を適切に組み合わせたバランス型ファンドを活用する「低ボラティリティ運用」を検討しましょう。
債券は、一般的に株式よりも価格の変動が小さく、定期的な利子収入が得られるため、資産価格が安定しやすい特徴があります。また、バランス型ファンドは、リスク資産(株式)と安全資産(債券やREITなど)を自動的に組み合わせることで、市場が大きく変動した場合でも、全体としての値動きを穏やかに抑える効果があります。
これにより、リスク許容度が低い人でも精神的なストレスを少なく、運用を長期的に継続しやすくなります。
「一括投資」を避け「ドル・コスト平均法」で時間を味方につける
投資タイミングを予測し、一度に全額を投じる「一括投資」は、もし高値で始めてしまうと、その後の下落局面で一時的に大きな含み損を抱えやすくなります。元本割れのリスクを大幅に軽減するうえで非常に有効なのが、「ドル・コスト平均法」を用いた定期的な積立投資です。
ドル・コスト平均法とは、毎月一定額を継続的に購入していく投資手法です。価格が高い時には自動的に購入口数が少なくなり、価格が安い時には購入口数が多くなるため、結果として長期的に見て購入単価を平準化し、高値掴みによる短期的なリスクを分散できます。
特に、NISAの「つみたて投資枠」やiDeCoは、このドル・コスト平均法を前提とした積立投資を推奨しており、時間をかけてリスクを分散することが可能です。
資産運用に関するQ&A
資産運用を始める際によく寄せられる疑問について、専門的な知見に基づきQ&A形式で回答します。
Q. 低リスクな投資商品は?
現時点で安全性が高い投資先の1つとして、「個人向け国債(特に変動10年)」が挙げられます。日本国が元本と利子を保証しており、元本割れのリスクは実質的にありません。
特に「変動10年」タイプは、今後市場金利が上昇した場合、それに連動して受け取れる利子も増える仕組みになっているため、インフレ・金利上昇局面に強いのが特徴です。発行から1年経過すれば中途換金も可能で、預貯金より高いリターンを目指せる「守りの資産」の代表格です。
Q. 資産運用したほうがよい人の特徴は?
資産運用を積極的に行うべきなのは、前述の「しないほうがいい人」の特徴に該当しない、以下の条件を満たす人です。
- 緊急時の備えとなる生活防衛資金をすでに確保し、使う予定のない余剰資金がある人。
- 老後資金や教育資金など、運用期間を10年以上の長期で設定できる目的を持っている人。
- インフレによる現金の購買力低下リスクを理解し、リスクを取ってでも実質的な価値の維持・向上を目指したい人。
- カードローンやリボ払いなどの高金利な負債がなく、手元の資産を効率よく成長させたい人。
- 日々の値動きに感情を左右されず、長期的な視点で資産を「放置」できる精神的余裕のある人。
特に、上記のような条件を満たし、NISAやiDeCoを活用できる人は、資産運用をしないと強力な税制優遇を捨てる機会損失のリスクが非常に大きくなります。
Q. NISAにはデメリットもある?
NISAは非課税という大きなメリットを持ちますが、いくつかの構造上の注意点(デメリットと捉えられる点)があります。
1つ目は、損益通算ができない点です。特定口座や一般口座では、他の投資で出た利益と損失を相殺して課税所得を減らす「損益通算」が可能ですが、NISA口座内で損失が出た場合、その損失を他の口座の利益と相殺して税金を減らすことができません。
2つ目は、繰越控除ができない点です。その年に発生した損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺する「繰越控除」の仕組みも、NISA口座では利用できません。
これらは運用上の制約ではありますが、利益が非課税になるというメリットが、通常はこれらのデメリットを上回るため、適切に活用すべき制度であることに変わりはありません。
まとめ
資産運用には、元本割れや流動性リスク、詐欺リスクが存在し、特定の状況にある人(生活防衛資金がない、高金利負債があるなど)は「しないほうがいい」という意見には合理性があります。
しかし、現在進行するインフレリスクや、公的年金に依存できない将来の備えを考慮に入れると、「何もしない」という選択が、将来の購買力を失うもっとも大きなリスクとなり得ます。現金の価値を守り、非課税制度による強力な機会損失を避けるためには、長期的な視点での資産形成が現代社会では不可欠です。
資産運用の準備として、まずは高金利な負債を返し、生活防衛資金を確保することから始めましょう。その上で、税制優遇を最大限に活用し、ドル・コスト平均法や低ボラティリティ商品の選択で「守りの運用」を行うのが、リスクを抑えたい方にはおすすめです。
「資産運用をすること」と「しないこと」、両方のリスクを理解したうえで、自分に合った資金の育て方を実践していきましょう。
≫あなたは資産運用するべき?最適な運用を3分で診断
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
高橋 明香
- ファイナンシャルアドバイザー/CFP®認定者
みずほ証券(入社は和光証券)では、20年以上にわたり国内外株、債券、投資信託、保険の販売を通じ、個人・法人顧客向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2021年に株式会社モニクルフィナンシャル(旧:株式会社OneMile Partners)に入社し、現在は資産運用に役立つコンテンツの発信に注力。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格(証券外務員一種)保有。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。