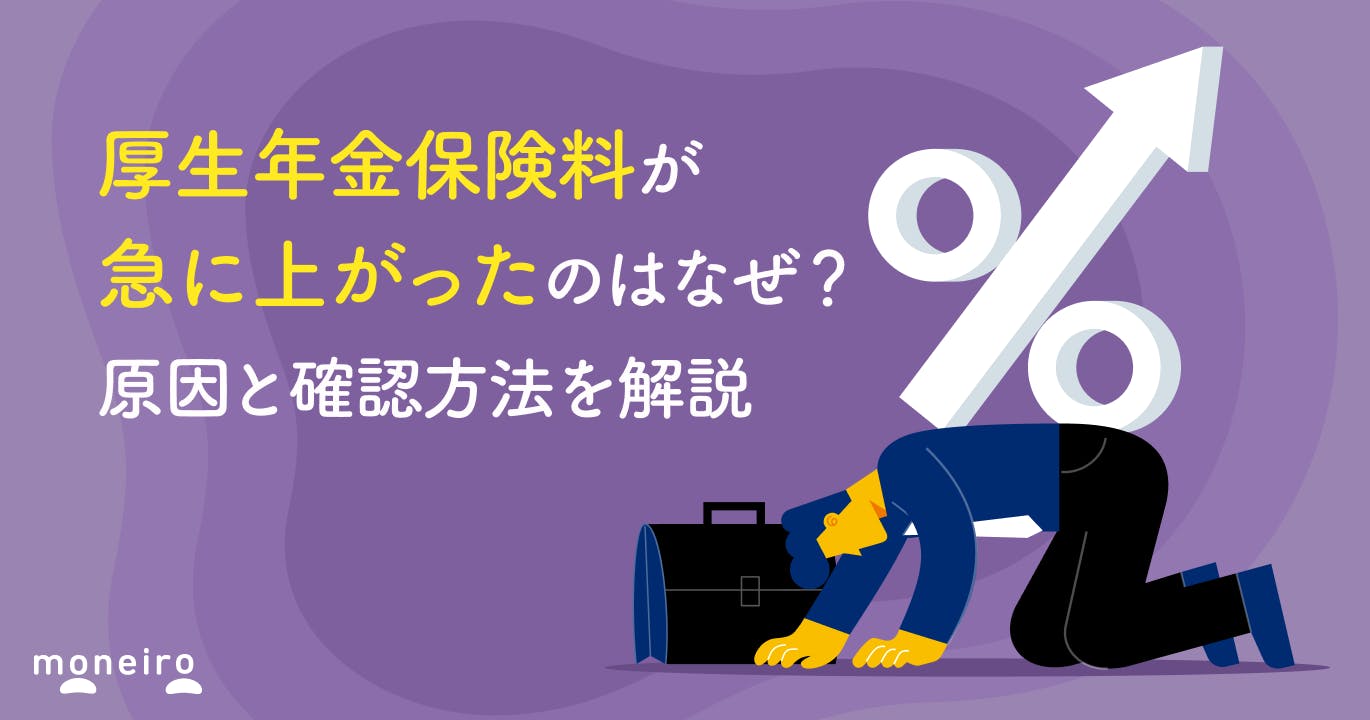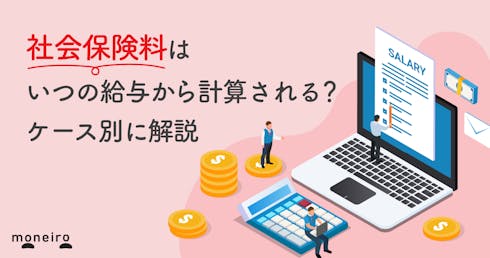
通勤手当が課税される理由とは?税理士が税金の仕組みと確認ポイントを解説
無料診断:老後に必要な資金が3分でわかる
「通勤手当は非課税では?」「交通費も課税対象?」と会社から支給される通勤手当について、こんな疑問を持った人も多いのではないでしょうか。
通勤手当は原則として一定額まで非課税ですが、支給額や通勤手段によっては課税対象になるケースもあります。
本記事では、通勤手当が非課税になる条件や課税される理由を税理士監修のもとわかりやすく解説します。
さらに、給与明細での確認方法や、マイカー通勤・併用通勤の扱いについても具体例で紹介します。「なぜ課税されているのか」を正しく理解しましょう。
- 通勤手当は一定の限度額までは非課税。ただし、条件次第で課税される
- 通勤手当が課税されるのは「非課税限度額を超えた時」「制度外の交通手当や一時金として支給された時」
- 通勤手当が課税された場合、年末調整や住民税、社会保険料の計算に反映される
給与から引かれる税金が気になるあなたへ
現在の収入から無理なく将来資金を準備しましょう。
マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
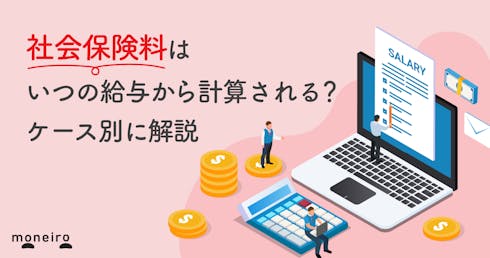
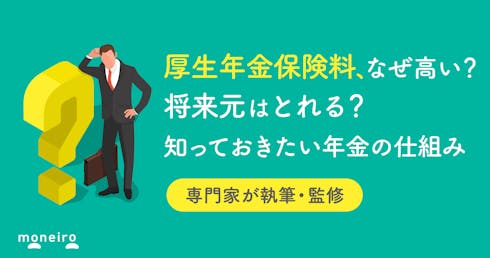
通勤手当の対象と支給の仕組み
通勤手当とは、従業員が職場へ通うためにかかる交通費などの費用を、企業が一定範囲で補助する手当のことです。
公共交通機関の定期券代、自動車やバイクのガソリン代、距離に応じた通勤補助などが主な対象となります。
企業によって支給方法や上限額に差はありますが、一般的には「通勤にかかる実費を弁償する」という目的のもと、毎月の給与とともに支給されます。
そもそも通勤手当は課税対象?→条件次第で課税される
通勤手当は、会社が従業員の通勤にかかる費用を補助する目的で支給するものです。原則として、一定の限度額までは非課税とされています。
この「非課税枠」は、通勤手段や距離によって異なり、例えば電車やバスなどの公共交通機関を使う場合は月15万円までが非課税です。
自家用車や自転車での通勤には、通勤距離に応じて非課税の限度額が細かく定められています。
ただし、これらの非課税枠を超えた金額が支給された場合、その超過分は課税対象となり、所得税や住民税の計算に含まれます。
通勤手当の課税・非課税の考え方
通勤手当は、すべてが非課税になるわけではありません。通勤手段や距離、支給額などの条件に応じて、「非課税」となる上限額が定められており、それを超える分は課税対象となります。
通勤手当が一定額まで非課税とされるのは、従業員が通勤にかかる費用を会社が補填するものであり、これは給与(所得)とは性質が異なる「実費弁償」とみなされるためです。
国税庁も、通勤手当は「住宅事情等からみた場合にその全額を課税対象とすることは妥当でないとの政策的配慮に基づくもの」と位置づけています。
通勤にかかるお金は、労働の対価というよりは、業務に必要な経費の一種と捉えられているため、一定の範囲内であれば税金がかからないという考え方です。
通勤手当が課税されるのはどんな時?
通勤手当は以下のケースに該当した場合、課税対象となります。
非課税限度額を超えた時
通勤手当は「要件を満たす一定の範囲内」であれば非課税として扱われます。所得税法上の非課税限度額は、通勤手段や通勤距離に応じて国税庁により細かく定められています。
通勤方法ごとの非課税限度額を把握しておきましょう。
公共交通機関(電車・バス)の場合
公共交通機関(鉄道・バス)を利用して通勤する場合の非課税限度額は、1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額です。
「合理的な運賃等の額」とは、通勤経路が最も経済的かつ合理的であると認められる定期券の料金などを指します。
実際に支払った通勤費のうち、月額15万円を超える部分は課税対象となります。
マイカー・バイク通勤の場合
自動車やバイクで通勤する場合は、通勤距離に応じた金額が非課税限度額として定められています。2024年時点では以下のような基準です。
参考)マイカー通勤手当の非課税限度枠の引き上げ
政府は物価高やガソリン価格の上昇を受け、マイカー通勤にかかる非課税枠を見直す方針を打ち出しています。2025年秋を目処に、非課税限度額の引き上げが予定されています。
徒歩通勤の扱い
徒歩通勤の場合、一般的には通勤手当が支給されません。これは、通勤手当が「通勤にかかる実費を弁償する」ためです。
電車賃やガソリン代のような直接的で明確な費用が発生しない徒歩通勤に対して、会社が手当を支給する義務はありません。
制度外の交通手当や一時金として支給された時
通勤手当として支給されていても、支給方法や金額によっては課税対象になることがあります。
例えば、実費を超える金額が「交通費」や「移動手当」として支給されたり、明確な支給基準がない場合は、給与の一部とみなされて課税されます。
また、就職や転勤のための引っ越し費用の補助など、実費を超える一時的な支給も課税対象になることがあります。
通勤手当は、通勤実態に基づき毎月支給されることが原則で、それ以外の支給は課税の対象となるため注意が必要です。
参考)交通費と旅費交通費の違い
「交通費」とは、従業員が自宅から勤務先まで通勤するためにかかる費用のことです。通勤手当として支給されるこの交通費は、一定の限度額までは非課税となります。
一方、「旅費交通費」は、出張や業務での移動にかかる費用を指します。例えば、出張時の電車代・飛行機代・宿泊費、取引先への移動費などが該当します。
旅費交通費は、業務上必要な実費として会社が支給するもので、原則として全額非課税です。これは給与所得ではないため、課税対象にはなりません。
通勤手当が課税対象になった場合の確認方法・影響
通勤手当が非課税限度額を超えた場合、その超過分は給与所得とみなされ、課税対象になります。
例えば、公共交通機関を使った通勤で月16万円の通勤手当が支給されている場合、非課税限度額の15万円を1万円超えます。
そのため、非課税限度額を超えた1万円分が給与に加算され、所得税・住民税・社会保険料の対象になります。
具体的な処理は以下の通りです。
課税となった場合の確認方法と源泉徴収の影響
通勤手当が課税対象となった場合、毎月の給与明細で確認することができます。
給与明細での確認方法
多くの場合、給与明細の「支給項目」欄には、「基本給」「残業手当」「通勤手当」などが記載されています。
このうち、非課税限度額を超えた通勤手当の金額は「課税対象額」として他の課税される給与と合算されて表示される、もしくは「課税通勤手当」といった項目で明記されることがあります。
総支給額は非課税分も含めた合計額で記載され、その下の「課税支給額合計」のような項目で、実際に課税される給与の総額を確認できます。
源泉徴収への影響
課税対象となった通勤手当は、毎月の給与に上乗せされた所得として扱われるため、その月の所得税(源泉徴収税額)が通常よりも高くなる場合があります。
結果として、手取り額が想定よりも少なくなる可能性があります。
年末調整・住民税・社会保険への反映
課税対象となる通勤手当は、年末調整や住民税、社会保険料の計算にも反映されます。
年末調整への反映
会社員の場合、毎年11月~12月に行われる年末調整で、その年の1月1日から12月31日までのすべての所得が再計算されます。
課税された通勤手当も、この年間の給与所得に含めて計算されるため、最終的な所得税額や還付・徴収額に影響します。
仮に月々源泉徴収された所得税額とその人の一年間の所得に対する所得税に差額がある場合、年末調整で精算されます。
住民税への反映
住民税は、前年の所得に対して課税されます。そのため、課税対象となった通勤手当は、翌年度の住民税額の計算の対象となります。
所得が増えると、住民税の所得割額が増加する可能性があります。
社会保険料への反映
通勤手当は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)の計算基準となる「報酬月額」や「賃金総額」に含まれるのが一般的です。
したがって、課税対象となった通勤手当は、社会保険料の算定基礎額にも含まれ、結果として社会保険料の負担が増える可能性があります。
社会保険料の金額が増えると、将来受け取る年金額にも影響を与えることがあります。

課税されたら手取りはいくら減る?
通勤手当の一部が課税対象になると、給与に上乗せされる形で課税所得が増えます。結果として所得税や住民税、社会保険料の負担が増えることになり、手取り額が減少する可能性があります。
以下のような流れで課税金額を算出してみましょう。
2.通勤手段・距離に応じた非課税限度額を確認(例:1万8700円)
3.支給額から非課税限度額を差し引いた分が「課税対象」(例:3万円-1万8700円=1万1300円)
課税対象分が1万1300円上乗せされた給与で、所得税・住民税・社会保険料が算出されます。
通勤手当の課税でよくある質問
通勤手当の税務上の扱いは複雑なため、さまざまな疑問が生じやすいものです。
よくある質問について回答します。
Q.自転車通勤に通勤手当は支給される?
はい、自転車通勤に対しても通勤手当が支給される場合があります。会社が自転車通勤手当を支給するかどうかは、企業の任意です。
所得税法上、自転車は自動車やバイクと同じ部類になります。そのため、非課税となる1ヶ月当りの支給限度額はマイカー・自転車通勤と同じになります。
Q.リモートワーク中心でも通勤手当は支給される?
リモートワーク(テレワーク)中心の場合、通勤手当が支給されないケースが多いです。会社への通勤が全く発生しない場合は、通勤の実態がないため通勤手当は支給されません。
一方、週に数日だけ出社する「ハイブリッド勤務」の場合、定期券の支給ではなく、実際に出社した日の交通費を実費精算する形を取る会社が増えています。
この実費精算された交通費は、非課税の対象となります。
リモートワーク中心の働き方の場合、会社によって通勤手当のルールが異なります。会社の規程を確認し、不明点は人事・経理担当者に相談しましょう。
Q.転居・引越しで通勤経路が変わったらどうなる?
転居や引越しにより通勤経路が変わった場合、通勤手当の変更手続きが必要です。
引越し後、速やかに会社の人事・経理担当者に連絡し、新しい通勤経路と通勤費を勤務先に届出ます。会社は新しい通勤経路に基づいて通勤手当を再計算し、新しい非課税限度額を確認します。
また、新しい通勤経路の距離や運賃に応じて、非課税限度額が再計算されます。
まとめ
通勤手当は、従業員の通勤費用の実費を弁償するために企業から支給される手当です。一定の範囲までは、所得税・住民税がかからない「非課税枠」があります。
例えば、公共交通機関を使う場合は月額15万円まで、マイカーや自転車通勤の場合は通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。
ただし、この上限を超えた分は「給与」として課税対象になり、手取りの減少や源泉徴収額の増加につながります。また、年末調整や翌年の住民税・社会保険料への影響も考えられます。
なお、自転車通勤やリモートワークが基本の勤務形態では、通勤手当の支給や課税の扱いが企業ごとに異なるため、社内ルールや国税庁の情報を確認しましょう。
給与から引かれる税金が気になるあなたへ
現在の収入から無理なく将来資金を準備しましょう。
マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶NISAで始める資産運用~基本編~:NISAの基本と資産運用の始め方入門
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
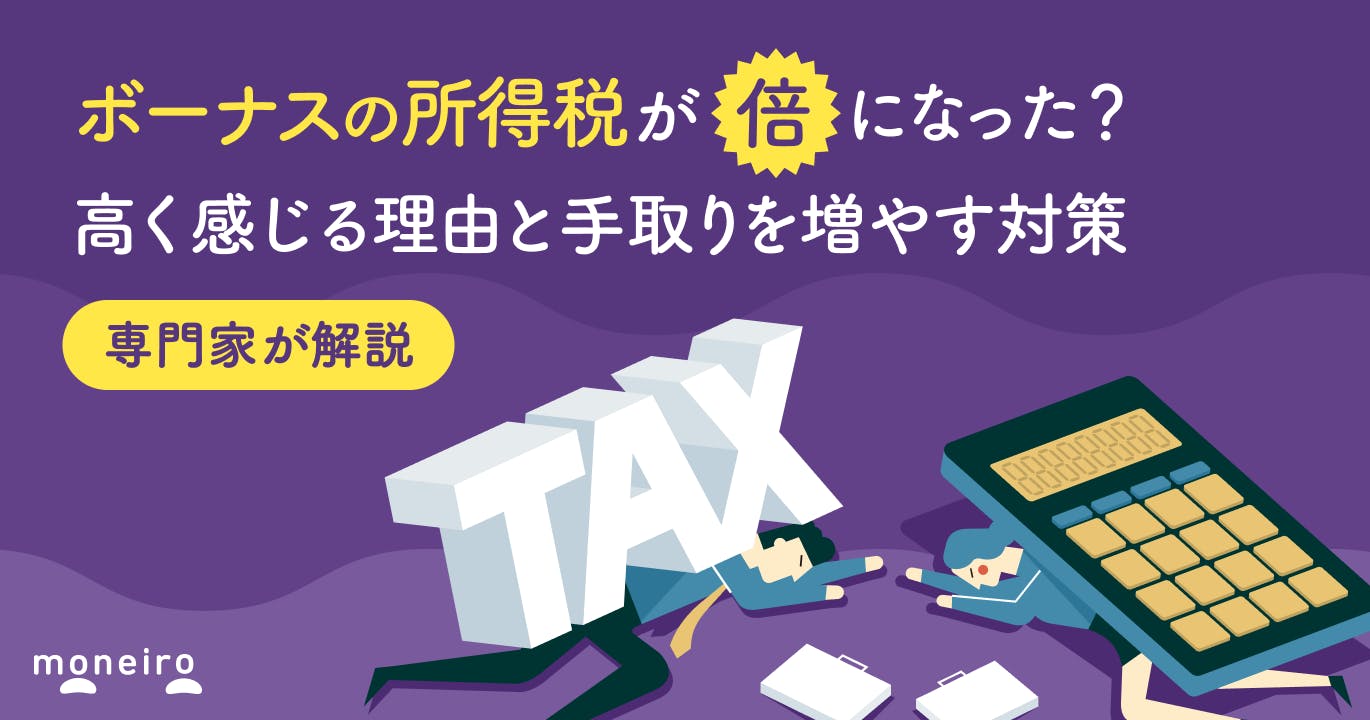
ボーナスの所得税が倍になった?高く感じる理由と手取りを増やす対策を専門家が解説

独身税とは?対象者と負担額は?2026年4月スタートの子ども・子育て支援金制度を解説
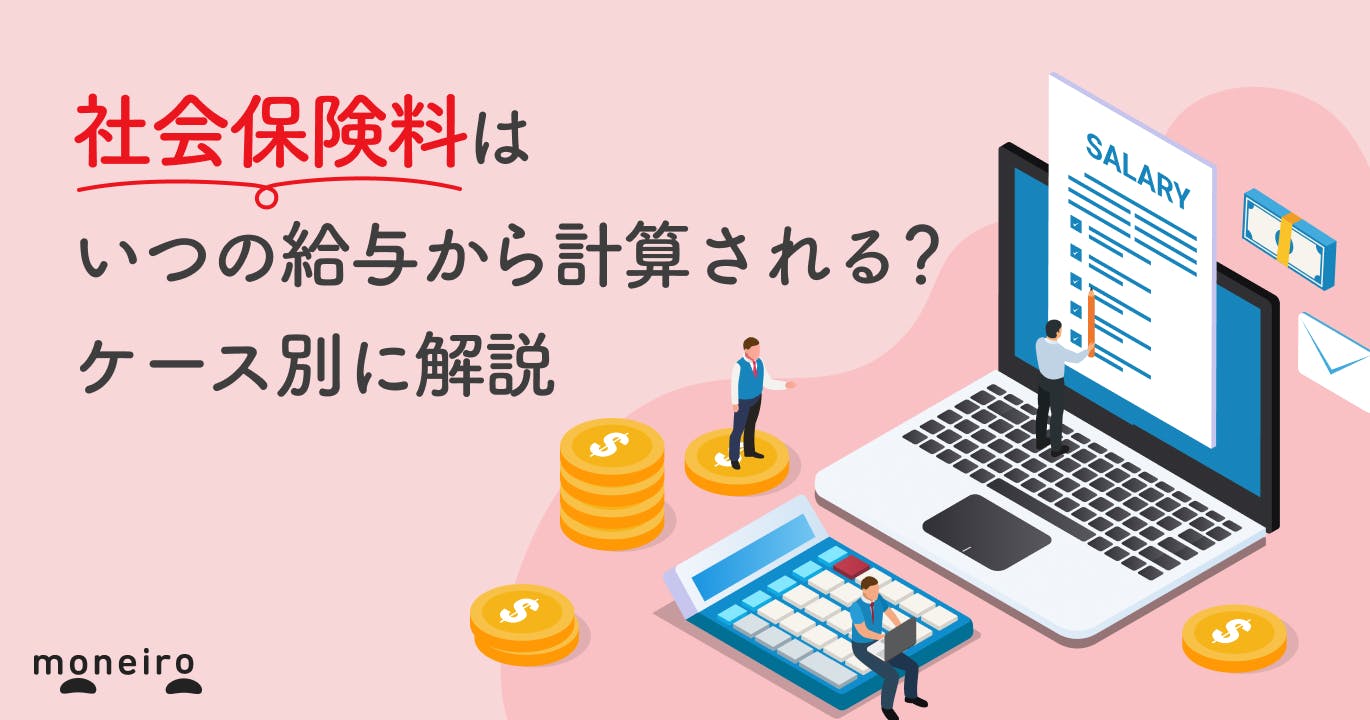
社会保険料はいつの給与から計算される?給与支払い日のケース別に解説