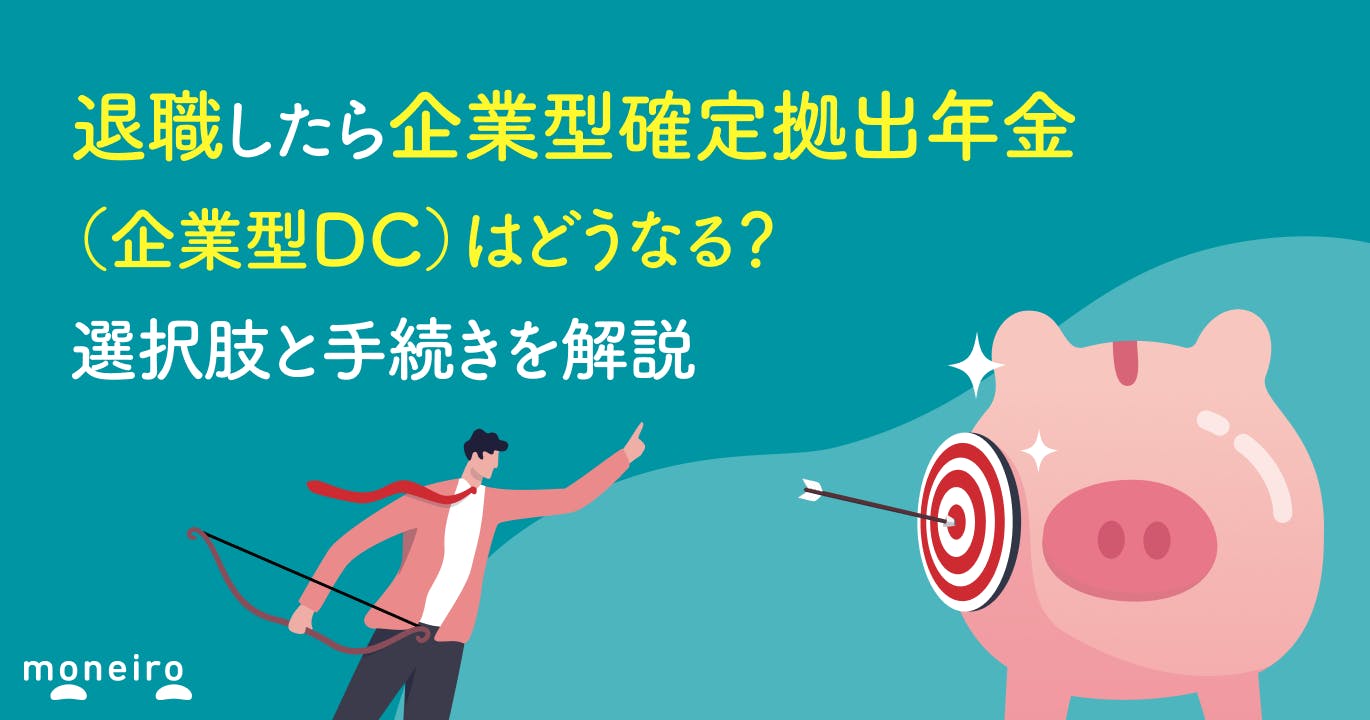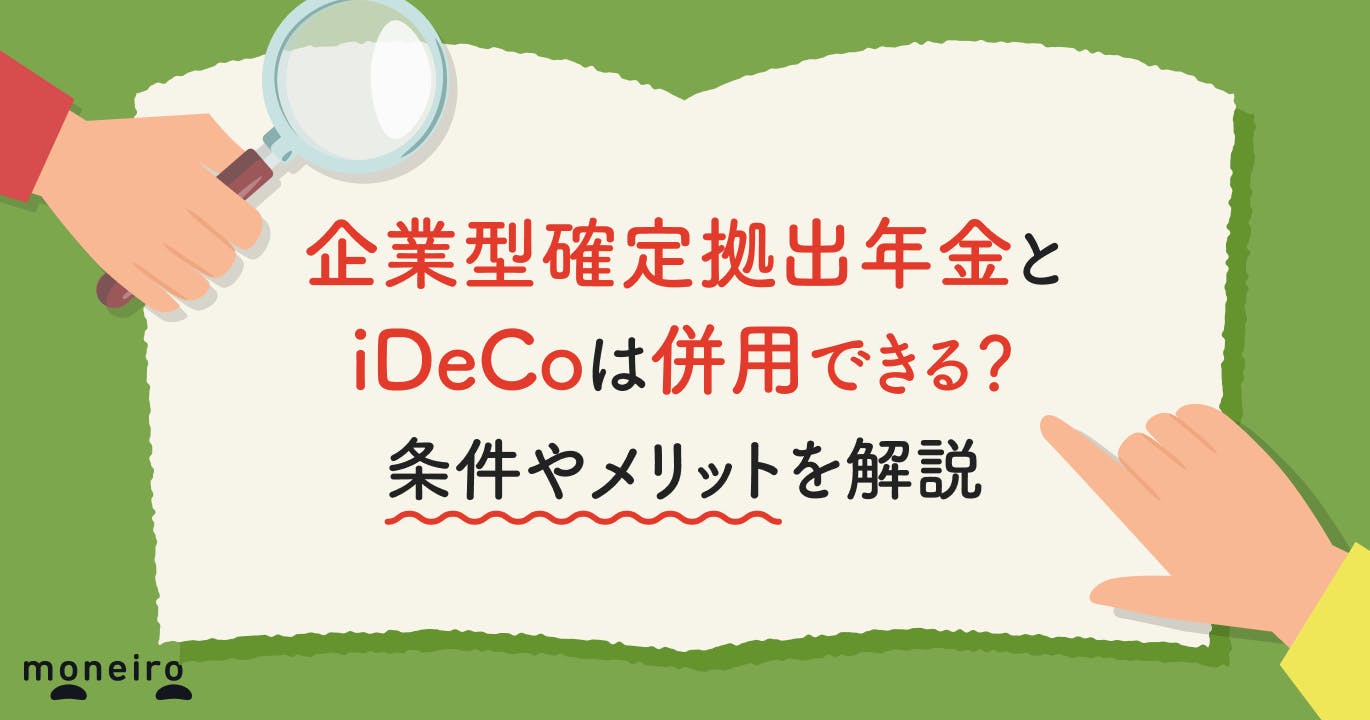
退職したら企業型確定拠出年金(企業型DC)はどうなる?選択肢と手続きを解説
>>将来のお金は足りる?あなたの必要額を3分で診断
会社を退職したら企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産はどうなる?と疑問に感じている方もいらっしゃるでしょう。企業型DCは老後の資産形成において非常に重要な役割を果たしますが、退職後の手続きを怠ると、資産の運用が止まり、不利な状況に陥る可能性があります。
本記事では、退職・転職後の企業型DCの取り扱いについて、放置した場合のデメリットから、適切な5つの選択肢、そして具体的な移換手続きまでを詳しく解説していきます。
- 企業型DCを退職・転職後に放置した場合に生じる自動移換のデメリット
- 退職・転職時に企業型DCの資産に対して選択できる5つの具体的な選択肢
- 企業型DCの資産を次の制度へ移換するために必要な手続きのステップ
老後の資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
退職・転職後に企業型確定拠出年金(企業型DC)を放置したらどうなる?
企業型確定拠出年金(企業型DC)の資産は、退職または転職によって加入資格を喪失した後、そのままにしておくと大変不利な状態に移行してしまいます。
国民年金基金連合会へ自動移換される
企業型DCの加入資格を喪失したにもかかわらず、原則として6ヶ月以内に次の移換先への手続きを完了しない場合、それまでのDC資産は自動的に国民年金基金連合会へ移されます。
この「自動移換」は手続きが不要であるため一見すると楽に感じますが、その実態は資産形成において大きなデメリットを伴います。
自動移換のデメリット
自動移換は、将来の年金資産を守る上で避けるべき事態です。以下で具体的なデメリットを見ていきましょう。
運用が停止する
自動移換されたDC資産は、それまでの運用商品(投資信託など)からすべて現金化され、特別な運用は行われずに現金として管理されます。
これにより、資産が増える機会を失うだけでなく、インフレによって実質的な価値が目減りしていくリスクに晒されます。つまり、老後の資産形成というDC制度の目的から逸脱した状態になってしまいます。
手数料が発生する
自動移換中であっても、国民年金基金連合会に対して管理手数料が発生します。
具体的には、自動移換時に所定の手数料が差し引かれるほか、その後も国民年金基金連合会に対し、月々の管理手数料が資産から引かれ続けます。
運用益が得られない状況にもかかわらず、手数料によって資産が目減りし続けるという二重の損失を被ることになります。
税制優遇が受けられない
企業型DCやiDeCo(個人型確定拠出年金)の大きな魅力は、拠出時・運用時・受取時の3段階で受けられる強力な税制優遇(所得控除、非課税運用、退職所得控除など)です。
しかし、資産が自動移換されている期間中は、これらの税制優遇措置は適用されなくなります。これは、単なる資産の「保管」状態となり、年金制度としての機能が停止してしまうためです。
再移換手続きが必要
自動移換されてしまった資産を、再び企業型DCやiDeCoで運用するためには、改めて「再移換」の手続きを行う必要があります。再移換の手続きは煩雑であり、申請書類の提出や審査に時間がかかることが一般的です。
この手間と時間を避けるためにも、退職後6ヶ月以内に適切な手続きを行うことが極めて重要です。
退職・転職したらどうする?5つの選択肢
退職や転職によって企業型DCの加入者資格を喪失した場合、資産を自動移換から守るために、以下の5つの選択肢の中から最適なものを選び、速やかに手続きを行う必要があります。
転職先の企業型DCへ移換する
転職先の企業が企業型DC制度を導入している場合、これがもっとも一般的な選択肢です。旧勤務先の資産を新しい勤務先の企業型DCに移し替え、そのまま継続して運用と拠出を続けることができます。これにより、税制優遇を途切れさせることなく、スムーズに資産形成を継続することが可能です。
確定給付年金(DB)へ移換する
転職先が確定給付年金(DB)制度を導入している場合、一定の要件を満たすことにより、企業型DCの資産をDB制度へ移換できる場合があります。
ただし、この移換が可能かどうか、また具体的な移換手続きの詳細は、転職先のDB規約や制度設計に依存するため、必ず事前に確認が必要です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)へ移換する
転職先に企業型DCがない場合や、自営業者となる場合、または専業主婦(夫)となる場合など、個人型確定拠出年金であるiDeCoへ資産を移換することが可能です。
iDeCoも企業型DCと同様に、税制優遇(特に所得控除)を受けながら運用を継続できますが、掛金の拠出限度額や運営管理手数料が企業型DCとは異なります。
脱退一時金として受け取る
確定拠出年金は老後の資産形成を目的とする制度であるため、原則として60歳まで資産を引き出すことはできません。
ただし、特定の厳格な要件(例えば、国民年金の保険料免除者であること、加入者期間が短いことなど)をすべて満たした場合に限り、脱退一時金として受け取ることが認められる場合があります。
脱退一時金としての受給はデメリットが大きい
脱退一時金の受給要件を満たし、資産を受け取れたとしても、これは将来受け取るはずだった年金資産を取り崩すことを意味するため、老後の生活設計にとって大きなデメリットとなります。また、受け取る一時金は「一時所得」として課税されます。
しかし、脱退一時金を受けるとそれまでの加入期間(勤続年数)がリセットされてしまうため、その後に再度企業型DCに加入したとしても税負担を軽減する退職所得控除額が小さくなり、結果的に税負担が重くなるケースが多く、税制上のメリットを十分に活かせません。
【60歳以上の場合】老齢給付金として受け取る
退職時に60歳以上であり、かつ企業型DCの加入期間が10年以上など、老齢給付金の受給要件を満たしている場合は、老齢給付金として資産を受け取ることが可能です。
受給方法は、一時金として一括で受け取る方法、年金として分割で受け取る方法、または両方を併用する方法があり、受け取り方によって適用される税制優遇(退職所得控除や公的年金等控除)が変わるため、慎重な選択が必要です。
老後の資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
退職・転職後の企業型確定拠出年金(企業型DC)の移換手続き
企業型DCの移換手続きは、退職後の6ヶ月以内に完了させる必要があり、主に以下の4つのステップで進められます。
Step1.転職先の企業型DCの有無を確認
まず、転職先の企業に企業型確定拠出年金(企業型DC)制度が導入されているかを確認します。この確認によって、資産の移換先が「転職先の企業型DC」となるのか、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」となるのかが決定されます。
どちらに移換するかによって、その後の手続きや必要書類が変わってきます。
Step2.必要書類の準備
移換先が決定したら、必要な書類の準備に取り掛かります。旧勤務先の運営管理機関や、移換先の運営管理機関、または国民年金基金連合会から「加入者資格喪失届」「移換申出書」などの書類を入手し、記入します。
特に、資格を喪失した月(退職日の翌日を含む月)から6ヶ月以内という期限があるため、書類の準備は迅速に進める必要があります。
Step3.申請書類の提出
準備し、必要事項を記入した申請書類を、指定された提出先(移換先の運営管理機関、またはiDeCoの運営管理機関など)へ提出します。
この提出が期限(資格喪失月から6ヶ月以内)に間に合わない場合、前述した自動移換となってしまうため、提出期限を厳守することが非常に重要です。
Step4.移換完了の確認
書類提出後、運営管理機関にて審査・手続きが進められ、数ヶ月を経て移換が完了します。
移換が完了すると、新しい運営管理機関から「加入者口座開設完了通知書」などの通知が送付されます。この通知をもって、資産が正しく移換され、新しい制度下での運用が開始されたことを確認できます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)に関するQ&A
企業型確定拠出年金に関するよくある質問と回答をまとめました。
Q. 企業型DCと退職金は両方もらえる?
企業型DCは退職金制度の1つとして位置づけられますが、多くの企業ではDC制度とは別に、従来の退職一時金制度や確定給付企業年金(DB)制度が併用されています。したがって、企業によっては両方を同時に受け取ることが可能です。
ただし、税制上の注意が必要です。同じ年に企業型DCの一時金と会社の退職一時金の両方を受け取る場合、それらを合算した金額に対して退職所得控除額が一度だけ計算されます。
受け取る年をずらすことで、それぞれで控除を適用できる場合もありますが、過去4年以内に受け取った退職金がある場合など、控除額の計算が複雑になるケースもあるため、事前に会社の担当部署や専門家へ確認することをおすすめします。
Q. 企業型DCは退職後いつからもらえる?
企業型DCの資産は、原則として60歳に到達し、かつ加入者期間などの要件(通常は10年以上)を満たした場合に、老齢給付金として受給資格を得ます。加入者期間が短い場合は、受給開始年齢が最大で65歳まで段階的に引き上げられる場合があります。
退職した時点ではなく、受給資格年齢に達した後に受け取りが開始されます。
Q. 企業型DCと厚生年金は両方もらえる?
はい、両方受け取ることができます。
厚生年金は国の公的年金制度の一部であり、企業型DCは私的な企業年金制度です。企業型DCは、公的年金だけでは不足しがちな老後の所得を補完し、上乗せする役割を果たします。それぞれの制度の受給要件を満たせば、同時に受け取ることが可能です。
まとめ
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、老後の生活を支える重要な私的年金制度ですが、退職や転職の際には、自動移換によるデメリットを避けるため、6ヶ月以内という期限内に適切な移換手続きを行うことが最優先事項です。自動移換されてしまうと、運用停止、手数料の発生、税制優遇の喪失、再移換の手間の増大といった複数の不利益を被ることになります。
資産を有効活用し続けるためには、「転職先の企業型DC」「DB制度」「iDeCo」「確定給付年金」への移換、あるいは受給要件を満たした上での「老齢給付金」の受け取りという5つの選択肢から、自分の状況に合った最適な方法を速やかに選び、手続きを進めることが大切です。
>>将来のお金は足りる?あなたの必要額を3分で診断
老後の資金が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
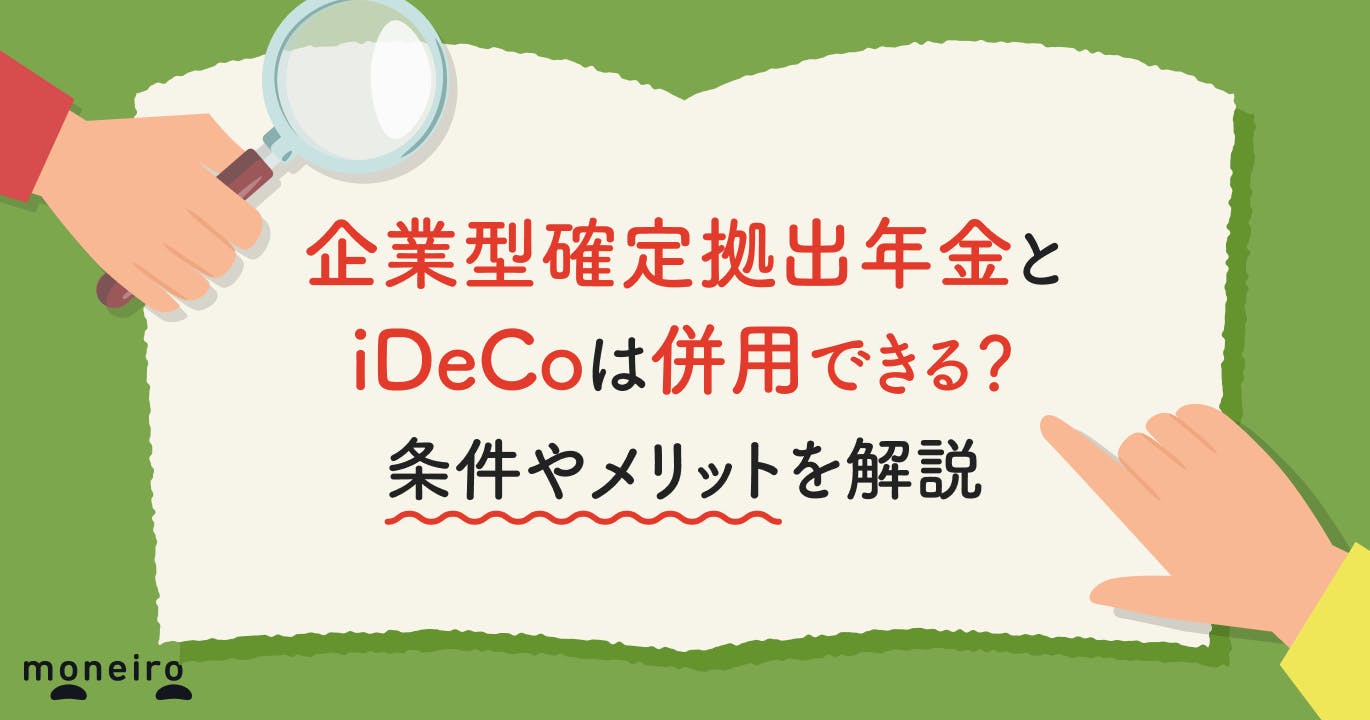
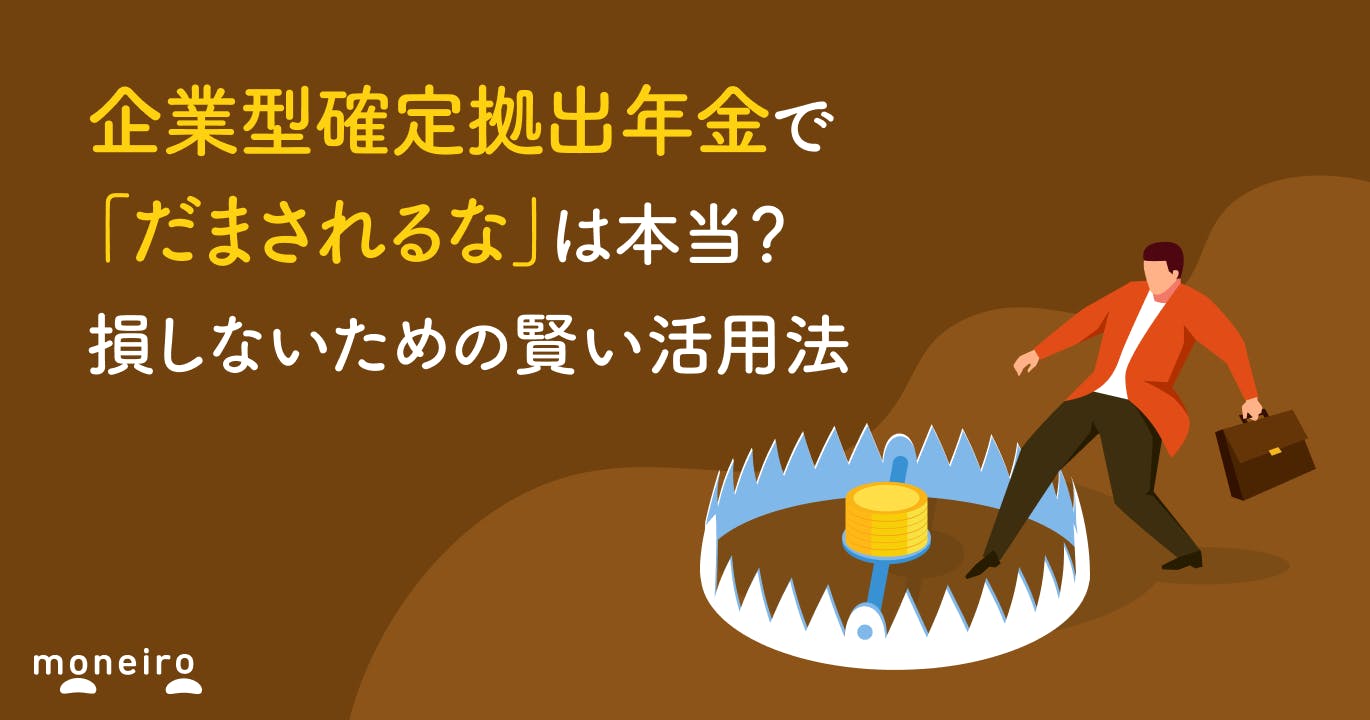
企業型確定拠出年金(企業型DC)で「だまされるな」は本当?損しないための賢い活用法
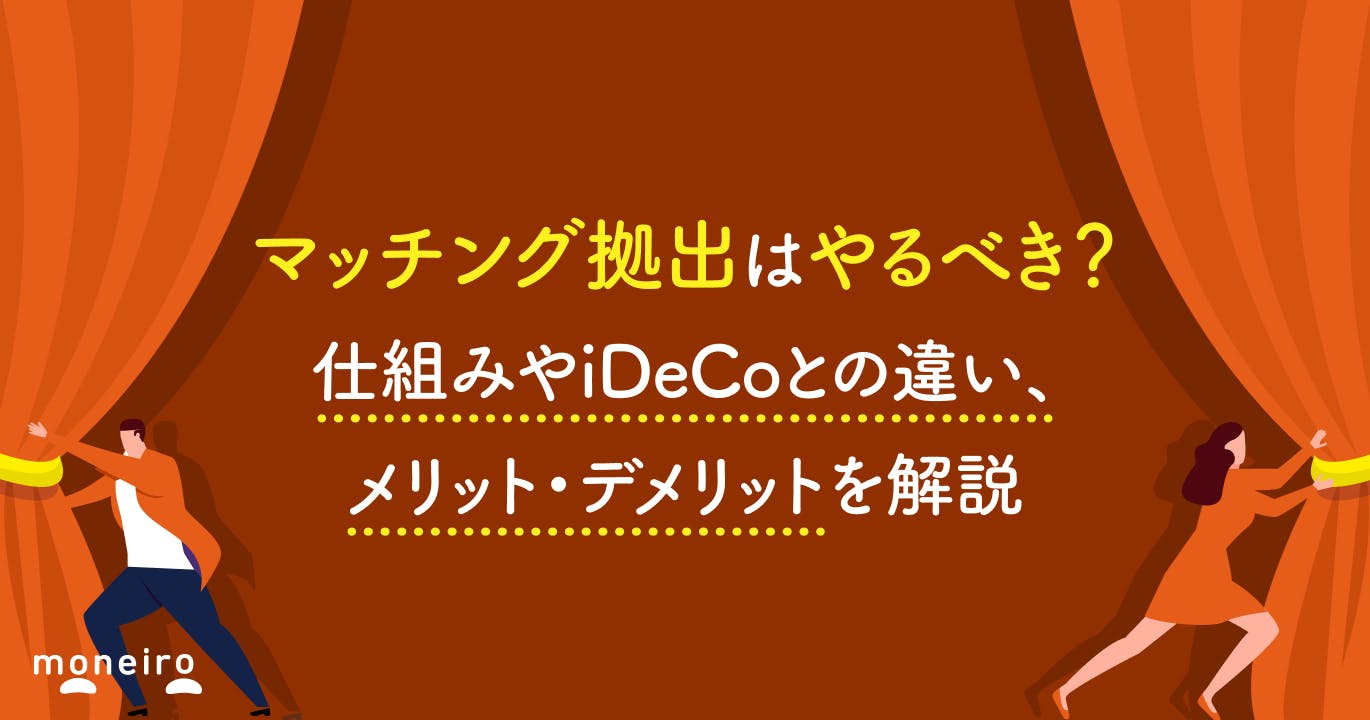
マッチング拠出はやるべき?仕組みやiDeCoとの違い、メリット・デメリットを解説
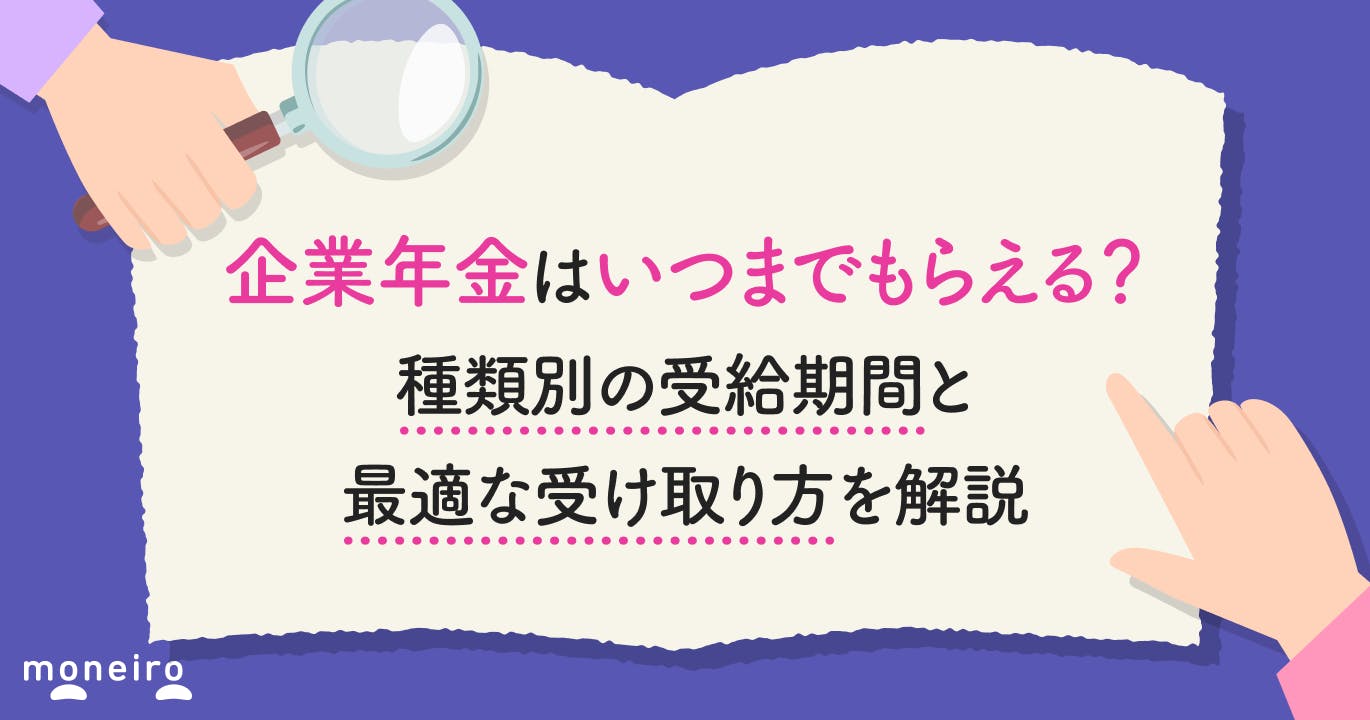
企業年金はいつまでもらえる?種類別の受給期間と最適な受け取り方を解説
監修
山本 務
- 特定社会保険労務士/AFP/第一種衛生管理者
東京都練馬区で、やまもと社会保険労務士事務所を開業。企業の情報システム、人事部門において通算28年の会社員経験があるのが強みであり、情報システム部門と人事部門の苦労がわかる社会保険労務士。労務相談、人事労務管理、就業規則、給与計算、電子申請が得意であり、労働相談は労働局での総合労働相談員の経験を生かした対応ができる。各種手続きは電子申請で全国対応が可能。また、各種サイトで人事労務関係の記事執筆や監修も行っている。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。