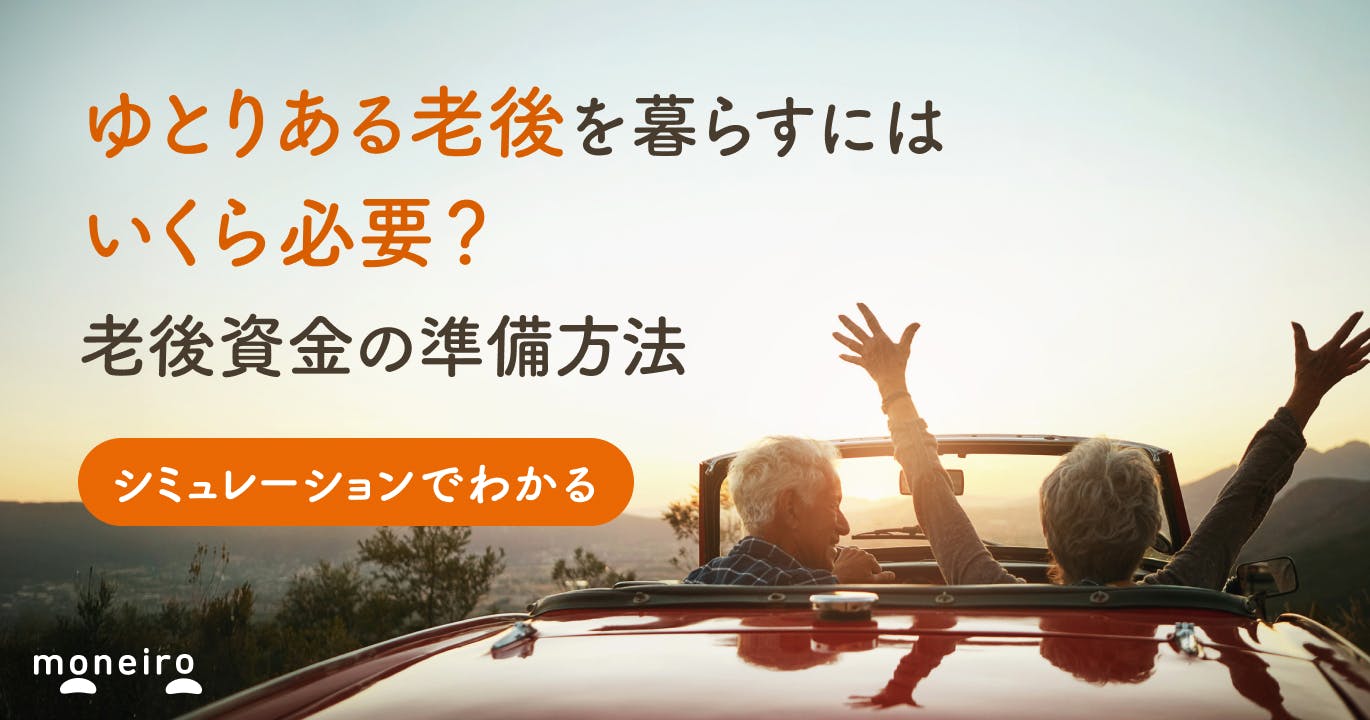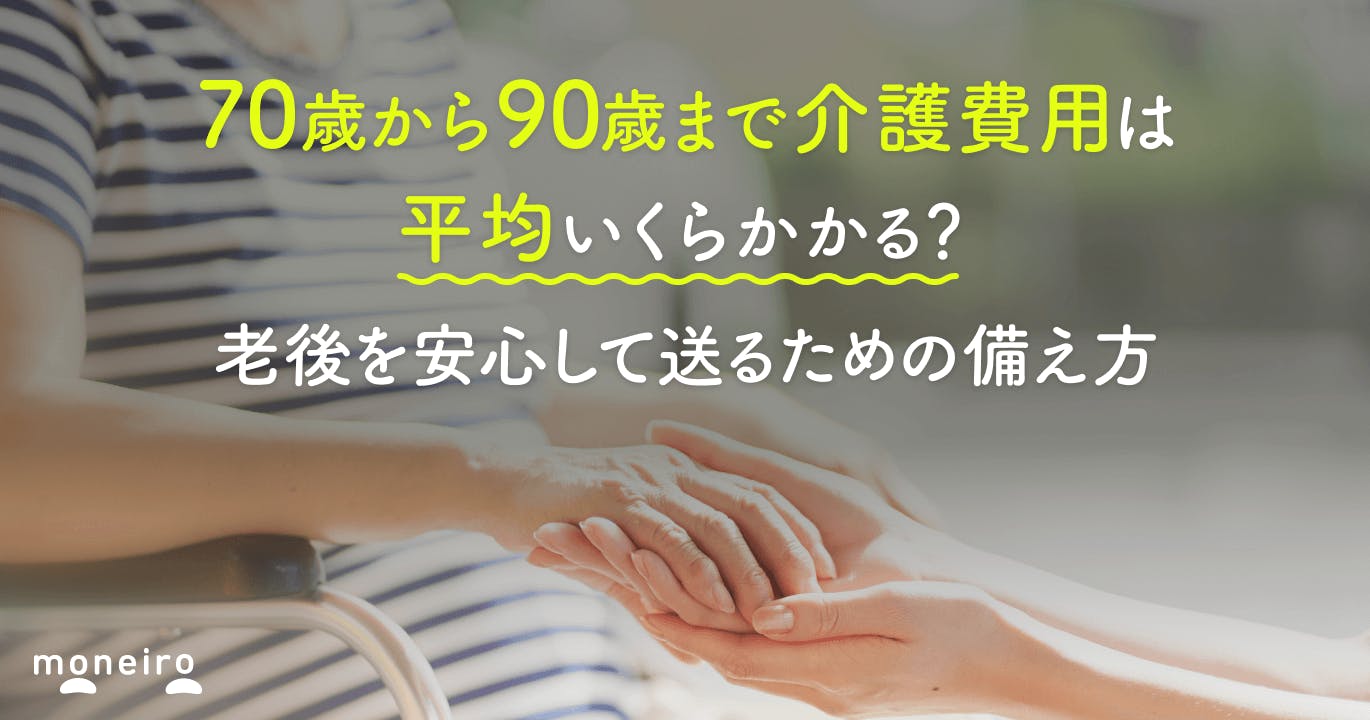
親を扶養に入れるデメリットは?専門家が悩んだ時の判断ポイント・条件・注意点を解説
»現在の貯蓄で老後は安心できる?無料診断
「親を扶養に入れるデメリットはある?」と親を自身の扶養に入れるか悩んでいる人も少なくありません。
親を扶養に入れると、税金や社会保険料の負担を軽減できる可能性があります。一方で、「別居していても生計を一にしているといえる?」「扶養に入れると介護サービスの自己負担が増えるって本当?」など、判断が難しい場合があります。
本記事では、税法上と社会保険上の扶養の違い、控除額や保険料の変化、収入制限の具体例などを専門家がわかりやすく解説します。
(税金関連 監修:中川 美佐子|税理士)
※本記事の社会保険関連の内容は令和7年の改正内容を反映しており、税関連の内容は令和6年以前の取り扱いになります
※令和7年分以後は、所得税の基礎控除の見直しが行われます
(参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁)
(参考:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省)
- 親を扶養に入れるメリット・デメリット(社会保険上の場合)は「社会保険料の負担が軽減される」「介護保険料や医療費、介護費用の負担が増える可能性がある」
- 親を扶養に入れるメリット・デメリット(税法上の場合)は「扶養控除が使える」「ケースによっては扶養控除が使えない」
現在の収入で資産形成するには?
これから先、お金の不安なく暮らすために、将来に必要なお金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
「親を扶養に入れる」とは?
「親を扶養に入れる」とは、自分の親の生活費を主に負担し、その事実によって税金や社会保険料の面で優遇を受けることを指します。
この扶養には、大きく分けて「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があります。
社会保険上の扶養|保険料負担が減る条件
社会保険上の扶養とは、主に会社員や公務員が加入する健康保険において、被扶養者(親)が自身で健康保険料を支払うことなく、扶養者の健康保険に加入できる仕組みです。
年金については、国民年金の第3号被保険者(配偶者のみで親は対象外)となります。
保険料負担の軽減: 親が国民健康保険に加入している場合、社会保険の扶養に入れることで、親自身が国民健康保険料を支払う必要がなくなります。
【主な条件】
- 親の年収が原則として180万円未満であること(親が60歳未満の場合は130万円未満)、かつ、扶養者の年収の2分の1未満であること
75歳以上の親の場合は後期高齢者医療制度に移行するため、社会保険の扶養に入れることはできません。
※今後年収106万円未満の短時間労働者は企業規模に関係なく社会保険の加入対象となります。改正法は、公布から3年以内(2027年頃まで)に施行される予定です
(参考:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省)
税法上の扶養|対象条件と控除の仕組み
税法上の扶養とは、所得税や住民税の計算において、扶養親族がいる場合に受けられる「扶養控除」のことを指します。これにより、納税者(子)の課税所得が減り、税金が安くなります。
扶養親族1人につき一定額の所得控除が適用されます。
【主な条件】(令和6年分以前)
- 親の年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 扶養者と「生計を一にしている」こと(同居していなくても認められる場合あり)
- 青色申告や白色申告の事業専従者ではないこと
など
※本記事の税関連の内容は令和6年以前の取り扱いになります
※令和7年分以後は、所得税の基礎控除の見直しが行われます
(参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁)
社会保険上と税法上の扶養者は別でも問題ない
社会保険上の扶養者と税法上の扶養者は、必ずしも同じである必要はありません。
例えば、夫婦で共働きの場合、夫の社会保険の扶養に親が入っていても、税法上の扶養は所得の高い妻が適用するといった選択が可能です。
親を扶養に入れるメリット・デメリット|社会保険上の場合
デメリット…介護保険料や医療費、介護費用の負担が増える可能性がある
親を社会保険上の扶養に入れることができれば、親自身が国民健康保険料を支払う必要がなくなります。親の家計から支出される保険料がなくなり、世帯全体としての健康保険料負担が軽減されます。
特に、親の年金収入が一定額以上で国民健康保険料が高額になっている場合には、大きなメリットとなります。
一方、親を扶養に入れることで、健康保険料が増えることはありませんが、親が高齢の場合、医療費や介護費用の負担が増える可能性があります。
高額療養費制度の自己負担限度額や介護サービスの自己負担額は世帯年収によって異なるため、親と同一世帯にして扶養に入れた場合、医療費や介護費用が増えるケースがあるためです。
ケース別の扶養可否|社会保険上の場合
社会保険の扶養に親を入れるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
収入がある場合
まず、親の年収が原則として180万円未満であること(60歳未満の場合は130万円未満)、さらに自身の年収の2分の1未満であることが求められます。
年金やパート収入については、支給額の「額面」が基準額を下回っているかどうかで判断されます。
なお、親が75歳以上になると後期高齢者医療制度へ移行するため、社会保険の扶養に入れることはできません。
※今後年収106万円未満の短時間労働者は企業規模に関係なく社会保険の加入対象となります。改正法は、公布から3年以内(2027年頃まで)に施行される予定です
親が別居している場合
社会保険上の扶養で別居の場合は仕送りの事実が必要となります。
年間の仕送り額が親の年収以上であること、かつ、親の年収が130万円未満であなたの年収の半分未満であることなど、より厳格な基準が設けられています。
親を扶養に入れるメリット・デメリット|税法上の場合
デメリット…ケースによっては扶養控除が使えない
親を税法上の扶養に入れることで、納税者の所得税と住民税の負担が軽減されます。所得控除額は、親の年齢などに応じて異なります。
例えば70歳以上の親であれば、所得税で一律48万円(同居老親等は58万円)の扶養控除が適用され、税負担を大きく減らすことができます。
所得税率が高い人ほど節税効果が高まります。
一方、親に年金収入やパート収入がある場合、収入額が税法上の扶養の所得制限(合計所得金額48万円以下)を超えてしまうと、扶養控除は利用できません。
ケース別の扶養可否|税法上の場合
税法上の扶養に入れられるかどうかは、年間の所得額や生計を一にしているかどうかといった条件によって判断されます。
ケース別に税法上の扶養可否について見ていきましょう。
※以下の扶養可否の内容は令和6年以前の取り扱いになります
※令和7年分以後は、所得税の基礎控除の見直しが行われます
(参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁)
収入がある場合
同居している親の年間合計所得金額が48万円以下であれば、税法上の扶養に入れることができます。
年金収入がある場合
公的年金等収入は「公的年金等に係る雑所得」として扱われます。この雑所得は、年金収入(額面)から「公的年金等控除額」を差し引いて計算されます。
例えば、65歳以上の親の場合、年金収入が158万円以下であれば、公的年金等控除額(一律110万円)を差し引くと合計所得金額が48万円以下で扶養の対象になります。
パート収入がある場合
パート収入は「給与所得」として扱われます。給与収入(額面)から「給与所得控除額」(最低55万円)を差し引いた金額が給与所得となります。
この給与所得が48万円以下であれば扶養に入れます。
例えば、給与収入が103万円以下であれば、給与所得は48万円となるため、扶養の対象になります。
年金とパート収入がある場合
年金による雑所得とパート収入による給与所得を合算した「合計所得金額」が48万円以下であれば、税法上の扶養に入れることができます。
親が別居している場合
税法上の扶養の場合、別居の場合でも、親の収入以上の生活費等の仕送りをし、その金銭で親が生活を維持しているのであれば、扶養に入れることができます。
扶養の事実を証明するために、銀行の送金記録などが必要になります。
親を扶養に入れるか迷ったら|判断のポイント
親を扶養に入れるかどうか迷った際の判断ポイントは、メリット・デメリット、そして金銭以外の要素を総合的に考えることです。
扶養控除・保険料・医療費のトータルで比較
- 節税額:親を扶養に入れた場合の所得税・住民税の軽減額を試算する
- 親の保険料負担:親の国民健康保険料がどれだけ安くなるかを確認する
- 医療費・介護費の支出:親の健康状態や介護の有無を考慮し、将来的な医療費・介護費の負担を予測する
金銭以外の「見えない負担」を考慮する
同居する場合のプライバシー、家事分担、生活習慣の違いなどを考慮する必要があります。
また、介護が必要になった場合の時間的・精神的な負担、介護サービス利用の可否など、介護の現実的な負担についても考えましょう。
さらに、親の扶養に関して、兄弟姉妹間での協力体制や不公平感が生じないかを確認することも大切です。
親自身の状況と希望を確認
親の年収が扶養の要件を満たしているか、また要件を満たしていない場合の税負担を確認しましょう。
また、親自身が扶養に入りたいと考えているか、あるいは自立した生活を望んでいるのかなど、親の気持ちを尊重することも必要です。
判断に迷った時は専門家に相談する
税金や社会保険の扶養は、個人の状況や家族構成によって計算が複雑になります。
迷った場合は、税理士・社会保険労務士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、具体的なシミュレーションを行うことで、最適な選択ができます。
まとめ
親を扶養に入れることで、扶養者の税負担が軽くなり、親の保険料負担も減らせるメリットがあります。
税法上と社会保険上では扶養の条件が異なり、親に年金やパート収入があっても扶養に入れられるケースがあります。別居している場合でも、条件を満たせば扶養に入れる可能性があります。
ただし、親の収入制限や、将来的な医療・介護費の増加、同居や介護に伴う精神的・時間的な負担も視野に入れておく必要があります。
最終的な判断は、金銭的・非金銭的な側面を含めて家族で話し合い、親の希望や状況も踏まえて行います。迷った時は、専門家に相談してシミュレーションを受けると安心です。
現在の収入で資産形成するには?
これから先、お金の不安なく暮らすために、将来に必要なお金を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶2025年に変わるお金の制度セミナー:お金に関する最新の制度をやさしく解説
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
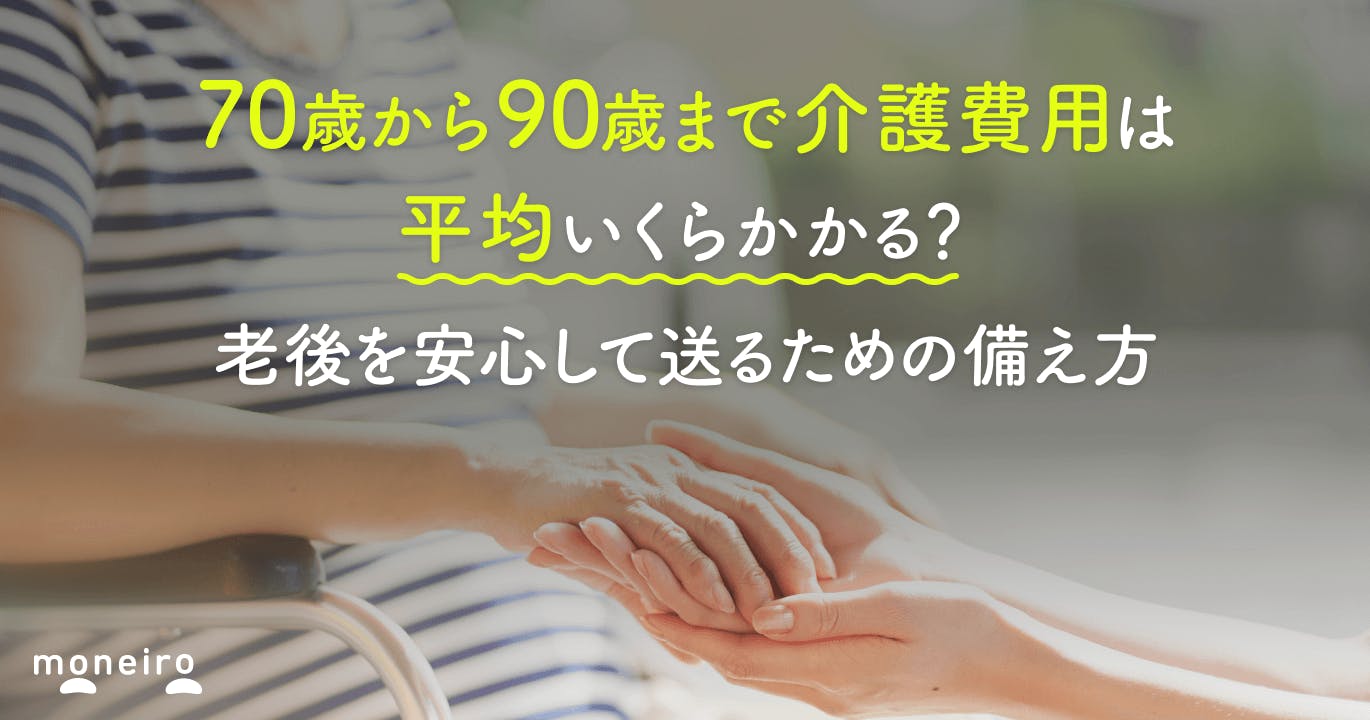

定期預金より堅実なお金の増やし方をプロが厳選!賢くお金を増やす方法を徹底解説

社会保険と国民健康保険、どっちが得?違いとケース別の選択肢を専門家が徹底解説
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。