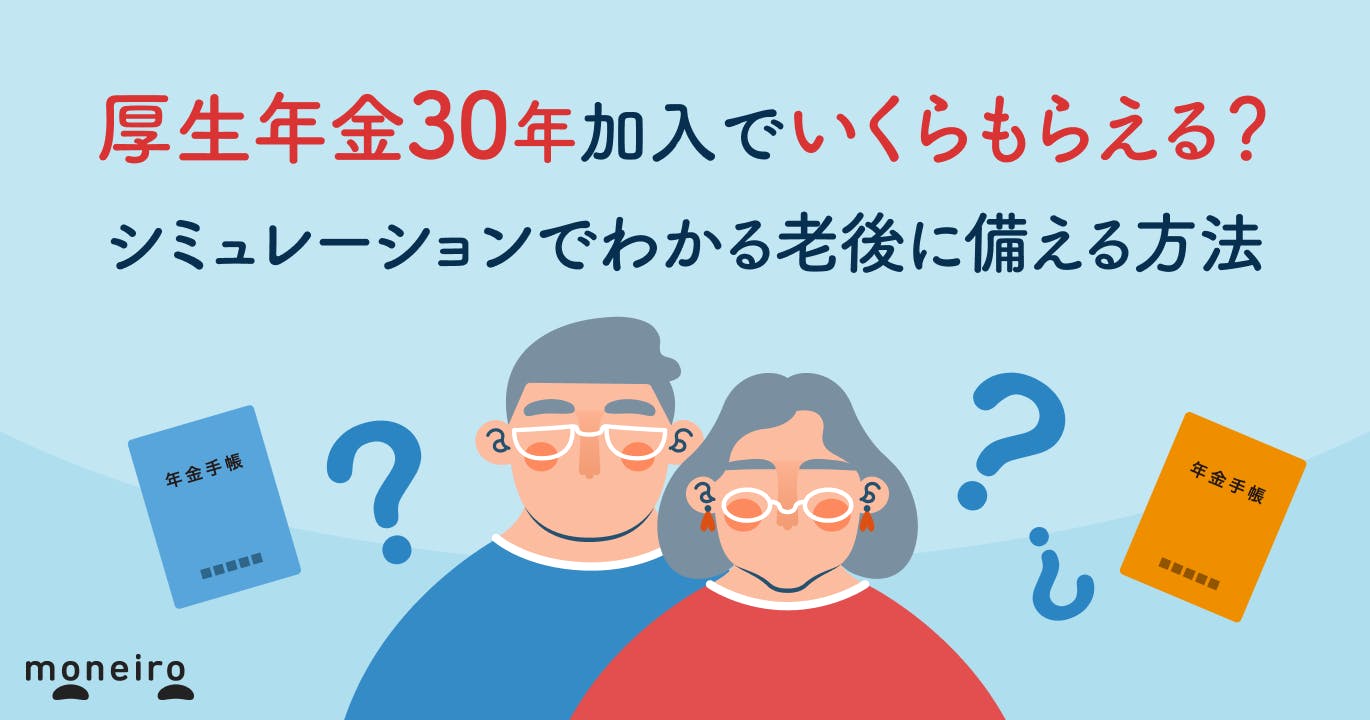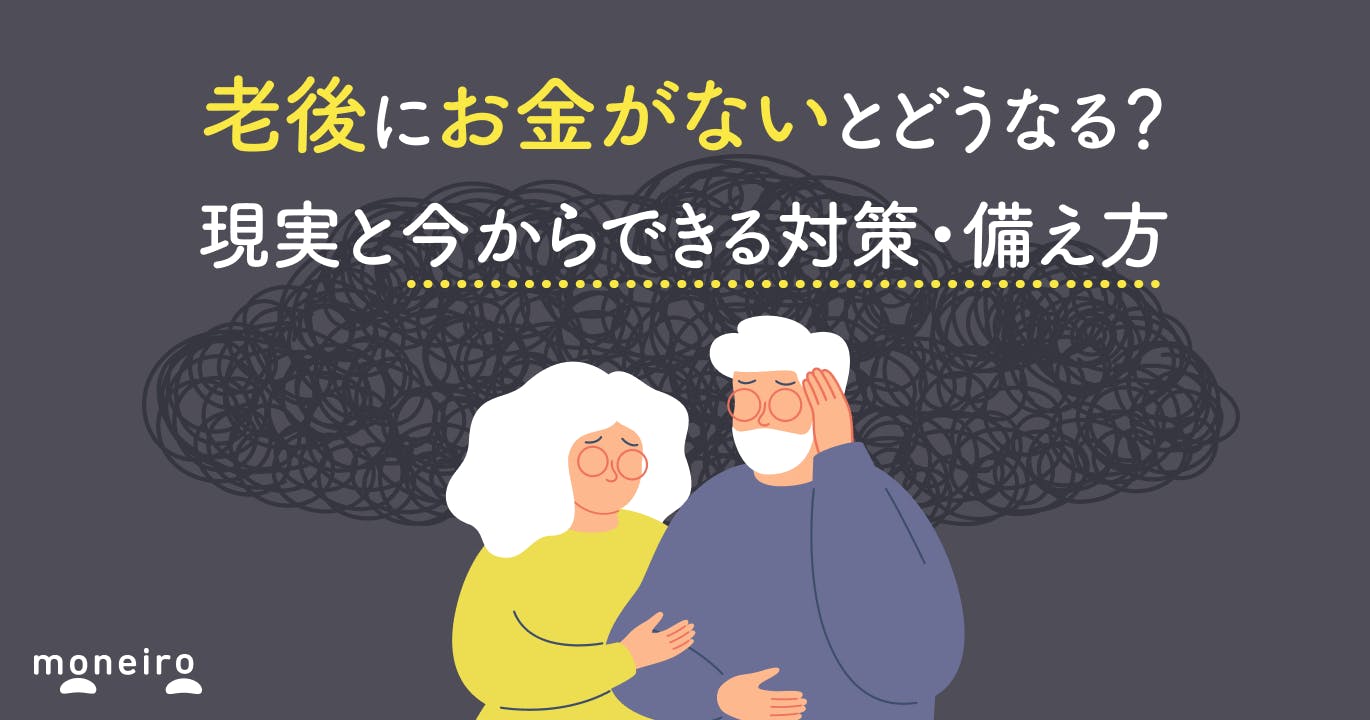
厚生年金30年加入でいくらもらえる?シミュレーションでわかる老後に備える方法
»将来年金だけで暮らせる?あなたの老後資金をいますぐ無料診断
「厚生年金を30年払ったら、老後はいくらもらえる?」定年や再雇用を見据えて、実際の受給額を把握しておきたい人は多いでしょう。厚生年金は「加入期間」と「平均年収」によって金額が決まります。30年の加入であれば受給資格は十分ありますが、生活費をすべてまかなうには不足するケースも多く、対策が必要です。
本記事では、厚生年金30年加入時の平均受給額を、年収別・世帯別モデルケースでわかりやすく解説します。さらに、足りない分を補うための具体策(iDeCo・NISA・繰下げ受給など)を専門家視点で紹介します。
- 厚生年金30年加入時の年収別シミュレーション
- 国民年金のみの場合との受給額の比較
- 将来の年金を着実に増やすための5つの方法
将来の年金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
厚生年金30年でいくらもらえる?平均受給額の目安
厚生年金に30年加入した場合の受給額は、現役時代の平均年収によって大きく変動します。
日本の公的年金は、全国民が加入する「国民年金」を1階部分、会社員や公務員が加入する「厚生年金」を2階部分とする2階建て構造です。
厚生年金の受給額は、収入に応じて保険料を納める「報酬比例」の仕組みになっているため、収入が高いほど将来の年金額も増えます。
厚生年金の仕組み
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する国民年金(基礎年金)を1階部分とし、その上に会社員や公務員が加入する厚生年金が2階部分として上乗せされる構造になっています。
これにより、厚生年金加入者は国民年金のみの加入者に比べて、より手厚い保障を受けることができます。
また、厚生年金保険料は、毎月の給与や賞与から天引きされる形で納付します。従業員と会社が半分ずつ負担する「労使折半」という仕組みが採用されているのが大きな特徴です。個人で全額を負担する国民年金保険料とは異なり、負担が軽減されています。
厚生年金の受給額は、現役時代の収入と加入期間に応じて決まる「報酬比例」という考え方に基づいています。具体的には、毎月の給与を一定の範囲で区切った「標準報酬月額」と賞与を基に保険料が計算され、その納付実績が将来の年金額に反映されます。
収入が高く、加入期間が長いほど、老後に受け取れる年金額も多くなる仕組みです。
厚生年金30年の受給額シミュレーション(年収別)
厚生年金に30年間(360ヶ月)加入した場合の年金受給額を、現役時代の平均月収別にシミュレーションしてみましょう。
年金額は、全国民共通の「老齢基礎年金」と、収入に応じて変動する「老齢厚生年金」の合計で決まります。
老齢厚生年金の概算額は、以下の計算式で求められます。
- 老齢厚生年金額(年額) = 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
この計算式と、令和7年度の老齢基礎年金の満額(年額83万1700円、月額6万9308円)を基に、年収別の受給額目安を算出しました。
平均月収30万円(年収360万円)の場合、老齢厚生年金は年額約59.2万円(月額約4.9万円)です。これに老齢基礎年金を加えると、総受給額は月額約11.8万円となります。
平均月収40万円(年収480万円)の場合、老齢厚生年金は年額約78.9万円(月額約6.6万円)です。老齢基礎年金と合わせると、総受給額は月額約13.5万円となります。
平均月収50万円(年収600万円)の場合、老齢厚生年金は年額約98.7万円(月額約8.2万円)です。老齢基礎年金と合算した総受給額は月額約15.1万円となります。
これらの金額はあくまで概算であり、賞与の額や加入時期によって変動します。
男女差・世帯差による違い
年金の受給額は、性別や世帯構成によっても差が見られます。これは、現役時代の働き方や収入の違いが年金額に反映されるためです。
「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局」によると、厚生年金受給額(受給権者)の平均月額は男性が約16.7万円であるのに対し、女性は約10.7万円となっています。
この差は、男性の方が平均勤続年数は長く、また平均収入が高い傾向にあることが主な要因と考えられます。出産や育児によるキャリアの中断が、女性の年金額に影響を与えている現状がうかがえます。
また、世帯単位で見ると、その差はさらに明確になります。
- 会社員の夫と専業主婦の妻の世帯
- 夫の厚生年金(国民年金含む)と妻の国民年金を合わせて、月額約23万円程度がモデルケースとなります
- 共働きの夫婦世帯
- 夫婦それぞれが厚生年金を受給するため、世帯の合計受給額は月額約27万円〜28万円程度となり、片働き世帯よりも手厚い保障が期待できます
このように、個人の働き方だけでなく、世帯全体のキャリアプランが老後の収入を大きく左右することを理解しておくことが重要です。
最新データ(令和6年度基準)で見る平均受給額
「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局」のデータから、平均的な受給額を見ていきましょう。
まず、自営業者や専業主婦(夫)などが受け取る国民年金(老齢基礎年金)の平均月額は、約5.8万円です。一方、会社員や公務員が受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)の平均月額は、約14.7万円となっています。国民年金の平均額と比較すると、2階建て部分である厚生年金があることで、受給額が大きく上乗せされていることがわかります。
ただし、これらの数値はあくまで全体の平均値であり、特に厚生年金は現役時代の収入や勤続年数によって個人差があります。
厚生年金20年・40年加入との違い
厚生年金の受給額は、加入期間が長くなるほど着実に増えていきます。これは、受給額の計算基礎となる「報酬比例部分」が加入月数に比例するためです。
30年加入の場合と比較して、20年や40年ではどの程度の差が生まれるのかを理解しておきましょう。
具体的には、厚生年金への加入期間が1年延びるごとに、将来の年金額が年単位で数万円増加するイメージです。そのため、1年でも長く厚生年金に加入して働くことが、老後の収入を安定させる上で非常に有効な手段となります。
次の項目では、具体的な年収例を基に、加入期間による年金額の増え方を詳しく見ていきます。
加入期間による年金額の増え方
厚生年金の受給額は加入期間に応じて増加します。具体的にどのくらい増えるのか、平均年収500万円(平均標準報酬額41.7万円)のケースで比較してみましょう。なお、厚生年金に加入していない期間は、国民年金にも加入していないと仮定します。
- 加入期間20年(240ヶ月)の場合
- 老齢厚生年金は約55万円、老齢基礎年金(20年分)は約42万円となり、合計で年間約97万円(月額約8.1万円)です。
- 加入期間30年(360ヶ月)の場合
- 老齢厚生年金は約82万円、老齢基礎年金(30年分)は約62万円となり、合計で年間約144万円(月額約12万円)です。
- 加入期間40年(480ヶ月)の場合
- 老齢厚生年金は約110万円、老齢基礎年金は満額の約83万円となり、合計で年間約193万円(月額約16万円)です。
この例では、加入期間が10年増えるごとに、年間の受給額が40万円以上増えていることがわかります。
1年でも長く加入することが、将来の年金額を増やす上でいかに重要かが理解できるでしょう。
なお、厚生年金に加入していない期間は、国民年金保険料を払うことで、老齢基礎年金を満額に近付けることができます。
将来の年金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
厚生年金30年で生活できる?老後の支出と比較
厚生年金に30年加入した場合の受給額で、老後の生活をまかなえるのでしょうか。結論から言うと、年金収入だけで「ゆとりある生活」を送ることは難しく、多くの場合で自助努力が必要になります。
「2025(令和7)年度 生活保障に関する調査|生命保険文化センター」よれば、夫婦2人でゆとりある老後生活を送るために必要とされる費用は月額平均で約39.1万円です。これに対し、厚生年金30年加入の平均的な受給額では不足が生じる可能性が高いでしょう。
さらに、この平均的な支出には、急な病気や怪我による医療費、住宅のリフォーム費用、介護費用などは含まれていません。こうした想定外の出費も考慮すると、年金以外の収入源や資産の取り崩しが必要になることが現実的です。
単身・夫婦それぞれの老後生活費の目安
老後の生活にどれくらいの費用がかかるかは、世帯構成やライフスタイルによって大きく異なります。公的な調査データを参考に、単身世帯と夫婦世帯それぞれの生活費の目安を見ていきましょう。
「家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における平均的な消費支出は月額約25.7万円です。これはあくまで平均であり、食費や住居費、交際費など、日々の暮らしを維持するための基本的な費用と捉えることができます。
単身世帯の場合、支出は夫婦世帯より少なくなりますが、基本的な生活費に加えて、将来の医療や介護への備えは同様に必要です。
自身の希望する老後生活を基に、「最低限の生活費」と「ゆとりある生活費」の両方を想定しておくことが、具体的な資金計画を立てる上で重要になります。
年金受給額との差額はいくら?
老後の生活費の目安がわかったところで、年金受給額との差額を具体的に計算してみましょう。
ここでは、平均月収40万円で30年間厚生年金に加入した夫と、専業主婦の妻という世帯をモデルケースとします。なお、夫が厚生年金に加入していない期間は国民年金保険料を全額払っているものと仮定します。
この場合、夫の年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が月額約13.5万円、妻の老齢基礎年金が満額で約6.9万円となり、世帯の合計年金受給額は約20.4万円です。
この収入に対し、夫婦2人の平均的な生活費である約25.7万円と比較すると、毎月約5.3万円の赤字となります。年間では64万円、30年間では約1900万円の不足です。
さらに、「ゆとりある老後生活」を目指す場合、必要な生活費は約39.1万円です。この場合、年金収入との差額は毎月約19万円にもなり、年間で228万円、30年間では6840万円もの資金が別途必要になる計算です。
このように、年金だけでは最低限の生活も赤字になる可能性があり、ゆとりある生活のためには大きな不足額が生じることがわかります。この差額をどう補うか、早期に計画を立てることが重要です。
医療・介護など“想定外の支出”にも注意
老後の資金計画を立てる際、日々の生活費だけでなく、突発的に発生する大きな支出も考慮に入れる必要があります。特に、年齢を重ねるにつれてリスクが高まる医療費や介護費用は、家計に大きな影響を与える可能性があります。
平均的な生活費のデータには、こうした特別な支出は通常含まれていません。例えば、先進医療を受ける際の技術料や、長期的な介護が必要になった場合の施設利用料、自宅のリフォーム費用などは、数百万円単位のまとまった資金が必要になることもあります。
老人ホームや介護サービスを利用する場合、その費用は公的介護保険だけではカバーしきれない部分が多く、自己負担額は決して少なくありません。
これらの「想定外の支出」に備えるためには、年金収入や基本的な生活費とは別に、ある程度の予備資金を確保しておくことが、安心して老後を過ごすための重要な鍵となります。
年金+貯蓄+運用の3本柱で備えるのが理想
公的年金だけでは老後資金が不足する可能性が高い現代において、安定した老後を迎えるためには、複数の収入源を組み合わせることが理想的です。
具体的には、「公的年金」「貯蓄」「資産運用」の3本柱で備えるという考え方が重要になります。
まず、老後の生活の土台となるのが公的年金です。これは終身で受け取れる安定した収入源であり、資金計画の基本となります。
次に、現役時代からコツコツと準備する貯蓄です。定期預金などを活用し、急な出費や計画的な支出に備えるための資金を確保します。元本が保証されているため、安全資産として重要な役割を果たします。
そして、インフレに負けない資産を育てるための資産運用が3本目の柱です。iDeCo(個人型確定拠出年金)、NISA(少額投資非課税制度)といった税制優遇制度を活用することで、効率的に資産を増やすことが期待できます。
特にiDeCoは、掛金が所得控除の対象になるなど、老後資金作りに特化したメリットがあります。
これら3つをバランス良く組み合わせることで、公的年金の不足分を補い、より豊かで安心な老後生活を実現することが可能になります。
厚生年金30年と国民年金だけの人ではどれくらい違う?
会社員や公務員として厚生年金に30年加入した人と、自営業者などで国民年金のみに加入してきた人とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生まれます。結論として、厚生年金加入者の方が月額にして6~8万円程度多く受け取れるのが一般的です。
この差額の理由は、日本の年金制度が2階建て構造になっていることにあります。国民年金のみの加入者は1階部分の「老齢基礎年金」しか受け取れませんが、厚生年金加入者はそれに加えて、現役時代の収入に応じた2階部分の「老齢厚生年金」が上乗せされます。
この「老齢厚生年金」が、老後の収入に大きな違いをもたらします。この差は、特に夫婦世帯で考えると、老後の生活の安定度に直接影響するため、自身の加入状況を正しく理解しておくことが重要です。
国民年金のみの場合の平均月額
自営業者やフリーランス、または扶養に入っている配偶者など、国民年金のみに加入している場合、老後に受け取れる年金は「老齢基礎年金」となります。
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金受給者の平均年金月額は約5.8万円です。
この金額は、令和7年度の満額である月額約6.9万円よりも低い水準です。平均額が満額に達しない主な理由としては、未納や、経済的な理由による保険料の免除・猶予制度の利用などが挙げられます。これらの期間があると、その分だけ将来の受給額が減額されるため、平均値が押し下げられるのです。
月額5.8万円という金額は、老後の生活費を単独でまかなうには厳しい水準です。そのため、国民年金のみに頼る場合は、現役時代から計画的に他の資産形成手段を準備しておく必要性が非常に高いと言えます。
厚生年金加入者は“報酬比例分”で月6〜8万円多くもらえる
厚生年金加入者と国民年金のみの加入者との間には、受給額に明確な差が存在します。この大きな差を生み出しているのが、厚生年金の2階部分にあたる「報酬比例部分」です。
報酬比例部分とは、現役時代の給与や賞与の額、そして加入期間に応じて年金額が計算される仕組みを指します。つまり、収入が高く、長く働くほど、この上乗せ部分が大きくなります。
国民年金が加入期間のみで金額が決まる定額制であるのに対し、厚生年金にはこの報酬比例部分があるため、30年間の加入でも月々6万円から8万円程度の差が生まれるのです。
この差額は老後の生活水準に直結するため、非常に重要なポイントと言えるでしょう。
夫婦で考えると世帯受給額は月25万円前後に
老後の生活を考える上では、個人だけでなく世帯単位での収入を見積もることが重要です。特に厚生年金加入者がいる世帯では、その恩恵が大きくなります。
一般的な厚生年金加入者のいる世帯(※厚生年金加入30年とは限らない)で見てみましょう。
例えば、夫が平均的な収入の会社員で、妻が専業主婦(第3号被保険者)だった世帯の場合、夫の老齢厚生年金(老齢基礎年金を含む)と妻の老齢基礎年金を合わせると、世帯の年金収入は月額で約22万円~約23万円が一つの目安となります。
一方、夫婦ともに会社員として厚生年金に加入していた共働き世帯では、それぞれが老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。この場合、世帯の合計年金額はさらに増え、月額で約28万円を超えることも珍しくありません。
このように、世帯に厚生年金の受給者が一人いるか二人いるかで、老後の収入基盤は大きく変わります。国民年金のみの自営業世帯と比較すると、その差は歴然です。世帯全体での働き方を考えることが、将来の年金額を左右する重要な要素となります。
年金を増やす・減らさないための5つの方法
将来受け取る年金額は、現役時代の働き方や制度の活用次第で増やすことが可能です。また、意図せず減らしてしまう事態を避けるための知識も重要です。
ご自身のライフプランや経済状況に合わせて、最適な選択をすることが、より豊かな老後生活につながります。
① 定年後も働き続けて加入期間を延ばす
老後の年金額を増やす最も直接的で効果的な方法の一つが、60歳の定年後も働き続けることです。特に厚生年金に加入して働くことで、複数のメリットが期待できます。
厚生年金は最長で70歳まで加入することが可能です。加入期間が1年延びるだけでも、将来の老齢厚生年金額(報酬比例部分)は着実に増加します。例えば、年収300万円で10年間(60歳から70歳まで)働き続けると、年金額が年間約16万円増えるという試算もあります。
また、働くことで安定した勤労収入を得られるため、年金の受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を選択しやすくなるという利点もあります。さらに、社会とのつながりを持ち続けることは、健康維持や生きがいの面でも大きなプラスとなるでしょう。
高年齢者雇用安定法の改正により、企業には70歳までの就業機会確保が努力義務となっており、高齢者が働きやすい環境が整いつつあります。
② 任意加入・付加年金で空白期間を埋める
国民年金の保険料納付期間が40年(480ヶ月)に満たない場合、60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入することで、将来の老齢基礎年金額を増やすことができます。学生時代の未納期間や、転職などで保険料を納めていなかった期間がある方にとって有効な手段です。
任意加入によって納付月数を1年増やすごとに、老齢基礎年金が年額で約2万円増加します。これにより、満額に近づけることが可能です。ただし、老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は任意加入できません。
さらに、国民年金第1号被保険者の方は、通常の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めることで、将来の年金額を上乗せできる「付加年金」制度も利用できます。
付加年金は「200円 × 付加保険料納付月数」で計算された金額が毎年加算されるため、2年以上受給すれば支払った保険料以上のリターンが期待できる非常にお得な制度です。
③ iDeCo・企業型DCで自助年金を積み立てる
公的年金だけでは不安な場合、私的年金を活用して「3階部分」を自分で構築することが重要です。その代表的な制度がiDeCo(個人型確定拠出年金)と企業型DC(企業型確定拠出年金)です。
iDeCoは、個人が掛金を拠出し、自分で選んだ金融商品で運用して老後資金を形成する制度です。最大のメリットは税制優遇にあり、掛金が全額所得控除の対象となるため、毎年の所得税や住民税が軽減されます。さらに、運用によって得られた利益も非課税となり、受け取る際にも税制上の優遇措置が受けられます。
一方、企業型DCは、企業が掛金を拠出し、従業員がその資金を運用する制度です。勤務先にこの制度があれば、iDeCoよりも有利な条件で老後資金を準備できる場合があります。
これらの制度は、公的年金に上乗せする形で自分専用の年金を作るためのツールです。老後資金の不足分を補うための自助努力として、積極的に活用を検討しましょう。
④ 繰下げ受給で年金額を最大84%アップ
年金の受給額を増やすための選択肢が「繰下げ受給」です。これは、原則65歳から受け取れる年金を、66歳以降に遅らせて受け取る制度です。
年金の受け取りを1ヶ月遅らせるごとに、受給額が0.7%ずつ増額されます。この増額率は一生涯変わることがありません。例えば、70歳まで5年間繰り下げると、受給額は42%(0.7% × 60ヶ月)も増加します。
さらに、2022年4月からは繰下げの上限年齢が75歳まで引き上げられました。もし75歳まで10年間繰り下げた場合、増額率は最大で84%(0.7% × 120ヶ月)にも達します。仮に65歳時点で月15万円もらえる人が75歳まで繰り下げると、月額約27.6万円を受け取れる計算になります。
ただし、繰り下げている期間は年金収入がなくなるため、その間の生活費を貯蓄や勤労収入でまかなう必要があります。
自身の健康状態やライフプランと照らし合わせて慎重に判断することが重要です。
⑤ 社会保険料控除・節税を活用して可処分所得を増やす
将来の年金額を直接増やすだけでなく、現役時代の手取り収入(可処分所得)を増やすことも、間接的に老後資金準備を後押しします。そのために有効なのが、社会保険料控除などの税制優遇を最大限に活用することです。
iDeCoの掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象になります。これにより、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されるため、実質的な手取り収入が増えるのです。
例えば、毎月2万円(年間24万円)をiDeCoに拠出した場合、所得税率が20%の方であれば、所得税と住民税を合わせて年間で約7.2万円もの節税効果が期待できます。この浮いたお金を貯蓄や別の投資に回すことで、老後資金の準備をさらに加速させることが可能です。
このように、将来のための積立を行いながら、現在の税負担も軽くできる制度を賢く利用することが、効率的な資産形成につながります。
自分の将来受給額を確認する方法
老後の資金計画を具体的に立てるためには、まず自分自身が将来いくら年金を受け取れるのか、その見込み額を正確に把握することが不可欠です。
日本年金機構が提供している「ねんきん定期便」と「ねんきんネット」という2つのツールを活用することで、誰でも簡単に自分の年金情報を確認できます。
定期的に自身の年金記録を確認し、ライフプランの変化に合わせて見込み額を再計算する習慣をつけることが、安心して老後を迎えるための第一歩となります。
まとめ
厚生年金に30年間加入した場合の受給額は、現役時代の平均収入に大きく左右されます。平均的な収入の方であれば、国民年金と合わせて月額12万円から15万円程度が目安となりますが、これだけでゆとりある老後生活を送るのは難しいのが実情です。
重要なのは、まず「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を活用してご自身の正確な年金見込み額を把握することです。その上で、老後の理想の生活費と比較し、不足額がどのくらいあるのかを明確にしましょう。
不足分を補うためには、60歳以降も厚生年金に加入して働く、受給開始を遅らせる「繰下げ受給」を検討する、iDeCoやNISAで計画的に資産形成を行うなど、今からできる対策が数多くあります。
ご自身の状況に合わせた具体的な老後資金計画を立てていきましょう。
»年金だけで暮らせる?不足金額と準備方法を無料診断
将来の年金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
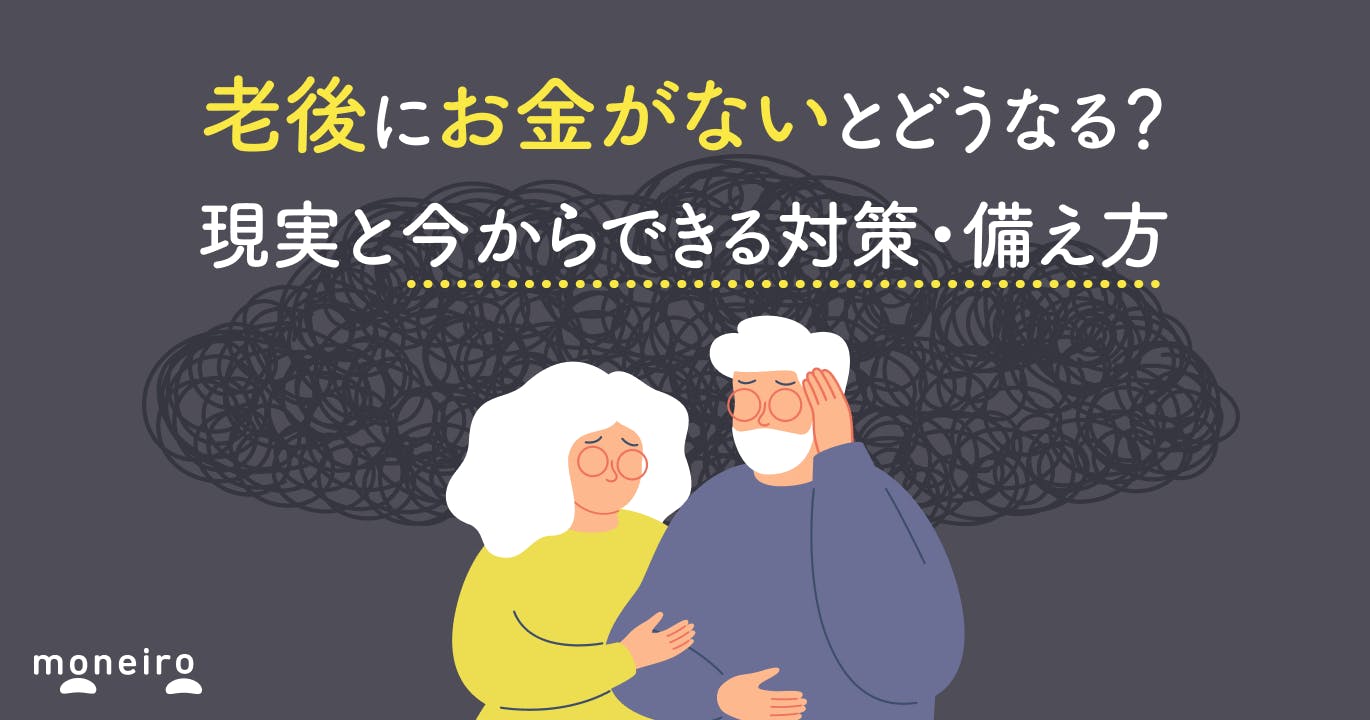
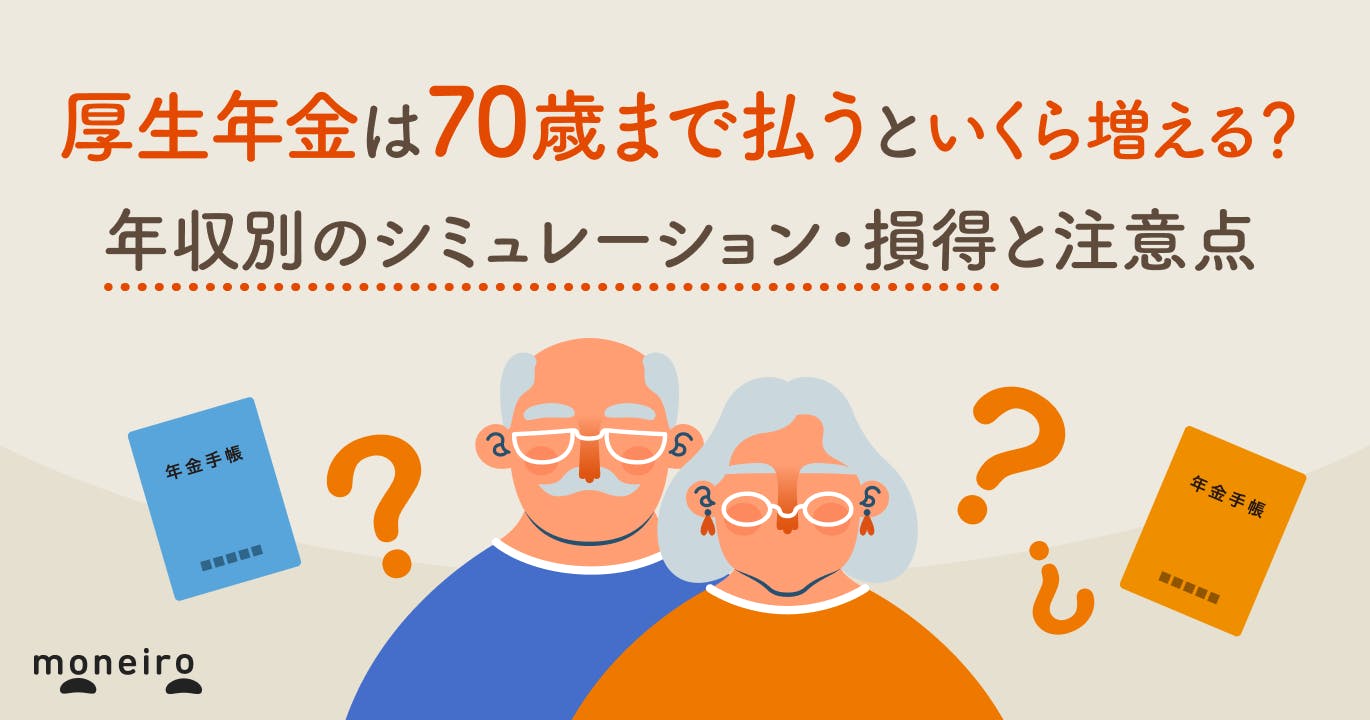
厚生年金は70歳まで払うといくら増える?年収別のシミュレーション・損得と注意点
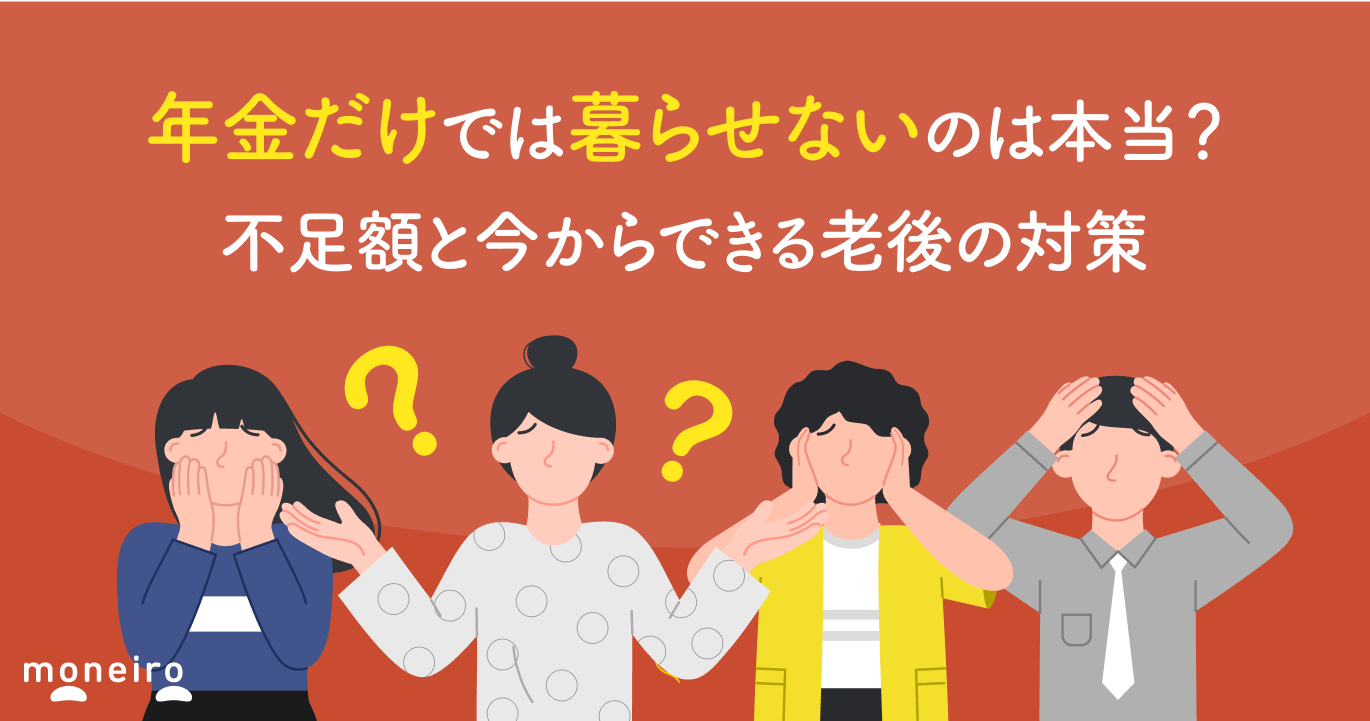
年金だけでは暮らせないのは本当?不足額と今からできる老後の対策をお金の専門家が解説
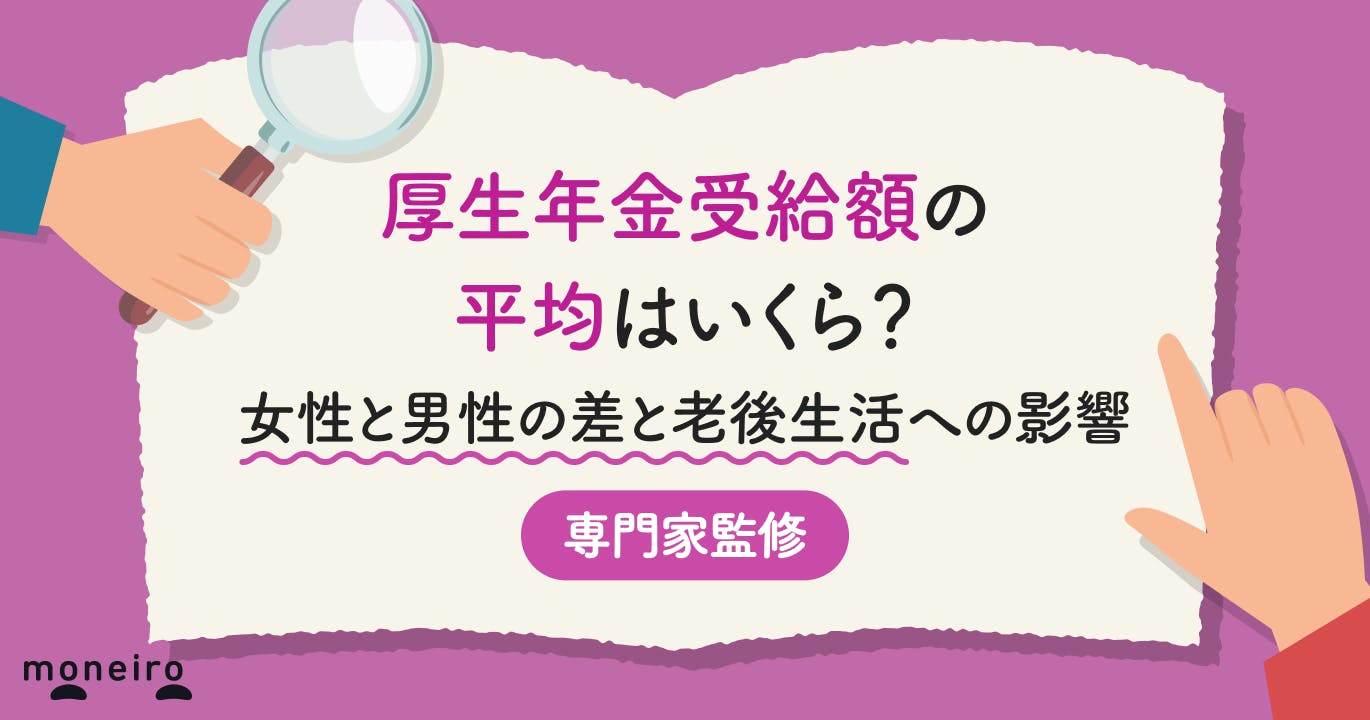
厚生年金受給額の平均はいくら?女性と男性の差と老後生活への影響を徹底解説
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。