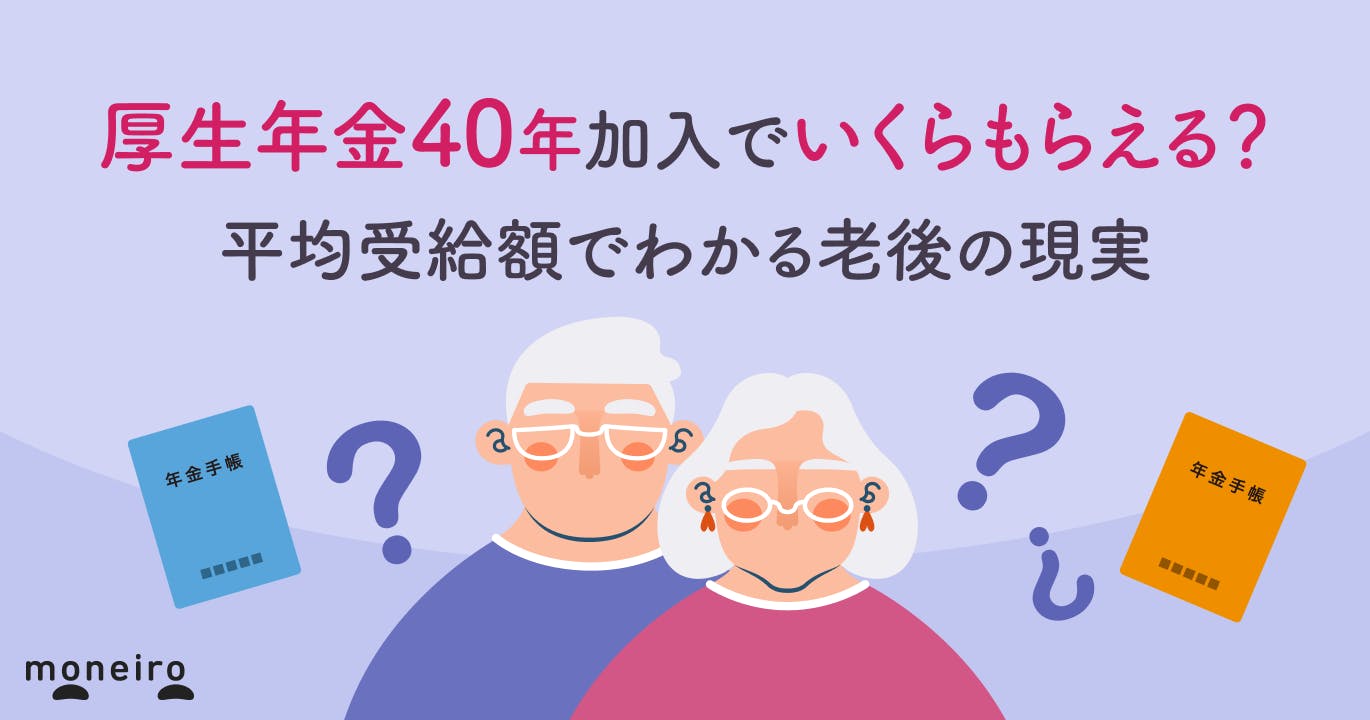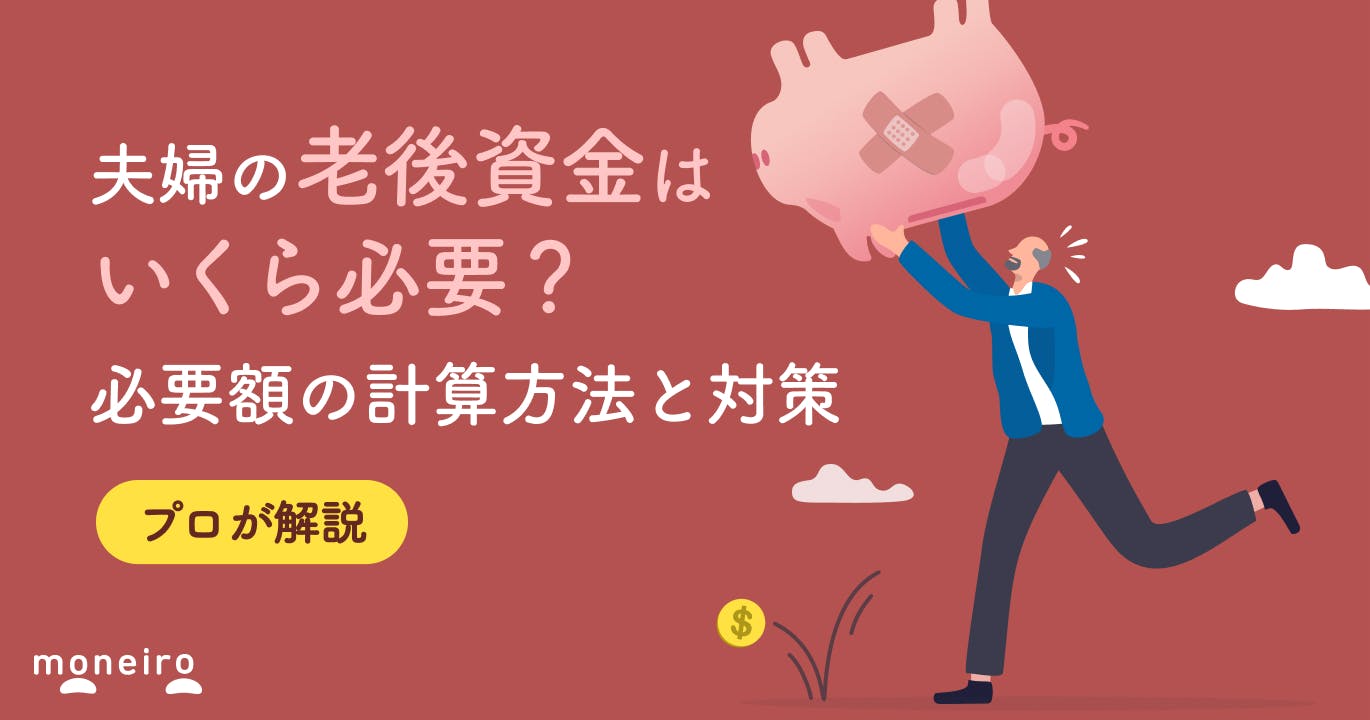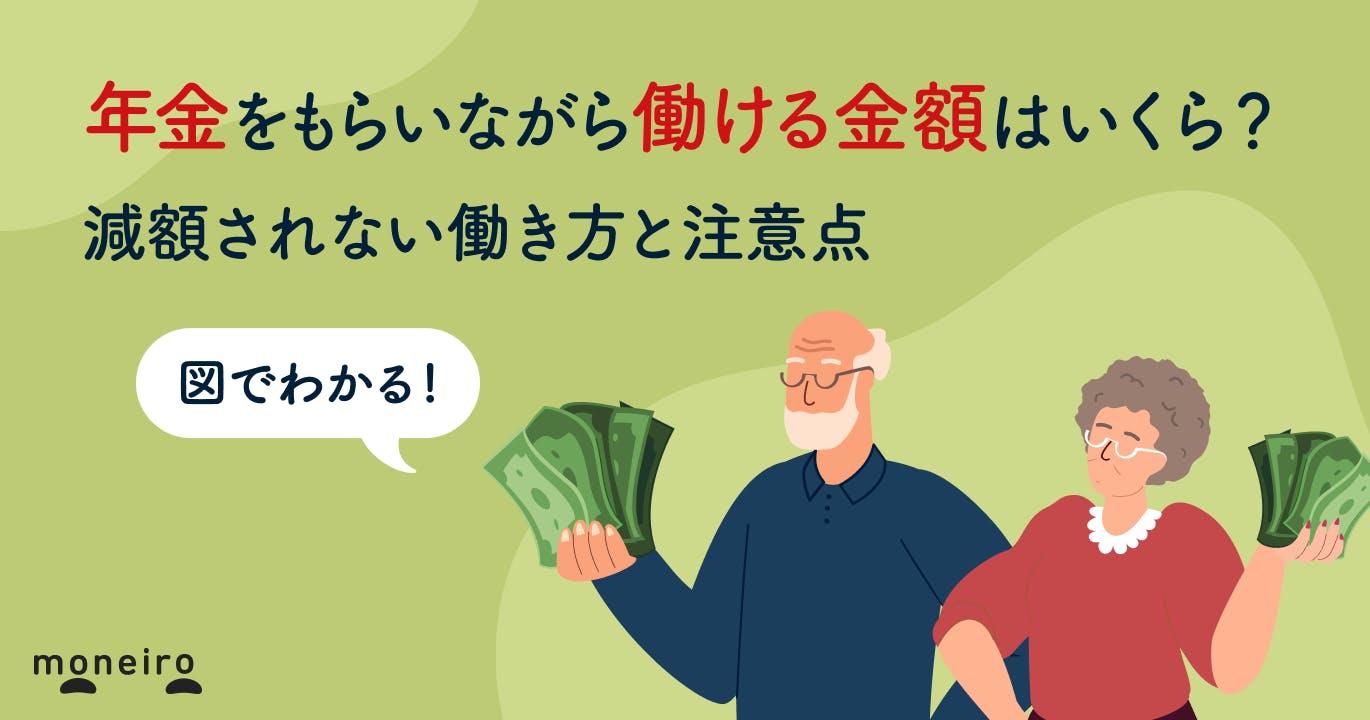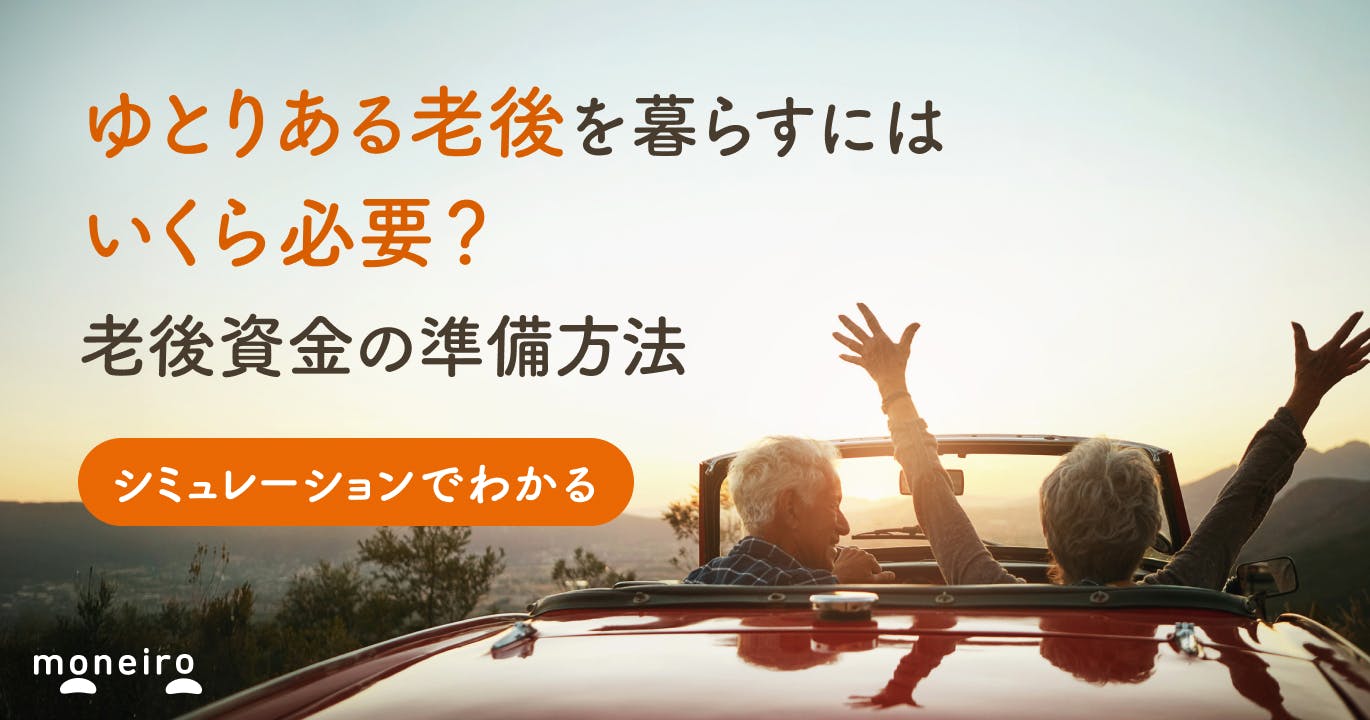厚生年金40年加入でいくらもらえる?シミュレーションと平均受給額でわかる老後の現実
»将来年金だけで暮らせる?あなたの老後資金をいますぐ無料診断
「厚生年金を40年払ったら、老後はいくらもらえる?」─定年や再雇用を迎える世代にとって、最も気になるテーマです。厚生年金は「加入期間」と「平均年収」で受給額が決まります。40年勤務すれば受給額は増えますが、それでも老後の生活費をすべてまかなえるとは限りません。
本記事では、厚生年金40年加入時の平均受給額を年収別・夫婦別にシミュレーションし、20年・30年との違いもわかりやすく比較します。さらに、足りない分を補うための現実的な方法(iDeCo・NISA・繰下げ受給など)を専門家視点でわかりやすく解説します。
- 厚生年金の加入期間(20年・30年・40年)別の受給額シミュレーション
- 老後の平均的な生活費と年金受給額の比較
- 将来の年金を増やすための4つの具体的な方法
将来の年金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
厚生年金40年でいくらもらえる?
厚生年金に40年加入した場合の受給額は、現役時代の収入によって大きく変動します。日本の公的年金は2階建て構造になっており、厚生年金加入者は国民年金に上乗せして報酬比例の年金を受け取れるため、手厚い保障が期待できます。
厚生年金は基礎年金+報酬比例の2階建て構造
日本の公的年金制度は、全国民が加入する「国民年金(老齢基礎年金)」を1階部分とし、会社員や公務員が加入する「厚生年金(老齢厚生年金)」が2階部分に乗る、2階建ての構造になっています。
このため、厚生年金の加入者(第2号被保険者)は、将来、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取ることができます。
一方、自営業者や学生など(第1号被保険者)は国民年金のみの加入となるため、受給する年金は老齢基礎年金だけです。この構造の違いが、将来の年金受給額に大きな差を生む要因となります。
厚生年金40年加入時の平均受給額
厚生労働省が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金受給者の平均年金月額は約14.7万円(※加入期間40年とは限らない)です。この金額には、1階部分である国民年金(老齢基礎年金)が含まれています。
ただし、この数値はあくまで全体の平均値です。実際の受給額は、個人の厚生年金加入期間や現役時代の平均収入(標準報酬月額・標準賞与額)によって大きく変動します。
40年間厚生年金に加入した場合でも、収入水準によって受給額は一人ひとり異なる点を理解しておくことが重要です。
男女差・職種別による受給額の違い
厚生年金の受給額には、男女間で差が見られます。「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省年金局」によると、令和5年度の平均年金月額(受権者)は男性が約16.7万円に対して、女性は約10.7万円となっています。
この差が生まれる主な理由は、現役時代の働き方の違いにあります。一般的に、男性の方が女性に比べて厚生年金の加入期間が長く、また平均収入も高い傾向にあるため、それが報酬比例部分の金額に反映され、結果として受給額の差につながっています。
職種による直接的な違いはありませんが、収入水準の高い職種ほど、将来の厚生年金受給額も高くなる傾向があります。
厚生年金20年・30年加入との違いは?加入期間で変わる受給額
厚生年金の受給額は、加入期間が長くなるほど増えるのが基本です。20年以上の加入は「加給年金」の対象となる可能性があるため、重要な節目といえます。
加入年数によって受給額がどのように変わるのかを具体的に見ていきましょう。
加入年数別の受給額シミュレーション早見表
厚生年金の受給額は、加入期間と現役時代の平均年収によって大きく変わります。以下の早見表は、20歳から60歳まで国民年金に40年加入し、老齢基礎年金を満額(約83.2万円/年)受給することを前提とした、厚生年金の加入期間と平均年収別の年金受給額の目安です。
【年収・加入期間別】年金受給額の目安(年額)
※老齢基礎年金(満額約83万1700円)と老齢厚生年金の合計額
※老齢厚生年金は「平均年収÷12×0.005481×加入月数」で概算
表からわかるように、加入期間が長くなるほど、また平均年収が高くなるほど、受給額は着実に増加します。
例えば、平均年収500万円の場合、20年加入と40年加入では年間で約55万円もの差が生まれます。
再雇用・継続雇用で働くメリットと注意点
60歳以降も再雇用や継続雇用で働き続けることには、将来の年金を増やすという大きなメリットがあります。厚生年金は70歳まで加入できるため、長く働くほど加入期間が延び、その分だけ老齢厚生年金の受給額が増加します。
例えば、年収300万円で60歳から70歳まで10年間働き続けると、老齢厚生年金が年間で約16万円増える計算になります。これは生涯にわたって受け取れるため、長期的に見ると大きな差となります。
ただし、注意点もあります。働きながら年金を受け取る場合、「在職老齢年金」という制度が適用されます。これは、給与と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止される仕組みです。
働き方や収入によっては、せっかくの年金が減額される可能性もあるため、制度をよく理解しておくことが重要です。
厚生年金40年でも足りない?老後の生活費と比較してみよう
将来の年金受給額が分かっても、その金額で安心して生活できるかは別の問題です。老後にどれくらいの生活費がかかるのかを把握し、年金収入との差額を理解することが、具体的な老後資金計画の第一歩となります。
単身・夫婦それぞれの平均生活費
老後の生活費は、ライフスタイルによって大きく異なりますが、平均的なデータを知ることは計画の参考になります。「生活保障に関する調査」/2025(令和7)年度|生命保険文化センター」によると、夫婦2人世帯が最低限の日常生活を送るために必要な費用は、月額で平均23.9万円とされています。
一方で、旅行や趣味などを楽しむ「ゆとりある老後生活」を送るためには、月額で平均39.1万円が必要という結果が出ています。単身世帯の場合は、これらの金額の6~7割程度が目安となるでしょう。
理想の老後をイメージし、どれくらいの生活費が必要になるかを考えてみることが大切です。
受給額との差を数値で比較
老後の生活費と年金受給額を比較すると、多くの場合で不足額が生じる可能性があります。例えば、夫婦2人の最低限の生活費が月23.9万円であるのに対し、厚生年金の平均受給額は約14.7万円(国民年金含む)です。
仮に夫が平均的な厚生年金(約14.7万円)、妻が国民年金のみ(約5.8万円)を受給する場合、世帯の合計年金収入は約20.5万円となり、最低限の生活費に対しても毎月約3.4万円の赤字となります。
ゆとりある生活(月39.1万円)を目指すのであれば、不足額はさらに大きくなります。
この差額を現役時代からの貯蓄や退職金、私的年金などでどう補うかが、老後資金計画の重要なポイントです。
医療・介護など“想定外の支出”にも備えが必要
老後の資金計画では、毎月の生活費だけでなく、突発的に発生する「想定外の支出」にも備える必要があります。特に大きな割合を占めるのが、医療費や介護費用です。
高齢になると病気やケガのリスクが高まり、入院や手術でまとまった費用が必要になることがあります。また、将来的に介護が必要になった場合、在宅介護でも住宅のリフォームや介護サービスの利用料、施設に入居する場合はその費用がかかります。
これらの費用は公的な保険で一部カバーされますが、自己負担も決して少なくありません。平均的な生活費とは別に、こうした万が一の事態に備えるための予備資金を準備しておくことが、安心して老後を過ごすための鍵となります。
安心して暮らすには「月+5万円」の備えを意識
老後の生活において、最低限の生活費に加えてどれくらいの余裕を持つべきか、一つの目安として「月額プラス5万円」を意識すると良いでしょう。
この追加の5万円があれば、趣味やレジャー、友人との交際費など、生活に彩りを与える活動に充てることができます。
生命保険文化センターの調査でも、ゆとりある生活のための上乗せ額の平均は約15万円となっていますが、まずは月5万円、年間で60万円の余裕資金を目標にすることで、より具体的な資金計画を立てやすくなります。
この「プラス5万円」を公的年金以外でどのように確保するか、iDeCoやNISA、個人年金保険などを活用した資産形成を現役時代から計画的に進めることが重要です。
厚生年金40年と国民年金だけの人ではどれくらい違う?
日本の公的年金は、働き方によって加入する制度が異なります。会社員などが加入する厚生年金と、自営業者などが加入する国民年金では、将来受け取れる年金額に大きな差が生まれます。ここでは、その具体的な違いについて解説します。
国民年金(満額)との比較
国民年金(老齢基礎年金)は、20歳から60歳までの40年間、保険料をすべて納付した場合に満額を受け取ることができます。令和7年度の満額は年額83万1700円、月額に換算すると6万9308円です。
この金額が、自営業者など国民年金のみに40年間加入してきた方が受け取る年金額のです。
厚生年金40年加入者との差は2〜3倍以上に
「令和7年度年金額改定についてお知らせします|厚生労働省」によると、厚生年金40年加入者の平均的な年金受給額は、老齢基礎年金含めて月額約16.3万円です。国民年金のみ40年加入者の受給額約6.9万円と比較すると、その差は約2.4倍にもなります。
この大きな差は、厚生年金が国民年金に上乗せされる2階建て構造になっているためです。厚生年金加入者は、自身の給与や賞与に応じた保険料を納めることで、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取ることができます。
現役時代の働き方が、老後の収入にいかに大きく影響するかがこの比較から明確にわかります。
夫婦で考えると月25〜28万円程度が平均ライン
夫婦2人世帯で老後の年金収入を考える場合、働き方によって受給額の合計は大きく異なります。
例えば、夫が会社員で厚生年金に40年加入し、妻が専業主婦として国民年金に40年加入した場合、夫の年収が平均的であれば世帯の年金収入は月額23万円が一つの目安となります。
一方、夫婦ともに会社員として厚生年金に加入していた共働き世帯の場合、それぞれの受給額を合算できるため、世帯収入はさらに多くなります。
平均的な収入の夫婦であれば、月額30万円程度の受給が見込めるでしょう。この金額は、老後の生活設計を立てる上で重要な基準となります。
夫婦で年金はいくらもらえる?世帯別の受給額
老後の生活設計を立てる上で、夫婦2人分の年金収入がいくらになるのかを把握することは重要です。働き方の組み合わせによって、世帯としての年金受給額は大きく変わります。
代表的なモデルケース別に受給額の目安を見ていきましょう。
共働き夫婦の平均受給額
夫婦ともに会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合、それぞれが老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。
厚生労働省のデータによると、厚生年金受給者の平均月額は約14.5万円です。単純にこの平均額を2人分合算すると、世帯の年金収入は月額約29万円となります。
もちろん、これはあくまで平均値であり、夫婦それぞれの加入期間や現役時代の収入によって金額は変動します。例えば、夫の年収が600万円、妻の年収が300万円で共に40年加入した場合、世帯の年金月額は約30万円程度が見込まれます。
夫が厚生年金40年+妻が国民年金満額の場合
夫が会社員として厚生年金に40年間加入し、妻が専業主婦(第3号被保険者)として国民年金保険料を満額納付した場合のモデルケースです。
この場合、夫は老齢基礎年金と老齢厚生年金、妻は老齢基礎年金を受け取ります。夫が平均的な収入、妻の国民年金が満額(月額約6.9万円)だとすると、世帯の合計年金収入は月額約23.3万円となります。
(参考:令和7年度年金額改定についてお知らせします|厚生労働省)
共働き世帯と比較すると受給額は少なくなりますが、これが伝統的な片働き世帯の一つの目安となるでしょう。
月々の支出26万円との比較で見る“黒字/赤字”の分かれ目
老後の生活費の一つの目安として、「家計調査報告 〔 家計収支編 〕 2024年(令和6年)平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の支出(消費支出・非消費支出含む)は月額28万6877円です。仮にこれを「支出28.7万円」と設定して、各世帯モデルの年金収入と比較してみましょう。
- 共働き夫婦(平均): 年金収入約29.4万円に対し、支出28.7万円なので月0.7万円の黒字
- 片働き夫婦(夫:厚生年金40年、妻:国民年金満額): 年金収入約23.3万円に対し、支出28.7万円なので月5.4万円の赤字
このように、共働きであったかどうかで、年金収入だけで生活できるかどうかの分かれ目が見えてきます。赤字になる場合は、その不足分を貯蓄や退職金、その他の収入で補っていく必要があります。
厚生年金を増やす・減らさないための4つの方法
公的年金は老後の生活を支える基盤ですが、それだけでは十分な生活が送れない可能性もあります。将来受け取る年金額を増やしたり、減らさないようにしたりするための方法がいくつか存在します。
代表的な4つの方法をご紹介します。
① 繰下げ受給の活用
老齢年金の受給開始は原則65歳ですが、この開始時期を66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」を選択できます。
受給を1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増額され、最大で75歳まで繰り下げることで、年金額を84%も増やすことが可能です。
例えば、65歳時点で月15万円もらえる年金を75歳まで繰り下げると、月額約27.6万円にまで増えます。65歳以降も働く予定があり、当面の生活資金に余裕がある方にとっては、将来の年金額を大きく増やす有効な手段です。
② 定年後も働き続けて加入期間を延ばす
厚生年金は70歳まで加入することが可能です。定年後も再雇用などで働き続けることで、厚生年金の加入期間を延ばし、将来の受給額を増やすことができます。
加入期間が長くなるほど、年金額計算の基礎となる報酬比例部分が増えるため、生涯にわたって受け取る年金額を底上げできます。例えば、年収300万円で60歳から70歳まで10年間厚生年金に加入すると、年金額は年間約16万円増加します。長く健康に働くことは、老後資金を充実させるための確実な方法の一つです。
③ iDeCoや企業型DCで“自助年金”を作る
公的年金に上乗せする形で、自分自身で老後資金を準備する「私的年金」の活用も重要です。代表的な制度がiDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(企業型確定拠出年金)です。
これらの制度は、自分で掛金を拠出し、投資信託などの金融商品で運用して、原則60歳以降に受け取る仕組みです。最大のメリットは税制優遇にあり、掛金が全額所得控除の対象になるため、毎年の所得税や住民税の負担を軽減できます。さらに、運用によって得られた利益も非課税となります。
公的年金だけでは不安な場合、こうした制度を活用して積極的に「自助年金」を作ることが推奨されます。
④ 任意加入・付加年金で空白期間を補う
国民年金の保険料納付期間が40年に満たない場合、60歳から65歳までの間に「任意加入」することで、納付期間を増やし、将来の老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。学生時代に未納期間がある方などに有効な手段です。
また、自営業者などの第1号被保険者の方は、毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして納める「付加年金」を利用できます。これにより、将来「200円×付加保険料納付月数」で計算される金額が年金に加算されます。2年以上年金を受け取れば元が取れる、お得な制度です。
ライフステージに合わせて選ぶのがポイント
将来の年金を増やす方法は一つではありません。紹介した「繰下げ受給」「継続雇用」「iDeCoの活用」「任意加入」といった選択肢の中から、自身のライフステージや価値観に合った方法を選ぶことが重要です。
例えば、健康で働く意欲がある方は継続雇用が有効ですし、税金の負担を減らしながらコツコツ積み立てたい人にはiDeCoが向いています。また、年金の受給開始を遅らせることに抵抗がないなら、繰下げ受給の増額効果は大きいでしょう。
まずはご自身の年金見込額を確認し、理想の老後生活とのギャップを把握した上で、どの方法が最適かを総合的に判断することが、賢い老後資金計画につながります。
自分の将来受給額を確認する方法
老後資金計画を立てる第一歩は、自分が将来いくら年金を受け取れるのかを正確に把握することです。日本年金機構では、そのための便利なツールを提供しています。
これらを活用して、ご自身の年金見込額を確認しましょう。
「ねんきん定期便」で現時点の見込み額を確認する
毎年誕生月に日本年金機構から郵送される「ねんきん定期便」は、自分の年金情報を手軽に確認できる重要な書類です。これまでの保険料納付額や年金加入期間が記載されています。
特に注目すべきは、記載されている年金額です。50歳未満の人には「これまでの加入実績に応じた年金額」です。
一方、50歳以上の人には「現在の加入条件が60歳まで続いたと仮定した場合の年金見込額」が記載されており、より具体的な将来像を把握できます。
まずはこの金額を確認し、老後設計の出発点としましょう。
想定より少ない時に見直すべき3つの視点
年金見込額が、想定よりも少ないと感じることもあるでしょう。その場合は、以下の3つの視点から現状を見直し、対策を検討することが重要です。
働き方を見直す
厚生年金の受給額は、加入期間と収入に比例します。より長く、より高い収入で働くことができれば、将来の年金額を増やすことが可能です。
転職やスキルアップによる収入増、あるいは定年後の再雇用などを検討してみましょう
私的年金の活用を検討する
公的年金だけでは不十分な場合、iDeCoや企業型DC、個人年金保険といった私的年金を活用して、自分で年金を上乗せする「自助努力」が不可欠です。
税制優遇のある制度を最大限に活用しましょう
支出(ライフプラン)を見直す
収入を増やすだけでなく、老後の支出をコントロールすることも重要です。現在の家計を見直し、将来どのような生活を送りたいのか、そのためにはいくら必要なのかを具体的にシミュレーションし、現実的な資金計画を立て直しましょう
まとめ
厚生年金に40年間加入した場合の受給額は、現役時代の平均年収に大きく左右されますが、平均的には国民年金と合わせて月額16.3万円が目安となります。
ただし、この金額だけでは、特に都市部での生活やゆとりある老後を送るには不十分と感じる方も多いでしょう。
重要なのは、まず「ねんきん定期便」などでご自身の正確な見込額を把握することです。その上で、繰下げ受給の活用、60歳以降も働き続ける、iDeCoやNISAで私的年金を準備するなど、具体的な対策を早期に始めることが求められます。
本記事で紹介したシミュレーションや対策を参考に、ご自身のライフプランに合った最適な老後資金計画を立てていきましょう。
»年金だけで暮らせる?不足金額と準備方法を無料診断
将来の年金が気になるあなたへ
この先、お金の不安なく暮らすために、老後資金の必要額を早めに把握して準備を始めましょう。マネイロでは、将来資金の準備をかんたんに進められる無料ツールを利用できます。
▶老後資金の無料診断:将来必要になる金額を3分で診断
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事
監修
森本 由紀
- ファイナンシャルプランナー/AFP(日本FP協会認定)/行政書士
行政書士ゆらこ事務所(Yurako Office)代表。愛媛県松山市出身。神戸大学法学部卒業。法律事務所事務職員を経て、2012年に独立開業。メイン業務は離婚協議書作成などの協議離婚のサポート。離婚をきっかけに自立したい人や自分らしい生き方を見つけたい人には、カウンセリングのほか、ライフプラン、マネープランも含めた幅広いアドバイスを行っている。法律系・マネー系サイトでの記事の執筆・監修実績も多数。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。