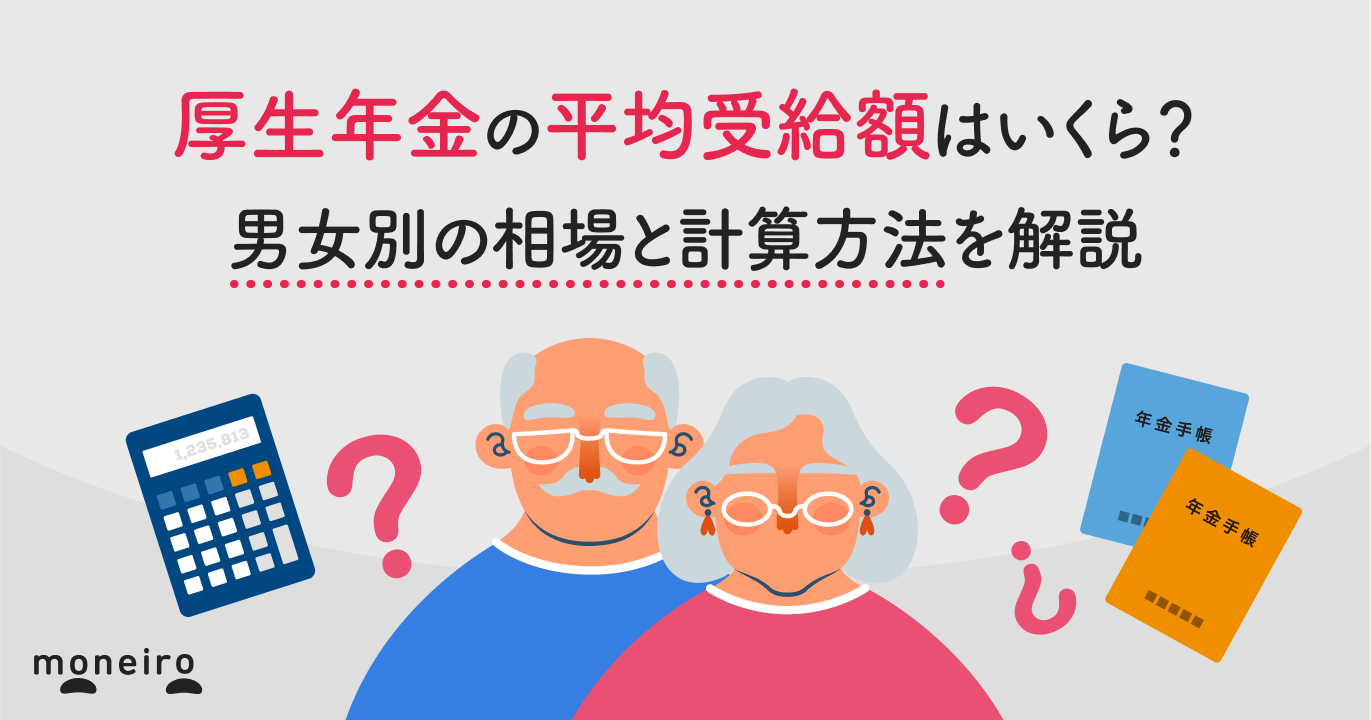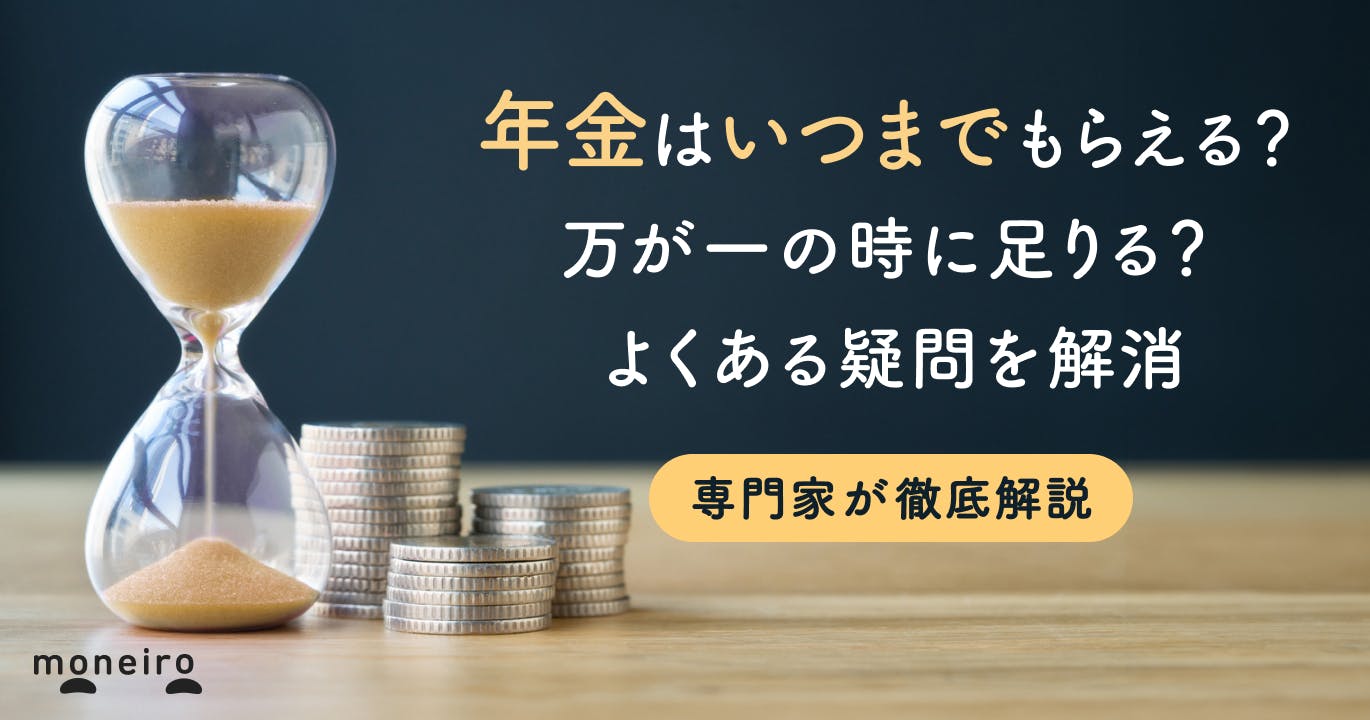厚生年金の平均受給額はいくら?男女別の相場と計算方法を解説
≫年金だけで足りる?あなたの老後の本当の必要額を診断
「厚生年金の平均受給額はいくら?」「年金額はどう計算される?」そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。老後の生活設計において、公的年金、特に厚生年金がいくら受け取れるかは非常に重要な関心事です。
そこで本記事では、厚生労働省の最新統計に基づき、平均受給額を徹底解説するとともに、国民年金のみとの比較や受給額の計算方法、ねんきんネットでの確認方法、そして将来の受給額を増やすための具体的な方法までを詳しく解説していきます。
- 厚生労働省の最新統計に基づく厚生年金の平均受給額
- 厚生年金の受給額がどのように決定され、計算されるかの仕組み
- ねんきんネットの活用方法と、将来の受給額を増やすための戦略
年金の受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
厚生年金の平均受給額は14万6429円
厚生労働省が公表している「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢厚生年金(老齢基礎年金を含む)の受給権者全体の平均年金月額は、14万6429円です。
この金額は、長年会社員や公務員として働き、厚生年金に加入していた方が受け取る年金の目安となります。
ただし、この平均額はあくまで全体平均であり、個人によって現役時代の収入や加入期間が異なるため、受給額には大きな差が生じます。
男女別・厚生年金の平均受給額
厚生年金の平均受給額を男女別、かつ65歳以上の受給権者に絞って見ると、金額に大きな違いがあることが分かります。
- 男性(65歳以上)の平均受給月額:16万9484円
- 女性(65歳以上)の平均受給月額:11万1479円
男女間で差が生じる主な要因としては、主に現役時代の平均標準報酬額(平均年収)の違いや、女性の非連続的なキャリアパス(結婚・出産によるキャリアの中断など)、厚生年金への加入期間の長さが挙げられます。
一般的に、女性の方が平均標準報酬額が低い、または加入期間が短い傾向にあるため、男性と比較して厚生年金の上乗せ部分が少なくなりやすい傾向があります。
【参考】国民年金の平均受給額は5万7584円
会社員や公務員が加入する厚生年金は、すべての国民が加入する「老齢基礎年金(国民年金)」に「老齢厚生年金」が上乗せされる二階建ての構造になっています。
一方で、自営業者や専業主婦(夫)など、国民年金のみに加入している方(老齢基礎年金のみの受給者)の平均受給額は、月額5万7584円です。
この比較から、厚生年金加入者は国民年金のみの受給者と比較して、平均で約9万円近く多くの年金を受け取っていることが分かります。
厚生年金の受給額はどうやって決まる?
厚生年金(報酬比例部分)の受給額は、主に現役時代の給与水準を示す「平均標準報酬額(≒平均年収÷12ヶ月)」と、厚生年金に加入していた「加入期間」の2つの要素によって決定されます。
加入期間が長く、かつ平均年収が高いほど、将来受け取れる年金額は増える仕組みです。
厚生年金受給額の計算方法
老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算は複雑ですが、おおよその受給額を把握するための簡易計算式があります。老齢厚生年金(上乗せ部分)の目安は、以下の月ベースの簡易計算式で求められます。
年金(年額) = (平均年収 ÷ 12) × 0.005481 × 厚生年金加入月数
例えば、現役時代の平均年収が480万円で、40年間(480ヶ月)厚生年金に加入した(全期間が平成15年4月以降と仮定する)場合で試算してみましょう。
(480万円 ÷ 12) × 0.005481 × 480ヶ月 = 105万2352円(年額)
つまり、月額の目安は8万7696円となります。
上記の年金額は、加入期間を平成15年4月以降のみと仮定して簡易的に算出した見込額の目安です。平成15年3月以前の加入期間がある場合や、平均標準報酬額の算出方法(賞与の扱いなど)により、実際の受給額とは異なります。
国民年金(老齢基礎年金)受給額の計算方法
上の簡易計算で求めた金額は、厚生年金の上乗せ部分(報酬比例部分)のみです。実際に受け取る年金総額は、すべての国民が「一階部分」として共通で受け取る「老齢基礎年金」がベースとなります。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべて保険料を納付した場合に「満額」を受け取ることができます。
令和7年度(2025年度)の老齢基礎年金の満額は、月額で6万9308円です。
したがって、受け取ることのできる年金総額の目安は、「老齢基礎年金(満額なら6万9308円)+ 老齢厚生年金(上乗せ部分) 」となります。
自分の年金見込額を正確に知る方法
平均額や簡易シミュレーションはあくまで目安であり、個々人の正確な年金見込額は、加入履歴や保険料の納付状況によって異なります。正確な見込額を知るためには、日本年金機構が提供する公的なツールを活用するのが最も確実です。
ねんきんネット
「ねんきんネット」は、日本年金機構が運営する個人向けのオンラインサービスであり、インターネットを通じていつでも自分の年金情報を確認できます。このサービスを利用することで、現在の状況に基づいた正確な老後資金計画を立てることができます。
ねんきんネットでできること
ねんきんネットでは、これまでの年金加入記録を詳細に確認できるほか、将来の年金見込額を様々な受給開始年齢や働き方のパターンで試算できます。
また、過去の保険料の納付状況、国民年金保険料の未納期間に対する追納可能額の情報確認など、多岐にわたる機能が利用可能です。
ねんきんネットの登録方法
ねんきんネットに登録するには、主に毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」(封書)に記載されている「アクセスキー」を利用する方法と、アクセスキーなしで基礎年金番号や氏名などの情報を使って登録する方法があります。アクセスキーを利用すれば、スムーズにユーザーIDが発行され、すぐに利用を開始できます。
また、マイナポータル(行政手続のオンライン窓口)を経由してねんきんネットを利用することもできます。ユーザーIDなしで利用可能です。
ねんきん定期便
ねんきん定期便は、毎年誕生月に日本年金機構から送付される書類です。この定期便には、これまでの年金加入期間や納付状況、および将来の年金見込額が記載されており、自身の年金記録などを確認する重要なツールとなります。
50歳未満の方には「これまでの加入実績に応じた年金見込額」が、50歳以上の方には「現在の加入条件が60歳まで継続した場合の年金見込額」が記載されます。
年金の受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
将来の厚生年金受給額を増やす5つの方法
公的年金の平均受給額だけでは老後の生活が不安な場合、自助努力で受給額を増やすための戦略を早期から立てることが可能です。ここでは、将来の年金受給額を増やすための具体的な5つの方法を解説します。
1. 繰下げ受給する(最大84%増額)
年金は原則65歳から受給可能ですが、受給開始時期を66歳以降に遅らせる「繰下げ受給」を選択すると、年金額が割増されます。
受給額は1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額され、最大75歳まで繰り下げることが可能です。
仮に75歳まで繰り下げた場合、65歳から受給するよりも最大で84%も受給額を増やすことができます。
ただし、繰下げ期間中は年金を受け取れないため、健康状態や生活資金の状況を十分考慮する必要があります。
2. 60歳以降も厚生年金に加入して働く(在職老齢年金)
定年後も会社員として働き続けることで、厚生年金への加入期間が延び、その分、将来の老齢厚生年金が増加します。また、60歳以降も厚生年金に加入し給与を得る場合、「在職老齢年金制度」の対象となります。
この制度は、給与(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計額が一定額(=支給停止調整額、令和7年度は51万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止される仕組みですが、働き続けることで年金を増やし続けることが可能です。
年金制度改正により、2026(令和8年)4月からは、在職老齢年金制度の支給停止調整額は「62万円」に引き上げられます。これにより、年金を受給しながらでも、働きやすくなります。
3. iDeCo(個人型確定拠出年金)などの私的年金で備える
iDeCoは、公的年金とは別に、自分で掛金を拠出し、運用することで老後の資産を形成する私的年金制度です。iDeCoの最大の魅力は、掛金が全額所得控除の対象となり、高い節税効果を得られる点です。また、運用益が非課税になる優遇措置もあります。
原則60歳まで引き出しができないため、計画的な運用が求められます。
4. 過去の未納期間・免除期間の分を追納する
過去に経済的な理由などで国民年金保険料の「免除」や「納付猶予」の承認を受けていた期間がある場合、年金額を満額に近づけるために「追納」が可能です。追納を行うと、その期間が保険料納付済期間として計算され、将来受け取れる老齢基礎年金の額を増やせます。
ただし、追納できる期間は、承認を受けた月の翌月から10年以内となるため注意が必要です。
5. 付加年金や国民年金基金を活用する(自営業・フリーランス向け)
自営業者やフリーランス(国民年金第1号被保険者)は、老齢厚生年金の上乗せ部分がないため、自助努力での備えが特に重要です。公的な年金上乗せ制度として、「付加年金」や「国民年金基金」があります。
付加年金は、定額の保険料を納めることで、将来の年金額が「200円 × 納付月数」分増額されます。
国民年金基金は、掛金全額が所得控除の対象となる、より手厚い私的年金制度です。
厚生年金の受給額(平均)に関するQ&A
厚生年金の受給額や仕組みに関して、多く寄せられる疑問に回答します。
Q. 厚生年金の平均受給額は「手取り」の額?
厚生労働省が公表している平均受給額(14万6429円など)は、年金から税金や社会保険料が引かれる前の「額面」の金額です。実際に受給者が受け取る「手取り」の額は、この額面から、所得税、住民税、介護保険料、国民健康保険料(または後期高齢者医療制度の保険料)などが差し引かれた後の金額となります。
公表されている平均額をそのまま生活費の計算に用いるのではなく、税金や保険料が引かれることを考慮する必要があります。
Q. 厚生年金を月20万円もらうには、現役時代の年収はいくら必要?
老齢厚生年金と老齢基礎年金(令和7年度の満額である月額6万9308円を想定)の合計で月20万円を受け取る場合を考えます。
この場合、老齢厚生年金は月額13万692円(20万円 - 6万9308円)が必要です。先述の簡易計算式に基づき、40年間(480ヶ月)加入した場合を逆算すると、老齢厚生年金の上乗せ部分で年額156万8304円(13万692円 × 12)を得る必要があります。ここから以下の計算式で計算してみましょう。
老齢厚生年金の年額(156万8304円)= (平均年収 ÷ 12) × 0.005481 × 480ヶ月
これを計算すると、現役時代の平均年収は、おおむね715万円程度が必要ということが分かります。
上記はあくまで平成15年4月以降の簡易計算式に基づく試算です。実際には平成15年3月以前の加入期間の乗率の違いや、賃金・物価スライドの影響により、必要な年収は変動します。
Q. 「ねんきん定期便」、ハガキと封書の違いは?
ねんきん定期便は、受給者の年齢や節目によって形式が異なります。
- 封書:35歳と45歳、59歳の節目の年の人に送付されます。これらの封書には、これまでの加入記録の詳細や、将来の年金見込額が記載されます。
- ハガキ:35歳と45歳、59歳以外の人に送付され、直近1年間の納付状況や将来の年金見込額が記載されています。
まとめ
厚生年金の平均受給額は14万6429円であり、国民年金のみの平均受給額(5万7584円)と比較して高水準です。しかし、年金額は現役時代の平均年収や厚生年金の加入期間、性別によって大きく変動します。
自分の正確な年金見込額を知るためには、「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を活用し、自身の加入記録と将来の試算額を確認することが不可欠です。
老後の生活の質を高め、将来の不安を解消するためには、繰下げ受給による増額、60歳以降の就労継続による加入期間の延長、iDeCoや国民年金基金といった私的年金制度の活用など、早い段階から受給額を増やすための具体的な戦略を立てて行動することが重要です。
≫年金だけで足りる?あなたの老後の本当の必要額を診断
年金の受給額が気になるあなたへ
老後をお金の不安なく暮らすために、まずは将来の必要額を知ることから始めましょう。マネイロでは、老後資金づくりをサポートする無料ツールを利用いただけます。
▶老後資金の無料診断:老後に必要な金額が3分でわかる
▶賢いお金の増やし方入門:貯金と投資でコツコツ増やす方法がわかる
▶年金の基本と老後資金準備:年金を増やす方法や制度の落とし穴を学ぶ
※本記事の内容は記事公開時や更新時の情報です。現行と期間や条件が異なる場合がございます
※本記事の内容は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください
オススメ記事

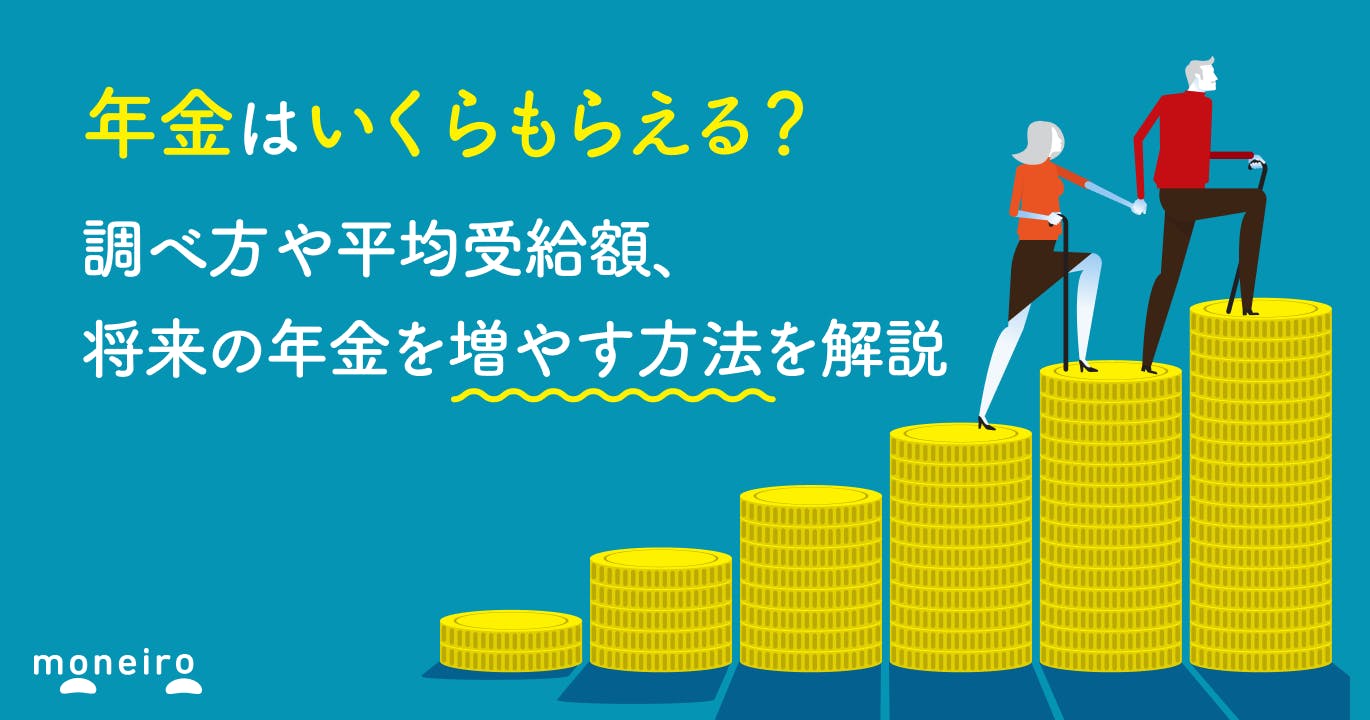
年金はいくらもらえる?調べ方や平均受給額、将来の年金を増やす方法を解説

【年収別】厚生年金はいくらもらえる?受給額の目安をケース別にシミュレーション
監修
西岡 秀泰
- 社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
同志社大学法学部卒業後、生命保険会社に25年勤務しFPとして生命保険・損害保険・個人年金保険販売を行う。保有資格は社会保険労務士と2級FP技能士。2017年4月に西岡社会保険労務士事務所を開設し、労働保険・社会保険を中心に労務全般について企業サポートを行うとともに、日本年金機構の年金事務所で相談員を兼務。
執筆
マネイロメディア編集部
- お金のメディア編集者
マネイロメディアは、資産運用に関することや将来資金に関することなど、お金にまつわるさまざまな情報をお届けする「お金のメディア」です。正確かつ幅広い年代のみなさまにわかりやすい、ユーザーファーストの情報提供に努めてまいります。